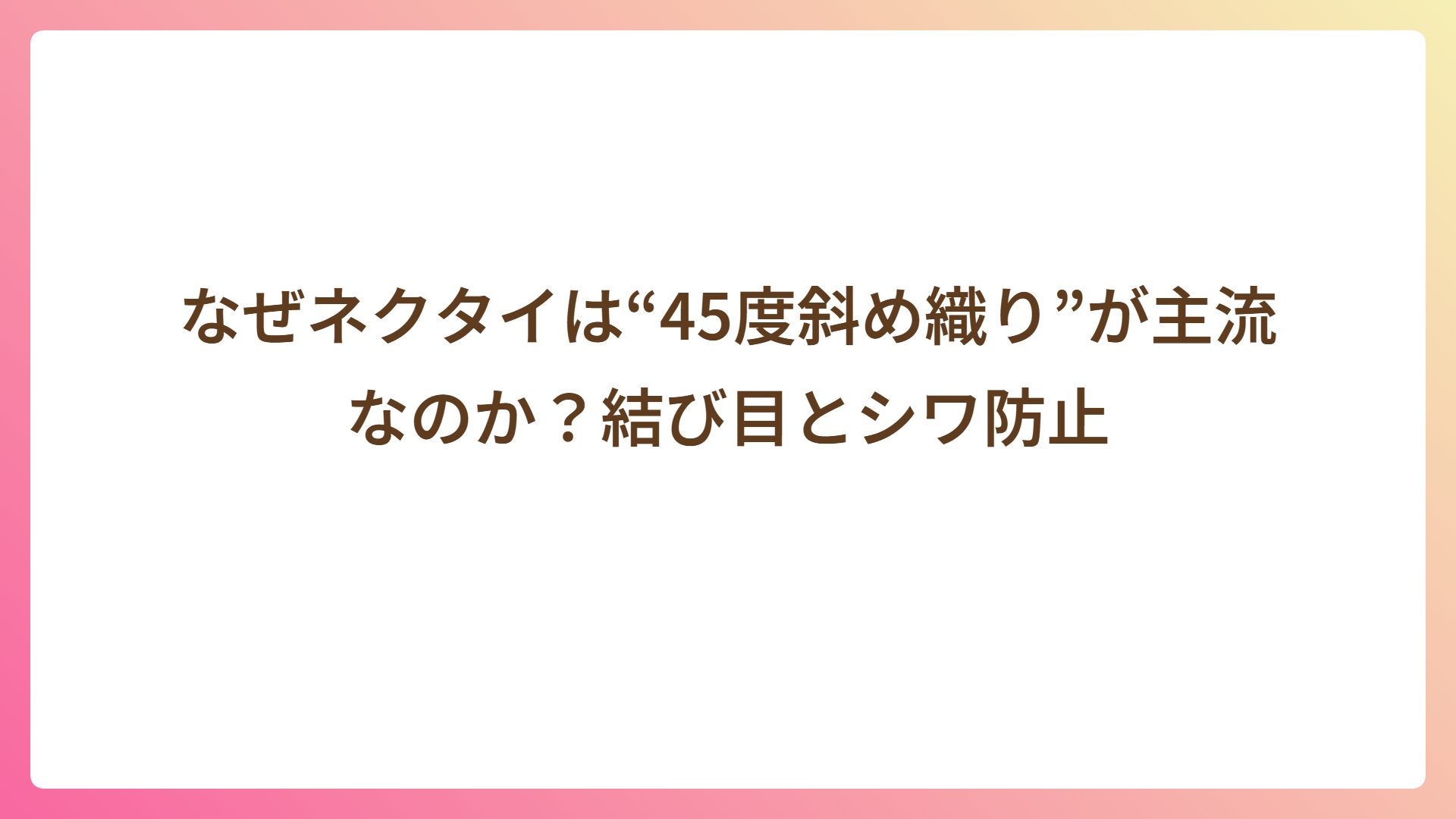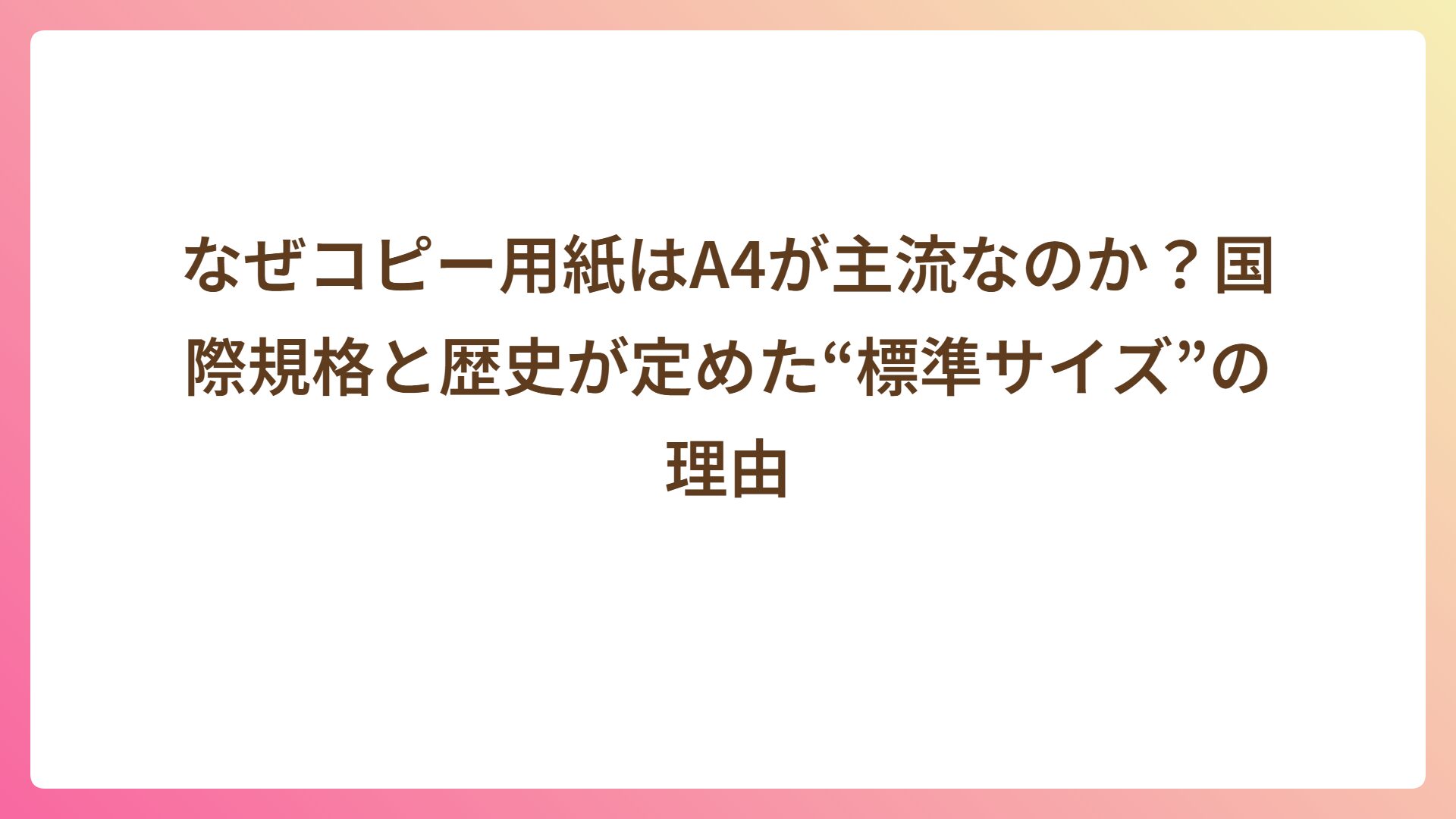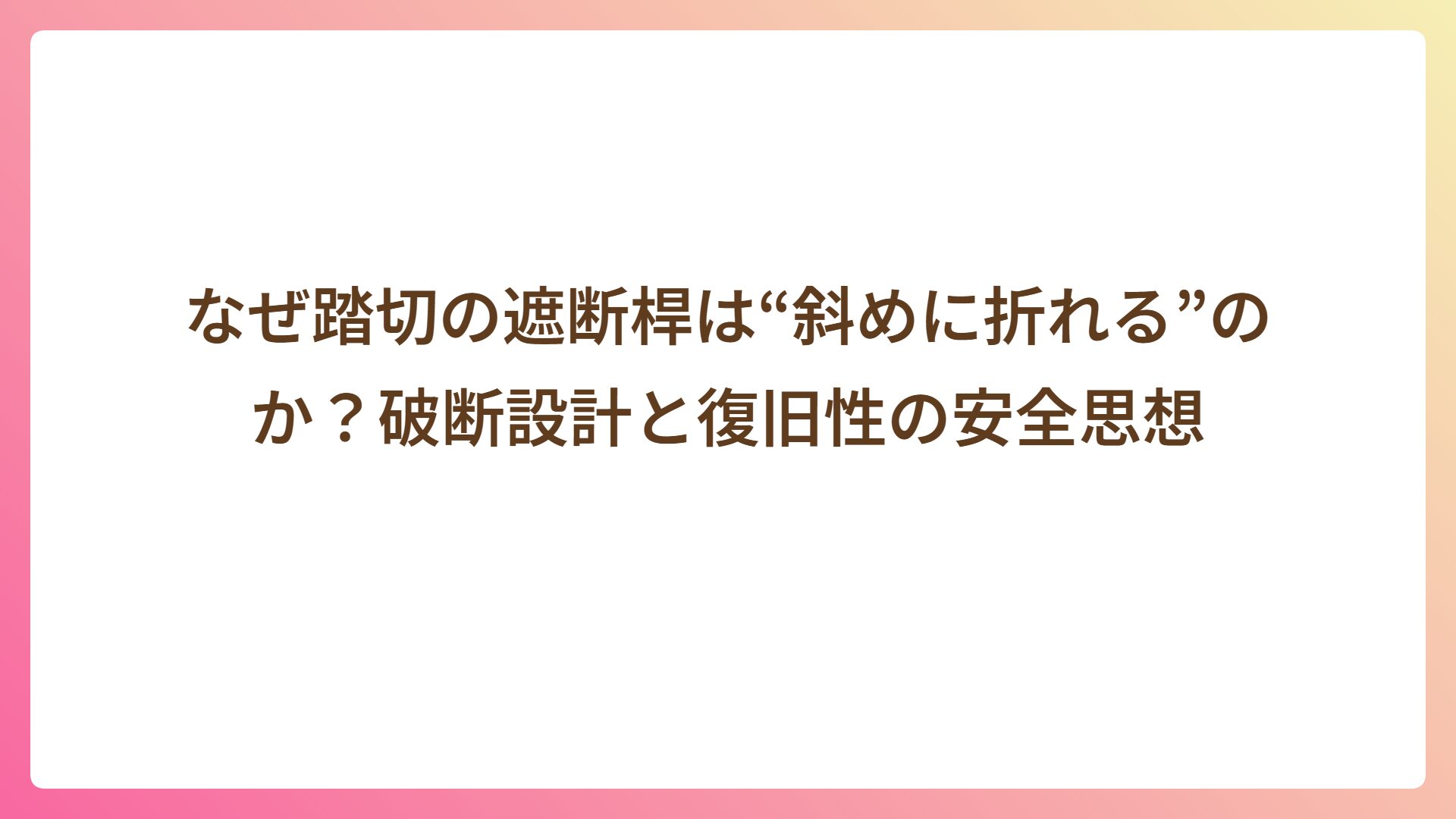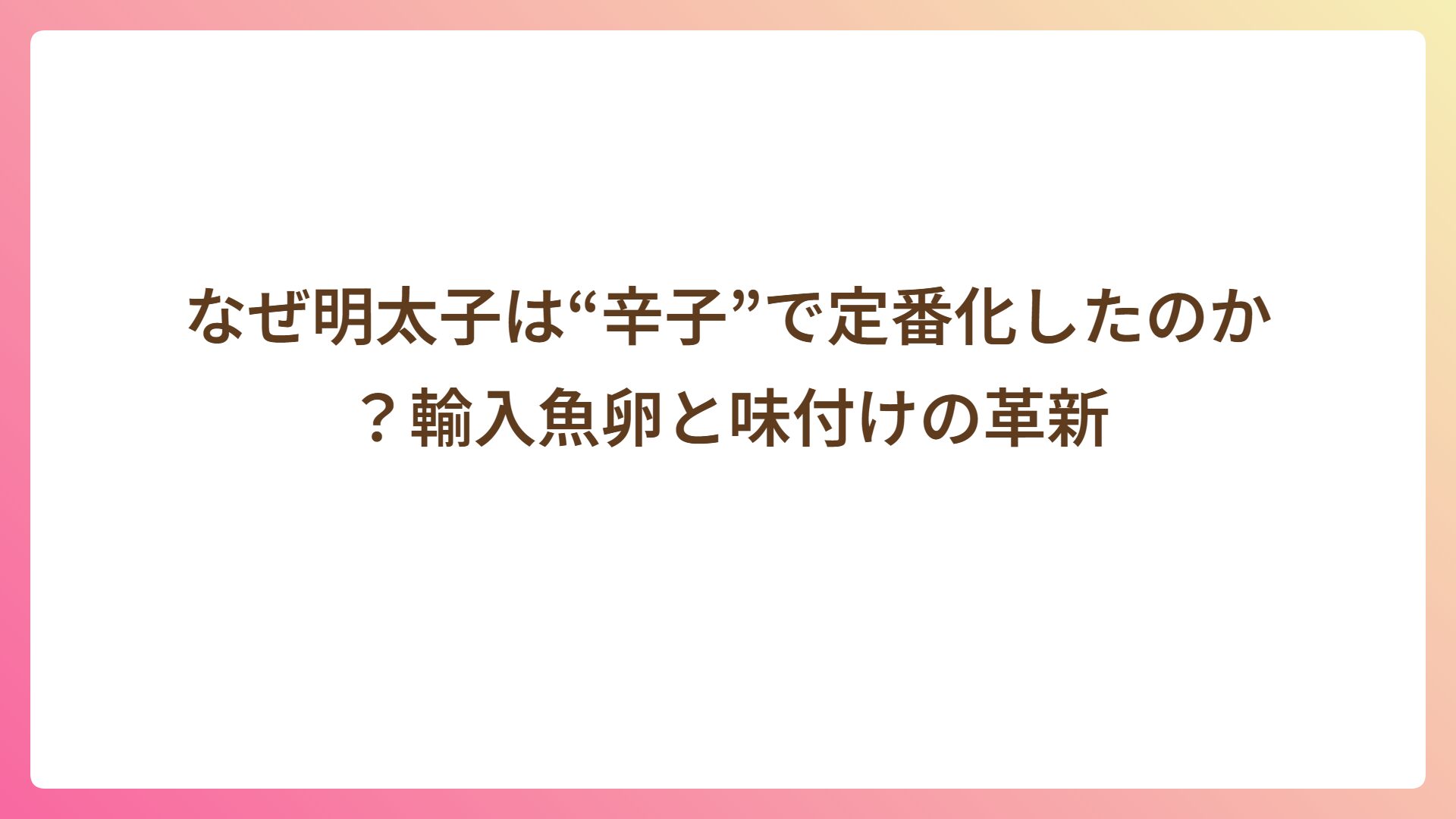なぜエレベーターの階数表示は“赤LED”が定番だったのか?視認性と寿命の合理設計
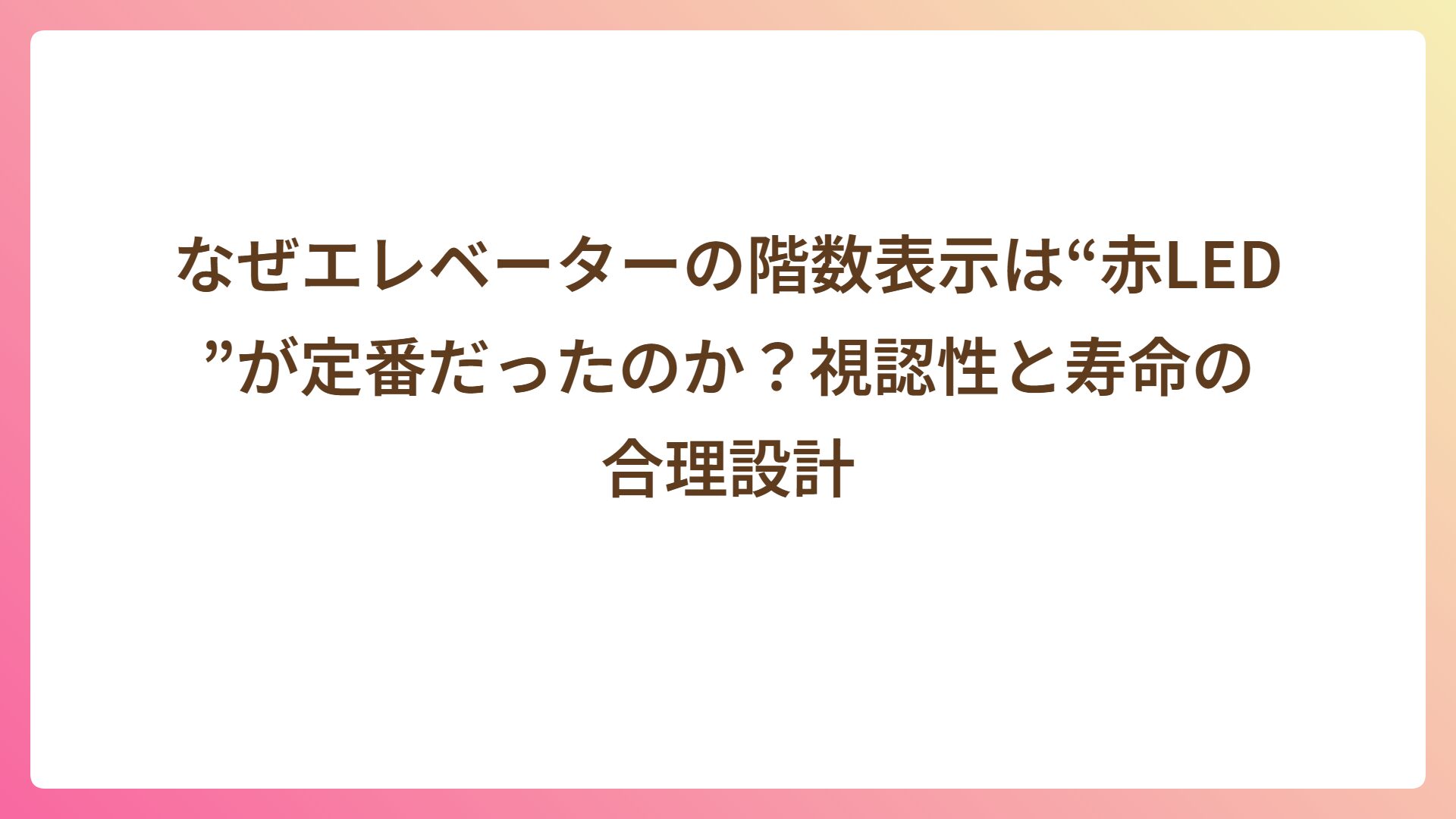
エレベーターに乗ると、階数を示す表示が赤い光で点灯しているのをよく見かけます。
なぜ青や緑ではなく、赤が定番になっているのでしょうか?
これは単なるデザインの好みではなく、視認性・コスト・耐久性といった工学的な理由が関係しています。
この記事では、エレベーターの階数表示に赤LEDが長年使われてきた理由を、歴史と技術の両面から解説します。
LED登場初期は「赤」しか実用的でなかった
現在ではフルカラーLEDが当たり前ですが、1960〜1980年代のLED技術はまだ発展途上でした。
当時、安定して長寿命・高輝度で動作するLEDは赤色(GaAsP=ヒ化ガリウムリン)のみ。
緑や青のLEDは十分な明るさを出せず、寿命も短かったのです。
そのため、1970年代から普及し始めたエレベーターや時計、電卓などのデジタル表示は、
ほぼすべてが赤色LEDで構成されていました。
つまり、赤は“技術的に最も実用的な色”だったのです。
赤は“最もエネルギー効率が良い”波長
赤い光(波長約620〜750nm)は、人間の視覚が感知できる範囲の中でもエネルギー消費が少ない色です。
同じ明るさを感じるために必要な電力が、青や緑より少なく済むため、
当時の低消費電力機器にとって省エネで長寿命な選択でした。
また、赤色LEDは発光効率が高く、熱による劣化も少ないため、
24時間稼働するエレベーター環境に最適とされました。
赤は“人間の目で最も見やすい”色のひとつ
人間の網膜には3種類の錐体細胞(赤・緑・青)があり、
その中でも赤色光に反応する細胞(L錐体)は最も感度が高い範囲を持ちます。
- 暗い場所でも認識しやすい
- 視認距離が長い
- 他の光源(蛍光灯や自然光)に埋もれにくい
そのため、薄暗いエレベーターホールでも赤い数字が最もはっきり見えるのです。
この特性は、信号機やブレーキランプなどにも共通して利用されています。
赤は“安全色”として心理的にも定着していた
赤は「注意」「警告」「行動」を促す色として、工業・交通分野で多用されてきました。
そのため、
- 「上昇中」「階数変化」などの動きを直感的に知らせる
- 暗い環境でも目を引く
- 緊急時でも識別しやすい
といった心理的な視認効果も期待できたのです。
結果として、「赤=情報を伝える色」としてユーザーの認知にも定着していきました。
LEDの寿命・コストでも“赤”が圧倒的に優れていた
LEDは色によって寿命や製造コストが異なります。
技術的に安定していた赤LEDは、
- 寿命:約10万時間(10年以上連続点灯でも使用可)
- コスト:他色に比べて1/3〜1/5程度
と、圧倒的に安価で長持ちでした。
エレベーターのように全国で常時稼働する設備では、
維持コストを抑えられる赤LEDが最も経済的な選択肢だったのです。
青や白が採用されるようになったのは“LED技術の成熟”以降
1990年代後半、青色LED(GaN系)の実用化によってLEDのカラーバリエーションが一気に広がりました。
これ以降、エレベーターでも
- 高級感を演出する白・青表示
- 可読性を高めるオレンジや緑
などが登場しましたが、依然として赤LEDが基準色として使われ続けています。
理由は、
- 高齢者にも視認しやすい
- 設備の互換性が高い
- 故障時に交換コストが安い
といったメンテナンス面での利点が残っているからです。
まとめ:赤LEDは“見やすさとコスパのベストバランス”
エレベーターの階数表示が赤いのは、
- 初期LED技術で唯一実用化された色だった
- 暗所でも見やすく、省エネで長寿命
- 製造・メンテコストが安い
- 「警告・情報色」として心理的に認知されている
といった、技術・人間工学・経済性の全てを満たした結果です。
つまり、赤は単なる「昔ながらの色」ではなく、
合理性に裏打ちされた“最適な選択”として採用されてきたのです。