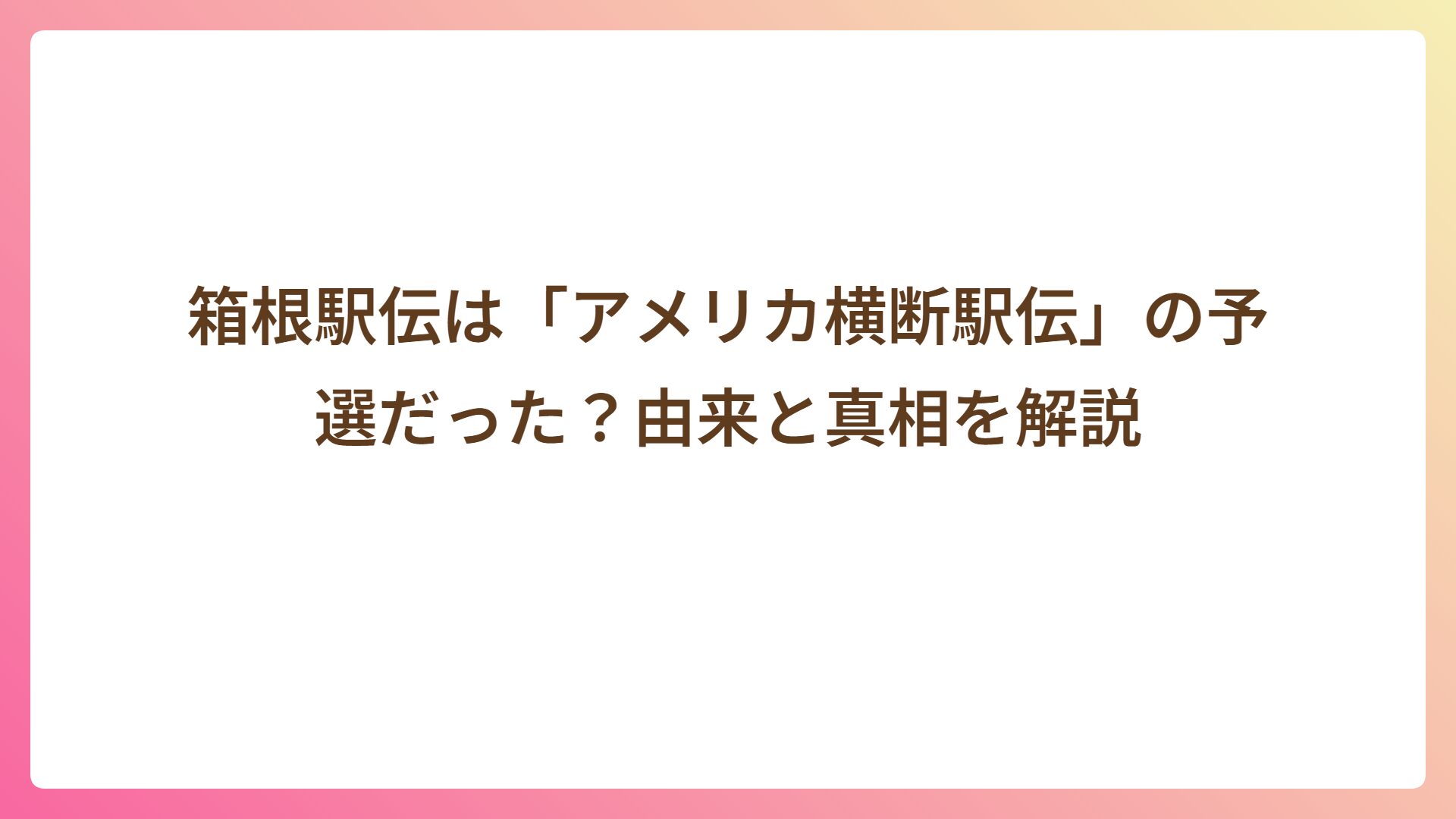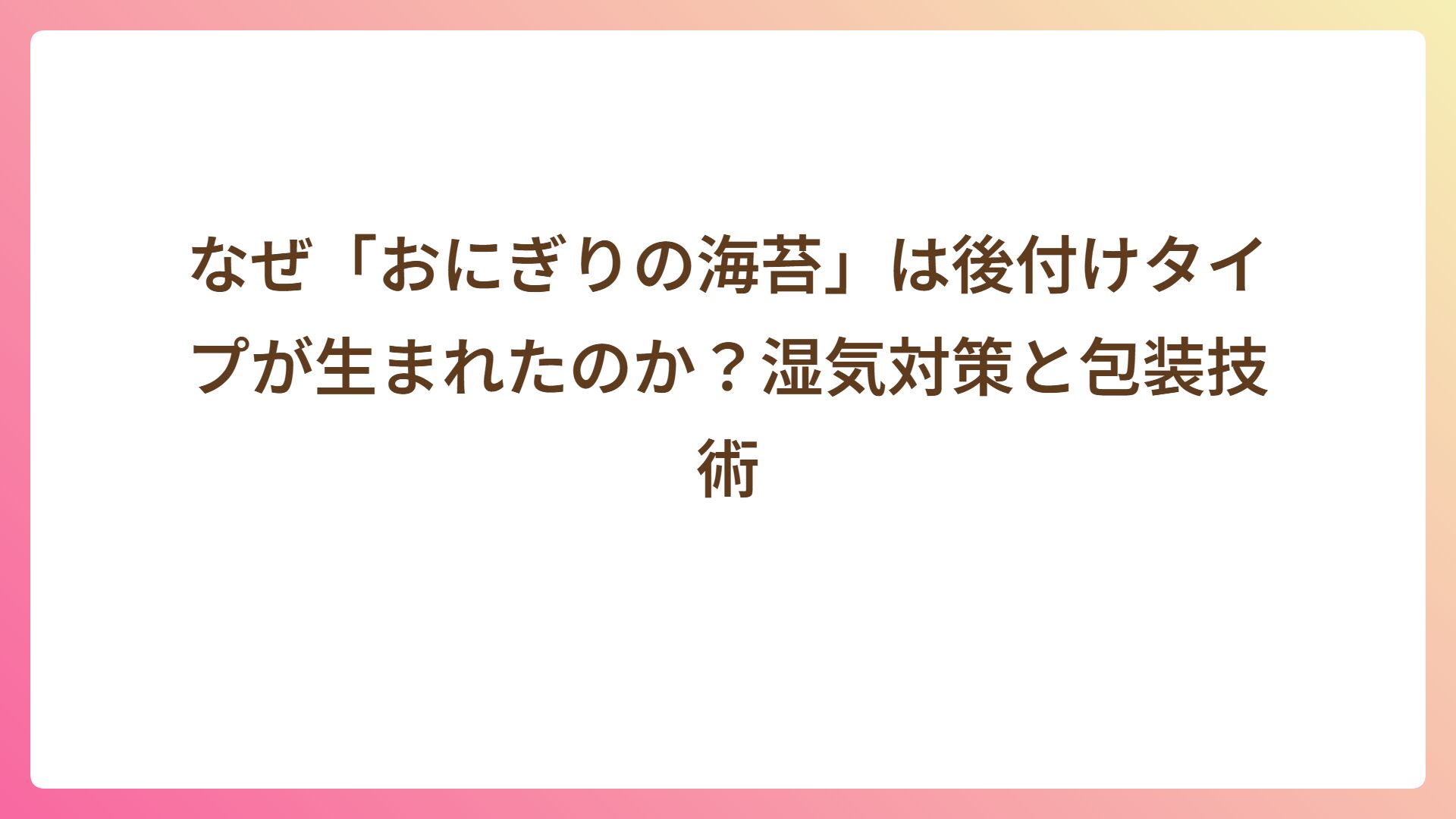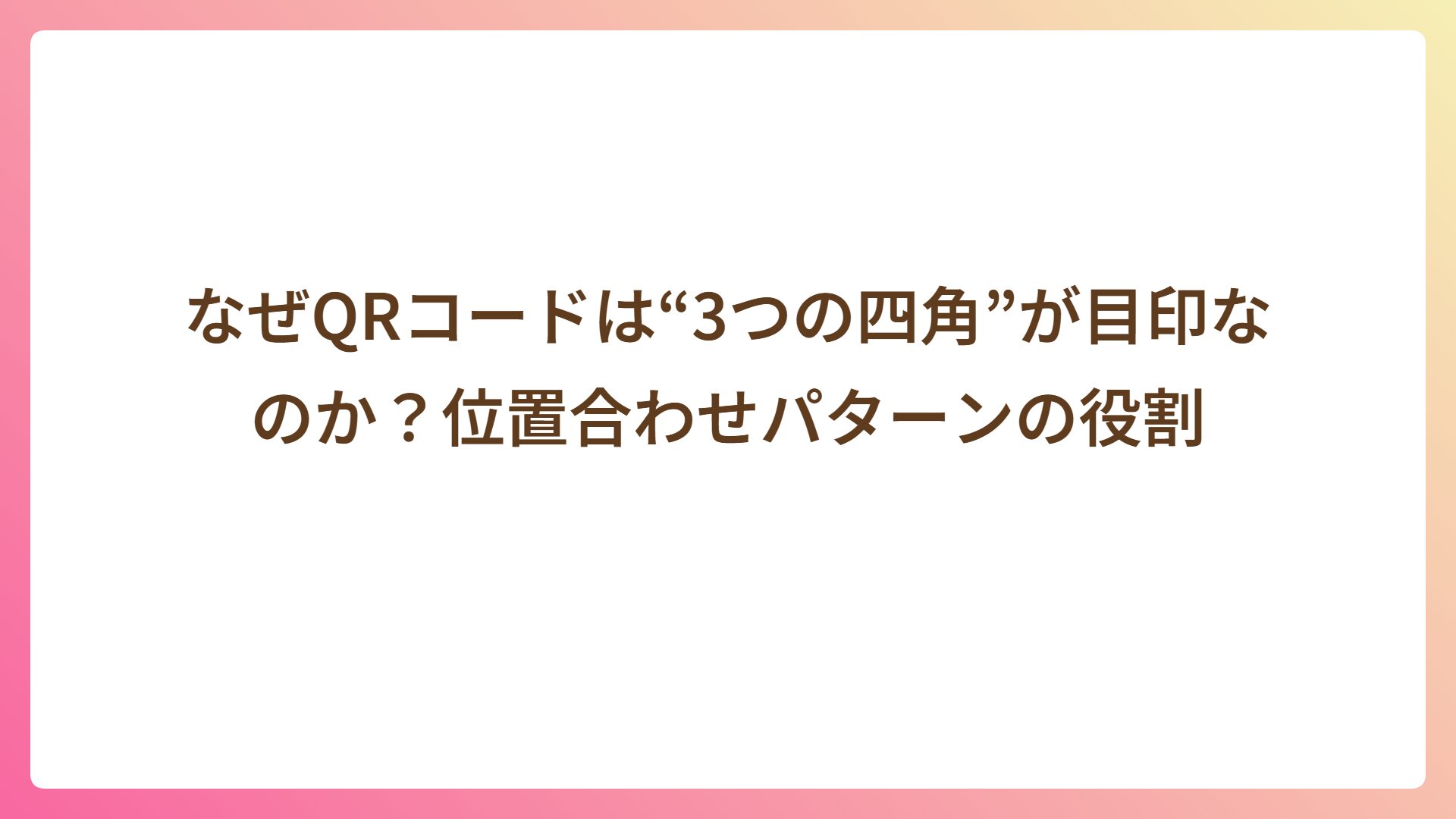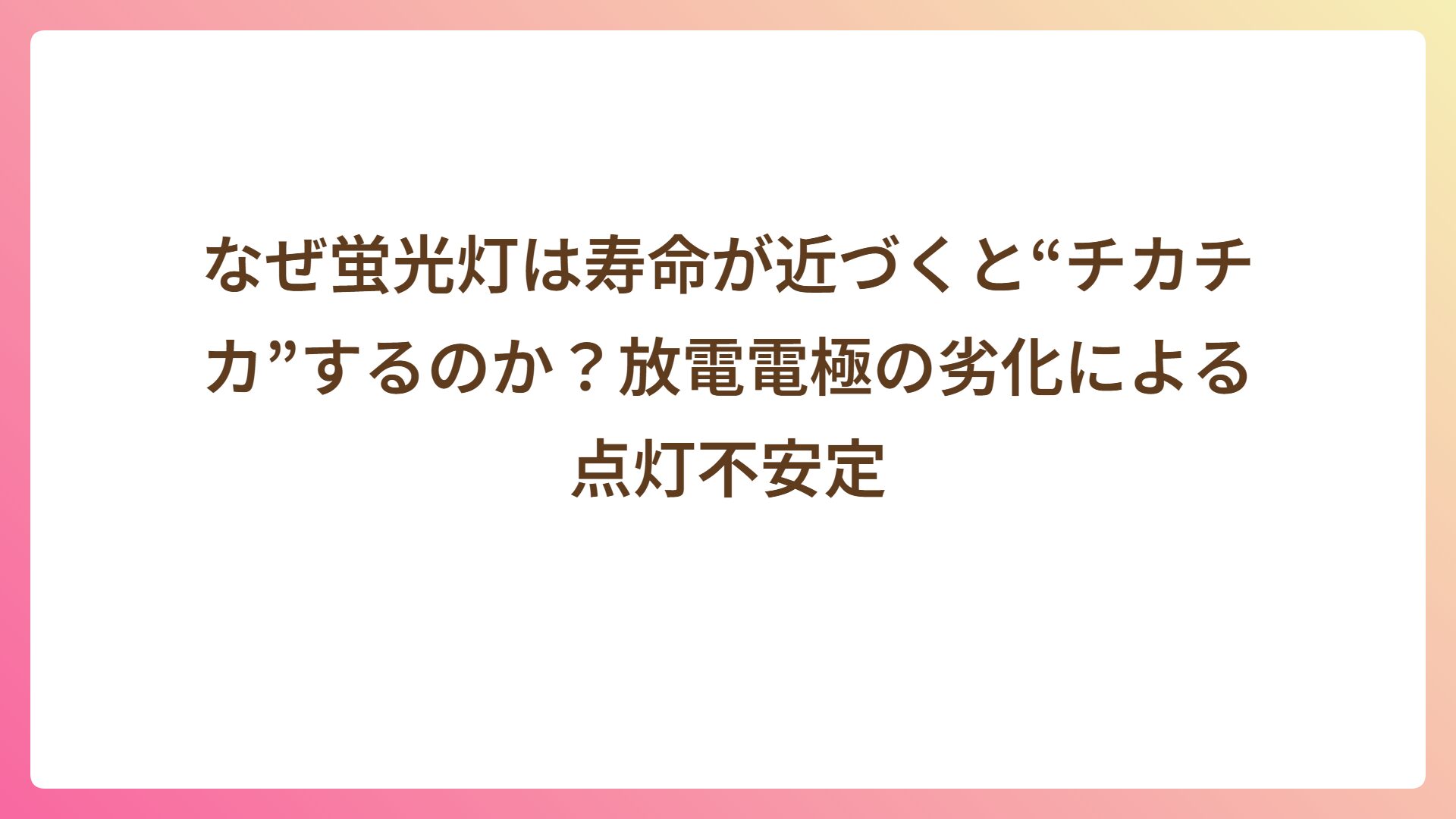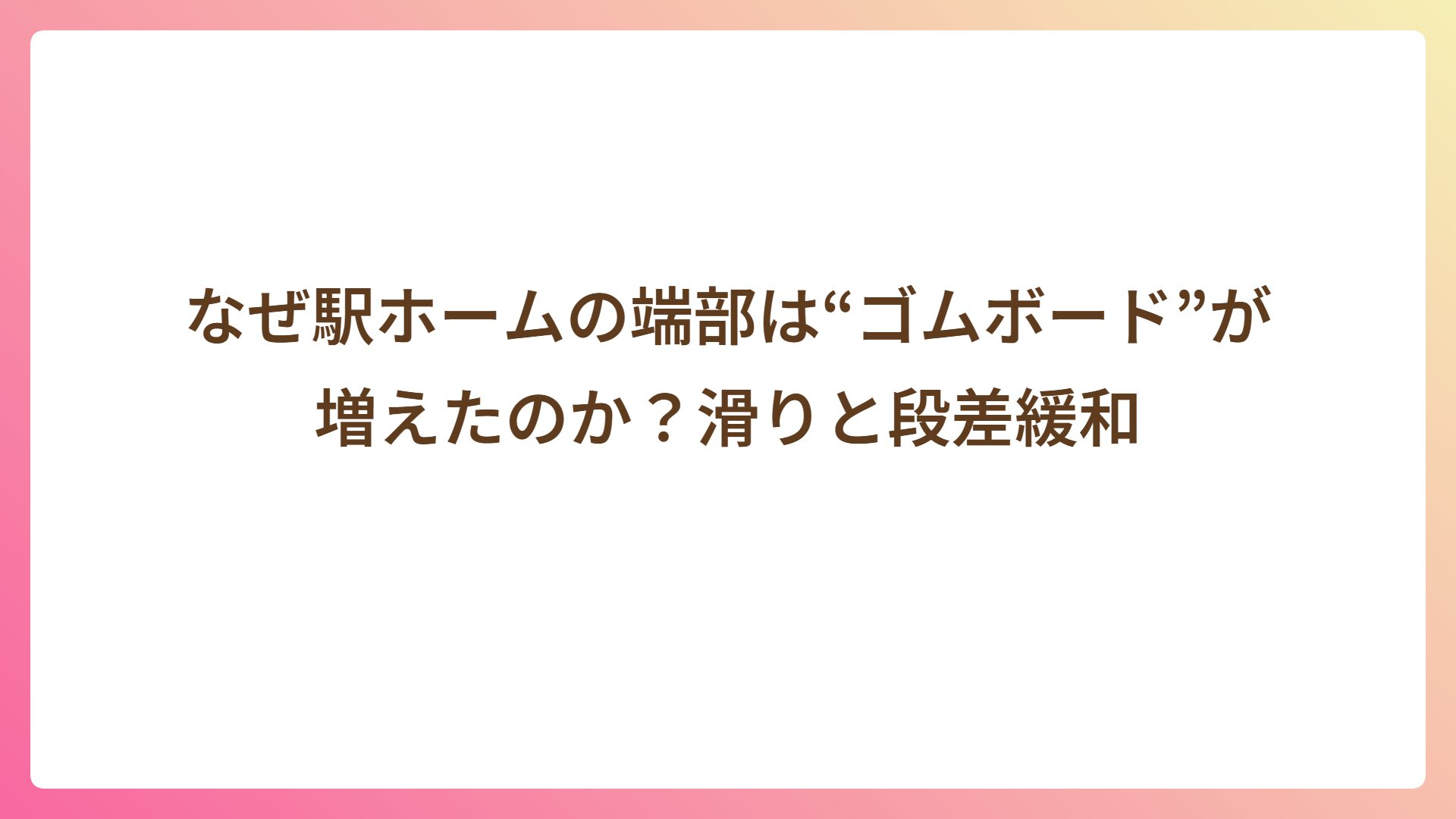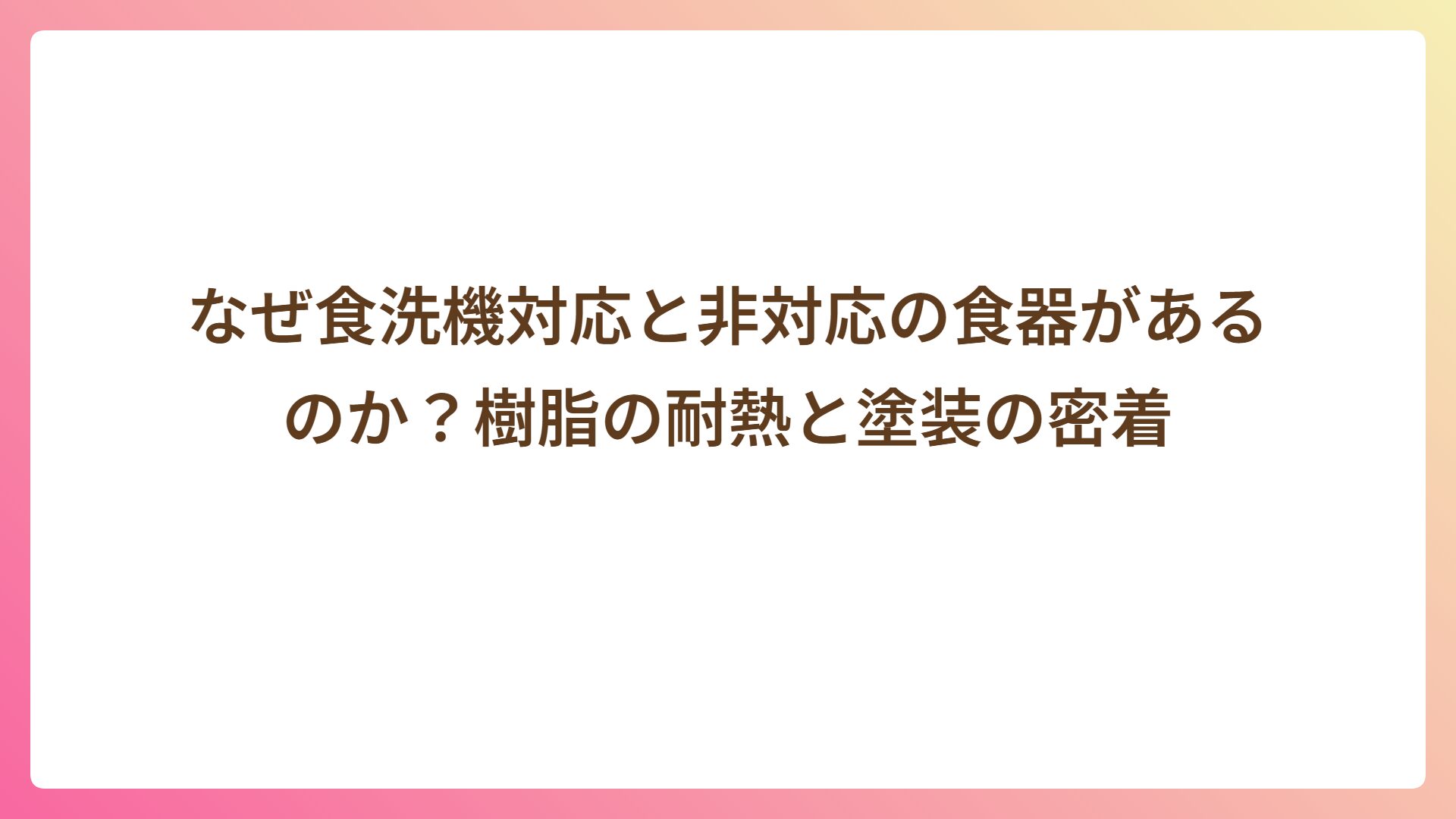なぜエレベーターピットに水抜きがあるのか?浸水対策と保守
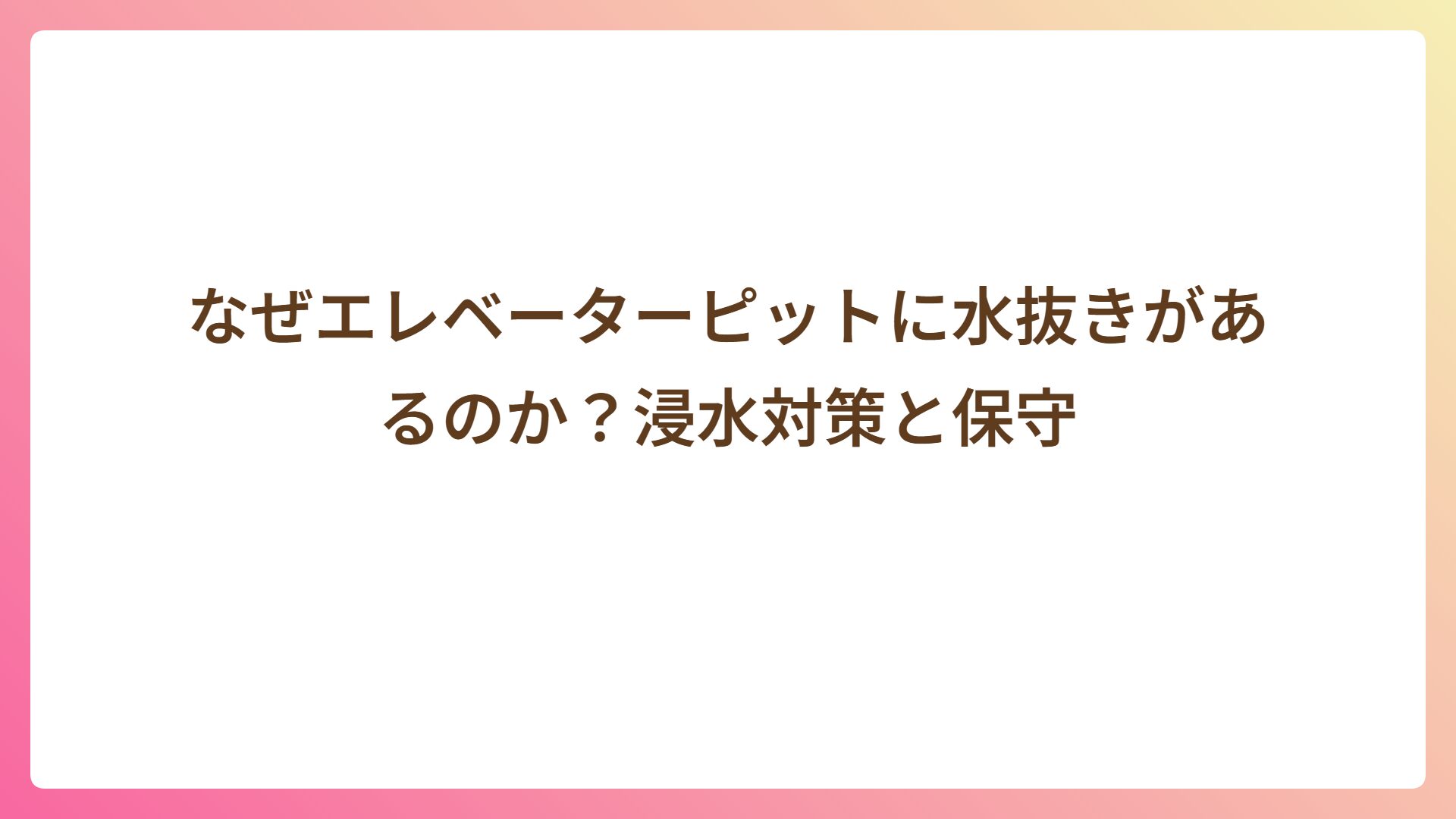
エレベーターの一番下にあるピット(昇降路の底部)には、必ずと言っていいほど水抜きや排水口が設けられています。
なぜ密閉構造のように見える昇降路の底に“水抜き”が必要なのでしょうか?
それは、建物の防水構造と機械保守の両立を目的とした、意外と重要な設計要素なのです。
ピットは“建物の最下点”にあるため水が集まりやすい
エレベーターピットは建物の地下部分や基礎の下に位置し、
建築構造上、最も低い場所に作られる空間です。
そのため、次のような原因で水が溜まりやすい環境になります。
- 地下水の上昇による浸み込み
- 雨水や清掃時の水が階下へ流入
- 配管や冷却水の漏れ
- 結露による水滴の蓄積
もしこの水を放置すると、モーターやブレーキ装置などの制御機器が腐食・絶縁不良を起こし、重大な事故につながるおそれがあります。
そのため、ピットには必ず水抜き孔や排水装置が設けられ、
意図的に水を逃がす構造になっているのです。
“水抜き孔+排水ポンプ”が標準構造
多くのエレベーターピットには、底面に水抜き用の溝(サンプ)が掘られており、
そこに溜まった水を自動的に排出する排水ポンプ(サンプポンプ)が設置されています。
この構造は以下のような仕組みで動作します。
- ピット底に溜まった水が一定量を超えると、
- フロートスイッチ(浮き)が反応してポンプが作動し、
- 建物の排水系統に自動で排出する。
つまり、水抜き孔は水を集める場所であり、
ポンプが“人の代わりに水を外へ逃がす”安全装置なのです。
防水構造ではなく“排水構造”として設計
エレベーターのピットは、完全な防水構造ではありません。
建物基礎と連続しているため、地下水圧や温度差でわずかな浸水を完全に防ぐことは不可能です。
そのため、「水を入れない」よりも「入っても安全に抜ける」ことを前提に設計されています。
この考え方は“防水”ではなく“排水”であり、建築防災と機械安全の折衷点なのです。
法規でも“水抜き設備”が義務付けられている
日本の建築基準法施行令第129条の7および昇降機構造規格では、
エレベーターピットに排水設備または水抜き口を設けることが明記されています。
特に、
- 地下階に設けるエレベーター
- 浸水の可能性がある建物
では、自動排水ポンプまたは手動排水装置の設置が必須です。
これは、万一の浸水時にも機器の故障や感電を防ぐための安全基準です。
定期保守でも“水抜き点検”は重要項目
エレベーターの定期点検では、
ピットの底に水が溜まっていないか、ポンプが正常に作動するかが必ず確認されます。
放置された水は、
- ワイヤーロープの錆
- 油圧装置の漏電
- ピット内のカビ・腐食
といった二次トラブルを引き起こします。
そのため、点検員は定期的に水抜き孔の詰まりや排水動作を確認し、
必要に応じて清掃・再防水処理を行っています。
非常時の“冠水対策”としても機能
豪雨や地下浸水など、建物全体が冠水した場合でも、
ピットの水抜き構造は排水経路として最後まで機能します。
これにより、ポンプ室や電源盤が水没する前にエレベーターの復旧作業を早期に行えるのです。
一部の大型ビルでは、非常用ディーゼルポンプや逆止弁付き排水経路を備え、
完全停電下でも水抜きが可能なシステムを採用しています。
まとめ
エレベーターピットに水抜きがあるのは、
地下水や漏水を逃がして安全を守るための設計だからです。
水は“侵入を完全に防ぐ”よりも、“入っても確実に排出する”ほうが合理的。
そのため、ピットには水抜き孔・溝・排水ポンプが一体化した構造が採用されています。
何気ないその排水口こそ、エレベーターの安全運行を支える縁の下の設備なのです。