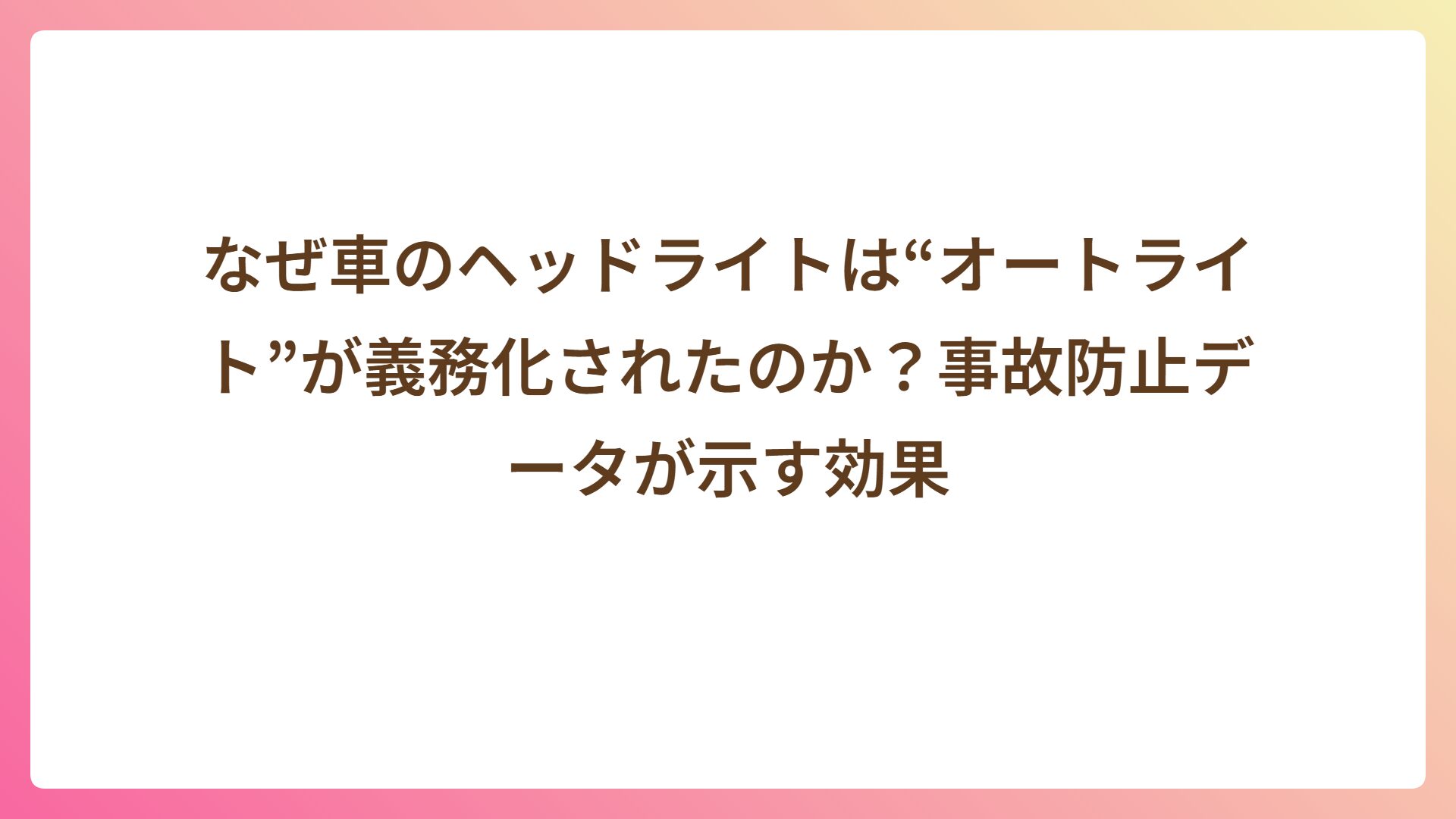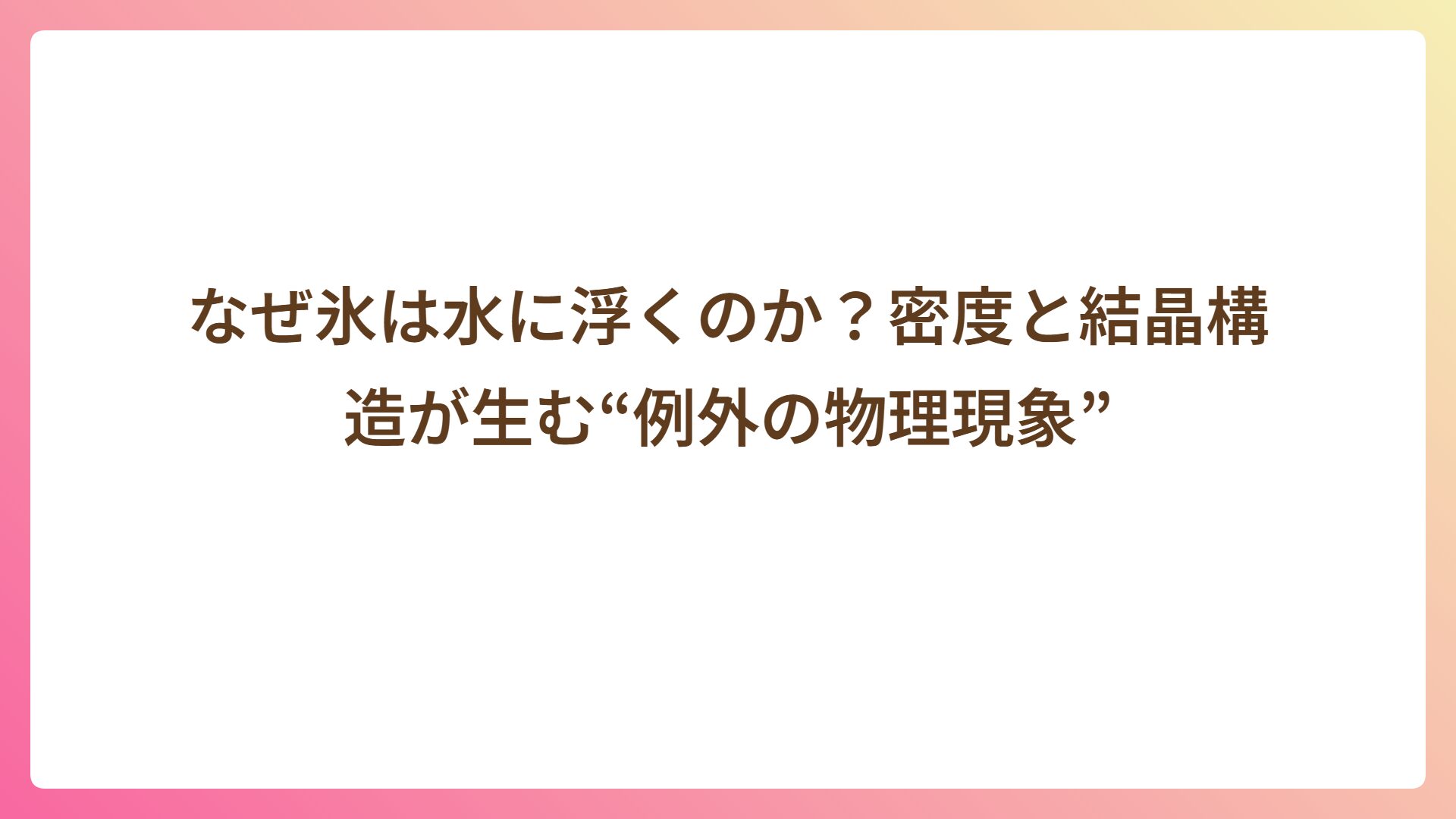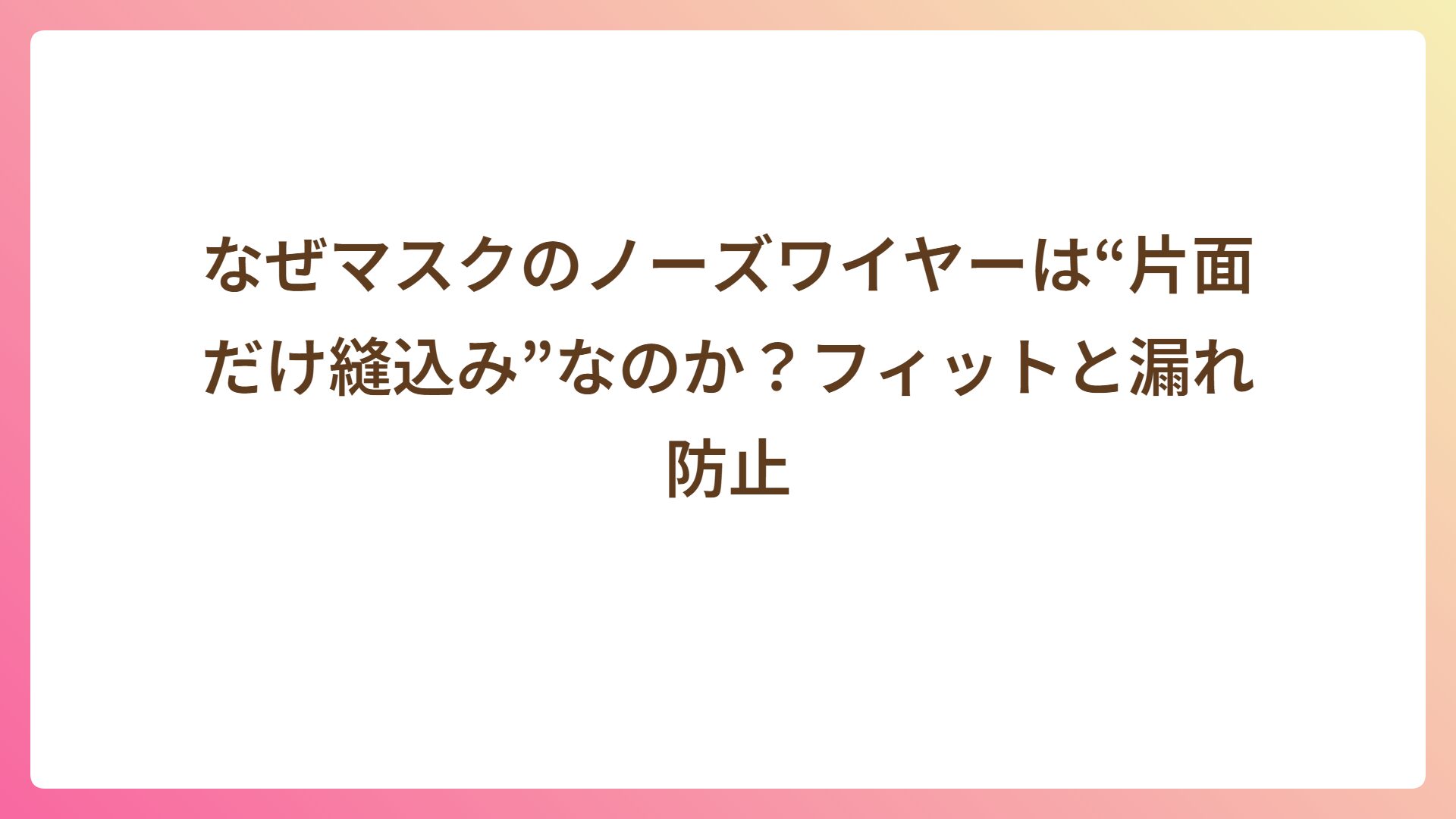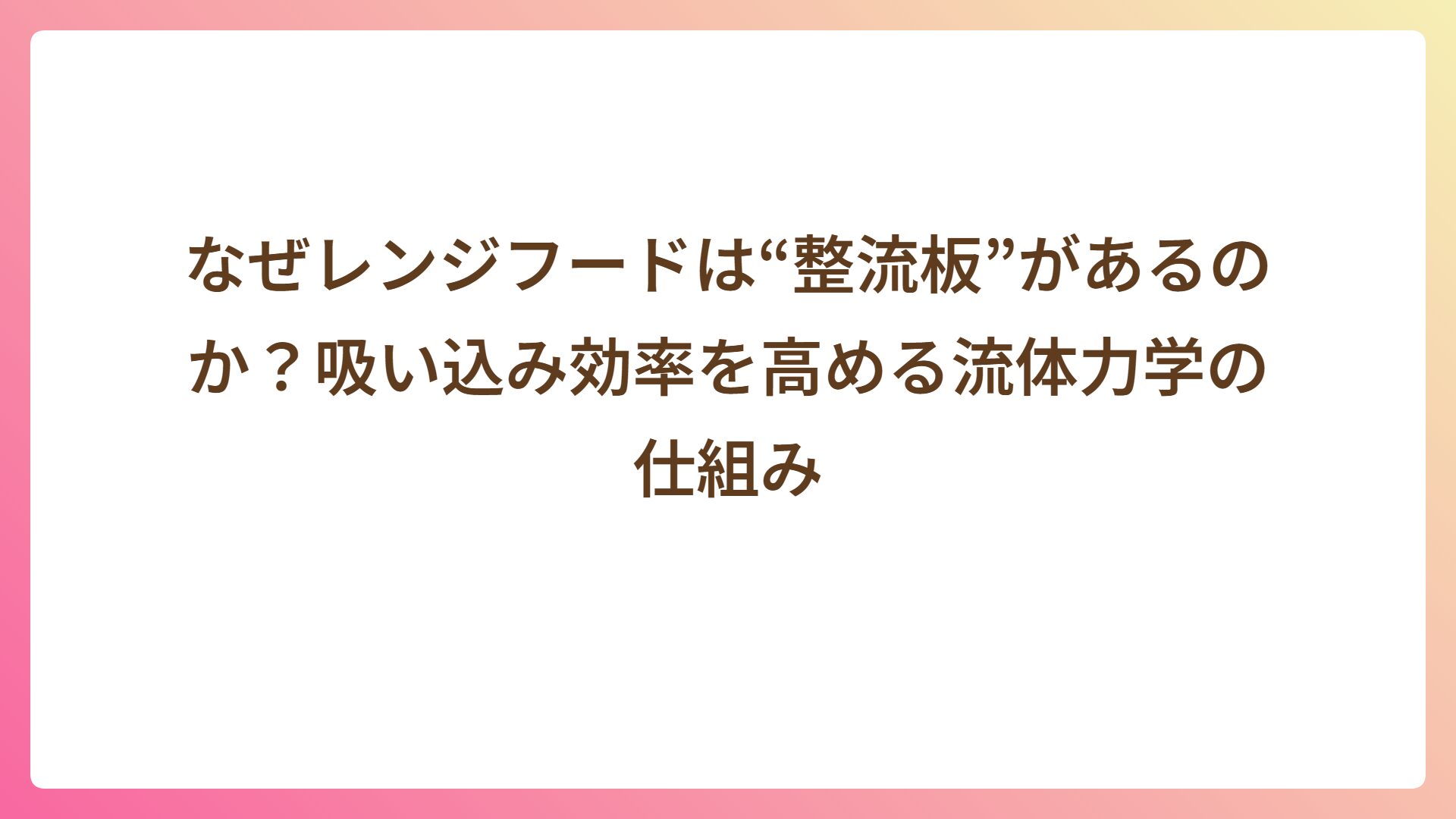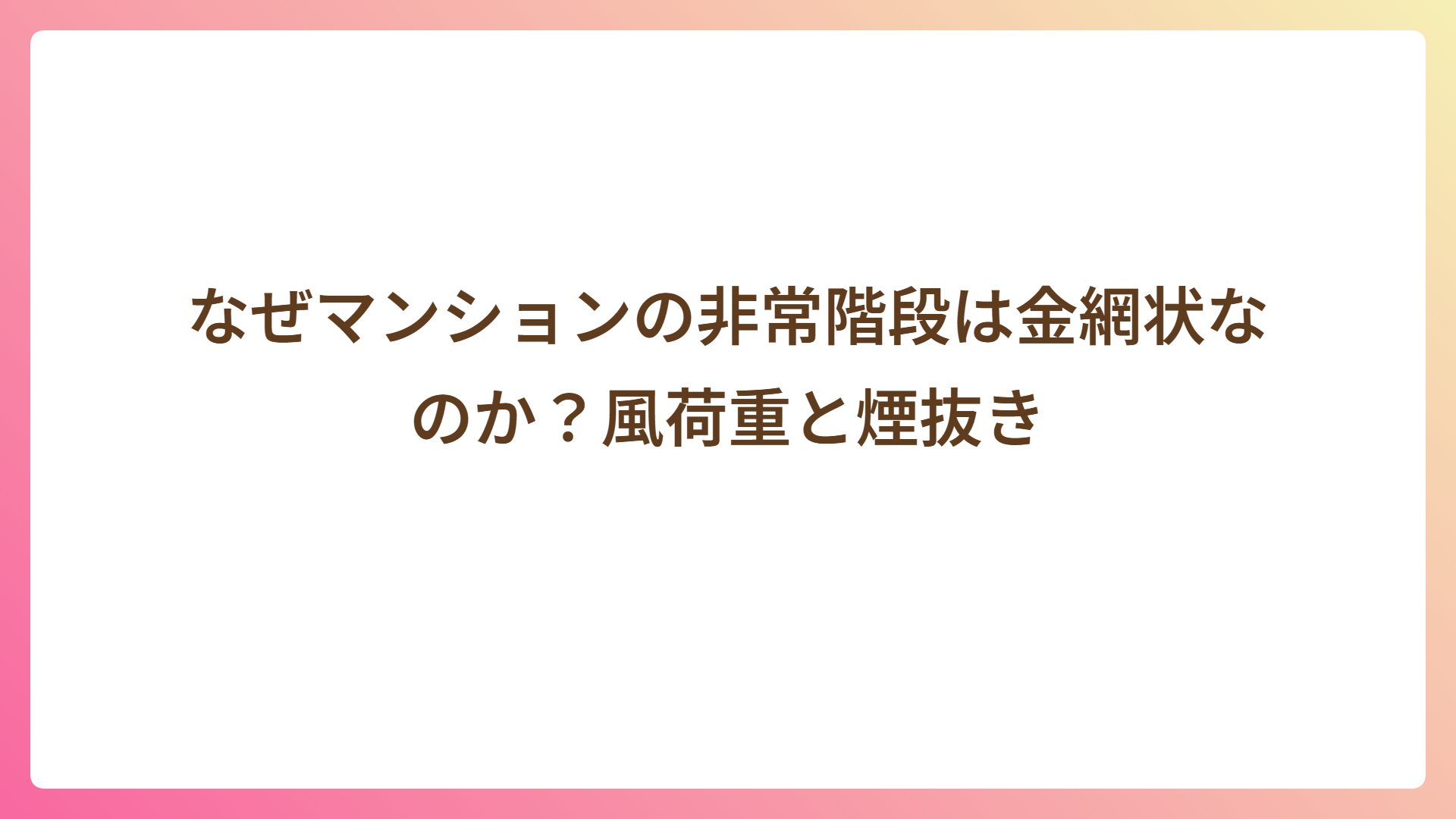なぜエレベーターの「閉」ボタンは“右寄り”なのか?操作頻度と人の利き手の設計思想
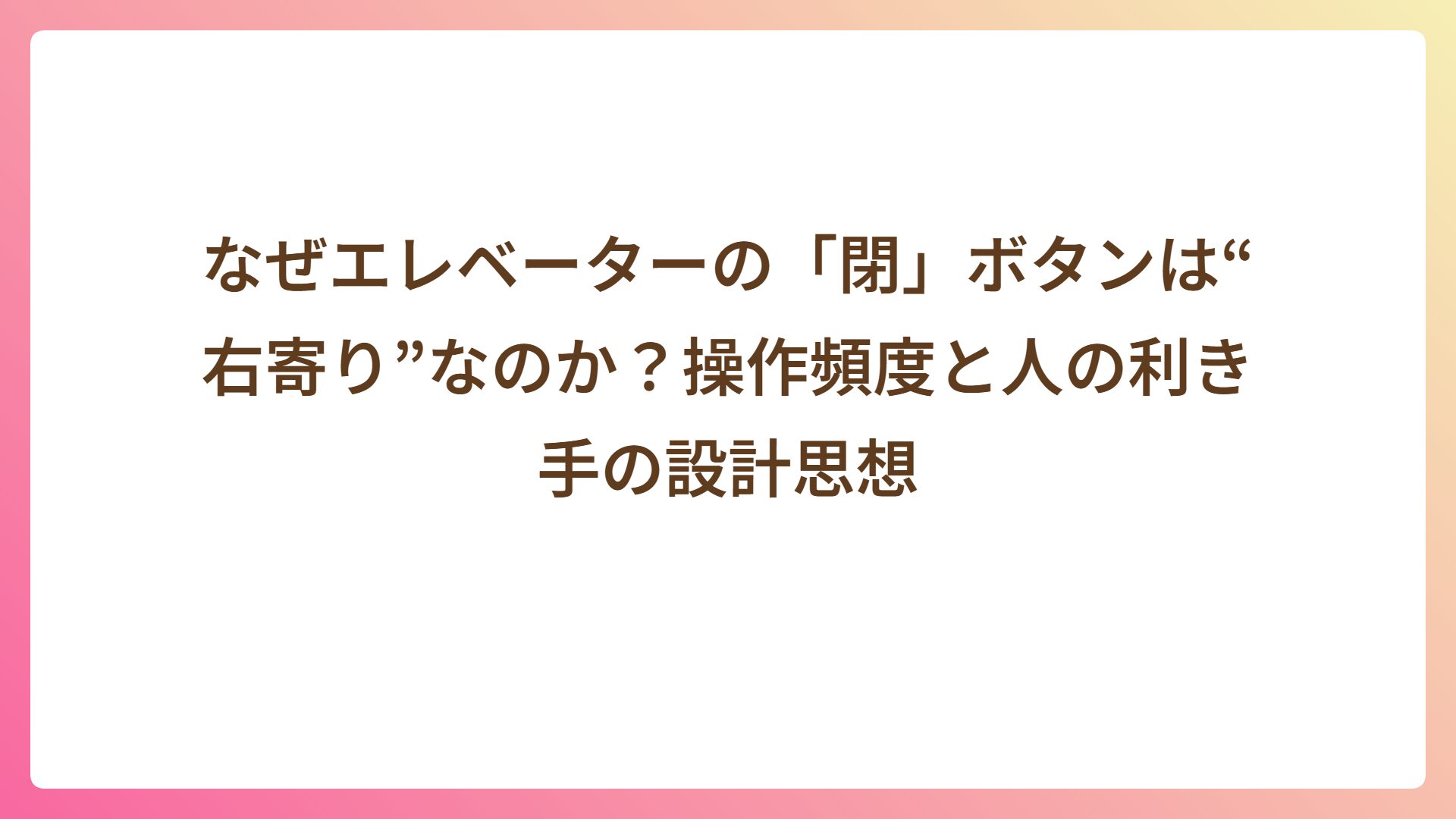
エレベーターに乗るたび、無意識に押している「閉」ボタン。
よく見ると、「開」よりも右側に配置されています。
なぜ左右を逆にしないのでしょうか?
実はこの配置には、人の利き手と使用頻度を徹底的に分析した“人間工学設計”の意図が隠されています。
この記事では、エレベーターの「閉」ボタンが右寄りになっている理由を、操作頻度・安全性・心理的効果の面から解説します。
「閉」が右、「開」が左――実は世界共通の配置
日本だけでなく、海外のエレベーターでも多くは「開(OPEN)」が左、「閉(CLOSE)」が右に配置されています。
この配置は国際的な設計基準(ISO 4190)にも準じており、視覚的にも直感的にも理解しやすいように統一されています。
- 「→ ←」という図形的アイコンで“閉じる動作”を表現
- 「← →」で“開く動作”を表現
左右のボタン配置をこれに合わせることで、見た瞬間に意味が伝わるデザインになっているのです。
理由①:「閉」ボタンのほうが“圧倒的に使用頻度が高い”
日常のエレベーター利用では、多くの人が閉ボタンを押す習慣があります。
特に日本では「他の人を待たせない」「ドアを早く閉めたい」という文化的背景もあり、
「閉」ボタンが押される回数は「開」ボタンの数倍にのぼります。
そのため、使用頻度の高い「閉」を操作しやすい右側(利き手側)に配置することで、
- 片手で自然に押せる
- ボタンの誤操作を防ぐ
- 操作感がスムーズ
といった快適性と効率性が向上します。
理由②:右利きが圧倒的多数だから
人間工学設計の基本は「右利き基準」です。
世界人口の約9割が右利きであることから、
- ドアの開閉スイッチ
- 家電の操作パネル
- ATM・券売機のテンキー配置
など、多くの機器は右手で扱いやすいよう設計されています。
エレベーターも同様で、右手でボタンを押しやすい位置に「閉」を配置し、
左側の「開」は補助的・安全用として扱うのが自然なのです。
理由③:「閉」は“意図的に押す”、一方「開」は“緊急時に押す”
エレベーターの設計思想では、
- 「閉」=利用者が自分の判断で積極的に押すボタン
- 「開」=他人や障害物への配慮・緊急対応で押すボタン
と位置づけられています。
つまり「閉」は主操作ボタンであり、
いつでも押しやすい右側に置くことが合理的です。
逆に「開」は安全・補助ボタンのため、あえて左側に分けて誤操作を防ぐ狙いがあります。
理由④:視覚的な流れも“右方向=閉じる”が自然
人の視線や動作には「左→右」方向への自然な流れがあります。
これは文字を読む方向や映像表現などでも共通する文化的な認知特性です。
- 「開く」動作=外向き(左へ)
- 「閉じる」動作=内向き(右へ)
このように、視覚的な動きとボタン位置を一致させることで、
無意識でも直感的に押し間違えにくい配置となっています。
理由⑤:操作盤の配置と立ち位置のバランス
エレベーターの操作盤は通常、ドアの右側の壁面に設置されています。
利用者はドアに向かって立ち、右手で自然にボタンを押す姿勢になります。
このとき、
- 右側に「閉」
- その隣に「開」
と配置することで、身体の向きと手の動きが一致します。
逆に「開」が右側にあると、手首を不自然にひねる必要があり、操作性が悪化します。
特殊なケース:左利き対応や車椅子対応エレベーター
一部の公共施設やバリアフリー設計のエレベーターでは、
操作盤を左右両側に配置したり、
ボタンを縦一列にして左右の差をなくすタイプも存在します。
これは左利き利用者や車椅子利用者にも配慮した設計で、
「右開き文化」に偏らないよう、ユニバーサルデザイン化が進んでいる例です。
まとめ:「閉」が右は“最も自然で安全な設計”
エレベーターの「閉」ボタンが右側にあるのは、
- 右利きが多く、操作性が高い
- 使用頻度が高い「閉」を主操作として配置
- 「開」を誤操作しにくい位置に分離
- 視覚的にも“右=閉じる”が自然
- 構造的に右手で押しやすい位置関係
という、人間の行動と安全性を徹底的に考えた結果です。
つまり、「閉」が右側にあるのは偶然ではなく、
“右手社会”に最適化されたユニバーサル設計の結晶なのです。