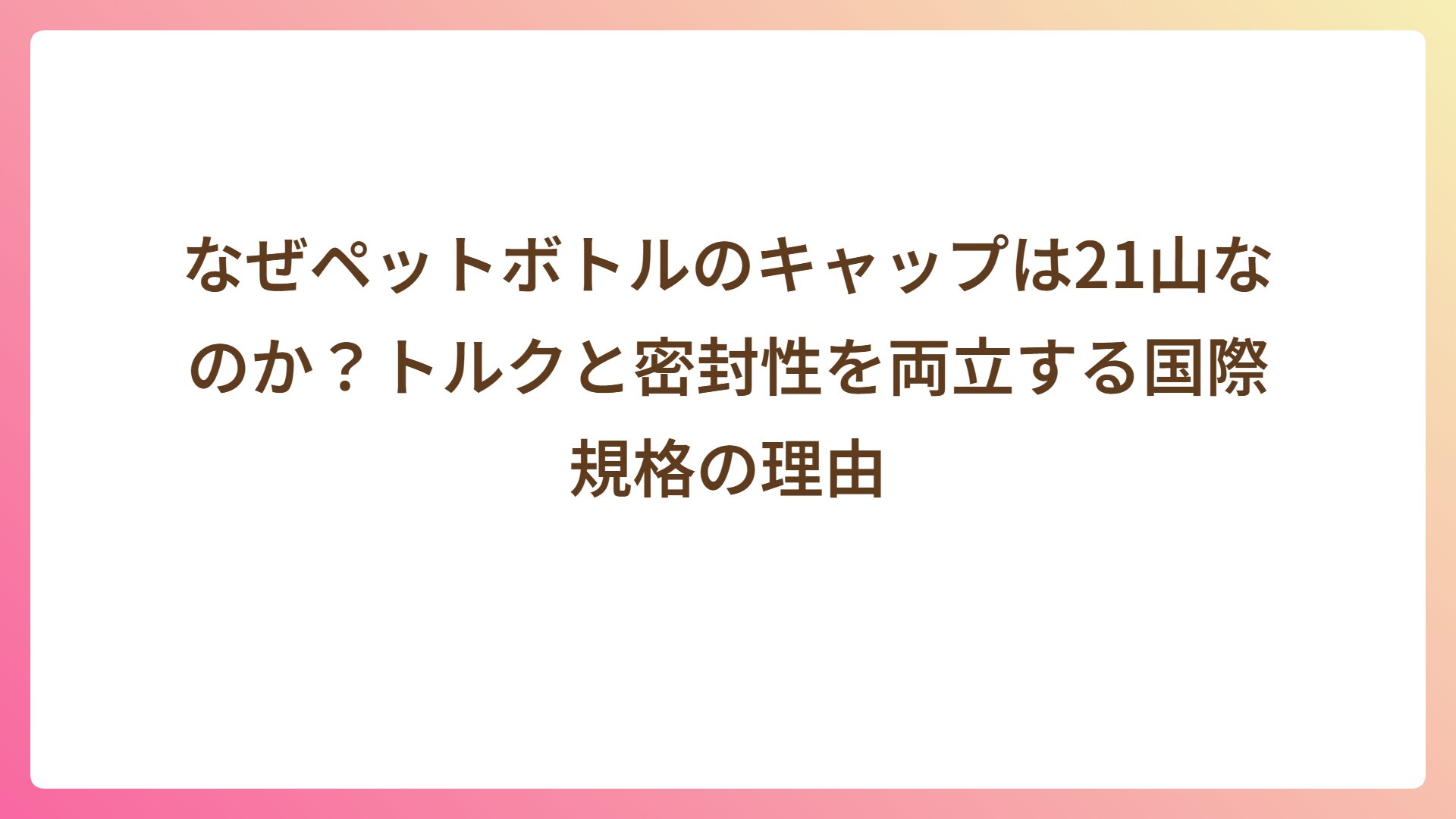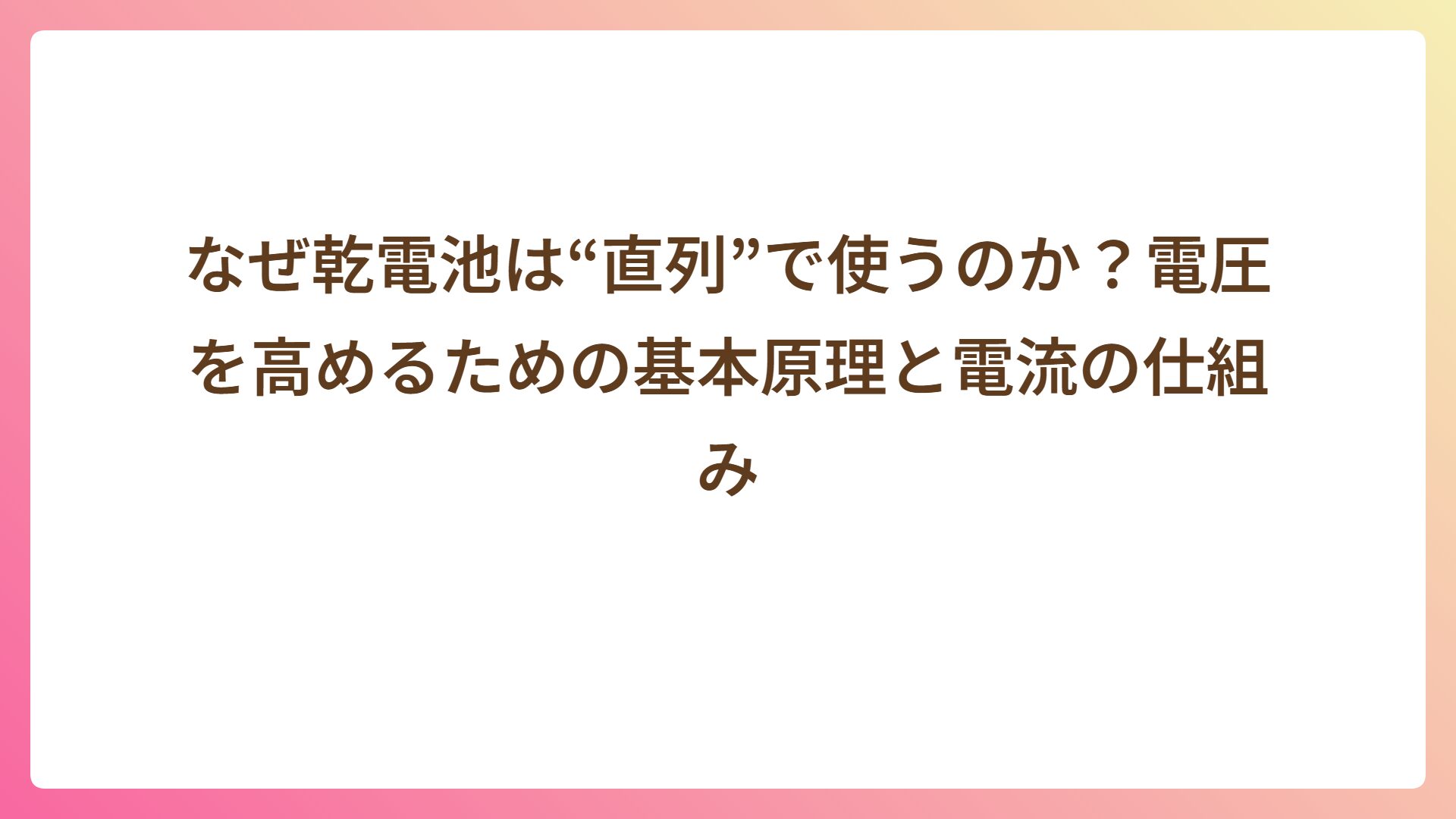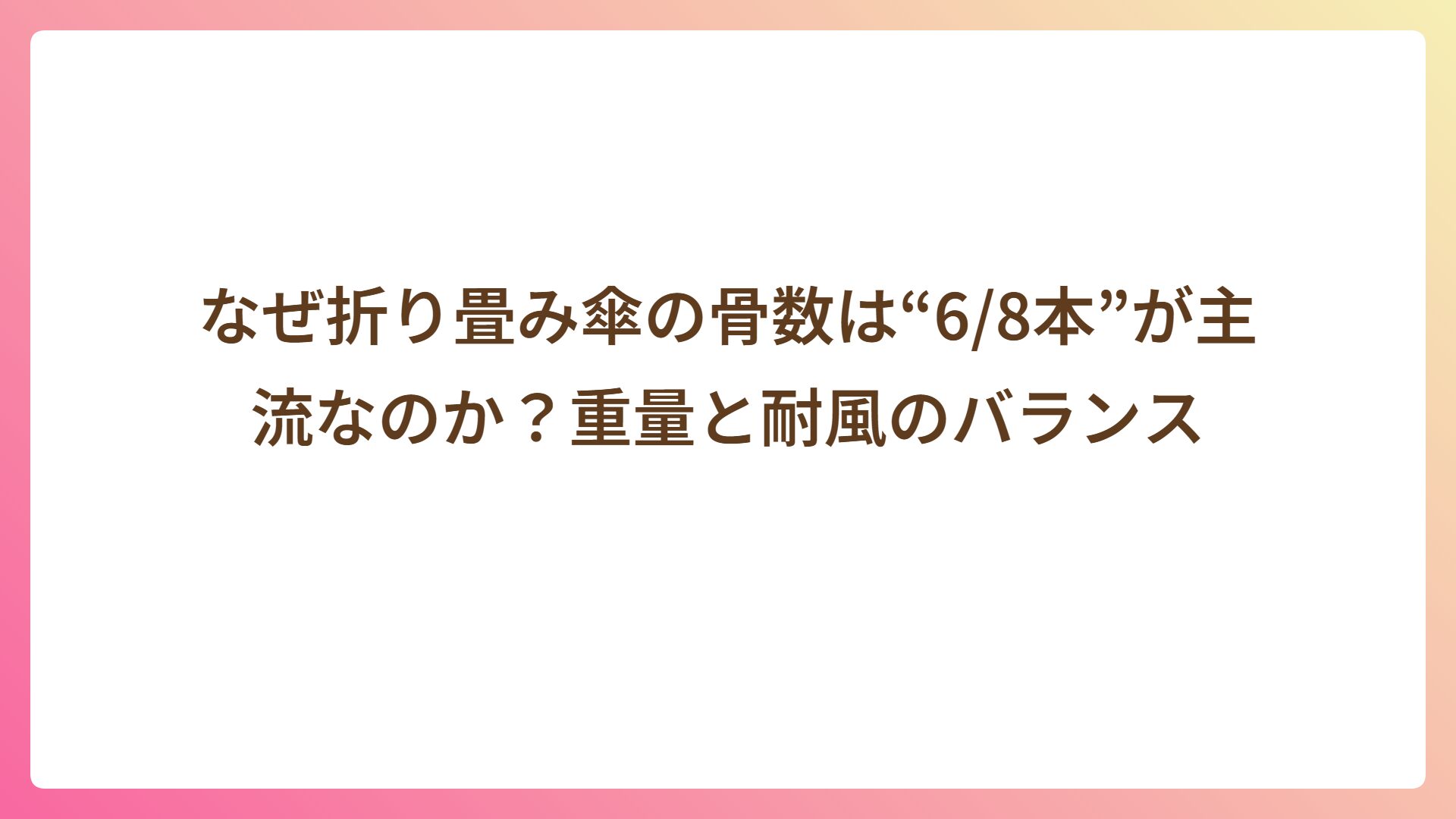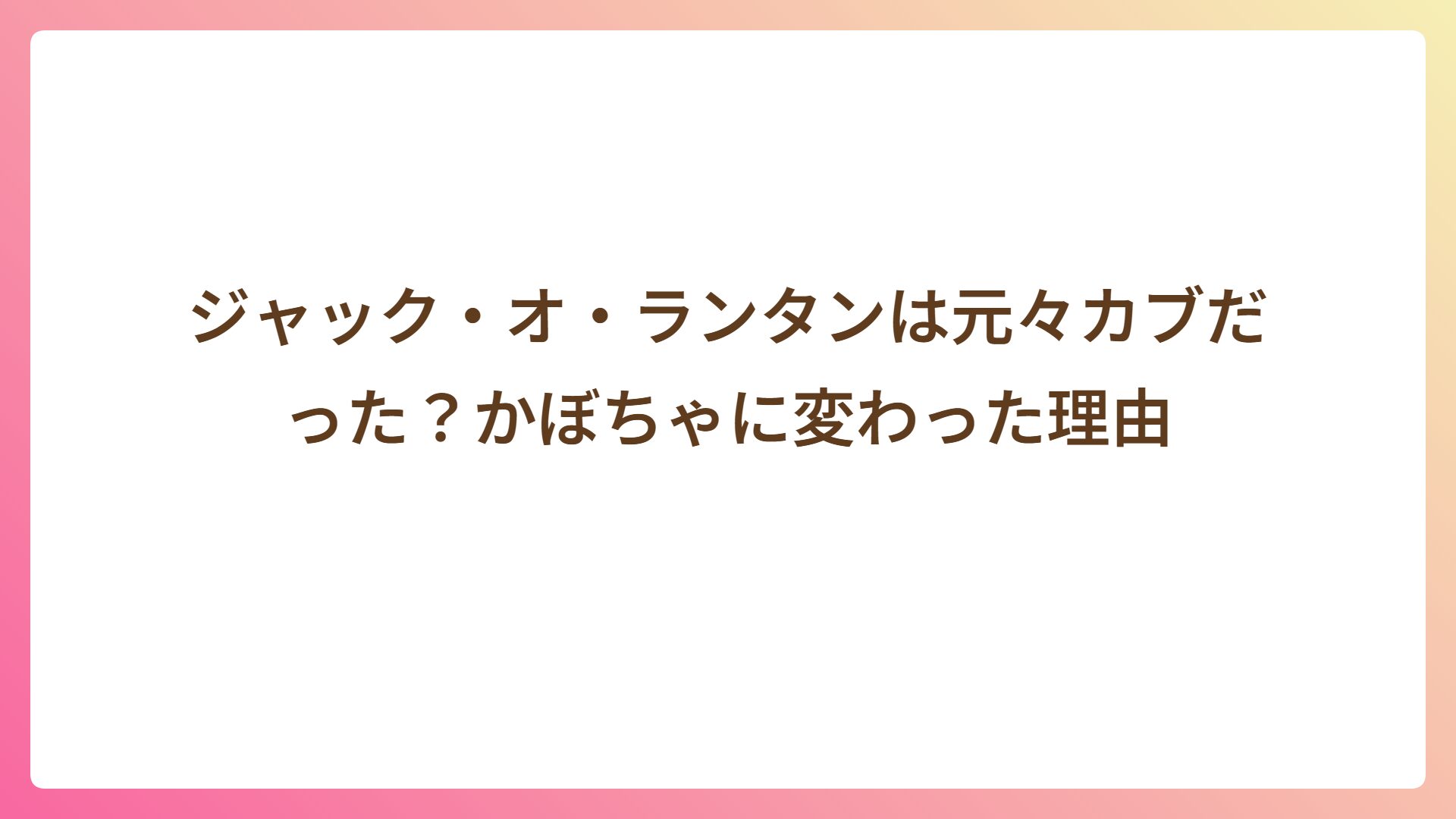なぜ絵馬は“馬の形”から板へ変わったのか?供物の変遷
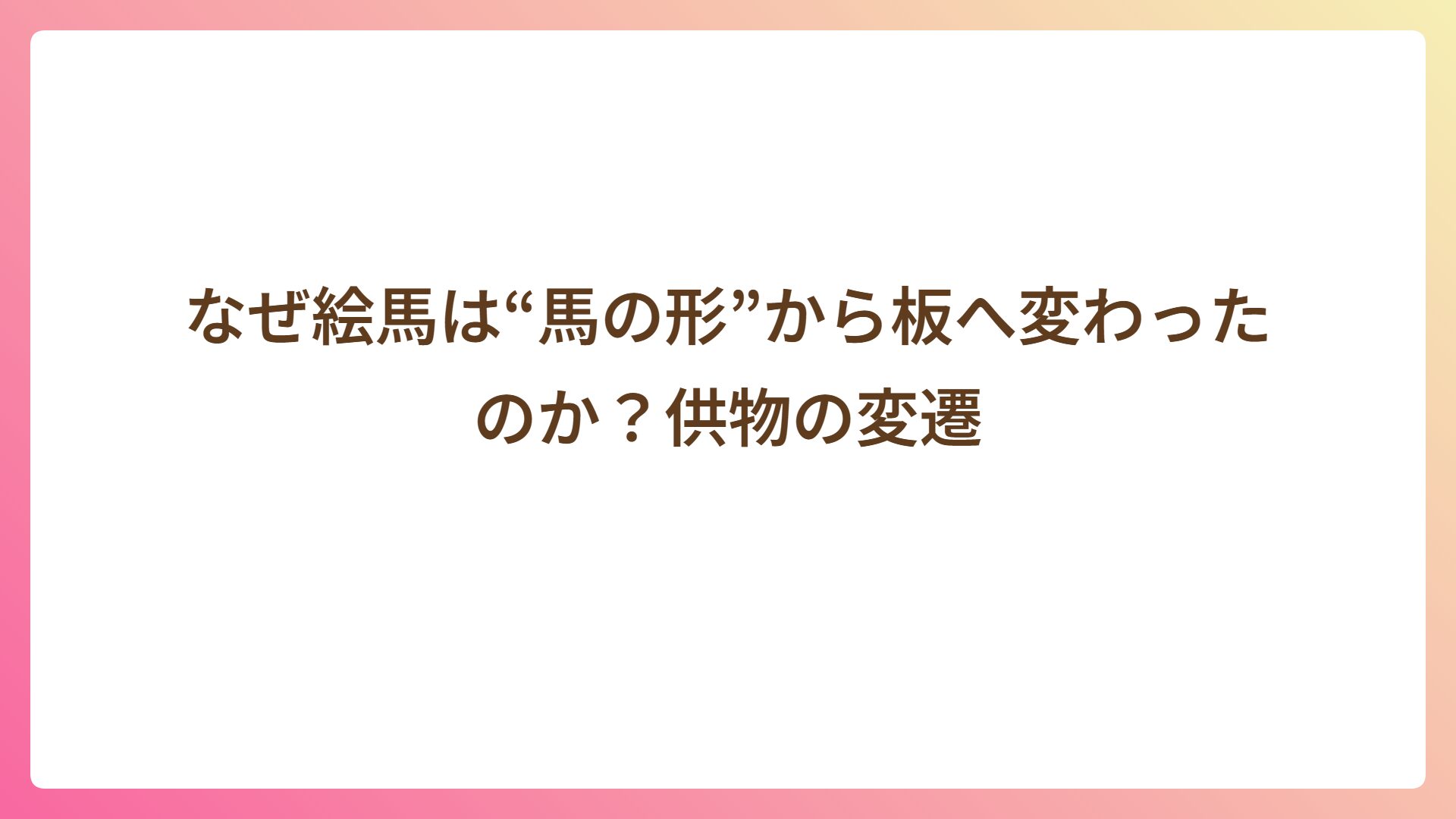
神社の境内で見かける絵馬は、願いごとを書いて奉納するおなじみの存在です。
しかし、なぜ「馬」の絵なのか、なぜ板の形になったのか――。
その背景には、古代の供物文化と信仰の合理化がありました。
絵馬の原型は“本物の馬”だった
もともと絵馬は、願いを神に届けるために生きた馬を奉納する習慣から始まりました。
馬は古代日本において、**神の乗り物(神馬/しんめ)**と考えられ、
雨乞いや豊作祈願、国家の安泰などの祈りの際に神前へ捧げられました。
この風習は『日本書紀』にも記録があり、
天武天皇の時代(7世紀頃)にはすでに「白馬=晴れ」「黒馬=雨」のように、
馬の毛色によって祈願の内容を表す信仰が行われていたとされます。
しかし、実際に馬を奉納することは、
費用も管理も大きな負担を伴うため、やがて象徴的な代替物が用いられるようになります。
実物から“木製の模型”へ
奈良〜平安時代になると、馬の代わりに木や土で作られた馬の像が奉納されるようになります。
この小型化は、経済的負担を減らしながらも信仰を続けるための工夫でした。
やがて、木馬を奉納する代わりに馬の絵を描いた板を奉げる形に簡略化され、
これが現在の絵馬の原型となります。
つまり、「絵の中の馬」が、実際の神馬の象徴として祈りを担うようになったのです。
“板絵の馬”が庶民に広まる
鎌倉時代以降、寺社文化が庶民に広がると、
絵馬は特定の階級に限らない一般的な祈願の道具となりました。
当初は大きな板に馬を描いて神社に奉納するもので、
職人による本格的な絵画作品としての側面もありました。
その後、江戸時代に入ると、参詣者が持参できるように小型の板絵馬が普及します。
これにより、庶民も「個人の願い」を神に伝えられるようになり、
絵馬は祈願の民主化を象徴する存在となりました。
馬以外の絵柄が増えていった理由
江戸期には、絵馬の題材が馬以外にも広がります。
安産祈願なら「犬」、商売繁盛なら「米俵」や「小判」、
病気平癒なら「体の患部」など、願いごとに応じた絵柄が描かれるようになりました。
それでも「絵馬」という呼び名が残ったのは、
あくまで起源が“馬の絵”であり、祈願の象徴=馬という伝統を引き継いでいたからです。
今日でも、多くの神社では馬が描かれた意匠が標準で使われています。
神社が“板の形”を採用した理由
板状の絵馬が定着した背景には、奉納の管理と保存のしやすさがあります。
木の板なら壁や棚にかけて保管でき、参拝者が自由に奉納できる。
また、墨や絵具で願いを書き入れることで、
**「言葉と絵が融合した祈り」**という新たな形が生まれました。
この構造は、神社の建築や儀礼にもうまく調和し、
江戸後期には全国の神社で絵馬掛け所(絵馬堂)が設けられるほど普及しました。
まとめ:絵馬は“祈りを絵に託す進化の記録”
絵馬が馬から板へ変わった背景をまとめると、次の通りです。
- 本来は神への供物として実際の馬を奉納していた
- 負担軽減のため、木馬→絵に描いた馬へと簡略化された
- 江戸時代に庶民が扱える小型の板絵馬が普及した
- 願いに応じて絵柄が多様化し、形式としての「絵馬」が定着した
つまり絵馬は、供物としての馬が“祈りの象徴”へと変化した文化の記録なのです。
一枚の板に描かれた馬や文字は、神に願いを届けると同時に、
人々が時代ごとに工夫を重ねながら祈りを形にしてきた証でもあります。