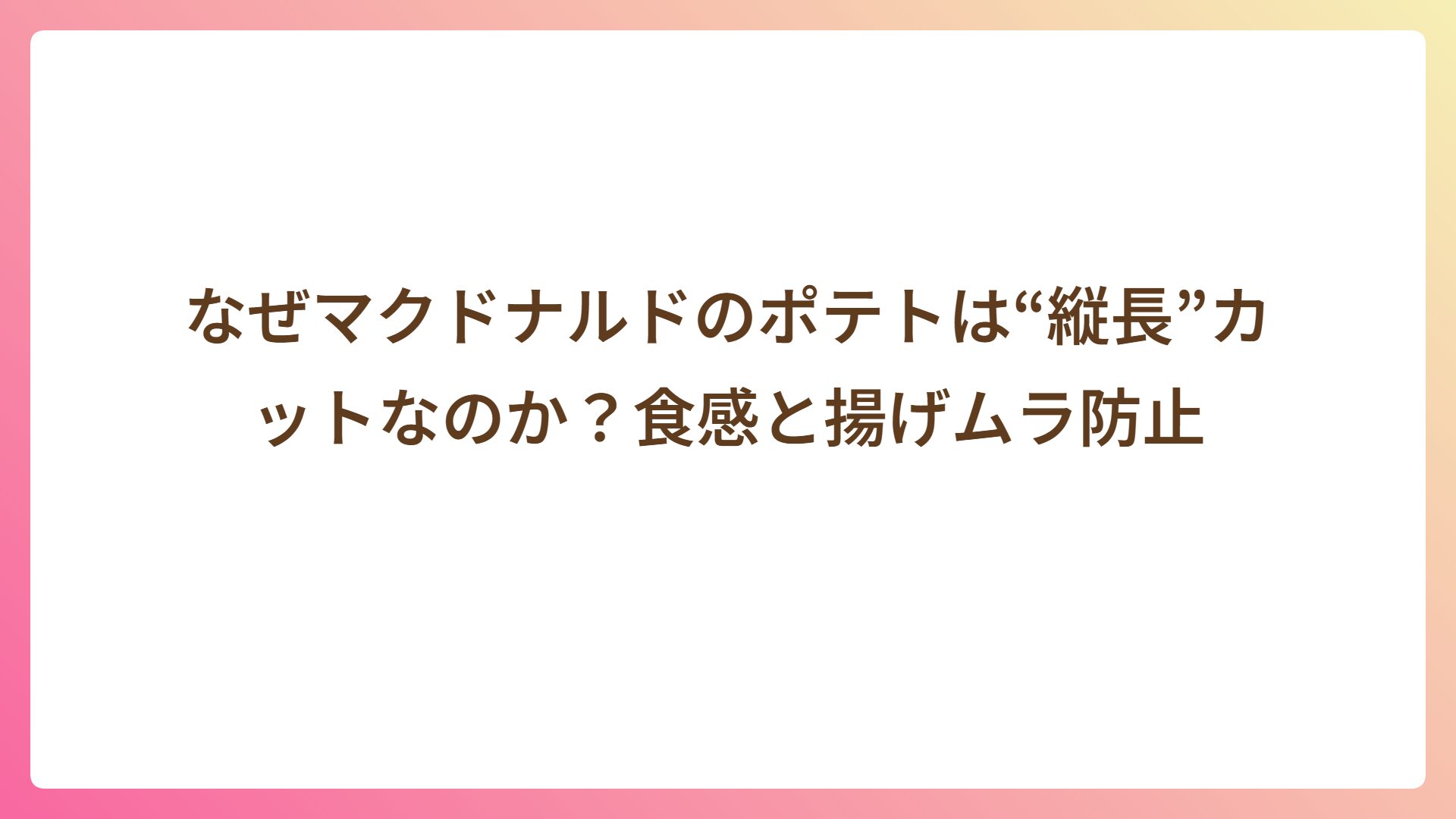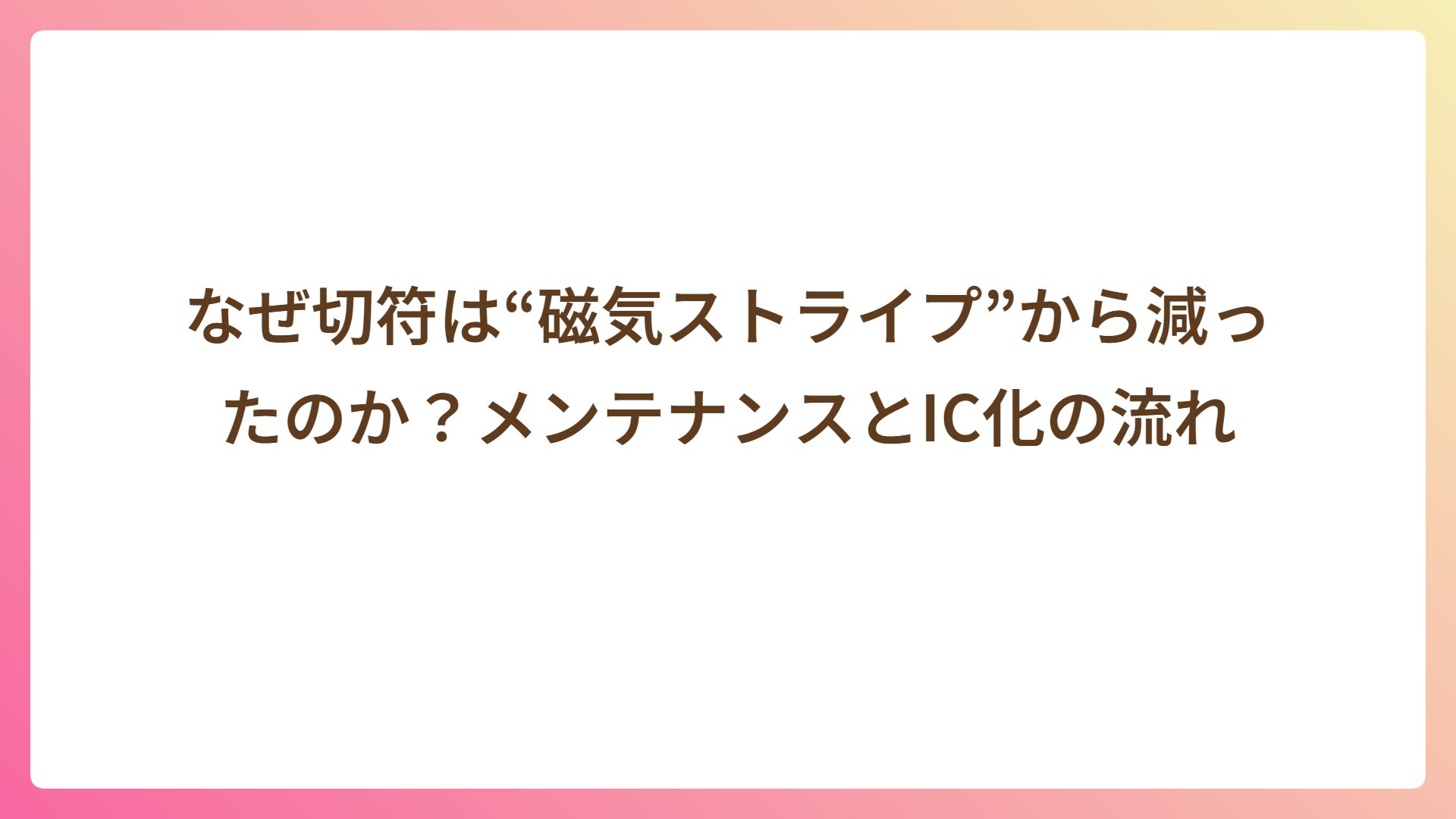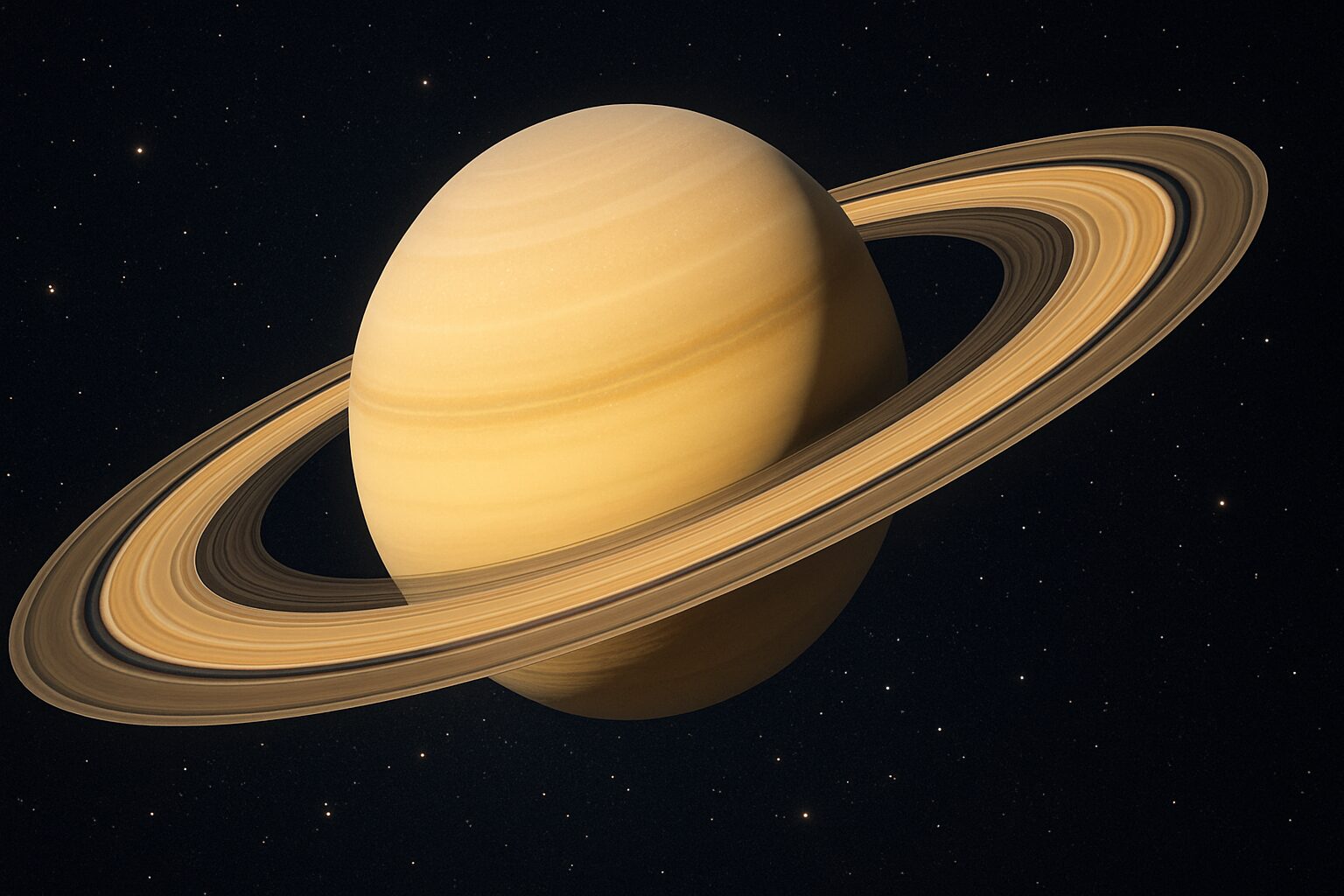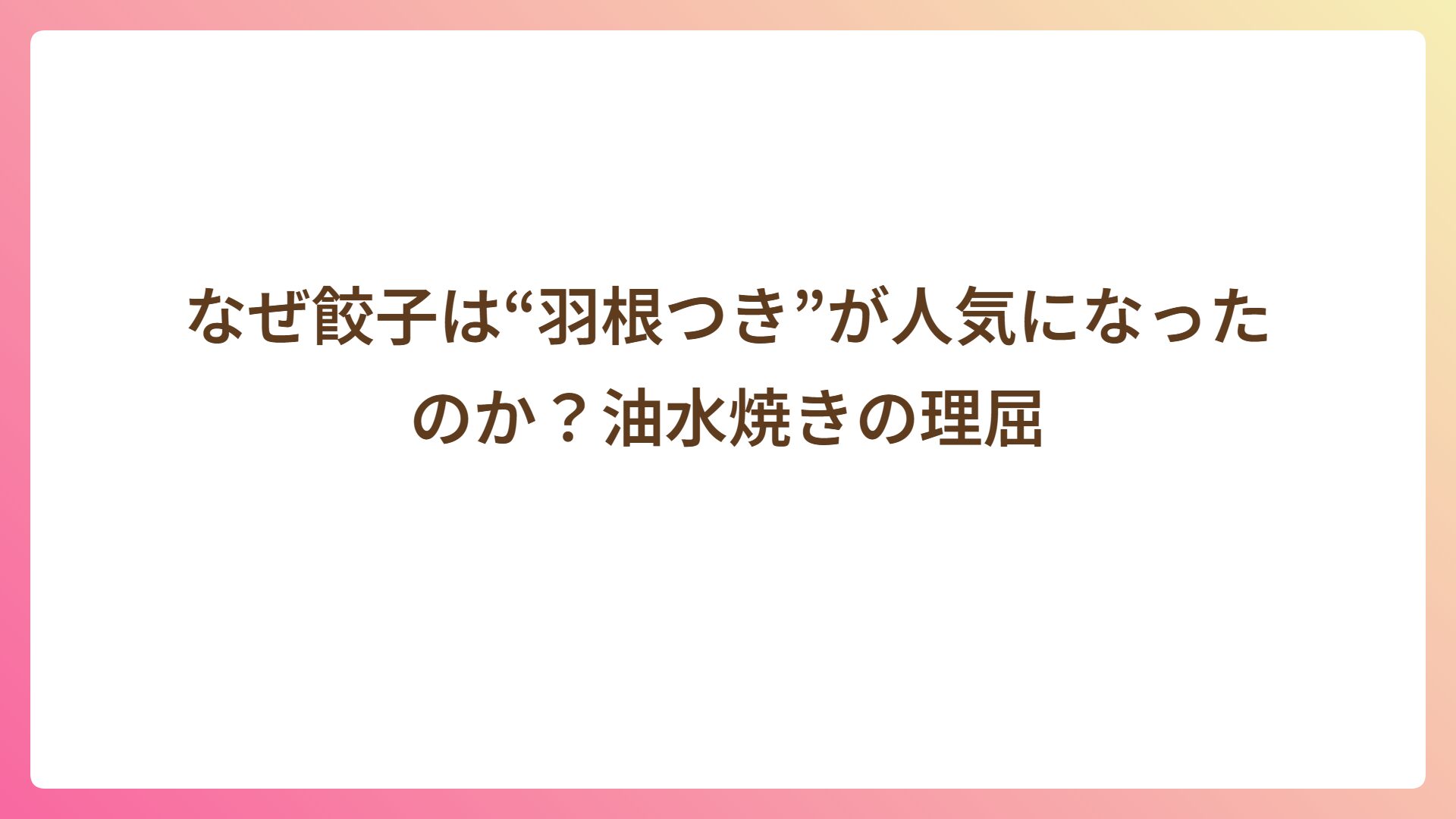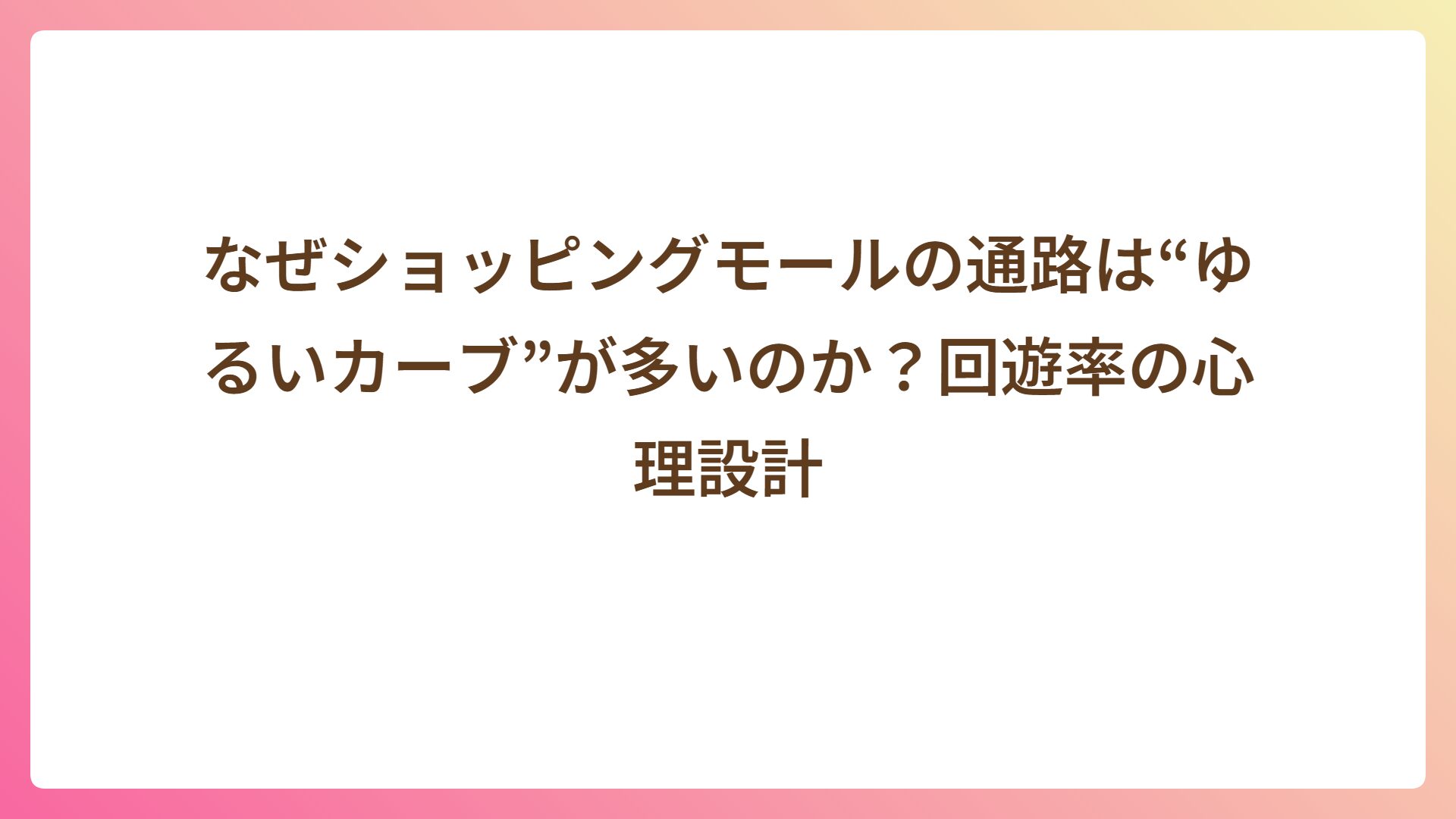なぜガソリンスタンドのホースは“上から”垂れているのか?左右どちらからも給油できる構造
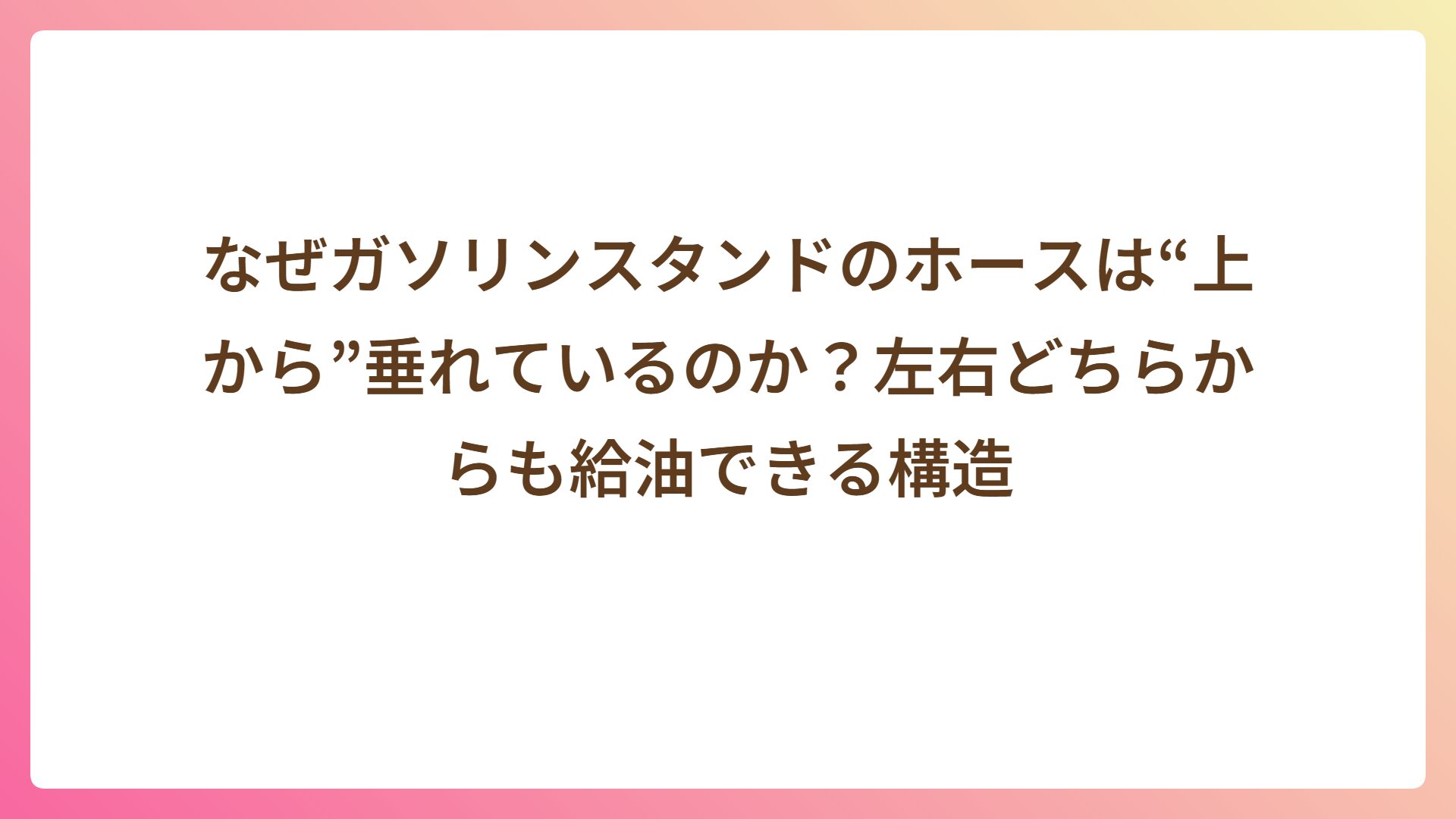
ガソリンスタンドに入ると、給油機のホースが“上から垂れ下がっている”ことに気づきます。
地面からではなく、天井やアームから伸びているのはなぜでしょうか?
実はこの構造、どんな車でもスムーズに給油できるように考え抜かれた設計なのです。
今回は、ガソリンスタンドのホースが上から吊り下げ式になっている理由を、安全性・効率・車種対応の視点から解説します。
かつては“下から”伸びるタイプが主流だった
昔のガソリンスタンドでは、ホースは給油機の下部から伸びていました。
この方式は構造が単純で、メンテナンスもしやすい反面、
- ホースが地面を引きずって汚れる
- 車体やタイヤに擦れて劣化しやすい
- 左右どちら側の給油口にも対応しにくい
といった問題がありました。
特に近年は、車種によって給油口が左側・右側どちらにも存在するため、
下からのホースでは「給油機の向きに制限が出る」ことが課題となっていました。
“上から吊る”ことで左右どちらの車にも対応できる
現在主流の天井吊り下げ式(オーバーヘッド型)では、ホースが天井のアームやリールからぶら下がっています。
これにより、
- 左右どちらの給油口にもホースを伸ばせる
- 給油機の正面・背面どちらからでも使える
- 車の停め方に関わらずスムーズに届く
という柔軟性が得られます。
つまり、給油口の位置が異なる車を1台の給油機で対応できるようになったのが、
上吊り式が採用された最大の理由です。
安全面の配慮:ホースが地面に触れない構造
上から吊ることで、ホースが地面に接触せず、
- 摩耗・汚れの軽減
- 車のタイヤで踏まれるリスクの防止
- 灯油やガソリン滴下による火災リスクの低減
といった安全性の向上も実現しています。
さらに、吊り下げ部分にはバネ式リールが内蔵されており、
ホースを引っ張ると必要な長さだけ伸び、離すと自動で巻き戻る構造になっています。
このため、ホースが垂れすぎて邪魔になったり、地面に触れたりすることもありません。
給油機の上部には“天井配管システム”がある
上吊り式のホースは、単に上から垂らしているだけではなく、
天井の内部には燃料を送る配管(パイプライン)が通っています。
タンクから天井を経由して各給油機へ燃料を分配することで、
- 地面下の配管よりも漏れ点検が容易
- 地下タンク周辺の工事が簡略化
- 配線・照明などの保守も同時に行いやすい
というメンテナンス性の向上にもつながっています。
作業効率の向上と“セルフ化”への適応
上吊り式ホースは、スタッフが動き回るフルサービス型でも、
運転者自身が操作するセルフスタンド型でも扱いやすい構造です。
セルフ給油では、
- ホースを引き出すだけで車のどの位置にも届く
- 給油中に絡まりにくく、戻すのも簡単
- 店舗側のレイアウトを自由に設計できる
といった利点があり、セルフスタンド普及の背景にもこの構造の進化があります。
海外との違い:地面固定型も残る
欧米の一部では、いまだにホースが下から出ているタイプもあります。
これは、車種の給油口位置が右側に統一されていたり、
安全基準・建築構造の違いにより上吊り配管が導入しにくい場合があるためです。
一方、日本では多様な車種(輸入車を含む)が走るため、
左右どちらからでも給油できる柔軟性が重視され、上吊り式が一般化しました。
まとめ:上吊りホースは“全車対応と安全性”の合理設計
ガソリンスタンドのホースが上から垂れているのは、
- 左右どちらの給油口にも対応できるため
- 地面を汚さず安全性を高めるため
- メンテナンス性・作業効率を向上させるため
という複数の理由が組み合わさった結果です。
つまり、あの上からぶら下がるホースは、見た目のためではなく「すべての車に安全かつ効率的に給油する」ための最適解なのです。