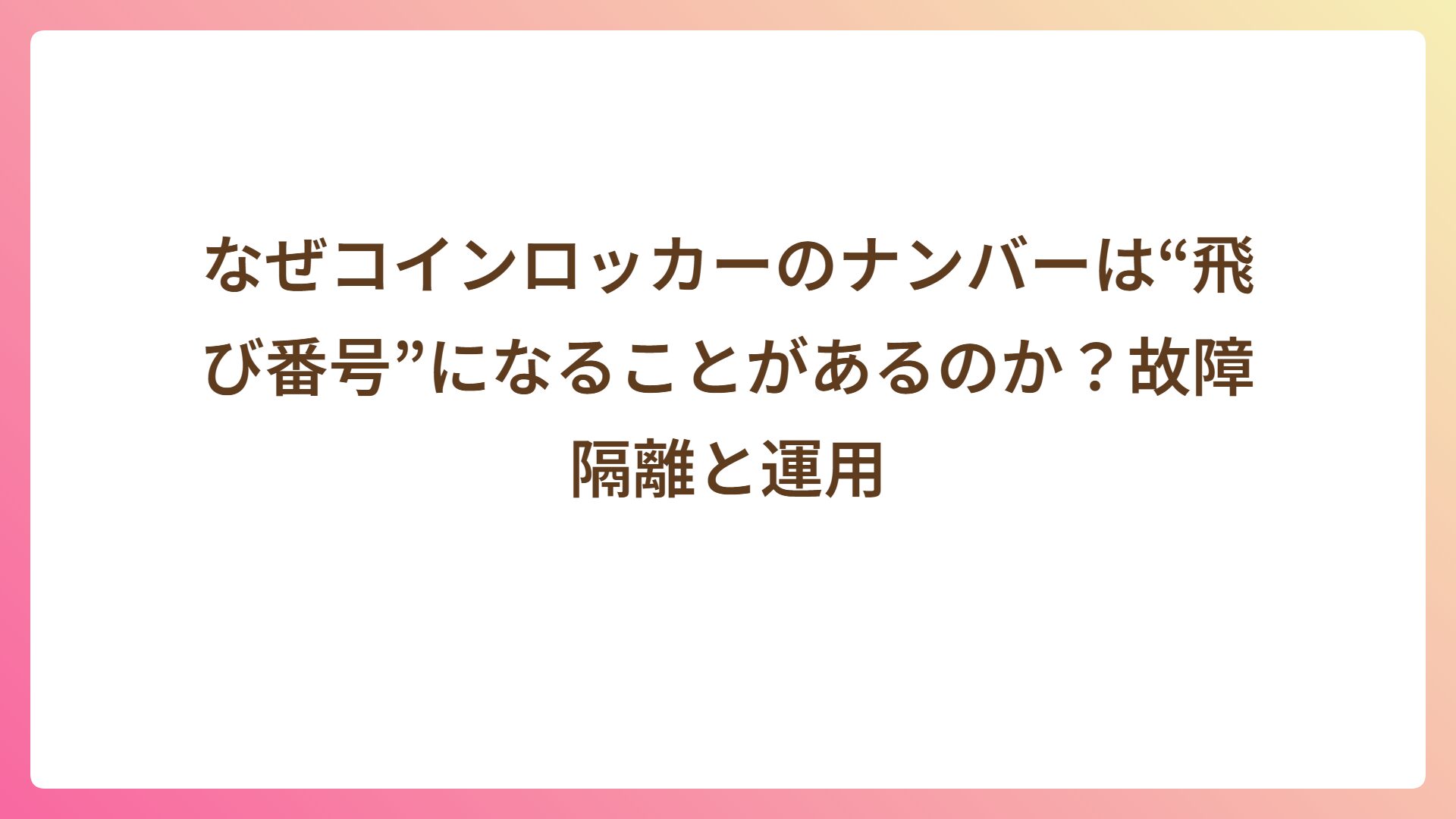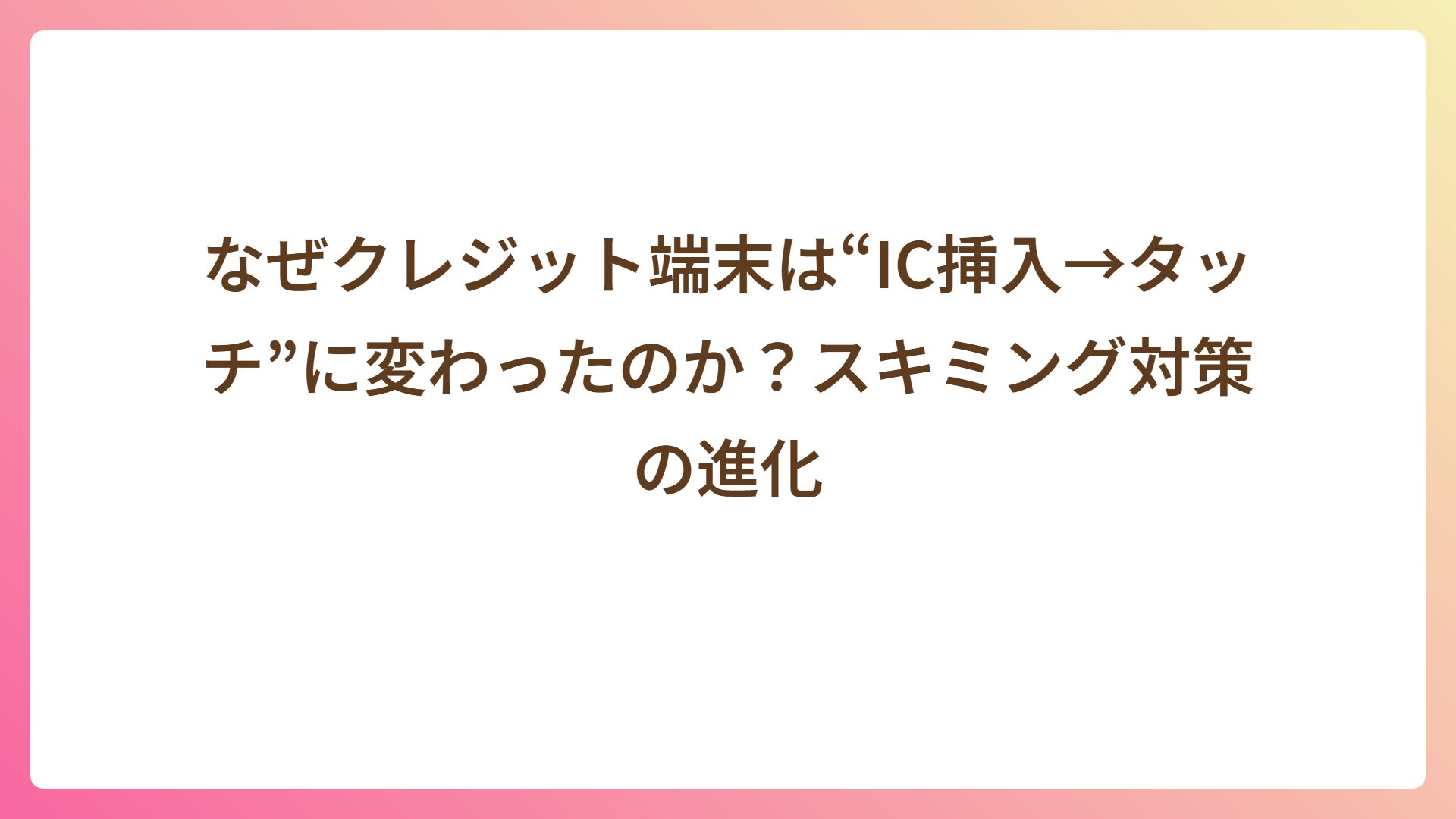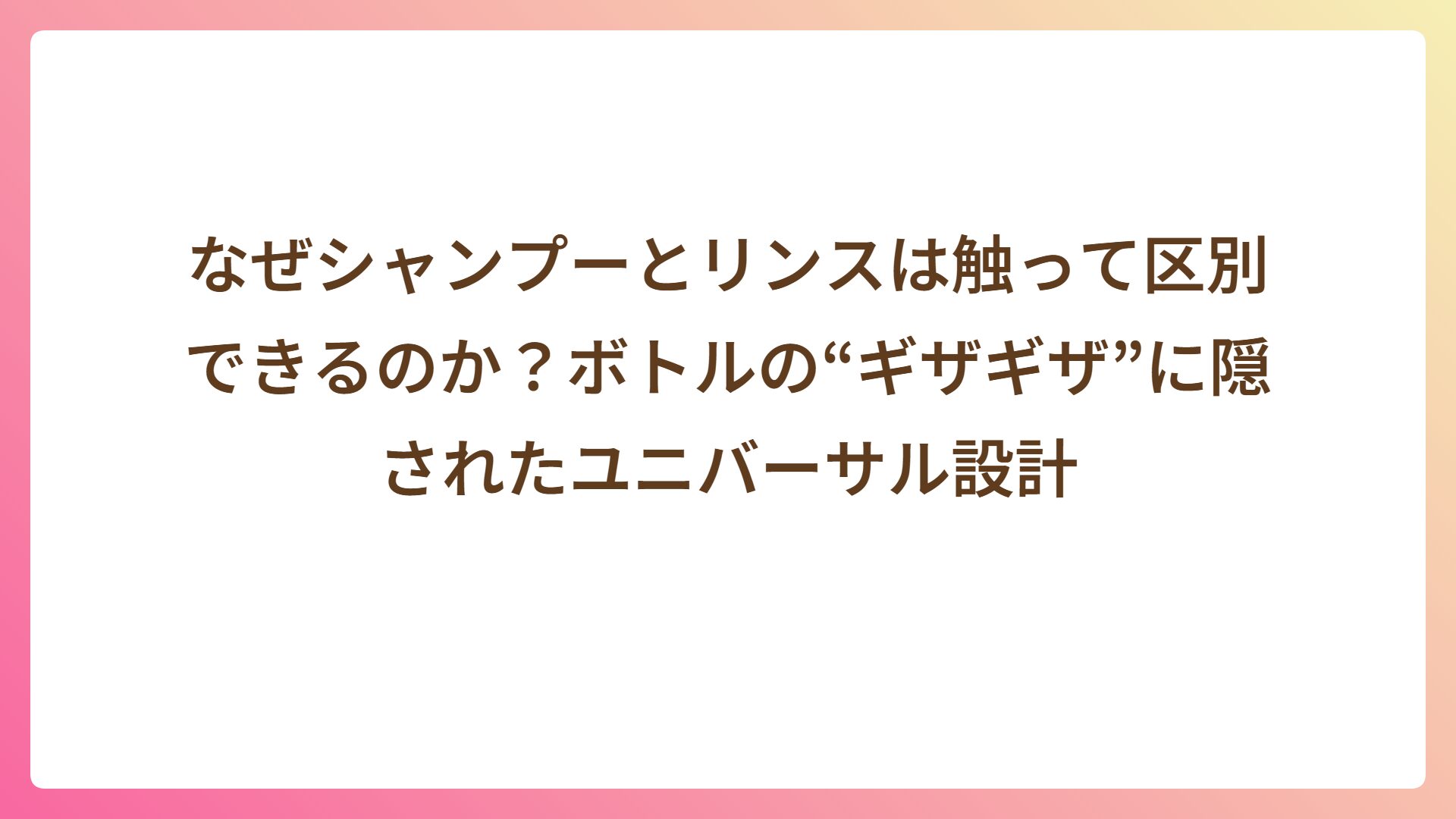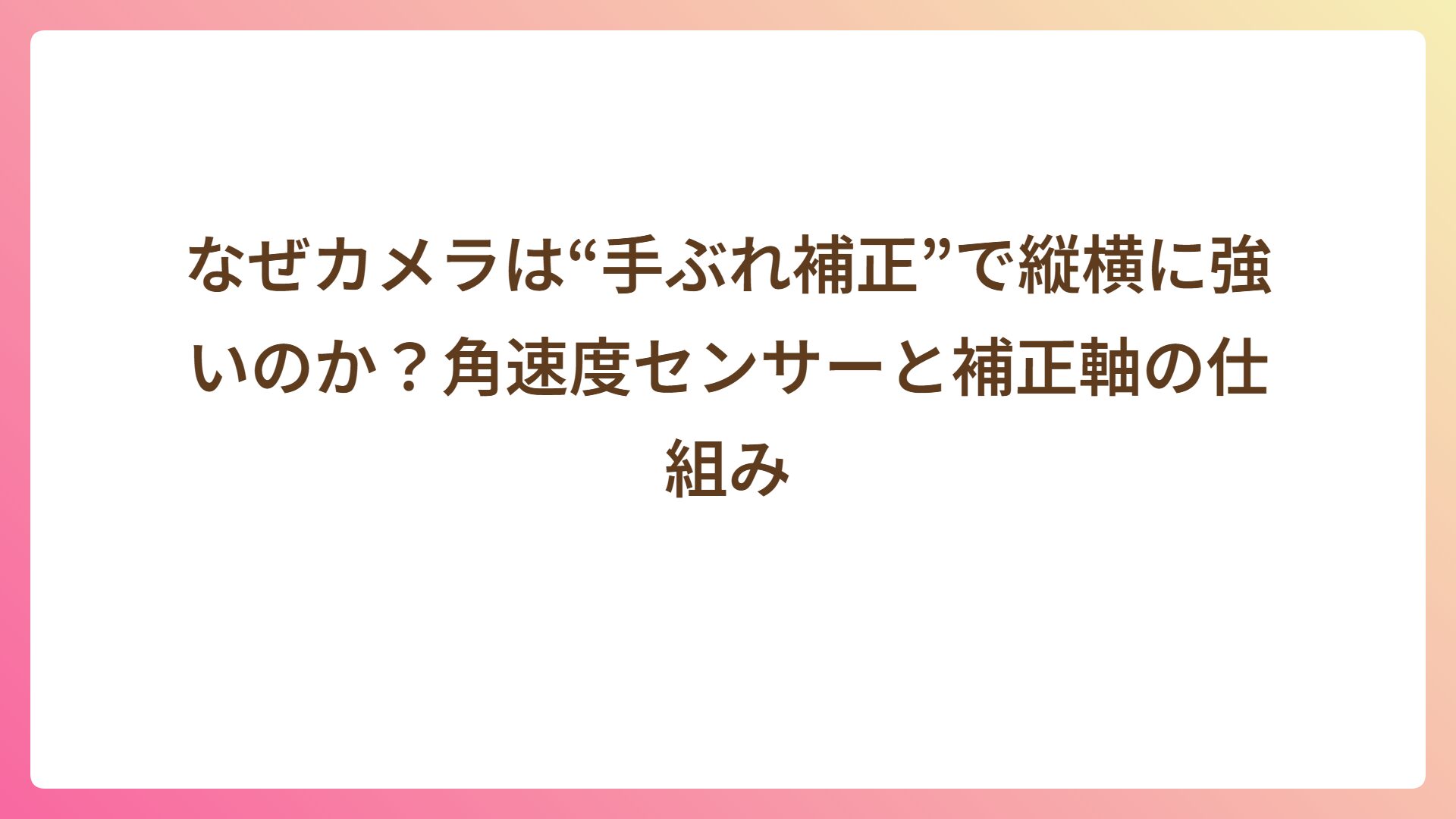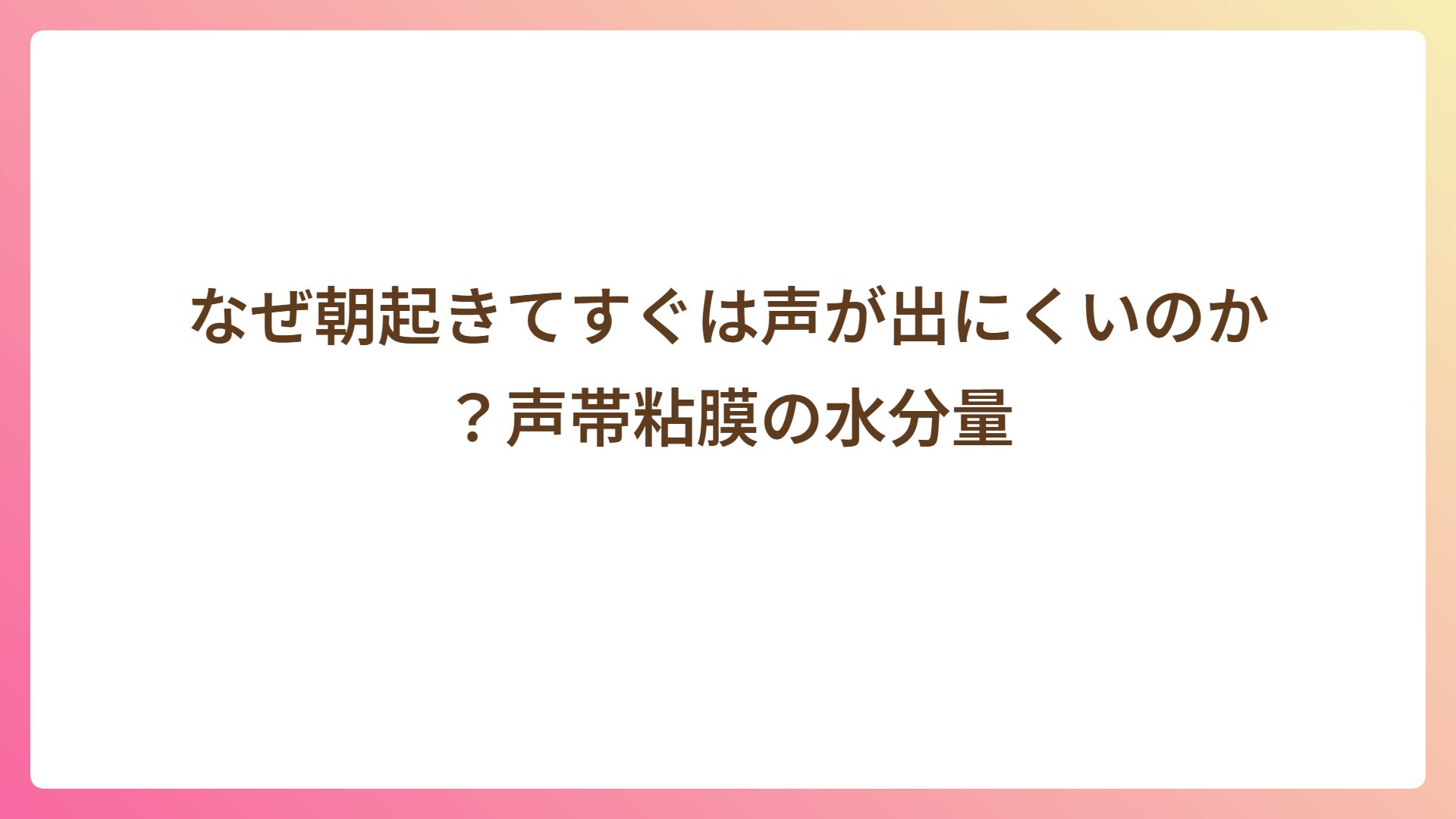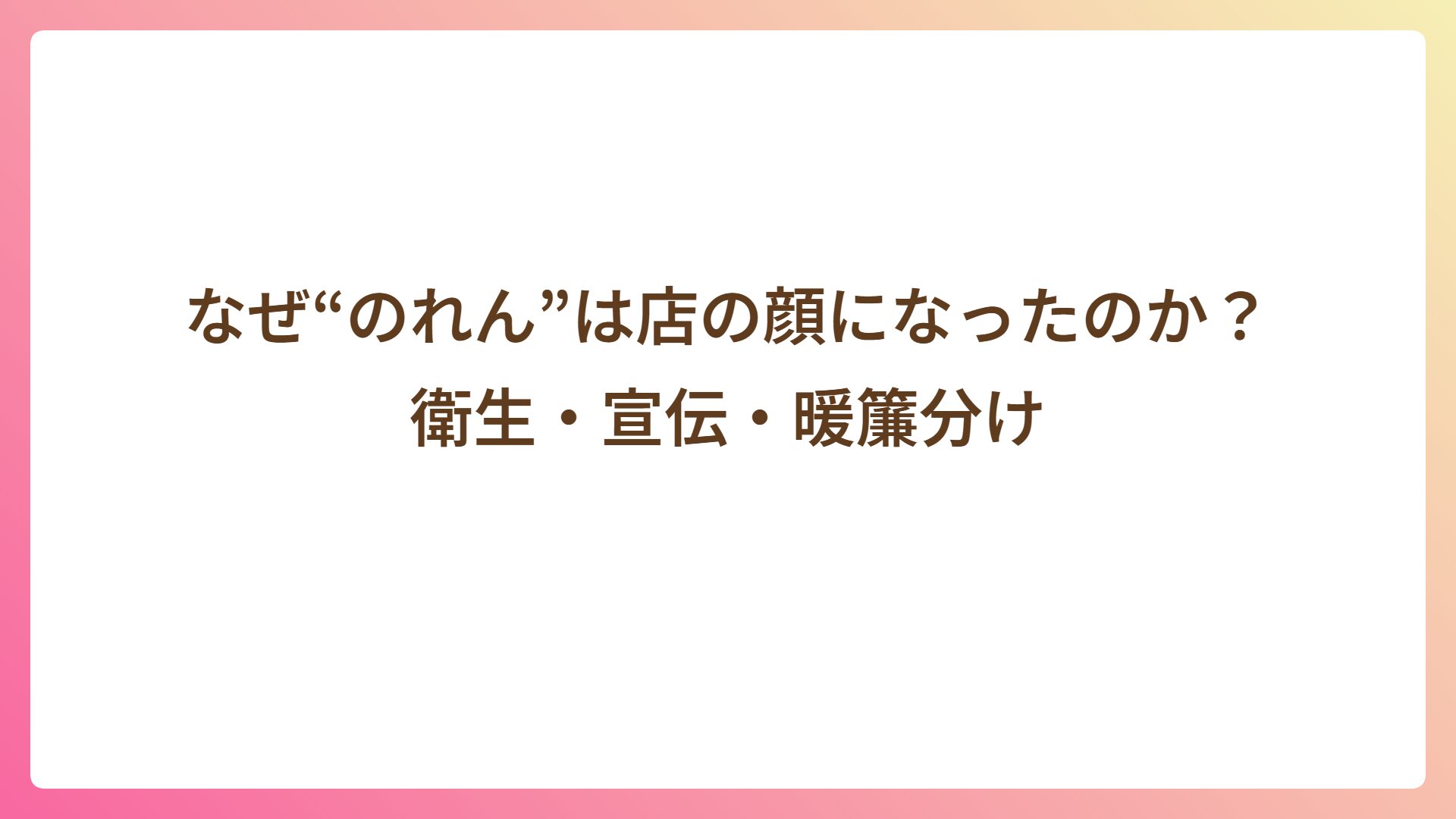なぜガムの味は長持ちしないのか?唾液と香料の放出曲線の科学

噛みはじめは強い甘さと香りが広がるのに、
数分後には「味がなくなった」と感じる──。
ガムを噛んでいて誰もが経験するこの現象、
実は唾液・香料・ポリマーの化学的なバランスによって説明できるのです。
味の主役は「糖・甘味料」と「香料」
ガムの“味”は、主に以下の2要素で構成されています。
- 糖・甘味料(甘さの源)
- 香料(味覚を補う香りの成分)
ガムのベース部分(ゴムのような弾性体)は味を持たず、
これらの成分が溶け出すことで「味がある」と感じます。
しかし、これらの成分は唾液に溶ける性質を持っており、
時間とともに溶出し尽くしてしまうのです。
甘味が消えるメカニズム:唾液による拡散と希釈
ガムを噛むと、口の中で唾液が常に分泌されます。
唾液は糖や甘味料を溶かしながら、
飲み込まれるたびに新しい唾液で希釈→排出されていきます。
つまり、ガムの外側にあった甘味成分は数分以内にほとんど失われ、
中心部に残る成分も徐々に溶出の限界(飽和点)を迎えます。
その結果、噛み続けても「甘くない」状態になるのです。
香りが先に消えるのは「揮発」と「放出曲線」のせい
ガムの「味がなくなる」と感じる最大の原因は、
香料成分(フレーバーオイル)の揮発です。
香料は揮発性の高い分子でできており、
噛むことで熱と空気が混ざり、分子がどんどん空気中に放出されます。
食品香料は通常、時間に対して放出曲線(release curve)を描き、
最初の1〜2分で急激に放出され、その後は緩やかに減少します。
このため、最初の数分で香りのピークが過ぎてしまうのです。
香りが薄れると、甘さが残っていても「味がしない」と感じてしまいます。
「ガムベース」自体には味がない
ガムのベースとなるゴム状成分(ポリマー)は、
食べても消化されず、味もほとんどありません。
そのため、味成分が溶け出した後に残るのは
無味のポリマーの弾力だけになります。
つまり、「味がしないガム」は、
味の元が抜けきってベース素材だけが残った状態なのです。
味を長持ちさせるための工夫:マイクロカプセル技術
近年のガムでは、味の持続を高めるために
「マイクロカプセル化香料」という技術が使われています。
香料分子を微細なカプセルで包み、
噛むたびに少しずつ壊れて香りを放出する仕組みです。
これにより、放出曲線を緩やかにし、
「徐放性(じょほうせい)」=ゆっくり味が出る設計が可能になりました。
一部の高級ガムや「ロングラスティングガム」はこの方式を採用しています。
まとめ:ガムの味が消えるのは“科学的に当然”
ガムの味が長持ちしないのは、
- 唾液で糖や甘味料がすぐ溶け出す
- 香料が揮発して短時間で失われる
- ベース素材には味がない
という、物理と化学の必然によるものです。
そして「3分程度で味がなくなる」ガムの設計は、
実は人間の集中力や咀嚼リズムに合わせた“味の放出曲線”に基づいています。
短い時間で強い満足感を与える、それがガムの科学的デザインなのです。