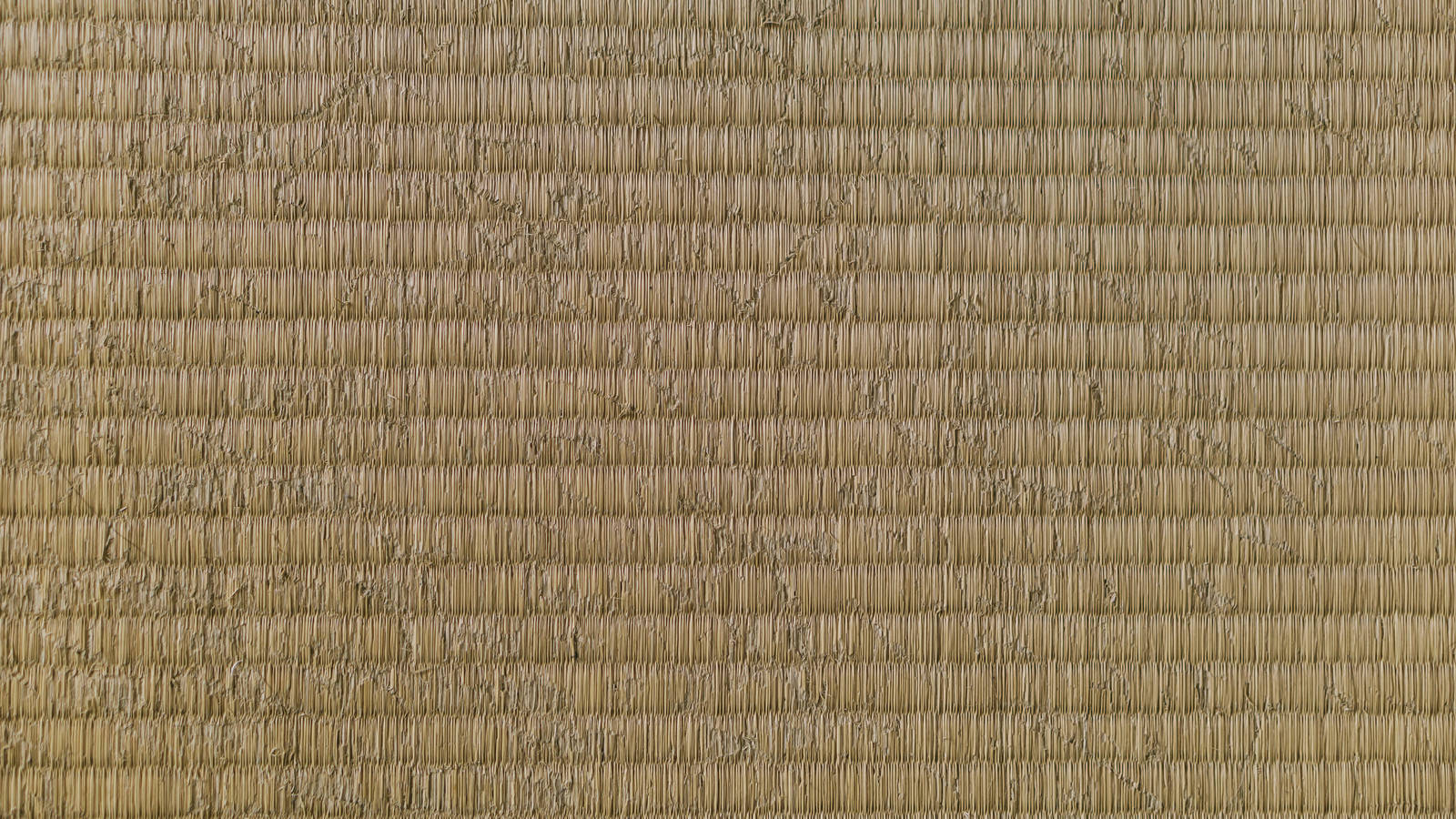花言葉は誰が決めてる?実は国によって違うし複数あるのも普通だった!

誰かに花を贈るとき、あるいはもらうとき、「この花の花言葉ってなんだろう?」と気になった経験はありませんか?
たとえばバラには「愛」や「美」、チューリップには「思いやり」など、花ごとにメッセージが込められている花言葉。しかしよくよく考えると、この花言葉って誰が決めているんでしょうか? そして、同じ花に複数の花言葉があるのはなぜなのでしょうか?
今回は、意外と知られていない花言葉の由来と決まり方についてわかりやすく紹介します。
花言葉の始まりは17世紀のトルコ「セラム」
花言葉の発祥には諸説ありますが、現在の定説では17世紀のトルコが起源とされています。
当時のトルコには「セラム(Selam)」という文化があり、花や果物などの品物に意味を込めて贈ることで想いを伝えるという独特の風習でした。
この風習がヨーロッパに伝わると、やがて「花限定の意味付け文化=花言葉」へと発展。1819年には、フランスで世界初の花言葉に関する書籍『Le Langage des Fleurs(花の言葉)』が出版され、花言葉という概念が一気に広まりました。
花言葉に統一ルールはない!国や文化で違う意味に
面白いのは、花言葉には正式な決定機関や世界共通ルールが存在しないという点です。
そのため、同じ花でも国や地域、さらには文化によって異なる意味を持つのが一般的。たとえば、日本ではポジティブな意味のある花が、海外では不吉な意味で扱われていることもあります。
また、1つの花に複数の花言葉があるのも珍しくありません。花の色によって意味が変わる場合や、国ごとの解釈の違いで複数の花言葉がつけられていることもあります。
新しい花の花言葉はどうやって決めているの?
では、品種改良などで新しい花が誕生したとき、その花の花言葉は誰が決めているのでしょうか?
実はこれにもルールはありません。ケースバイケースで、開発した生産者や販売元の企業が独自に決めることもあれば、花のイベントやキャンペーンで公募されて決まることもあります。
つまり、花言葉は感性と物語によって自然に生まれ、時代や文化に合わせて増えていくものなのです。
おわりに
特定の誰かが公式に決めたわけではないのに、花言葉という文化が世界中に根付いているというのはなんだかロマンがありますね。
中には「スイカ=かさばった思い出」「キンギョソウ=おしゃべり」といった、くすっと笑えるユニークな花言葉もたくさんあります。
ぜひこの機会に、身近な花の花言葉を調べてみてはいかがでしょうか。きっと意外な意味に出会えますよ。