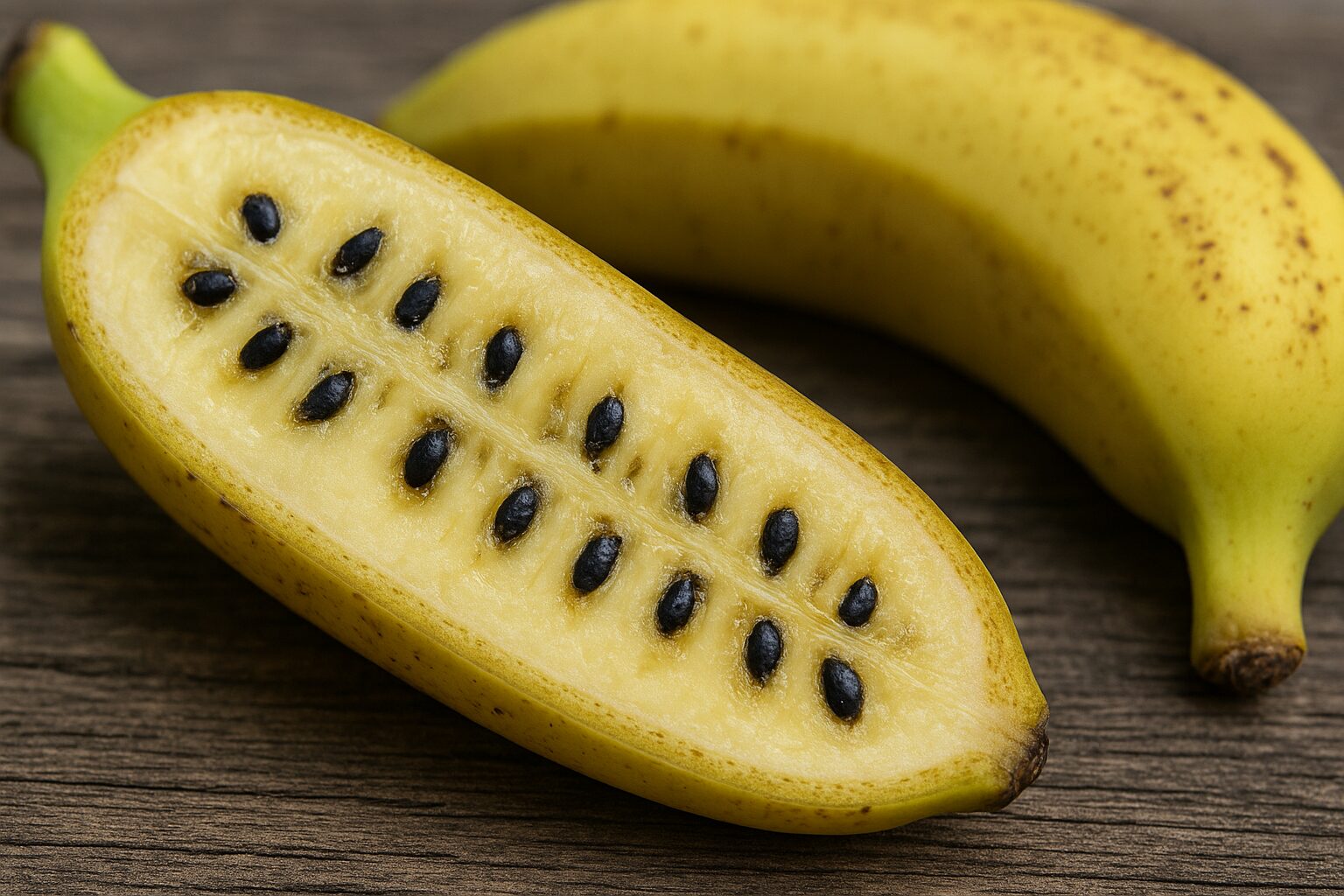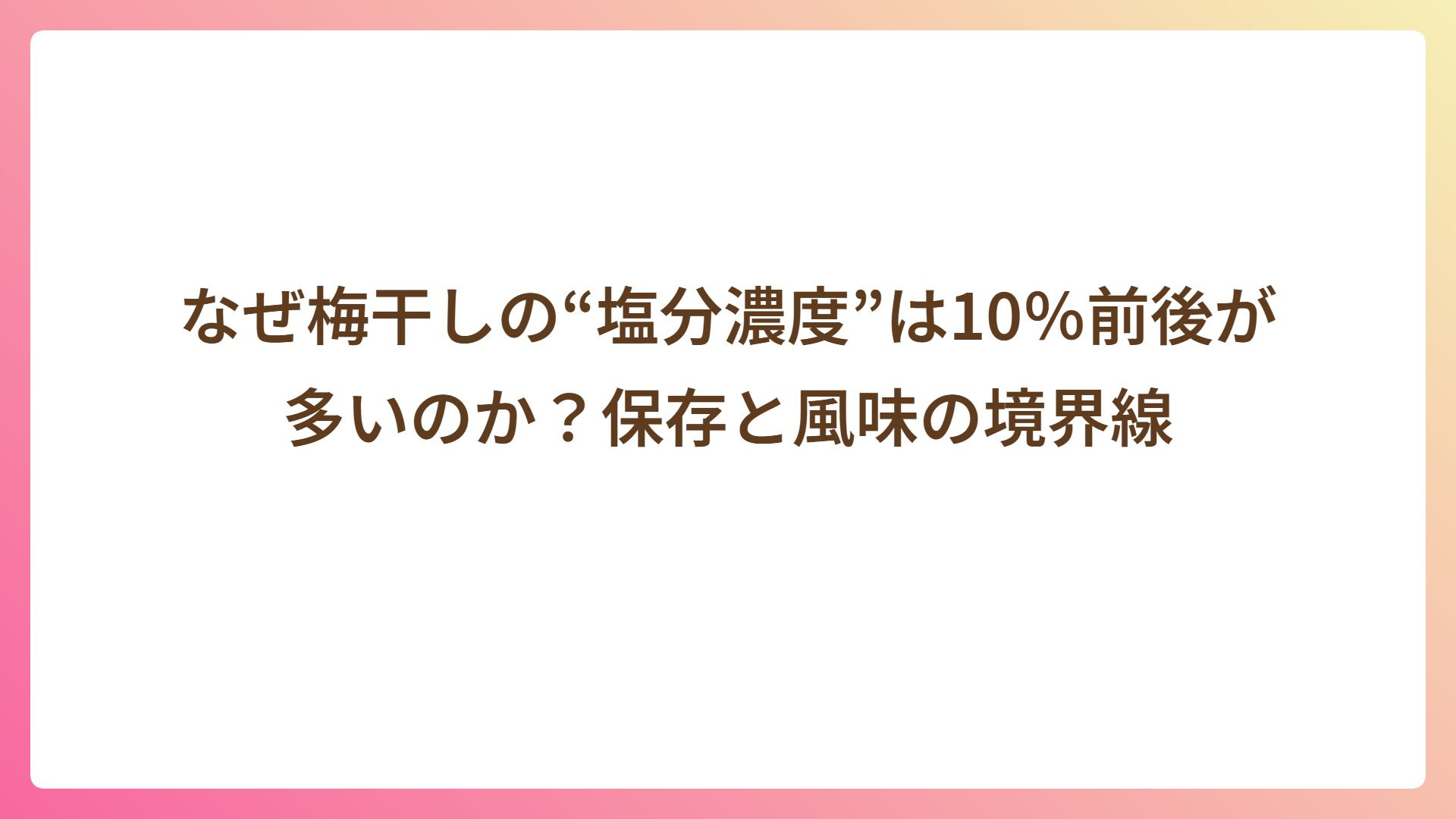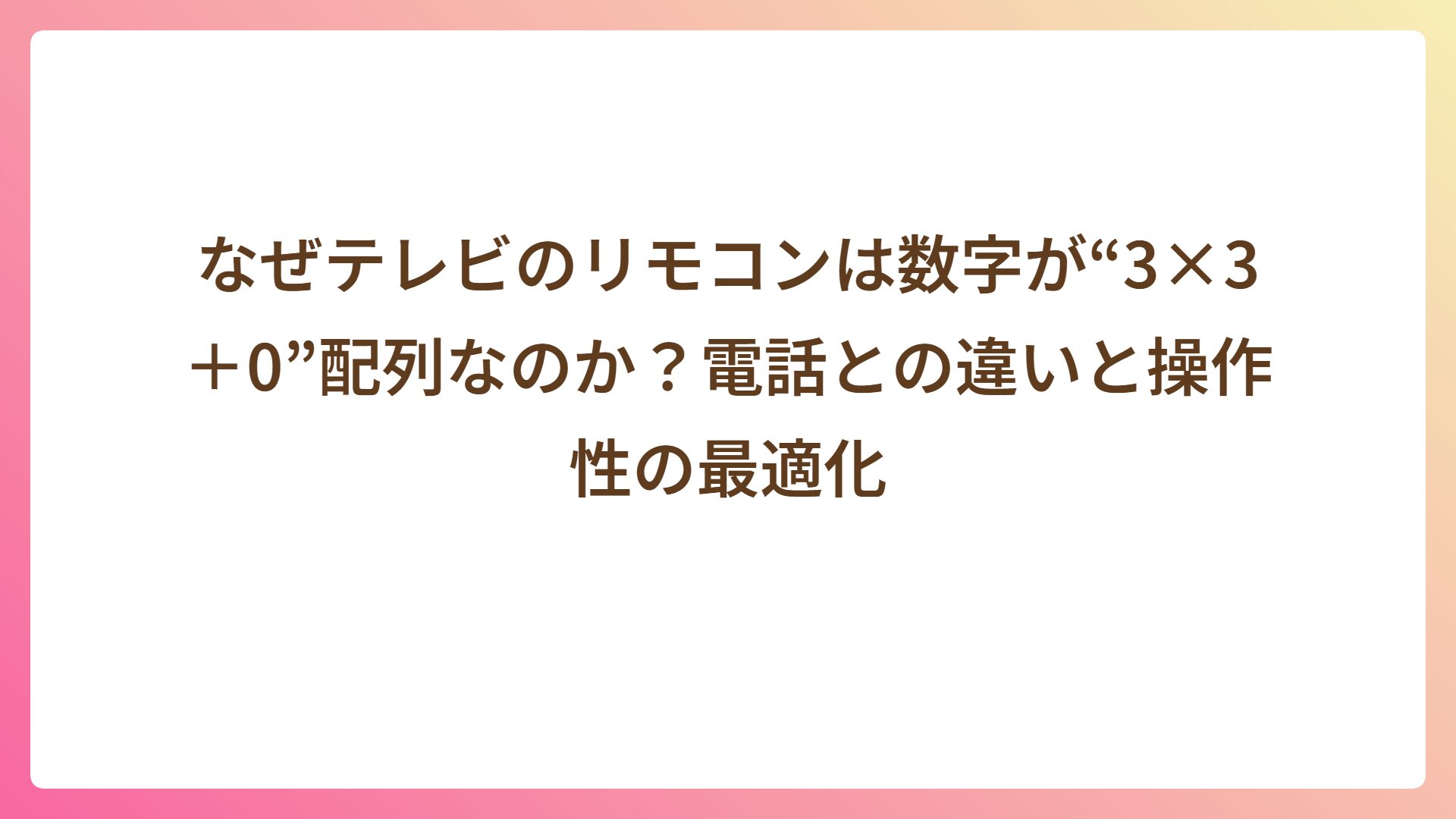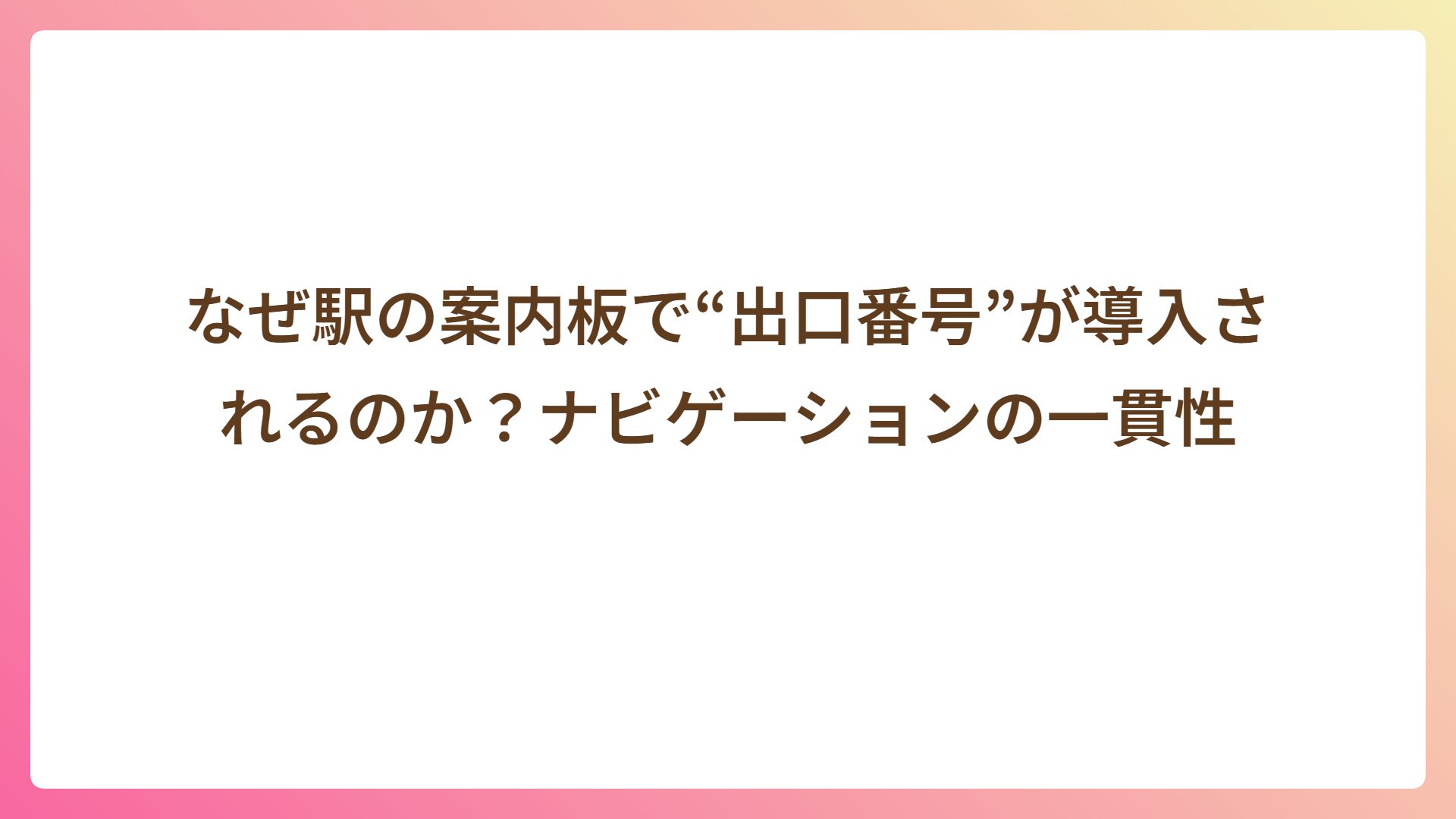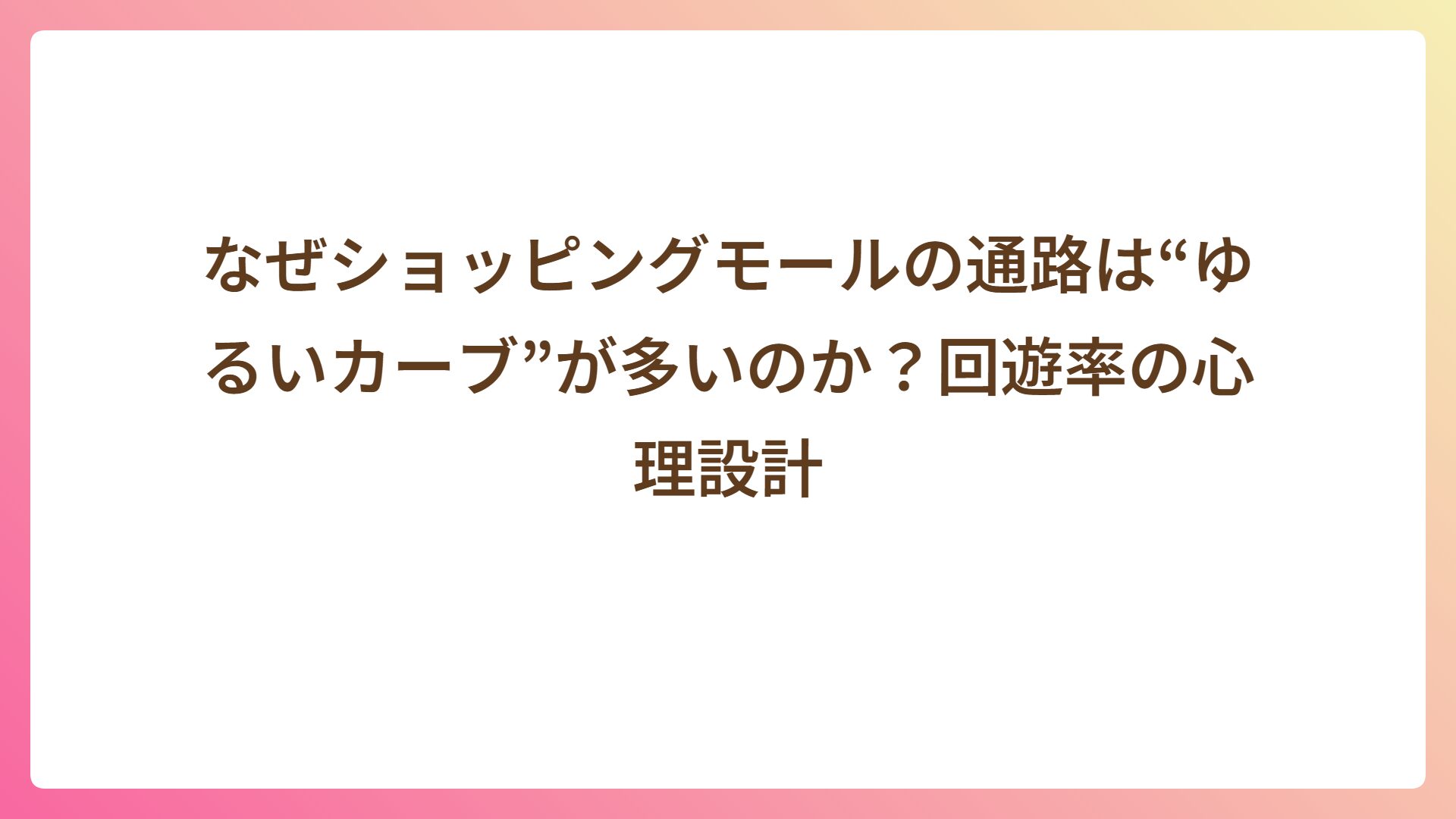なぜ鼻の穴は2つあるのか?空気抵抗と嗅覚の分散設計
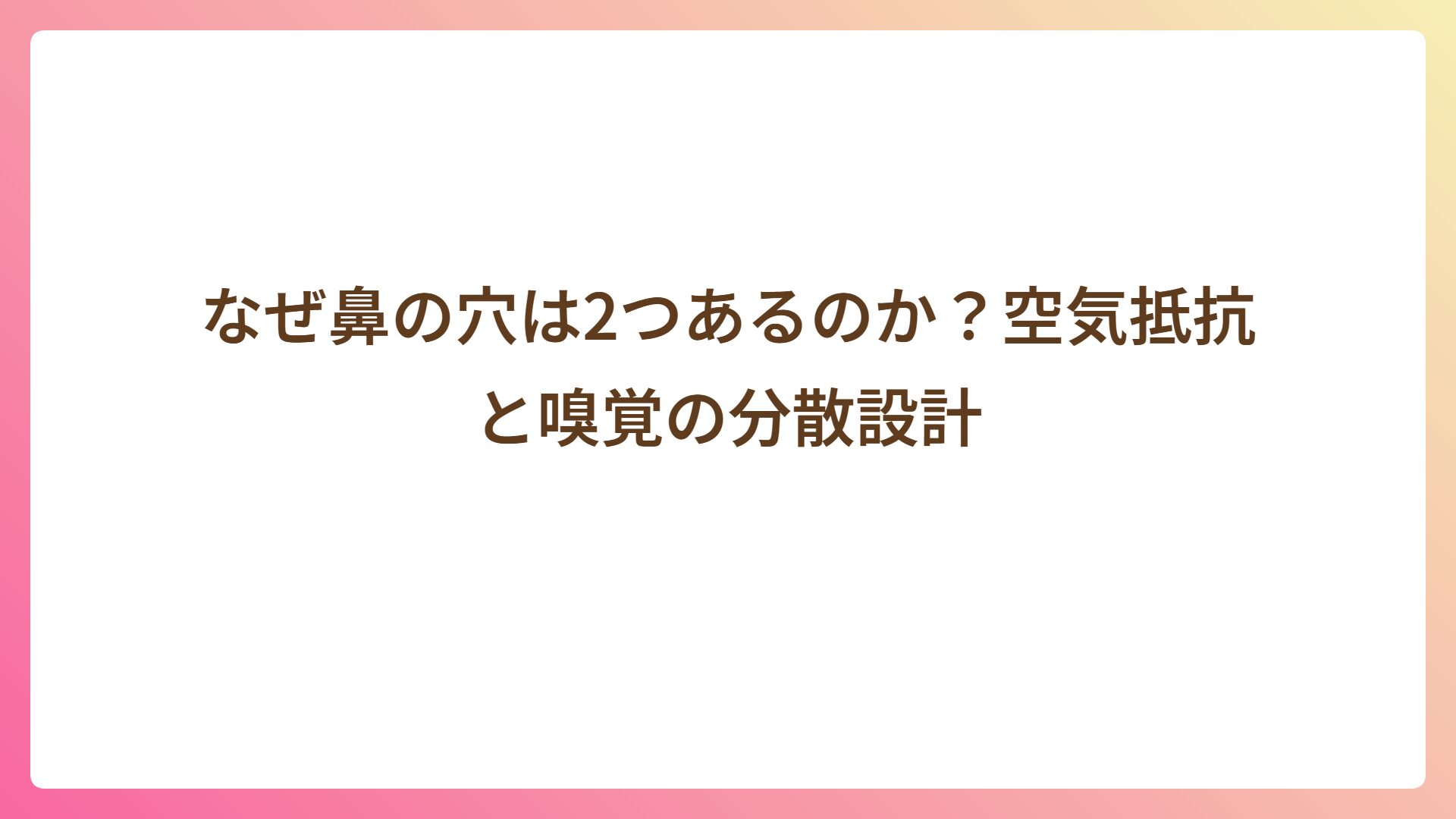
当たり前のように2つある「鼻の穴」。ですが、なぜ1つではなく2つ必要なのでしょうか?実は、鼻の構造は呼吸や嗅覚の効率を最大化するために緻密に設計されています。そこには、空気抵抗や匂いの検知に関わる驚くべきメカニズムが隠されているのです。
鼻の穴が2つある基本的な理由
まず、鼻の穴が2つあることで空気の流れを分散させ、呼吸を安定させることができます。1つの穴では空気の通り道が細くなり、呼吸の抵抗が大きくなってしまいます。2つに分かれていることで、空気がスムーズに流れ込み、肺へ効率よく送られるのです。
さらに、片方の鼻が詰まってももう片方で呼吸を維持できるという冗長性の仕組みにもなっています。これは、風邪や花粉症などで片側が詰まったときにも呼吸が途切れないようにする、生存上の安全装置といえます。
左右の鼻は交互に働いている
意外なことに、私たちの左右の鼻の穴は常に同じようには働いていません。
人間の体には「鼻周期(びしゅうき)」と呼ばれるリズムがあり、片方の鼻が優勢に空気を通す状態が数時間ごとに入れ替わっています。
この仕組みによって、一方の鼻の粘膜が休息して乾燥や炎症を防ぎ、もう片方が主に呼吸や匂いを担当するという交代制システムが成り立っています。つまり、2つの鼻の穴は常にバランスを取りながら働いているのです。
匂いの感知を助ける「分散設計」
嗅覚の観点から見ると、2つの鼻の穴を持つことには空気の流れを比較する機能があります。
両方の鼻で吸い込む空気の濃度や方向をわずかに変えることで、匂いの発生源の位置や強さをより正確に判断できるのです。
これはまるで、耳が2つあることで音の方向を判断できるのと同じ原理です。鼻が2つあるおかげで、私たちは匂いを「空間的」に感じ取ることができるのです。
まとめ
鼻の穴が2つあるのは、単なる左右対称のためではなく、呼吸の安定化と嗅覚の精度を両立するための進化的構造です。
2つの通り道があることで、空気の流れを分散し、匂いの情報を立体的に処理できるようになっています。何気なく呼吸しているその瞬間にも、体は見事な分業と設計のバランスで動いているのです。