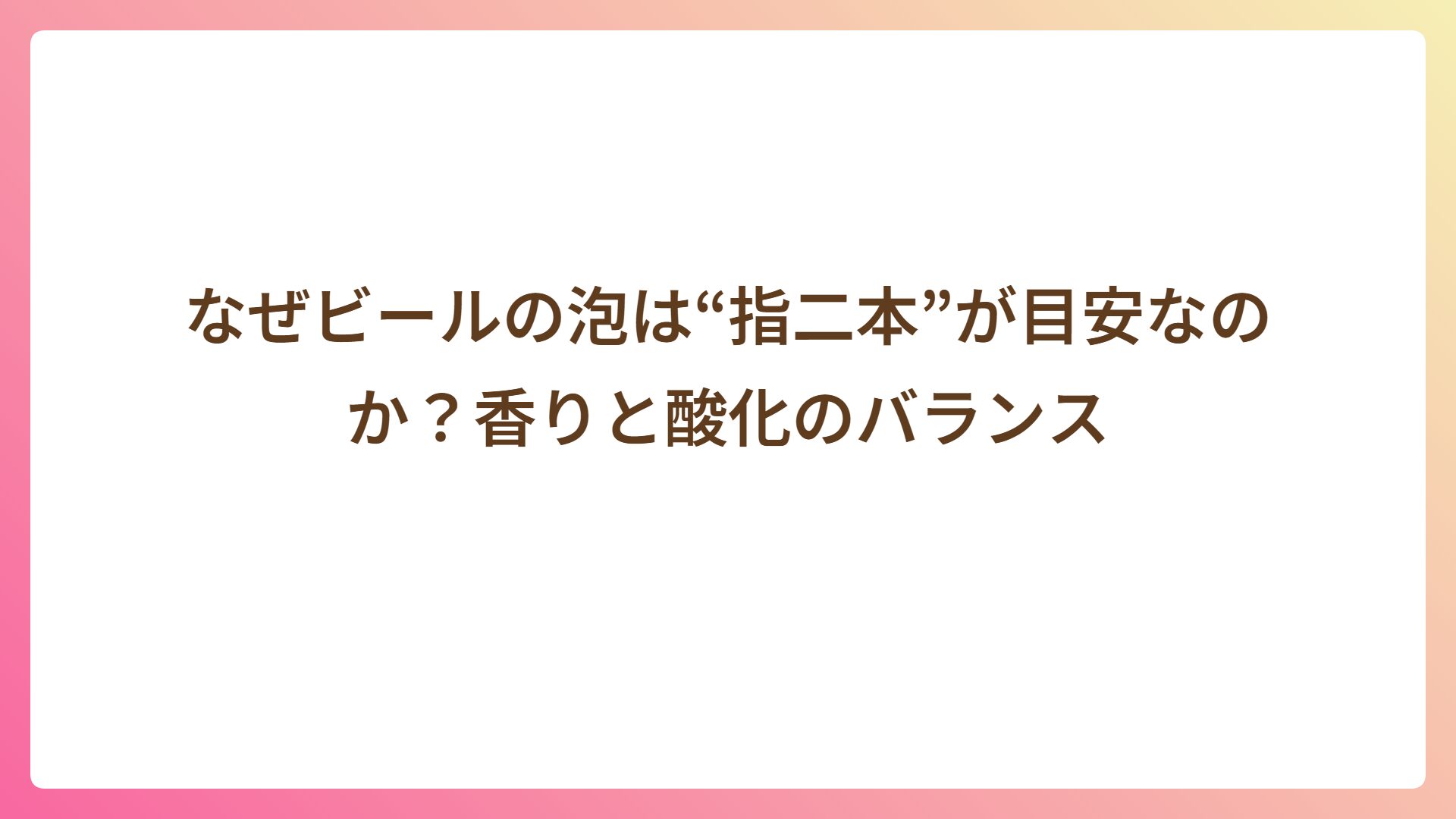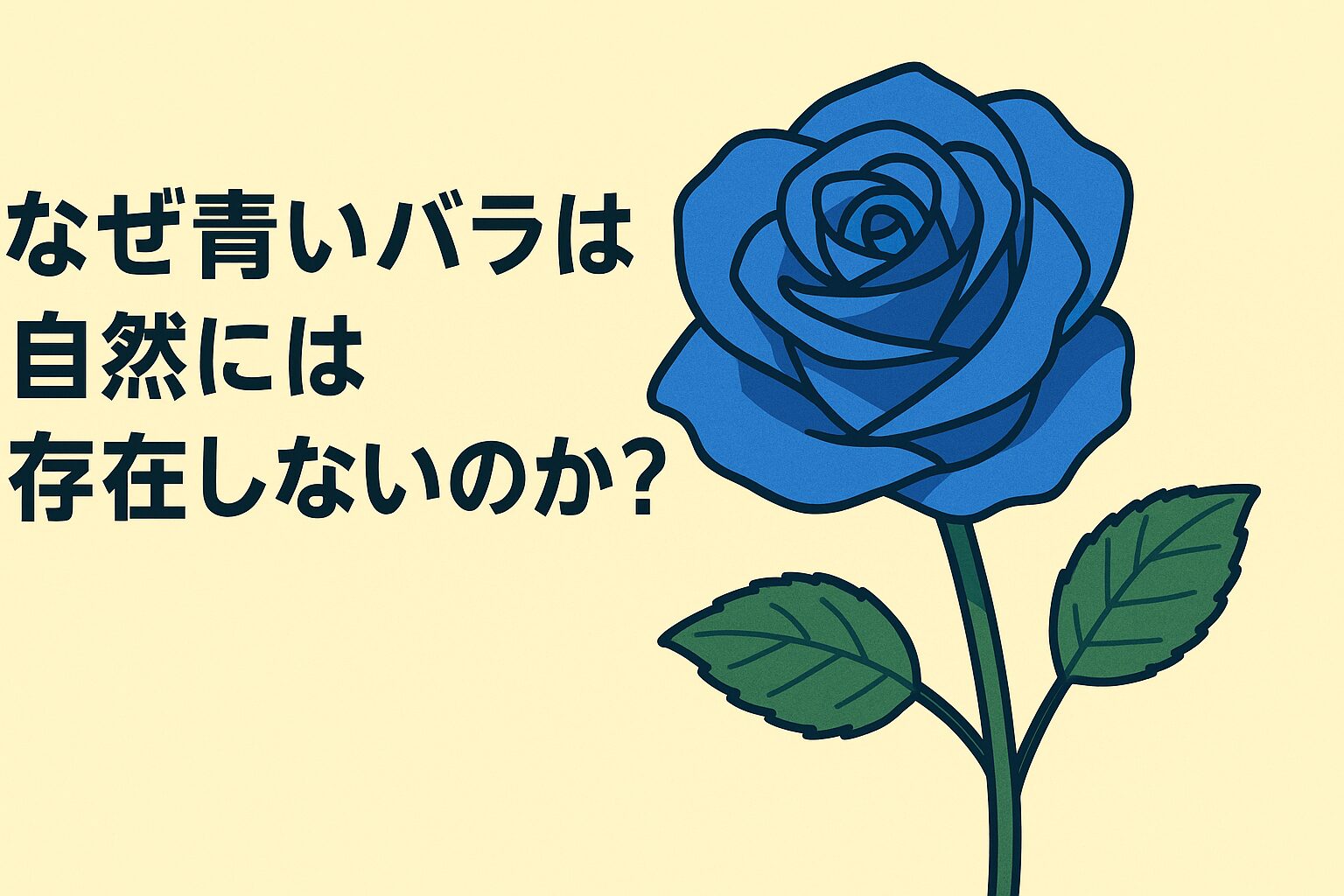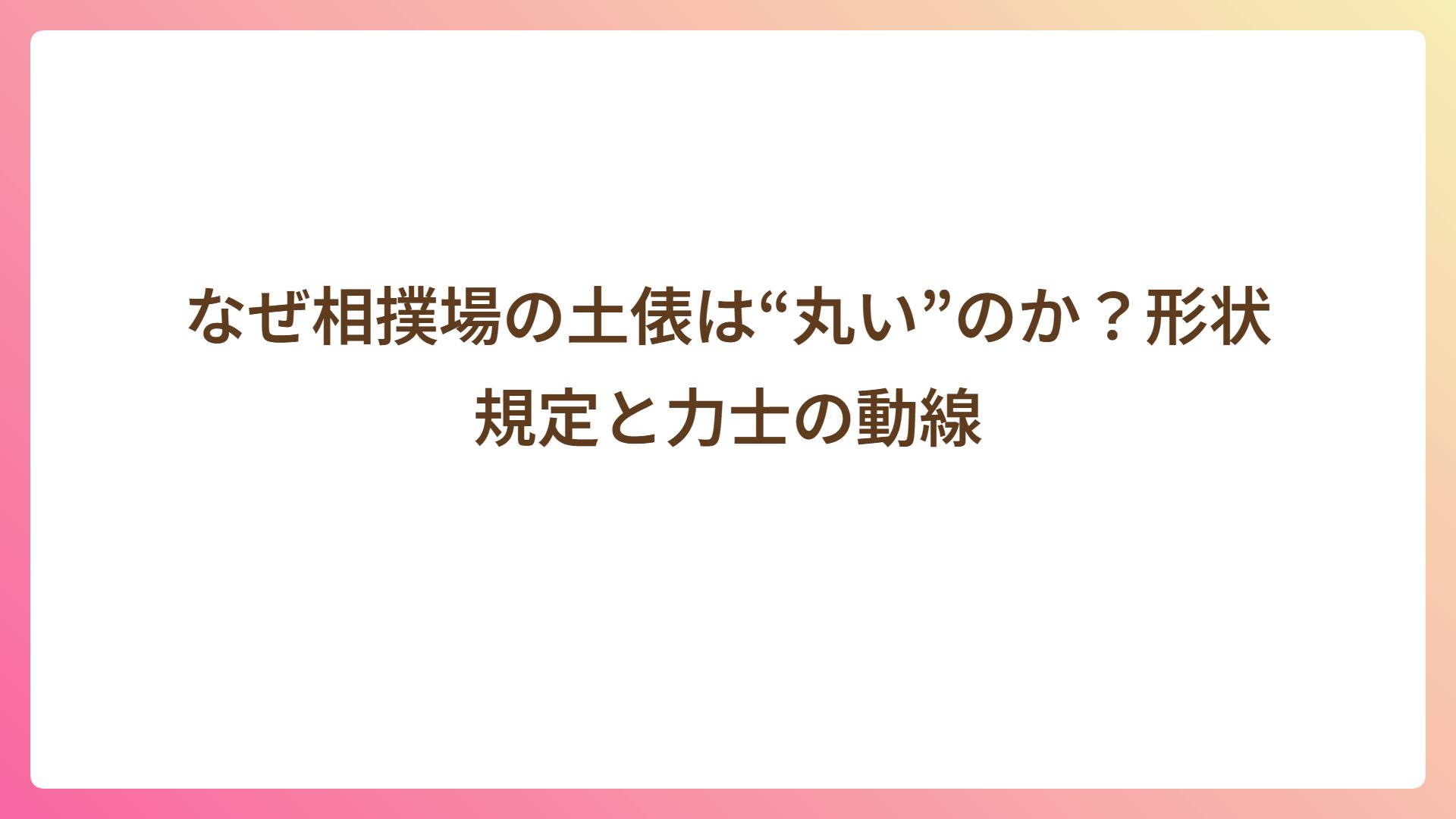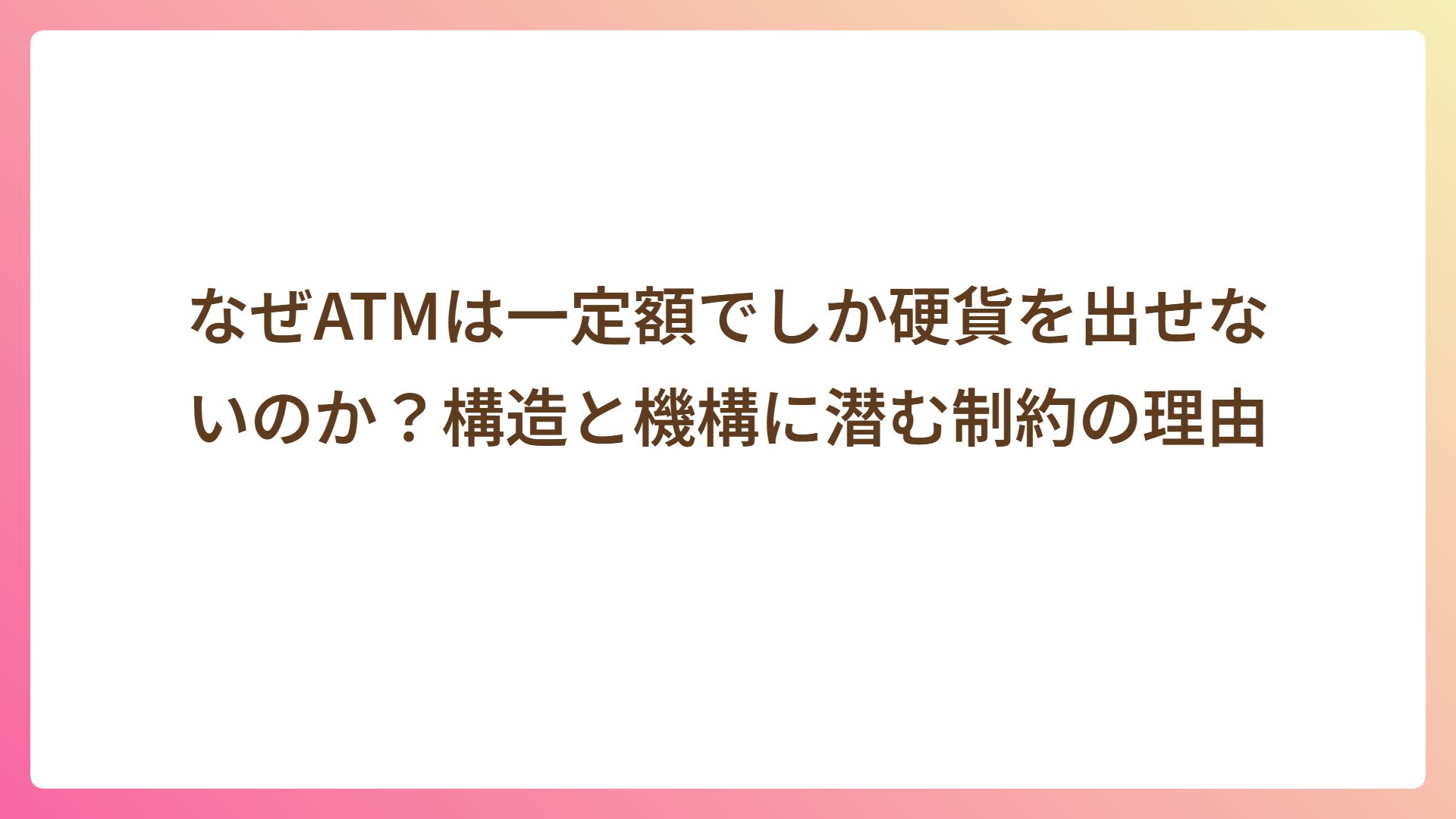なぜ飛行機の手荷物サイズは“3辺合計”で決まるのか?収納と安全の共通規格
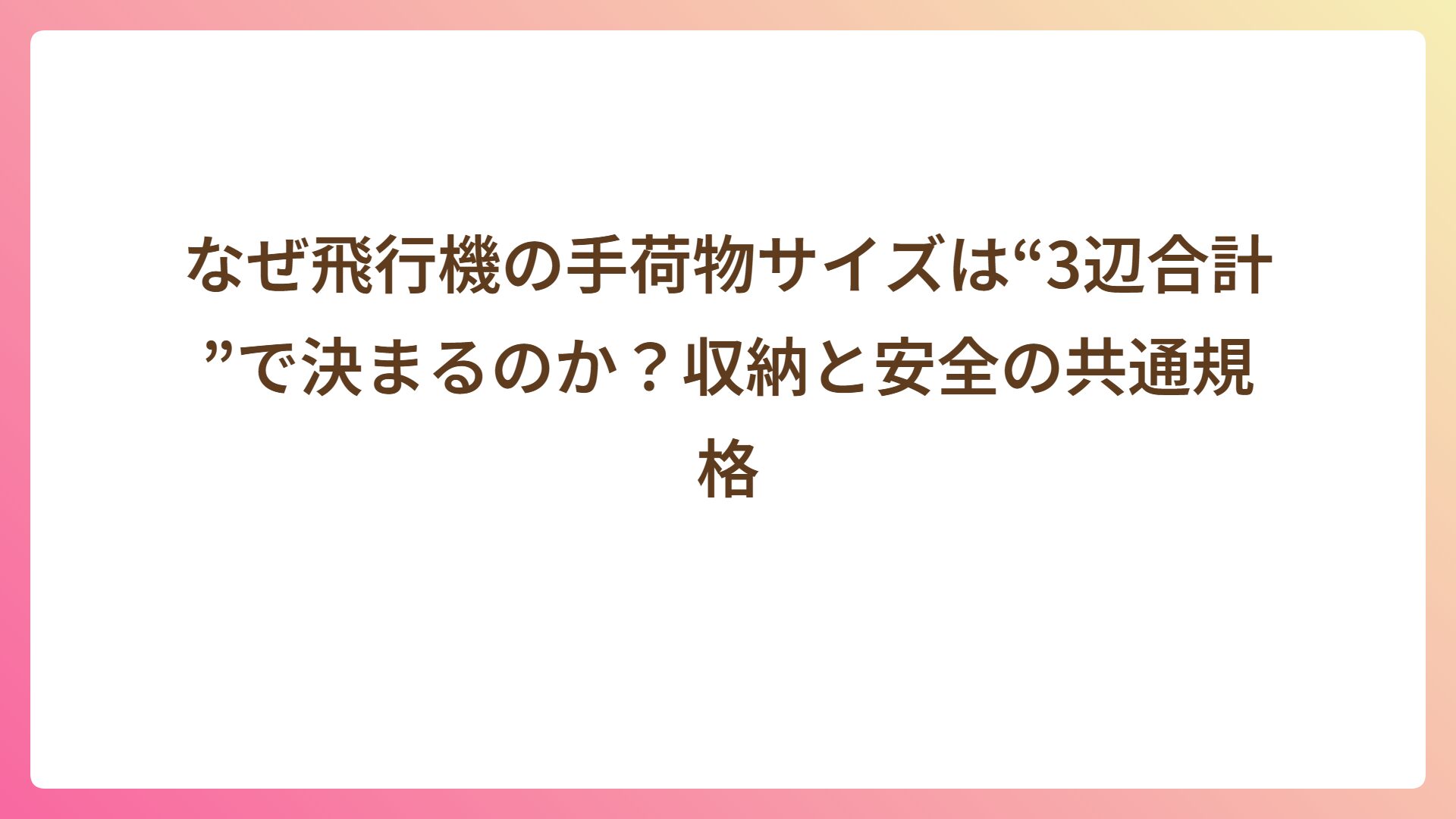
飛行機に乗るとき、「機内持ち込みは3辺の合計が115cm以内」などと案内されます。
なぜ縦・横・高さそれぞれの上限ではなく、3辺の合計で決められているのでしょうか?
その基準の裏には、収納効率と安全性を両立するための国際的な規格思想があるのです。
3辺合計は「収納スペース」に合わせた実用基準
飛行機の客室上部にある収納棚(オーバーヘッドビン)は、航空会社ごとに形状や寸法がわずかに異なります。
もし縦・横・高さそれぞれに厳密な上限を設けると、一部の機種では入るのに別の機種では入らないという不都合が生じます。
そこで、あらゆる機種に共通して収納できるように考えられたのが「3辺合計での統一基準」なのです。
たとえば、縦がやや長くても横が短ければ問題なく収まる場合もあります。
合計寸法で制限すれば、利用者にとって柔軟性がありつつ、航空会社にとっても収納可能性を保証できるという合理的なルールになります。
国際的な共通規格としての背景
この「3辺合計」の考え方は、国際航空運送協会(IATA)が定めた国際標準サイズに基づいています。
IATAでは、世界中の航空会社が共通で使えるサイズを定義しており、
機内持ち込み手荷物はおおむね「縦・横・高さの合計が115cm以内」と規定されています。
この基準を採用することで、航空機の型式や国をまたいでも同じルールで運用できるようになり、
国際線・国内線を問わずスムーズな搭乗が可能になります。
重量よりも「安全性」を優先した設計
飛行中、収納棚に入れられた荷物が動いたり落下したりすると、乗客の安全に関わります。
そのため、各航空会社は棚の強度や荷物の形状バランスを考慮して、
「3辺合計+重量」の両方を制限しています。
特に合計サイズの上限を設けることで、奥行きや厚みが極端な荷物が入りにくくなり、落下リスクを軽減できます。
つまり3辺合計は、単なる収納効率だけでなく、**安全設計上の“最大外形寸法”**としての意味も持っているのです。
手荷物検査・搭乗口での判定を簡略化
もう一つの理由は、現場での判定が簡単で公平であること。
縦・横・高さを個別に測るよりも、合計値だけで判断できれば、
検査員が短時間でチェックでき、トラブルを防ぎやすくなります。
空港の測定ゲージ(ボックス)もこの基準に合わせて作られており、
「3辺合計で収まる=どの向きでも入る」ように設計されています。
荷物の形状に柔軟性を持たせるメリット
スーツケースやリュックは形状がさまざまです。
3辺合計での制限なら、縦に長いケースや横に広いバッグなど多様なデザインを許容できます。
これにより、旅行スタイルや持ち物に応じた選択肢を確保しつつ、
航空会社側も収納効率を損なわないという、利用者と運営の双方に都合の良いバランスが取られているのです。
まとめ
飛行機の手荷物サイズが“3辺合計”で決められているのは、
機種を問わず収納できる共通性・安全性・運用効率を実現するためです。
合計寸法というルールは、単純ながらも世界中の航空会社と乗客を結ぶ共通言語。
旅行者が安心して荷物を預けられる背景には、航空工学と国際規格の知恵がしっかりと息づいているのです。