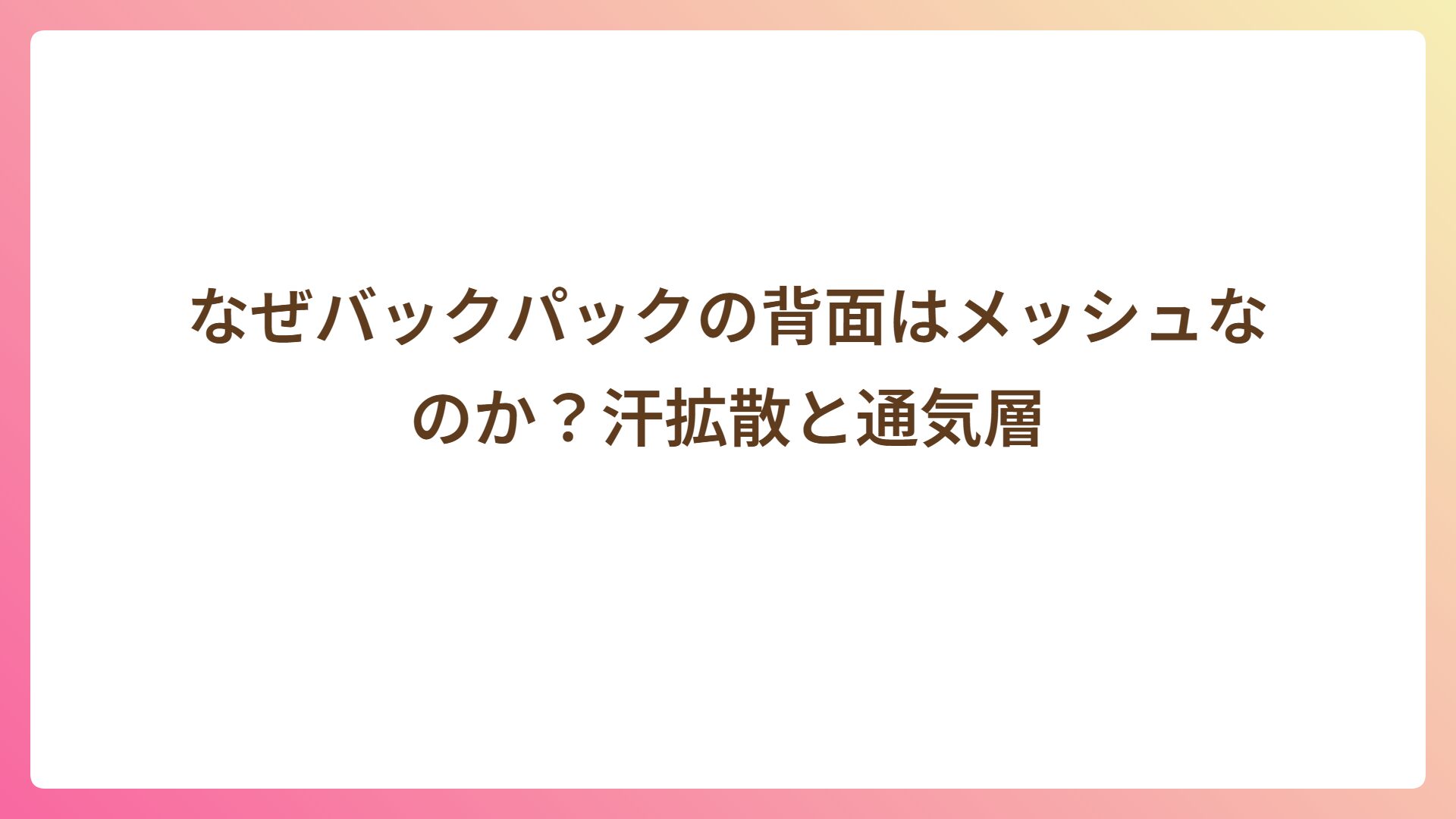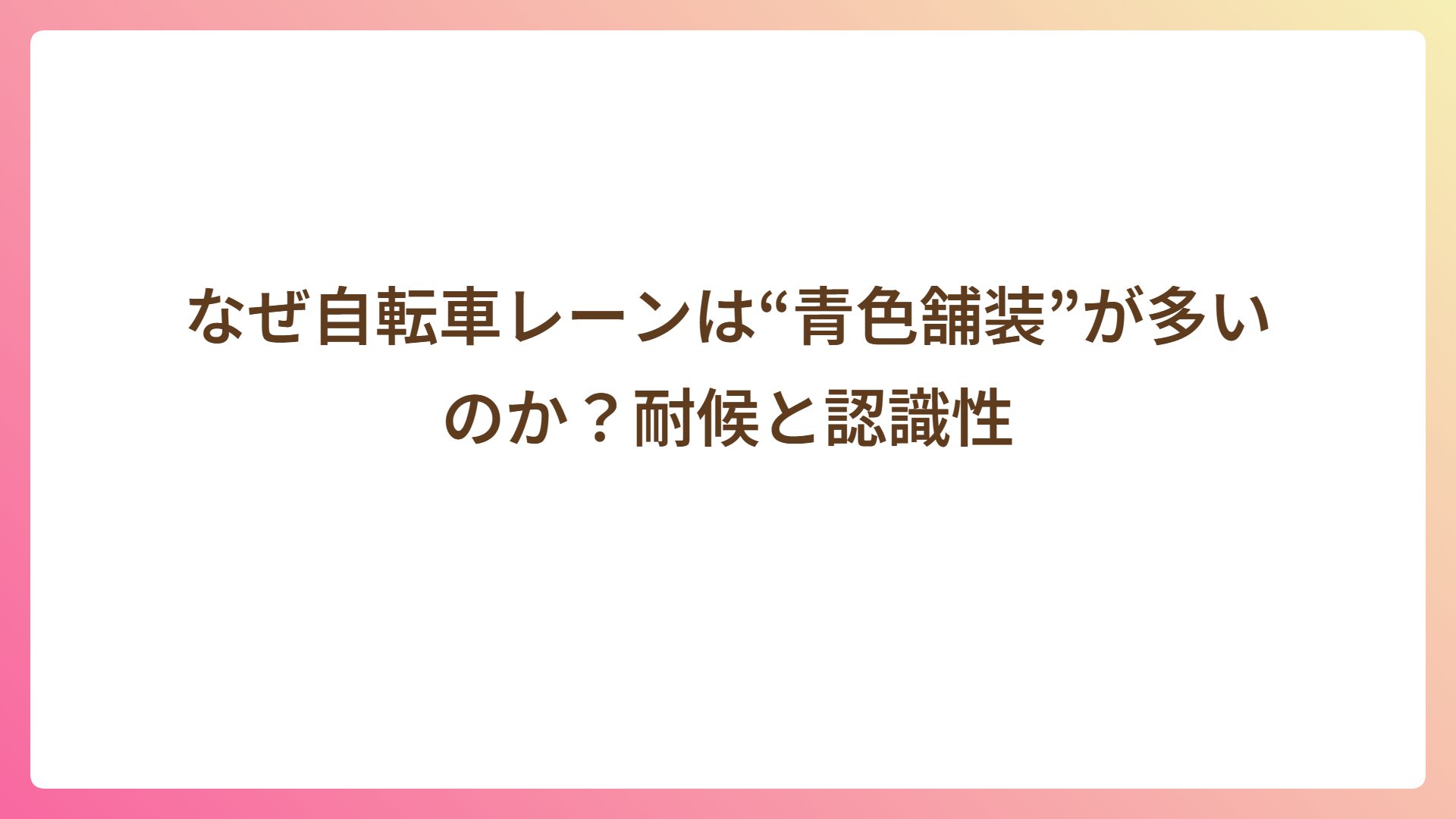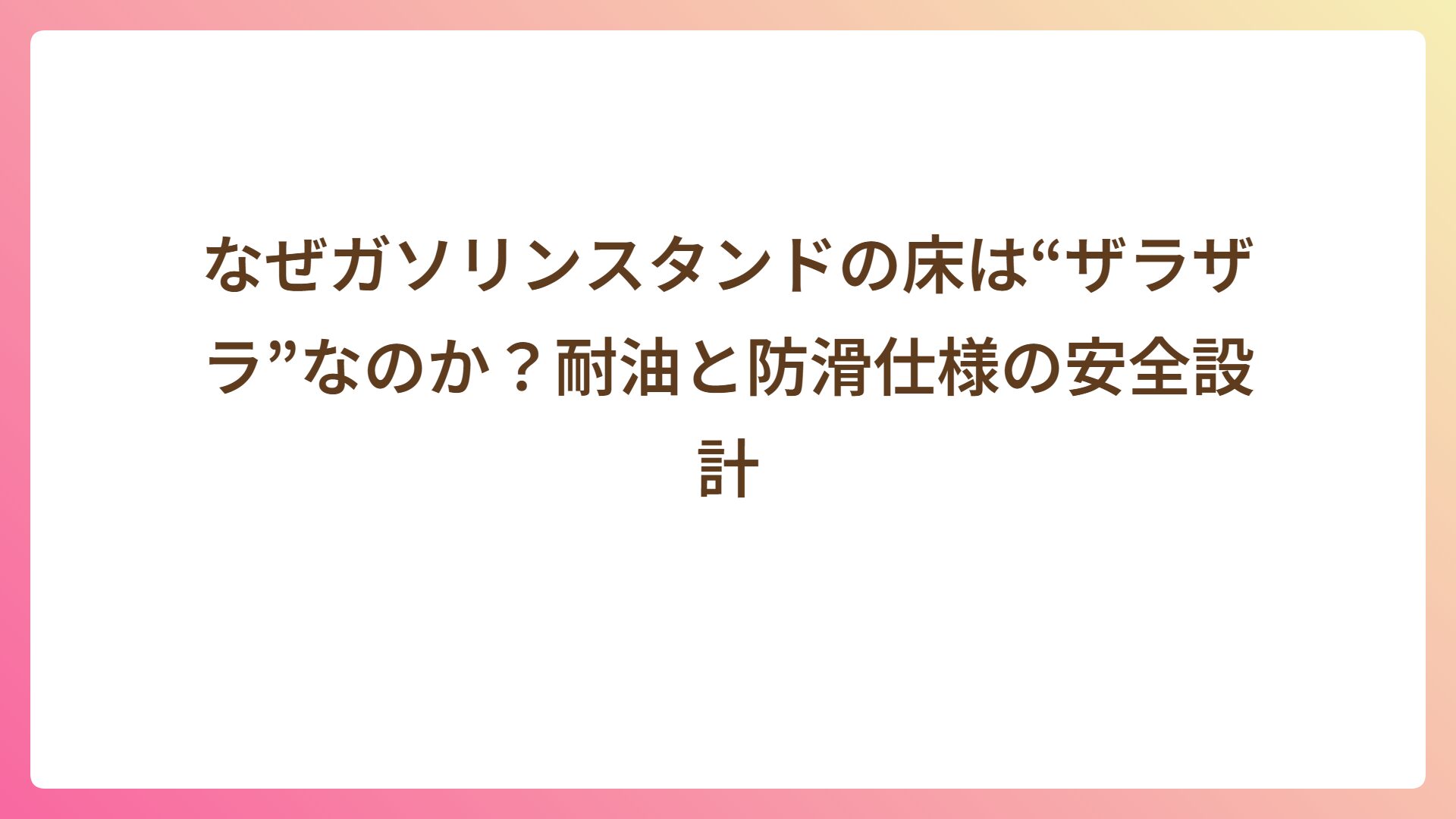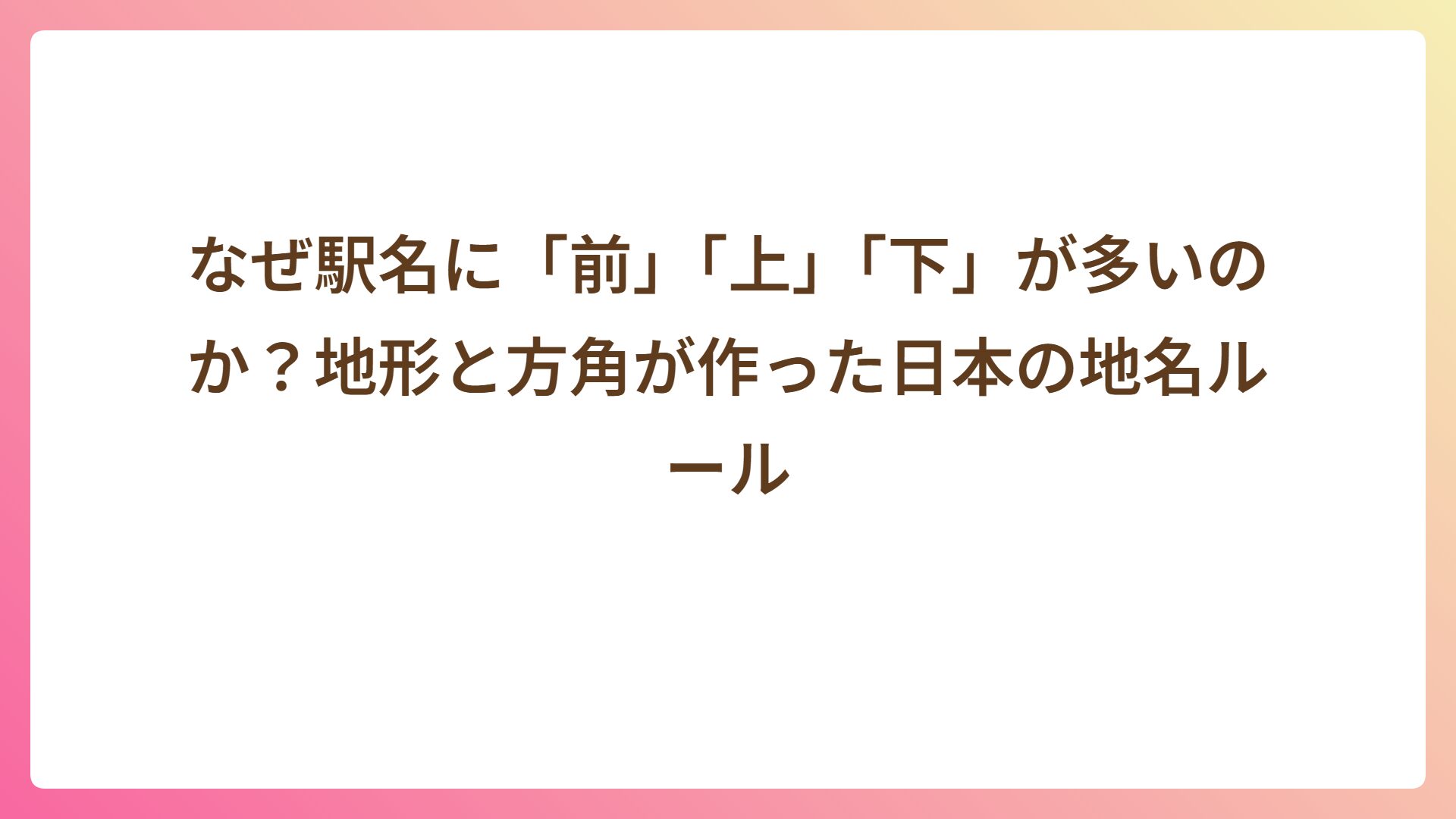なぜ飛行機の座席は左A列・右F列なのか?アルファベット配列に隠れた航空のルール
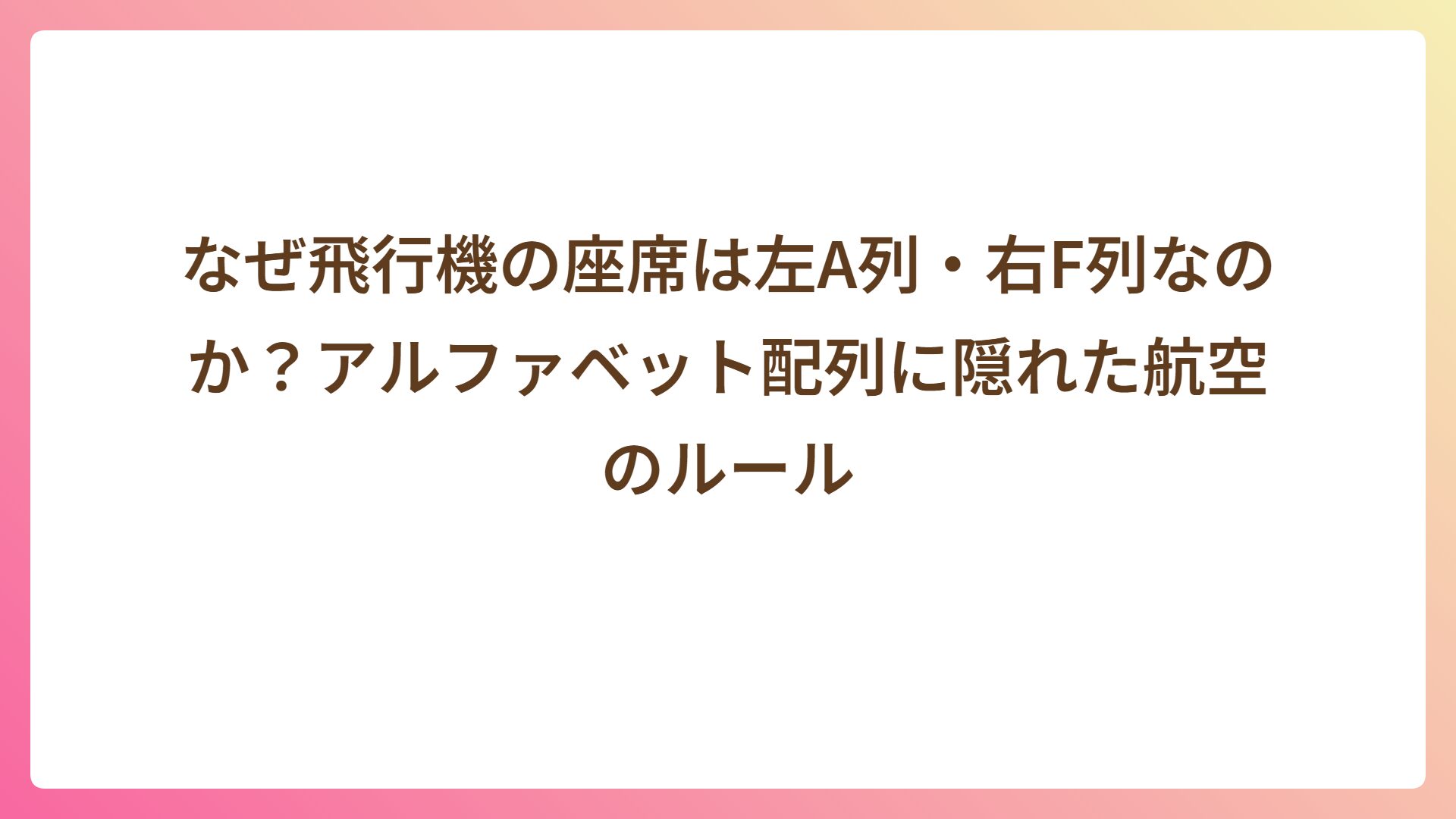
飛行機に乗ると、左側の窓際が「A列」、右側の窓際が「F列」となっています。
新幹線や映画館のように左右対称で“1〜6番”などの数字を使うわけではありません。
なぜ飛行機だけが、アルファベットでAからFのように座席を表すのでしょうか?
そしてなぜ「A列=左」「F列=右」なのでしょう?
このルールには、航空機の設計と国際的な慣習が深く関係しています。
Aは左側の窓際──“最初の文字”を左に置く航空業界の慣習
航空機では、A列=左側の窓際と決まっています。
これは世界中の航空会社で共通のルール。
理由は、航空の設計や運航手順で「左側=主導側」とされているからです。
実際に、
- 乗客の搭乗・降機は基本的に左側のドア(L1ドアなど)から行われる
- 航空機の左側は「ポートサイド(Port Side)」=港側と呼ばれる
つまり、左が基準になるため、座席も左端からAが始まるのです。
B・C・D・E・Fの並び方は「列の数」に対応
通常、エコノミークラスの座席は
3席+通路+3席の「3-3配列」が主流です。
その場合の座席記号は以下のようになります。
A B C 通路 D E F
左側3席がA・B・C、右側3席がD・E・F。
この配列は、通路を挟んでもアルファベット順が途切れず、
視覚的に分かりやすい配置になるよう設計されています。
通路が増えるとG・H・Jへ──IとOが使われない理由
大型機では「3-4-3」や「2-4-2」など、座席列がさらに増えることがあります。
その際の例がこちら。
A B C 通路 D E F G 通路 H J K
ここで気づくのが、「I(アイ)」と「O(オー)」が欠番になっている点。
これは、数字の1(イチ)や0(ゼロ)と混同しやすいため、
航空業界では混乱を避けてあえて飛ばしているのです。
たとえば「12I」と「121」を見間違えると大事故につながる可能性があるため、
国際的に「I」「O」は使用禁止の慣習が定着しています。
なぜ数字ではなくアルファベットなのか?
飛行機の座席は、数字(縦)×アルファベット(横)の組み合わせで管理されています。
- 数字:前後の列(1列目、2列目…)
- アルファベット:横方向の位置(A列、B列…)
この方式により、座席の位置を一意に特定できるわけです。
たとえば「12A」は「12列目の左窓際」ですが、
もし数字だけで表記すると、同じ12番が左右に存在して混乱します。
アルファベットを使うことで、国際便でも誤読しにくく、言語に依存しない表記が実現しました。
航空機メーカーによる配置の“ほぼ共通仕様”
航空会社ごとに内装デザインは異なっても、
座席番号とアルファベットの付け方はほぼ共通しています。
これは、
- 航空機メーカー(ボーイング、エアバス)側の図面規格
- 空港の予約・搭乗システム(IATA規格)
によって国際的に標準化されているためです。
たとえばボーイング737や777、エアバスA320でも、
「左A列/右F列」の基本構造は同じ。
世界中の乗客が直感的に座席を探せるよう、
あえて統一された配列ルールが維持されています。
例外:ビジネスクラスやLCCでは異なることも
ただし、機材によってはこのルールに例外があります。
- ビジネスクラスで1-2-1配列の場合:AとKのみ窓際になる
- LCC(格安航空)では簡略化のためA〜Fを統一せず
- 海外では一部でA〜Kを使わず「L列」まで続く機材も存在
それでも基本理念は変わらず、
左端をAにするという国際的慣習はほぼすべての航空会社で共通です。
まとめ:A列から始まるのは“航空世界の共通言語”
飛行機の座席が「左A列・右F列」である理由は、
- 左側が搭乗・基準側である航空慣習
- 右利き・視認性を考慮したアルファベット設計
- 国際規格による共通化
- IとOを避ける安全設計
といった、実務と安全を両立させる合理的なルールによるものです。
A列の窓際に座ったとき、
その「A」は単なる文字ではなく、100年以上続く航空文化の象徴なのです。