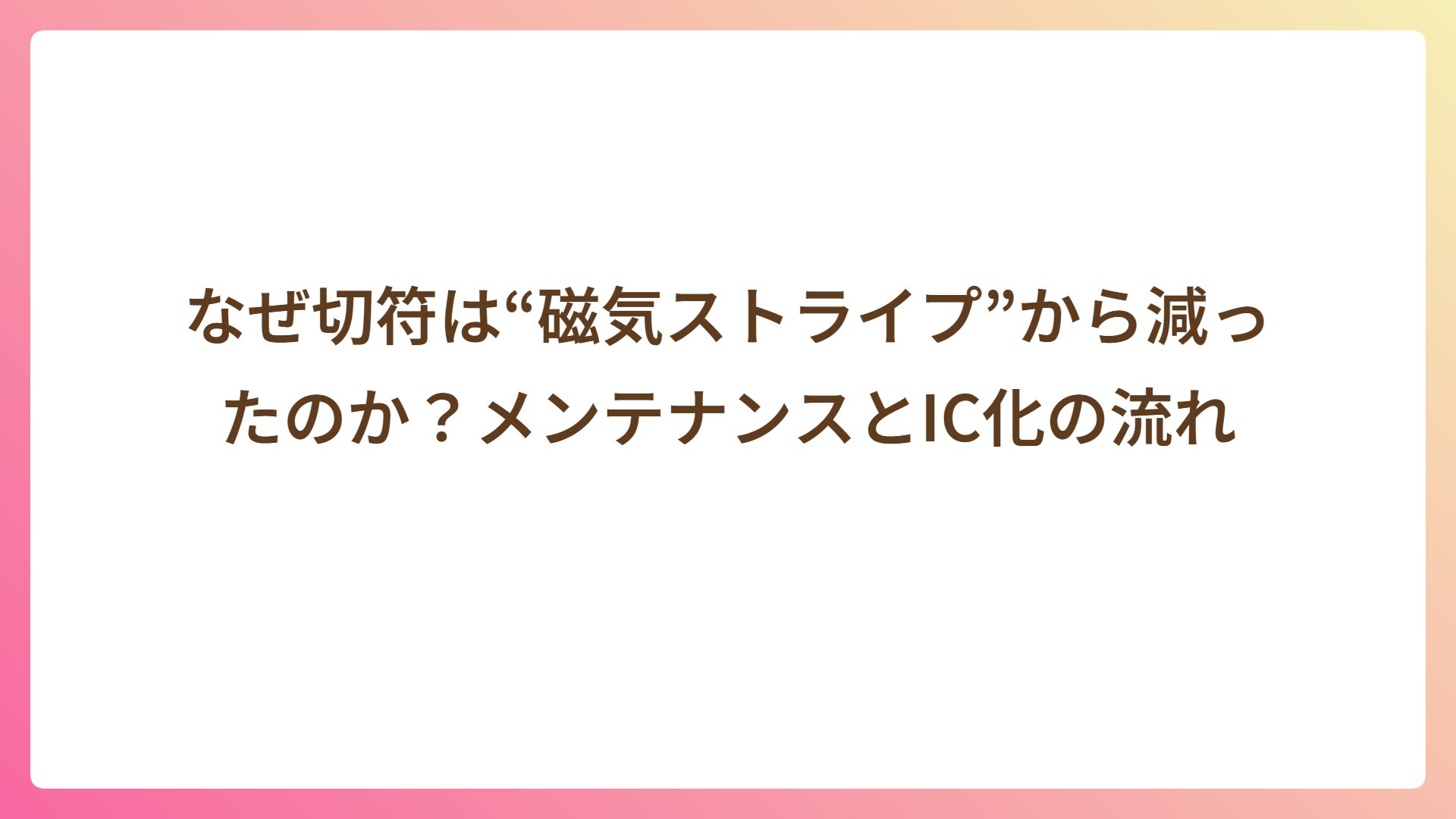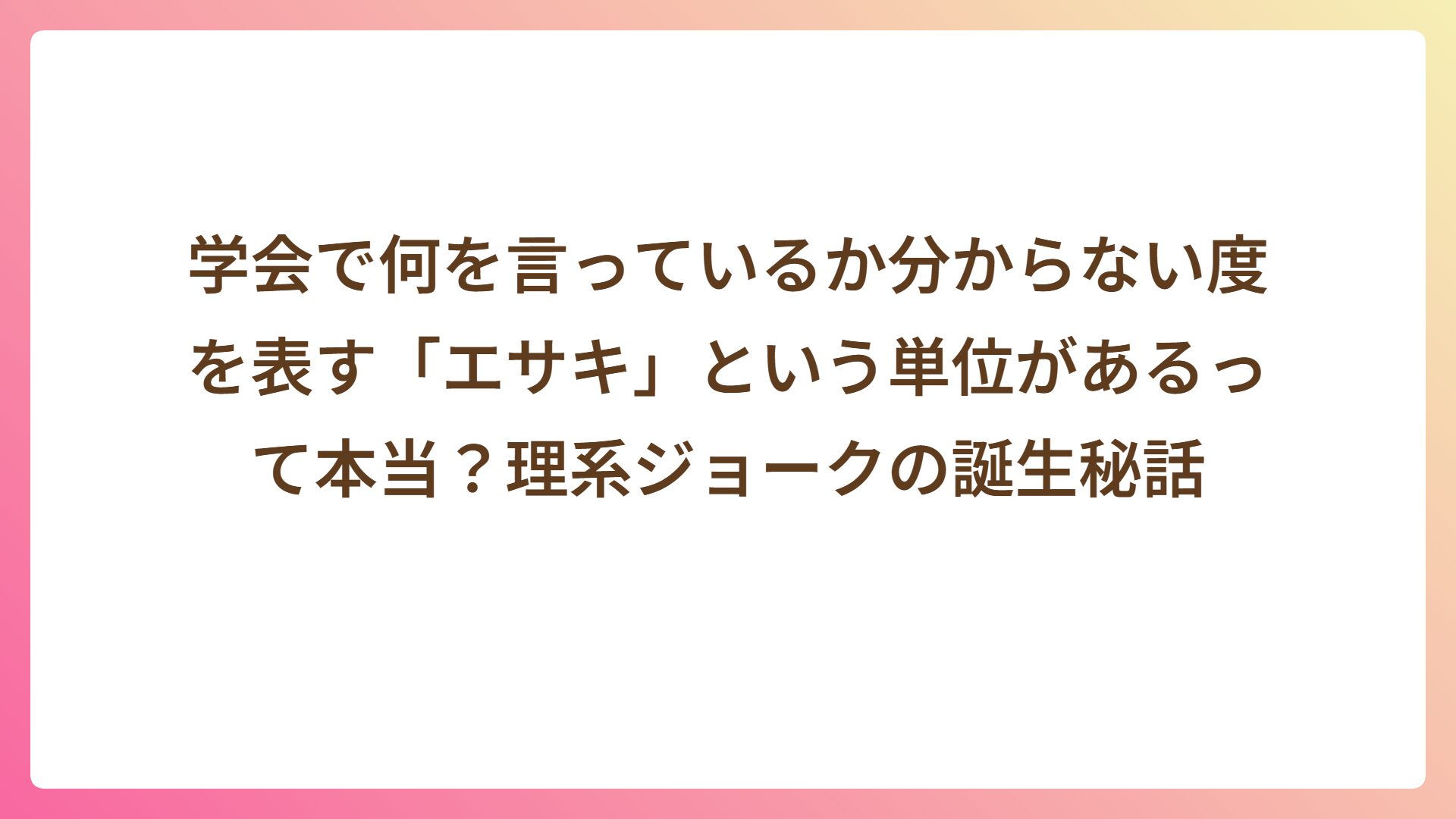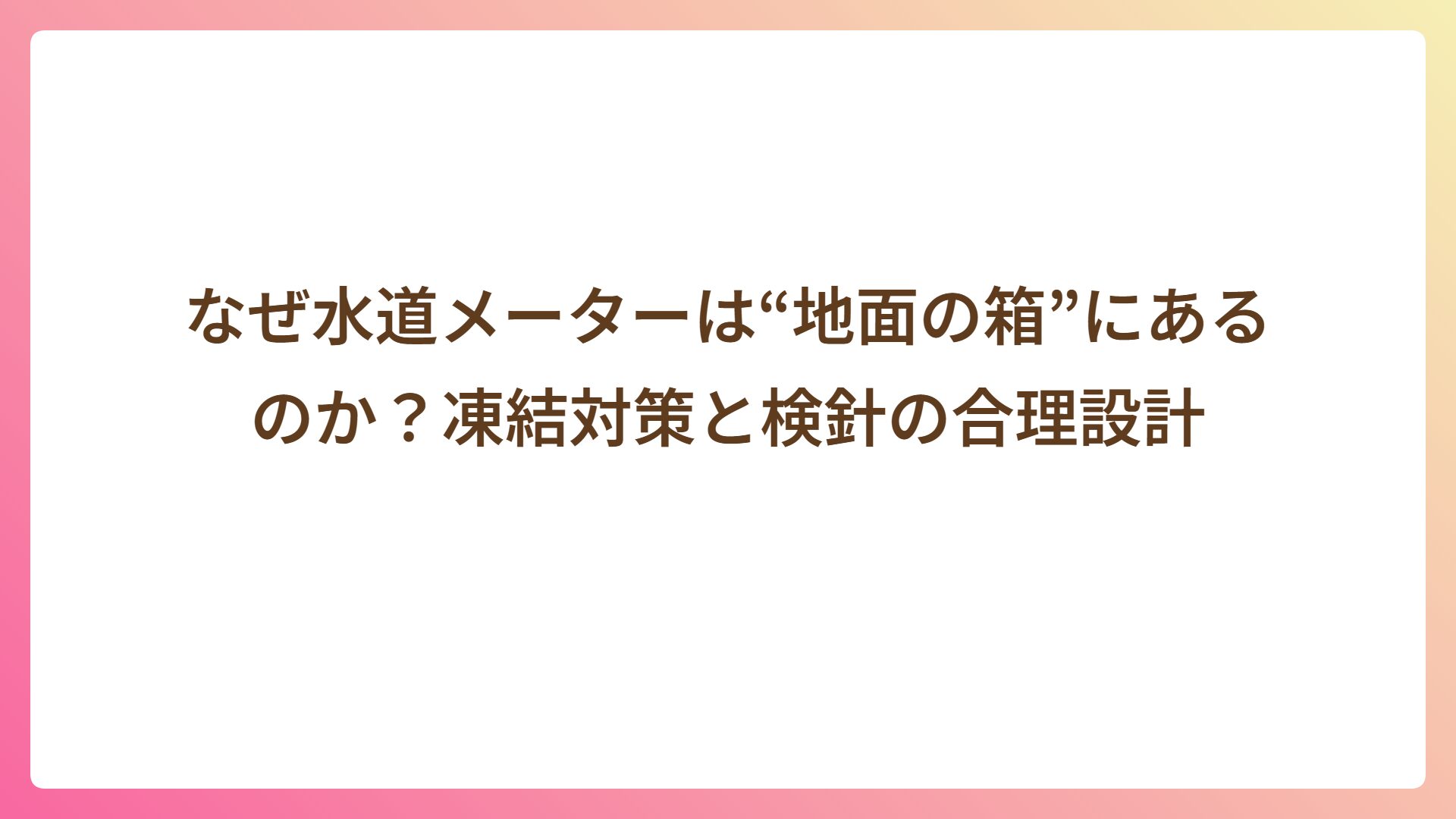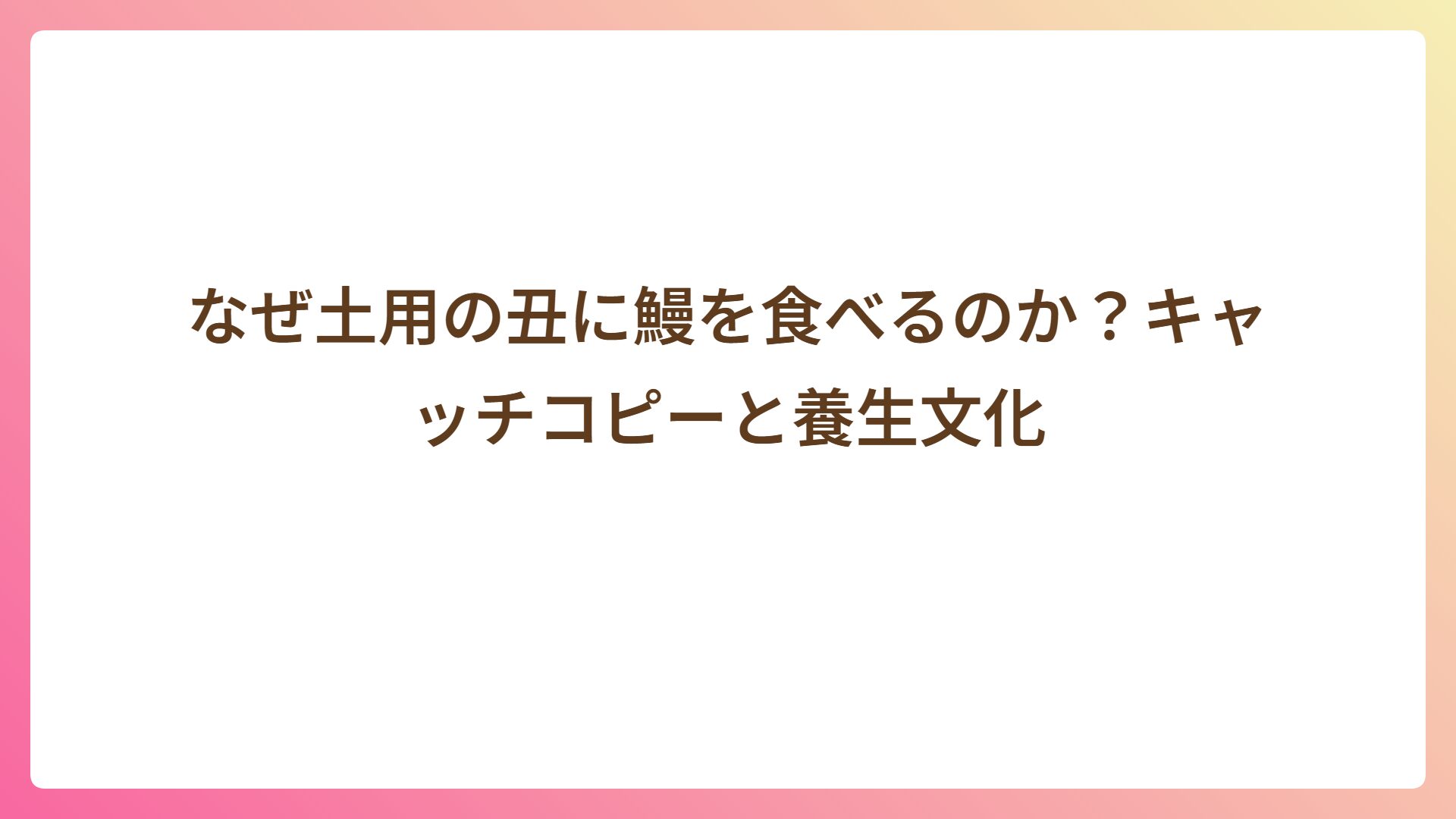なぜ交差点の信号制御は“歩車分離”が増えているのか?交通工学のトレードオフ
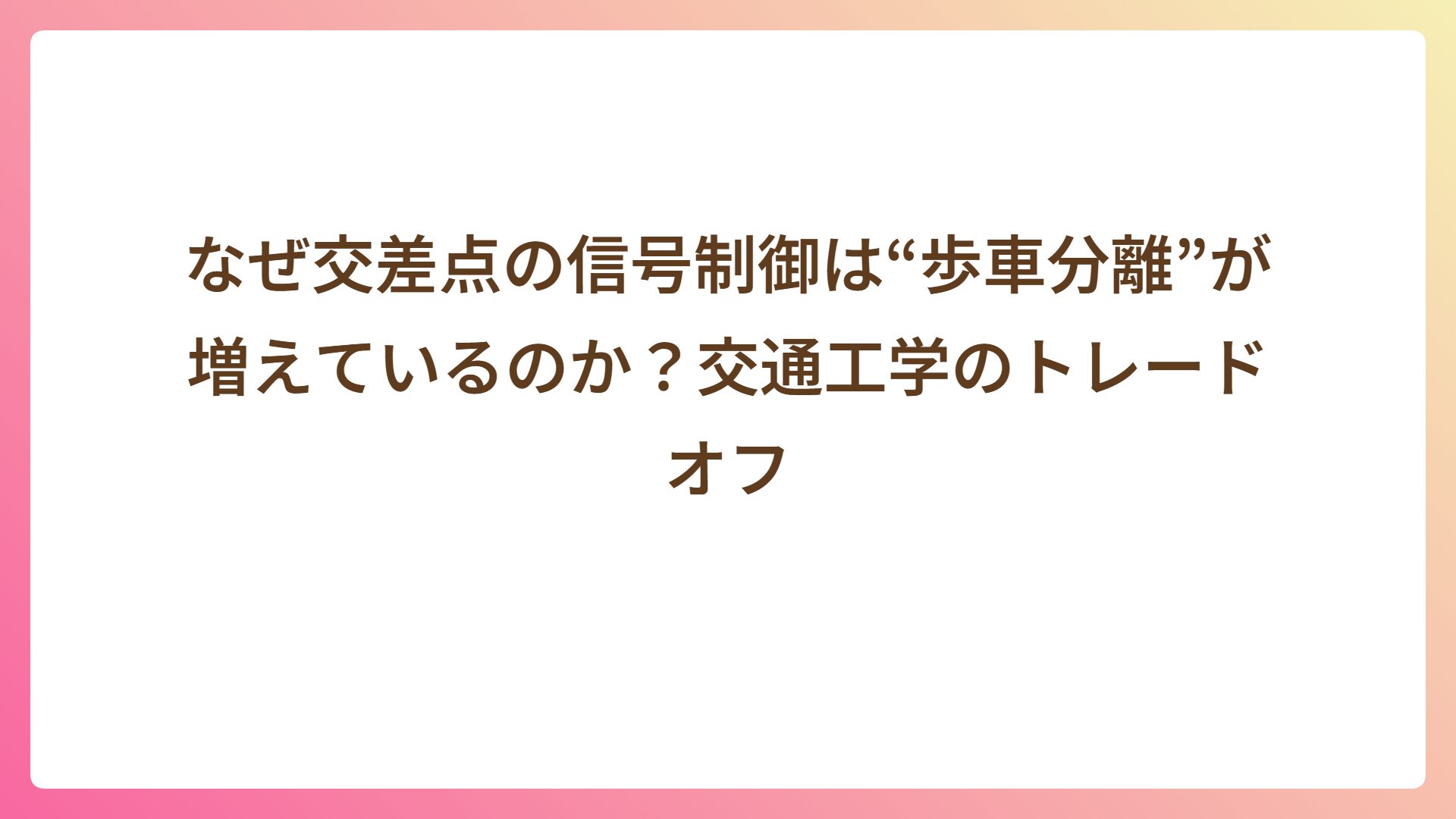
近年、都市部の交差点で歩車分離式信号を採用する場所が増えています。
これは、歩行者と車の青信号が重ならないように制御する方式です。
なぜ従来の「同時進行」から、わざわざ効率の悪い仕組みに変えているのでしょうか?
その背景には、交通事故の分析データと交通工学上のトレードオフがあるのです。
歩車分離式とは?
歩車分離式信号とは、交差点で車両と歩行者が同時に青信号にならないよう制御する方式です。
たとえば、車の青信号の間は歩行者は赤、
すべての車が赤になったタイミングで、歩行者だけが全方向に渡れるようになります。
この方式は、歩行者が右左折車両と交錯しないため、
車と人の接触事故を根本的に防げるのが最大の特徴です。
導入が増えた背景:右折事故の多発
警察庁の統計によると、交差点で発生する歩行者事故の約6割は右折車との接触が原因です。
特に信号が青であっても、車と歩行者が同時進行する従来型の信号では、
ドライバーが歩行者を見落とすケースが後を絶ちません。
そのため、2010年代以降は「安全最優先」の考えから、
交通量が多く歩行者が多い都市交差点を中心に歩車分離式へ改修が進められています。
安全性向上の効果
歩車分離式の導入後、警視庁の調査では
右左折巻き込み事故が約3〜5割減少したというデータがあります。
これは、車と人の動線を時間的に完全に分離したことで、
ドライバーが注意を分散させる必要がなくなったことによる効果です。
また、車道側も歩行者横断がなくなることで右左折の判断が単純化し、
運転者の心理的負担も軽減されます。
一方で“待ち時間が長くなる”デメリット
安全性が高い反面、歩車分離式には明確なデメリットもあります。
それは、信号サイクル(全体の時間)を長く取らなければならないという点です。
車・歩行者それぞれに独立した青信号時間を設けるため、
従来よりも1サイクルあたりの回転効率が下がり、
交通量が多い交差点では渋滞が発生しやすくなるのです。
交通工学的には、
- 事故率の低下(安全性向上)
- 交通処理能力の低下(効率悪化)
というトレードオフの関係にあります。
そのため、すべての交差点で採用されるわけではなく、
歩行者数や事故件数、道路構造を踏まえて導入の是非が個別に判断されています。
実際の設計では“歩車分離の強弱”を調整
近年の制御では、完全分離型だけでなく、
「右折時のみ歩行者と分離」「一方向だけ分離」など、
部分的な歩車分離制御も導入されています。
また、信号機の制御システムがAI化されたことにより、
時間帯や交通量に応じて**自動で歩車分離を切り替える“可変信号”**も増えています。
これにより、安全と交通流の両立を図る動きが加速しています。
高齢化社会とバリアフリー化の影響
高齢者や子どもが安心して横断できる環境を整える目的でも、
歩車分離式は効果的です。
視覚的にも「車が完全に止まってから渡れる」という安心感が得られるため、
ユニバーサルデザインの一環としての意味合いも持っています。
また、音響式信号や歩行者支援アプリとの連携も進み、
視覚障害者にとっても安全な横断環境を提供できる方式として位置づけられています。
まとめ
歩車分離式信号が増えているのは、
安全性と交通効率という相反する要素の最適化を図るためです。
確かに交通の流れは少し遅くなりますが、
その代わりに右左折巻き込み事故が減り、誰もが安心して渡れる街になる。
歩車分離の拡大は、“速度より安全”を選んだ都市交通デザインの象徴なのです。