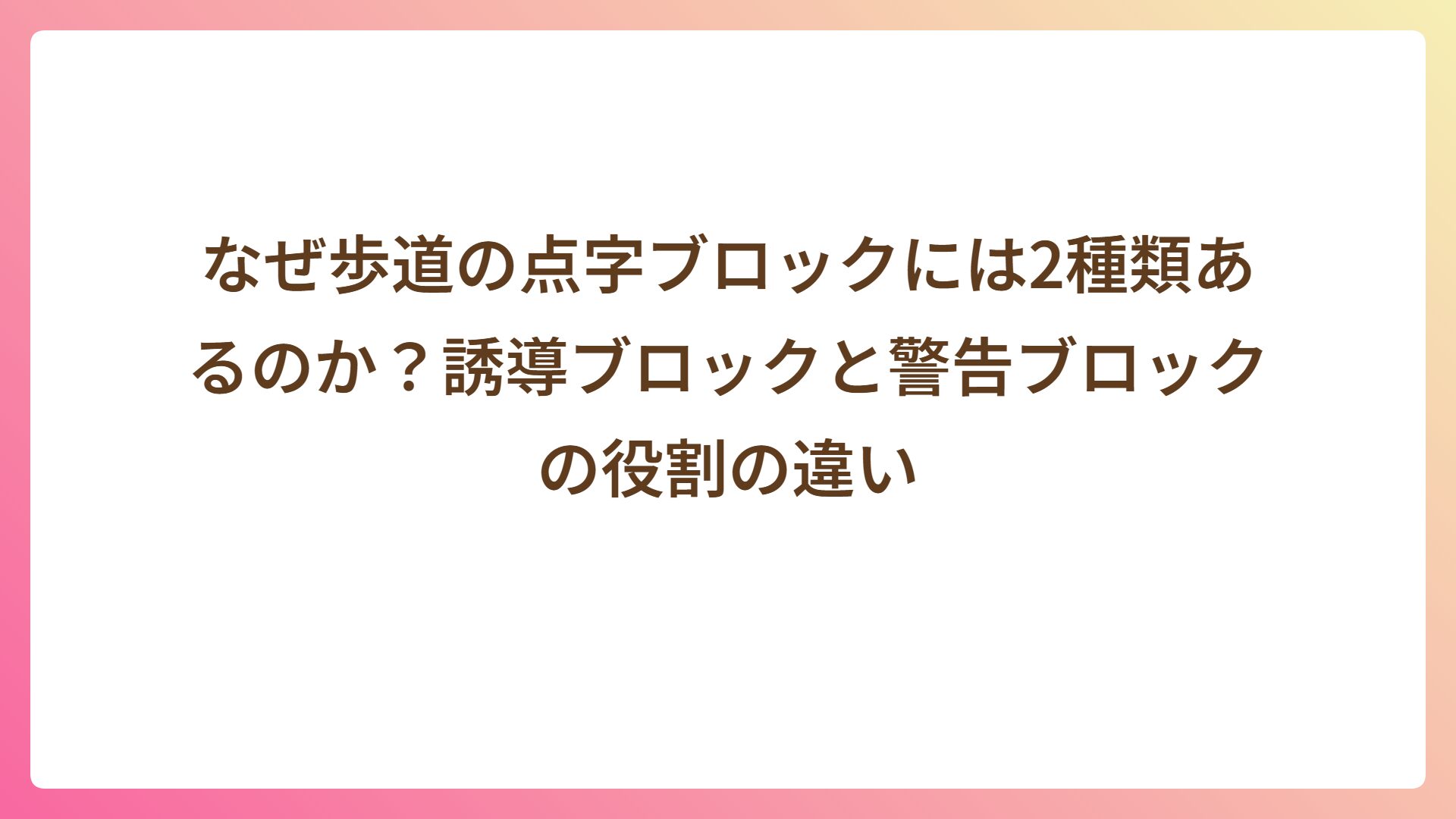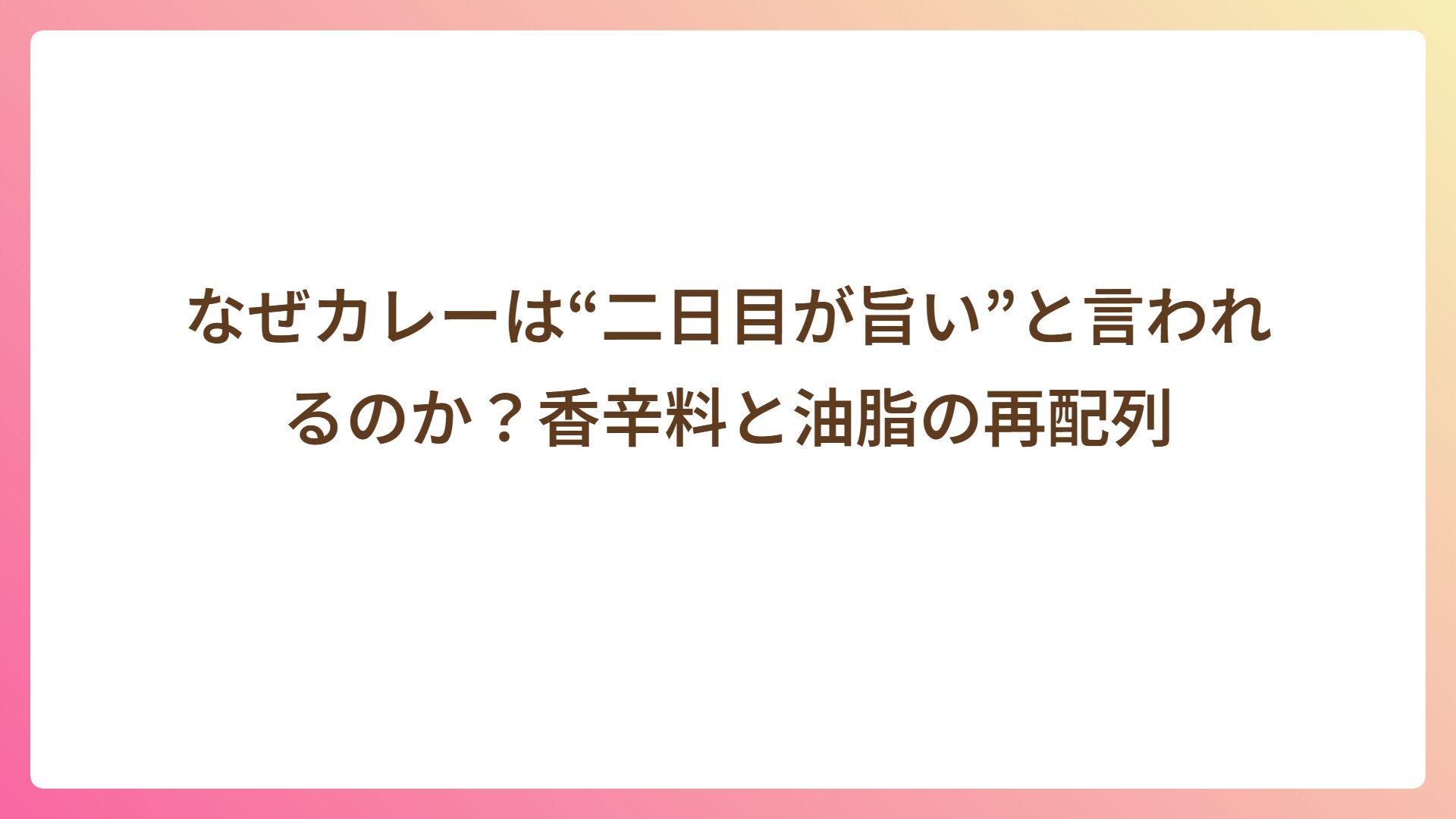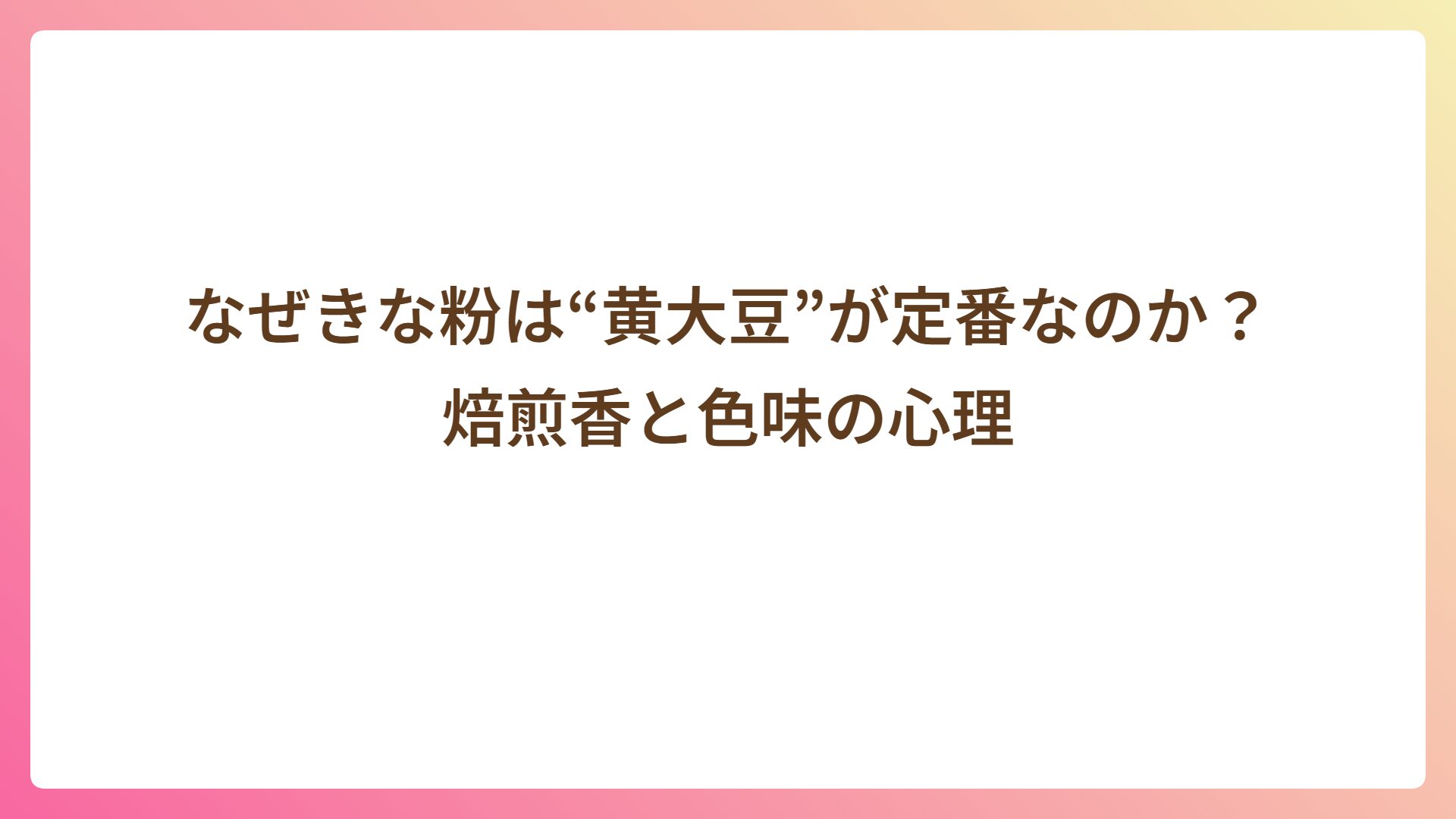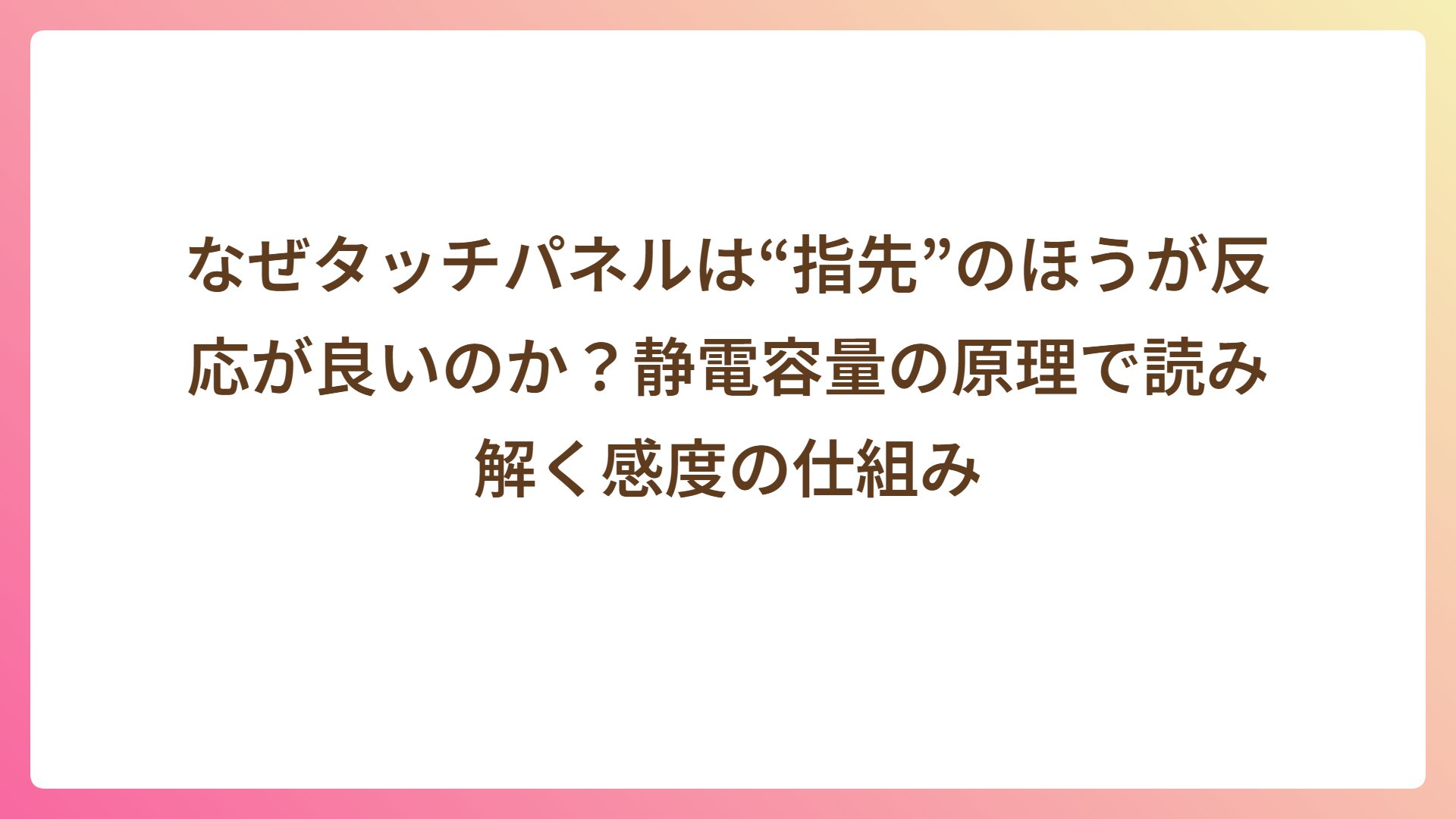なぜアイスの木棒は“白樺系”が定番なのか?割れにくさと口当たり
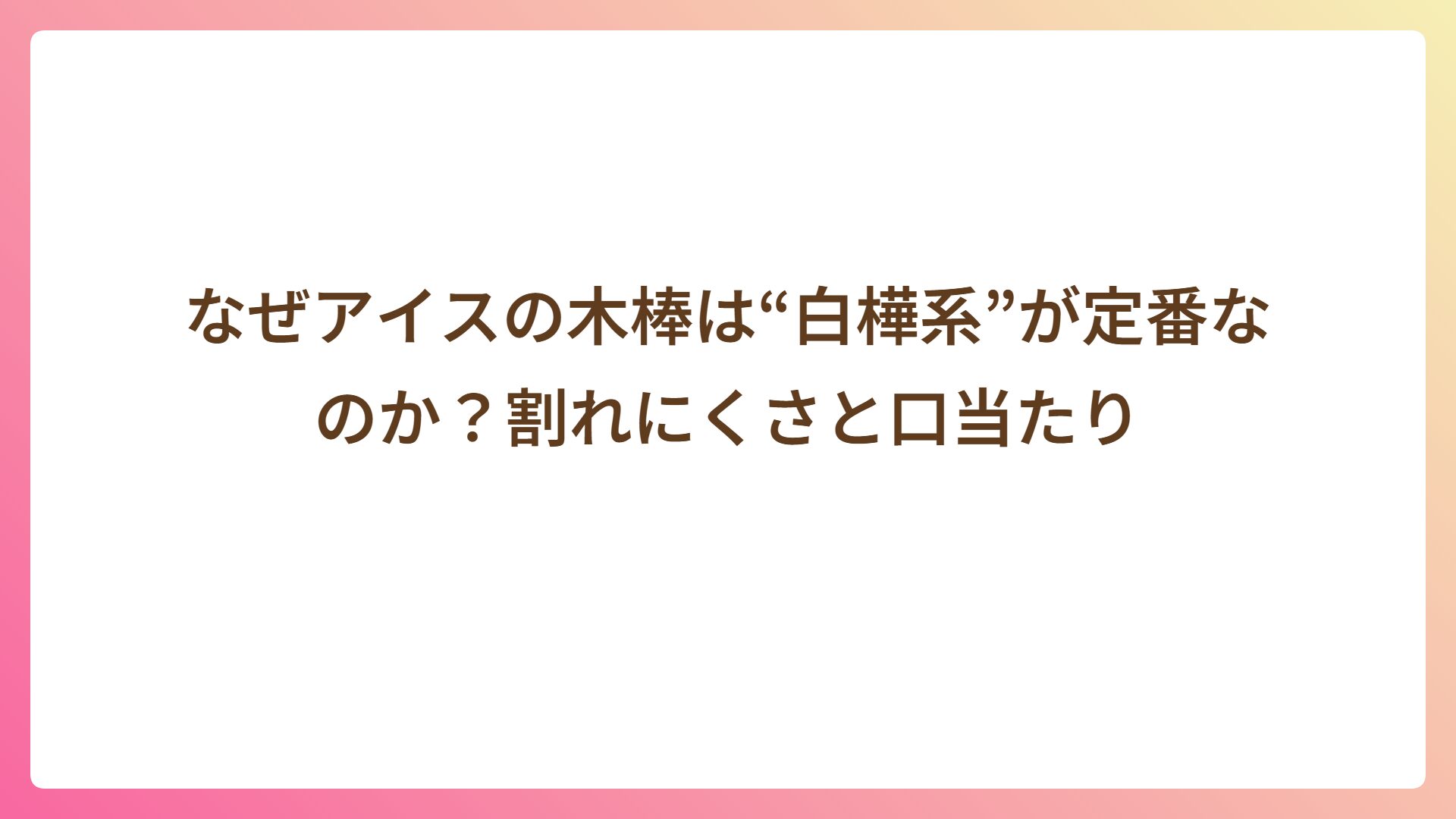
アイスバーを食べるときに必ず目にする木のスティック。
実はこの棒、ほとんどが白樺やバーチ(カバノキ)系の木材で作られています。
なぜ他の木ではなく、白樺が選ばれているのでしょうか?
その裏には、強度・衛生・食感のすべてを満たす理想的な素材特性が隠されています。
白樺系の木材が選ばれる理由
アイススティックの主流素材は、白樺(シラカバ)やダウンバーチ(欧州カバ)などのカバノキ科です。
これらの木は木目が細かく、繊維がまっすぐで均一なため、加工しても割れにくく、表面が滑らかに仕上がります。
同じ厚さのスティックでも、松や杉に比べて屈曲強度が高く、ささくれが出にくいのが特徴です。
つまり白樺は、薄く削っても強度が保てる「しなやかで丈夫な木」。
アイスを刺しても折れず、食べ終わるまで安全に使える構造的な安定性を持っています。
口に触れても“味や匂い”が少ない
もう一つの理由は、白樺の木は樹脂分や香り成分が少ないという点です。
アイスを食べるとき、木の棒が直接口に触れるため、木のにおいが強いと味に影響します。
白樺は木特有の苦味や渋みがほとんどなく、味や香りを邪魔しない中性の素材。
冷たい食品との相性が非常に良く、「無臭・無味・なめらか」な口当たりを実現できるのです。
滅菌・乾燥処理に適した構造
アイスのスティックは食品衛生法の管理下で製造され、高温乾燥や紫外線殺菌などの工程を経ます。
白樺は内部まで水分が抜けやすく、熱処理を行っても反りや変形が少ないため、
大量生産に向いた衛生的な素材としても優秀です。
また、繊維の密度が高く、細菌やカビが入り込みにくいため、
長期間の保管でも品質が安定しやすいというメリットもあります。
北欧発祥の“アイス棒文化”と白樺の関係
白樺が使われる背景には、北欧での木材利用文化も関係しています。
アイスバーが普及した20世紀初期、スウェーデンやフィンランドなど白樺の豊富な地域で、
医療用スパチュラや調理用スティックの素材として白樺が使われていたことが起源です。
その流れが食品業界に応用され、現在では日本でも同じ素材が定番となりました。
代替素材が主流にならない理由
竹やプラスチックも一時期検討されましたが、
・竹:繊維が硬く、割れやすくささくれが出る
・プラスチック:環境負荷が高く、口当たりが冷たく滑りすぎる
といった理由から主流にはなりませんでした。
白樺はその中間に位置し、自然素材でありながら加工性・安全性・快適性を兼ね備えた素材として、今もなお最適解とされています。
まとめ
アイスの木棒に白樺系の木材が使われているのは、
割れにくく・味を邪魔せず・衛生的に量産できる理想的な特性を持っているからです。
見慣れた一本のスティックにも、食の安全と心地よさを支える素材工学と文化の選択が詰まっているのです。