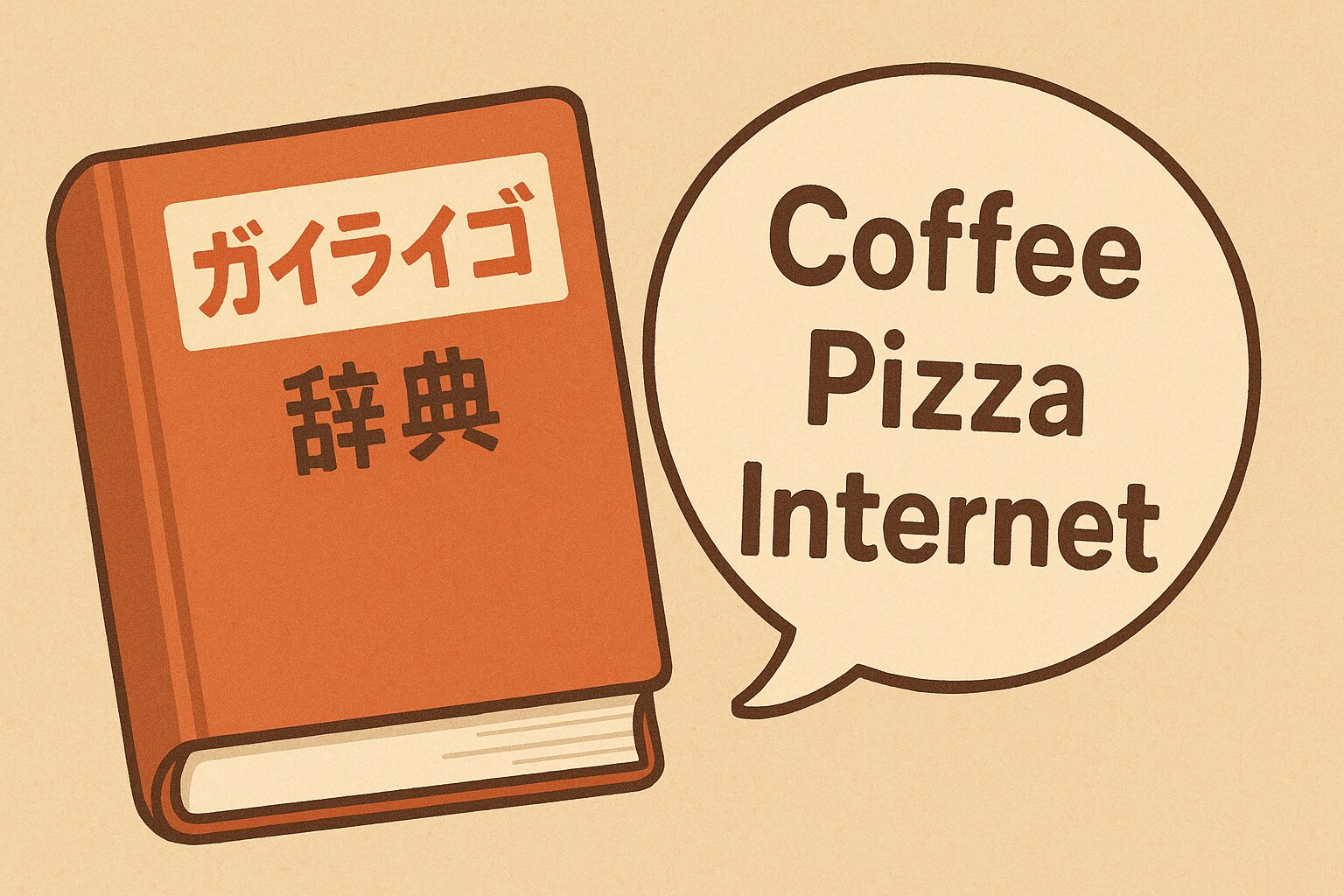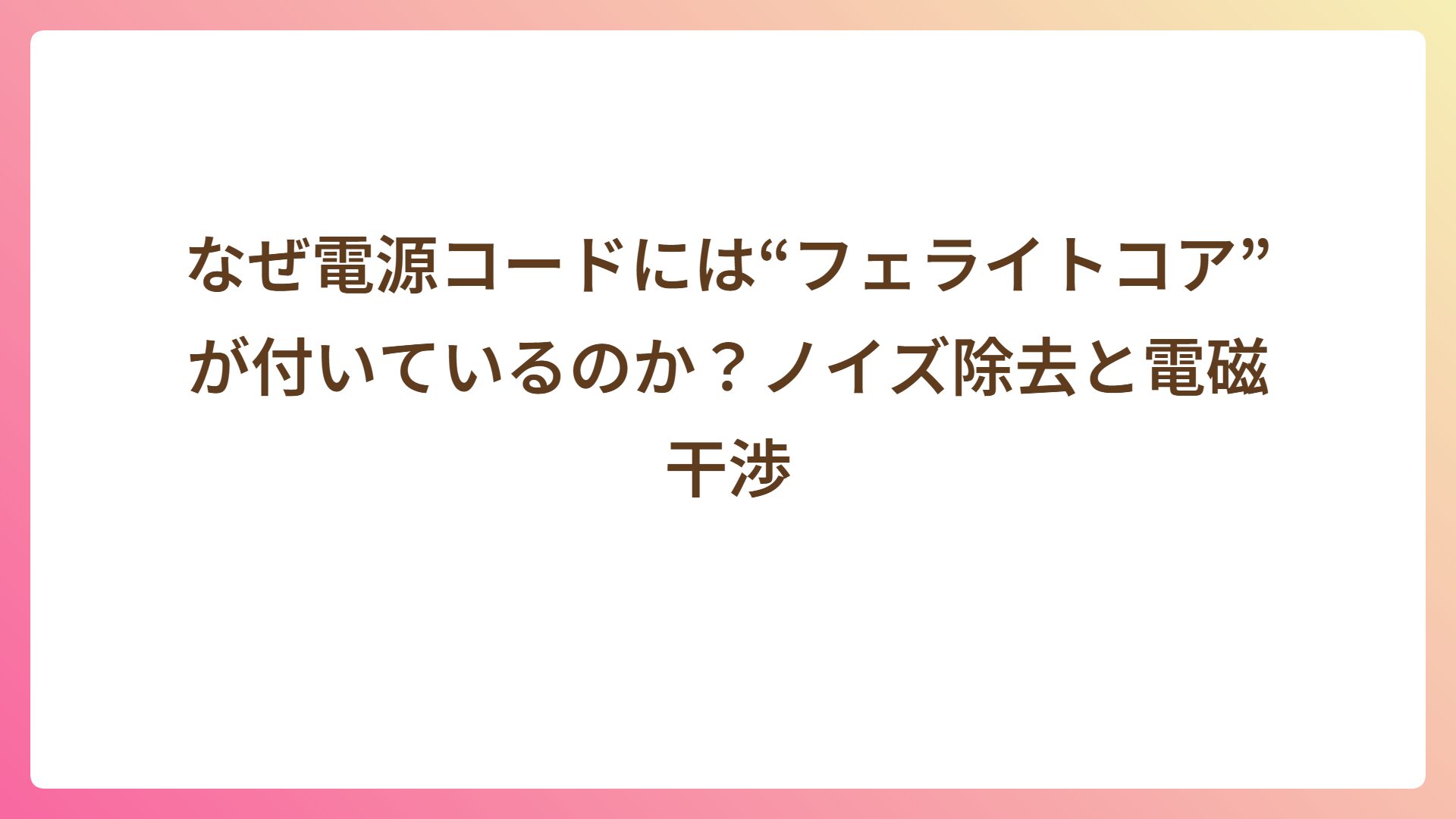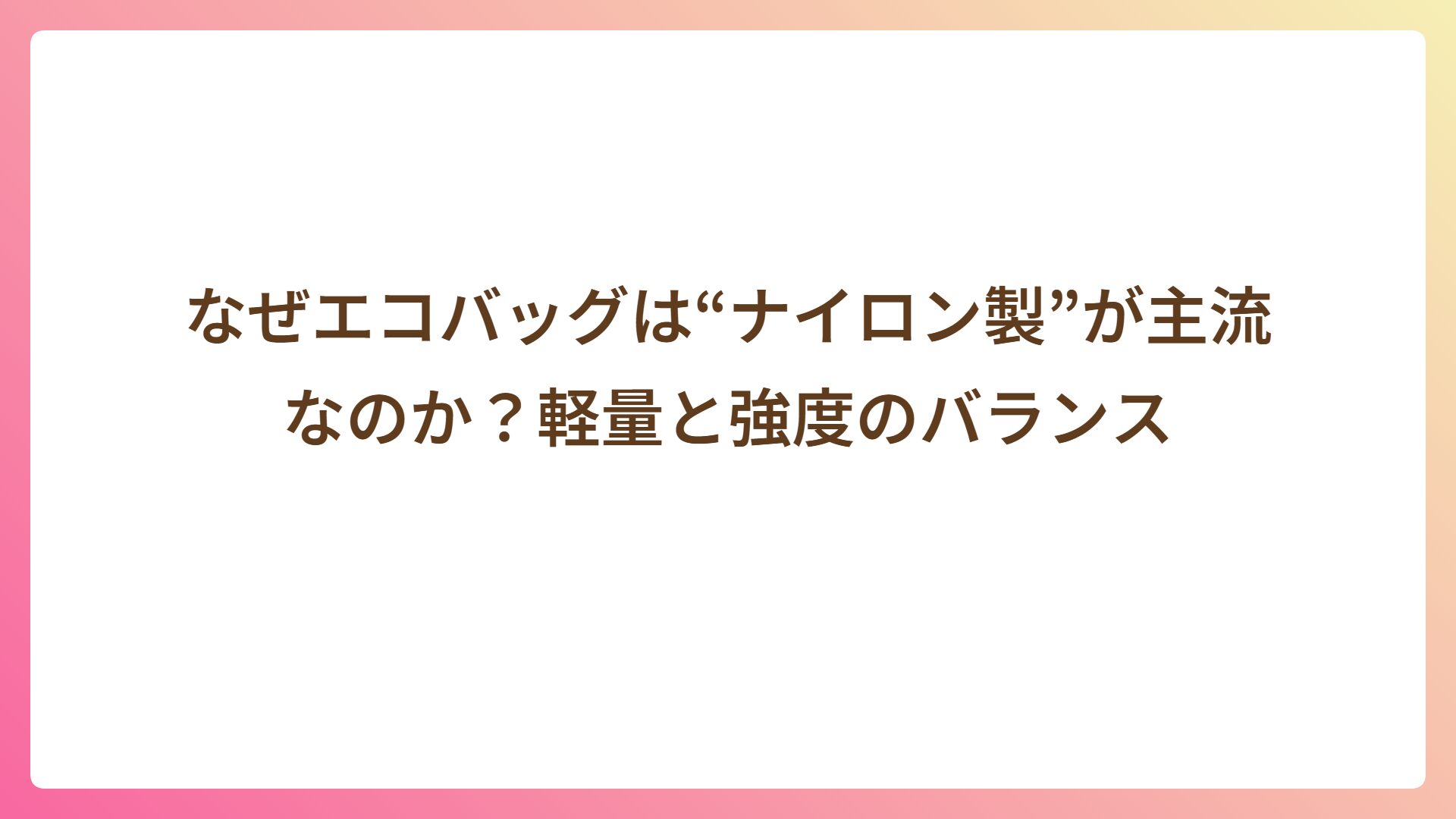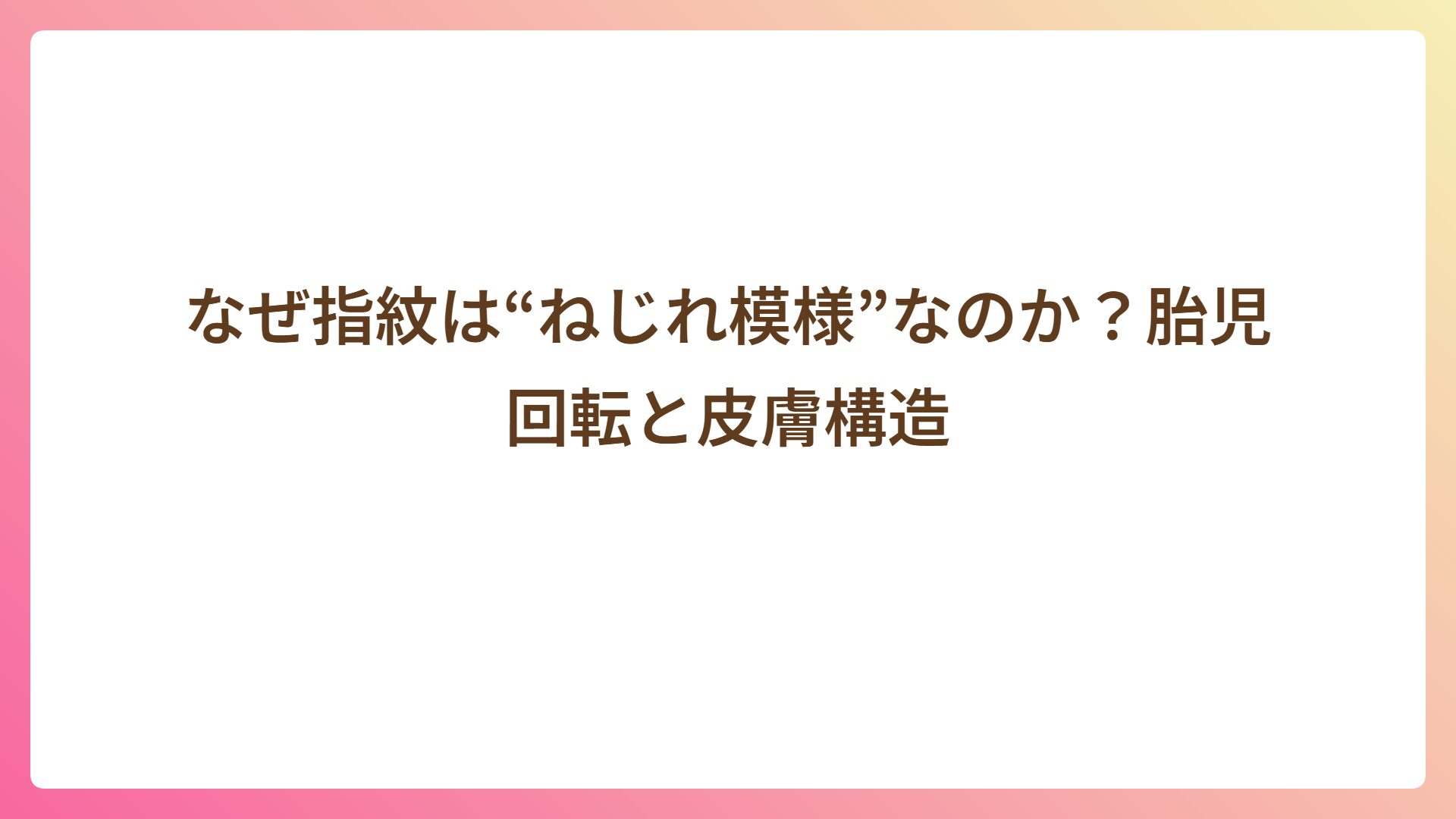なぜIHコンロでアルミ鍋が使えないことがあるのか?電磁誘導と素材の電気特性
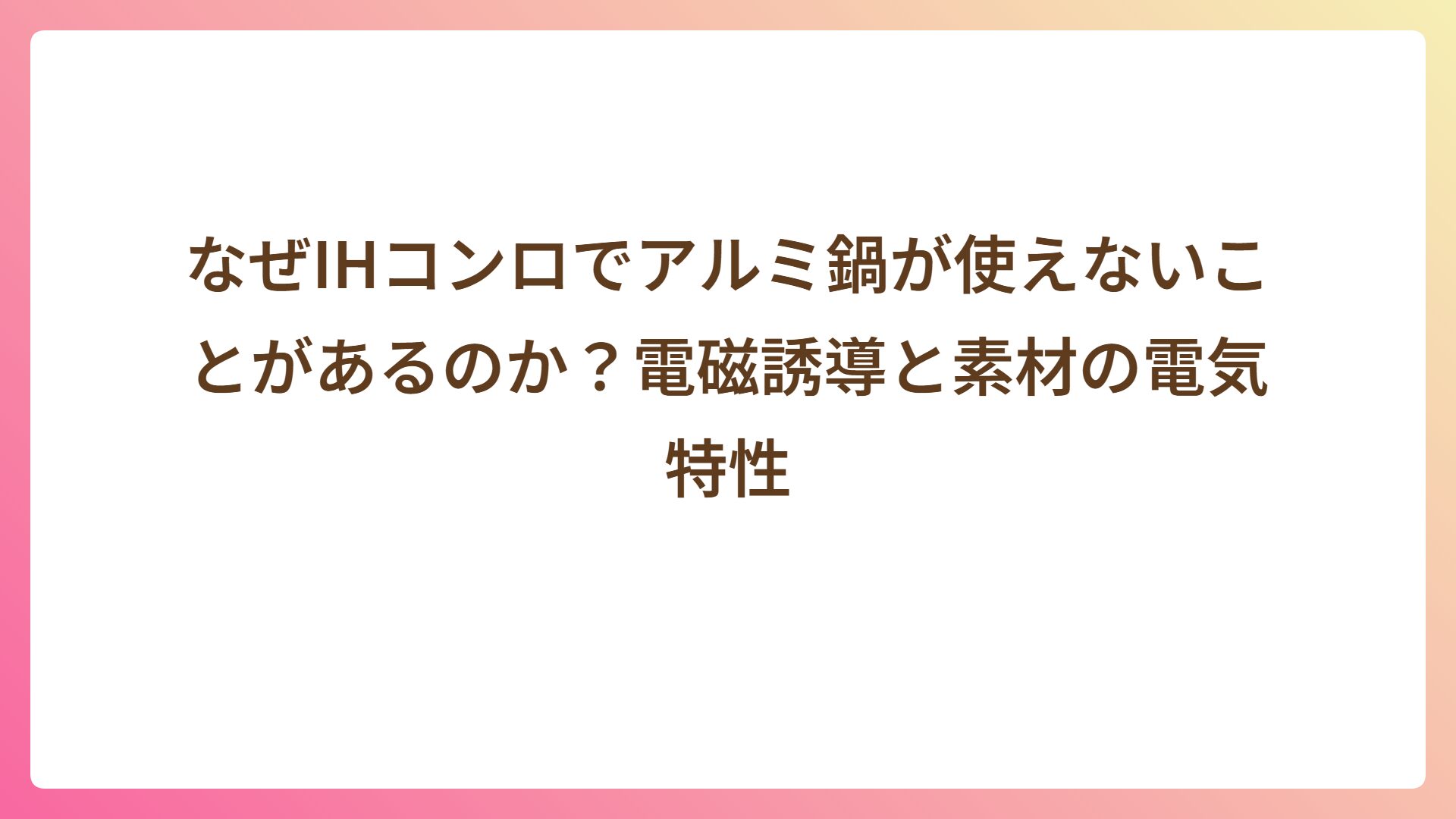
IHコンロにアルミ鍋を置いたのに「エラー」表示――そんな経験はありませんか?
ガスなら問題なく使えるのに、IHでは加熱しない。
実はそれ、電磁誘導加熱(IH=Induction Heating)という仕組みと、
金属の電気的性質が深く関係しています。
この記事では、IHコンロでアルミ鍋が使えない理由を、物理の原理からわかりやすく解説します。
理由①:IHコンロは“電磁誘導”で鍋を直接発熱させる仕組み
IHコンロは、電気を使って鍋そのものを発熱体に変える調理機器です。
内部のコイル(銅線)に高周波電流(20〜50kHz程度)を流すと、
その上にある金属鍋に磁力線が交差し、渦電流(うずでんりゅう)が発生します。
この渦電流が金属内部でジュール熱(電流の抵抗による発熱)を起こし、
鍋自体が熱源となって食材を加熱します。
つまり、IHは“ヒーターで鍋を温める”のではなく、
「電気を流して鍋自身を温める」方式なのです。
理由②:アルミや銅は“磁力を通しにくい”非磁性体
IH加熱が成立するためには、
- 磁力線が鍋の中を通りやすい(磁性体)
- 渦電流が発生して熱に変わる
という2つの条件が必要です。
ところがアルミや銅は、
磁性がほとんどない非磁性金属。
磁力線が通り抜けてしまうため、IHコイルからの磁束変化を受けても渦電流が十分に発生しません。
その結果、電磁誘導による発熱が起きず、コンロ側が
「加熱対象なし」と判断してエラー停止します。
理由③:鉄やステンレスが使えるのは“磁性体”だから
一方、鉄や一部のステンレス鍋がIH対応しているのは、
強い磁性(磁束を吸収する性質)を持っているためです。
磁力線が鍋内部を通過することで渦電流が生じ、
金属の電気抵抗で効率よく発熱します。
特に鉄系素材は、
- 比較的高い電気抵抗値
- 高い透磁率(磁束を通しやすい)
という特性を持つため、IH加熱に最適なのです。
理由④:アルミは電気は通すが“磁束を通さない”
アルミや銅は、電気伝導率は非常に高い金属です。
実際、電線や導体としても使われるほどです。
しかし、電気を通すことと「IHで発熱できること」は別。
IHは磁束変化による誘導電流が必要なので、
磁束を遮断する非磁性金属では、電流の流れ方が浅く、
発熱量が極端に小さいのです。
つまり、
- 電気的には優秀
- 電磁的には不向き
という特性が、アルミ鍋がIHで使えない理由なのです。
理由⑤:IH対応アルミ鍋は“底面に鉄を仕込んでいる”
最近の「IH対応アルミ鍋」には、
底面に鉄や磁性ステンレスのプレートを貼り合わせてあります。
この構造により、
- 鉄部分が磁力を吸収して発熱
- その熱がアルミ層へ伝わる
という間接加熱方式でIH対応を実現しています。
つまり、アルミ自体が発熱しているのではなく、
「鉄の層がIH対応を担っている」という仕組みです。
理由⑥:IHコンロが“使える鍋”を自動判定している
IHコンロは、通電時に磁束応答を自動で検出しています。
磁性体がなければ反応が弱く、
「鍋なし」と判断してエラーを出す安全機構になっています。
これにより、
- 空焚き防止
- 誤加熱防止
- 調理器具の保護
が実現しており、非対応鍋を加熱しないのは安全機能の一部でもあるのです。
理由⑦:IHの周波数と金属の“スキン効果”も関係する
IHは高周波電流を使うため、電流は金属表面近く(スキン層)しか流れません。
アルミはこの「スキン効果」が非常に浅く、電流が表面を滑ってしまい、
内部で熱が発生しにくいという欠点があります。
一方、鉄はスキン効果が深く、磁場の吸収率も高いため、
内部でしっかり発熱できるというわけです。
まとめ:IHで加熱できるのは“磁力を吸収する金属”だけ
IHコンロでアルミ鍋が使えないのは、
- アルミが磁性を持たず、磁力線を通さない
- 渦電流が発生せず、ジュール熱が生まれない
- コンロ側が「鍋なし」と判断して停止する
といった理由によるものです。
IH加熱の本質は、「磁力で電流を誘導して鍋を直接温める」こと。
つまり、磁石がくっつく金属(鉄・磁性ステンレス)しか発熱できないのです。
アルミ鍋を使いたい場合は、底に鉄プレートを備えたIH対応モデルを選ぶのが正解です。