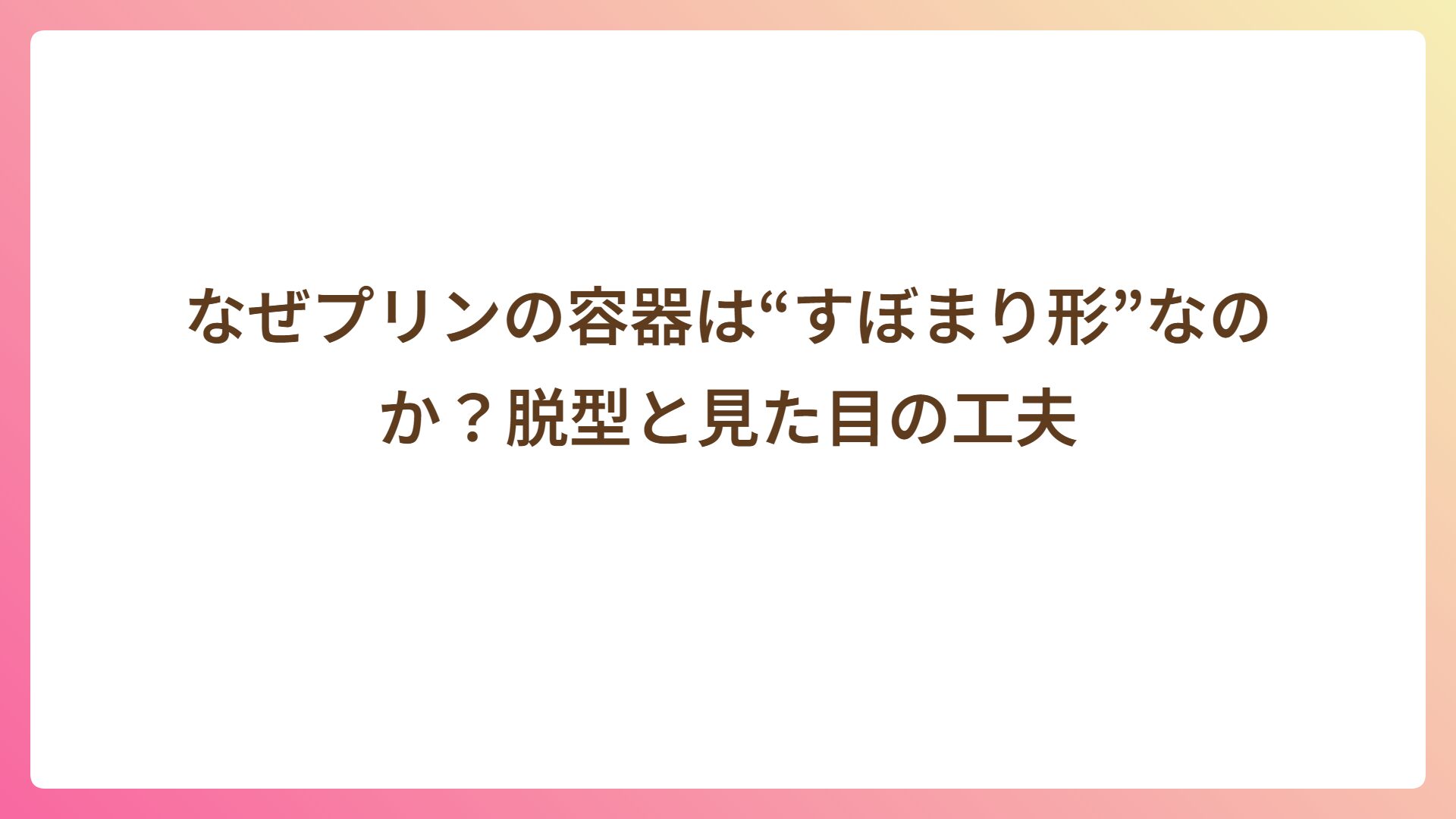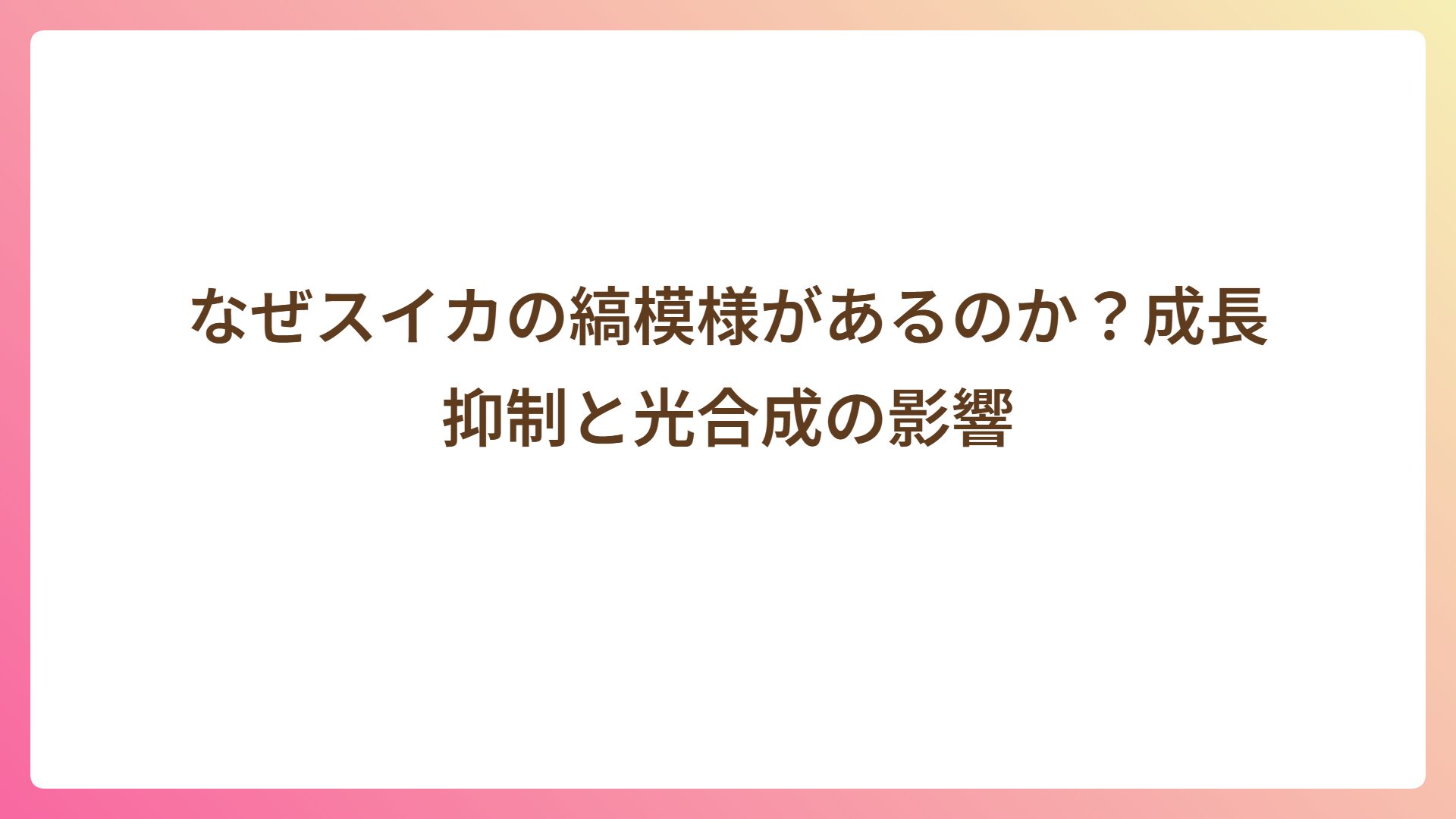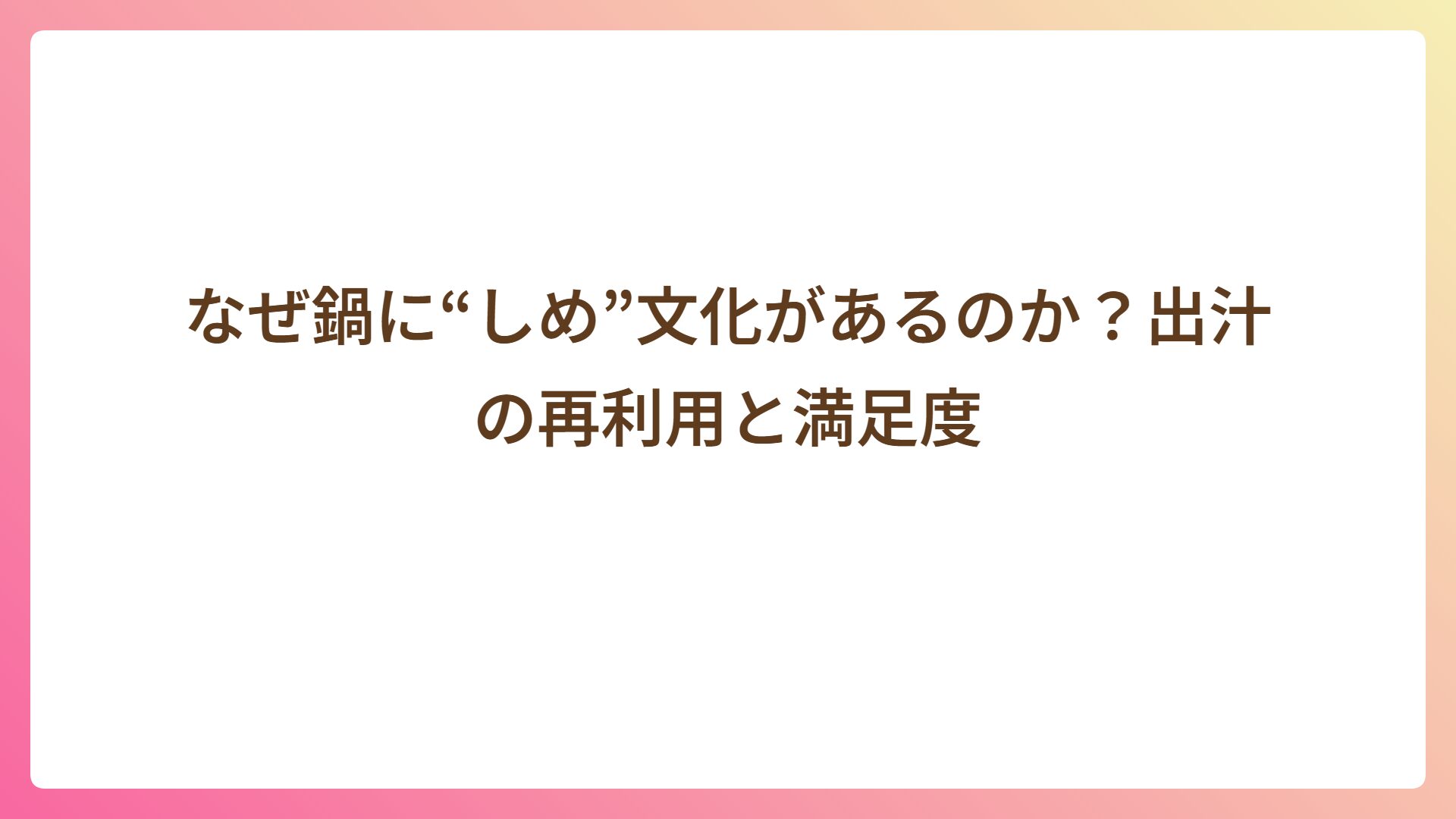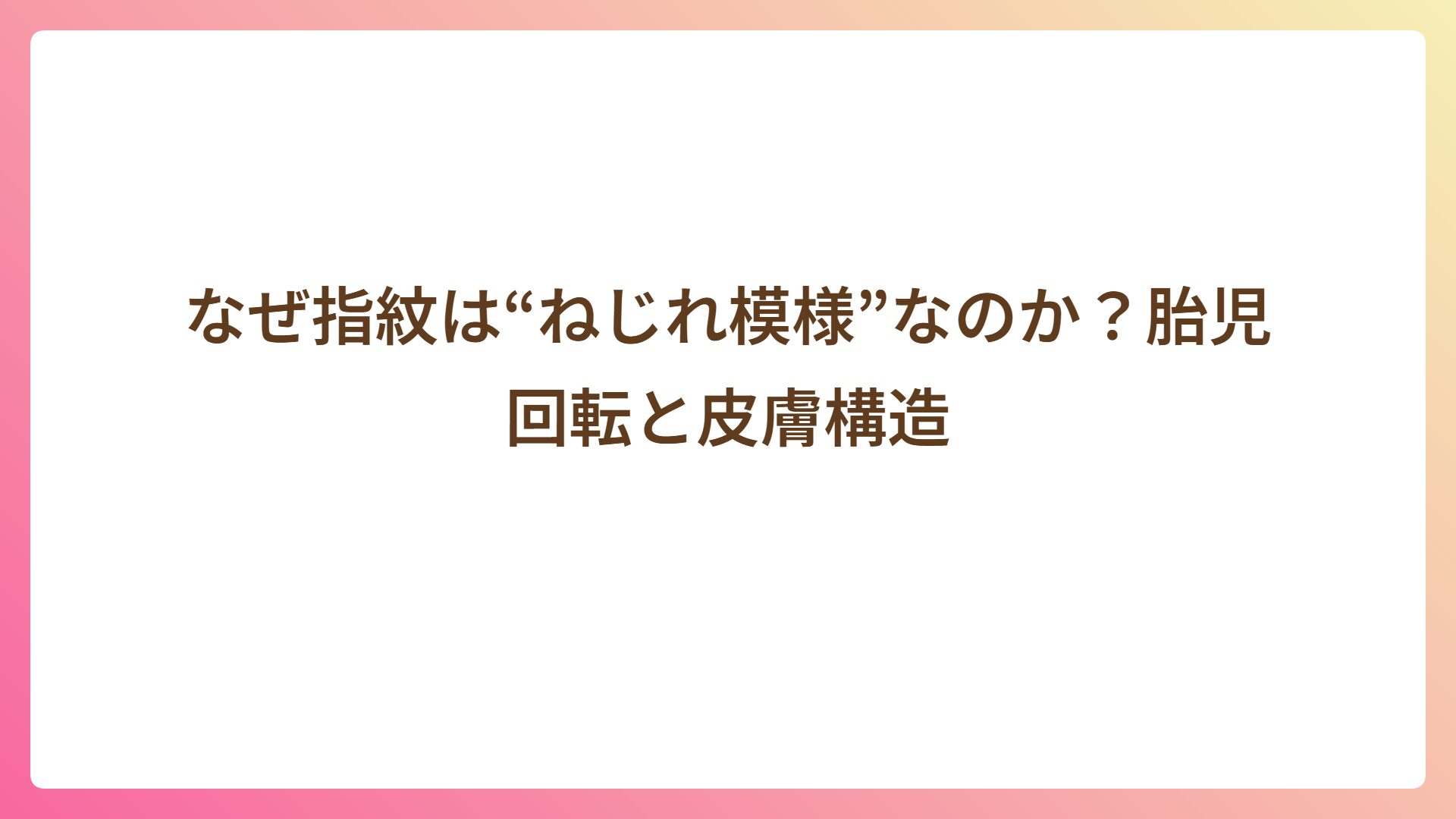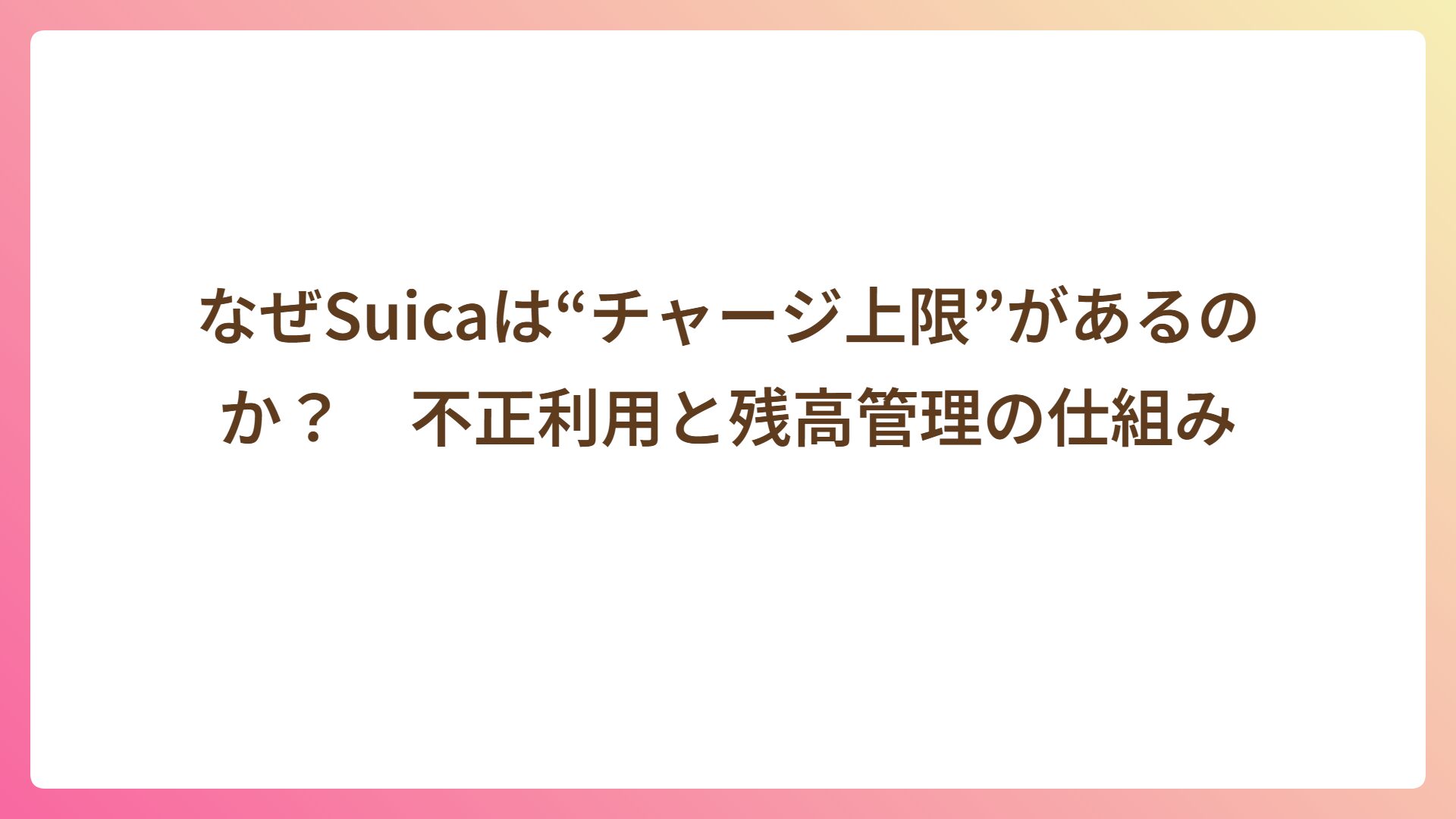なぜ隕石は燃えながら降ってくるのか?大気との摩擦と加熱の仕組みを解説

夜空を横切る光の筋――「流れ星」。
実はその多くは宇宙から飛来した小さな岩石=隕石(流星体)です。
なぜ彼らは、落ちながら燃え、時に眩しい光を放つのでしょうか?
この記事では、隕石が燃える理由を「大気摩擦」「圧縮加熱」「流星現象」の観点から解説します。
隕石が燃えるのは「摩擦熱」だけではない
よく「大気との摩擦で燃える」と言われますが、実はそれは半分正解で半分誤解です。
確かに空気との接触で熱が発生しますが、主な加熱の原因は――
大気が圧縮されることで生じる高温の空気による加熱です。
つまり、
- 隕石自身が“こすれて熱くなる”のではなく、
- 隕石の前方で“圧縮された空気が熱くなる”ことで、
その熱が表面を焼いているのです。
大気圏突入時の速度は秒速10km以上
隕石が地球の大気に突入する速度は、なんと秒速11〜70km(時速4万km以上)。
これは拳銃の弾丸の100倍以上の速さです。
この速度で突入すると、
空気の分子が隕石の前方で押しつぶされ、急激に圧縮されて高温(数千℃)になります。
その熱が隕石の表面に伝わり、岩石や金属が溶け、光を放ちながら燃えるのです。
光る正体は「流星現象」
隕石が燃えながら光る現象は、「流星(meteor)」と呼ばれます。
発光のメカニズムは次のとおりです👇
- 大気に突入 → 空気の分子と衝突してイオン化
- 高温のプラズマ(電離ガス)が発生
- そのプラズマが光を放つ
つまり、流星の光は隕石そのものが光っているのではなく、周囲の空気が発光しているのです。
大気圏で燃え尽きるか、地表に落ちるかの違い
隕石の大きさや構成によって、
- 完全に燃え尽きるもの(流星)
- 一部が残って地表に落ちるもの(隕石)
に分かれます。
| 種類 | 大きさの目安 | 結果 |
|---|---|---|
| 微小な塵(〜数mm) | 大気で完全に燃え尽きる | 流星(流れ星) |
| 数cm〜数m | 一部が溶け残り地上へ | 隕石として落下 |
| 数十m以上 | 空中で爆発・衝撃波を発生 | チェリャビンスク隕石など |
つまり、「燃えながら降る」現象は、地球が天然の“防御シールド”で守られている証拠でもあります。
燃え尽きたあとの“隕石の表面”にも痕跡が
地上に落下した隕石の表面を見ると、黒く焦げたような模様が見られます。
これは大気圏での加熱と融解によってできた「溶融皮膜(フュージョンクラスト)」と呼ばれるものです。
つまり、燃えながら降下した記録が、隕石の表面にそのまま残っているのです。
地球の大気は“天然のバリア”
もし地球に大気がなければ、隕石は燃えずにそのまま地表に衝突し、巨大な被害をもたらすでしょう。
大気は摩擦や圧縮を通じて隕石のエネルギーを減衰させ、
地球を守る天然の防護シールドとして働いているのです。
実際、地球に到達する隕石の99%以上は大気中で燃え尽きています。
まとめ:隕石が燃えるのは「大気の圧縮熱」が原因
隕石が燃えながら降ってくるのは、
- 大気との衝突で空気が圧縮されて高温になる
- その熱が隕石を加熱・発光させる
- プラズマ化した空気が光を放つ(流星現象)
という物理現象によるものです。
つまり、夜空を横切る流れ星の正体は、
宇宙の石と地球の大気が出会って燃え上がる、一瞬の物理ショーなのです。