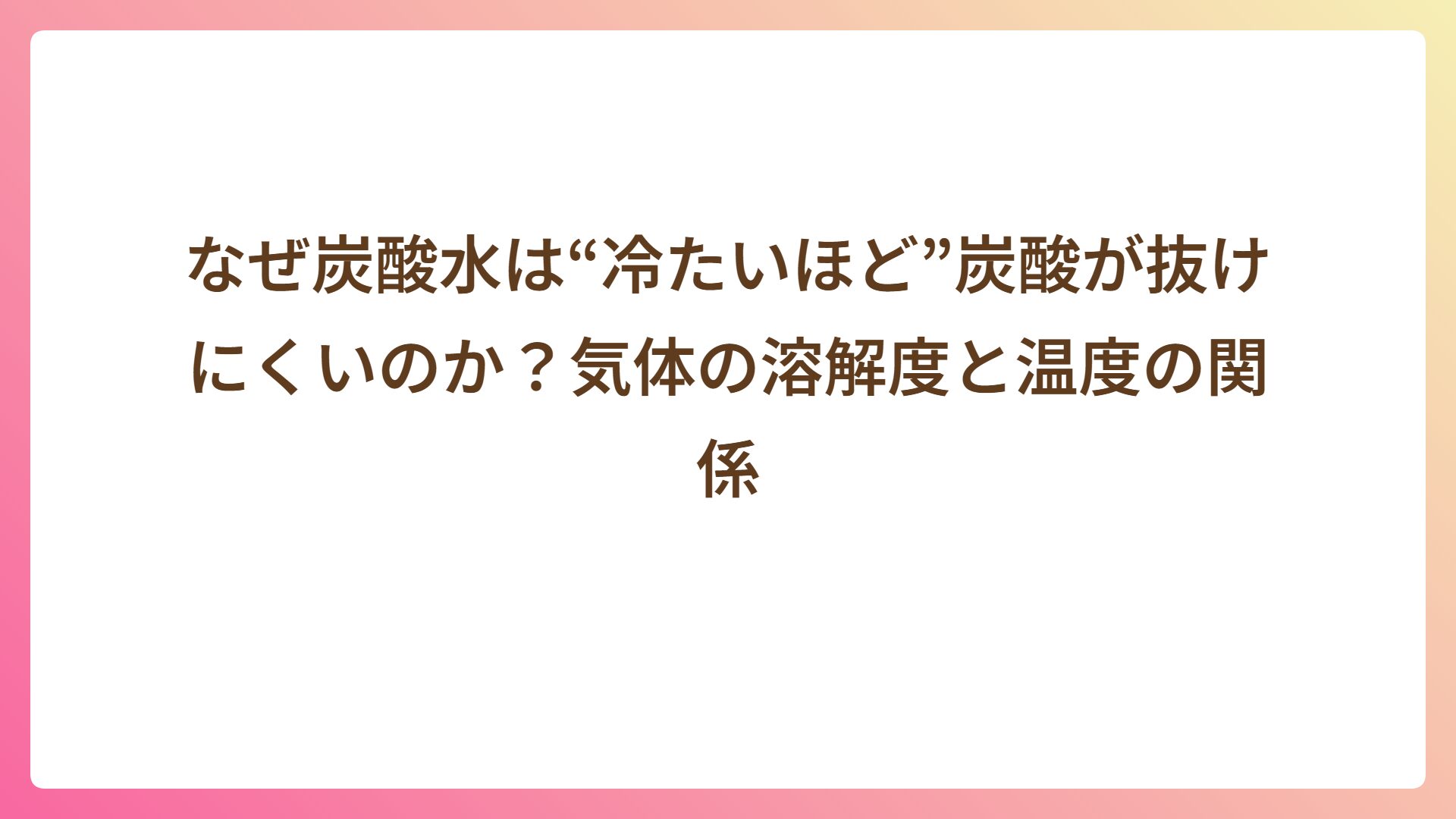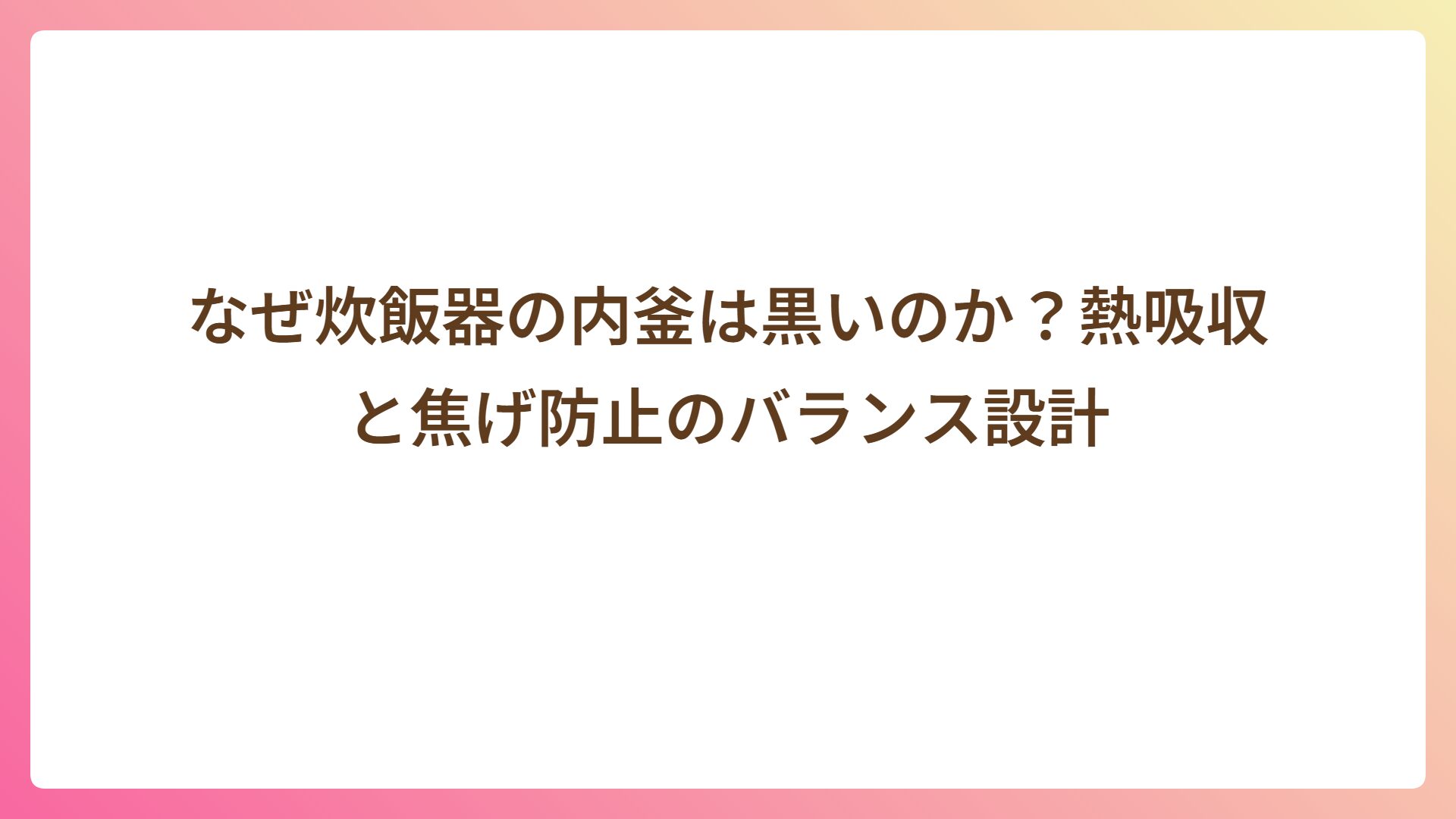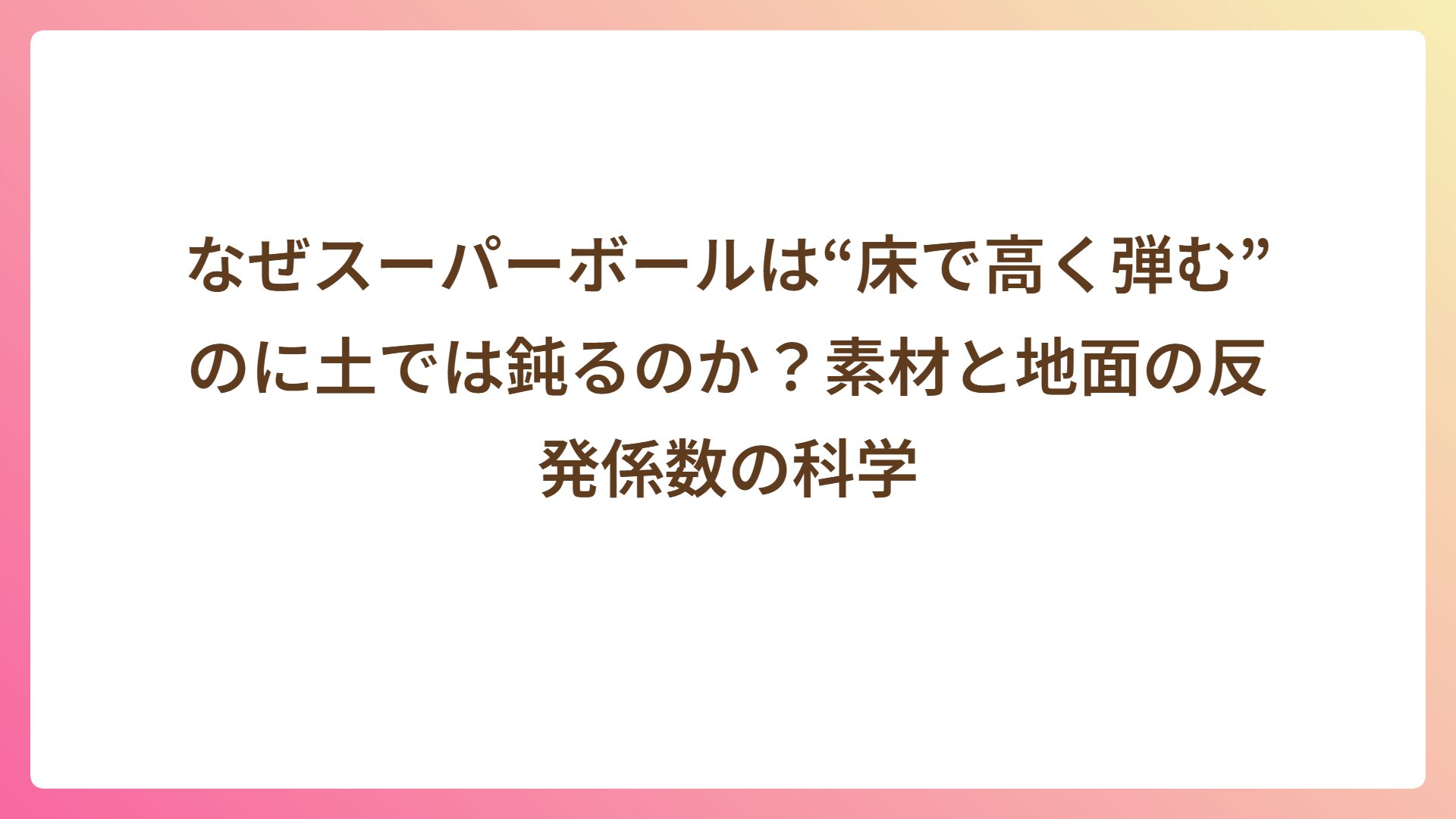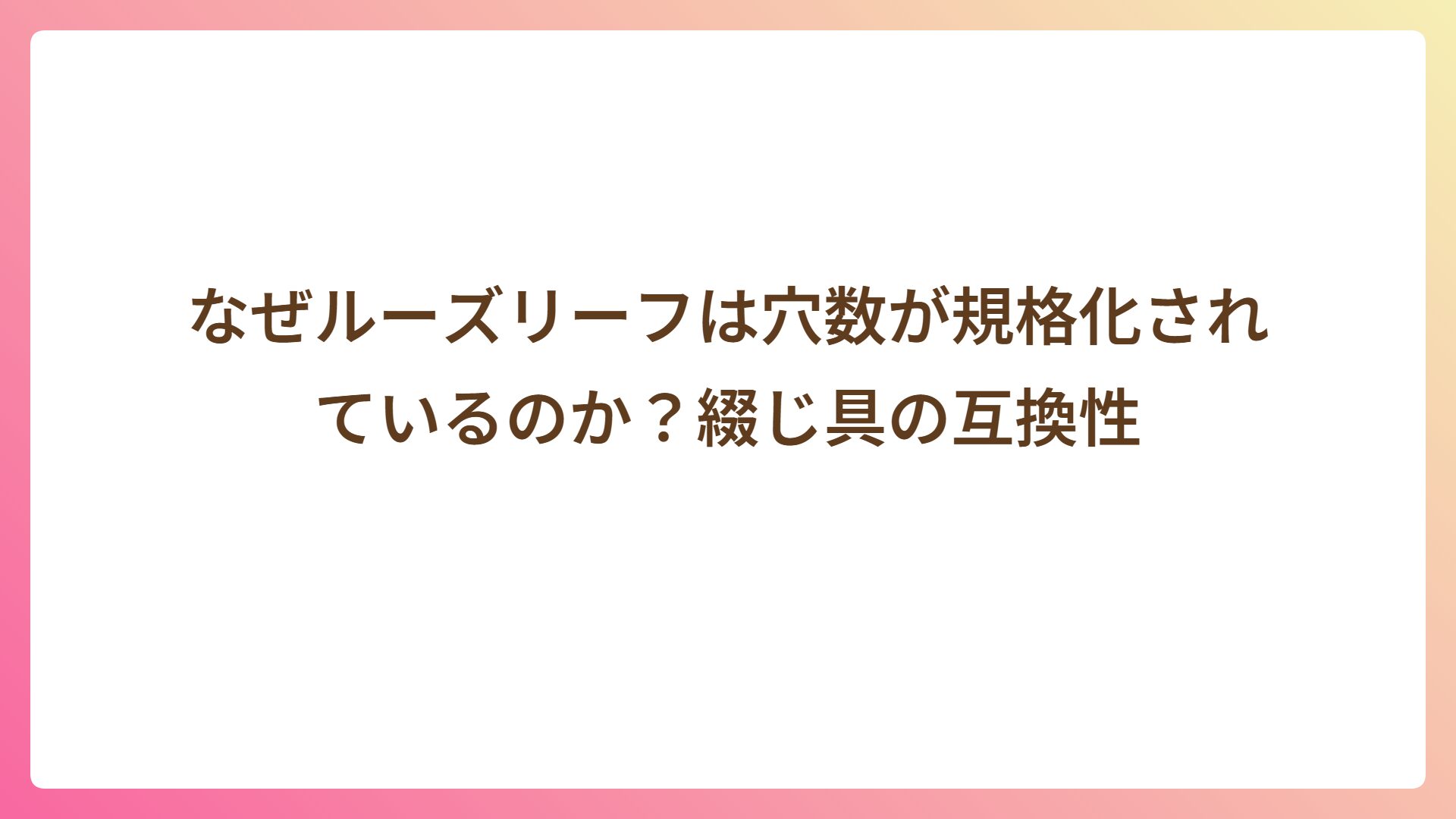なぜインターホンは“2線式”が根強いのか?既存配線と信頼性
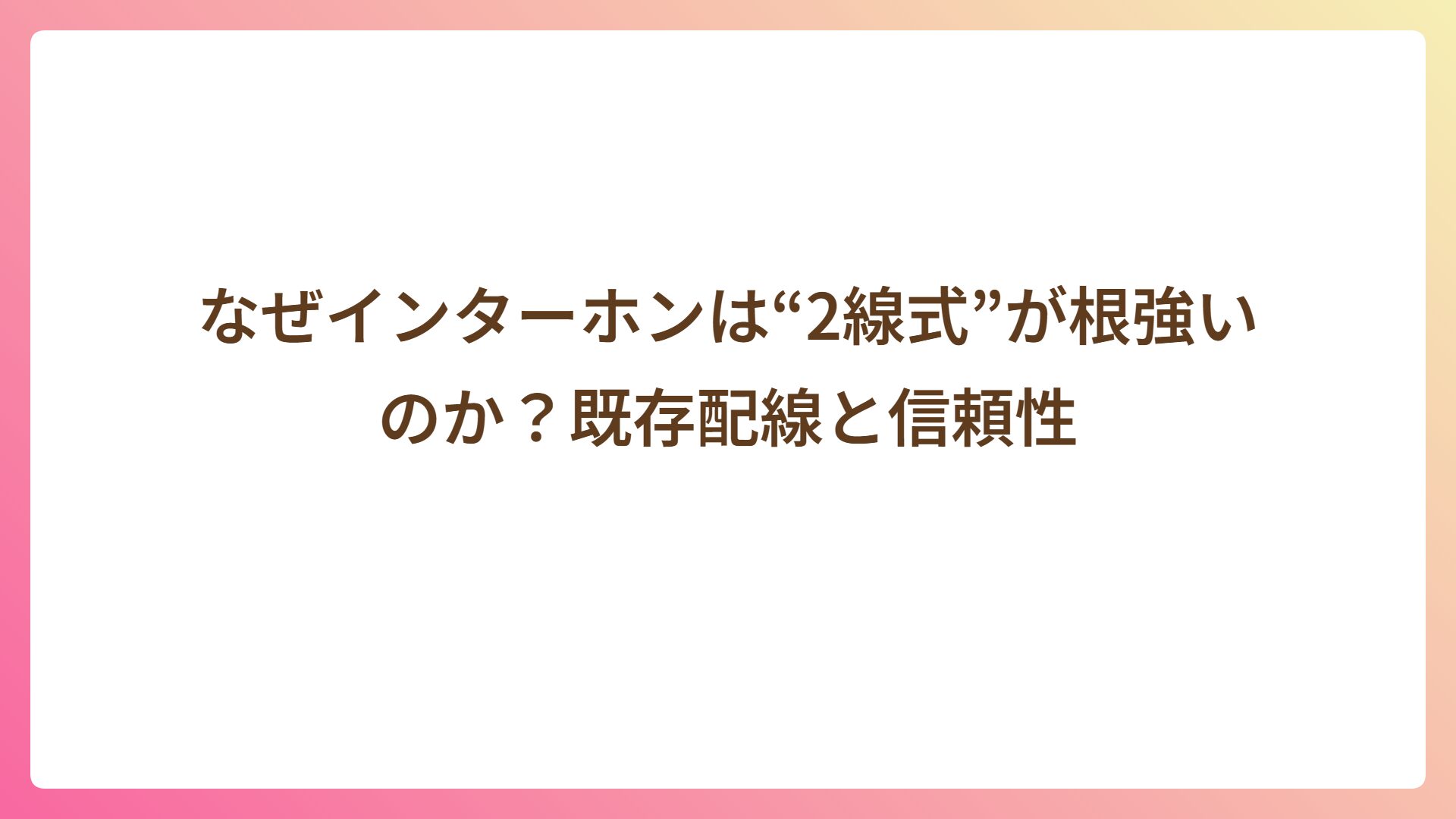
スマートドアホンや無線式の通信機器が普及している今でも、家庭用インターホンの多くは“2本のケーブル”だけで動作する「2線式」が主流です。
なぜ時代が進んでも、この古典的な仕組みが使われ続けているのでしょうか?
実はその背景には、既存配線との互換性・電源供給の安定性・施工の簡便さといった、実用上の強い理由があるのです。
2線式とは?最小限で“電力と信号”を送る仕組み
インターホンの2線式とは、わずか2本のケーブルで電源と通信信号を同時にやり取りする方式のことです。
電線のプラスとマイナスの間に微弱な電流を流し、押しボタン信号や映像データを重ねて伝送します。
このシンプルな構造により、配線の取り回しが容易で、断線のリスクも少ないというメリットがあります。
かつては音声のみの「呼び出しチャイム」から始まり、後に映像信号を重畳(じょうちょう)して送る仕組みが確立されました。
その発展形が、現在の2線式カメラインターホンです。
既存住宅との互換性を維持できる
日本の住宅では、1980年代以降に建てられた家の多くが2線式のチャイム配線を備えています。
そのため、リフォームや買い替え時に同じ2線配線をそのまま流用できることが大きな利点です。
配線を新しく引き直す必要がなく、壁の工事も最小限で済むため、導入コストと施工時間を大幅に削減できます。
メーカー各社が2線式を長く採用しているのは、こうした既存環境との互換性を維持するためでもあります。
電源供給が安定していてノイズに強い
2線式では、通信と電源が同じ経路を通るため、ノイズの影響を受けにくく安定した動作が可能です。
また、交流ではなく直流電流を使うため、長距離配線でも電圧降下が少なく、映像信号が乱れにくいという特性があります。
停電時にはバックアップ電源(親機側)で一定時間動作できる機種もあり、信頼性の高さが2線式の最大の強みといえます。
無線式が主流にならない理由
Wi-FiやBluetoothを使ったワイヤレスインターホンもありますが、電波干渉や接続切断のリスクが避けられません。
特に玄関と室内は距離や壁材の影響を受けやすく、映像遅延やノイズ混入が発生することもあります。
一方の2線式は物理的な有線通信のため、電波状況に左右されず常に安定した応答が保証されます。
加えて、無線式は親機と子機の両方に電源が必要ですが、2線式なら子機側に外部電源が不要。
玄関子機は親機から供給される微弱電流だけで動作するため、メンテナンスが非常に簡単です。
まとめ
インターホンがいまだに2線式を採用しているのは、既存配線の互換性・安定した電源供給・施工の簡便さ・通信の信頼性を兼ね備えているからです。
最新のスマート機能を取り入れつつも、このベース構造が変わらないのは、それが最も合理的な仕組みだから。
2本の細い線の中に、住宅設備としての信頼性と普遍的な設計思想が詰まっているのです。