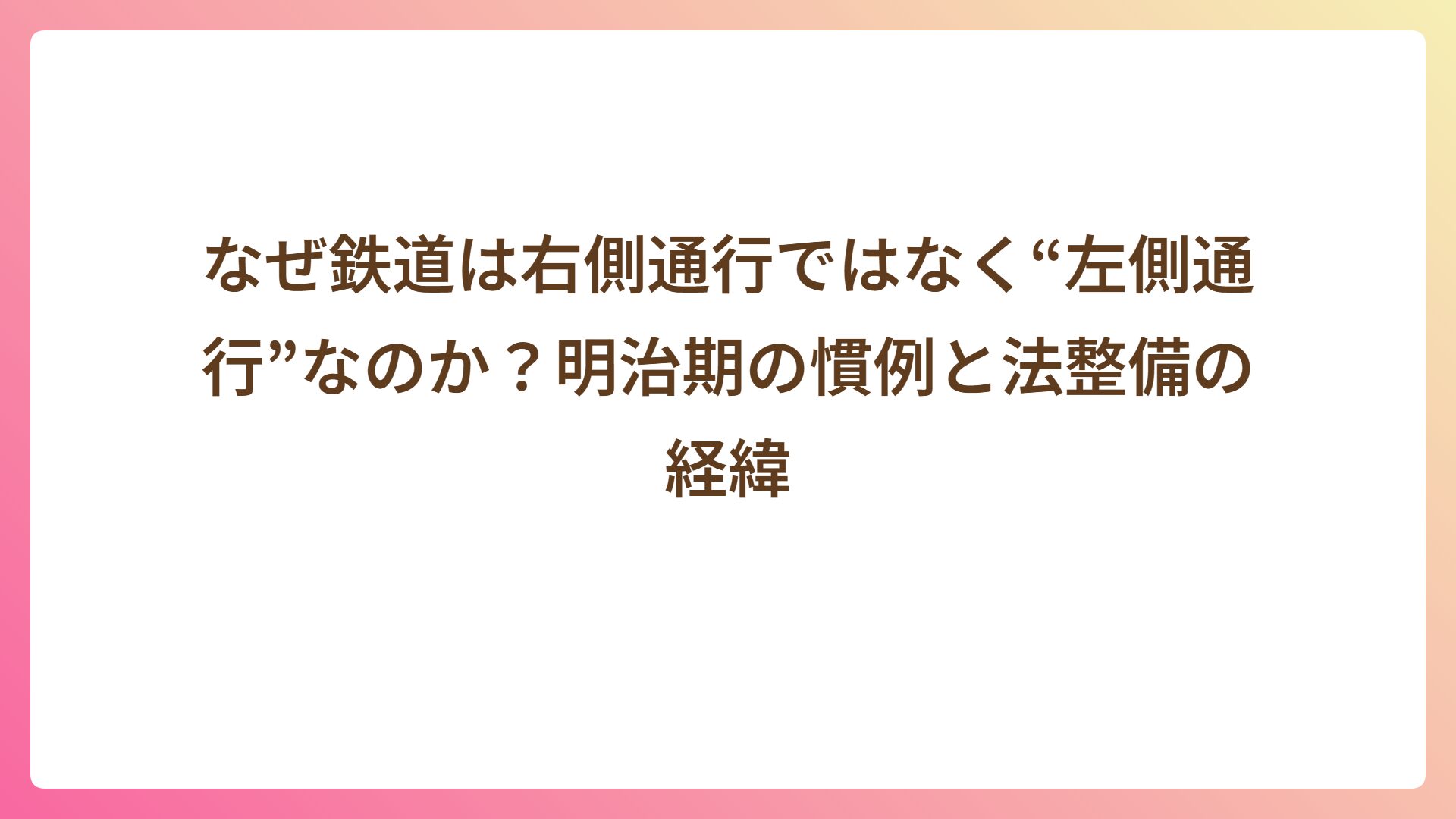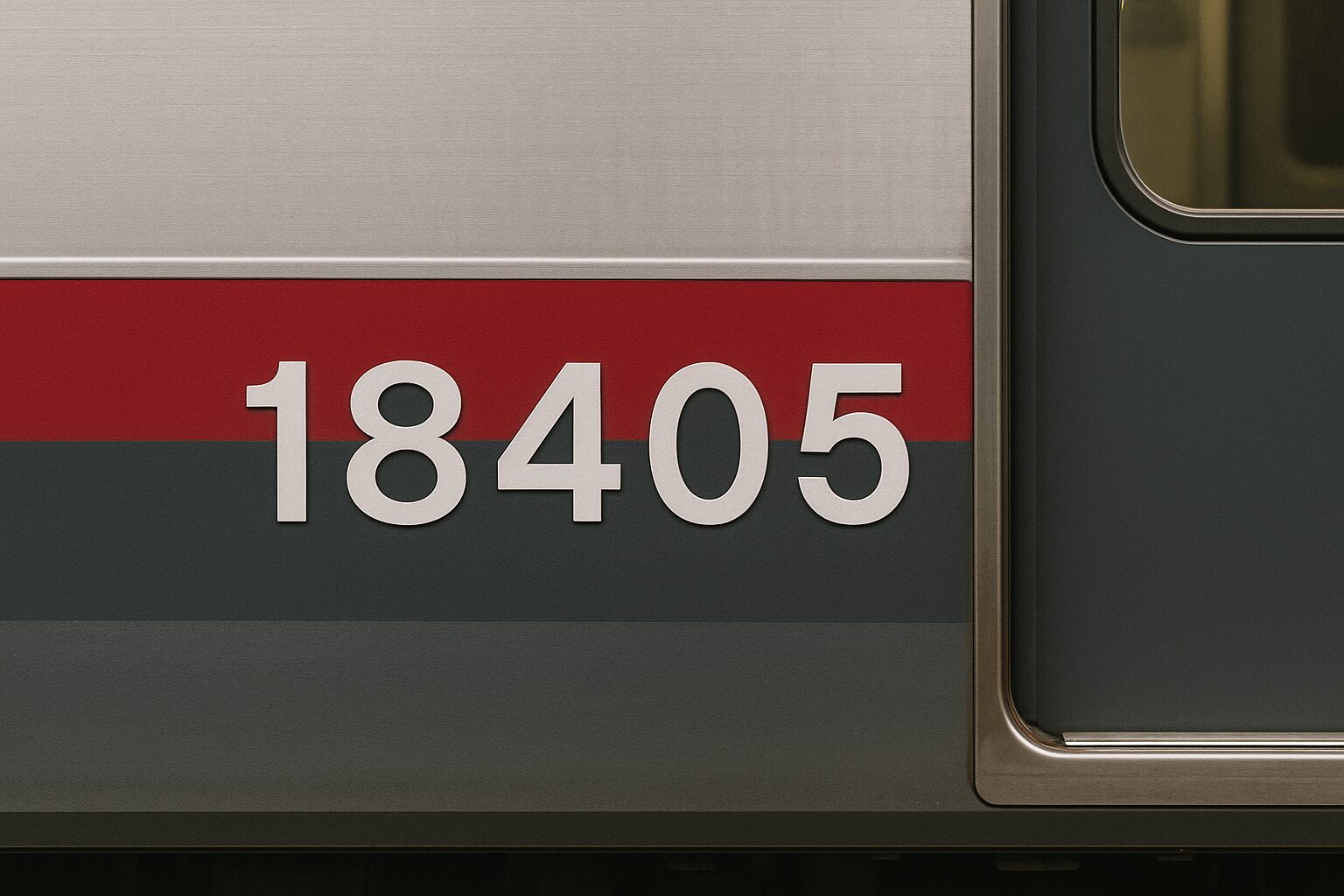なぜ柿の渋抜きに“焼酎”が使われるのか?タンニンとアルコール反応
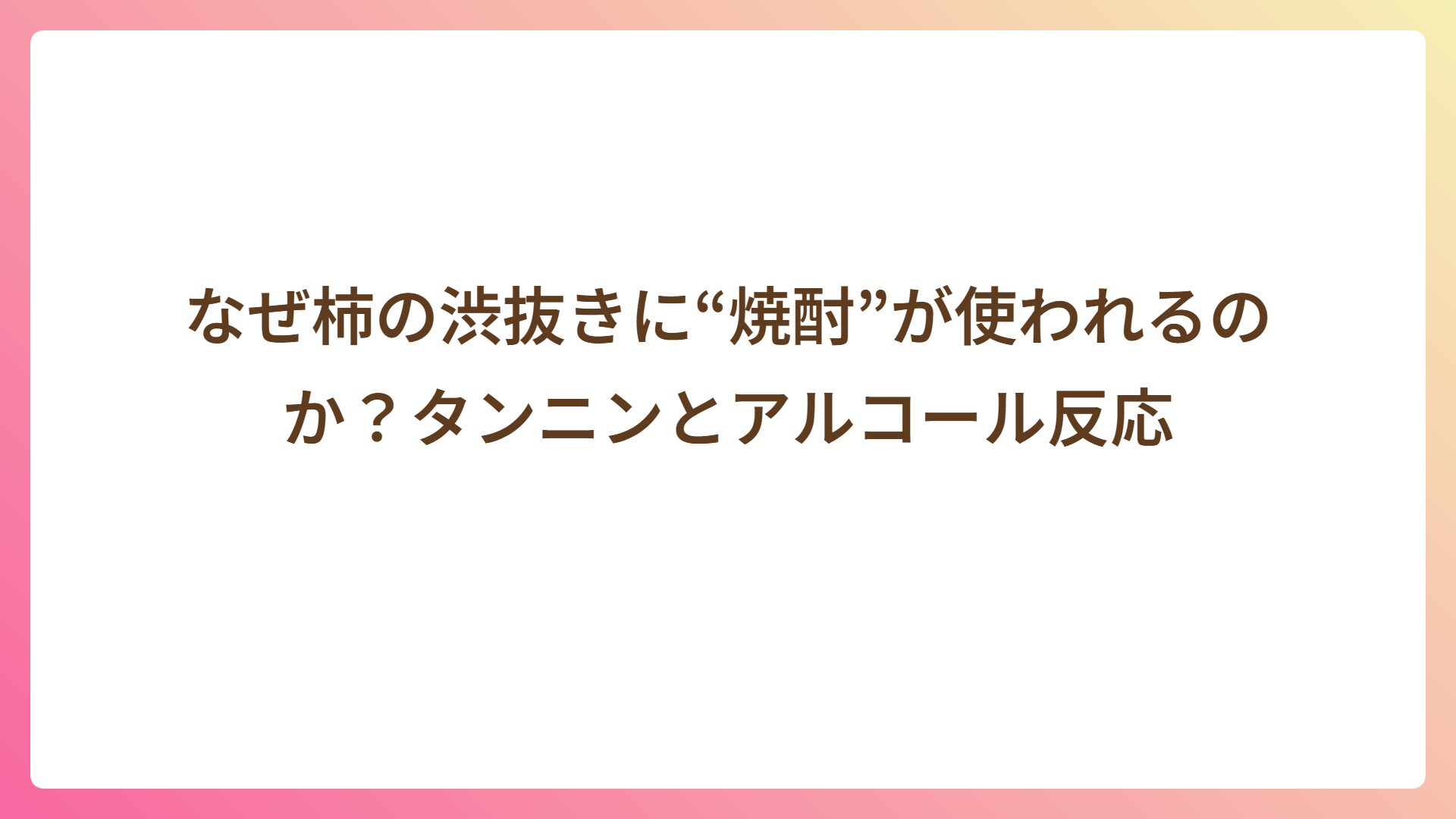
秋の味覚・柿。
そのままでは渋くて食べられない「渋柿」も、
焼酎で渋を抜くと、甘くてとろりとした味わいに変わります。
なぜ焼酎をかけるだけで、あの強烈な渋みが消えるのでしょうか?
その秘密は、タンニンという成分とアルコールの化学反応にあります。
渋みの正体は“可溶性タンニン”
渋柿の渋みを感じる原因は、果肉中に含まれる可溶性タンニン。
タンニンはポリフェノールの一種で、
唾液中のたんぱく質と結合して口の中を収縮させ、
あの「キュッとした渋さ」を生み出します。
甘柿との違いは、このタンニンの状態です。
- 甘柿:タンニンが細胞内で不溶化(固まっており、舌に触れない)
- 渋柿:タンニンが水に溶ける形(可溶性)で存在する
したがって、渋柿をおいしく食べるには、
タンニンを不溶化させて舌に感じさせないことが必要なのです。
焼酎が引き起こす“アルコール脱渋反応”
焼酎で渋を抜く方法は、アルコールによって果実内にエタノールガスを発生させる仕組みです。
果実に焼酎を吹きかけて密閉すると、
果皮からアルコールが内部に浸透します。
そのアルコールが果実の呼吸代謝によりアセトアルデヒド(酢酸アルデヒド)に変化。
このアセトアルデヒドがタンニンと結合し、
「可溶性タンニン → 不溶性タンニン」へと変化させます。
つまり、渋み成分は果実の中に残ったままですが、
化学的に舌に感じない形に“固定化”されているのです。
密閉するのは“ガス効果”を高めるため
渋抜きの際にビニール袋や密閉容器を使うのは、
アルコールが揮発して果実全体に行き渡るようにするためです。
アルコールの蒸気が柿の全体を包み、
果実内部でアセトアルデヒドが均等に発生することで、
ムラのない脱渋が実現します。
この「アルコール密閉法」は、
短期間(2〜3日)で安定した甘さを得られるうえ、
果肉の風味や色を損なわないという利点があります。
他の渋抜き法との違い
柿の渋抜きには、他にもいくつかの方法があります。
| 方法 | 原理 | 特徴 |
|---|---|---|
| 炭酸ガス法 | CO₂がアセトアルデヒド生成を促す | 業務用に多い |
| ドライアイス法 | ドライアイスのCO₂で密閉 | 均一で大量処理可能 |
| 干し柿法 | 乾燥で水分を飛ばし、タンニンを凝固 | 甘みが濃縮される |
| 焼酎法 | アルコールがアセトアルデヒド生成を誘発 | 家庭でも簡単・自然な甘味 |
焼酎法は特別な装置を使わず、
果実の呼吸とアルコールの揮発だけで脱渋が進む点が特徴です。
アルコール濃度は高いほど速い
一般的に使用される焼酎は35度前後のホワイトリカー。
濃度が高いほど気化しやすく、果実内への浸透も早いため、
より短時間で渋が抜けます。
ただし、40度を超えると表面が変色する場合もあるため、
35度前後が最適濃度とされています。
まとめ
柿の渋抜きに焼酎が使われるのは、
アルコールが果実内でアセトアルデヒドを発生させ、タンニンを不溶化するため。
この化学反応によって、
渋味を感じさせないまま甘味と風味を保つことができます。
焼酎は単なる“風味づけ”ではなく、
自然の化学を活かした最も効率的な渋抜き触媒なのです。