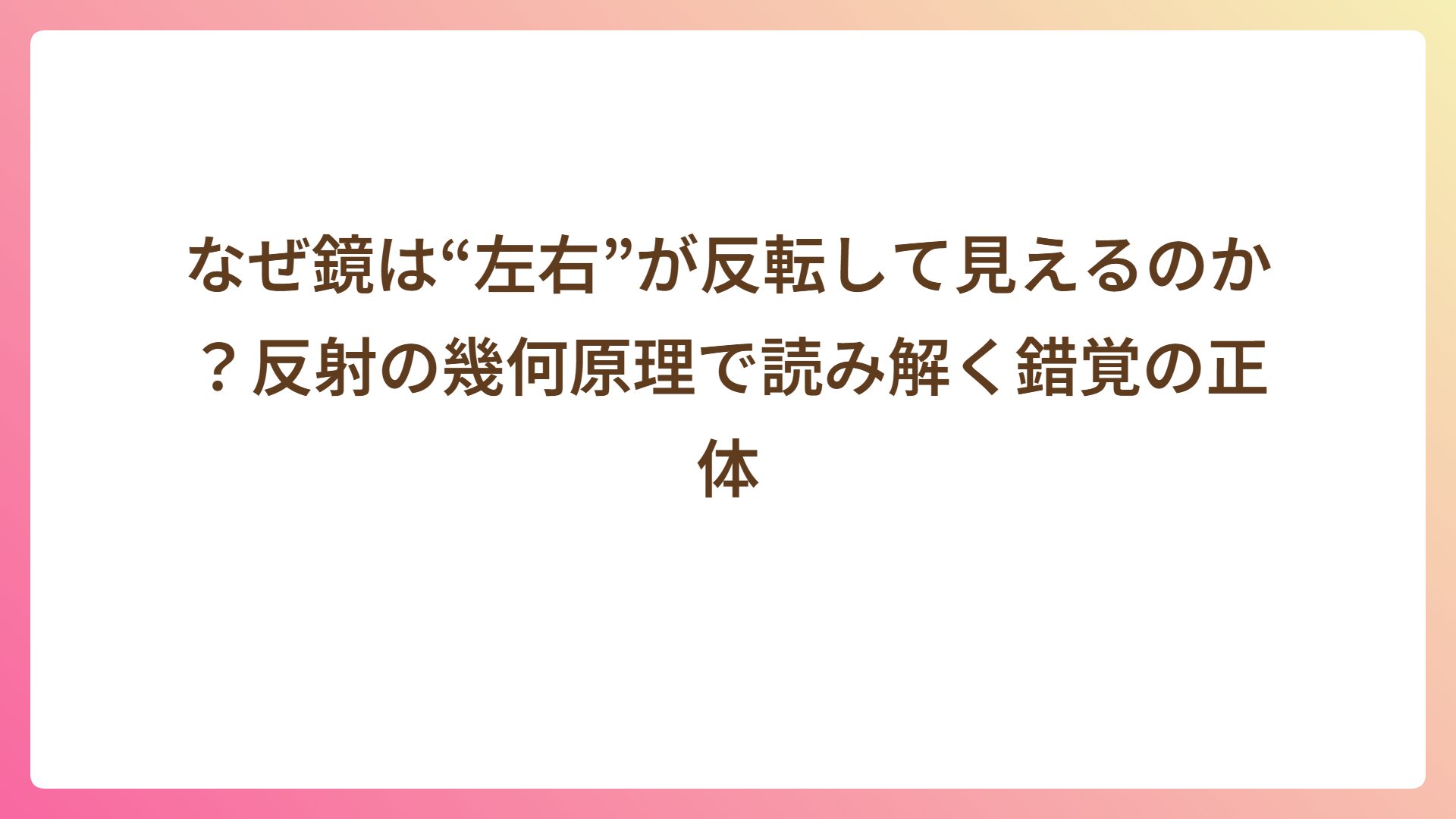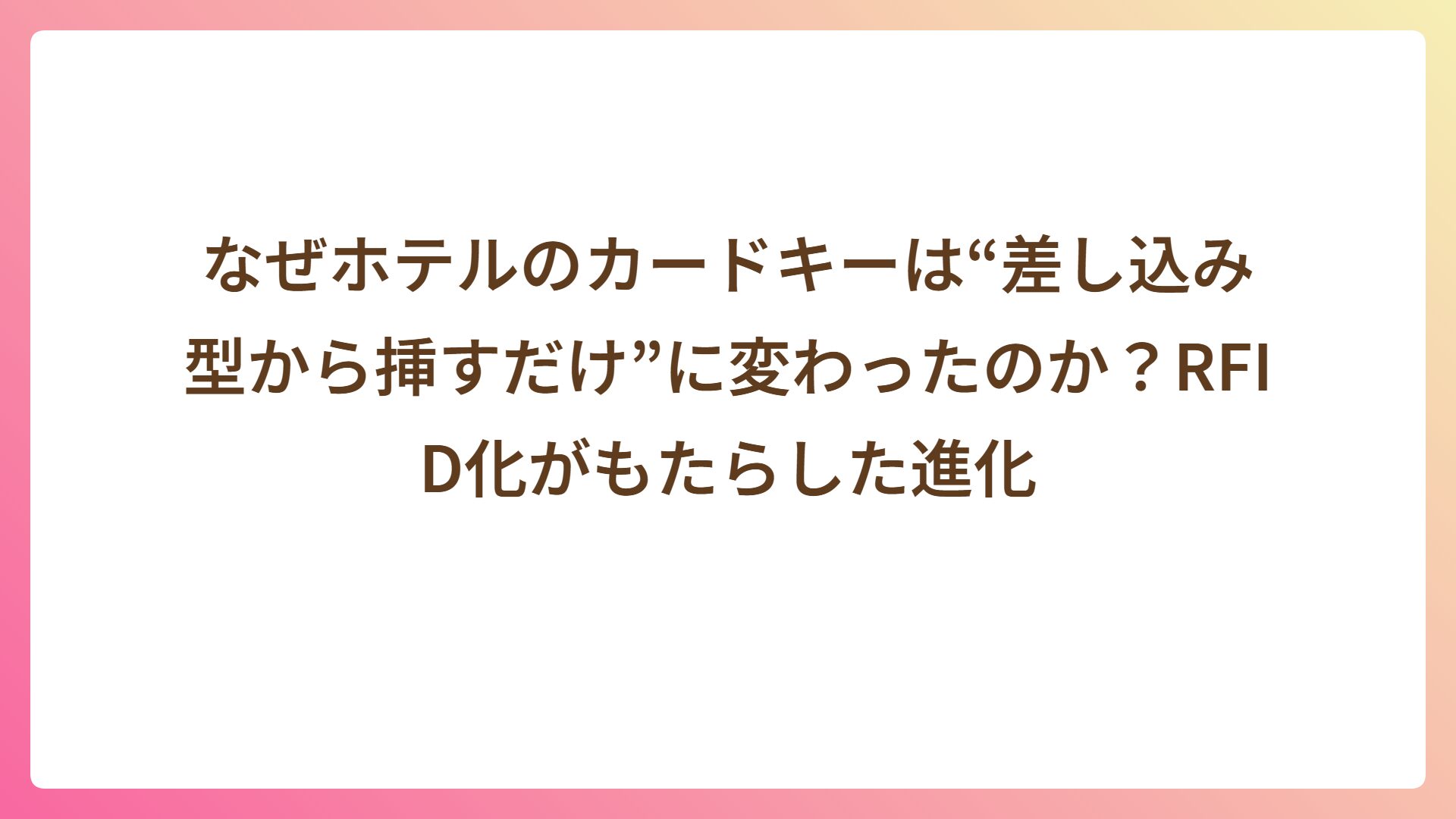「かまとと」という言葉の由来とは?江戸の遊郭で生まれた“うぶなふり”の隠語
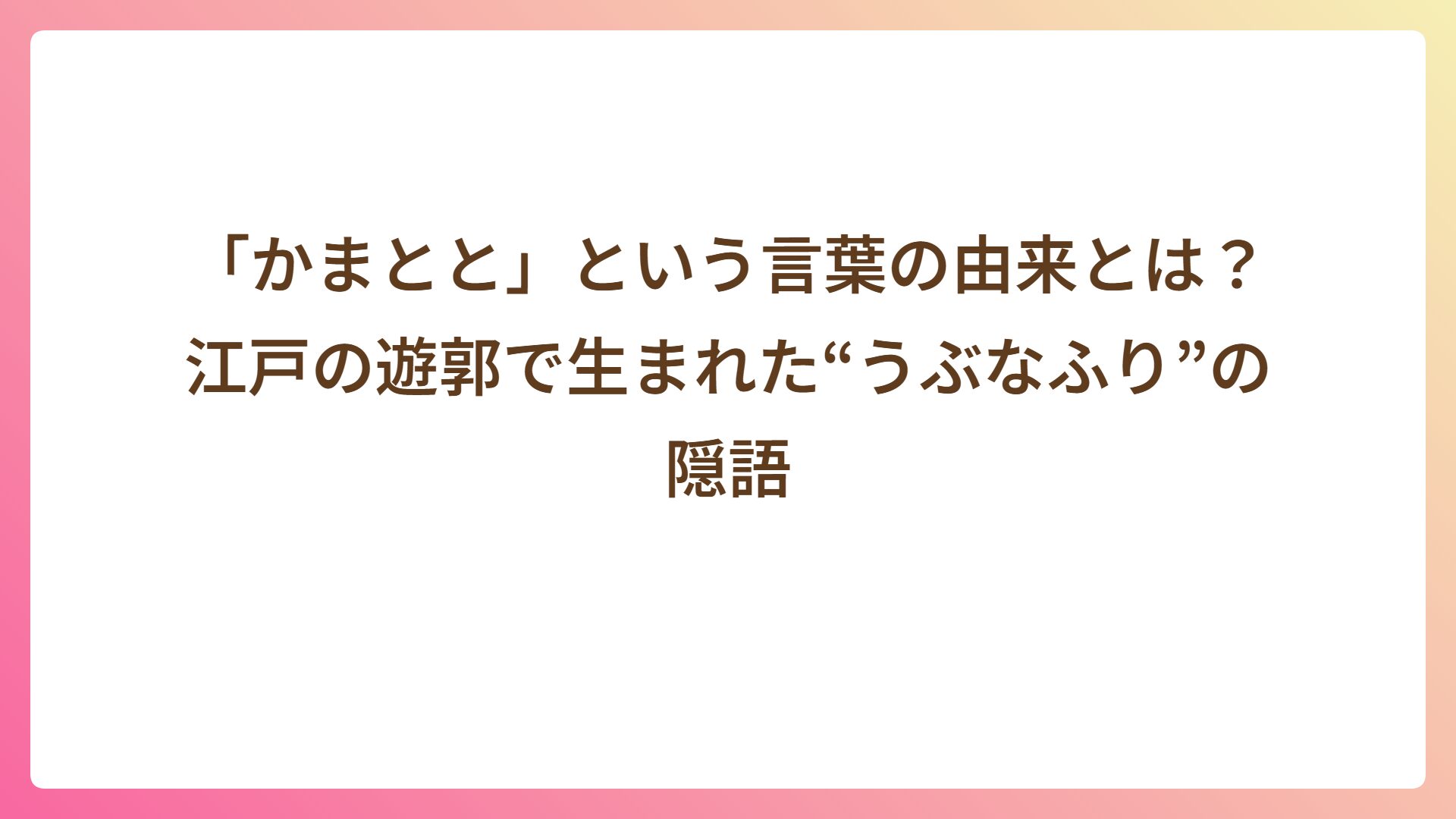
「そんなの知らな〜い、やだぁ♡」と、わざと知らないふりをする――そんな人を「かまととしい」と表現しますよね。
けれどこの「かまとと」、なぜそんな変わった言葉になったのでしょうか?実はその語源は、江戸時代の遊郭文化にまでさかのぼります。
「かまとと」は「蒲鉾(かまぼこ)」から生まれた
「かまとと」はもともと、「かまぼこの魚は何?」というセリフが由来だといわれています。
江戸時代、遊女がお客に「かまぼこって何の魚から作るの?」と、わざと知らないふりをして聞いた――
この芝居じみた“うぶな態度”をからかって、「かまぼこの魚=かまとと」と呼ぶようになったのが始まりです。
つまり、「かまととしい」とは知っているのに知らないふりをする、世間知らずを装うという意味の隠語だったのです。
「とと」は当時の言葉で“魚”のこと
この「とと」という言葉も、現代ではあまり使われませんが、当時は子どもや女性が使う魚の呼び方でした。
「おとと」「とと様」など、優しい響きを持つ語感から、女性的で柔らかい印象があります。
そのため、「かまぼこのとと=かまとと」という言葉自体が、あえて幼い・うぶな雰囲気を出す言葉遊びとしても機能していたのです。
江戸の遊郭文化が生んだ言葉
江戸時代の遊郭では、遊女が「清楚さ」「うぶさ」を演じることも一種の接客術でした。
お客に「こんなの初めて」と言ってみせることで、男性の優越感をくすぐる演出だったのです。
そうした芝居めいた“作られた純情”を皮肉って、「あの子はかまととだね」と言われるようになりました。
つまり「かまとと」は、本当の無知ではなく、演技としての無邪気さを指す言葉だったのです。
現代では“あざとさ”のニュアンスに変化
現代では「かまととしい」という言葉は、ややあざとい・計算高いというニュアンスで使われることが多くなりました。
かつての“うぶなふり”が時代を経て“わざとらしい”へと転じたわけです。
それでも、語源をたどれば、そこには言葉遊びと人間心理のかけひきが隠れているのです。
まとめ:「かまとと」は江戸の知恵が生んだ皮肉な言葉
「かまとと」という言葉は、「かまぼこの魚は何?」という一言から生まれた江戸時代の隠語でした。
うぶを装う女性のしたたかさと、それを見抜く男たちの皮肉――
そのやり取りの中から生まれた言葉が、今もなお「かまととしい」として生き続けています。