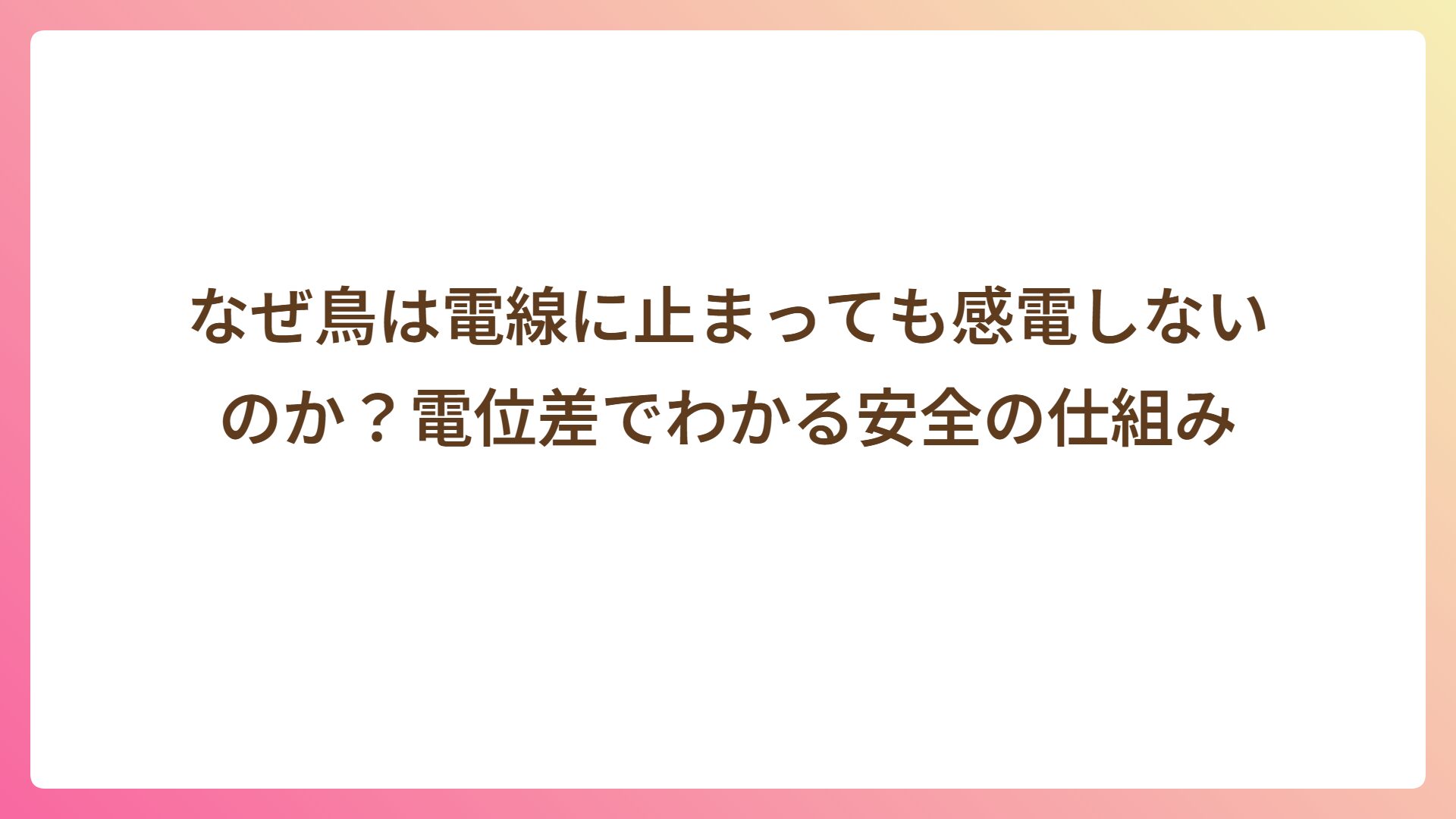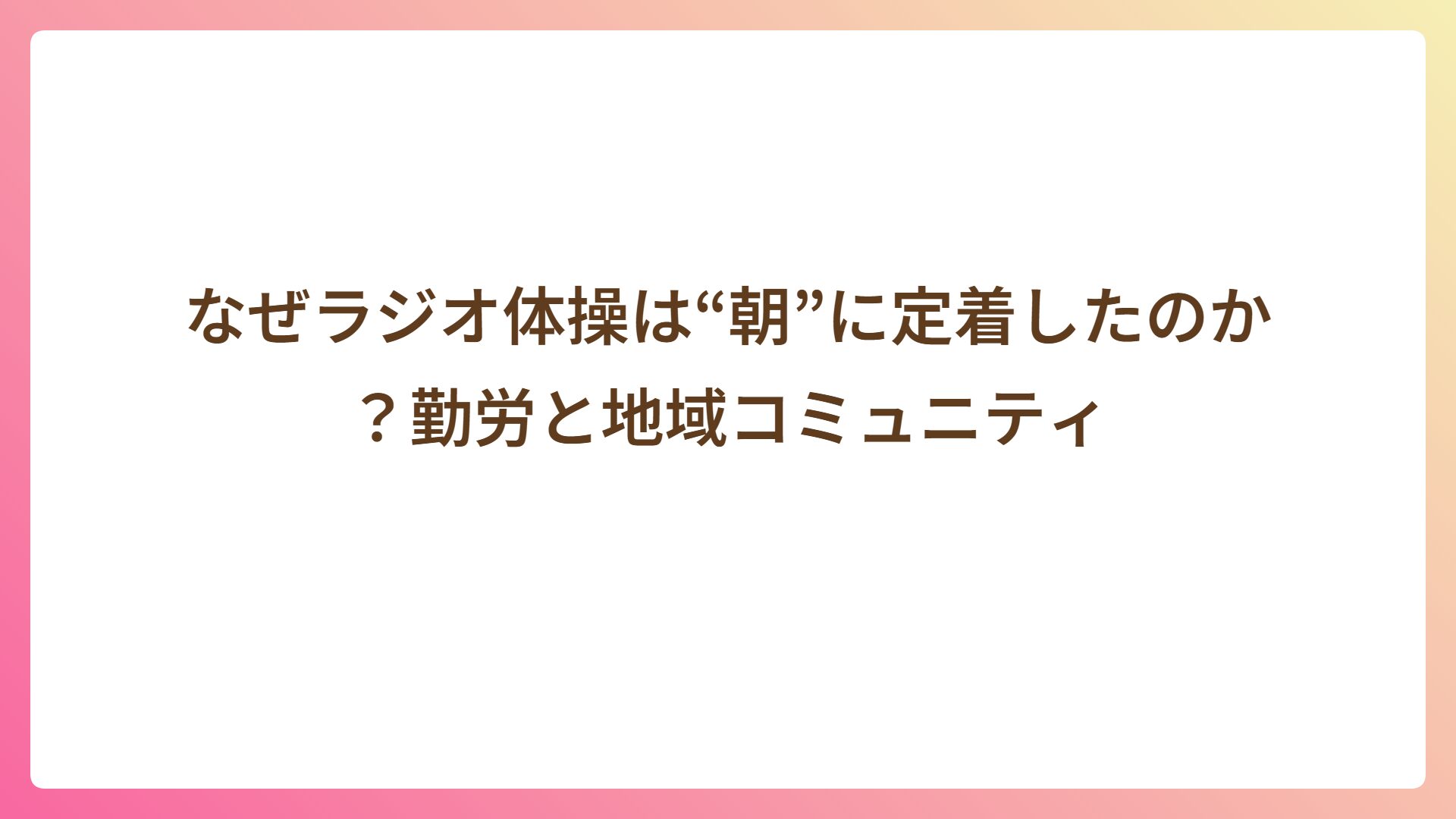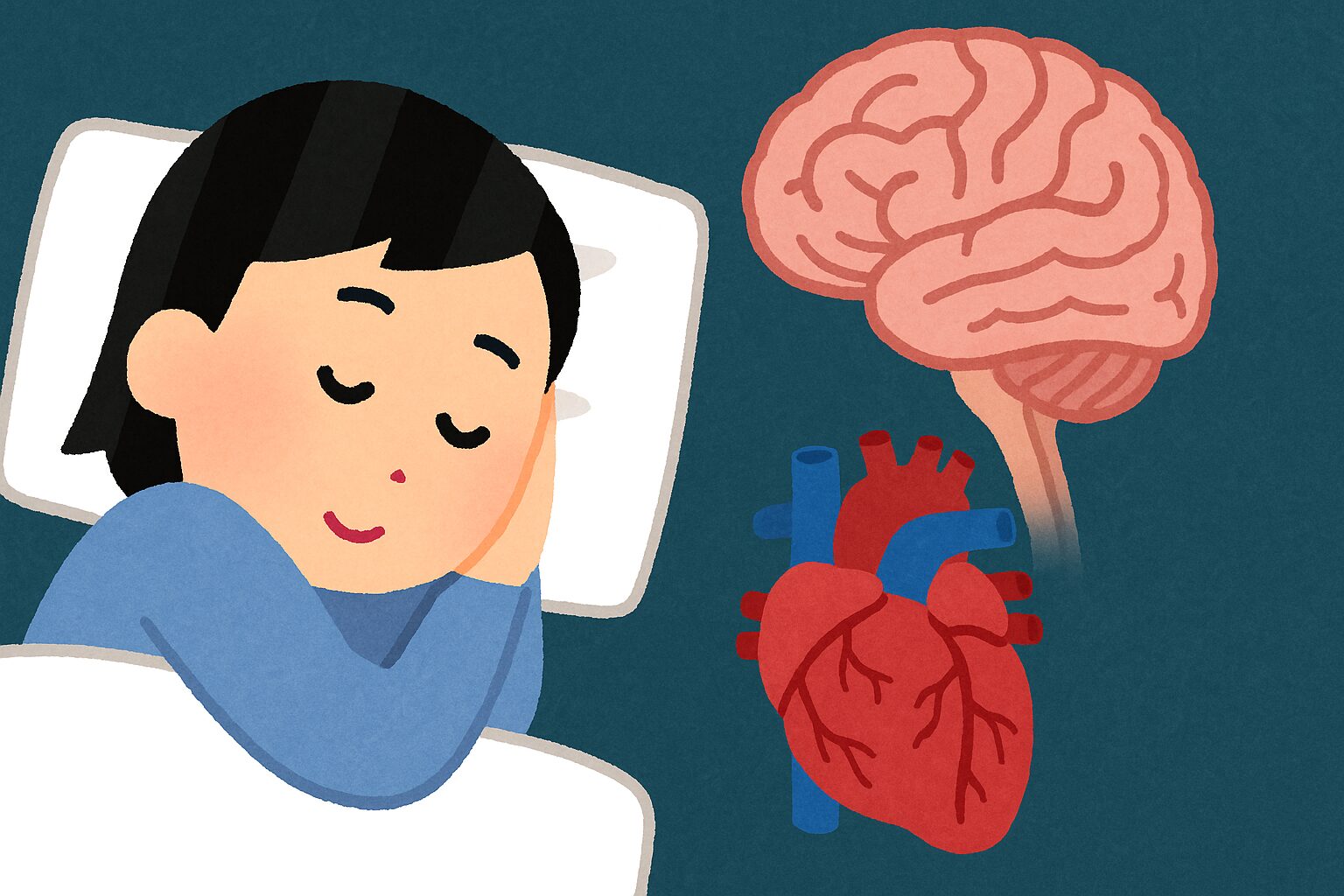カニカマは“人工クラゲ”の副産物だった?偶然生まれた海のヒット食品の裏側
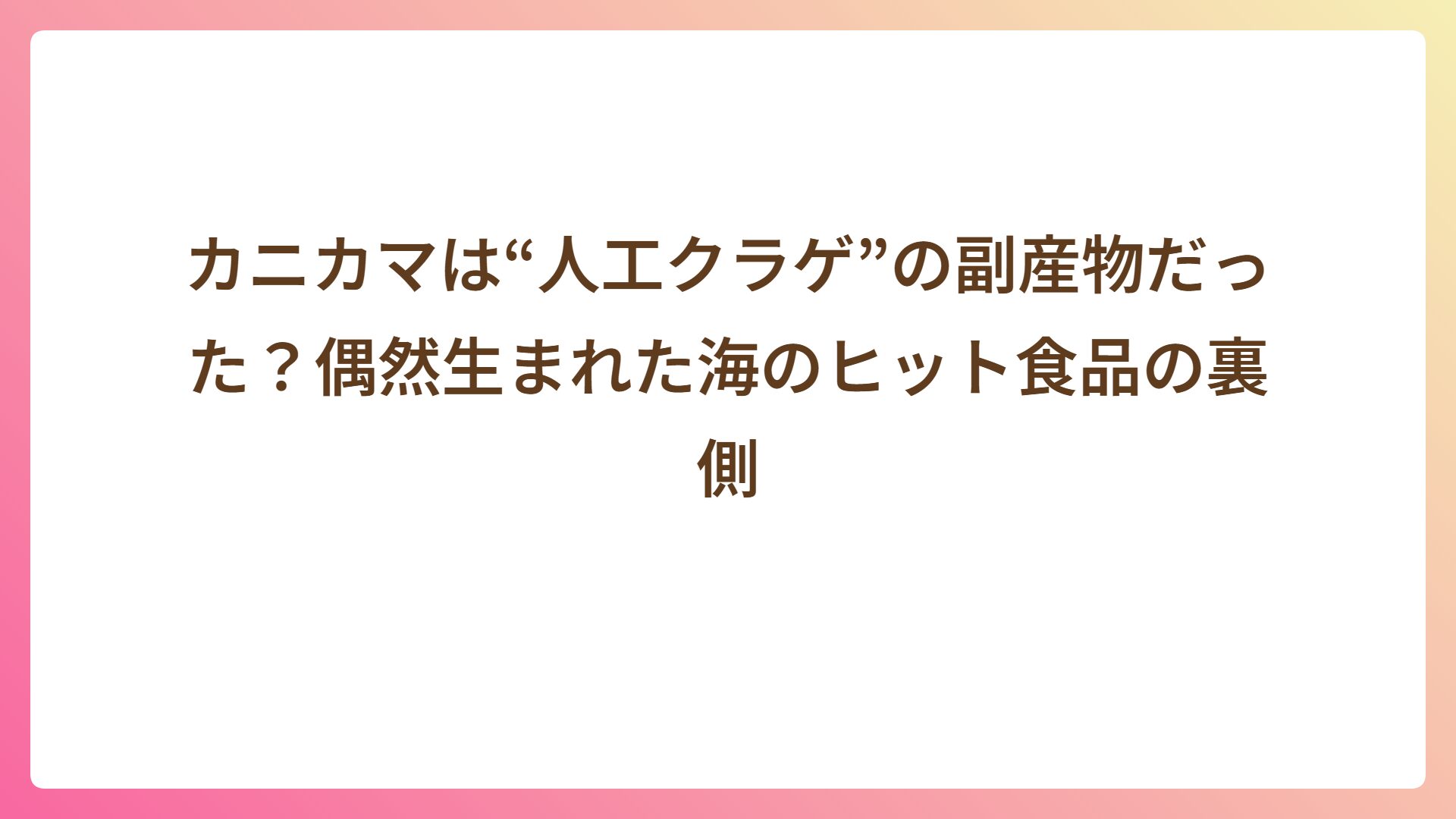
お弁当やサラダでおなじみの「カニカマ」。今でこそ“カニ風味かまぼこ”として定着していますが、実はその誕生の原点はカニではなくクラゲだったことをご存じでしょうか?
カニカマの開発は、当初まったく別の目的から始まった、まさに“偶然の発明”だったのです。
もともとは「人工クラゲ」を作ろうとしていた
1970年代初頭、魚のすり身(スケトウダラなど)を加工する食品メーカー各社は、新しい海産物代替品の開発を模索していました。
その中で登場したのが、「クラゲのような食感を人工的に再現できないか」という研究テーマ。
当時は中華料理ブームでクラゲの冷菜が人気を集めており、安く・大量に・安定して供給できる人工クラゲの開発が進められていたのです。
しかし、試作を重ねるうちに得られたのは、クラゲというよりも繊維質でほぐれる“肉っぽい”食感。
この予想外の結果が、後のカニカマ誕生につながる転機となりました。
失敗から生まれた「カニの身っぽさ」
人工クラゲとしては失敗作だったその試作品を、ある開発者が試食したところ、
「これはカニの身に似ているのでは?」と気づいたのです。
そこで、赤い着色料で色をつけ、細く裂くように加工した結果、まるでカニのほぐし身のような見た目に。
こうして生まれたのが、1972年に石川県のスギヨが発売した「かに風味かまぼこ」=カニカマです。
偶然の食感と発想の転換が、新しいカテゴリーの食品を生み出した瞬間でした。
ヘルシーで安価、そして世界へ
本物のカニは高価で、収穫量にも限りがありますが、カニカマは魚のすり身から作るため低コストで安定供給が可能。
さらに低脂肪・高たんぱくでヘルシーな点も評価され、瞬く間に人気商品となりました。
1970年代後半には欧米にも輸出され、現在では「SURIMI(すり身)」という言葉自体が世界共通語になっています。
まとめ:カニカマは“失敗”から生まれた成功作
カニカマの原点は、意外にも「人工クラゲ」の研究。
クラゲのようなぷるぷる食感を目指していた実験から、偶然にも“カニそっくり”の味と見た目が生まれたのです。
発想の転換と偶然が重なって誕生したカニカマは、いまや世界中で愛される日本発のヒット食品となりました。