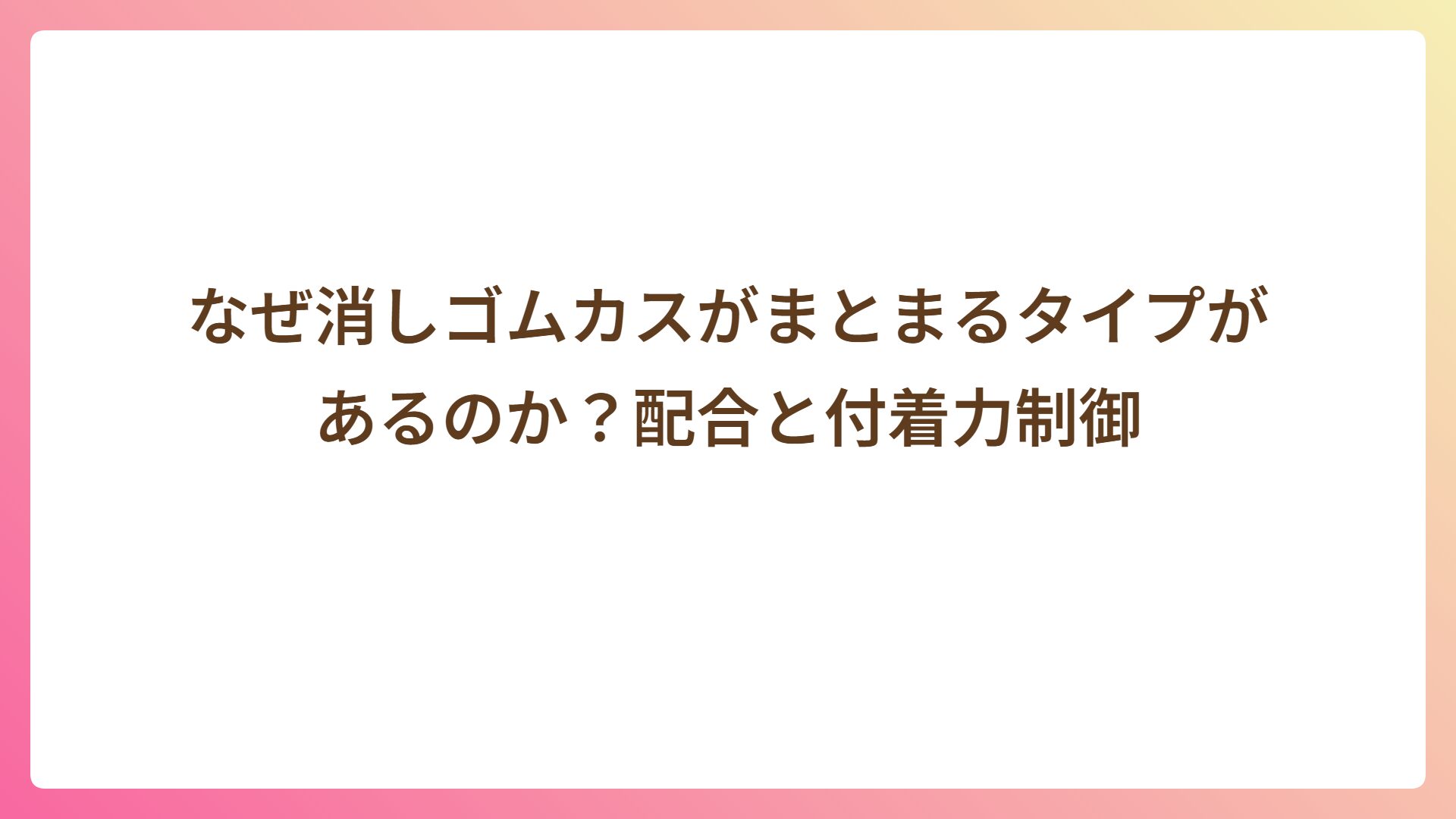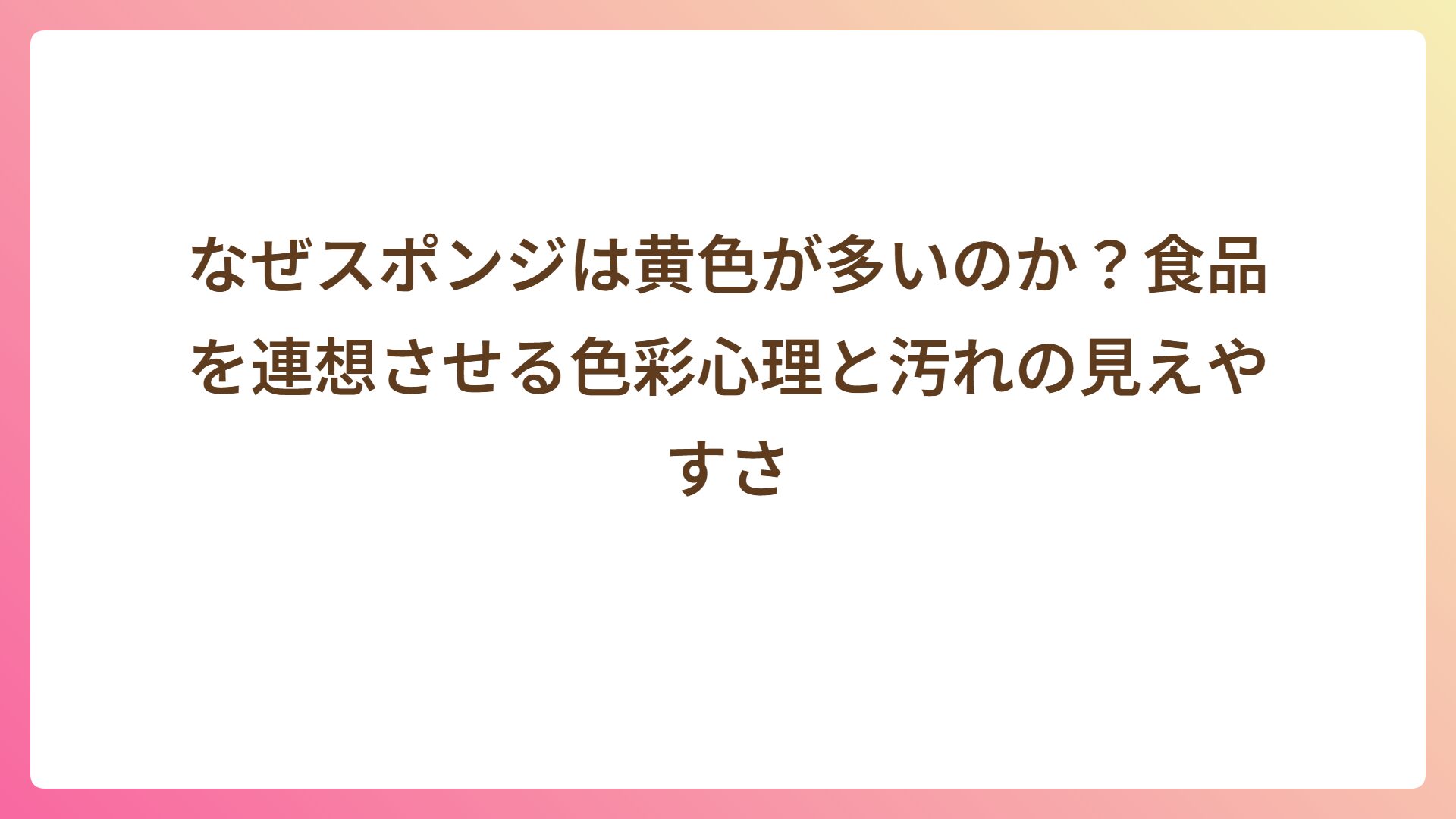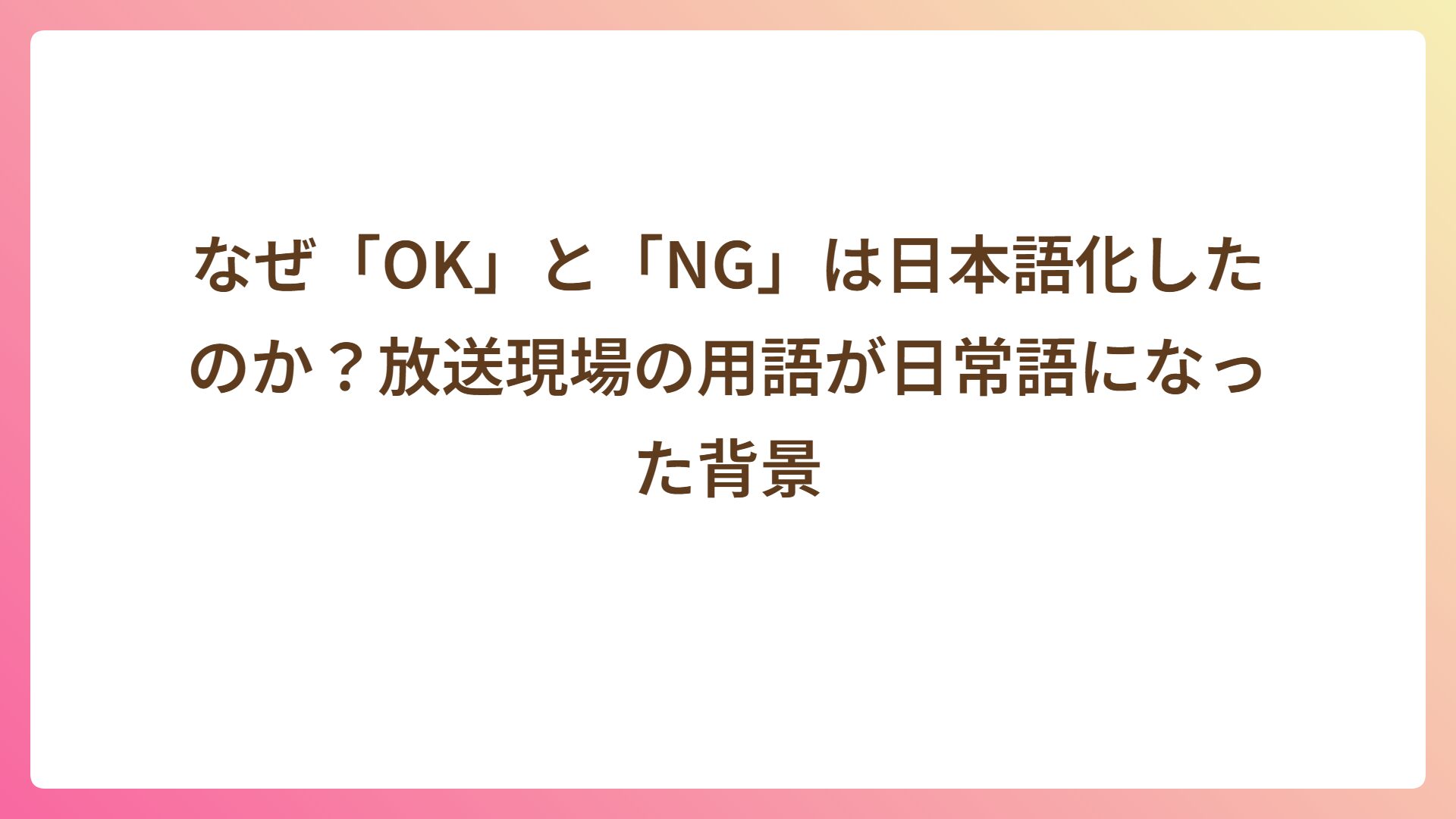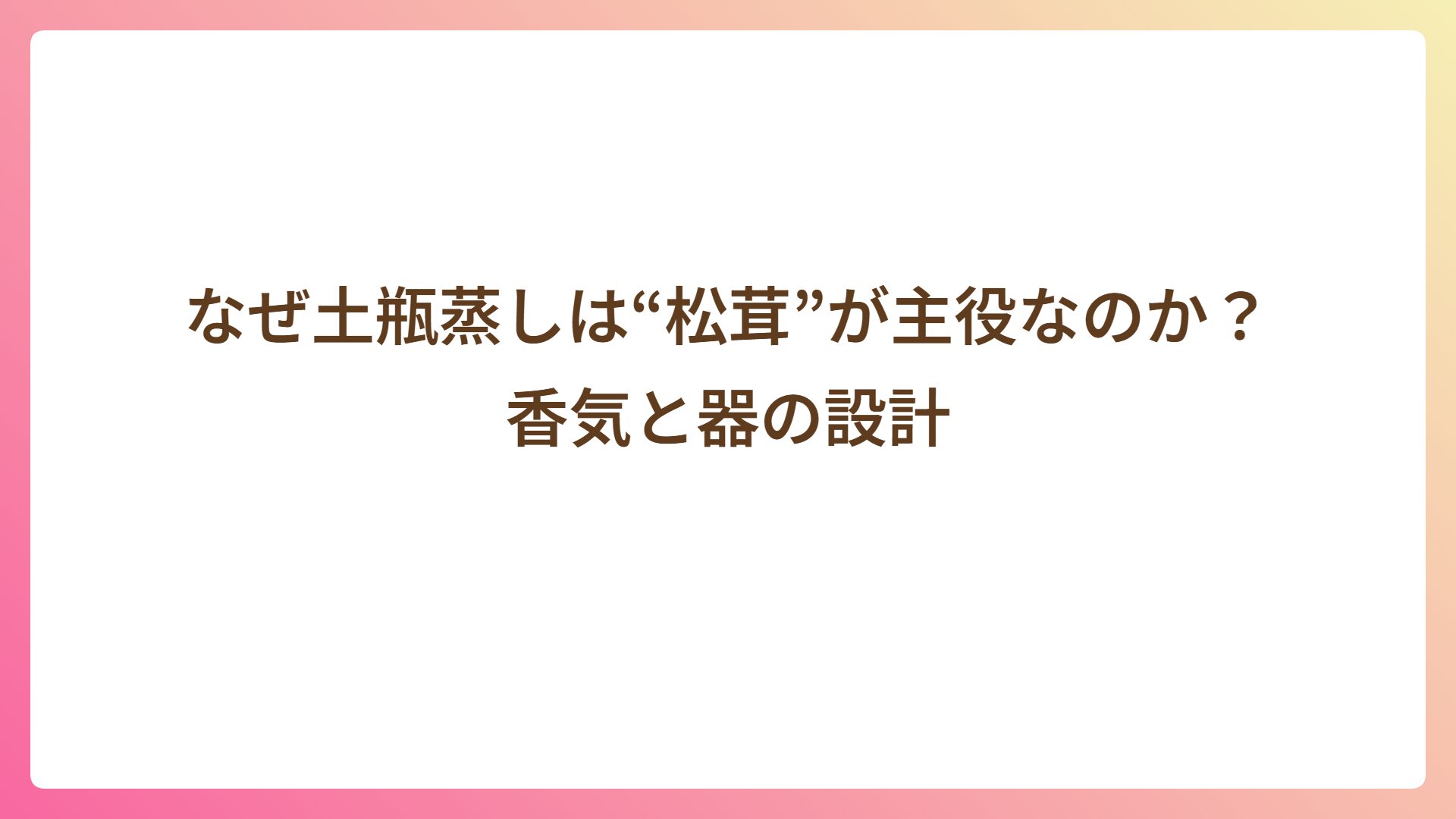なぜ観光案内図は“北が上”でない場合があるのか?現地一致の方位設計
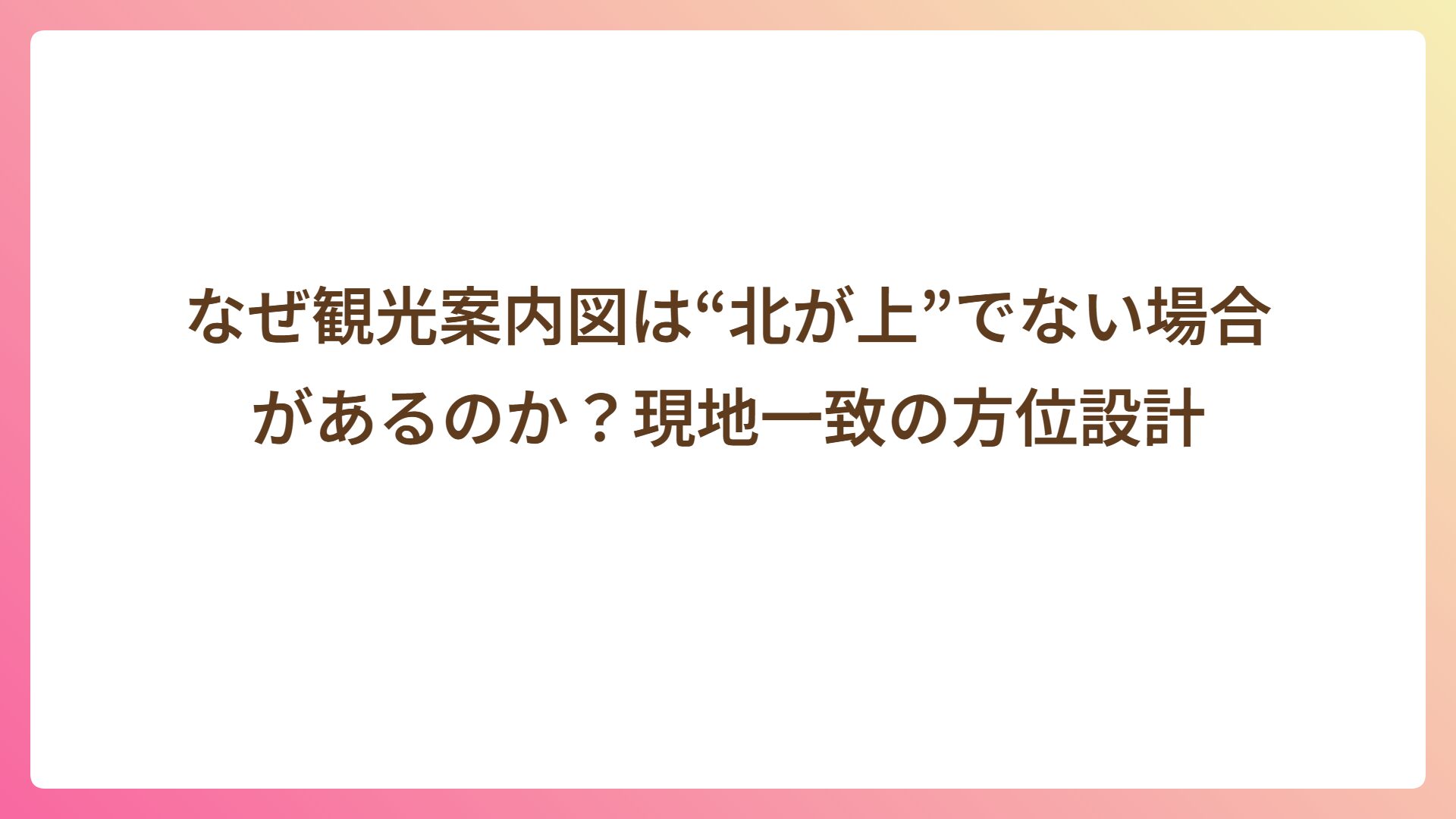
観光地で見かける案内図をよく見ると、一般的な地図と違って北が上になっていないことがあります。
「地図なのに上下が逆?」と不思議に思った経験がある人も多いでしょう。
しかしそれは誤りではなく、現地での方向感覚を重視した“現地一致設計”によるものなのです。
地図の基本は「北が上」
通常の地図やカーナビでは、北を上にする「北上図法」が基本です。
これは、磁北や真北を基準にして世界共通で方位を統一できるため、
地理的な位置関係を把握しやすいというメリットがあります。
しかし、観光地の案内板は「世界全体」ではなく、その場での直感的なわかりやすさを最優先に設計されています。
つまり、地理的正確さよりも「見た人がどちらへ進めばいいかわかるか」を重視しているのです。
現地一致方式とは?
観光案内図の多くは、「現地一致(ヘッドアップ)方式」と呼ばれる向きで描かれています。
これは、地図の上方向が実際に自分が向いている方向になるように設置する方式です。
たとえば、南向きの道路に案内板を立てる場合、
北を上にすると地図が“自分の見ている風景と逆向き”になってしまいます。
そこで、地図を180度回転させて現地の視界と一致させることで、
「この先が左」「川は右手」といった情報を直感的に把握できるようにしているのです。
方向感覚を失いやすい観光客への配慮
初めて訪れた観光地では、地元の人と違って方角の感覚がつかみにくいものです。
特に複雑な路地や階段が多い街並みでは、「北がどちらか」を考えるより、
今自分が見ている方向と地図の向きを一致させた方が圧倒的に理解しやすいのです。
このため、観光案内図やテーマパークマップ、登山口の案内板などでは、
「北が上でない地図」があえて採用されています。
案内図に小さく「方位マーク」がある理由
北が上でない地図の場合でも、必ずどこかに「北→」マークが記されています。
これは、現地一致で描かれていることを示すための印であり、
方向感覚を補うための“最低限の共通情報”として欠かせません。
また、地図の端には「現在地」や「進行方向→」などの表示を加えることで、
見る人が自分の位置と向きを即座に把握できるように工夫されています。
公共デザインとしての安全性
現地一致方式の地図は、観光客だけでなく高齢者や子どもにも理解しやすいというメリットがあります。
とくに避難経路や災害時の案内図では、
「右に曲がると避難所がある」といった視覚的な動線把握が重要なため、
北上図よりも現地一致方式が有効とされています。
国土交通省の「案内サイン指針」でも、公共空間における案内図は
“利用者の視点に合わせて現地一致を優先する”ことが推奨されています。
まとめ
観光案内図が北を上にしていないのは、現地での見え方を優先した「現地一致設計」だからです。
見た人が迷わず動けるように、地図の向きを現場の風景とそろえる——
それは、正確さよりも「わかりやすさ」を重視する、人間中心のデザイン思想なのです。