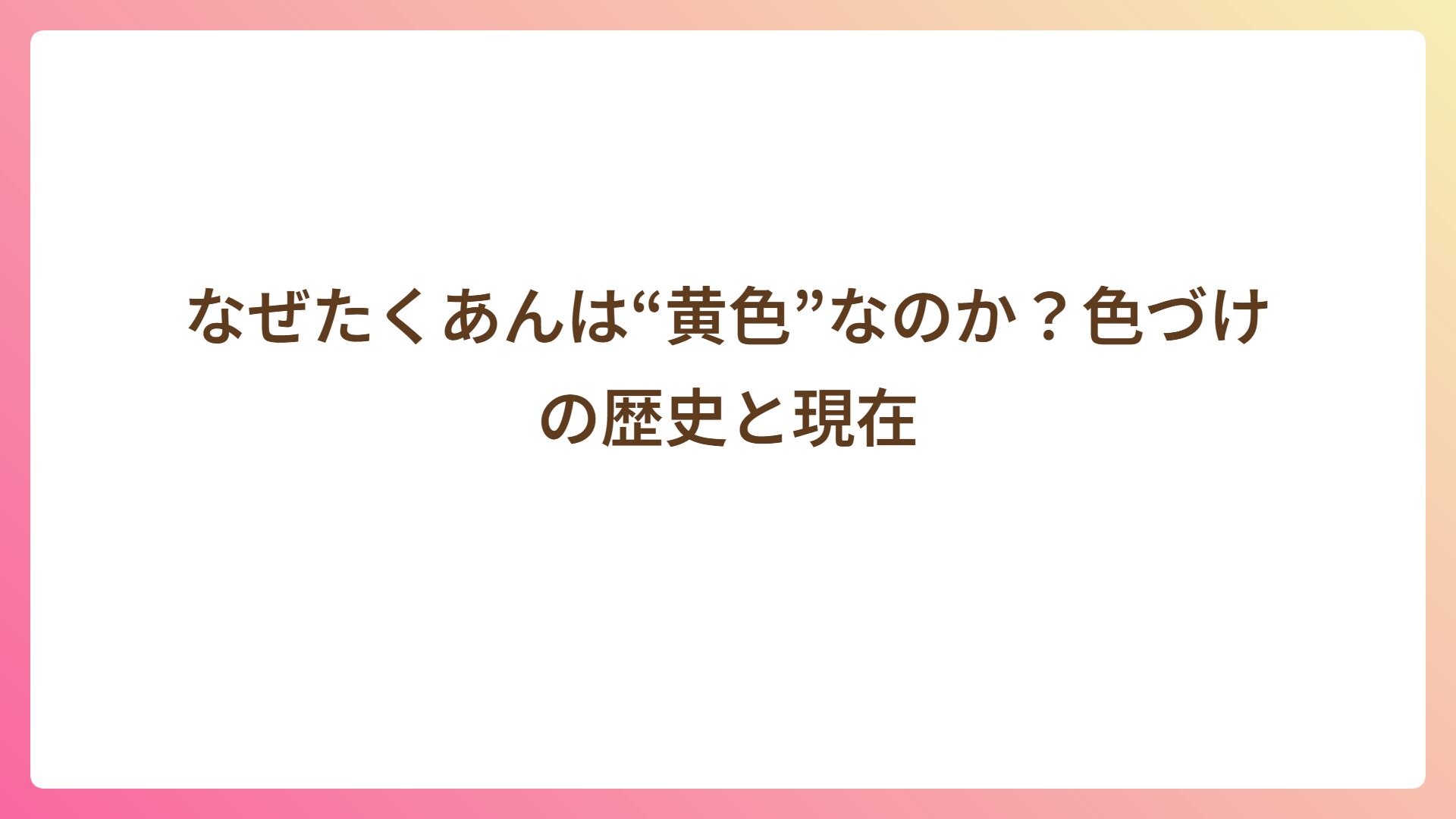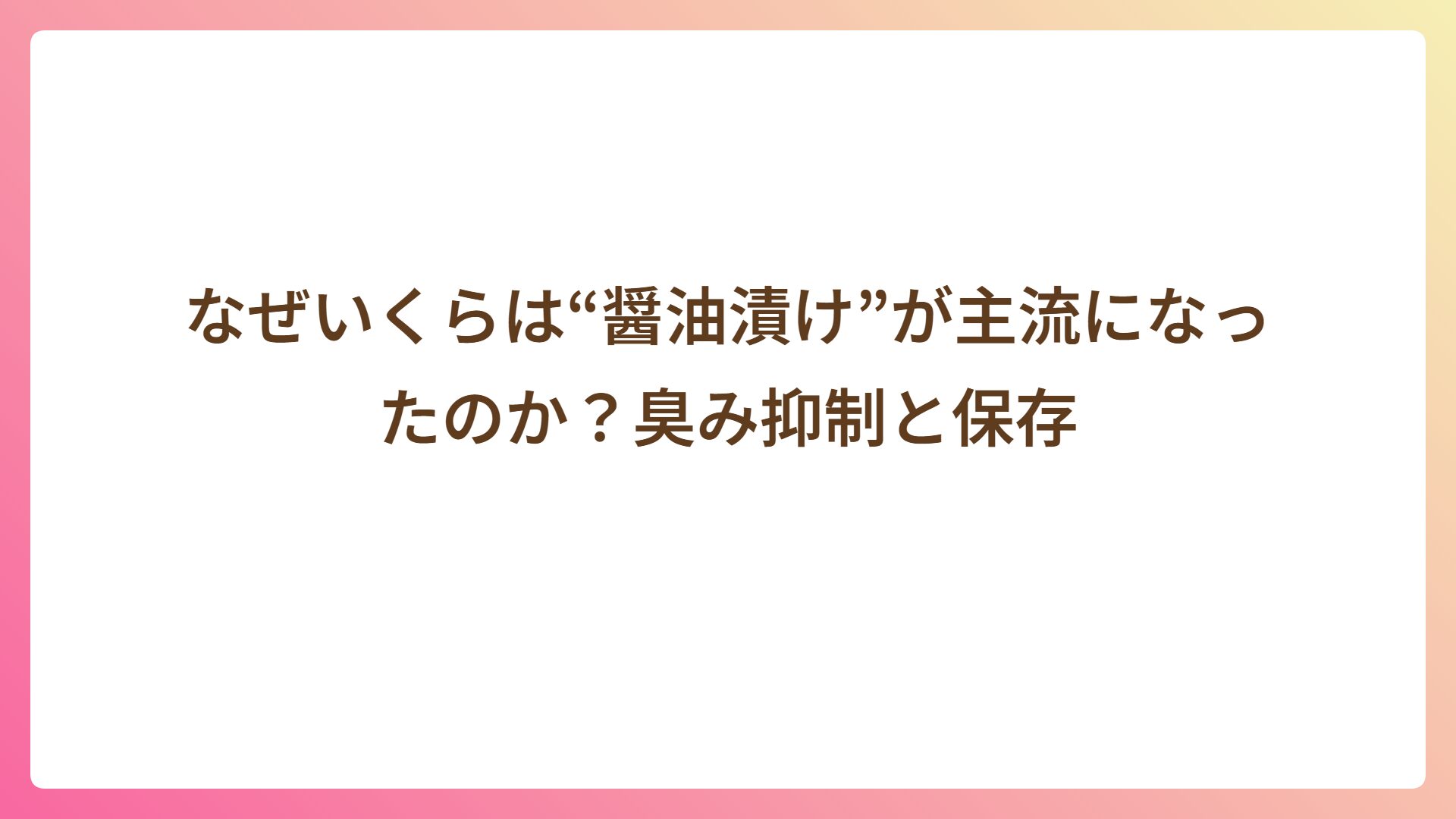「還暦」の意味とは?なぜ60歳で祝うのかを干支の仕組みから解説

赤いちゃんちゃんこで祝う還暦。今では長寿化で盛大に祝う習慣は減りましたが、なぜ還暦は60歳で迎えるのでしょうか? その答えは「干支の仕組み」に隠されています。この記事では、還暦の意味や数え年との関係、さらには別名についても解説します。
還暦とは「暦が還る」こと
「還暦」という言葉は「暦が還る」と書きます。「還」にはもとに戻るという意味があり、ここでいう暦は「干支(えと)」を指します。つまり、還暦とは「干支が一周して生まれた年に戻ること」を意味します。
干支は「十干」と「十二支」から成る
干支というと「子・丑・寅…」といった十二支を思い浮かべる人が多いですが、実は「十干(甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸)」との組み合わせで成り立っています。
十干は10種類、十二支は12種類。組み合わせの最小公倍数は60になるため、干支は60種類存在します。そして60年で一巡し、生まれたときの干支に戻るのです。
還暦は60歳?61歳?
還暦を「60歳」とするのは現在の「満年齢」の考え方によるものです。満年齢では誕生日に年を重ね、生まれた年を0歳と数えます。
一方、昔の日本で使われていた「数え年」では、生まれた時点を1歳とし、正月ごとに年を重ねます。この場合、還暦は61歳にあたります。
したがって、還暦を60歳とするか61歳とするかは、年齢の数え方による違いなのです。
還暦の別名「華甲」
還暦には「華甲(かこう)」という別名もあります。
- 「華」を分解すると「十」が6つと「一」が1つ → 61(数え年での還暦の年齢)
- 「甲」は十干の最初 → 干支の一巡の始まりを表す
このことから、華甲は還暦を意味する言葉として使われています。
還暦以外の長寿祝い
日本には還暦以外にも長寿祝いがあります。
- 米寿(88歳):「米」の字を分解すると「八十八」
- 卒寿(90歳):「卒」の略字「卆」が「九十」に見える
いずれも語呂や字の形に由来しており、本来は数え年で祝うのが伝統とされています。
まとめ
還暦は「干支が一巡して生まれた暦に還ること」を意味し、満年齢では60歳、数え年では61歳にあたります。華甲という別名や、米寿・卒寿などの他のお祝いとあわせて知っておくと、長寿祝いの理解がより深まるでしょう。