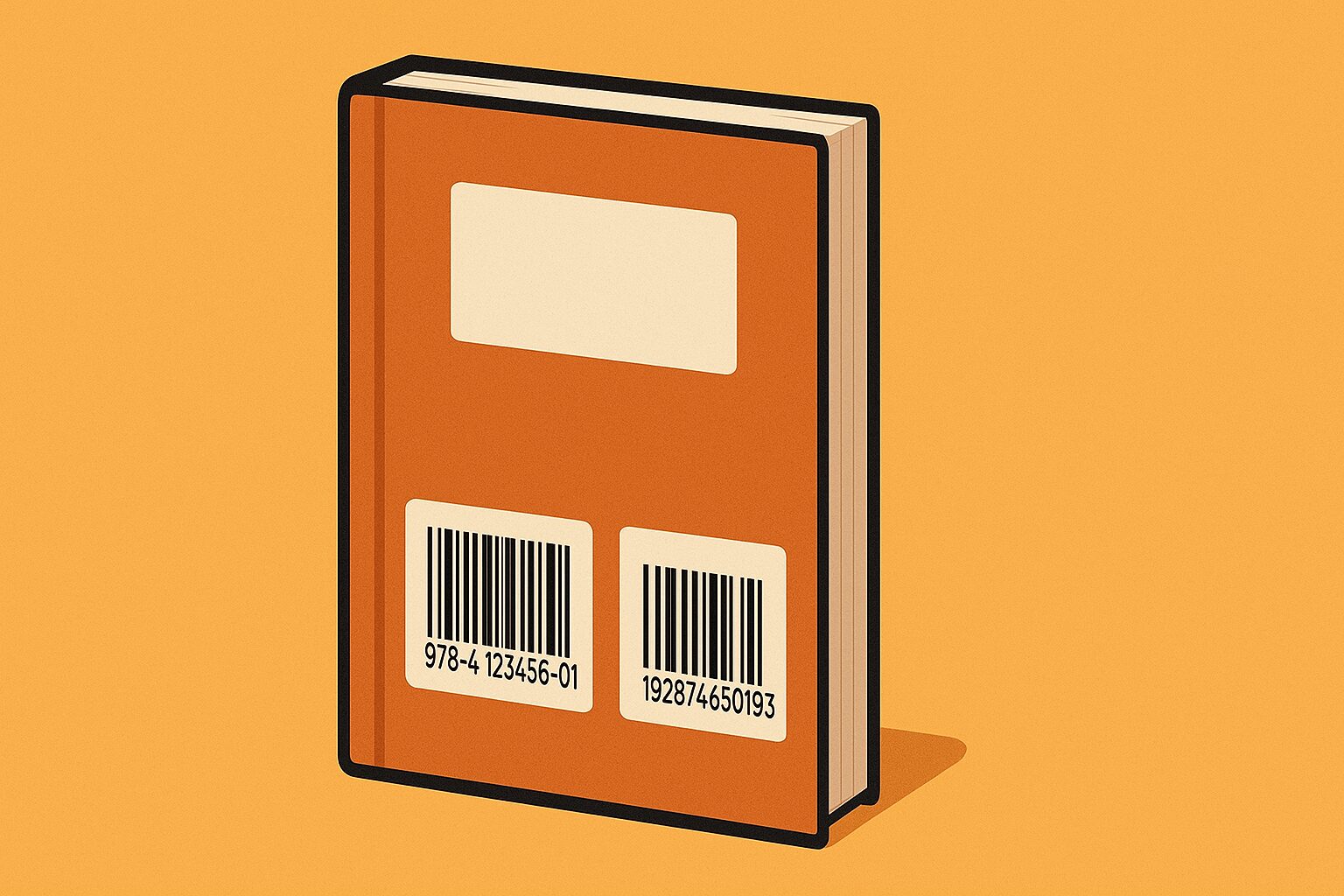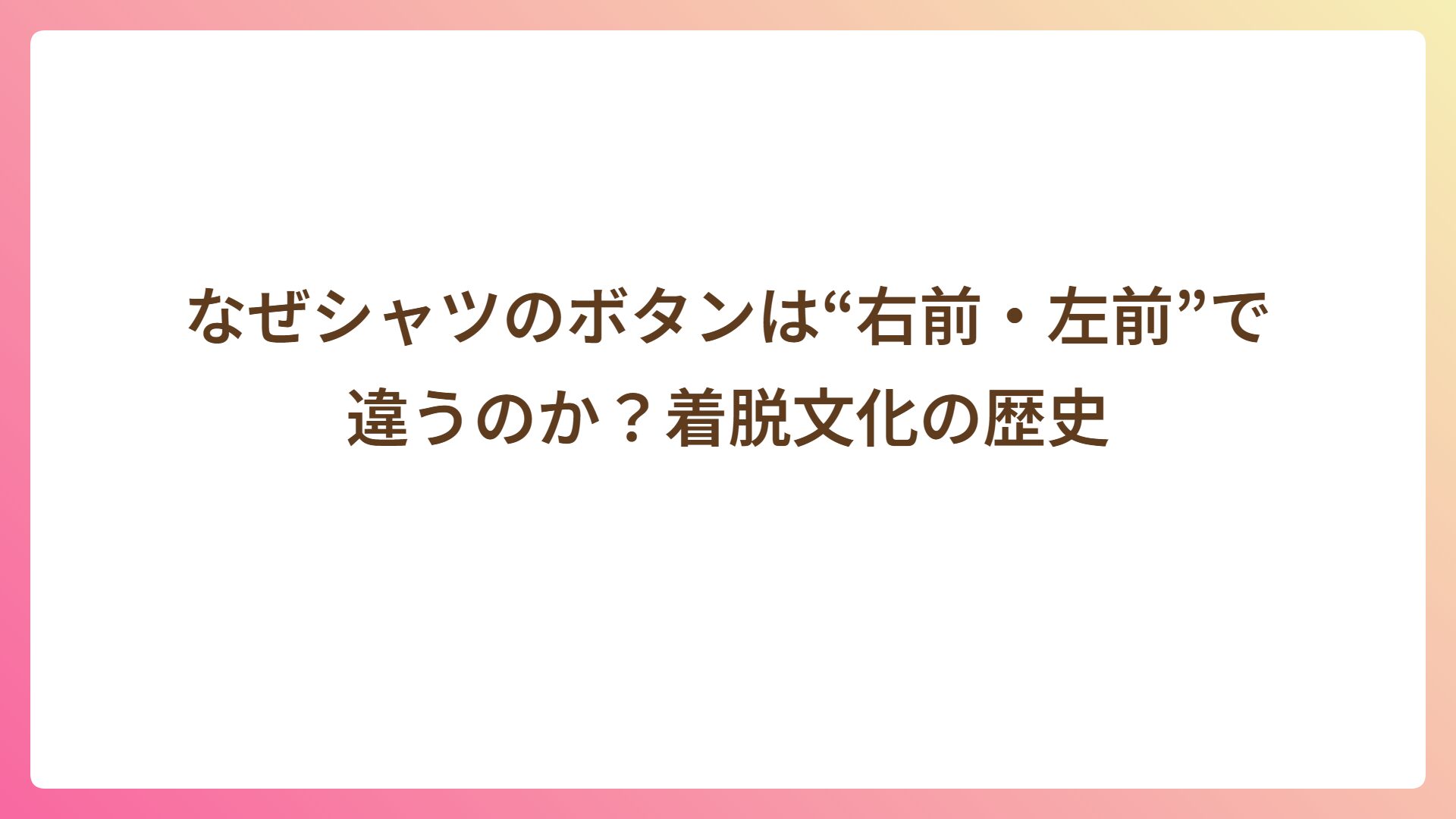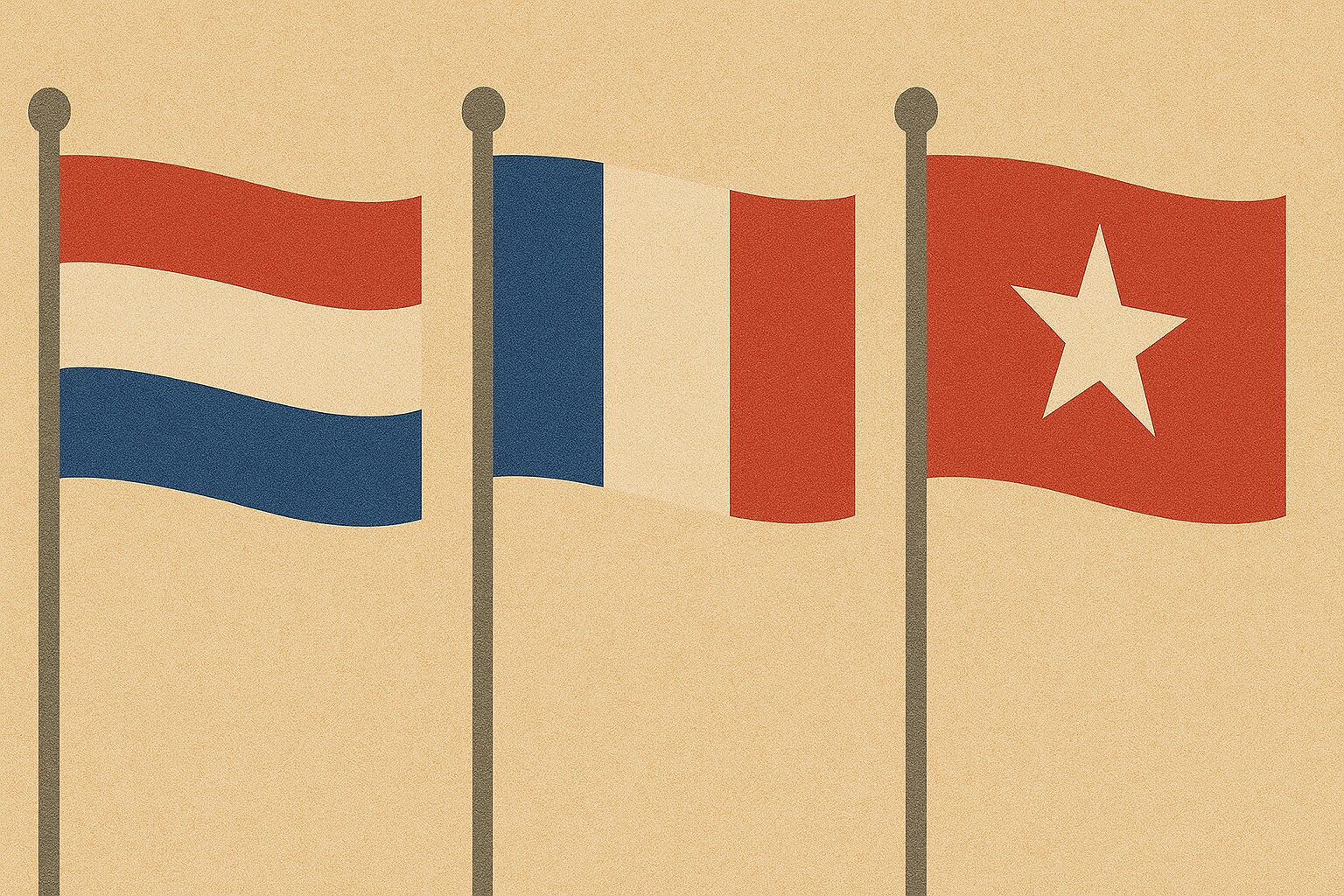なぜカラスは“道具を使う”と言われるのか?驚くべき知能と研究でわかった脳の仕組み

ペットボトルのフタをくわえて遊んだり、クルミを道路に落として車に割らせたり――
カラスの行動には「ただの鳥」とは思えない知性が感じられます。
実際、カラスは“道具を使う鳥”として、世界中の科学者から注目されています。
この記事では、カラスの知能の高さや道具使用の実例、そしてその脳構造について最新研究をもとに解説します。
カラスは「道具を作って使う」数少ない動物
道具を使う動物といえばチンパンジーが有名ですが、
カラス――特にニュージーランドガビチョウ(ニューカレドニアガラス)は、
自分で道具を作り、それを目的に合わせて使い分けることが確認されています。
例えば、木の穴に隠れた虫を取るために、
- 小枝を折って「フック状」に加工する
- 葉の茎をくわえて「棒状の道具」にする
といった行動をとります。
つまり、カラスは「自然物を改造して使う=“製作と利用”の両方を行う」極めて高度な知能を持っているのです。
実験で証明された“論理的思考”
ケンブリッジ大学の研究では、カラスが「水位上昇パズル」を解くことが確認されています。
実験では、透明な筒の中にエサを入れ、カラスが小石を落として水面を上げ、エサを浮かせて取るという課題を出しました。
結果は見事に成功。
しかも、
- 水に沈む石だけを選んで使う
- 浮くプラスチック片は使わない
といった「因果関係の理解」が見られました。
これは、“重いものを入れると水が上がる”という物理法則を理解していることを示しており、
人間の5〜7歳の子どもに相当する知能レベルと考えられています。
記憶力と観察力も超一流
カラスは他の個体の行動を観察して学ぶ能力(社会的学習)も非常に高いです。
人が投げたゴミ袋を見て“中身を覚える”、
一度危険を感じた人の顔を数年後まで記憶するといった研究結果もあります。
ワシントン大学の実験では、研究者がカラスを捕まえたあと、数年後に再びその顔で近づいたところ、
その顔を覚えて攻撃行動を取る個体がいたことが確認されています。
つまり、カラスは長期記憶と仲間への情報共有を組み合わせて、危険を学習しているのです。
脳の大きさは小さいが「密度」が高い
意外にも、カラスの脳のサイズはピンポン玉ほどしかありません。
それでも人間のような複雑な思考が可能なのは、神経細胞(ニューロン)の密度が非常に高いからです。
研究によると、カラスの脳の前頭部(“鳥類の前頭葉”に相当する部位)は、
サル類とほぼ同レベルのニューロン密度を持っており、
- 計画を立てる
- 道具の使い方をシミュレーションする
- 結果を予測して行動を変える
といった論理的・未来志向的な思考が可能だとされています。
社会性とコミュニケーション能力も高い
カラスは非常に社会的な鳥で、仲間同士の情報共有や協力行動も確認されています。
たとえば、
- 危険な敵を見つけると「警戒鳴き」で仲間に知らせる
- 他の個体がエサを見つけたとき、その場所を観察して覚える
- 敵を集団で追い払う(モビング)
など、人間社会のような“役割分担”に近い行動も見られます。
このような行動は、単なる反射ではなく、状況判断と意図の共有ができる知能の表れです。
まとめ:カラスは“空を飛ぶ研究者”
カラスが“道具を使う”と言われるのは、
- 木の枝や葉を加工して目的に合った道具を作る
- 水位を上げるなど因果関係を理解して問題を解く
- 顔を覚えたり仲間に情報を伝えたりする高度な社会性
といった、人間にも通じる知能を持っているからです。
つまり、カラスは単なる鳥ではなく、
観察・実験・共有を行う「空の研究者」ともいえる存在なのです。