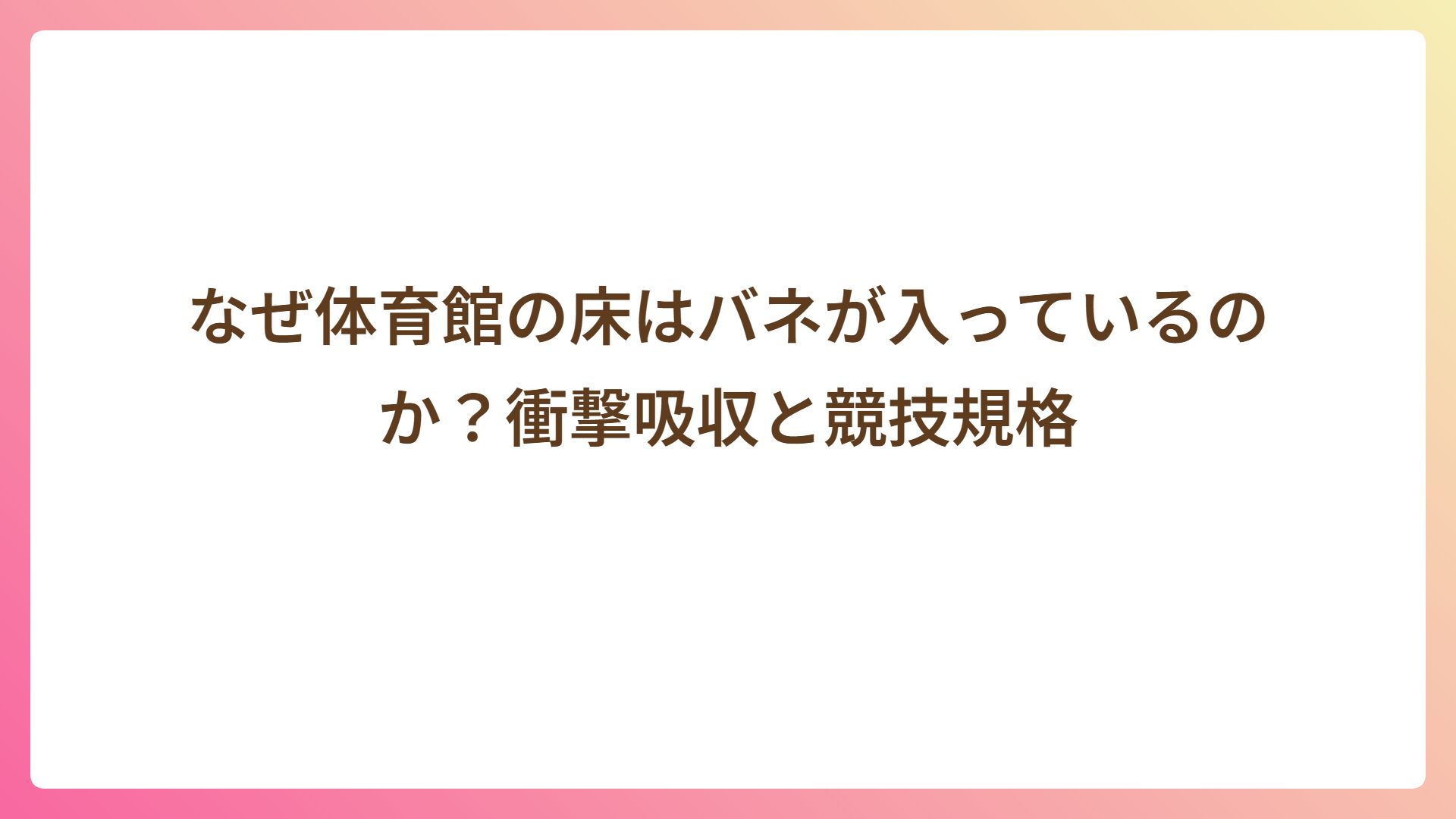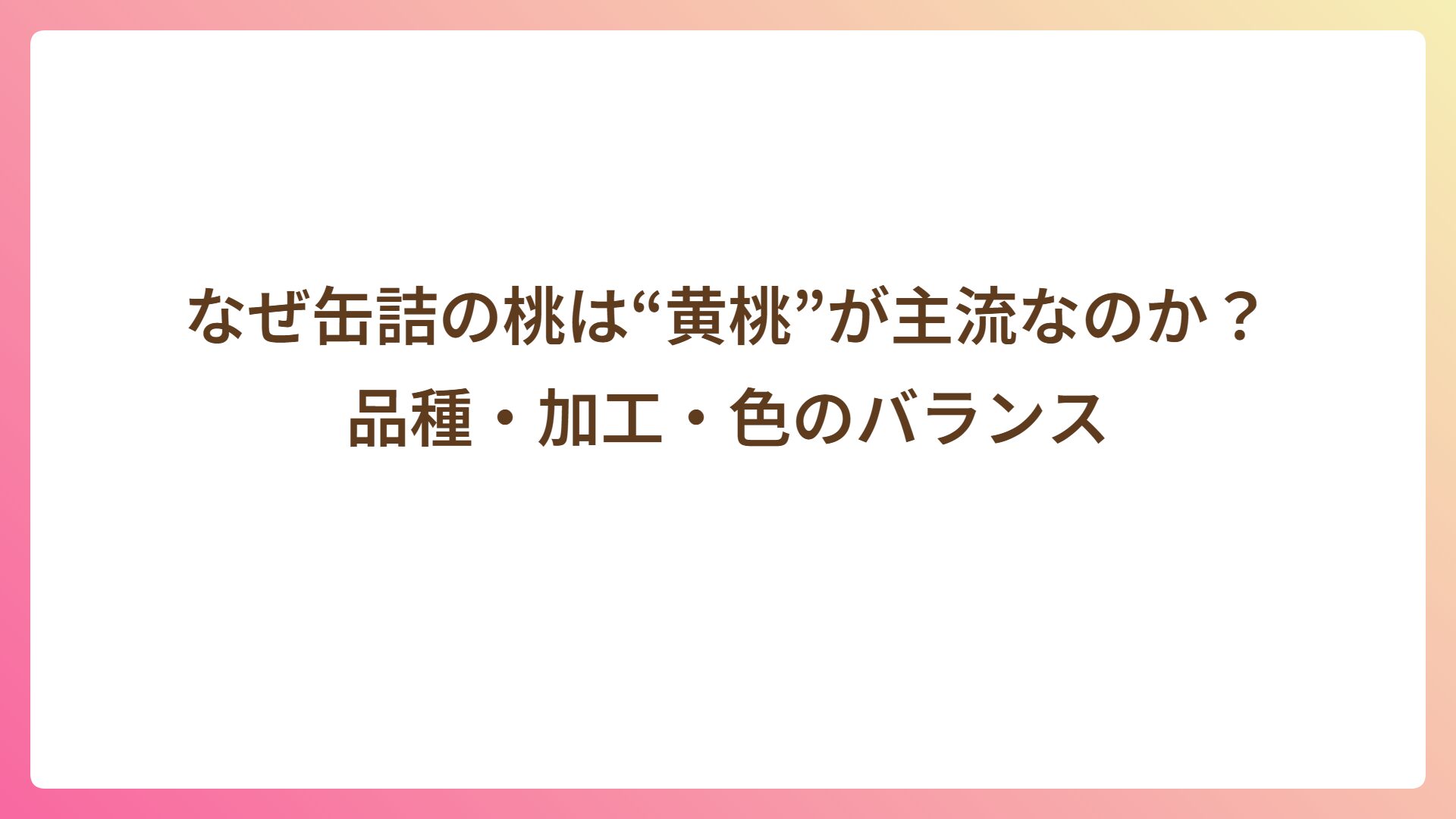なぜ折り畳み傘の骨数は“6/8本”が主流なのか?重量と耐風のバランス
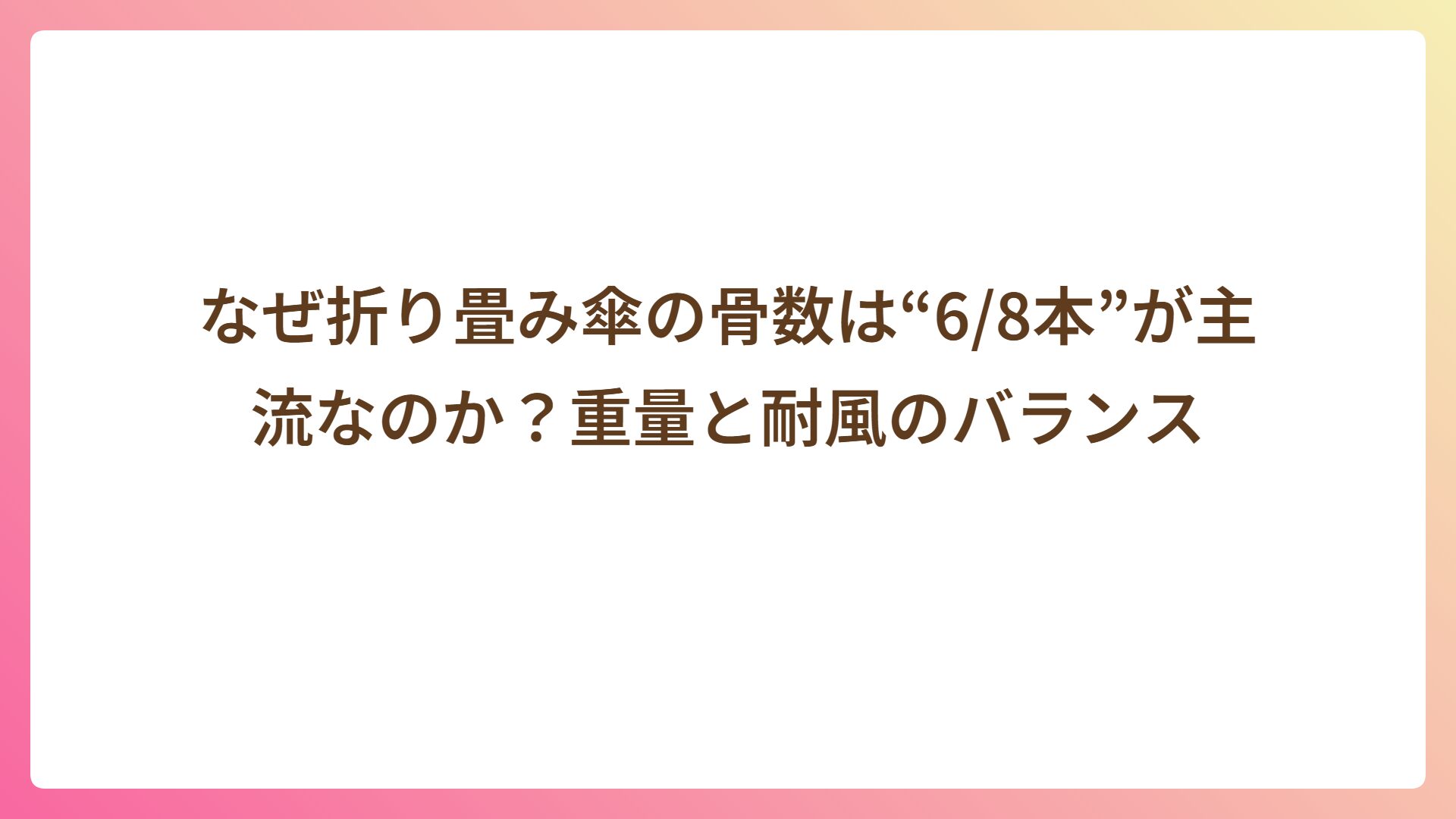
折り畳み傘をよく見ると、骨の数が6本や8本であることが多いと気づきます。
なかには10本や12本の傘もありますが、主流はあくまで6〜8本。
この本数には、軽量化・耐風性・機構の安定性といった複数の要素が関係しています。
実は、折り畳み傘の骨数は“偶然”ではなく、設計上のベストバランスとして導き出されたものなのです。
骨数が増えると強いが、重くなる
傘の骨(リブ)は、傘の形を支えるフレーム部分であり、風圧を受ける際の力の分散を担っています。
骨が多いほど風に対してしなりが分散され、構造的には強くなるのが一般的です。
しかしその分、金属部品やジョイントが増え、重量が大きくなるという欠点もあります。
折り畳み傘では携帯性が最優先されるため、
「強度を保ちながらも軽くしたい」という条件から、6本または8本が最も効率的な構成になったのです。
6本構造:軽量・携帯性を重視
6本骨の傘は、コンパクトさと軽さが魅力です。
1本あたりの骨が支える面積はやや広くなりますが、
カーボンファイバーやアルミ合金を採用することで、十分な強度を確保できます。
特に、ビジネス用や通勤用など「持ち歩く時間が長い傘」では、
軽量な6本構造が選ばれる傾向があります。
また、骨の本数が少ない分だけ開閉機構がシンプルで壊れにくいという利点もあります。
8本構造:安定性と耐風性を重視
一方で8本骨は、6本よりも風への耐久性と形状安定性に優れています。
風圧が均等に分散され、布の張りがきれいに保たれるため、
「雨に強い」「裏返りにくい」といった実用面での安定感があります。
特に自動開閉式や大きめの折り畳み傘では、
8本構造が採用されることで剛性と見た目のバランスを取っているのです。
骨数が増えすぎると逆に弱くなる場合も
骨を増やせば強くなるように思えますが、実際には部品点数の増加によるトラブルリスクも高まります。
ヒンジ部分が増えると可動部の遊び(ガタ)が出やすく、
強風時に力が分散しきれず1本が折れて連鎖的に破損するケースもあります。
また、折り畳み構造では、骨の収納位置が限られているため、
本数が多いと畳んだときに布が厚くなり、閉じにくくなるという問題も生じます。
素材の進化が“6/8本主流”を定着させた
かつての傘は鉄や真鍮などの重い金属を使っていたため、
耐風性を求めるには骨を増やすしかありませんでした。
しかし、近年は軽量アルミ・FRP(ガラス繊維強化プラスチック)・カーボンなどが普及し、
少ない骨でも十分な強度が確保できるようになりました。
こうした素材進化の結果、
「6本=軽量モデル」「8本=耐風モデル」という棲み分けが自然に定着したのです。
風洞実験による設計データ
メーカーによる風洞試験では、
6本と8本の傘で耐風限界(裏返りが発生する風速)は約15〜18m/sとほぼ同水準。
それ以上の風になると、本数よりも骨材の弾性率やフレーム構造の方が性能を左右することが分かっています。
つまり、6本と8本は軽さと強さのバランスが最も良いゾーンなのです。
まとめ
折り畳み傘の骨が6本や8本で作られているのは、
携帯性・強度・開閉機構・コストのバランスが最も取れているからです。
6本は軽くて持ち歩きやすく、8本は安定感と耐風性に優れる。
この“6/8本設計”は、素材と構造の進化が導き出した、人間工学的な最適解なのです。