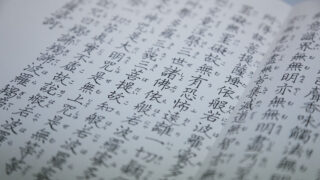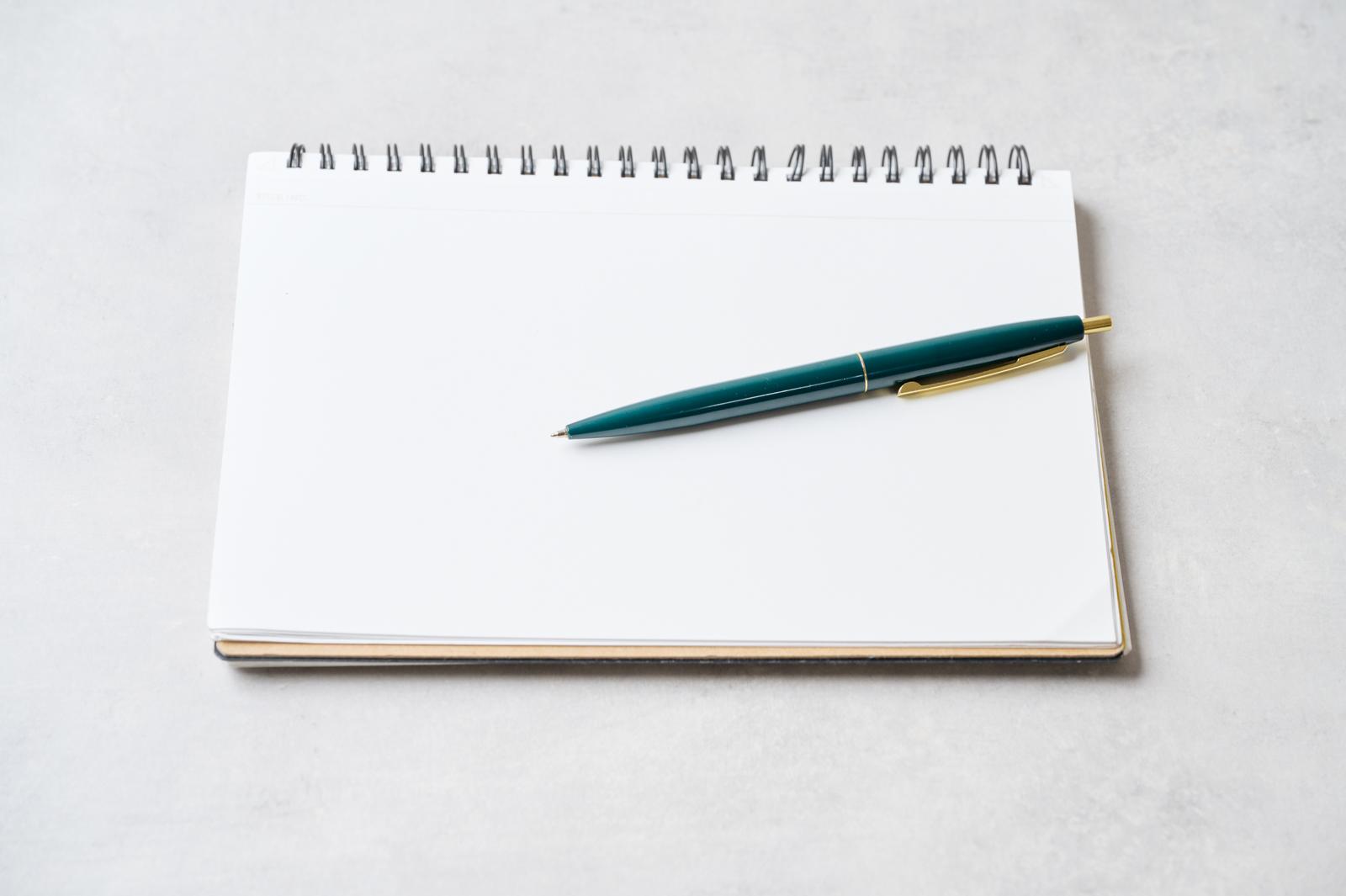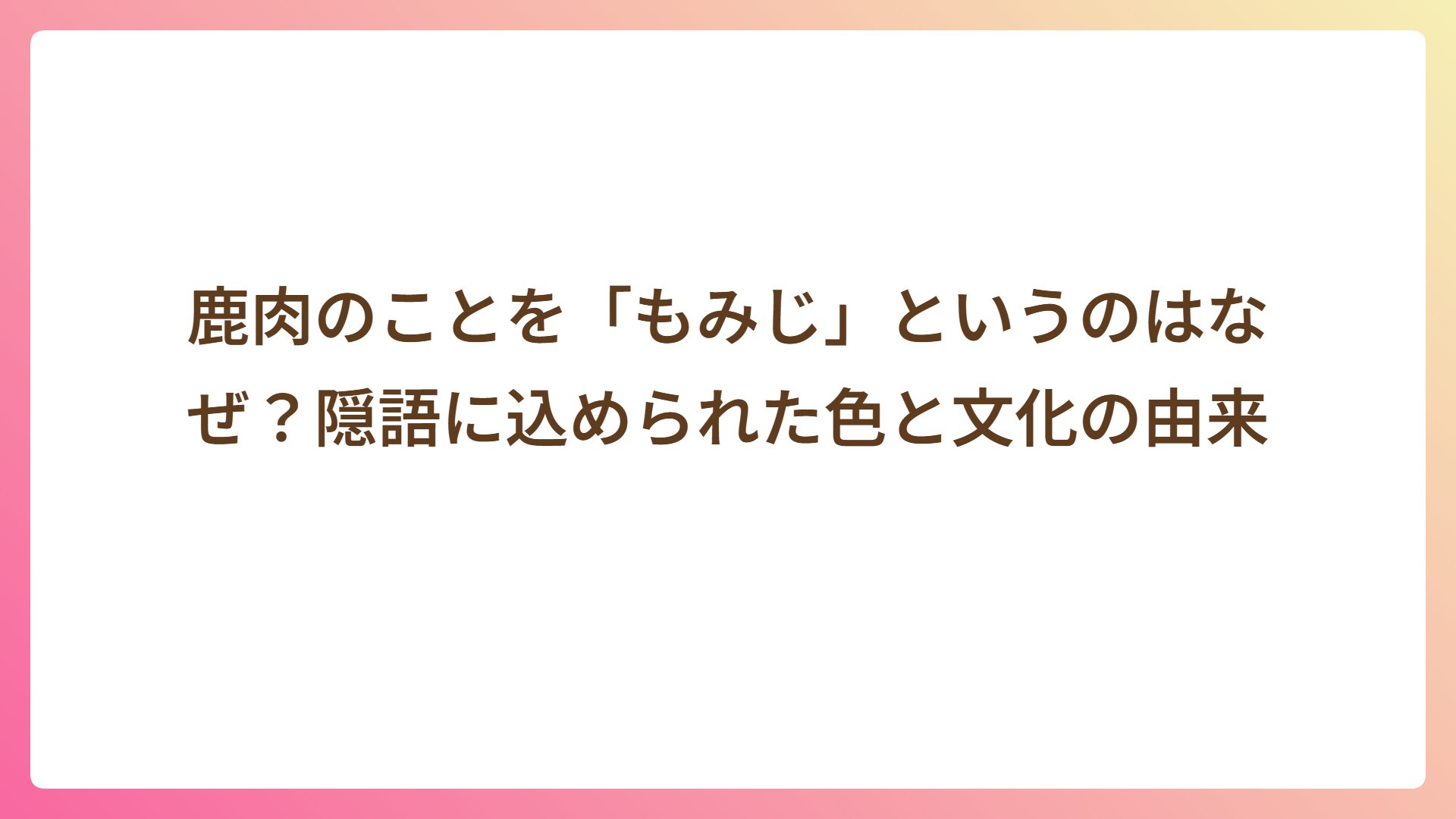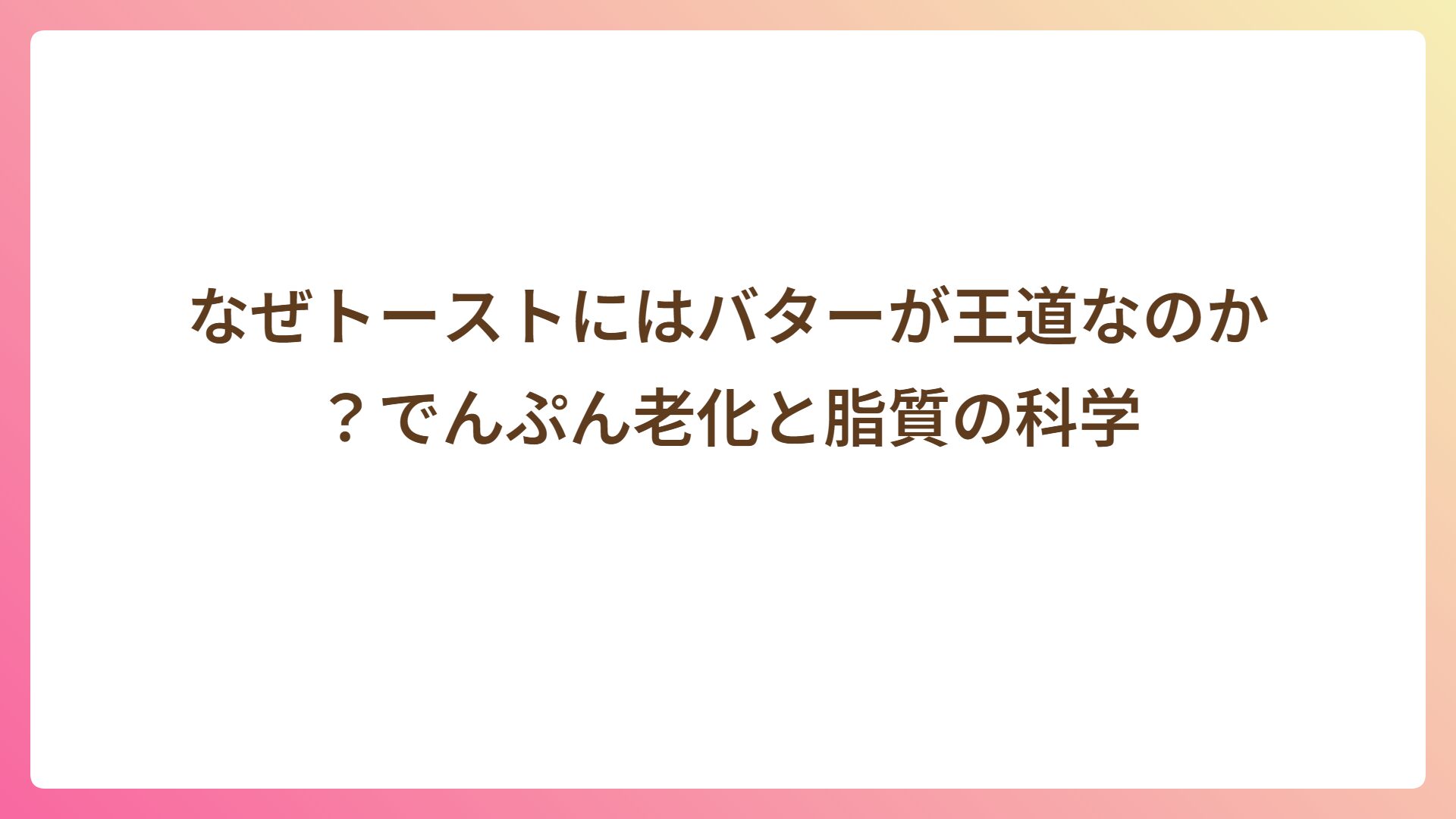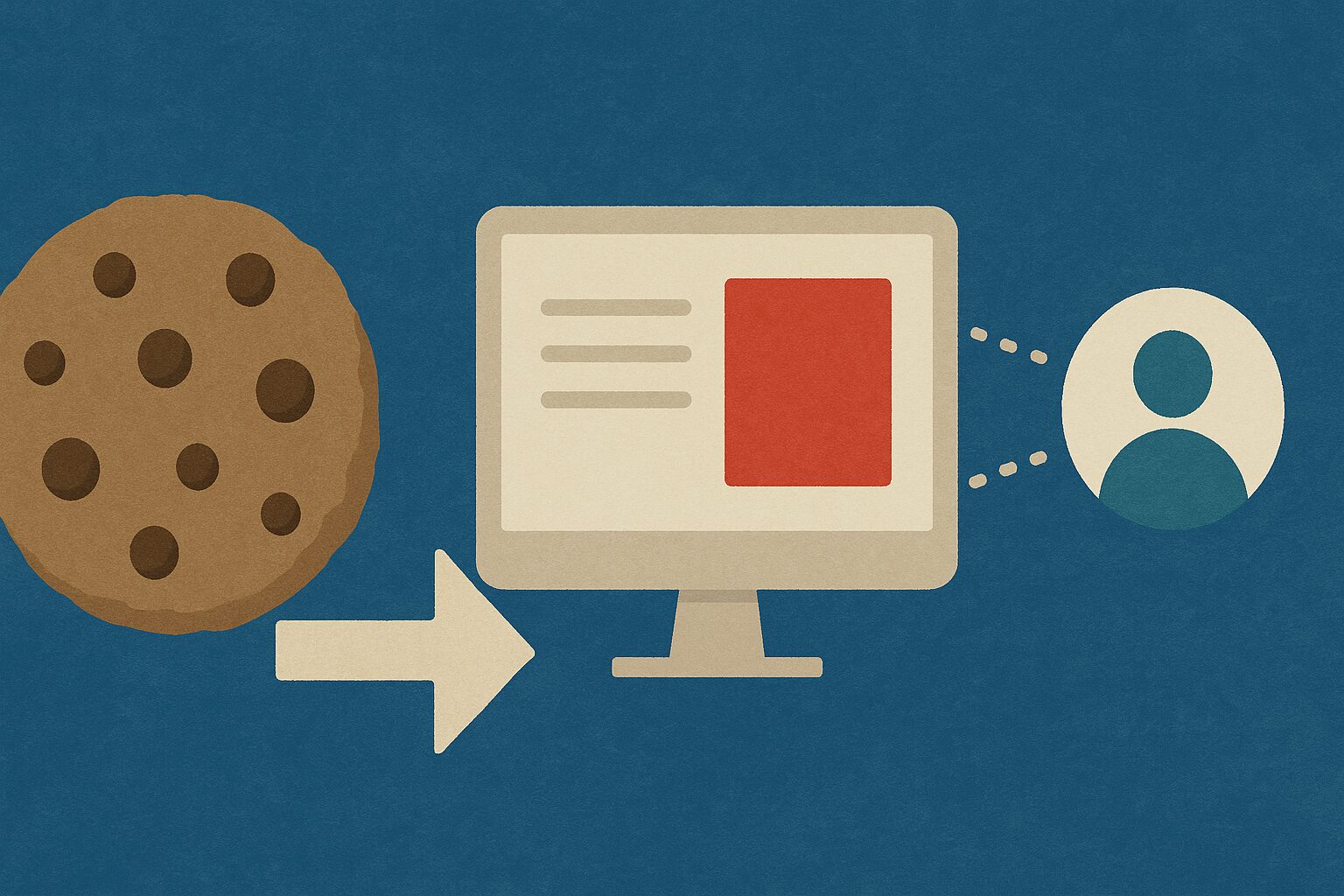ひらがなとカタカナはなぜ2種類ある?日本語に仮名が複数存在する理由とは
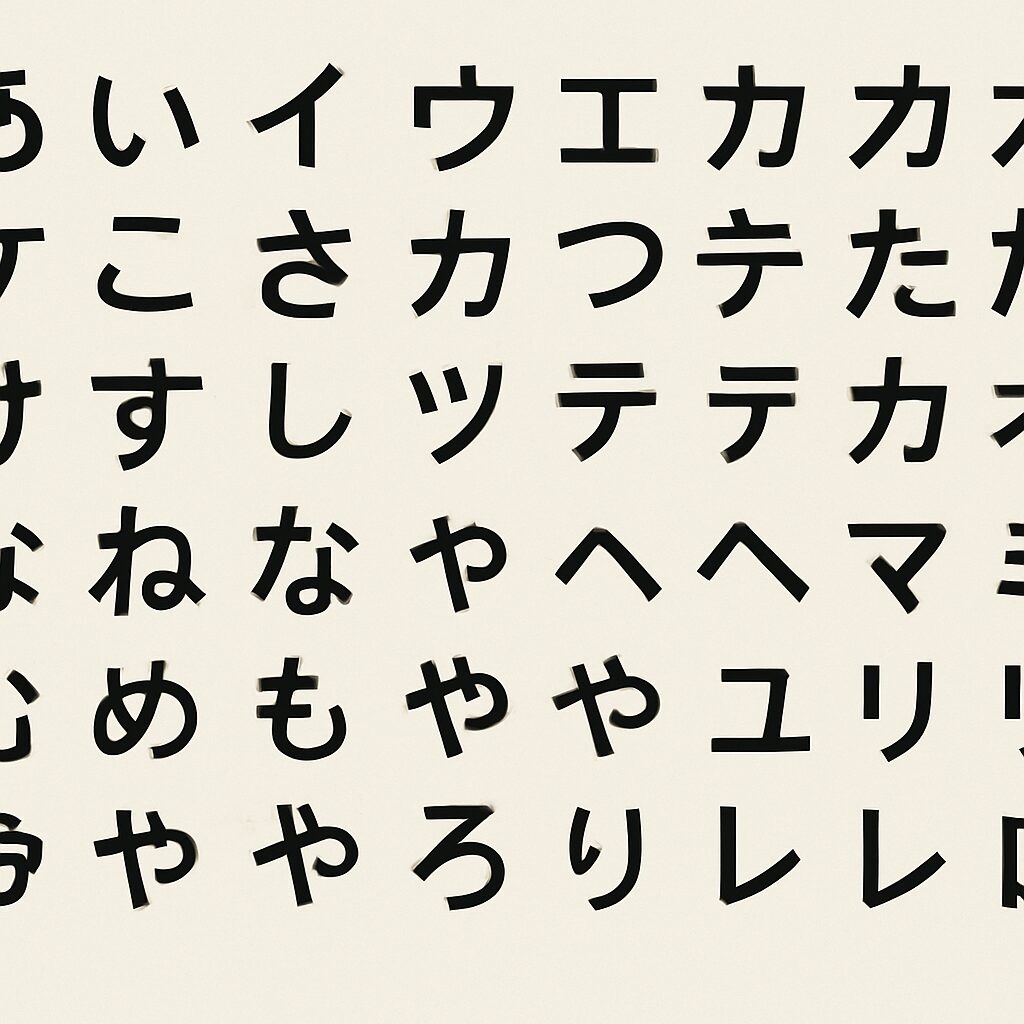
日本語には、漢字・ひらがな・カタカナという3種類の文字が使われています。
その中でも「ひらがな」と「カタカナ」という2つの仮名が、なぜ今も両方存在しているのか不思議に思ったことはありませんか?
実はそこには、平安時代の社会構造と文字文化の進化が深く関係しているのです。
日本語に文字がなかった時代と「万葉仮名」の登場
日本に漢字が伝わる以前、日本語には文字がありませんでした。そのため、当初の文章はすべて中国語(漢文)で書かれていたのです。
しかし、日本語の語順や発音は中国語と大きく異なるため、漢文だけでは日本語の表現には限界がありました。そこで登場したのが「万葉仮名(まんようがな)」です。
万葉仮名とは、漢字の意味ではなく「音」を借りて、日本語の発音を表す手法です。現代でいえば、「よろしく」を「夜露死苦」と書くようなイメージです。
画数が多すぎる万葉仮名に代わる書き方が生まれた
万葉仮名は便利ではあったものの、漢字をそのまま使っていたため、画数が多く書くのが大変でした。そこで漢字を簡略化し、省略・崩しを加えた新しい表記法が生まれました。それが「ひらがな」と「カタカナ」です。
ひらがなは女性中心に広まった「くずし字」
ひらがなは、万葉仮名を草書体(流れるように崩した筆記体)でくずしたことから誕生しました。奈良時代の終わり頃から使われはじめ、平安時代には現在の形に近いひらがなが確立します。
当時、ひらがなは「仮の文字」と見なされ、公式な場では使われない非公認の書体でした。しかしその簡便さから、日常的な文や手紙など、特に女性の間で広く使われるようになったのです。
『土佐日記』の冒頭にある「をとこもすなる日記といふものを…」という有名な書き出しからも、女性がひらがなを使っていた様子がうかがえます。
カタカナは僧侶による漢文読解のための補助文字
一方、カタカナは漢字の一部を抜き出してシンプルな形にしたものです。こちらも平安時代初期に生まれました。
では、カタカナは何のために作られたのでしょうか? 答えは「漢文を読み解くための補助記号」です。
当時の貴族や僧侶は、中国から伝わった漢文を学ぶことが必須でした。しかし漢文は日本語とは構造が異なるため、助詞や送り仮名を補わなければ読むのが難しい。そこで、漢字の横や間に小さく記す補助文字として、カタカナが使用されたのです。
このようにカタカナは、主に男性、特に僧侶や学者のあいだで実用的に使われていました。
ひらがなとカタカナが両方残った理由とは?
ひらがなとカタカナは、成り立ちも使う場面も大きく異なっていました。
- ひらがな:日常の手紙や文学、特に女性によって使用
- カタカナ:漢文の注釈や学術用途、僧侶・貴族によって使用
このように用途が明確に分かれていたことで、どちらか一方が消えることなく、両方が平行して生き残ったと考えられています。
現在でも、ひらがなは文章の主役として使われ、カタカナは外来語や強調、専門用語などに使われています。それぞれが役割分担を保ち続けているのです。
おわりに|仮名は日本語の多様性を支える存在
ひらがなとカタカナは、見た目は似ていても成り立ちも役割も違います。日本語の難しさの一因とも言われるこの「2種類の仮名」は、むしろ日本語の表現の豊かさと歴史の奥深さを物語っているのです。