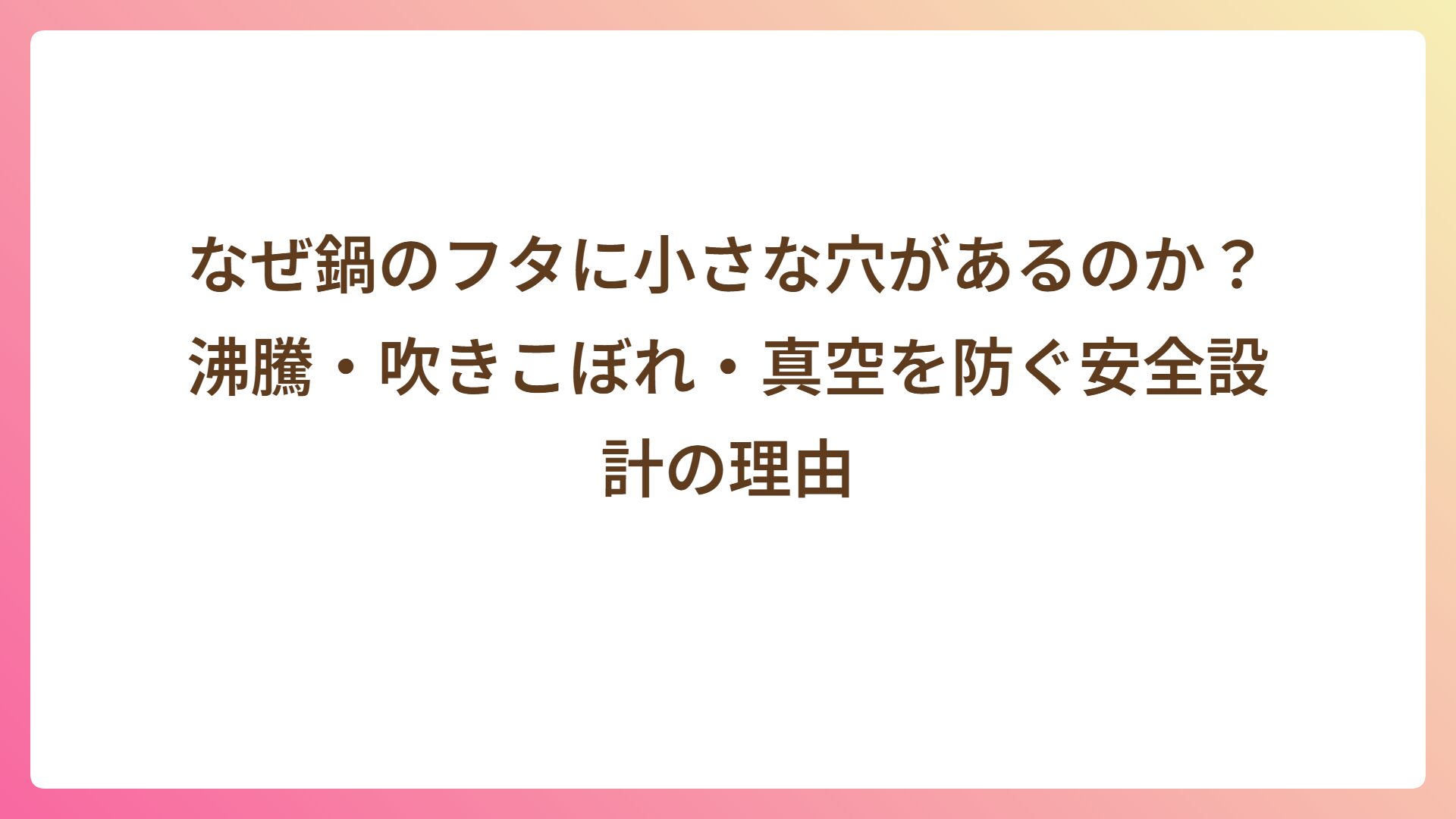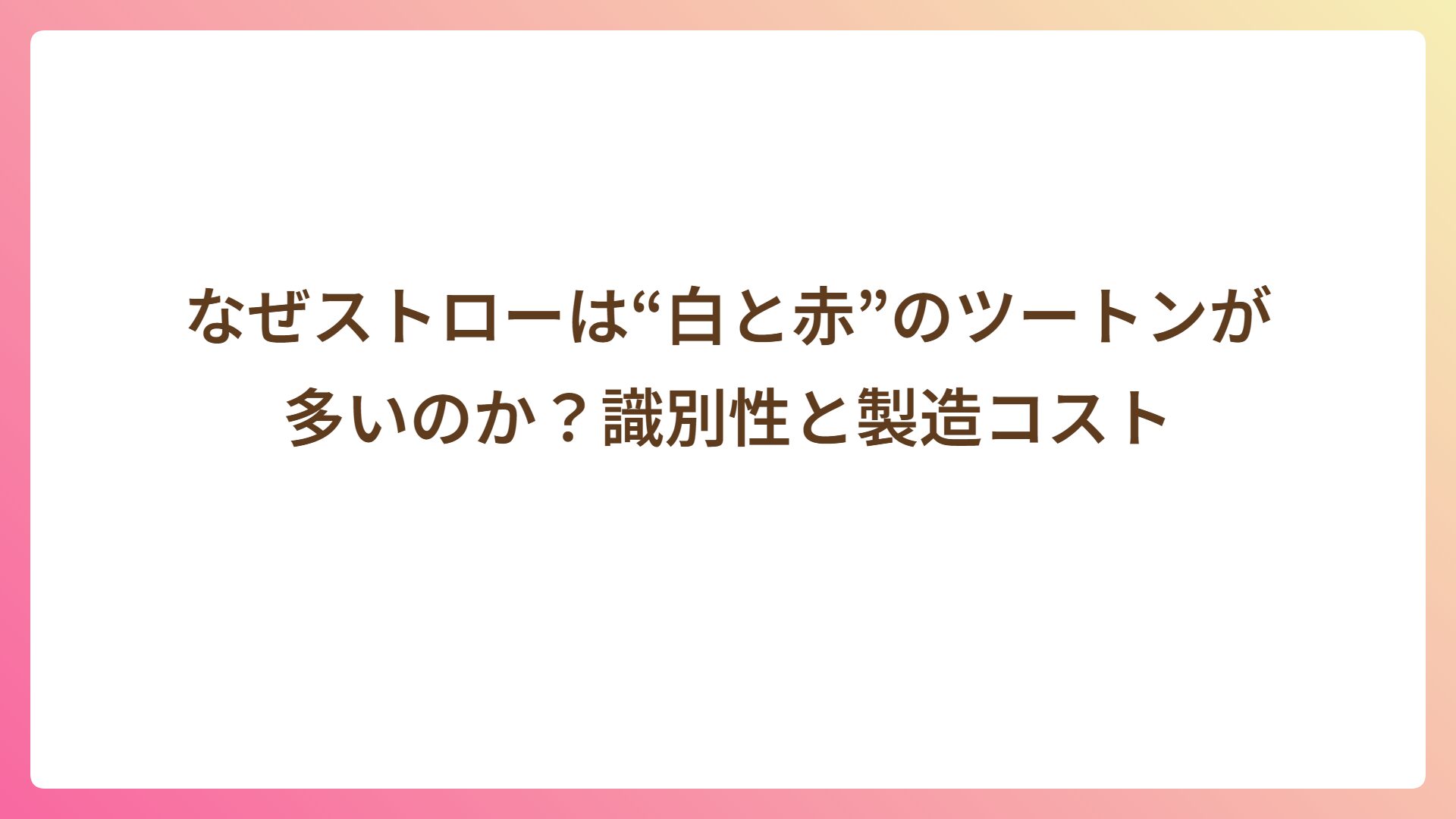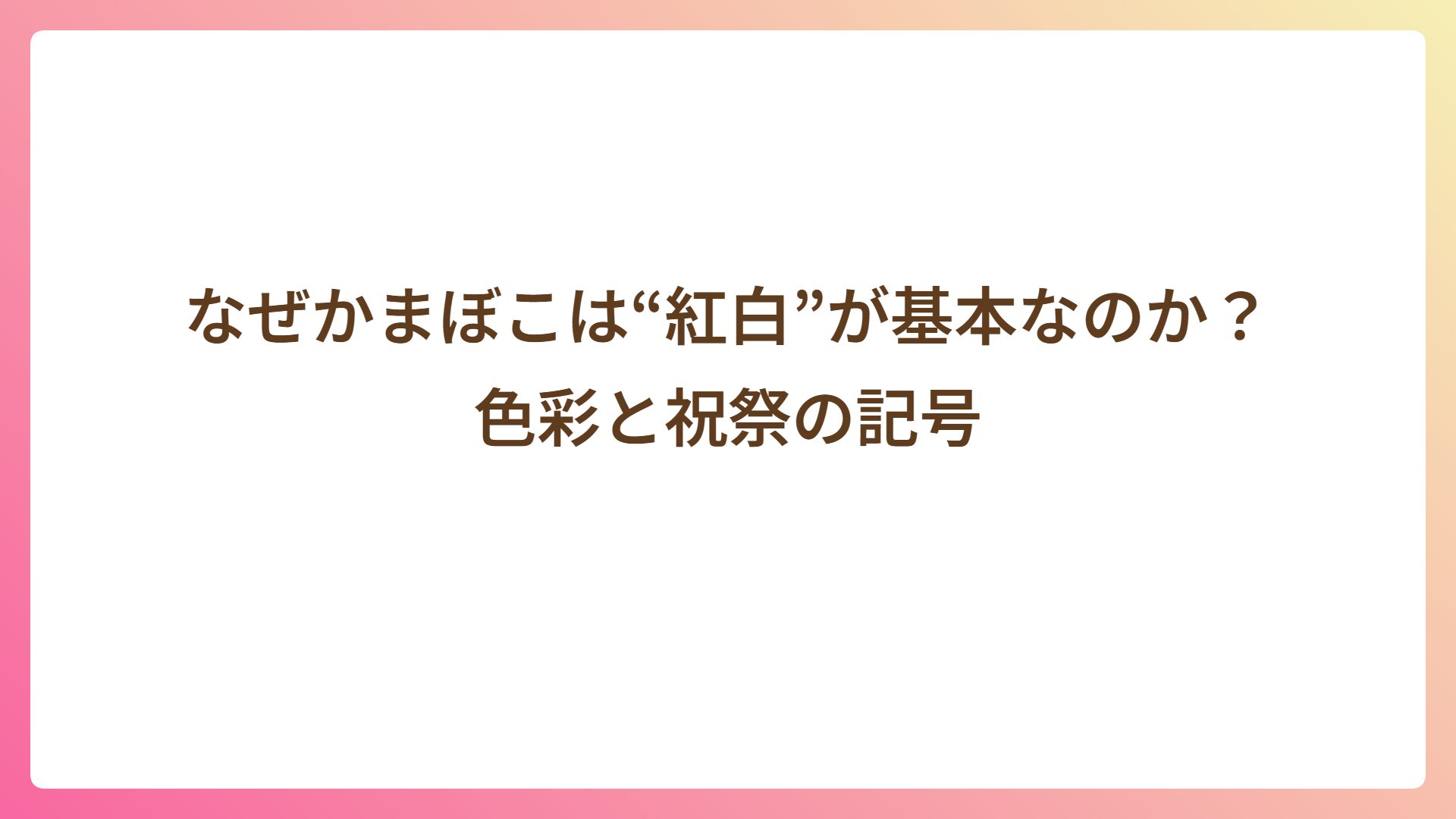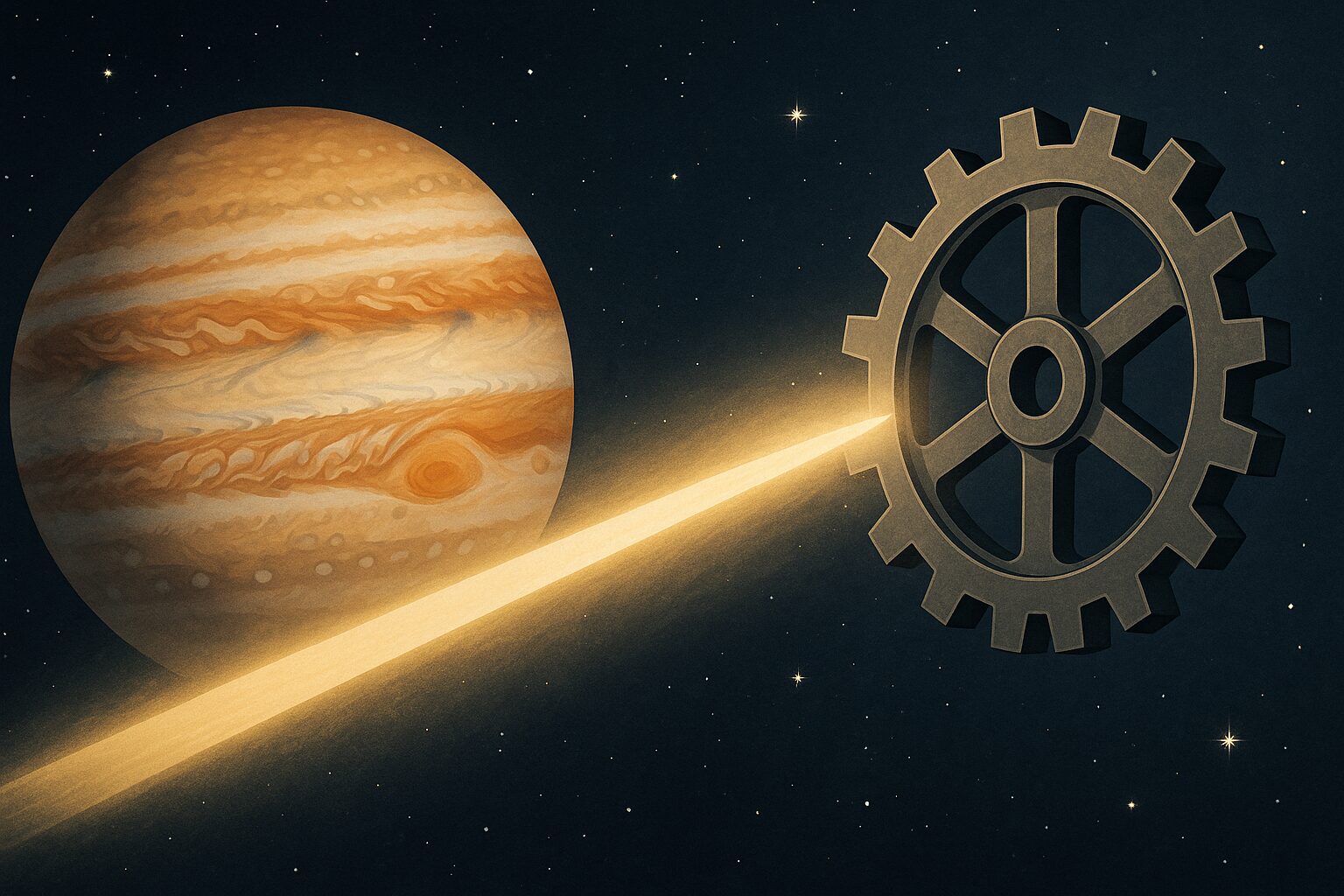なぜ“数え年”は今も一部で使われるのか?暦と通過儀礼
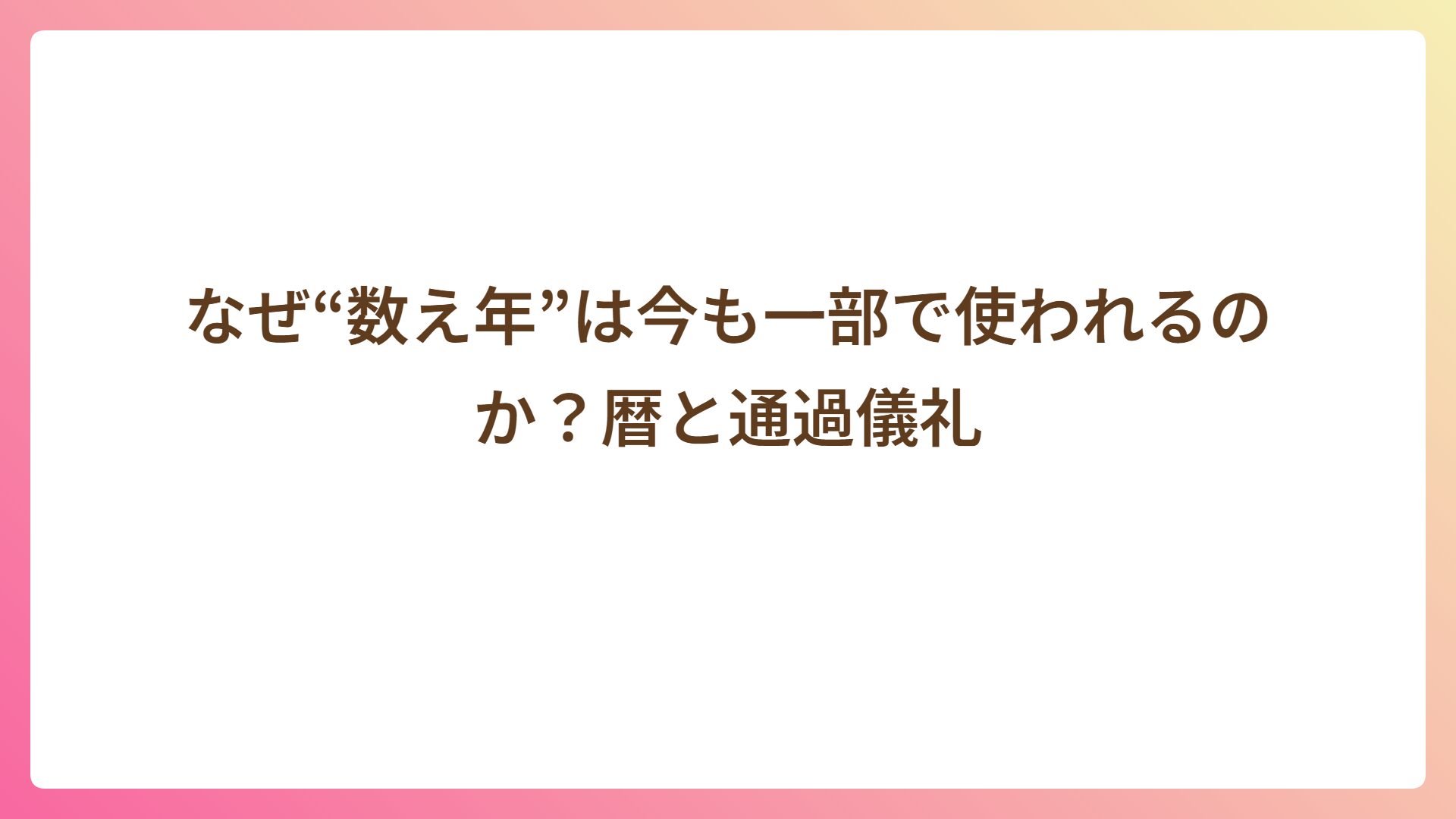
今では年齢といえば「誕生日を迎えるたびに一つ増える」満年齢が常識です。
それでも、七五三や厄年などの行事では「数え年」で数える場面が少なくありません。
なぜ古い数え方が現代まで残っているのでしょうか。
そこには、暦の区切りと人生儀礼を重ねてきた日本の歳時観が関係しています。
数え年とは“生まれた瞬間に一歳”
数え年とは、誕生日ではなく「生まれた時点で一歳」とし、
以後、正月を迎えるたびに一歳加える数え方です。
たとえば12月生まれの子どもは、翌年の元日で二歳になります。
この考え方の背景には、かつての日本人の時間感覚――
「一年=命の周期」という暦中心の年齢観がありました。
つまり、「生まれた年=命の始まり」「新年=命が一つ成長する節目」として、
個人の誕生日よりも社会全体の暦を基準にしていたのです。
満年齢が主流になったのは明治以降
明治時代に西洋式の暦(太陽暦)が導入され、
行政や学校制度では「誕生日ごとに年齢を加算する」満年齢制が採用されました。
これは統計や記録管理の合理化を目的とした制度で、
法律上も1950年の「年齢計算ニ関スル法律」により正式に統一されています。
しかし、それ以前は全国的に数え年が用いられており、
人々の生活リズムも「旧暦」「正月」「節句」など暦の節目に合わせた年齢観に根付いていました。
通過儀礼では“節目を共有する”意味が重視された
七五三や厄年などの行事で今も数え年が使われるのは、
**「人生の節目を社会全体で同時に祝う」**という考え方の名残です。
個人の誕生日ではなく、「年の区切り」で成長を祝うことで、
家族・地域・共同体が同じリズムで節目を共有できる。
これが数え年のもつ社会的な意義でした。
とくに子どもの行事では、「年明けとともに一つ成長した」と考えることで、
季節の巡りと生命の成長を重ねる感覚が生まれます。
七五三を「数え三歳・五歳・七歳」で祝うのも、こうした暦のリズムを受け継いでいるのです。
厄年における“数え年”の理由
厄年が数え年で計算されるのも、同じく旧暦的な年齢観によるものです。
もともと厄年は、「身体や運気の変化が起こりやすい節目」を示す民間信仰で、
数え年で「人生の節目=新しい年」を迎えたときに厄が訪れるとされました。
つまり、誕生日よりも「年の変わり目」こそが転機であり、
そこで身を慎むべき――という暦思想に基づいています。
厄払いを年明けに行う風習も、この考え方の延長線上にあります。
“満年齢でも数え年でも”という柔軟な現代感覚
現代では、七五三や厄年も「満年齢で行う」「数え年で行う」のどちらも認められています。
これは、行事が信仰よりも家族の記念や節目の行事として位置づけられるようになったためです。
ただし、寺社によっては今も「厄年=数え年」で案内しており、
信仰儀礼の場では古来の形式を尊重する傾向が残っています。
つまり、数え年は**神仏と暦に基づく“古来の時間の刻み方”**を今に伝える要素なのです。
まとめ:数え年は“暦で生きる文化”の名残
数え年が今も一部で使われる理由を整理すると、次の通りです。
- 古代では「正月に年を取る」という暦中心の時間感覚があった
- 満年齢の導入は明治以降で、もともと数え年が主流だった
- 通過儀礼や厄年では「節目を共有する」文化が重視された
- 現代でも寺社儀礼や伝統行事では旧暦的な考え方が残る
つまり、数え年は**「時間を社会とともに迎える」という古い暦文化の名残**なのです。
個人の誕生日よりも、年の初めに「一つ年を取る」という感覚には、
季節の巡りとともに生きてきた日本人の時間哲学が息づいているのです。