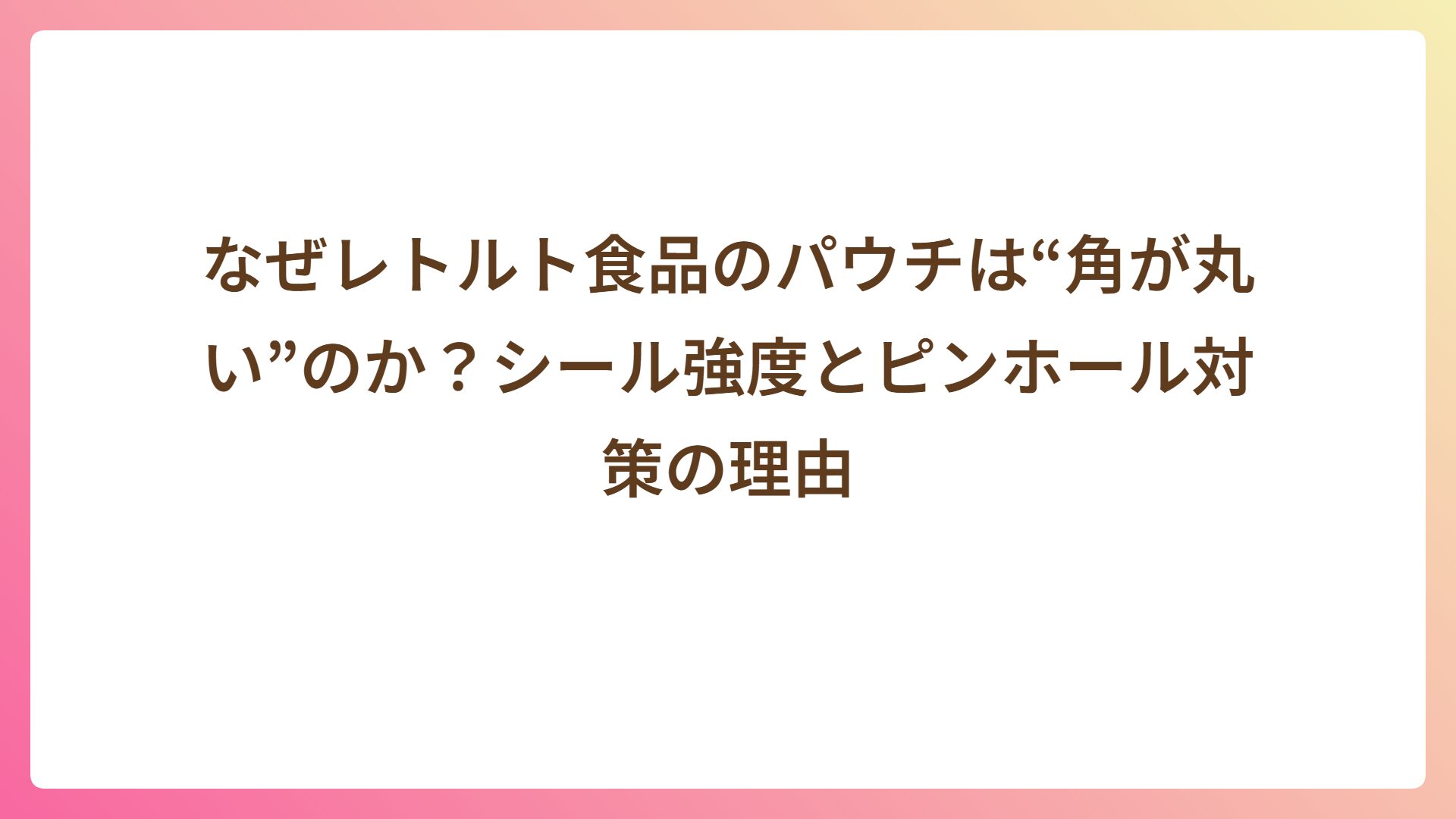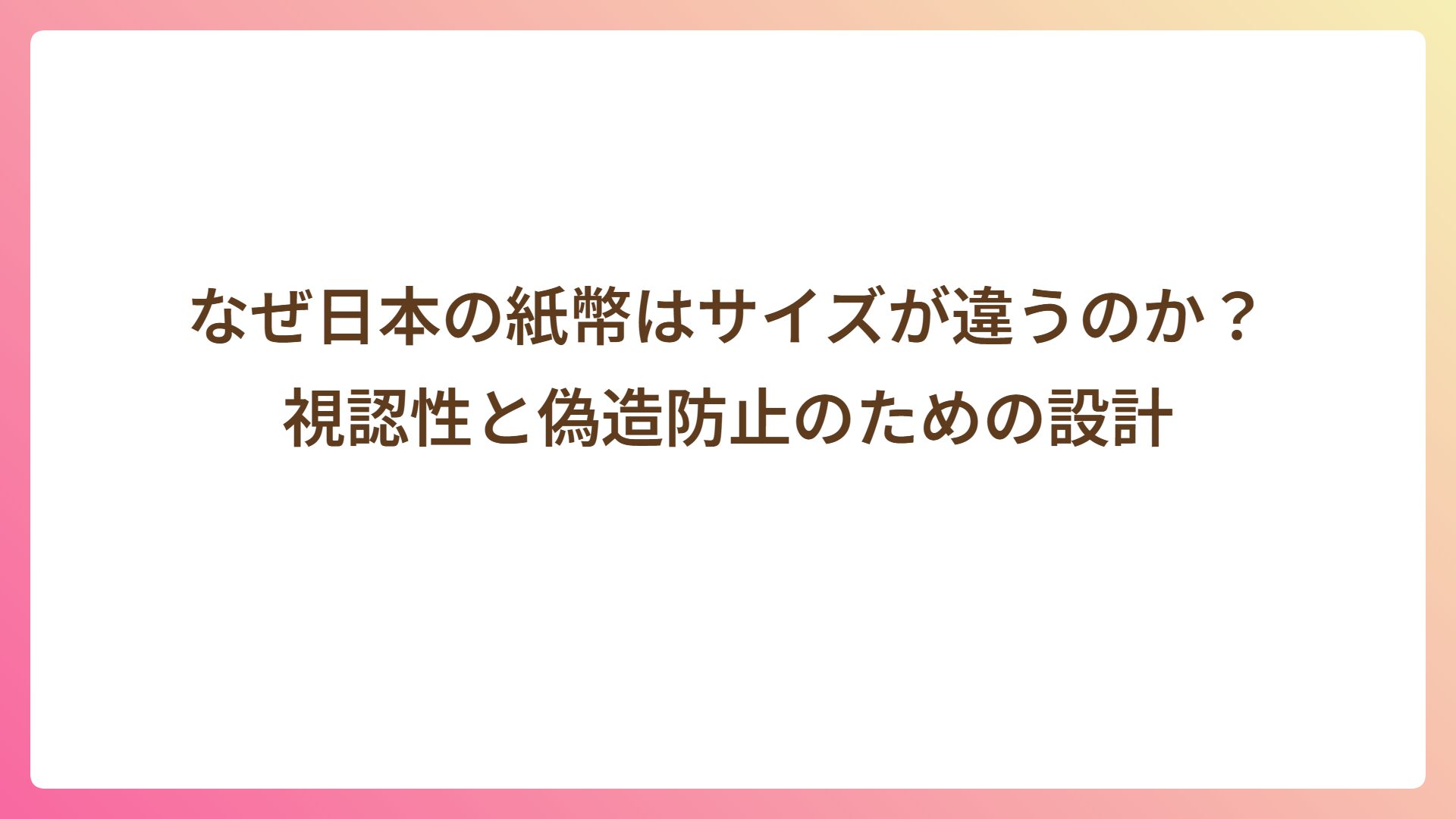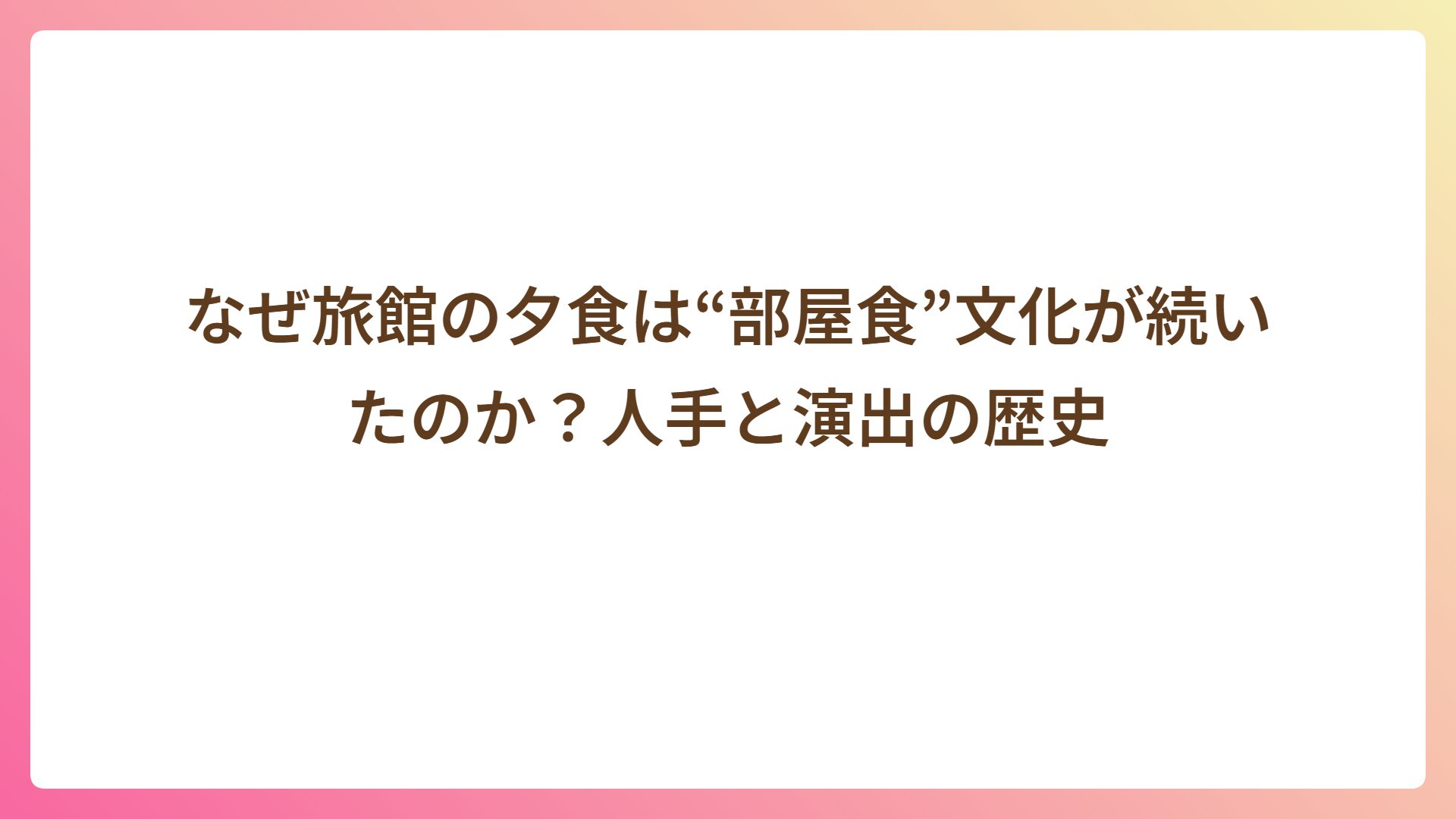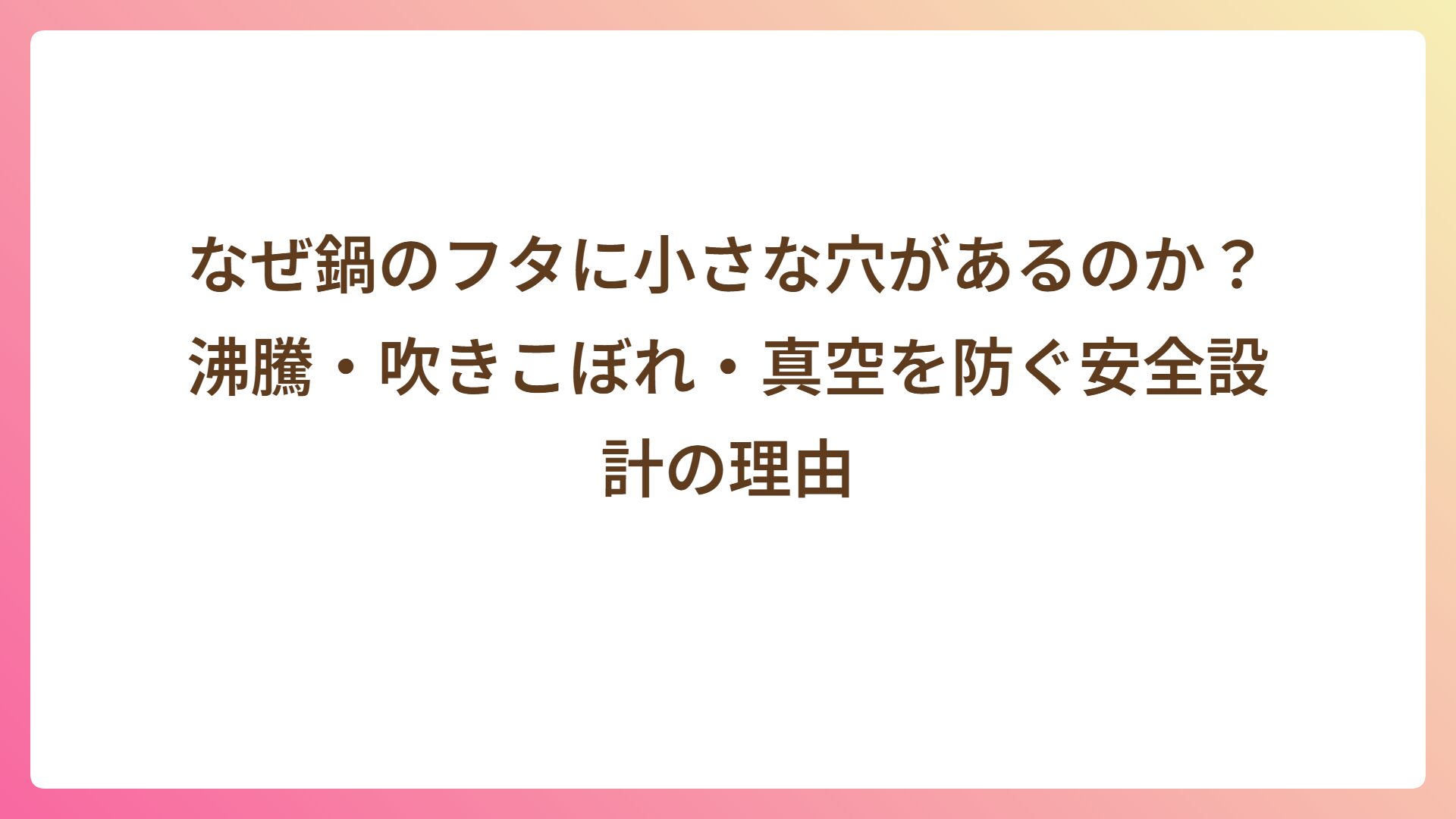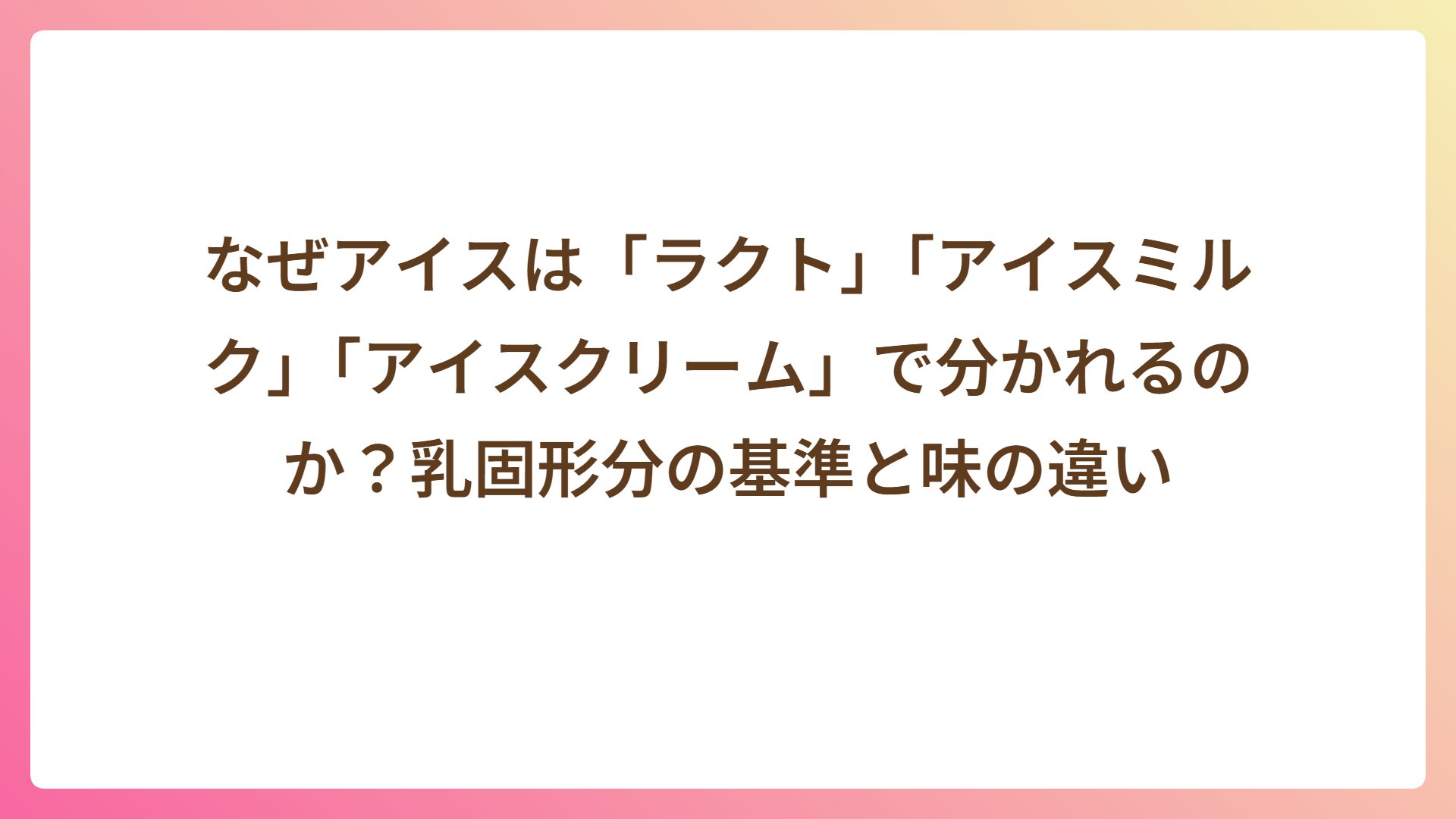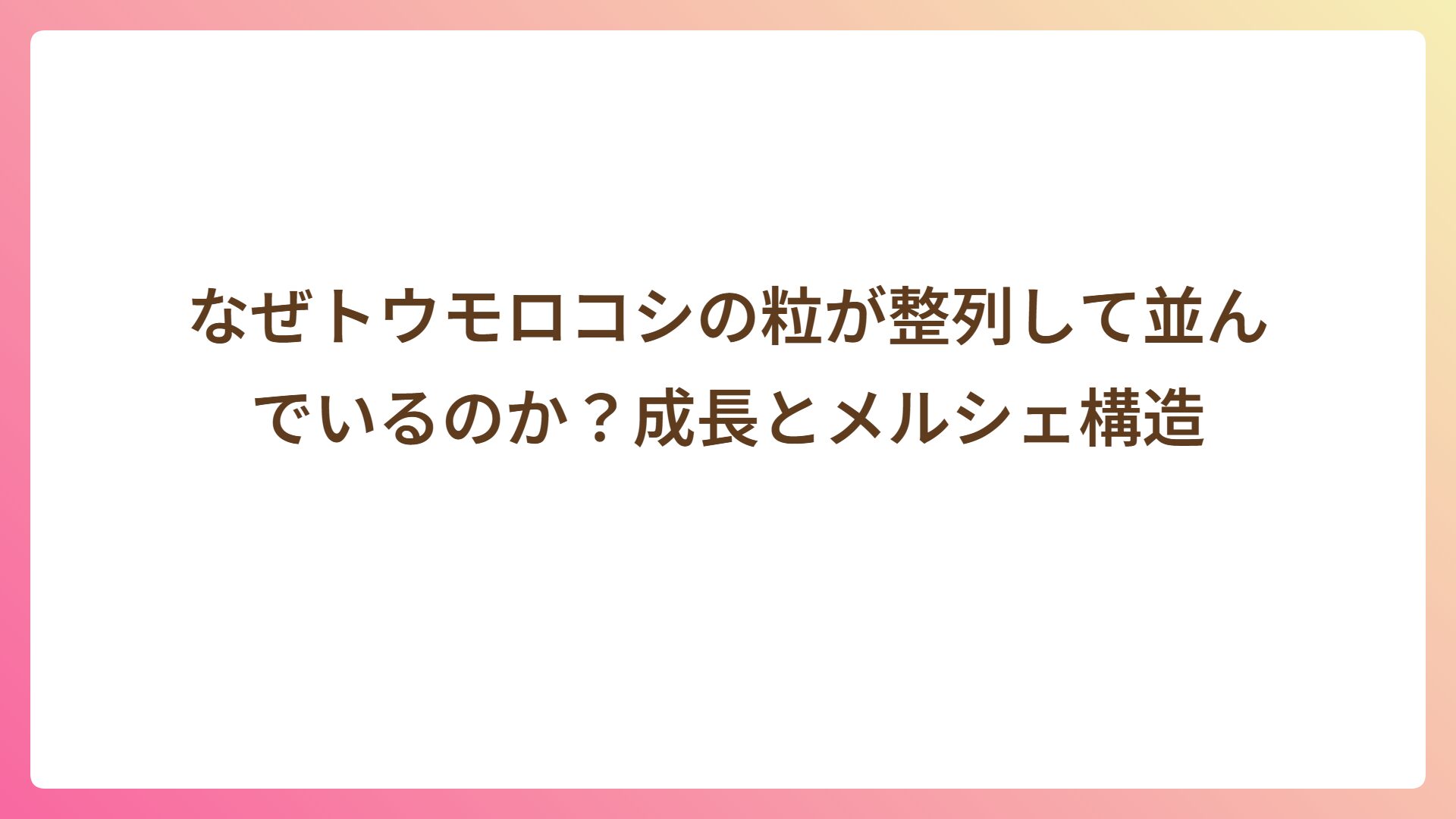なぜ東京だけ「警視庁」?警察庁との違いと名称のルーツを解説

ニュースやドラマ、小説などでよく見かける「警視庁」と「警察庁」。名前は似ていますが、実は全く異なる役割を担う組織です。
この記事では、それぞれの違いをわかりやすく整理し、「なぜ東京だけ“警視庁”なのか?」という疑問にも答えます。
警視庁は東京都の警察、警察庁は全国の調整機関
日本の警察は、各都道府県に「○○県警察」と呼ばれる地方警察が存在し、それぞれの公安委員会の下で地域の治安を守っています。東京都も例外ではなく、都内を管轄する地方警察がありますが、それは「東京都警察」ではなく「警視庁」と呼ばれています。
「警視庁」という名称は、東京都の地方警察本部を指す呼び方で、通常の道府県警察と同じように東京都公安委員会の管轄下にあります。一方、「警察庁」は国家公安委員会の下にある中央官庁で、全国の警察組織を調整・統括する国の機関です。複数県にまたがる広域事件の調整、大規模テロ対策、警察制度の設計などを担っています。
なぜ東京だけ「警視庁」と呼ぶのか?
他の道府県が「県警察」である中、なぜ東京だけが「警視庁」なのか。その由来は、明治時代に遡ります。
当時、ヨーロッパ各国の制度を参考に、内務省直属の首都警察を設けるべきだと提案したのが、警察制度の整備を進めた川路利良(かわじ・としよし)です。彼の建議を受けて、1874年(明治7年)に「東京警視庁」が設置されました。「首都の特別な警察」という意味を込めて、他の地域と異なる名称が採用されたと考えられています。
以降、制度変更や名称の整理を経ながらも、「警視庁」という呼称が定着し、現在に至ります。
誤解されがちな“2つの庁”を正しく理解しよう
「警視庁」と「警察庁」はしばしば混同されがちですが、実際には明確に役割が分かれています。警視庁は東京都内の警察活動を担う地方組織、警察庁は全国の警察を束ねる国の行政機関です。
東京都の警察が「東京都警察」ではなく「警視庁」と呼ばれる背景には、明治時代の制度設計と首都ならではの特別な事情があります。この違いを知っておくと、ニュースや推理小説などで警察組織が登場したときの理解がより深まるはずです。