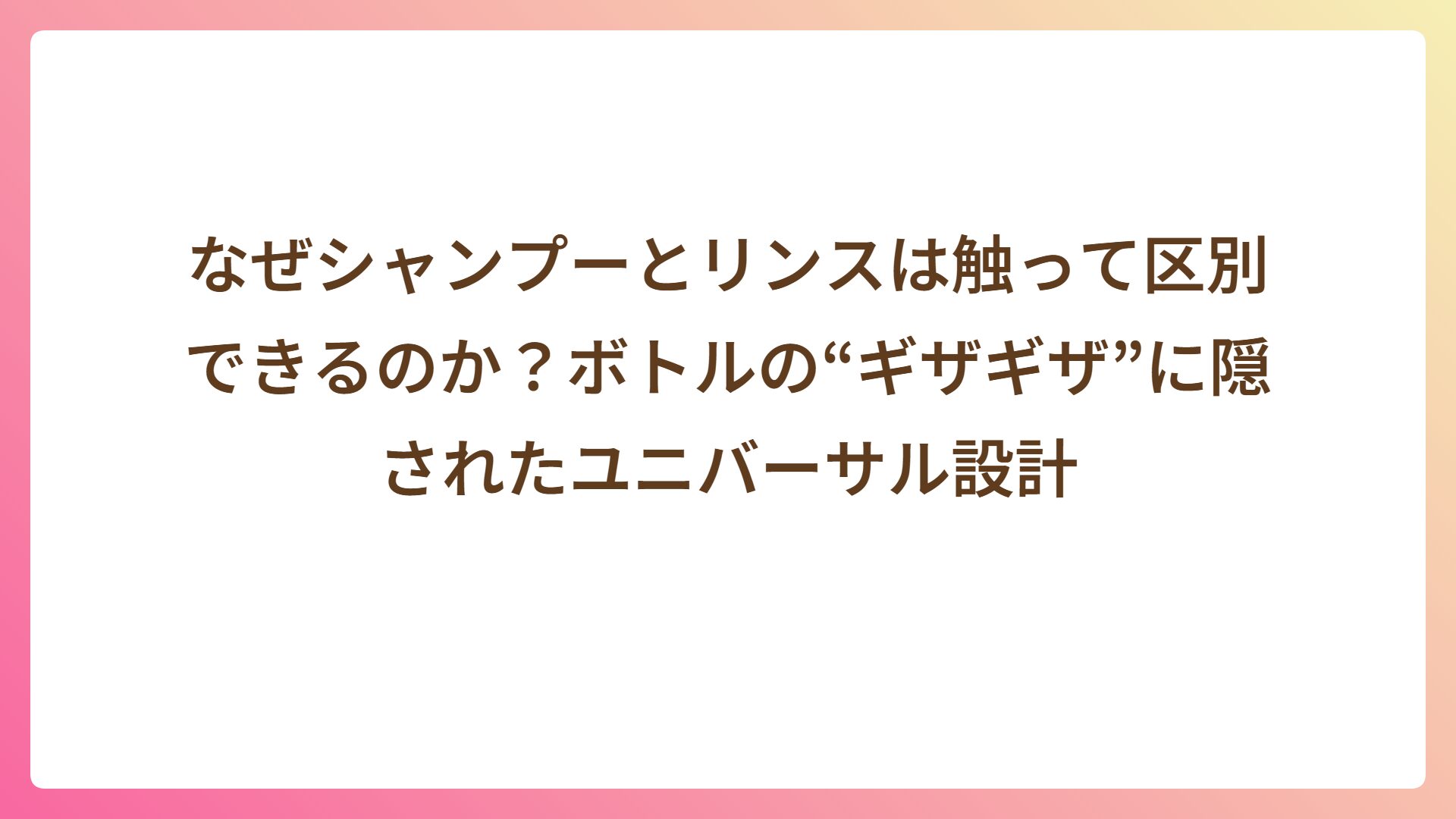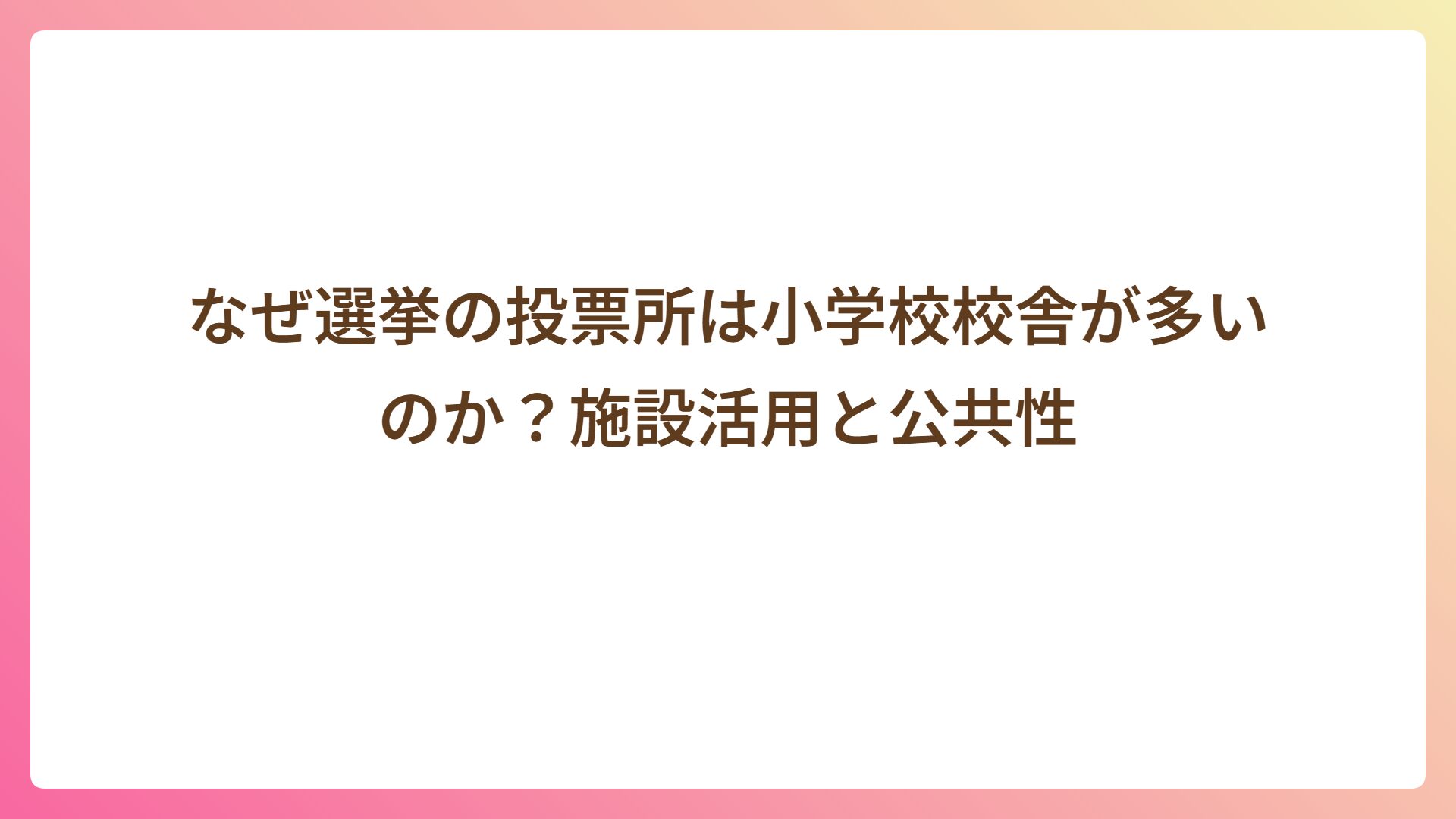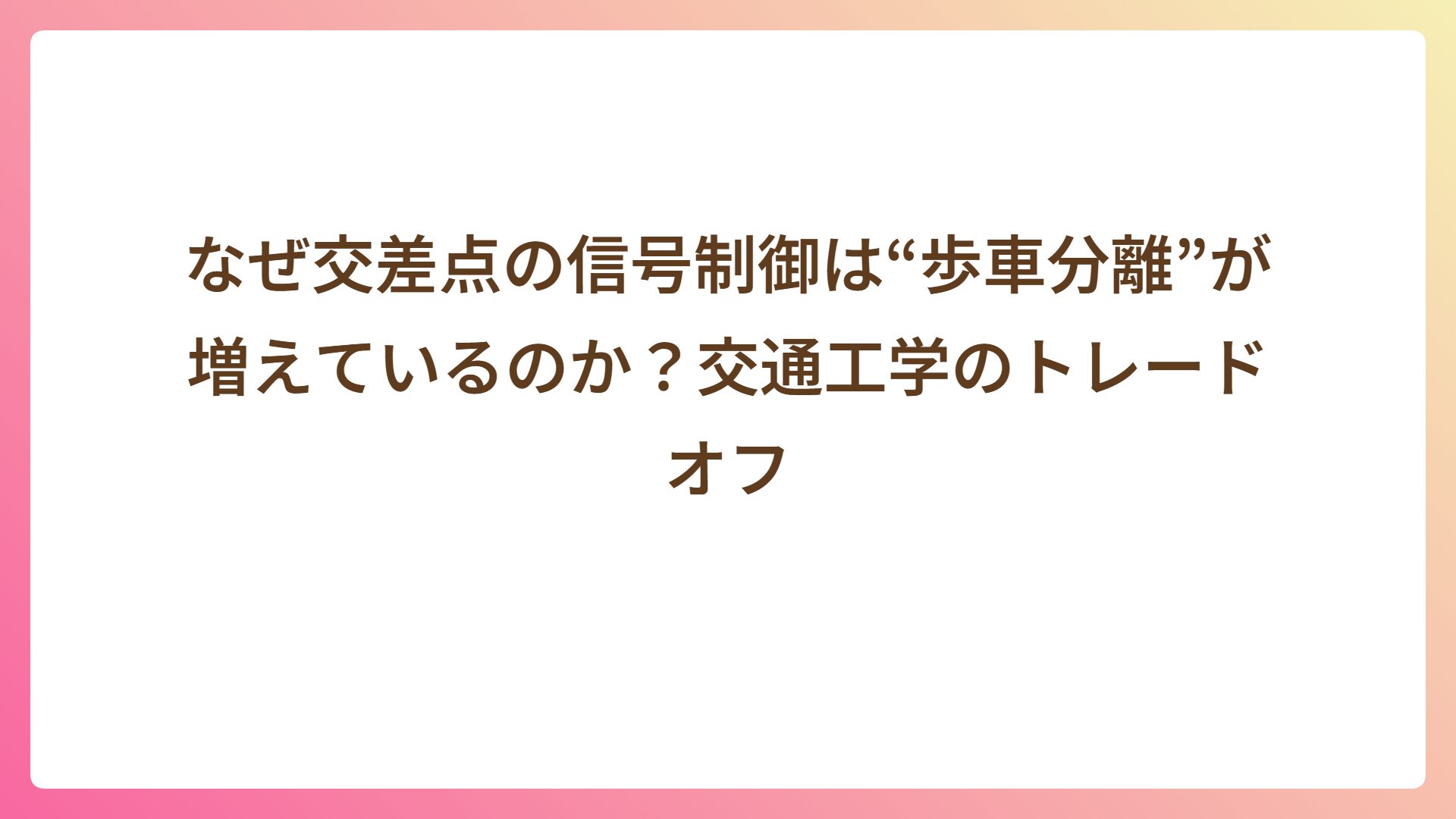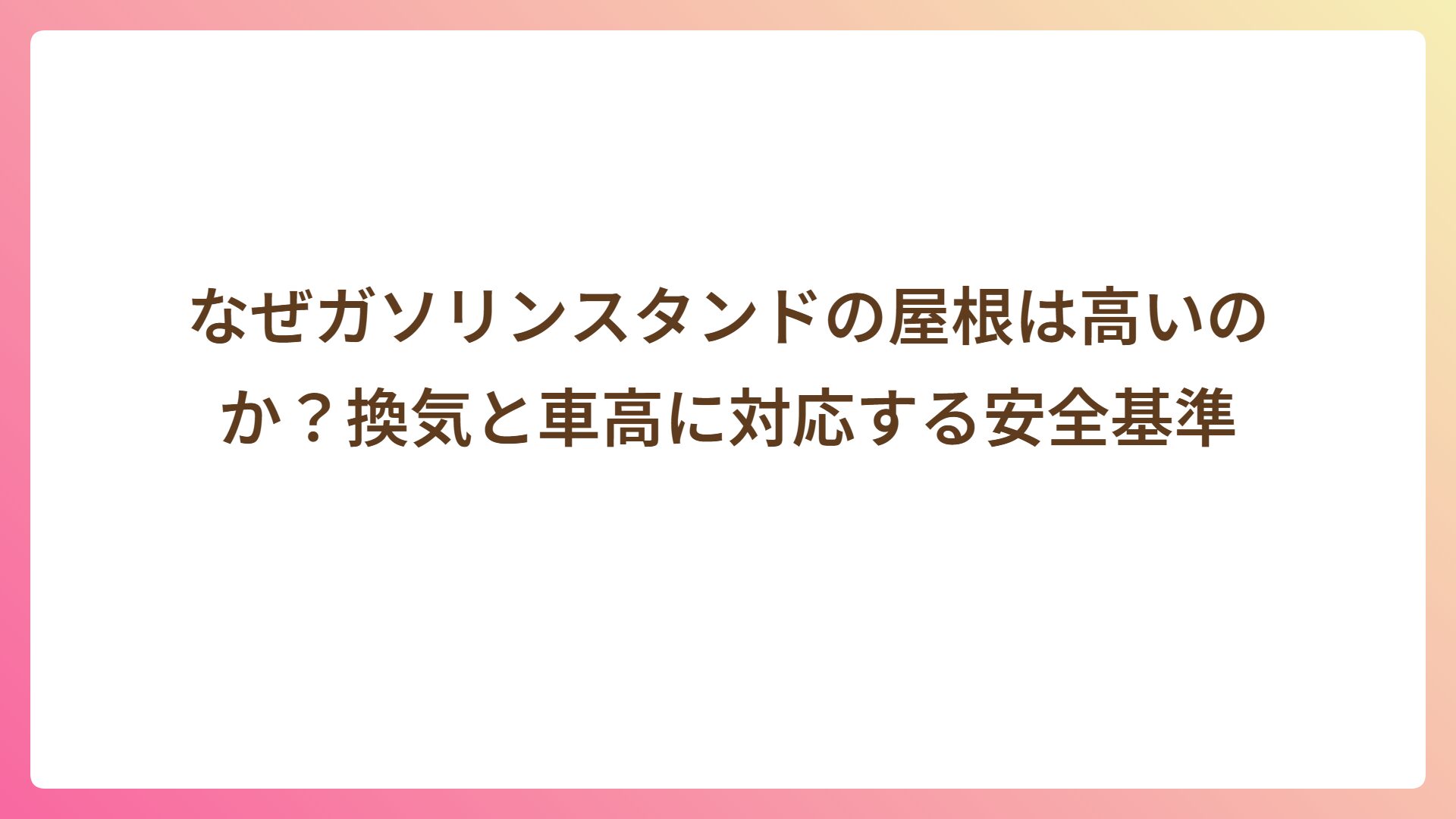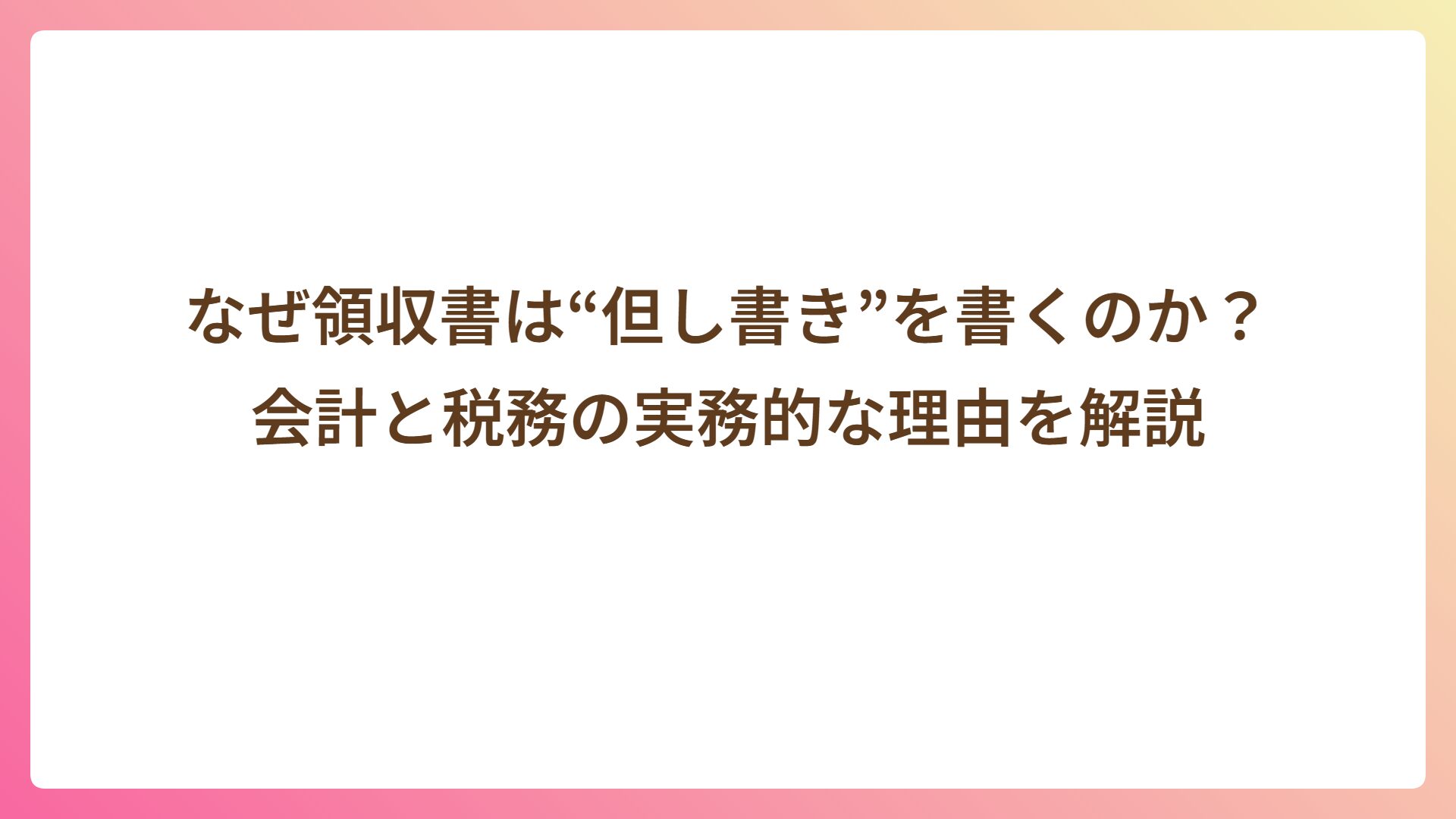季語は誰が決めた?直感とずれる理由と歴史的背景を解説

俳句を詠むうえで欠かせない「季語」。春には桜、秋には紅葉のように、季語は季節感を表す大切な存在です。
ですが、現代人の感覚からすると少しズレて感じる季語も多く存在します。
たとえば「花火」や「七夕」が秋の季語だと聞いて、驚いたことがある方も多いのではないでしょうか?今回は、そんな季語の決まり方と、そのズレが生まれた理由について解説します。
昔の季節の区切り方と暦の違い
季語と現代の季節感がズレている理由のひとつに、「暦(こよみ)」の変化があります。かつての日本では、次のように季節を3カ月ごとに分けていました。
- 春:1月〜3月
- 夏:4月〜6月
- 秋:7月〜9月
- 冬:10月〜12月
さらに、明治時代に旧暦(太陰暦)から新暦(太陽暦)に切り替わったことで、季節感がまるごと約1カ月ズレたのです。たとえば、旧暦7月に行われていた「七夕」や「花火」は、新暦では8月上旬頃。これは新暦での季節区分では「秋」にあたるため、これらが秋の季語とされているのです。
季語は誰が決めているのか?
「季語って誰が決めたの?」という疑問に対する答えは、意外と曖昧です。
季語は基本的に「歳時記(さいじき)」と呼ばれる季語のカタログに基づいて使われます。この歳時記こそが、季語を決める役割を果たしてきたといえます。
たとえば、平安時代の歌人・源俊頼は「月」を秋の季語と定めました。それ以降、連歌、俳諧、俳句へと文化が発展するにつれ、季語も増えていき、時代や地域ごとに変化を続けています。
つまり、季語は誰か一人が絶対に決めているわけではなく、その時代の文化や風習を反映した集合知として成立してきたのです。
現代の感覚で使ってもよい?
実は、俳句を近代に確立したとされる正岡子規は、「歳時記よりも実情を優先すべき」と述べています。つまり、厳密なルールに縛られるよりも、自分が感じた季節感や現実の出来事に基づいた表現の方が、より良い俳句になるという考え方です。
この考え方に従えば、たとえば「花火」を夏の季語として使うことも間違いとは言えません。歳時記はあくまでも参考であり、すべてを固定的に捉える必要はないのです。
おわりに
「花火が秋の季語」など、季語に対して違和感を持っていた方も、その背景や決まり方を知ると納得できたのではないでしょうか。
季語は過去の文化や暦によって形づくられたものですが、現代の生活や感覚に合わせた自由な表現もまた、俳句の魅力のひとつです。歳時記を参考にしつつ、のびのびと自分らしい俳句を詠んでみてくださいね。