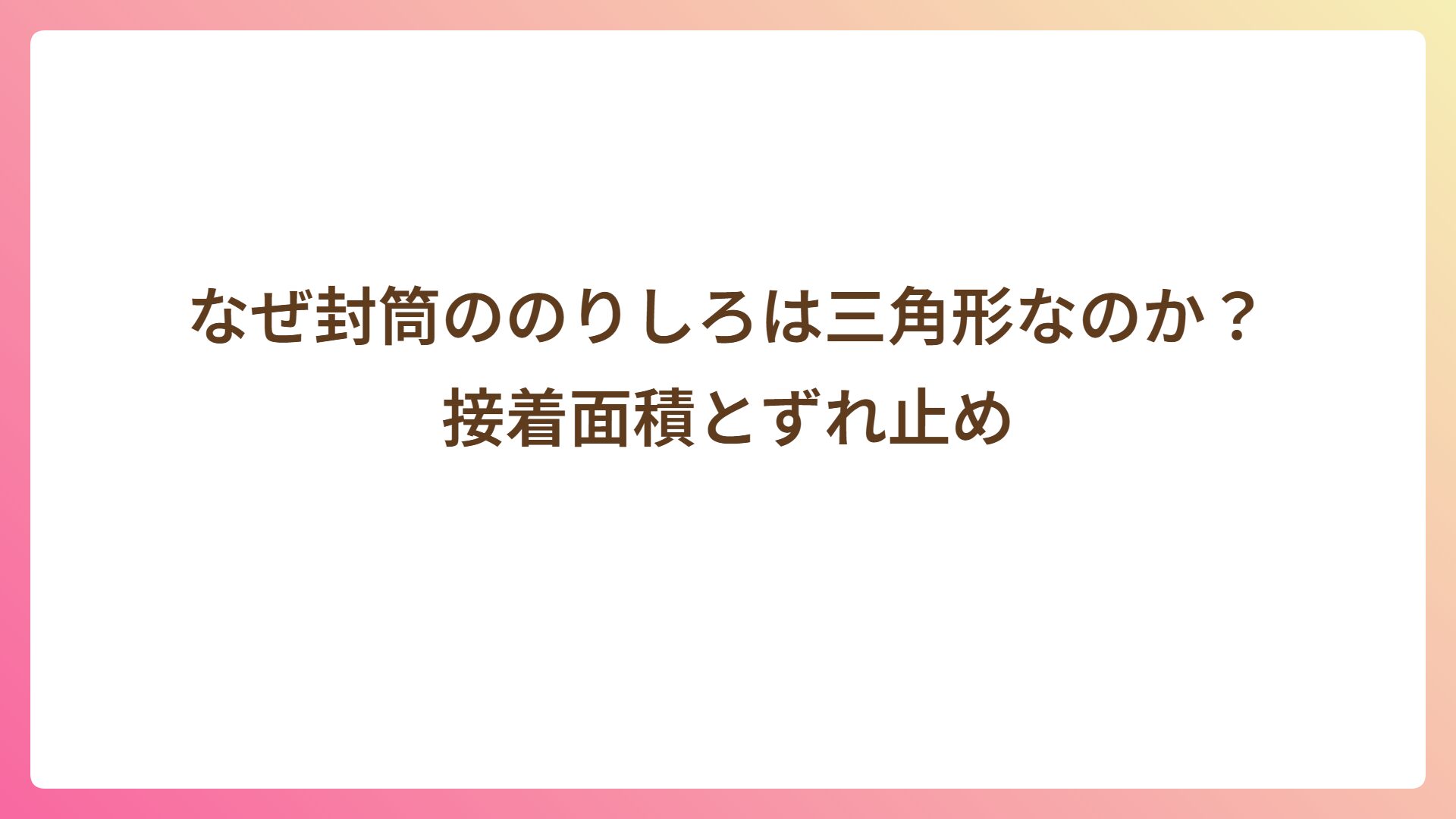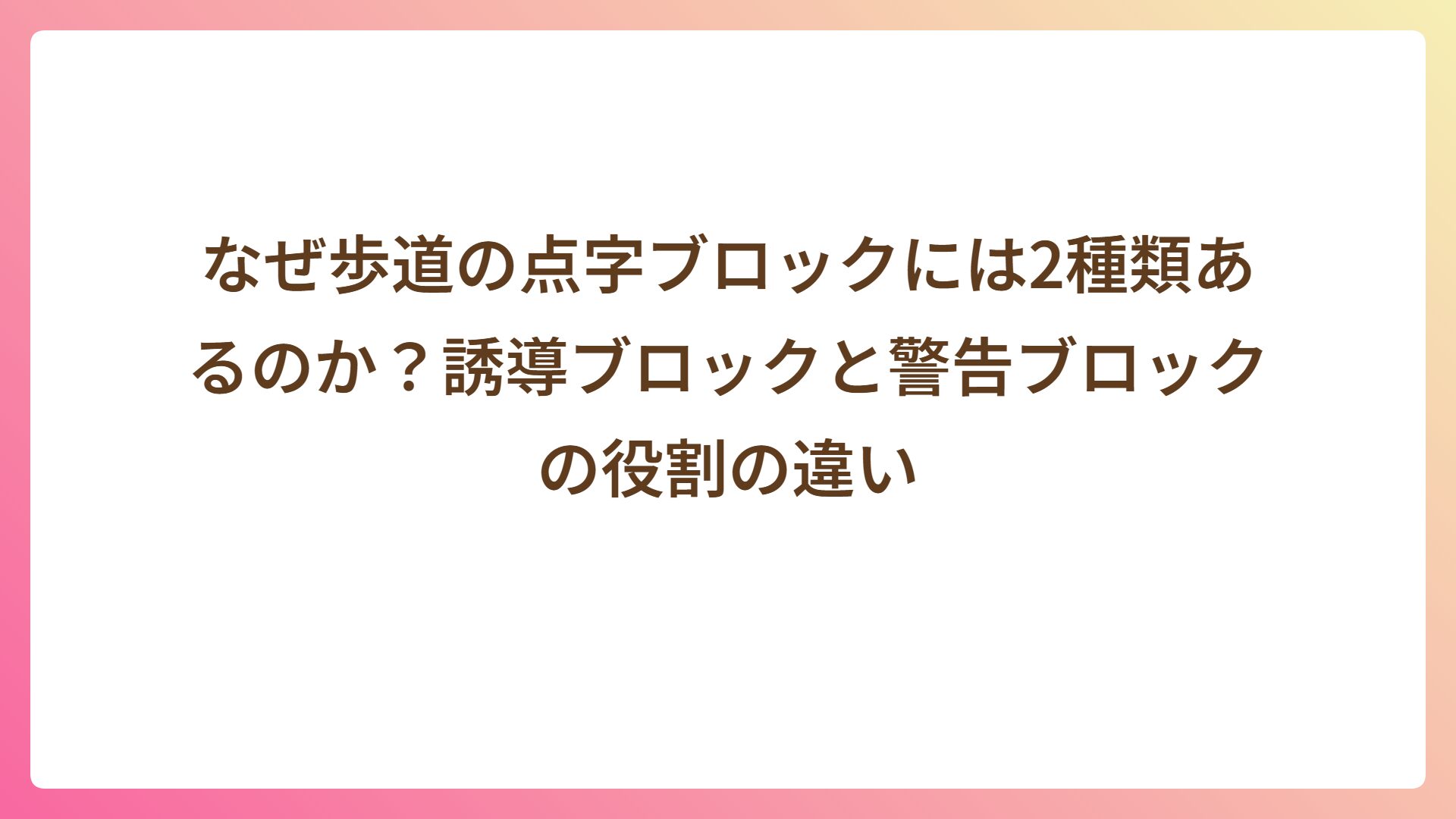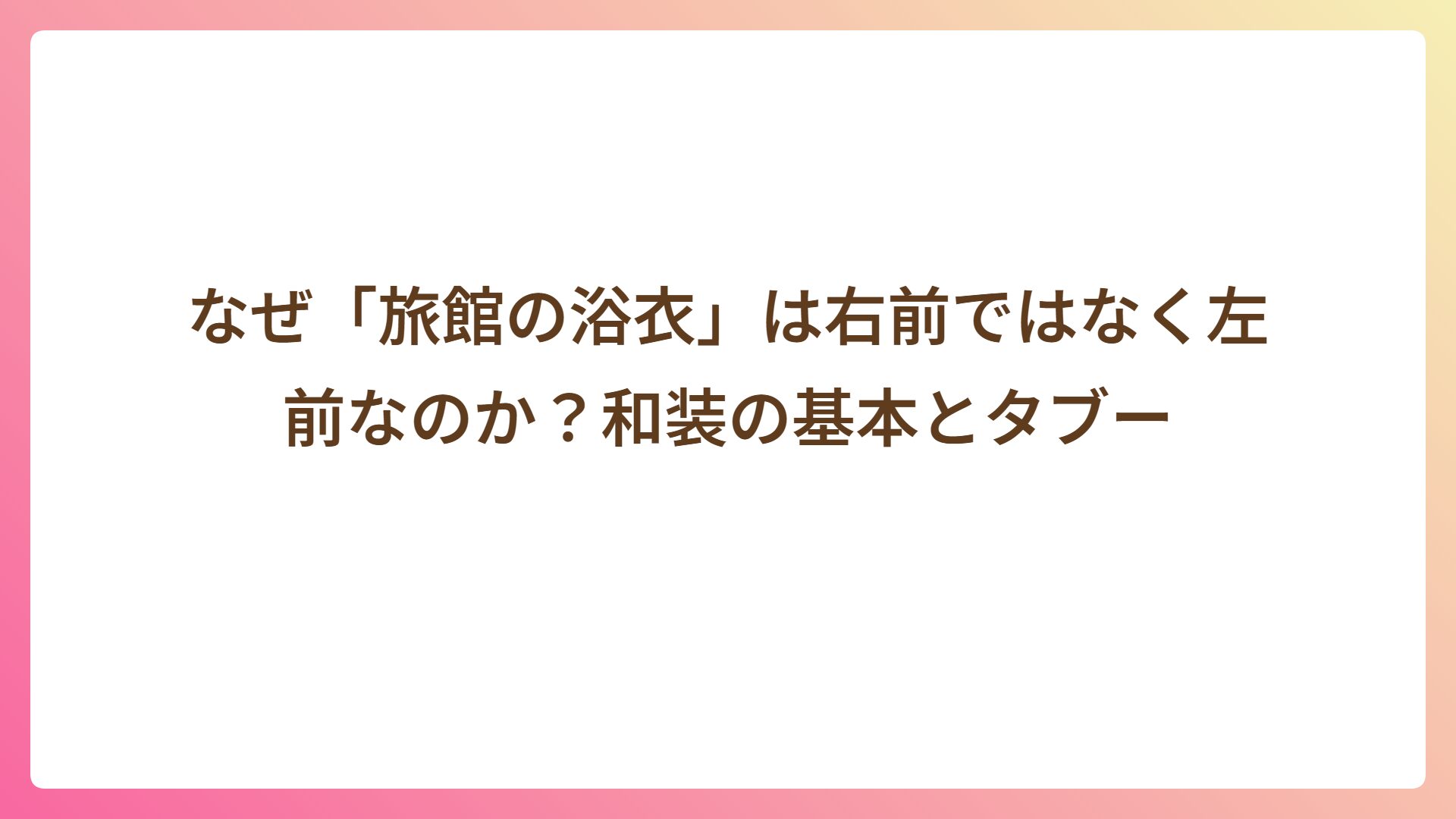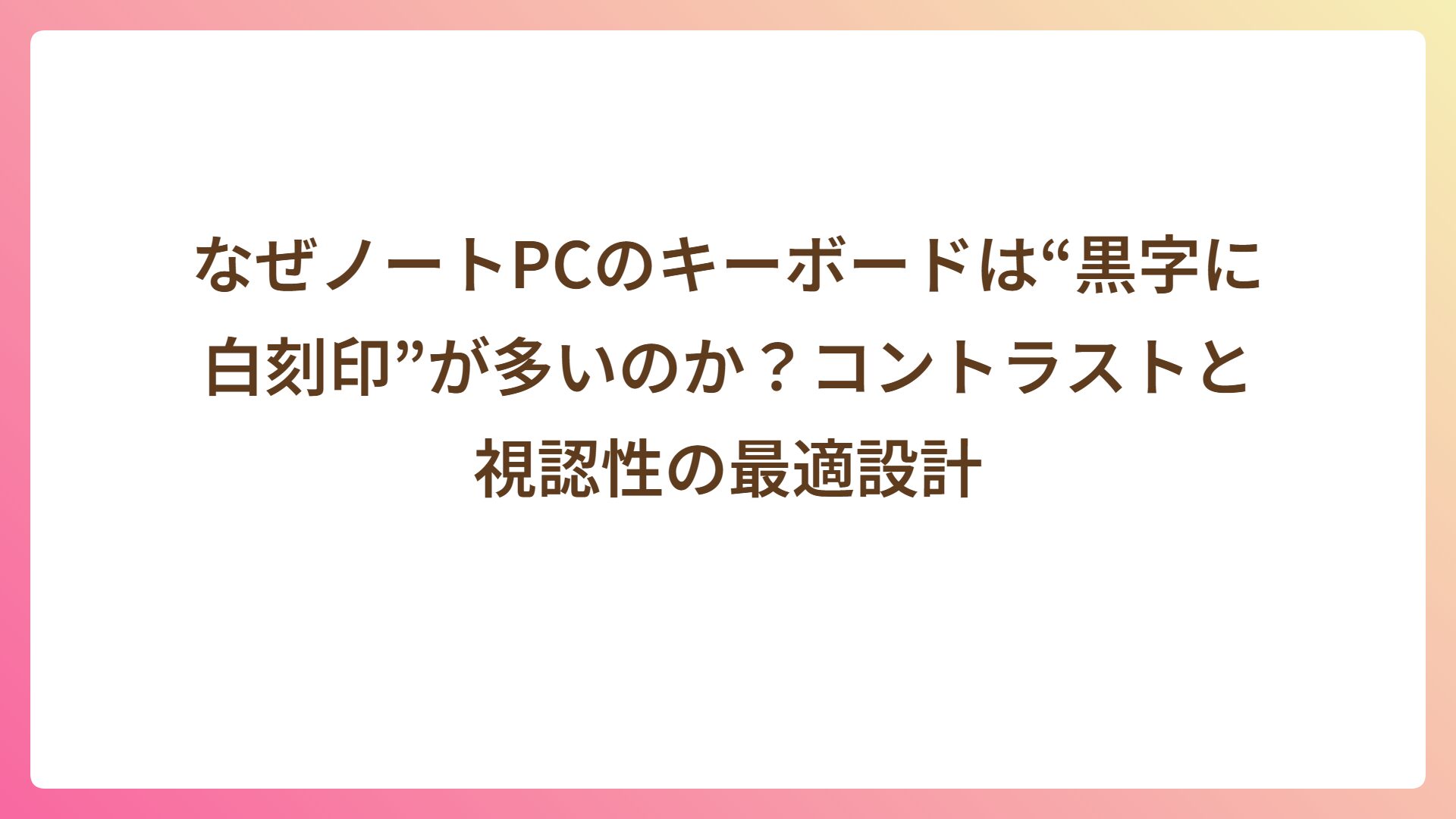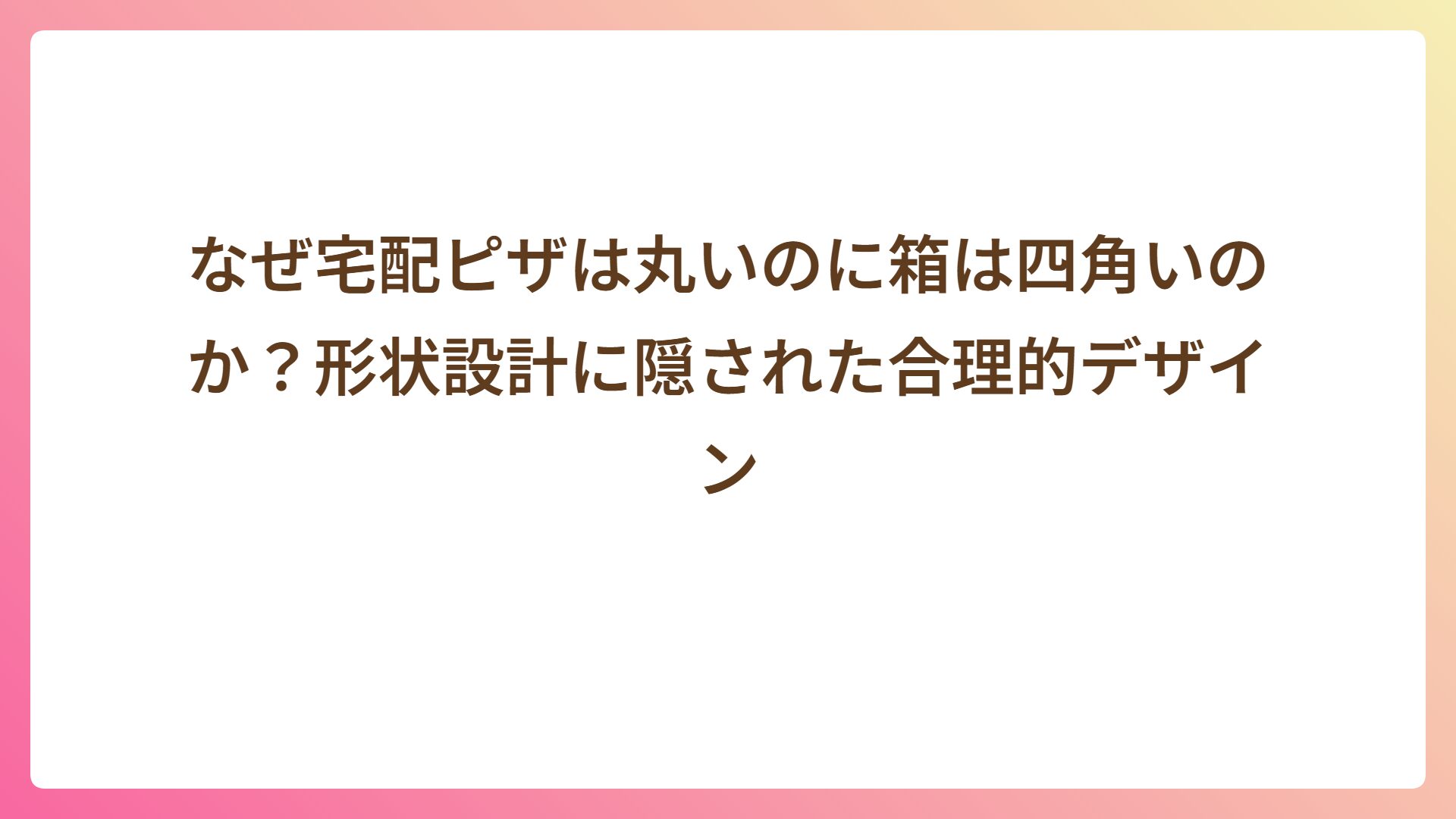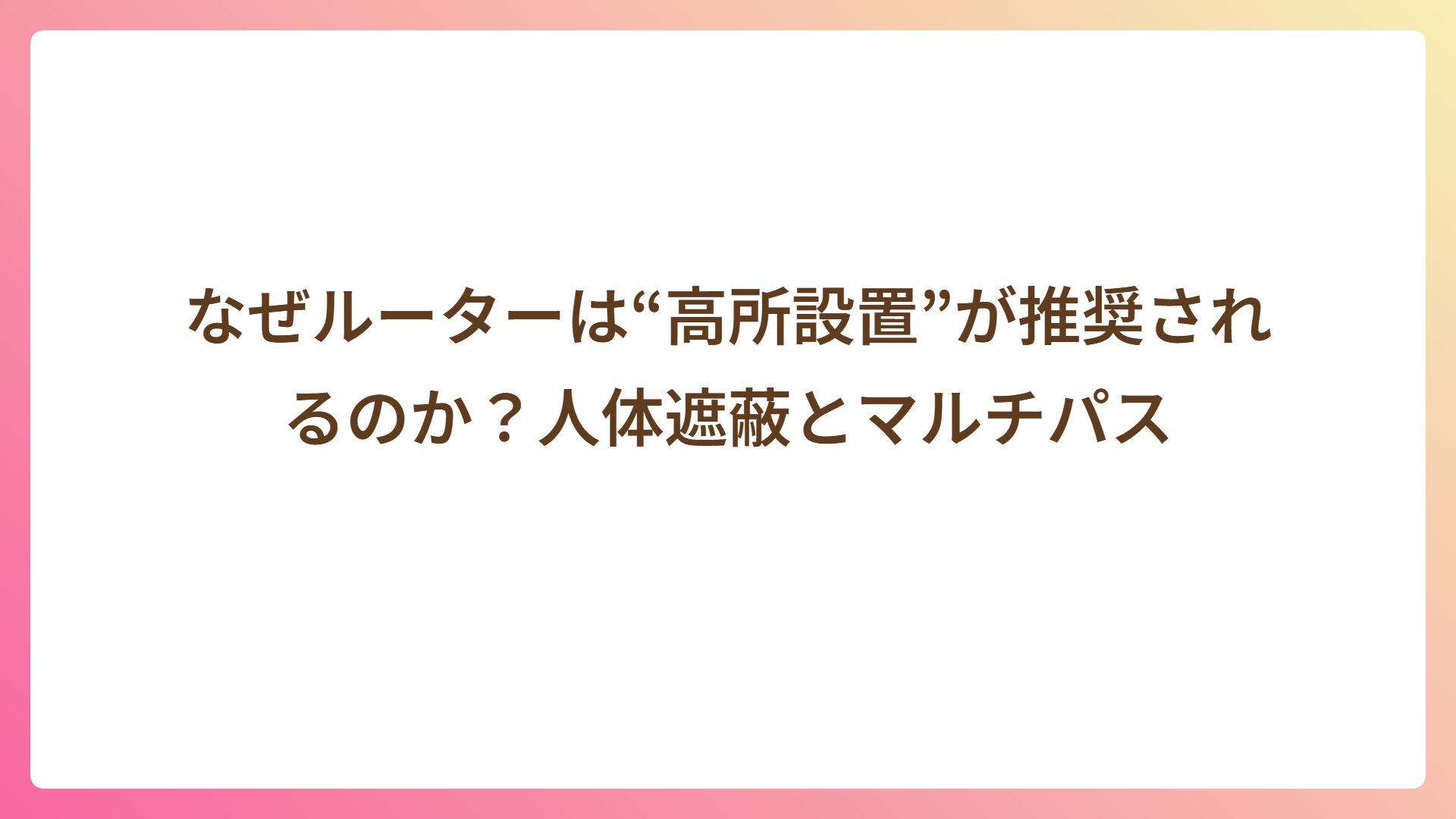なぜ機内でペットボトルが“ペコペコ”になるのか?気圧と容器剛性の関係
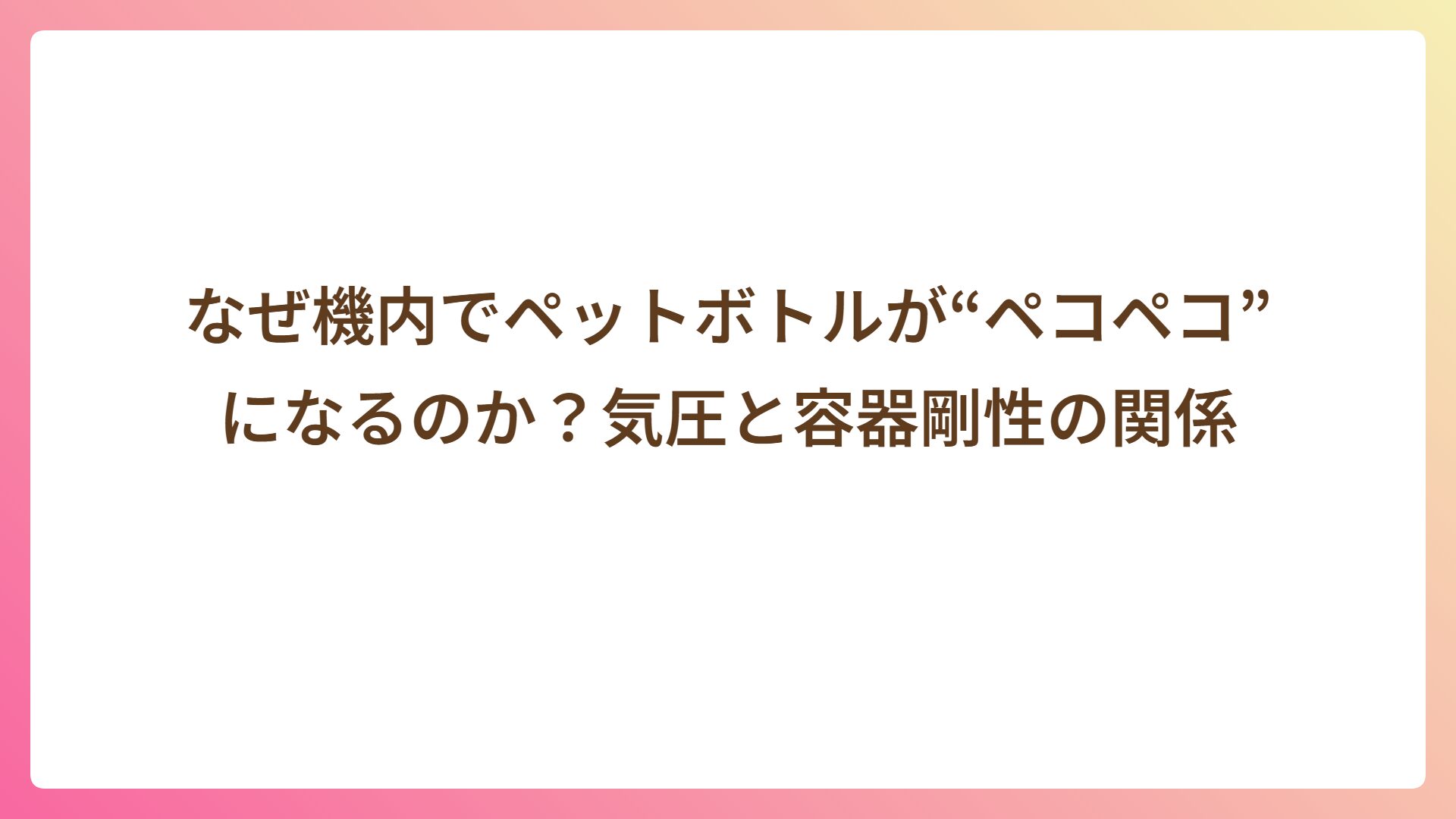
飛行機に乗ると、離陸後にペットボトルがペコペコへこむことがあります。
「気のせいかな?」と思いきや、着陸後には元に戻る――。
これは偶然ではなく、機内の気圧とペットボトルの構造が生み出す物理現象です。
この記事では、気圧変化によってなぜペットボトルが変形するのか、その仕組みを科学的に解説します。
機内は「地上より気圧が低い」
飛行機が高度1万メートル付近を飛行しているとき、外気圧はおよそ0.2気圧(地上の約1/5)しかありません。
そのままでは人間が呼吸できないため、機内は約0.8気圧(地上の標高2000m程度)に調整されています。
つまり、離陸して機内が安定高度に達すると、
ペットボトルの外側の気圧が下がることになります。
ペットボトル内の空気は“密閉されたまま”
ペットボトルの内部には、飲み物と少量の空気が閉じ込められています。
この空気は出入りできない密閉状態なので、外気圧の変化に追従できません。
- 地上で栓を閉めたとき:内圧=外圧(およそ1気圧)
- 離陸して気圧が下がると:外圧<内圧
このとき、内部の空気が膨張しようとします。
しかしボトルが完全に伸びるわけではないため、外形がわずかに変形し、「パンッ」と張ったような状態になります。
逆に、帰りの便で降下中に気圧が上がると、
外圧>内圧となり、ボトルが「ペコペコ」とへこむのです。
“ペコペコ”は気圧差+ボトルの薄さの組み合わせ
近年のペットボトルは軽量化が進み、わずか20〜25g前後の樹脂(PET)で成形されています。
壁が薄く柔軟にできているため、気圧差を受けると簡単に変形します。
この設計は意図的で、
- 材料コストの削減(環境対応)
- 飲み終わった後につぶしやすい
- 加圧充填飲料でも耐圧性を保てる最小構造
といったバランスを取る結果、“ペコペコしやすい構造”になっているのです。
気圧変化のタイミングと変形の方向
飛行中のペットボトルが膨張したりへこんだりするのは、
- 離陸直後(外圧低下) → ボトルがパンパンに膨らむ
- 着陸前の降下中(外圧上昇) → ボトルがペコペコにへこむ
という順序で起こります。
気圧差は数千メートル級の標高変化に相当するため、
硬い金属容器ならほとんど変形しませんが、柔らかいPET樹脂では形状が目に見えて変わるほど影響を受けます。
“ペットボトルで気圧を感じる”という副産物
実はこの現象、簡易的な気圧計としても利用できます。
飛行機が上昇中にペットボトルが膨らんできたら、機外気圧が下がっているサイン。
逆に降下中にボトルがへこんだら、外圧が上がっている証拠です。
登山や高地ドライブでも、同様にボトルの形がわずかに変化することがあります。
ペットボトルは、身近な“気圧センサー”でもあるのです。
まとめ:ペコペコの正体は“気圧差+柔軟な設計”
飛行機内でペットボトルがペコペコになるのは、
- 機内気圧が地上より低い
- 内部の空気が密閉されている
- ボトルが薄く柔軟な構造になっている
という3つの要素が重なった結果です。
つまり、ペットボトルの“ペコペコ”は不具合ではなく、
気圧の変化を忠実に反映する正常な反応。
軽く押して戻るあの感触こそ、1万メートル上空の空気の薄さを体感している瞬間なのです。