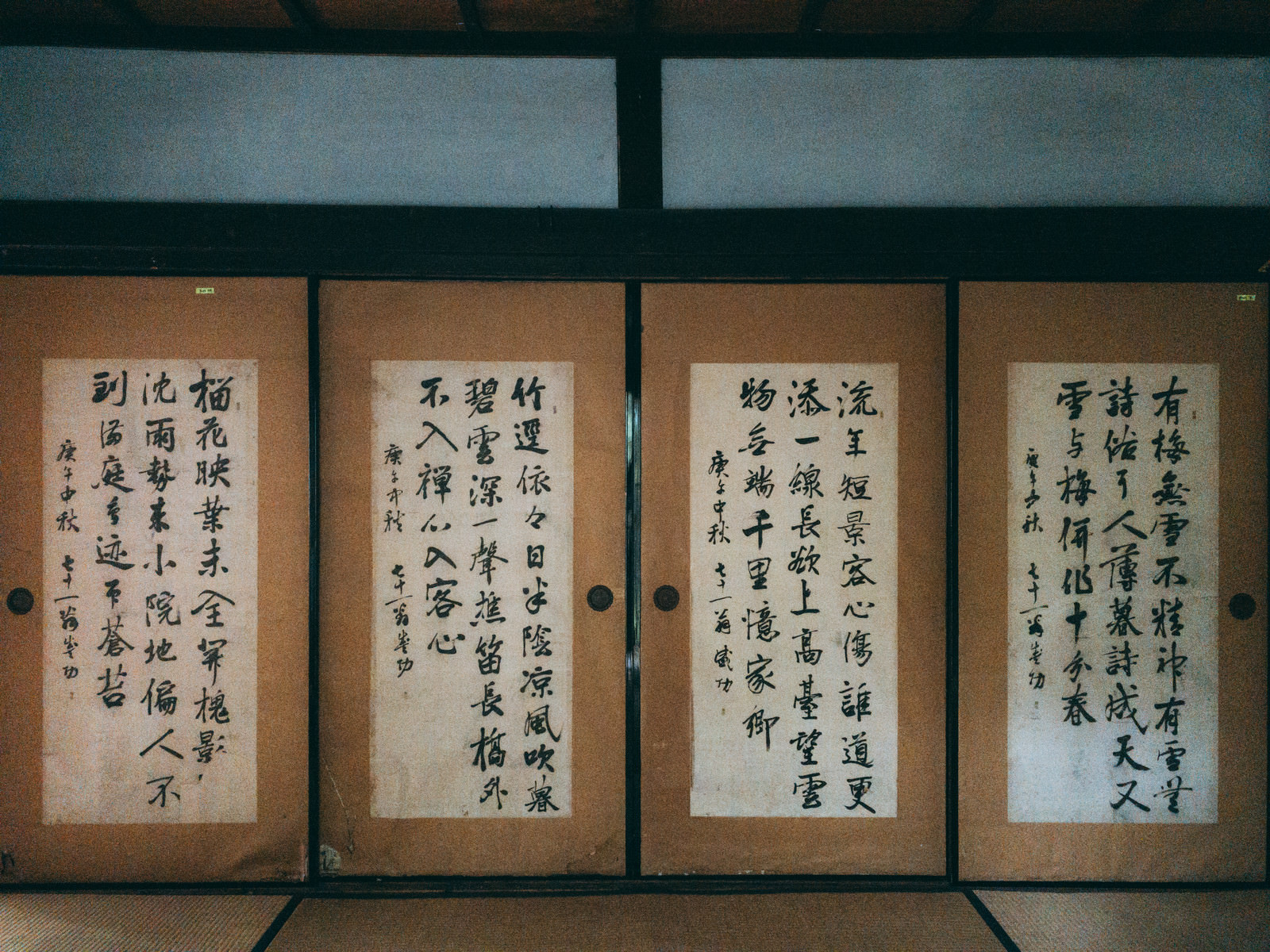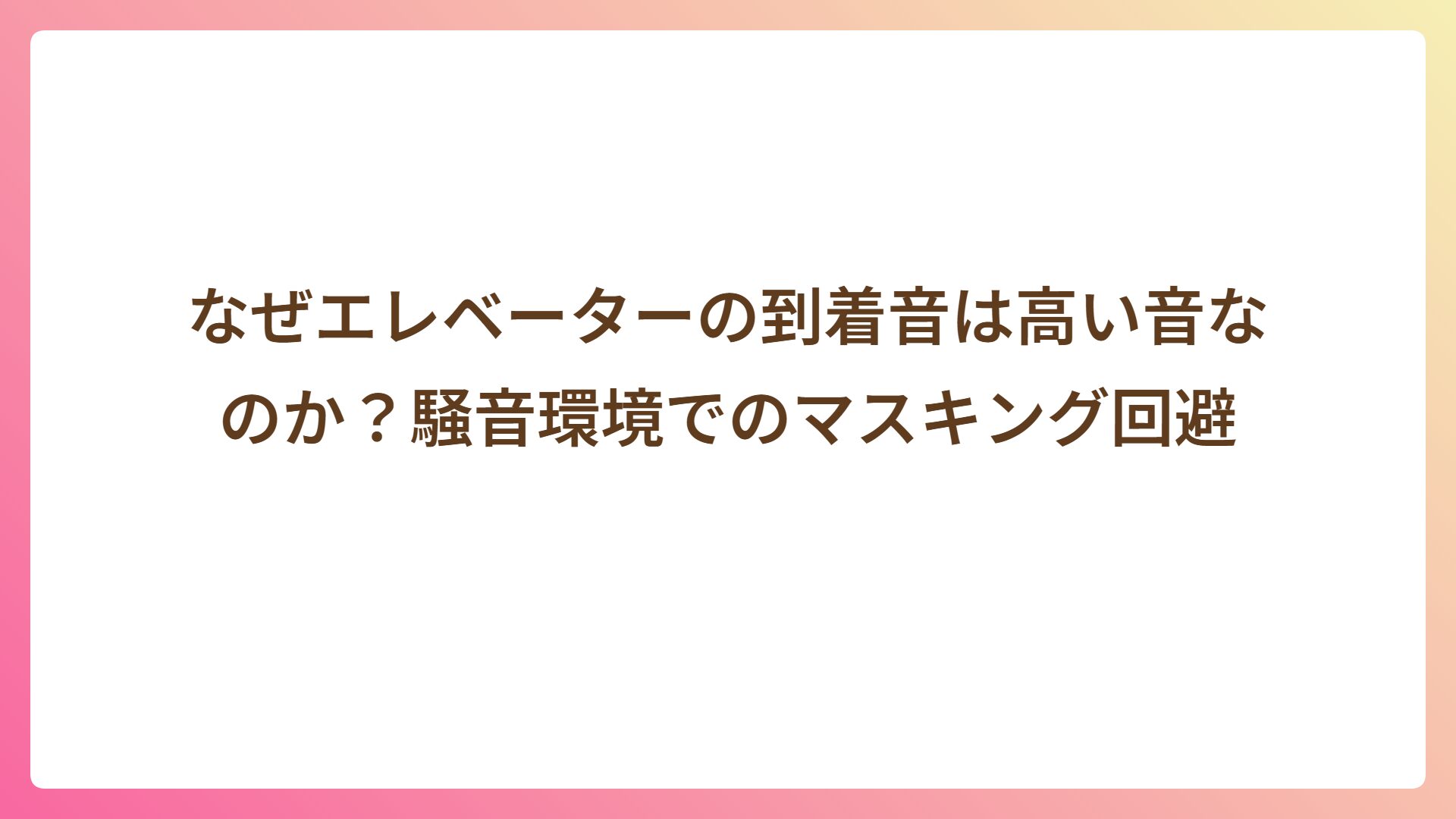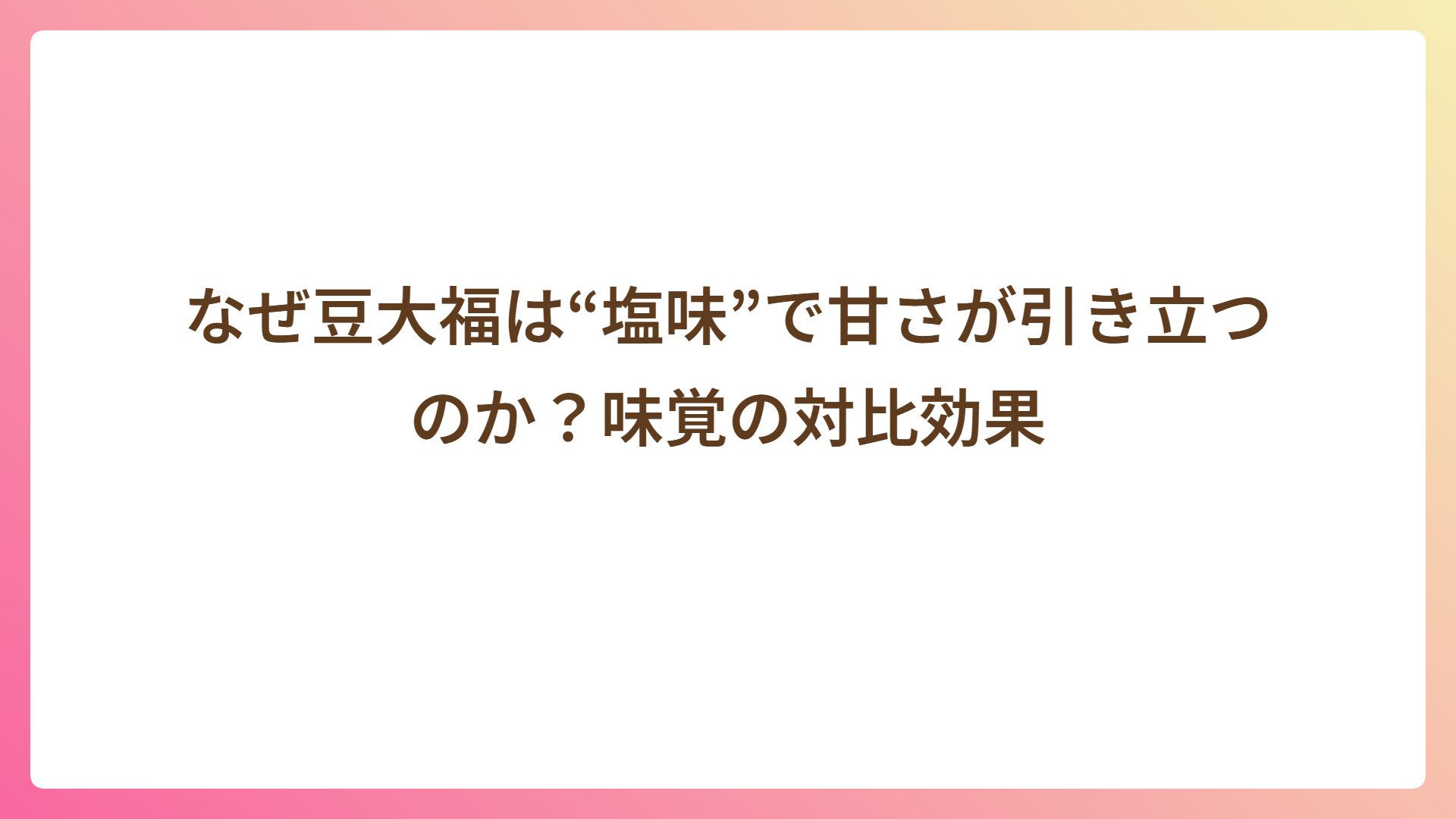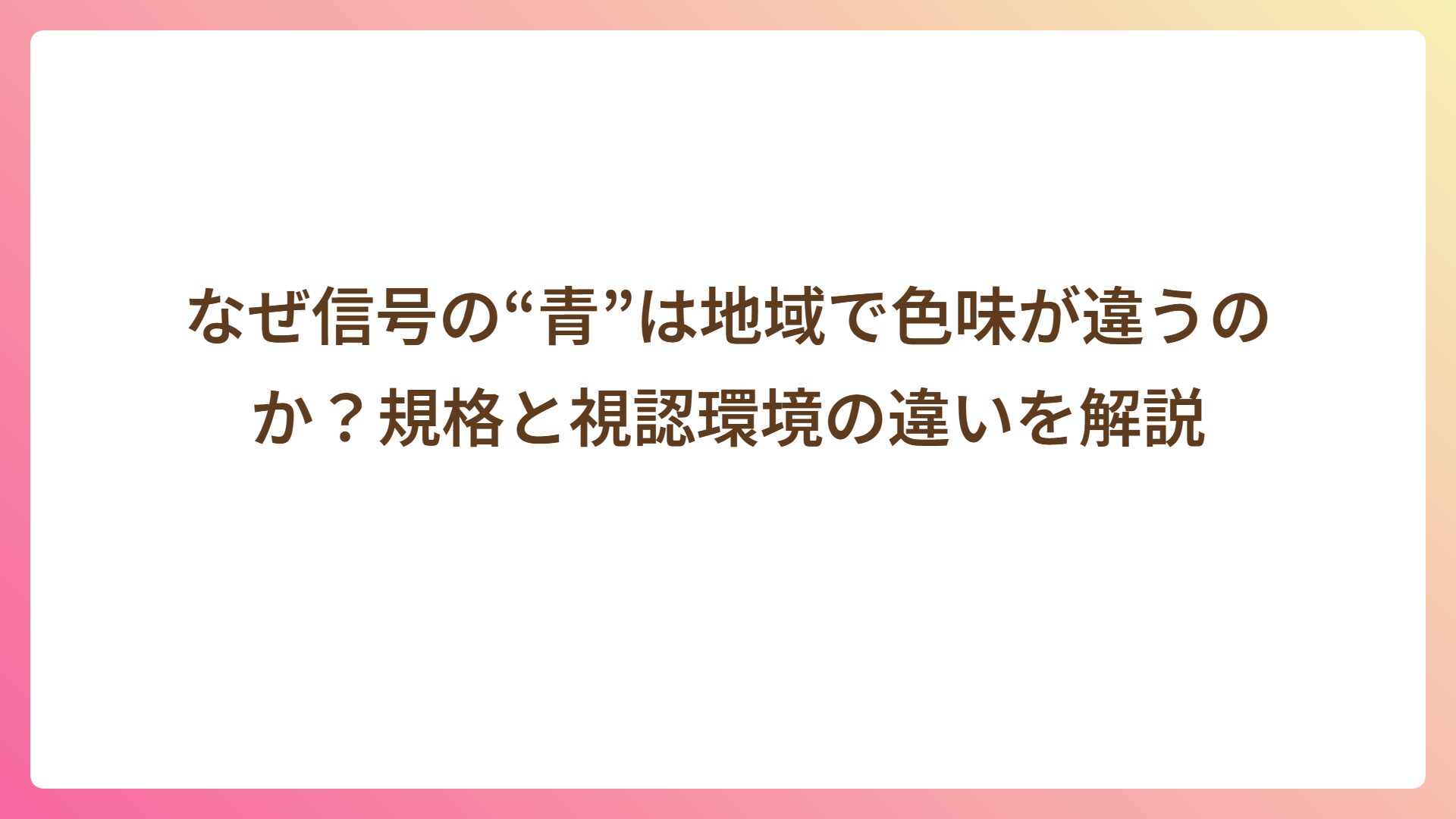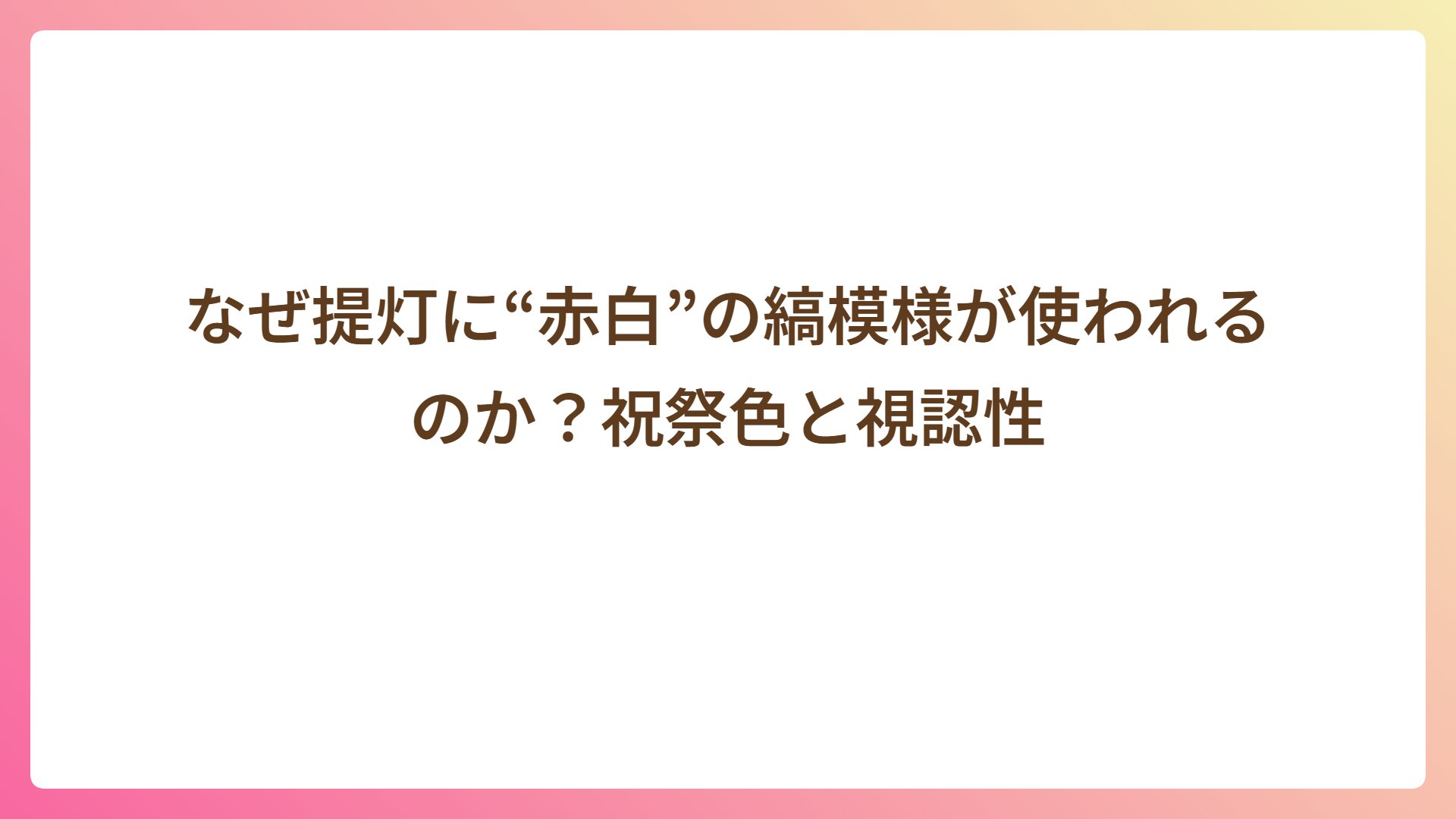なぜ“黒板は緑色”が主流になったのか?目の負担と塗料の進化
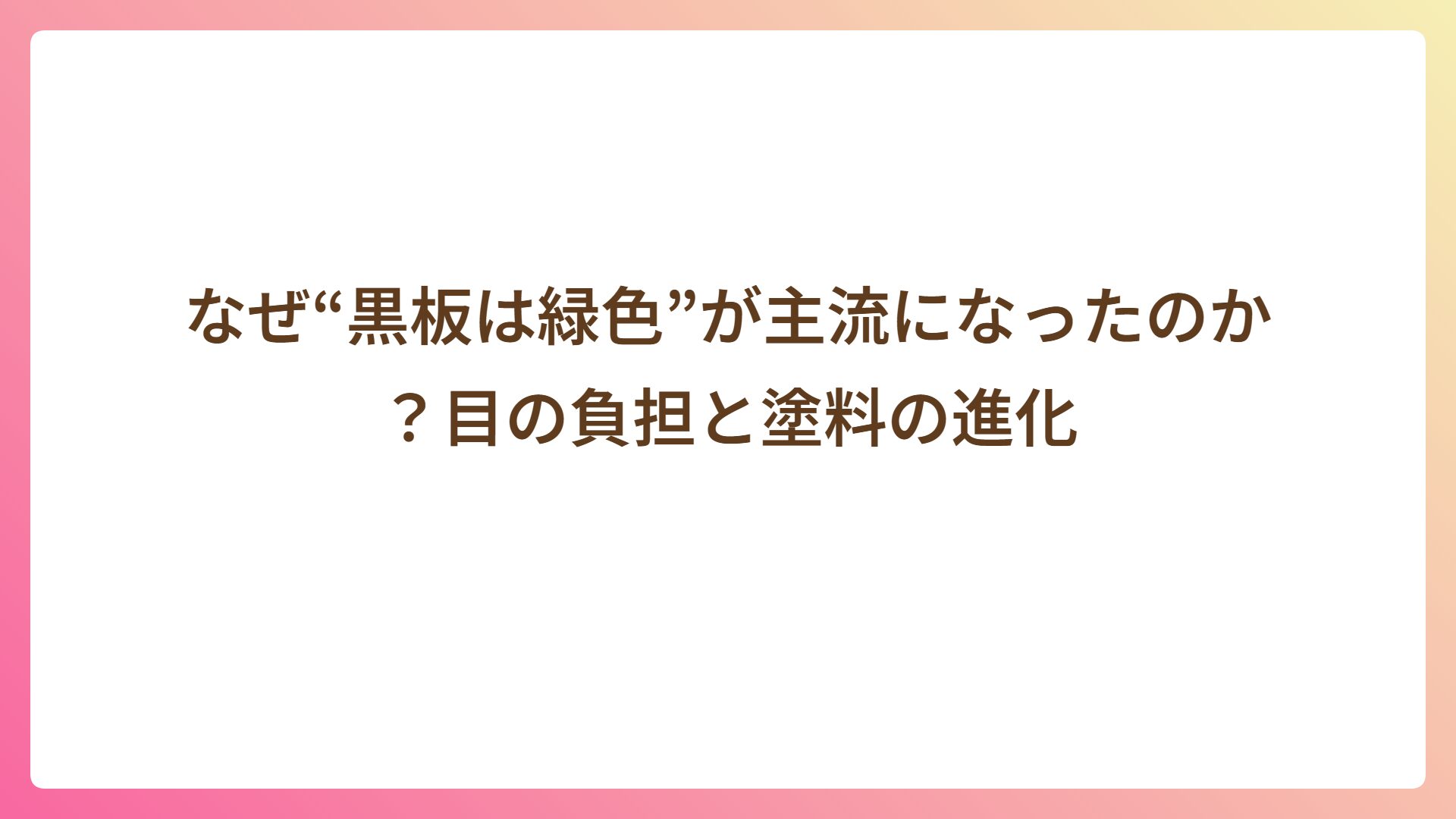
教室といえば、チョークで文字を書く黒板――。
ところがよく見ると、現代の黒板は“黒”ではなく“緑”。
いつの間にか当たり前になったこの色の変化には、
目の疲れ・照明環境・塗料技術の進化という3つの理由が関係しています。
元祖は本当に“黒い板”だった
黒板の起源は19世紀初頭のヨーロッパ。
当時は、天然のスレート(板岩)をそのまま使っており、
その表面が黒っぽかったことから「ブラックボード」と呼ばれるようになりました。
明治期に日本の学校教育が近代化すると、この黒板文化も輸入されます。
当初は本当に“黒”い板が使われ、
チョークの白とのコントラストが高く、文字がくっきり見えるのが特徴でした。
緑色が広まったのは“視力保護”のため
黒から緑への転換が始まったのは、1960年代のこと。
当時の照明技術が蛍光灯中心へと変わり、
強い白色光の下では黒い板がまぶしすぎるという問題が浮上しました。
黒は光を吸収しすぎるため、
チョークの粉が反射して“ギラつき”が生じ、目が疲れやすくなったのです。
そこで研究の結果、人の目に最も優しい色として選ばれたのが**深緑(グリーンボード)**でした。
緑色は可視光の中でも中間波長に位置し、
長時間見ても網膜への刺激が少ないため、
視認性と疲労軽減のバランスが最も良い色とされています。
“白チョークとの相性”が抜群だった
緑の板は、白チョークとのコントラストが柔らかく、
黒板のような強い反射が起こりません。
これにより、長時間の授業でも目が疲れにくく、
黒よりも**「自然な見え方」**が実現できるようになりました。
特に前列と後列の明るさ差が減り、
教室全体で均一に見やすいというメリットがありました。
このため、1965年ごろから教育委員会を中心に全国の学校へ普及していきます。
塗料技術の進化が“色の自由度”を高めた
従来の黒板は木や金属の板に黒い塗料を塗って作られていましたが、
1960年代以降、合成樹脂や特殊顔料を使った塗料が登場します。
これにより、緑や青など複数の色が選べるようになり、
黒一色だった黒板の世界に“色彩設計”の考え方が導入されました。
特に「グリーンボード」は耐久性・書きやすさ・拭き取りやすさが向上し、
教育現場に最適な素材として急速に浸透しました。
さらに磁石が使えるスチール製の黒板が登場し、
**機能面でも進化した“緑の時代”**を迎えたのです。
黒板から“ホワイトボード”への転換もこの流れの延長
やがて1990年代以降、学校やオフィスではホワイトボードが主流になります。
この流れも、目の負担を減らす・反射を抑えるという
「黒から明るい色へ」という思想の延長線上にあります。
ただし、黒板特有のチョークの質感や音、消し跡の味わいは根強く支持され、
現在も多くの学校では“緑の黒板”が現役で使われています。
まとめ:黒板の緑は“目と技術の進化の色”
黒板が緑色になった理由を整理すると、次の通りです。
- 蛍光灯照明の普及で黒がまぶしくなった
- 緑色が目に優しく視認性に優れていた
- 白チョークとのコントラストが自然だった
- 塗料・素材技術の進化で緑色が実現できた
つまり、緑の黒板は教育環境を科学的に最適化した結果なのです。
“黒板は緑”という当たり前の風景は、
子どもたちの目を守り、授業をより快適にするために選ばれた静かなデザイン革新なのです。