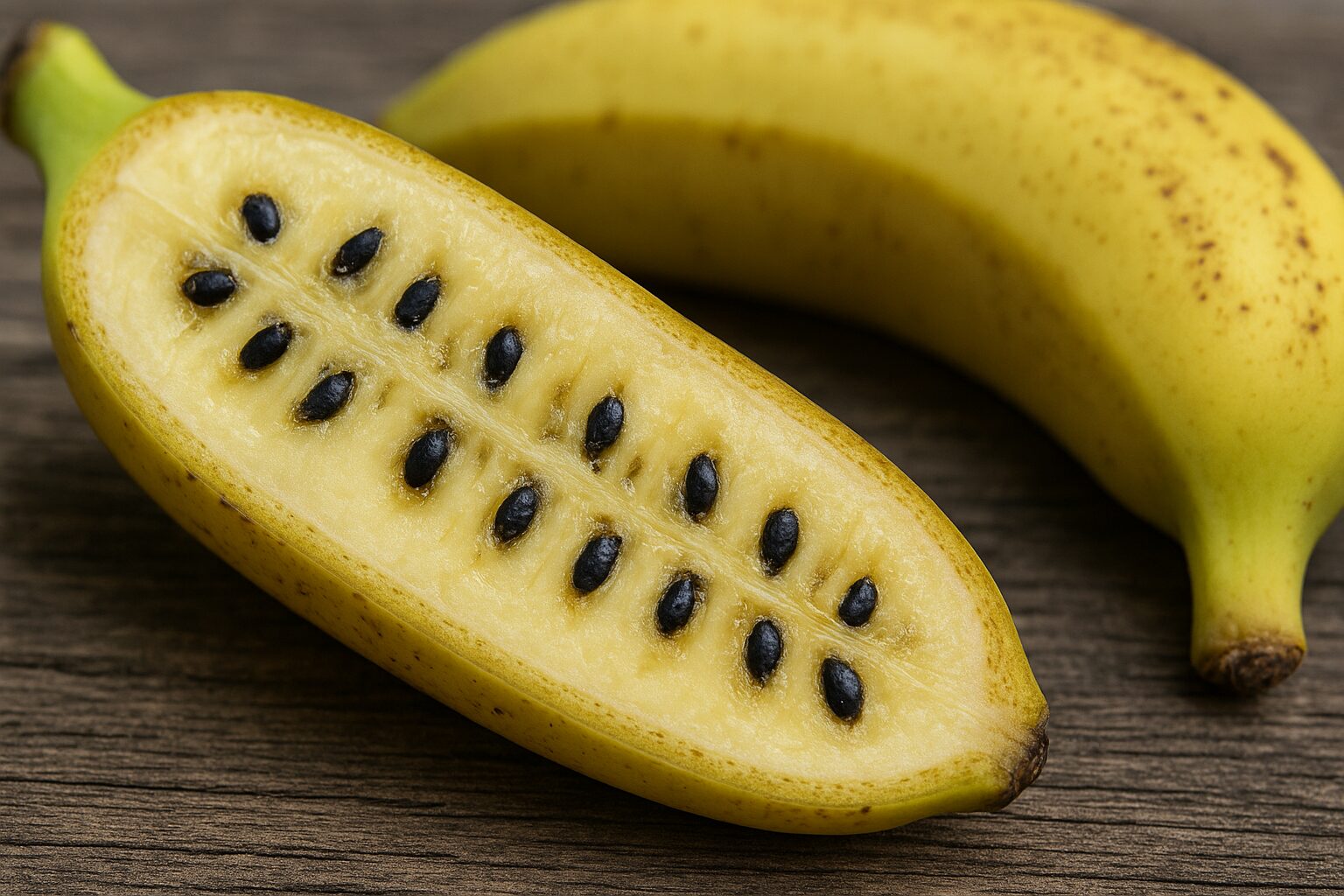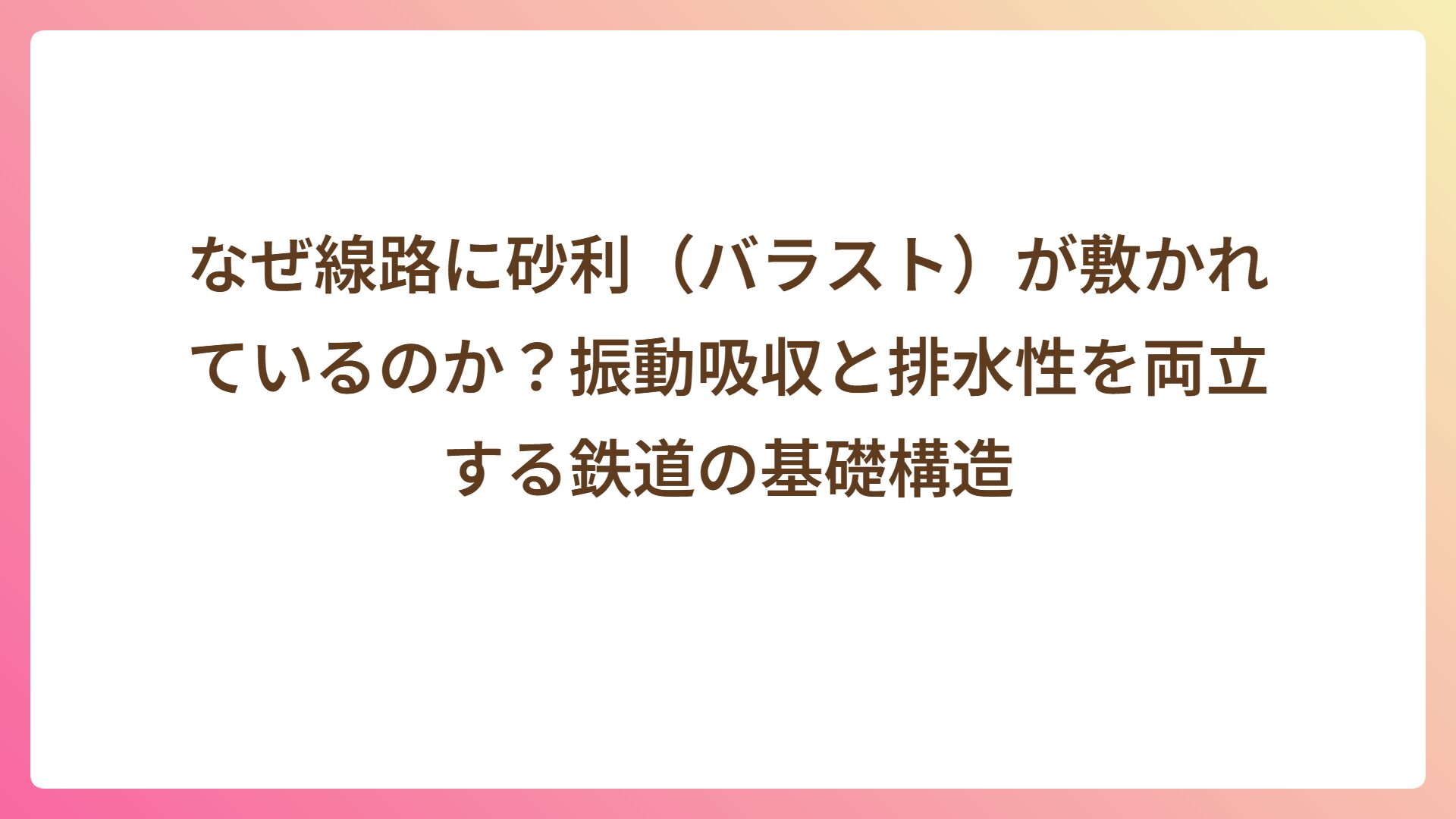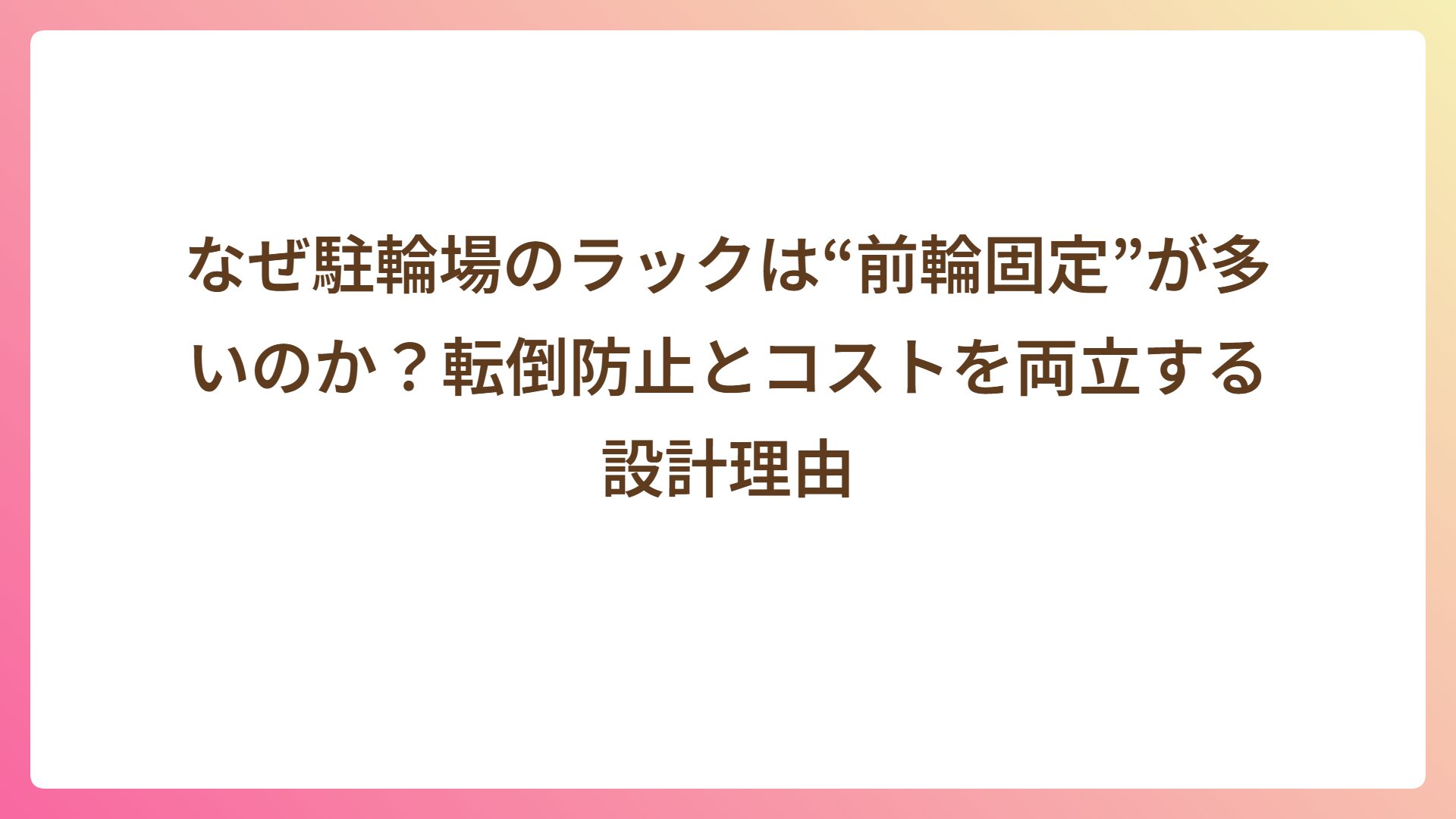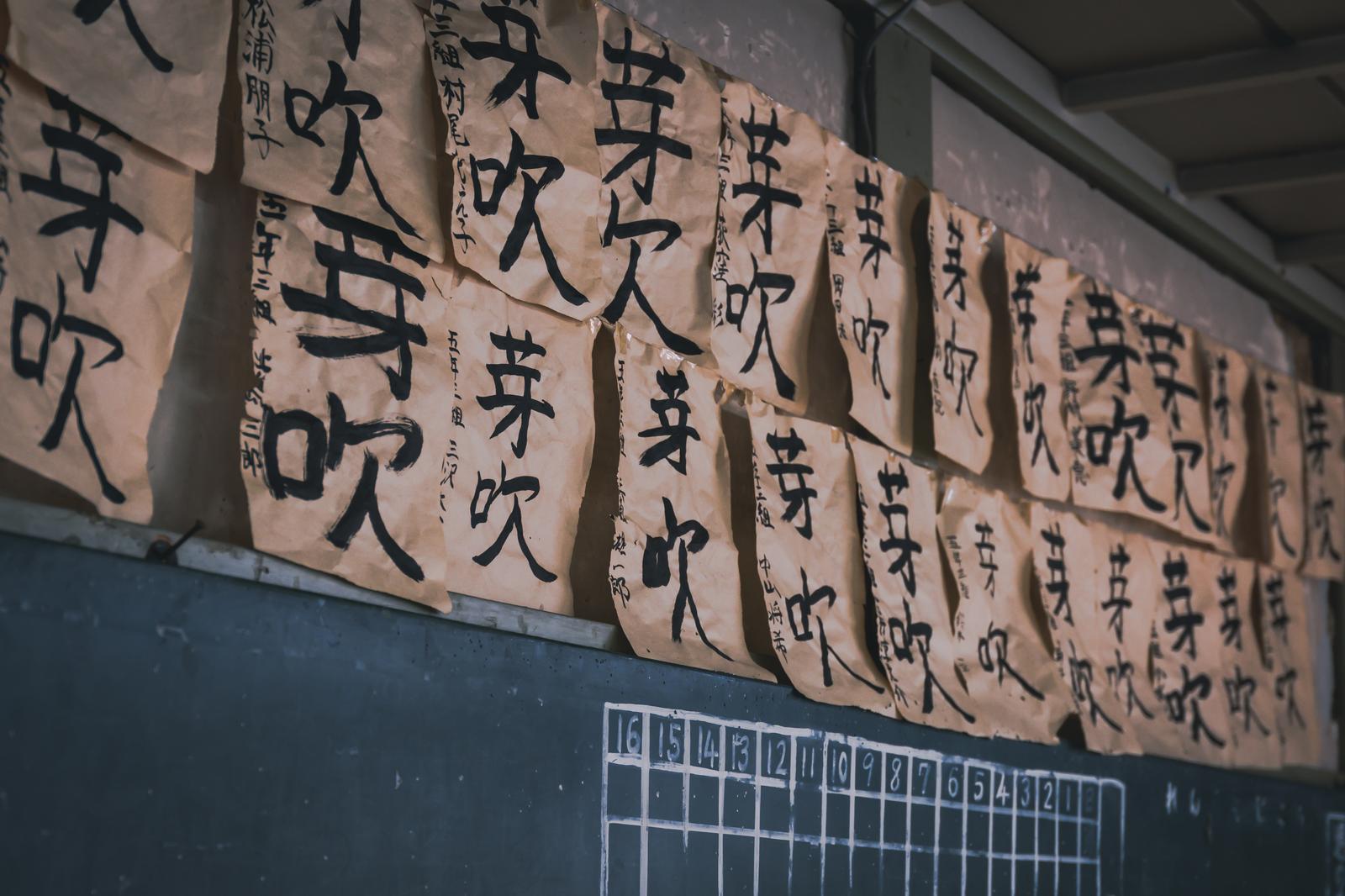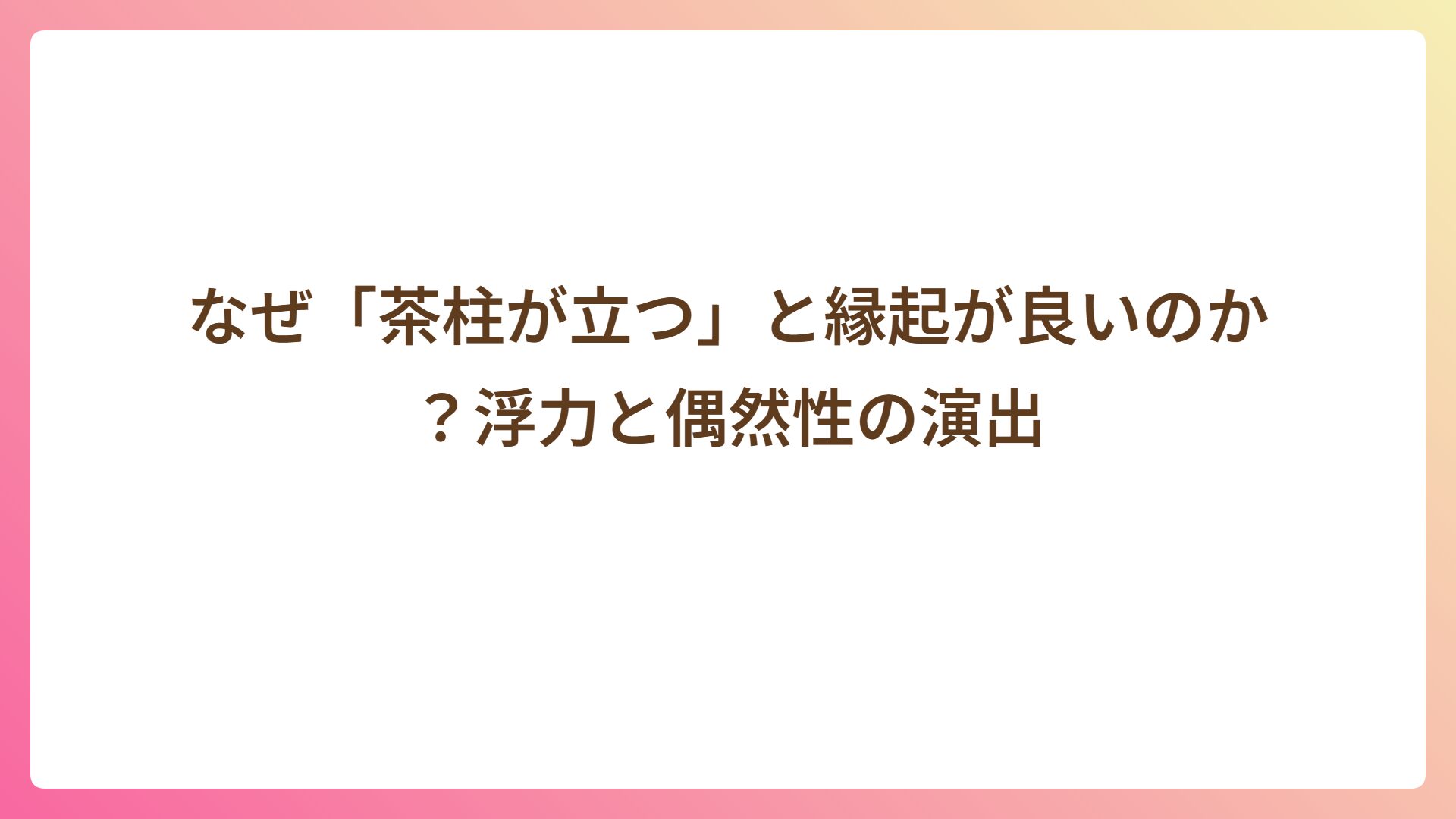なぜ昆布だしは“関西”、かつおだしは“関東”のイメージなのか?水質と出汁文化の分岐
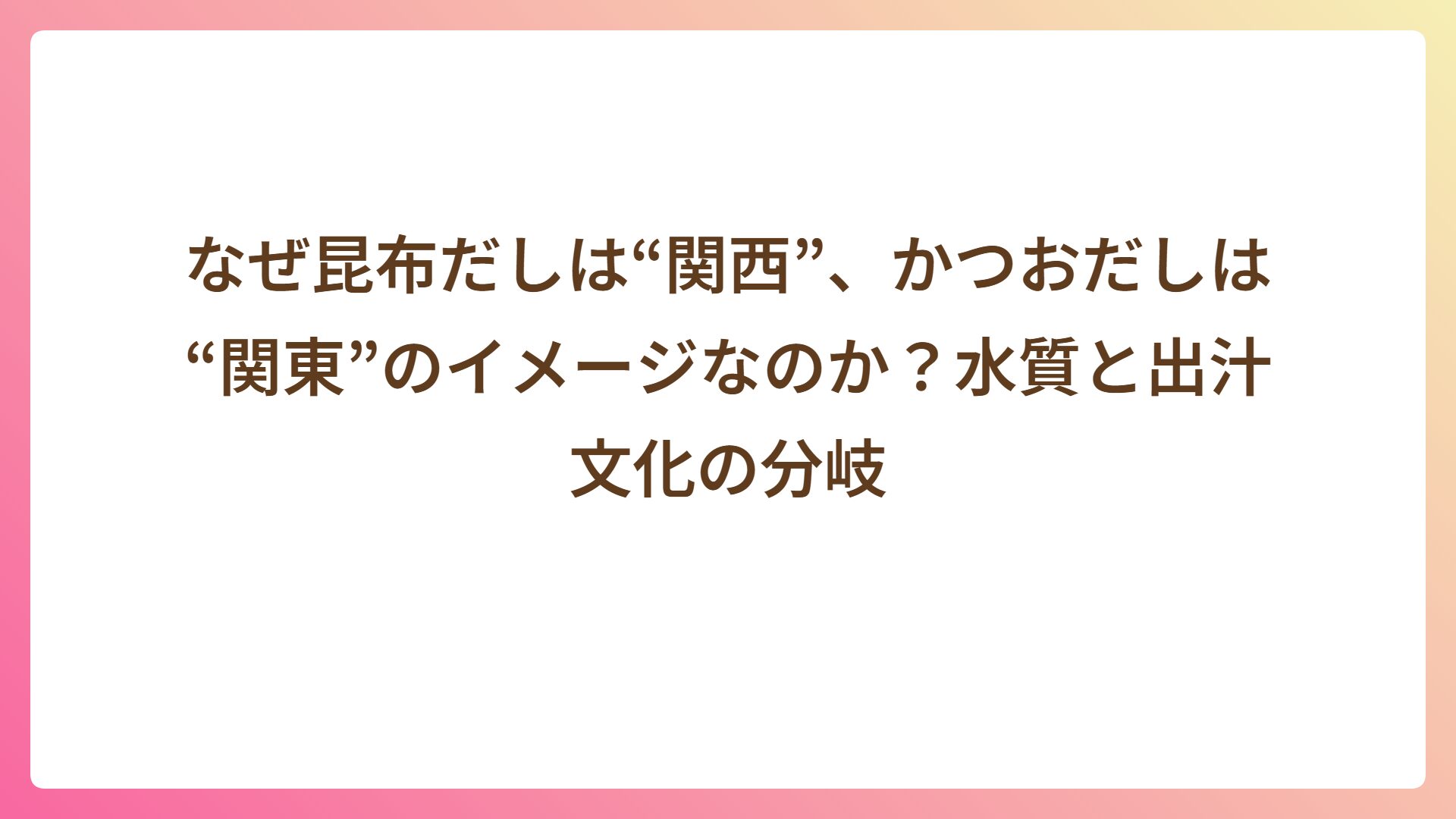
うどんやお吸い物を比べると、関西は淡く澄んだだし、関東は香ばしく濃いだし。
同じ「出汁文化」でも、地域でここまで味が変わるのはなぜでしょうか?
実はその理由は、水質・食材・歴史的背景という三つの要素が重なった結果なのです。
水の硬度がだし文化を分けた
最大の違いは「水」です。
日本の水は地域によって硬度が異なり、
関西は軟水(カルシウム・マグネシウムが少ない)、
関東はやや硬水の傾向があります。
昆布に含まれるうま味成分・グルタミン酸は、
軟水でよく溶け出す一方、硬水では抽出効率が悪くなります。
そのため、軟水が豊富な京都・大阪では昆布だしのうま味が出やすく、
逆に硬水気味の関東ではかつお節の香り成分が活きるだしが主流となりました。
つまり、水の違いが出汁文化を自然に二分したのです。
関西の昆布だし ― 繊細な料理文化との融合
京都を中心とする関西では、古くから京料理や懐石などの繊細な味付け文化が発展しました。
素材の持ち味を生かすため、色を濁らせず、味を引き立てる透明なだしが理想とされたのです。
昆布だしはグルタミン酸によるやさしいうま味が特徴で、
薄口しょうゆとの相性も良く、見た目にも上品な仕上がりになります。
この組み合わせが「関西=昆布だし」の印象を決定づけました。
関東のかつおだし ― 江戸の“速さと香り”
一方、江戸ではそば文化とともに、かつお節を使った濃いだしが発展しました。
江戸の水はやや硬く、昆布だしが出にくかったことに加え、
労働者が多く、短時間で強い風味を感じられるだしが求められたのです。
かつお節のうま味成分・イノシン酸は香りが立ち、
しょうゆやみりんと合わせると力強い味わいになります。
こうして、江戸では「濃口しょうゆ+かつおだし」という即効性のある味文化が定着しました。
明治以降の物流と地方定着
明治時代になると、鉄道と物流の発達により全国で食材が行き交うようになります。
しかし、地域の水質と調理文化は変わらず、
家庭の味として関西では昆布、関東ではかつおが主役のまま根付きました。
やがて「関西風うどん」「関東風そば」といった形で、
出汁そのものが地域アイデンティティとなっていきます。
まとめ
昆布だしが関西、かつおだしが関東に定着したのは、
水質の違い・料理文化の志向・都市生活のリズムが作り出した結果です。
関西の軟水が育んだ繊細なうま味、
関東の硬水と江戸文化が生んだ力強い香り。
出汁の味の違いは、まさに日本の食と風土の分岐点なのです。