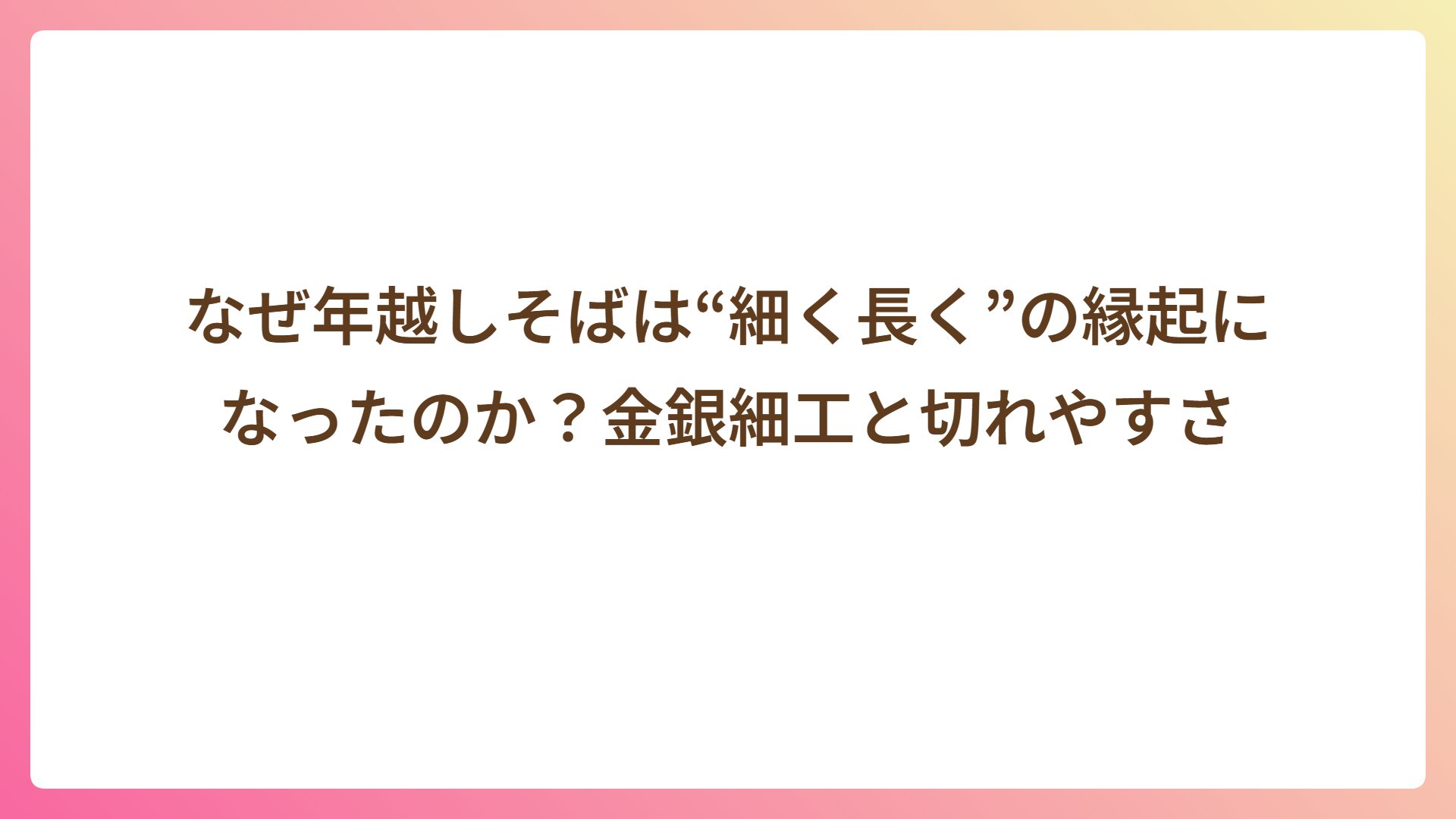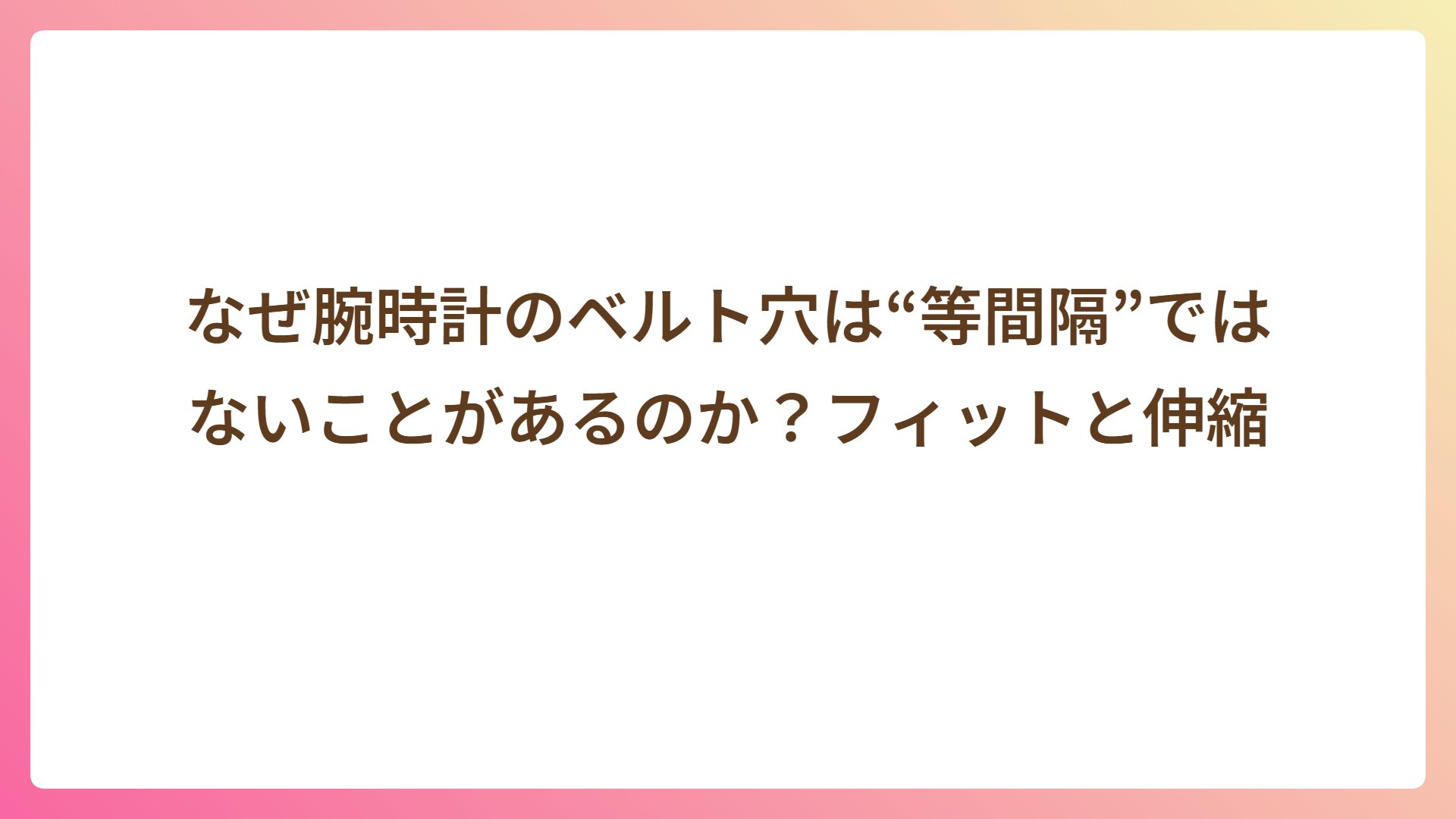なぜ公衆電話はまだ残っているのか?非常通信と冗長性の要件
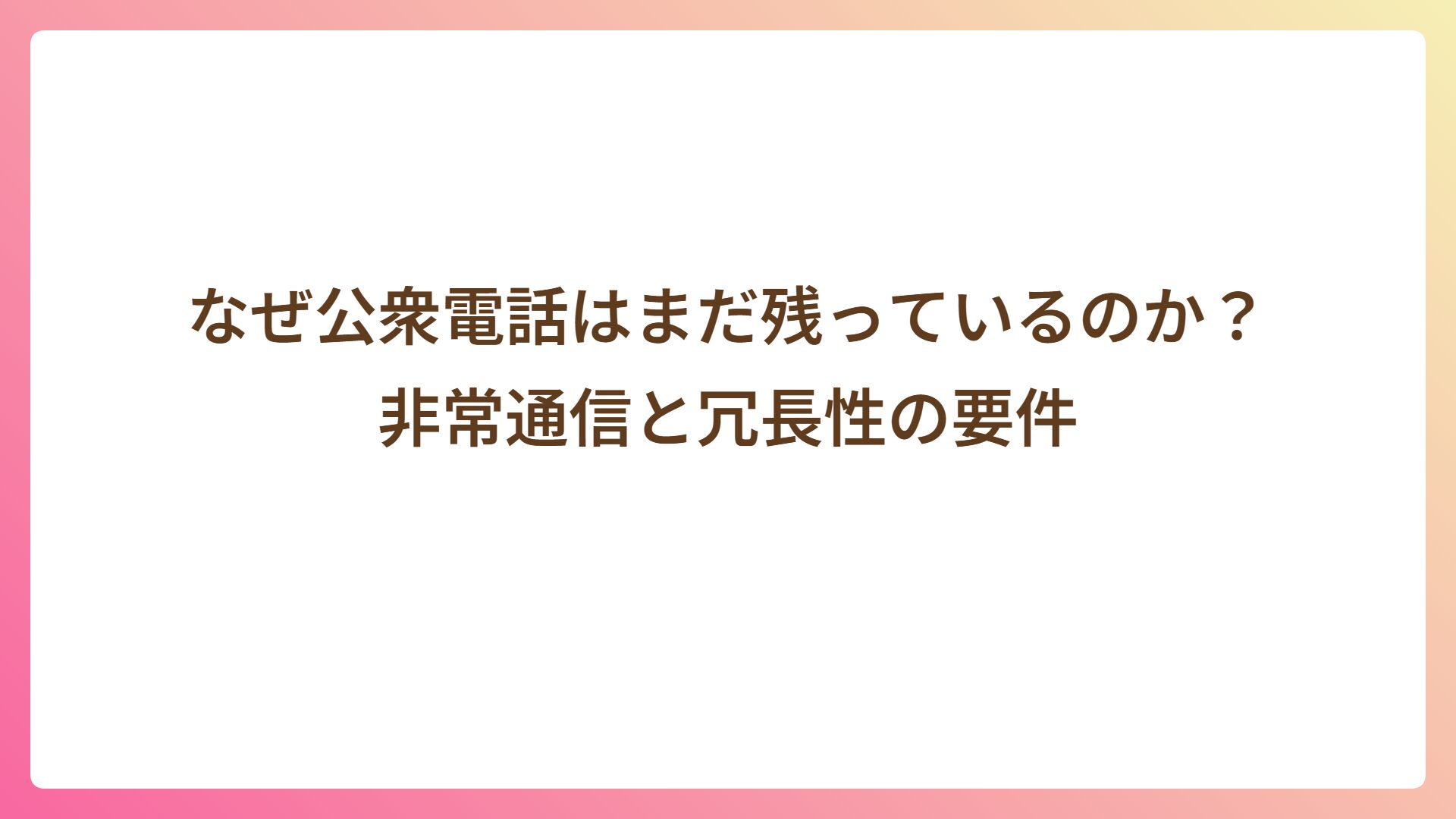
スマートフォンが当たり前になった現代でも、街の片隅には公衆電話ボックスが残っています。
ほとんど使う機会がないのに、なぜ撤去されずに維持されているのでしょうか?
その理由は、非常時の通信インフラとしての使命にあります。
公衆電話は“非常用通信網”として位置づけられている
公衆電話は単なる便利設備ではなく、法的に「非常通信設備」として位置づけられています。
電気通信事業法では、災害・停電・通信障害などの非常時に備え、
通信手段を確保することが義務付けられており、
これに基づいてNTTなどの通信事業者が全国に一定数の公衆電話を維持しています。
特に1995年の阪神淡路大震災や2011年の東日本大震災では、
携帯電話の基地局が停電や回線混雑で使えなくなる一方、
アナログ回線を利用する公衆電話は通じやすかったことが大きな教訓となりました。
停電しても使える“独立電源型”
多くの公衆電話(特に緑のタイプ)は、回線から給電される自立型設計になっています。
電話線そのものに直流電流(約48V)が流れており、
外部電源がなくても通話が可能。
つまり停電中でも発信・着信の両方が機能するのです。
一方、家庭用電話機や携帯電話はAC電源や基地局を経由するため、
停電時には使えなくなることが多く、
“最後まで残る通信手段”としての信頼性が評価されています。
通信網の“冗長性”を確保する目的
現代の通信インフラは、光回線や携帯ネットワークなどデジタル化が進んでいます。
しかし、これらは同じルート上にある中継局や電源が共通している場合が多く、
大規模障害が発生すると同時に通信不能になるリスクがあります。
公衆電話はアナログ回線を基盤とし、
独立したルートを通るため、**通信網の冗長性(バックアップ性)**を保つ役割を果たしています。
これは国の防災計画においても重要な要件とされており、
一種の“通信ライフライン”として維持されているのです。
災害時は無料で使える
地震や大規模停電などの災害発生時には、
NTTが自動的に「災害時無料通話モード」を有効化します。
これにより、硬貨やテレホンカードがなくても全国どこからでも無料で通話可能になります。
この仕組みはすでにシステム化されており、
通信制限がかかる携帯電話とは異なる緊急通信用の優先ルートが確保されています。
災害拠点や避難所に“計画的配置”されている
公衆電話は無作為に残されているわけではなく、
自治体や通信事業者が策定する「災害時公衆電話設置計画」に基づいて配置されています。
学校・役所・避難所・駅前・病院など、
災害時に人が集まる拠点を中心に一定距離ごとに設置されています。
また、屋外型・屋内型・特設型など複数のタイプがあり、
非常用電話線が地中配線で保護されている場合も多く、
地震や台風でも通信が途絶しにくい構造になっています。
子どもや外国人にも“使える最後の手段”
もうひとつの理由は、誰でも使える簡便さです。
スマートフォンが使えない高齢者や外国人旅行者でも、
硬貨1枚で通話ができるというシンプルさは、緊急時に大きな強みになります。
また、災害時の「171(災害用伝言ダイヤル)」にも直接接続できるようになっており、
情報伝達の初動を支える設計が維持されています。
まとめ
公衆電話が今も残っているのは、
災害・停電・通信障害時でも使える非常用通信インフラだからです。
携帯や光回線ではカバーできないリスクを補うための冗長性の要件として、
国家レベルで維持されている。
普段は目立たなくても、公衆電話は「もしものときに必ず動く通信の最後の砦」なのです。