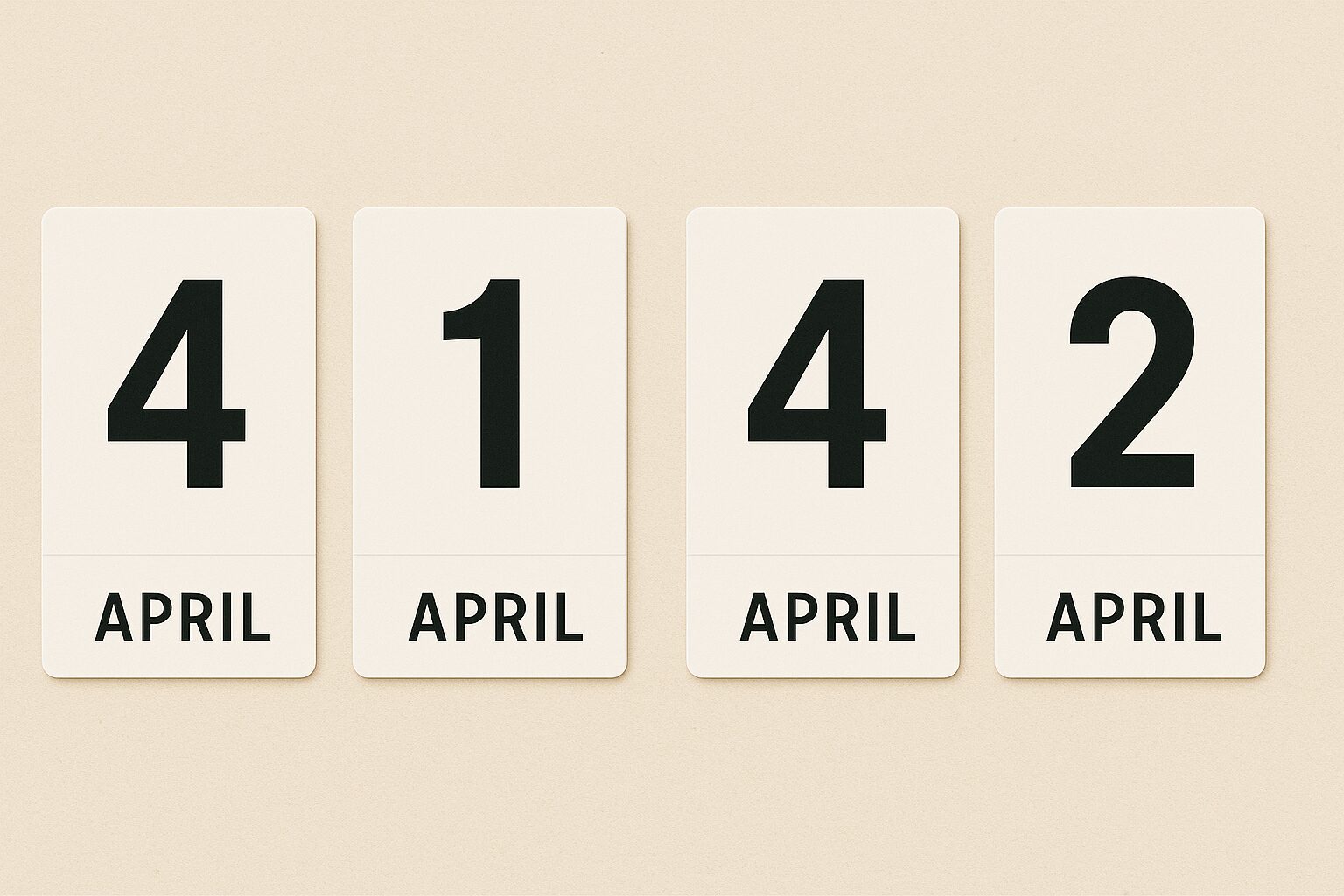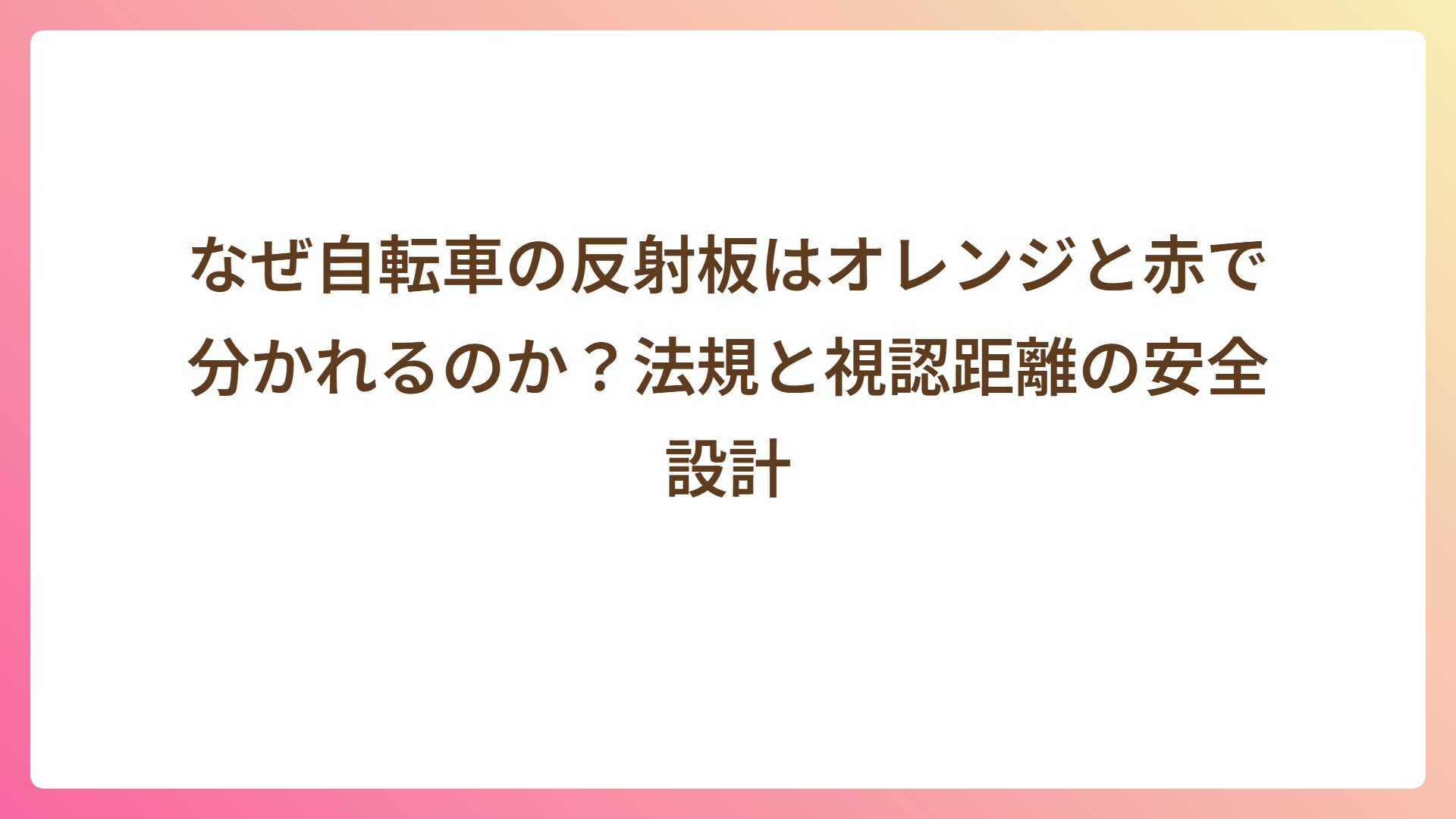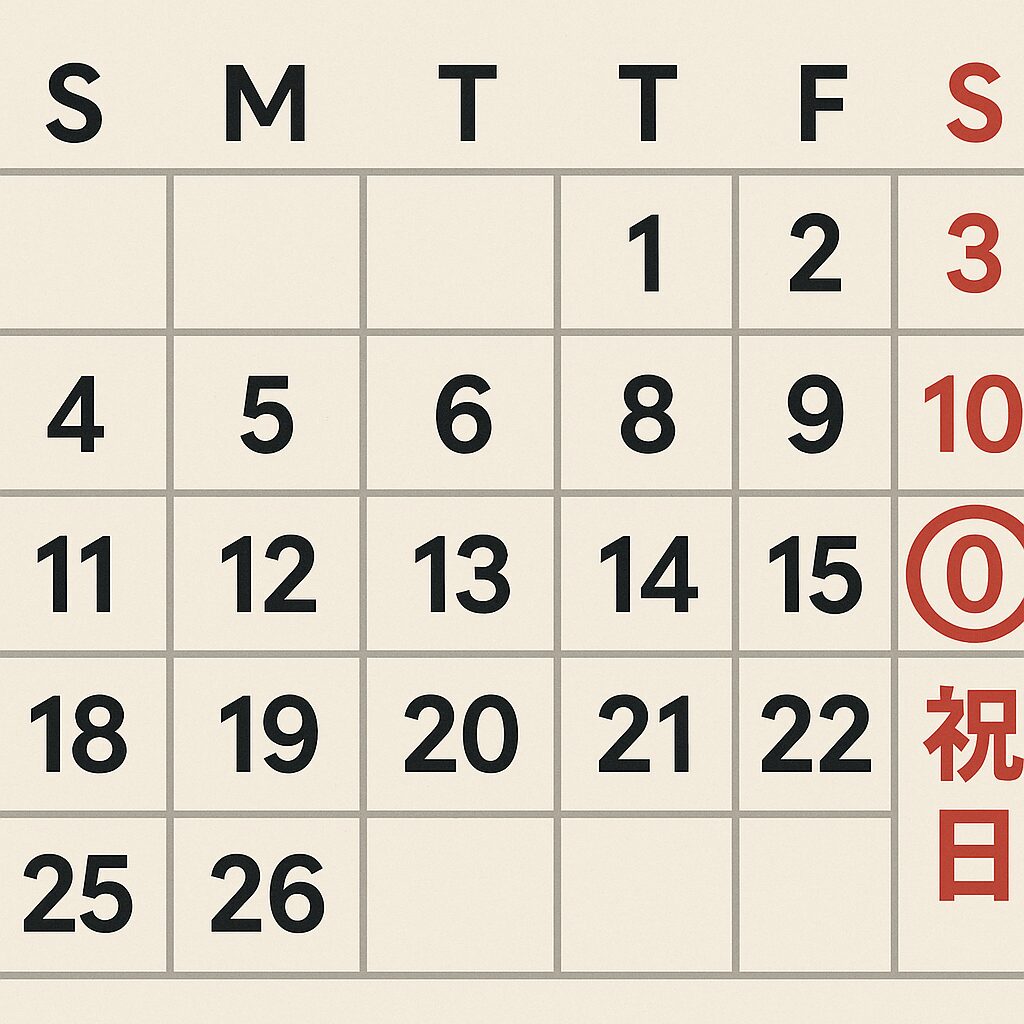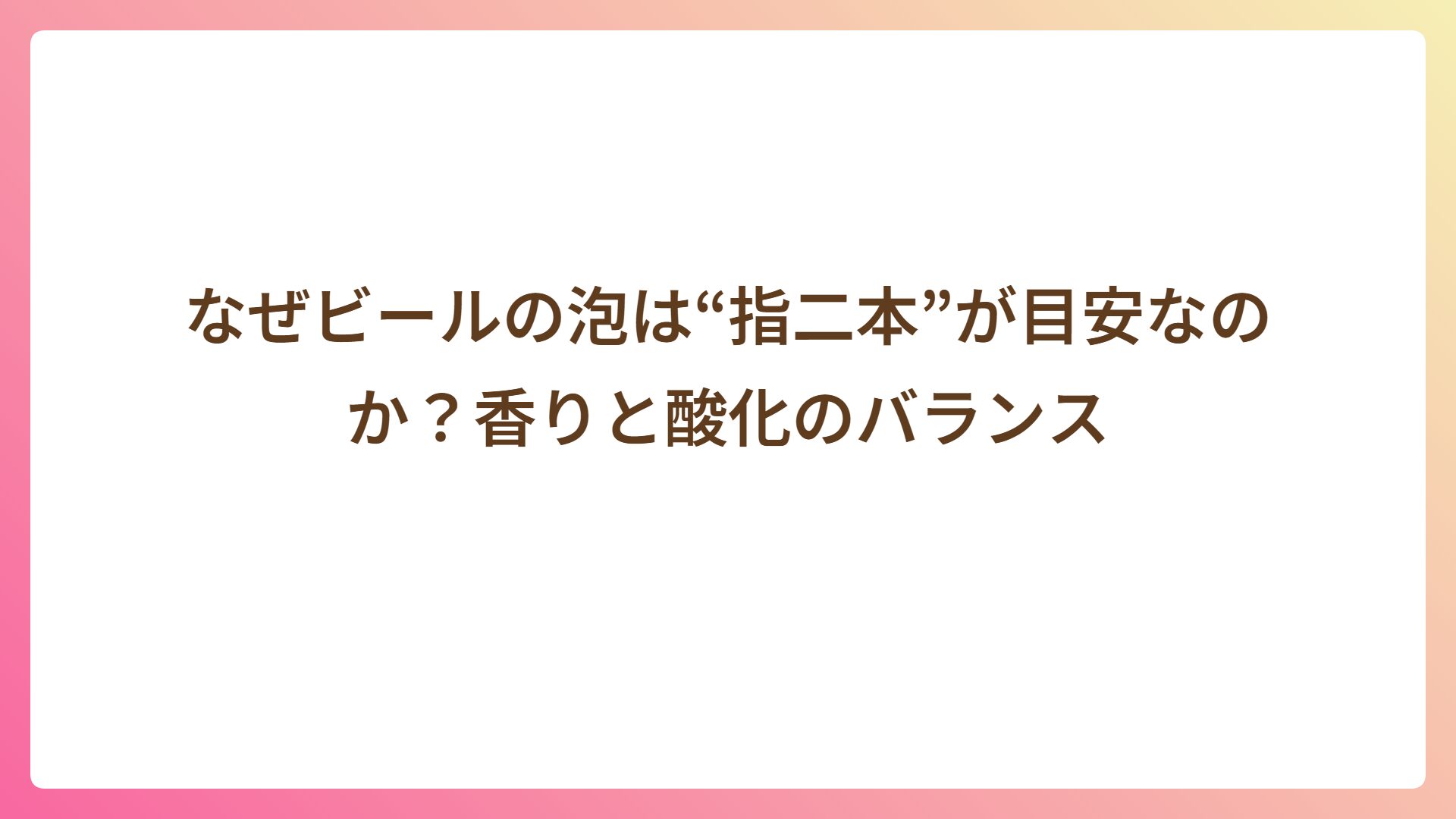なぜ電球の口金サイズはE26が多いのか?電圧と規格の世界標準
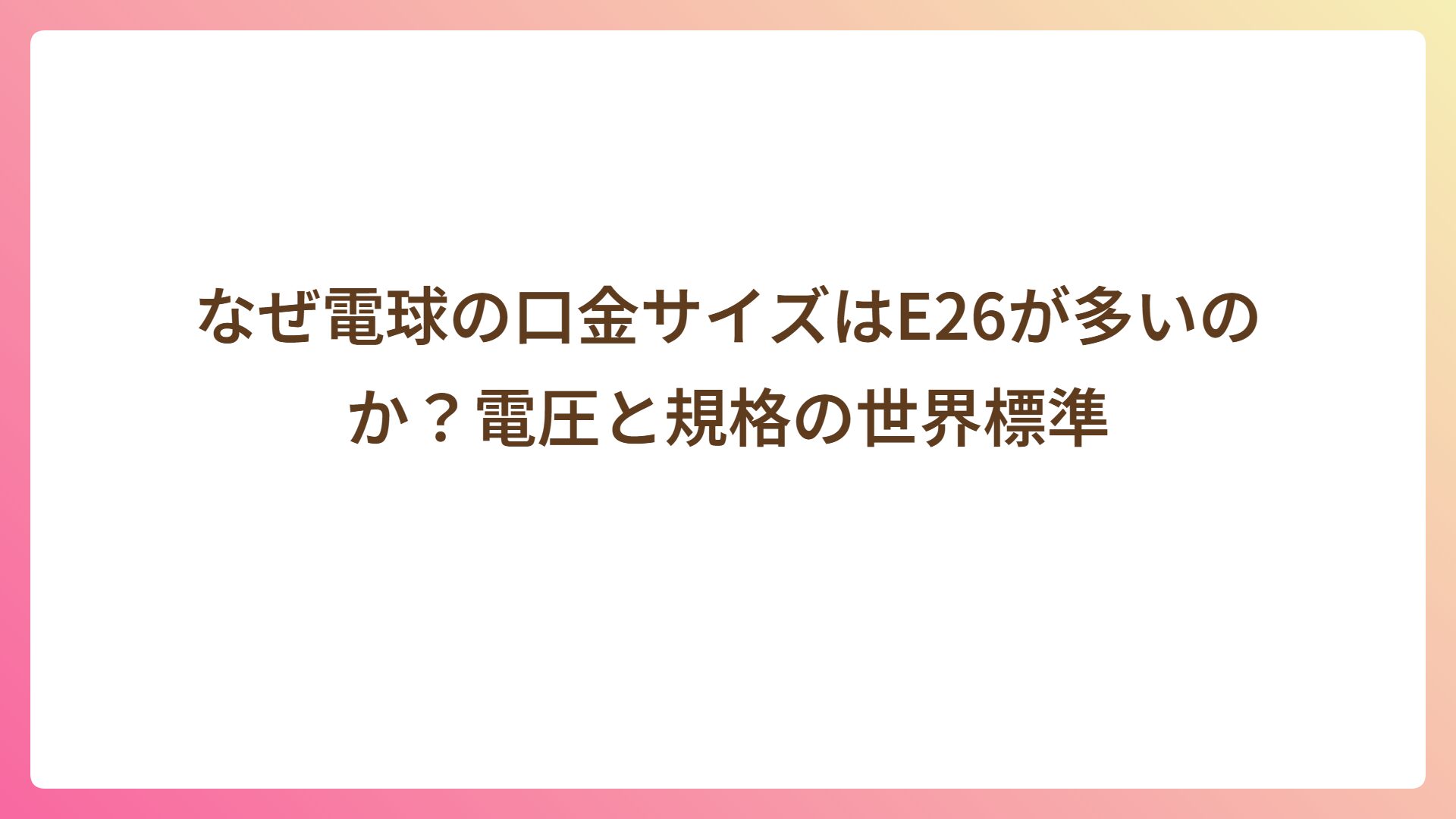
家庭で使う電球を買うとき、パッケージに「E26」や「E17」といった表記を見たことがあるでしょう。
この“E26”という数字は、単なる型番ではなく、世界共通の基準に基づいたサイズ規格を示しています。
では、なぜ数ある口金サイズの中で「E26」が最も多く使われているのでしょうか?
「E26」の“E”と“26”が示す意味
「E26」の“E”は、発明王エジソンの頭文字で、ねじ込み式口金(エジソンベース)を意味します。
“26”は金属ねじ部分の直径をミリメートル単位で示しており、つまりE26=直径26mmのエジソン口金ということになります。
この方式は19世紀にエジソンが開発し、その後IEC(国際電気標準会議)によって国際規格として定められました。
今では世界中の照明器具で互換性を保つための基準となっています。
100V級電圧との相性がちょうど良い
日本を含む多くの国の家庭用電源は、100V〜120Vの低圧電流です。
この電圧では、E26サイズの口金が最も安全で、放熱性・絶縁距離・強度のバランスが良いとされています。
より小さいE17やE12では熱がこもりやすく、長時間使用に不向き。
逆にE39などの大型口金は高電力照明(街灯や工場照明)用で、一般家庭にはオーバースペックになります。
その中間で安定性に優れたE26が、家庭用照明の“ちょうどいいサイズ”として定着したのです。
世界的にも「E26/E27」が標準サイズ
実は、日本のE26と欧州のE27はほぼ同一規格です。
国によって電圧は異なりますが、物理的なねじサイズはほぼ共通化されており、国際互換性の高い口金サイズとして広く採用されています。
この統一規格のおかげで、メーカーや国をまたいだ製品流通が容易になり、照明業界のグローバル化を支えています。
LED時代でもE26が生き残る理由
LED電球が主流になった今でも、E26口金が多いのは、既存の照明器具との互換性を維持するためです。
ソケット部分を変えずに電球だけを交換できるようにすることで、買い替えコストを抑え、普及を促進しています。
新しい技術が登場しても、古い規格を引き継ぎながら発展するのが照明の世界。
E26はまさに、その象徴といえる存在です。
まとめ
電球の口金がE26なのは、
100V電圧に最適な設計と、国際規格による標準化の結果です。
サイズにも、長い歴史と技術的な必然がある。
家庭の明かりを支えるE26は、時代を超えて受け継がれてきた“世界共通のねじ”なのです。