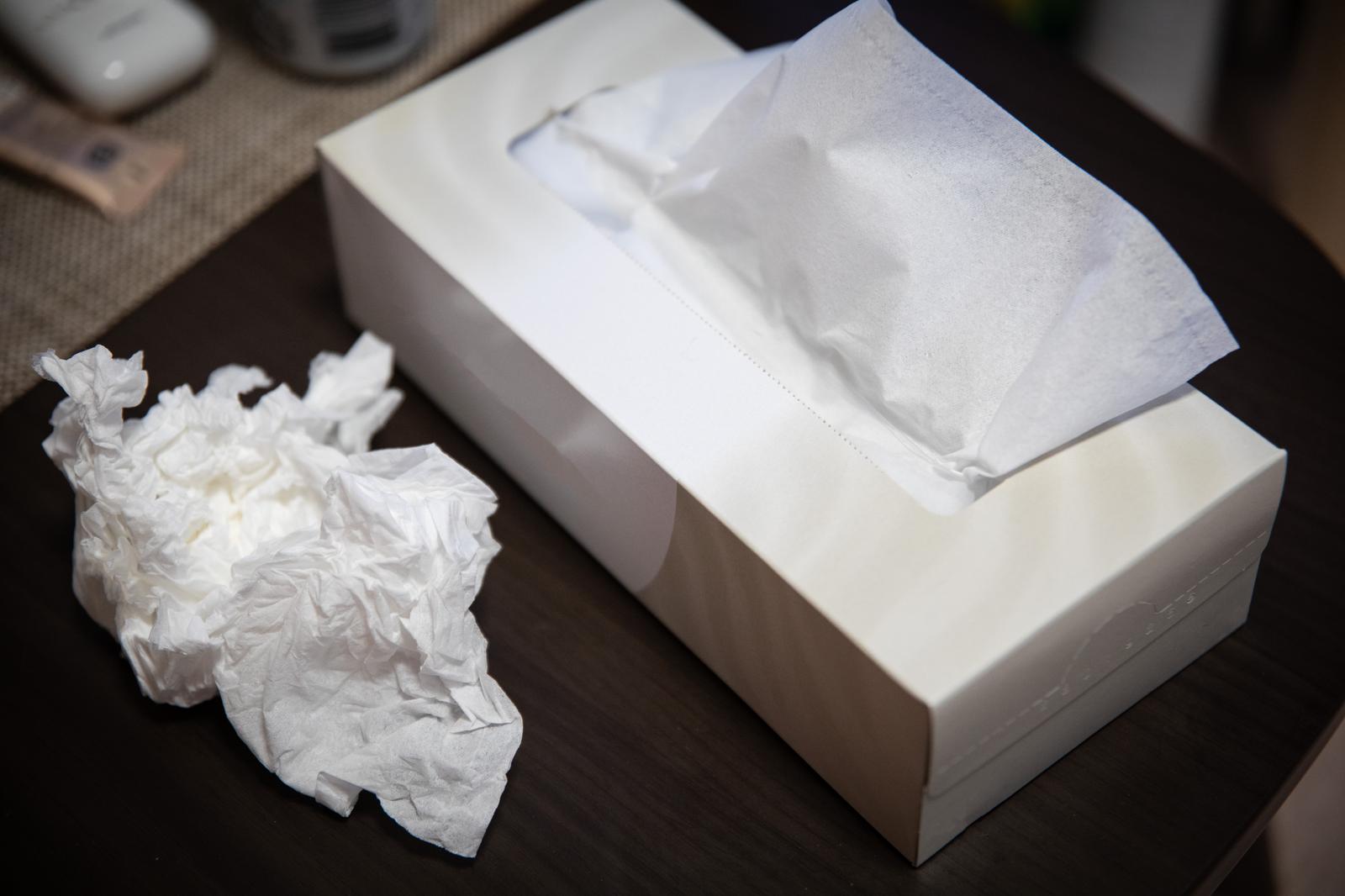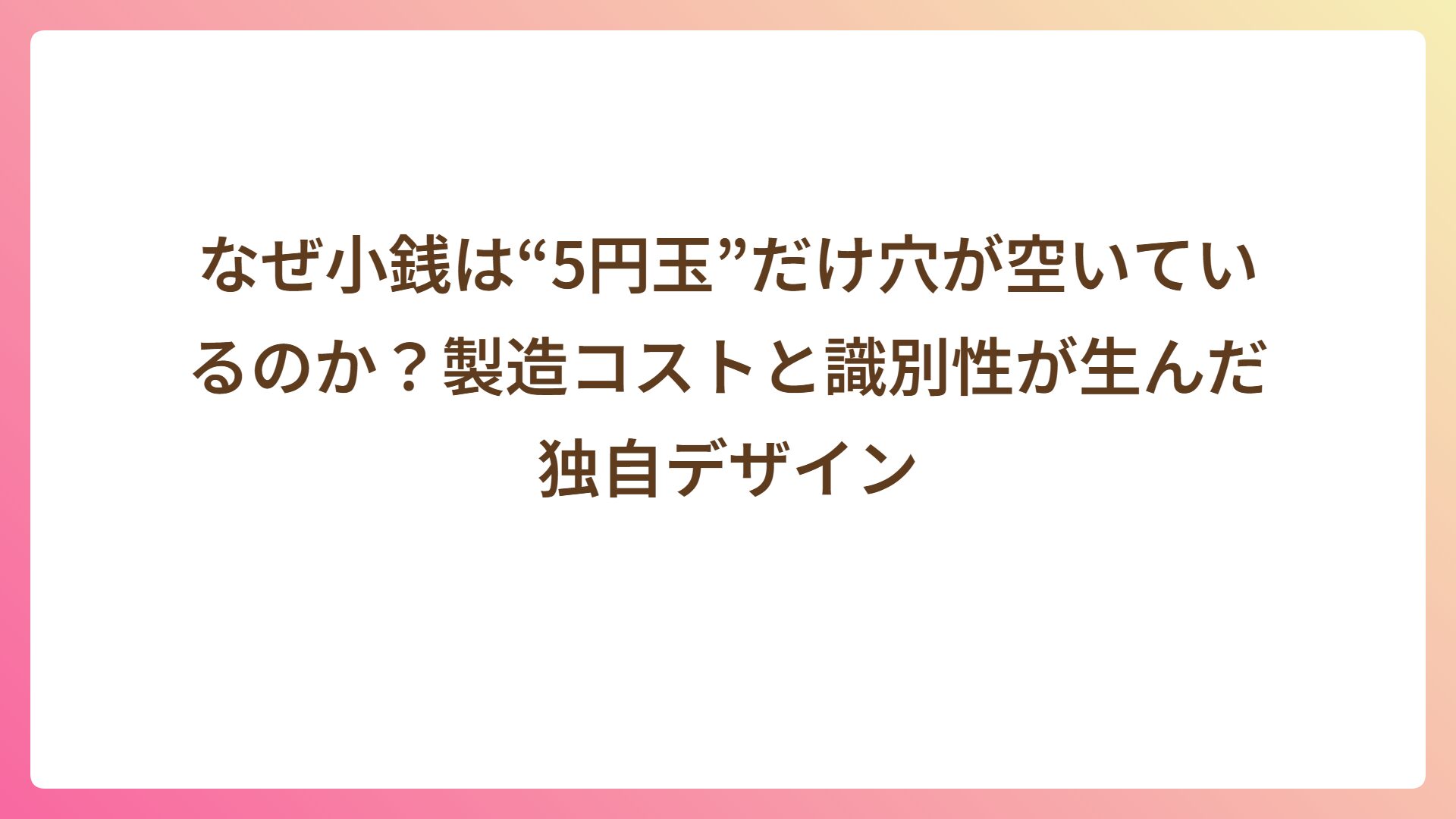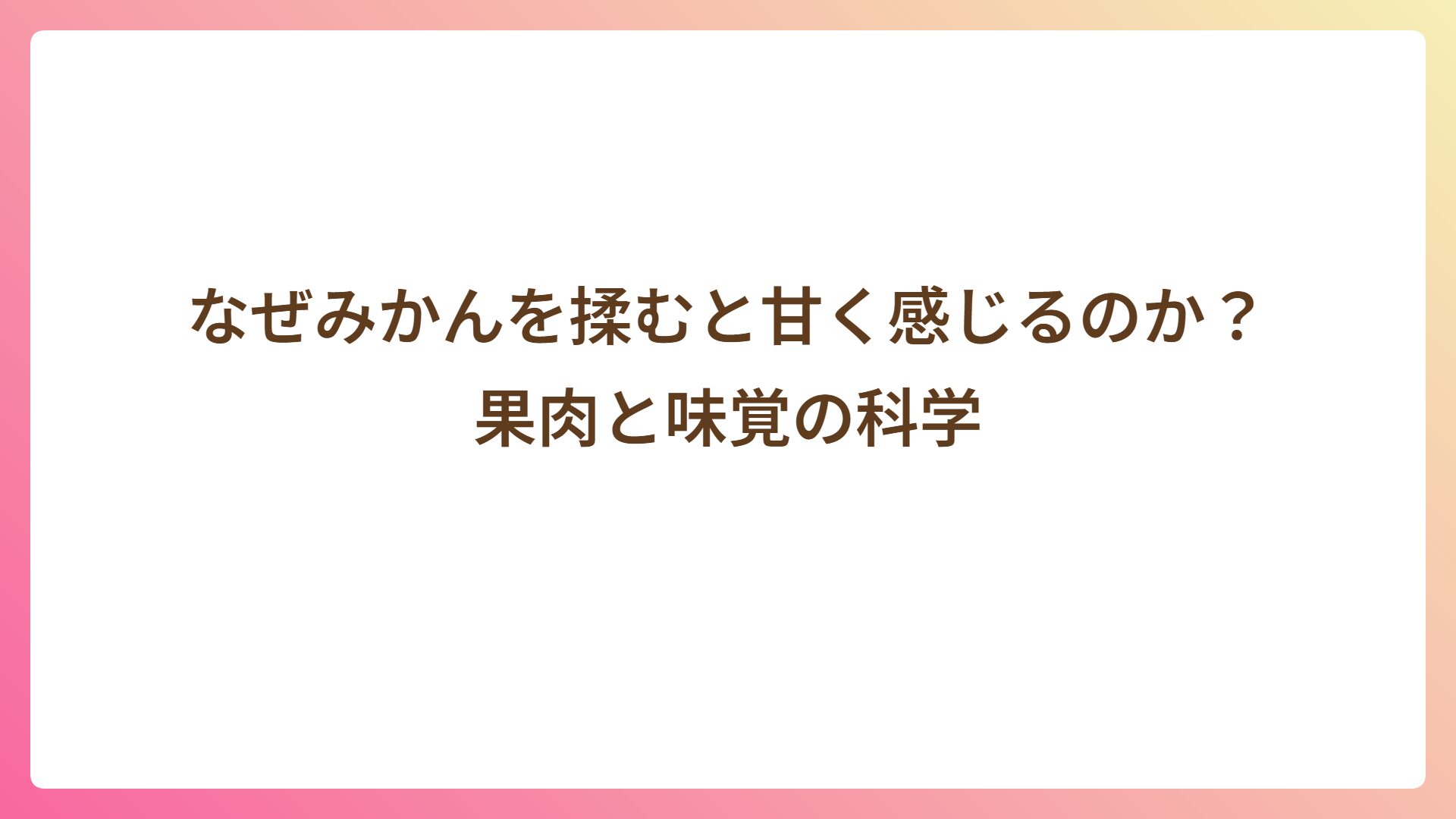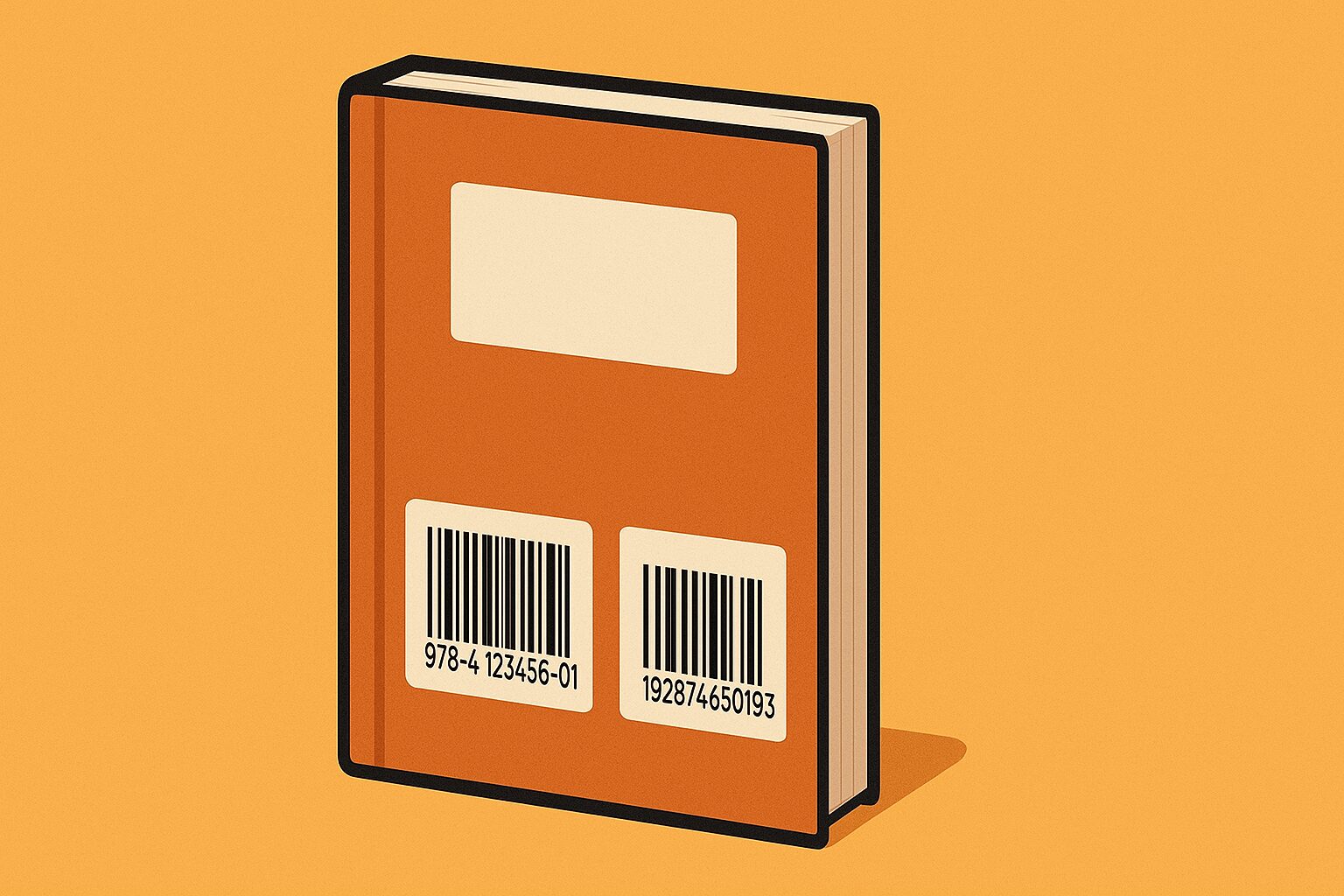なぜキュウリには「うなぎと一緒に食べるな」という俗説があるのか?栄養学と迷信の境界
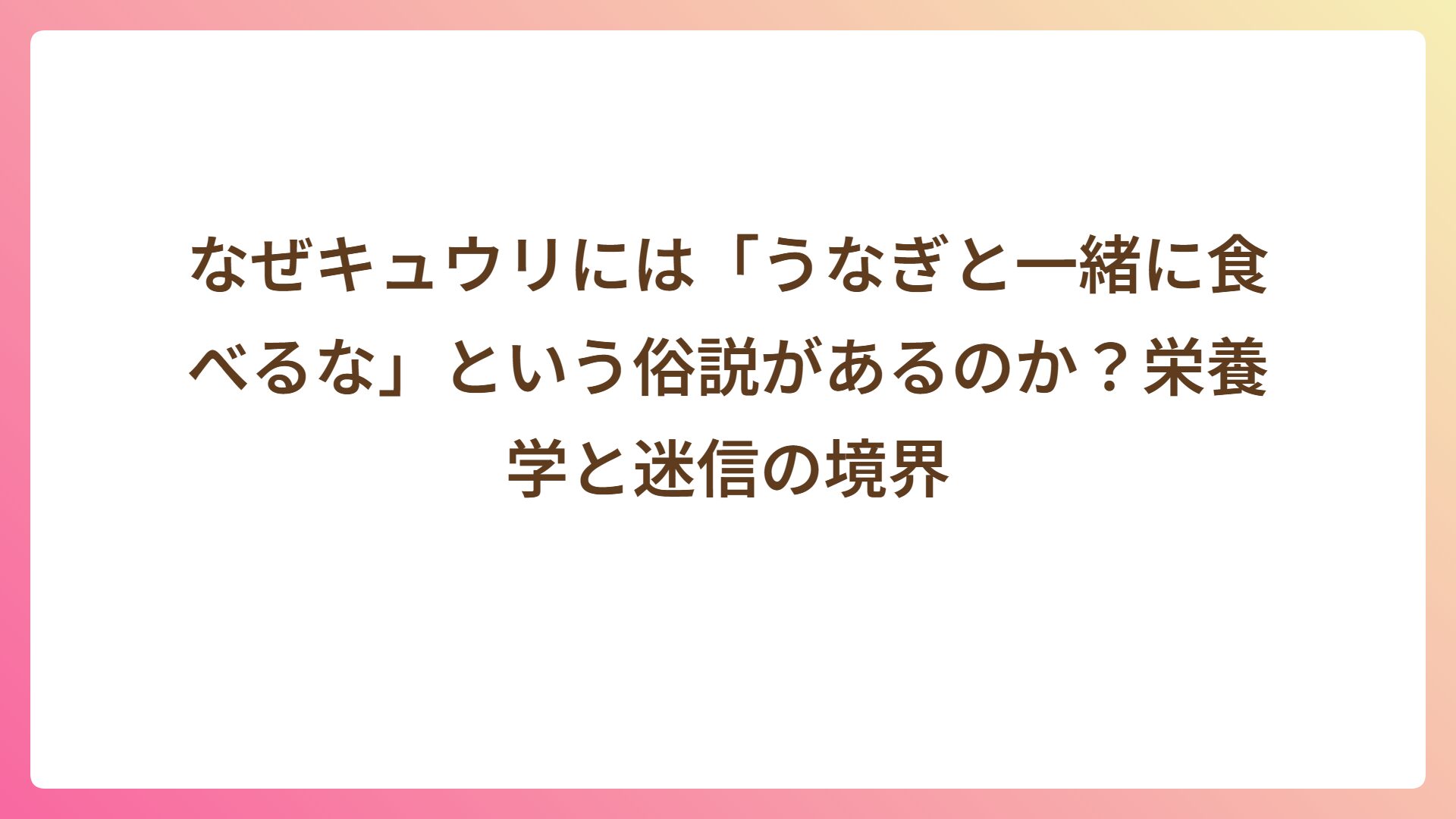
夏の定番食材である「うなぎ」と「キュウリ」。
どちらも暑さに疲れた体を癒す食べ物ですが、昔から「一緒に食べるとよくない」と言われてきました。
実際にはどんな根拠があるのでしょうか?
この言葉の背景には、古代の食養生と誤解の混在が見えてきます。
陰陽思想による「食べ合わせ」の考え方
この俗説のもとになっているのは、古代中国の陰陽五行思想に基づく“食べ合わせ”の考え方です。
食材には「体を温める陽性」と「体を冷やす陰性」があるとされ、
そのバランスが崩れると体調を崩すと考えられていました。
うなぎは脂が多く、体を温める「陽性食品」。
一方のキュウリは水分が多く、体を冷やす「陰性食品」。
この対極の性質を同時に取ると、消化に負担がかかり、胃を壊すと信じられていたのです。
栄養学的には問題なし
現代の栄養学的に見ると、うなぎとキュウリを一緒に食べても害はありません。
むしろ栄養面では、
- うなぎ:ビタミンA・D・E・B群、DHA・EPAなどの脂溶性栄養素
- キュウリ:水分・カリウム・ビタミンC
と、むしろ栄養バランスがよく、脂の多いうなぎをさっぱり食べられる理想的な組み合わせです。
実際、うなぎの酢の物や「うざく(うなぎ+キュウリ)」は伝統的な料理として存在しています。
つまり「一緒に食べるな」というのは、栄養的根拠というより昔の食養生の名残にすぎません。
「贅沢への戒め」としての俗説説
もう一つの説は、庶民への“ぜいたく禁止”の教えというものです。
江戸時代、うなぎは高級食材であり、キュウリも夏場に採れたては貴重なものでした。
そのため「高価なものを一度に食べるのはもったいない」という
倹約・節制の教えが「一緒に食べるな」という形で語られたとされています。
現代では「さっぱり合わせ」として定着
現在では、うなぎの脂をキュウリの酸味や水分で中和する料理法として
「うざく」や「うなぎの酢の物」が夏の定番となっています。
かつて禁じられた組み合わせが、現代ではむしろ理想的な食べ合わせに変わったのです。
まとめ
「キュウリとうなぎを一緒に食べるな」という俗説は、
陰陽思想の名残と倹約思想から生まれた文化的な迷信にすぎません。
実際には健康被害の心配はなく、むしろ栄養面では理想的な組み合わせ。
古い食べ合わせの知恵は、現代では“食文化の記憶”として楽しむべきものなのです。