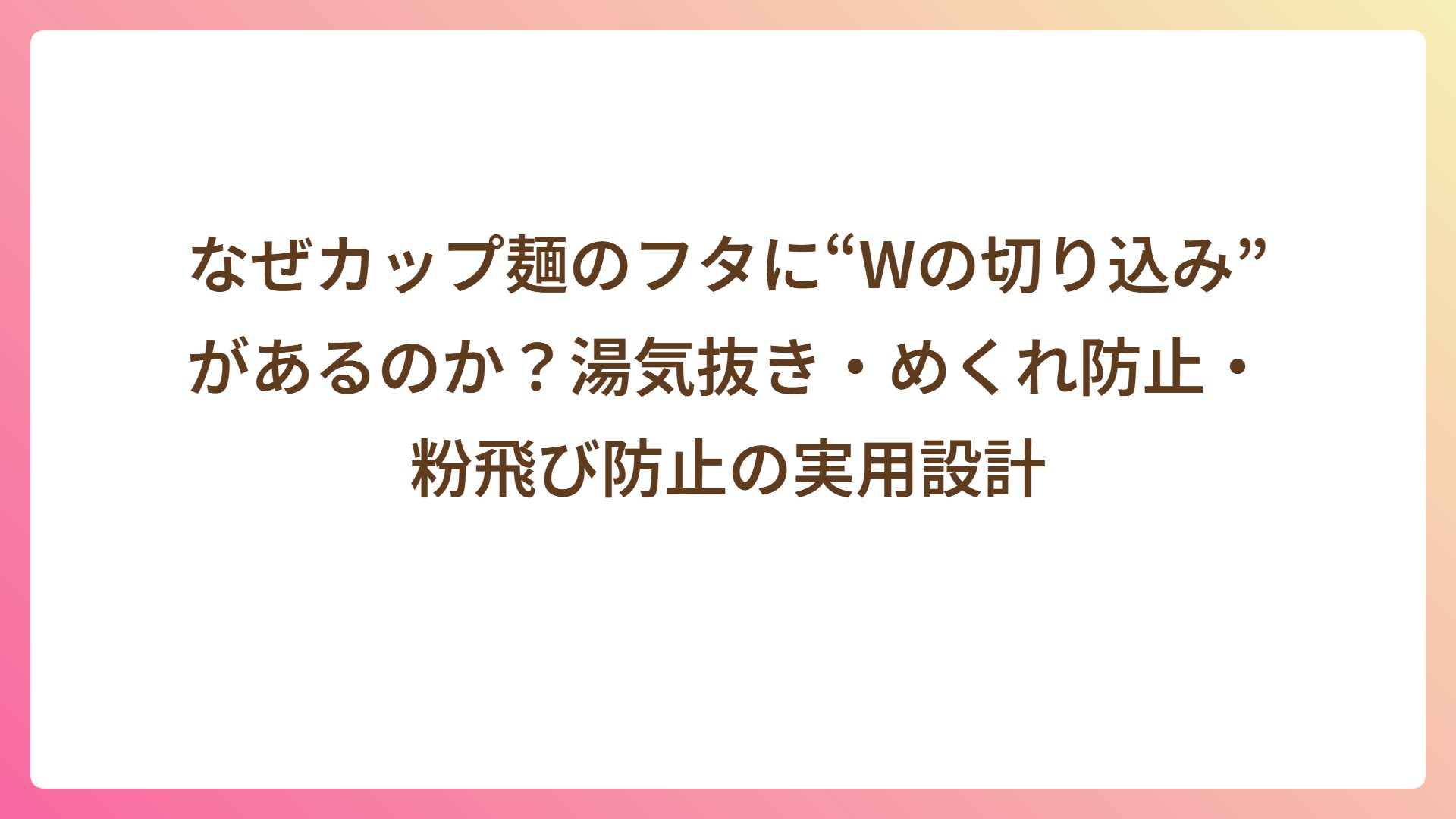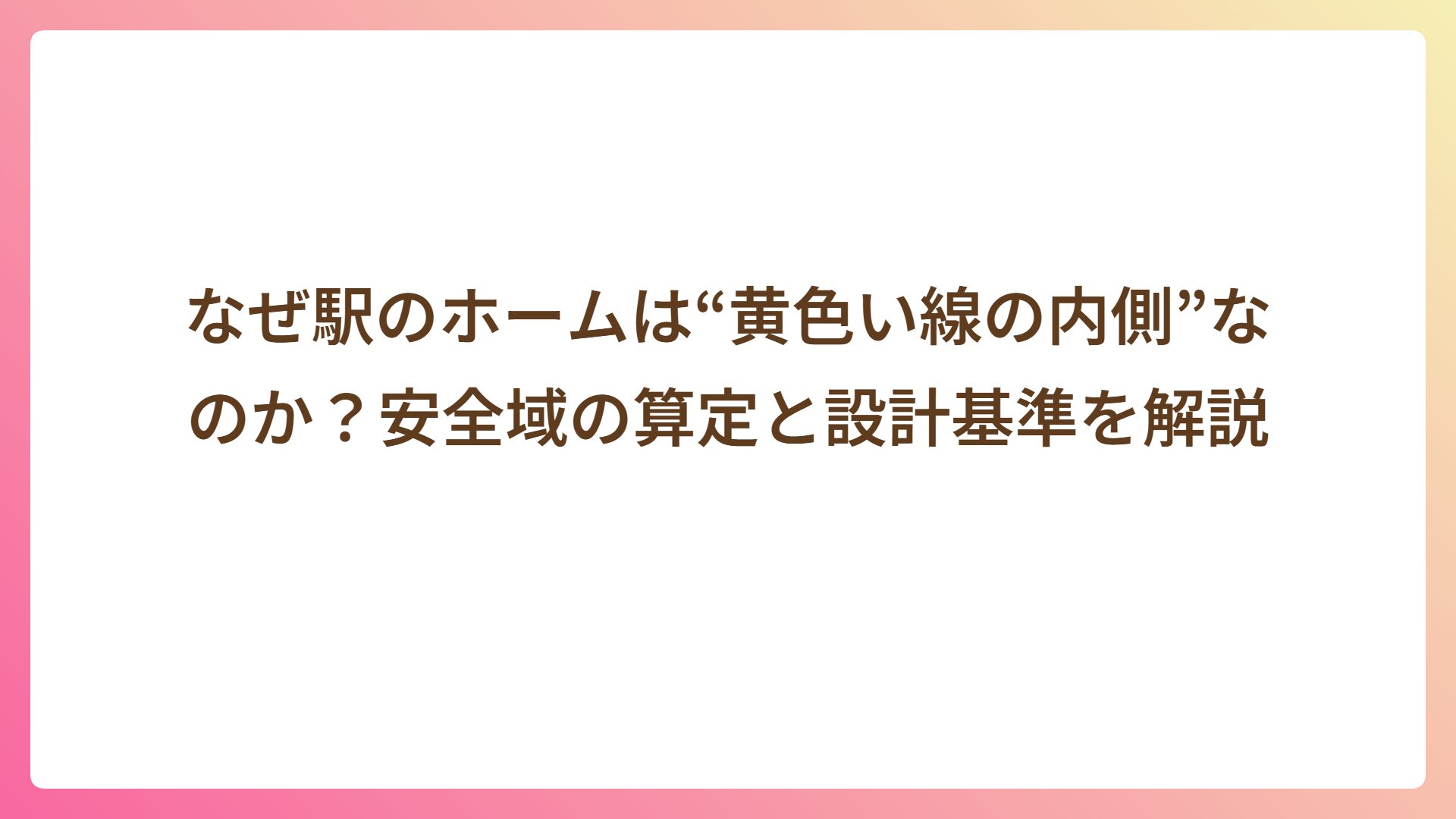なぜテストのマーク欄は楕円なのか?読取精度と塗りつぶし負荷
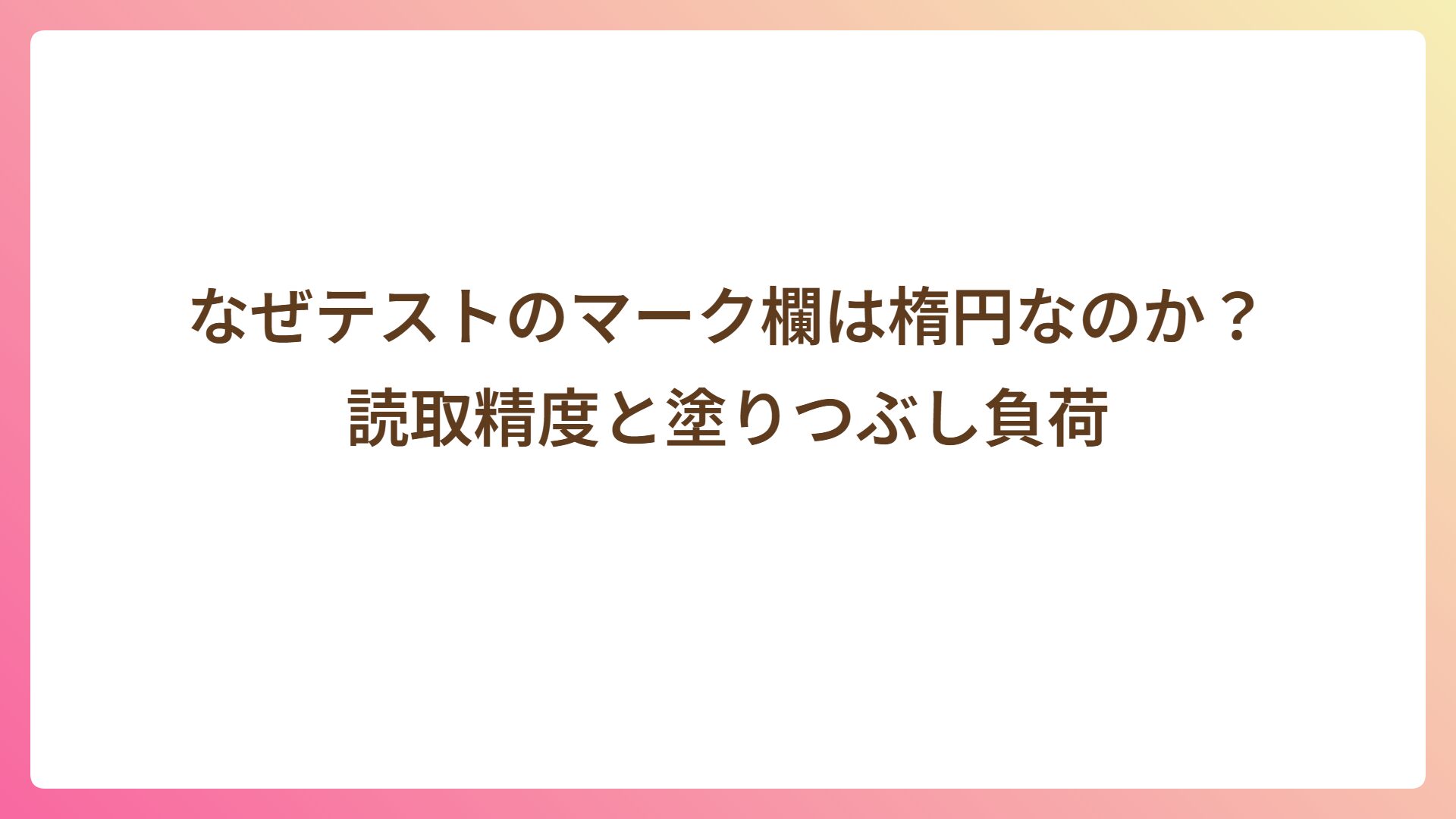
試験でおなじみのマークシート。
選択肢を塗る欄は、なぜか完璧な円ではなく、少し横に伸びた楕円形になっています。
単なるデザインではなく、実はこの形こそが正確な読み取りと手作業のしやすさを両立する最適形状なのです。
光学式読取機(OMR)の特性に合わせた形
マークシートは、**OMR(Optical Mark Reader)**と呼ばれる光学読取機で採点されます。
この機械は、用紙上の特定の位置に赤外線や可視光を照射し、
黒鉛(鉛筆)による反射率の差で「塗られている/いない」を判定します。
楕円形にすることで、
- 縦方向の位置誤差に強く、
- 塗りの濃淡や筆圧ムラがあっても認識しやすくなる
という特性があります。
つまり、楕円は**「読取精度を上げるための形」**なのです。
なぜ“円形”ではなく“楕円形”なのか
もしマーク欄が完全な円形だと、
塗る面積が広くなり、塗りつぶしに時間と力がかかるという欠点が生まれます。
逆に細すぎる線形や四角形だと、読取位置のズレや塗り残しによる誤判定が増えます。
そこで考えられたのが、
「光学的に十分な面積を持ちながら、人間が塗るストロークを短くできる形」=横長の楕円です。
筆記動作が自然で、1〜2回の往復で濃く塗れるため、疲労を最小限に抑えられるのです。
機械の読取ラインに沿った設計
OMRの多くは、縦方向(上下)にラインセンサーを動かして読み取る仕組みです。
このとき、マーク欄が上下に短く横に広い楕円形であれば、
センサーの走査ラインがマークの中央を通過しやすく、検知漏れを防げる構造になります。
もし縦長や円形にすると、センサーの通過タイミングで
「マークの端しか読み取れなかった」という部分欠損エラーが起きやすくなるのです。
印刷ズレ・記入ズレへの許容範囲が広い
大量印刷されるマークシートは、用紙によって数ミリ単位の印刷位置ズレが発生します。
また、受験者も完全に枠内をなぞるとは限りません。
楕円形はそのズレに対して許容範囲が広く、
多少中心から外れても反射率の変化を正しく検知できるようになっています。
この「ズレに強い形状」こそ、全国規模のテストなどで信頼性が高く評価される理由です。
“縦置き”と“横置き”で意味が違う
実は、マーク欄の楕円はテストによって縦置き型と横置き型があります。
- 縦置き(細長い楕円):読取機の走査方向と一致し、位置精度を優先
- 横置き(横長楕円):塗りやすさや筆圧安定を優先
大学入試共通テストなどでは、大量処理と読取精度のバランスから横長楕円が主流です。
受験者の“心理的負担”を減らす工夫
円形より楕円形のほうが、塗り終わりが視覚的に分かりやすいという効果もあります。
「どこまで塗ればいいかわからない」という不安を軽減し、
ミスや塗り残しを防ぐ心理的効果も確認されています。
特に子どもや受験初心者でも、楕円は一筆で埋めやすい形であり、
公平な条件で記入できるよう工夫されたデザインなのです。
まとめ
テストのマーク欄が楕円なのは、
光学読取の精度・塗りやすさ・ズレ許容性をすべて満たすためです。
円よりも塗りやすく、線よりも読み取りやすい。
その絶妙な中間形こそ、何百万人分の答案を正確に処理するための人と機械の最適解。
あの小さな楕円には、効率と正確さを極限まで追求した設計思想が詰まっているのです。