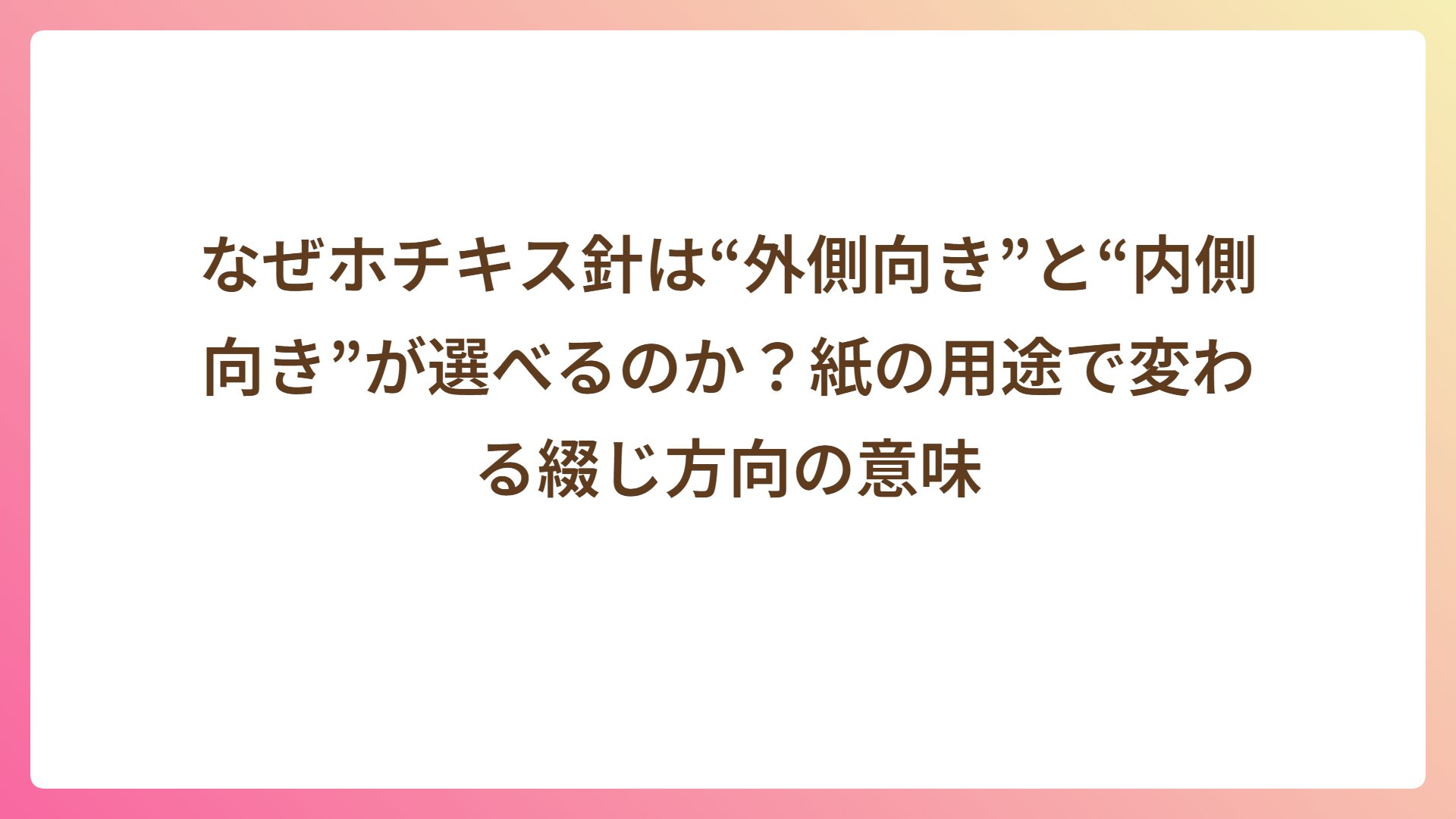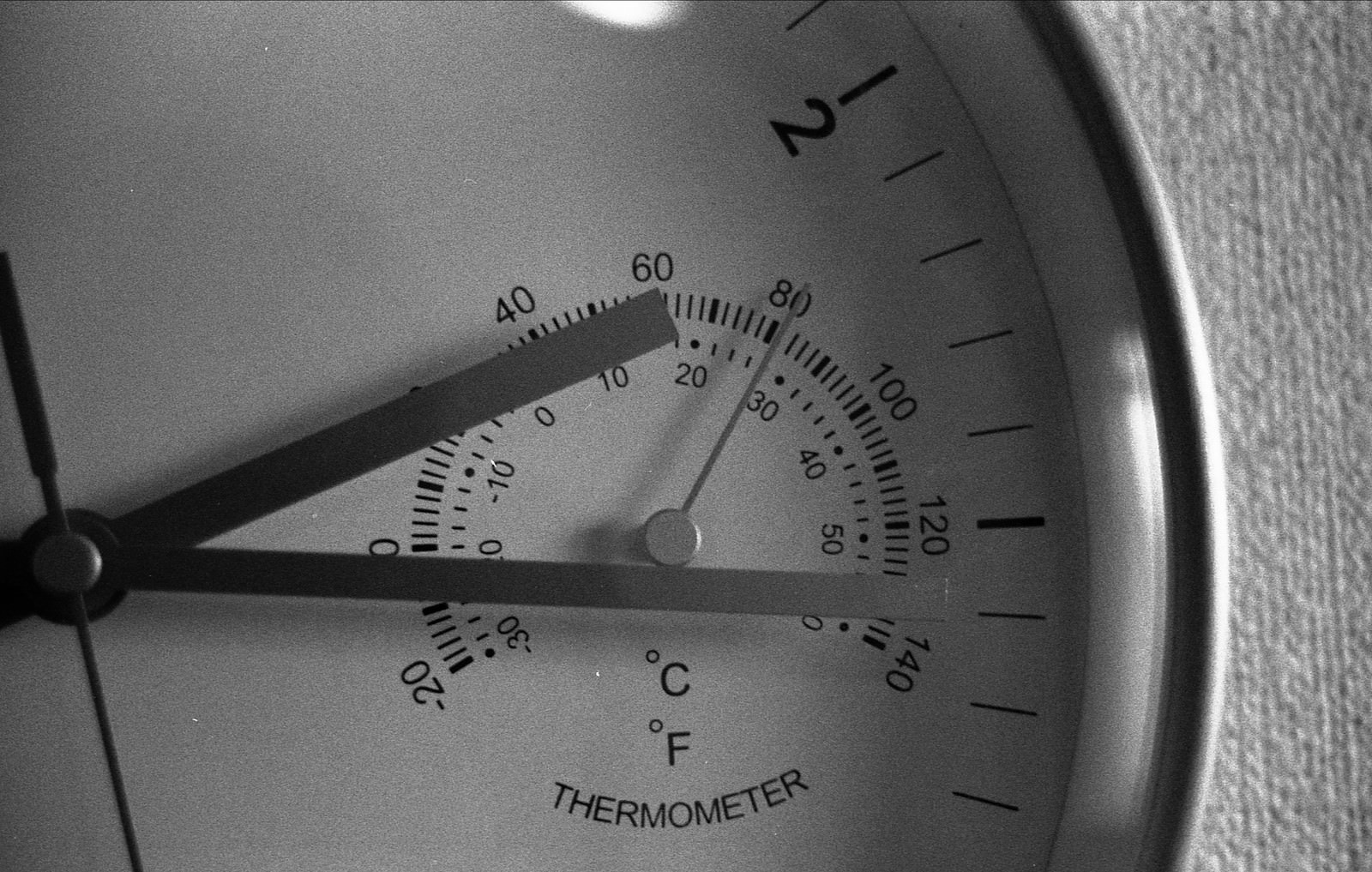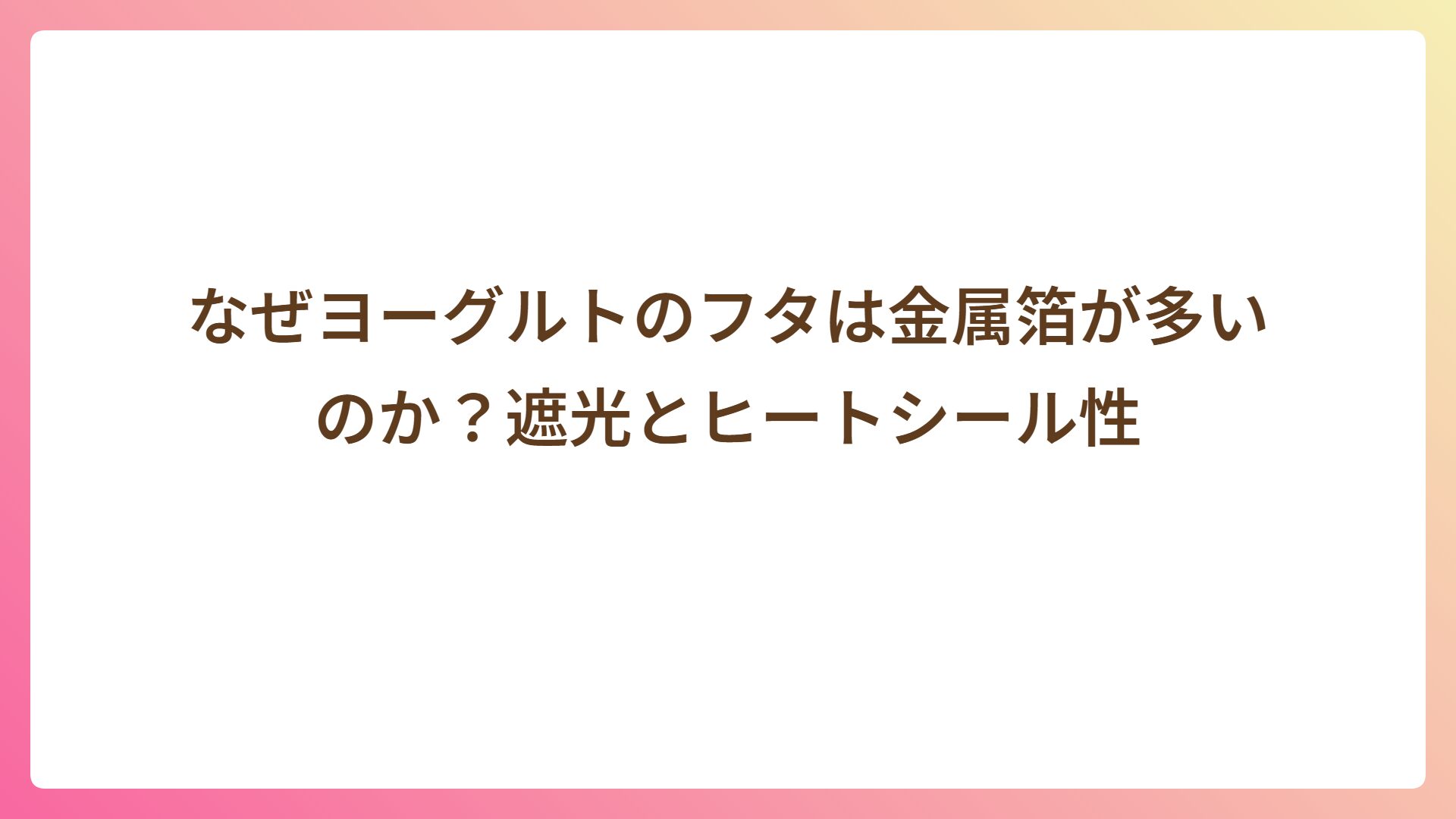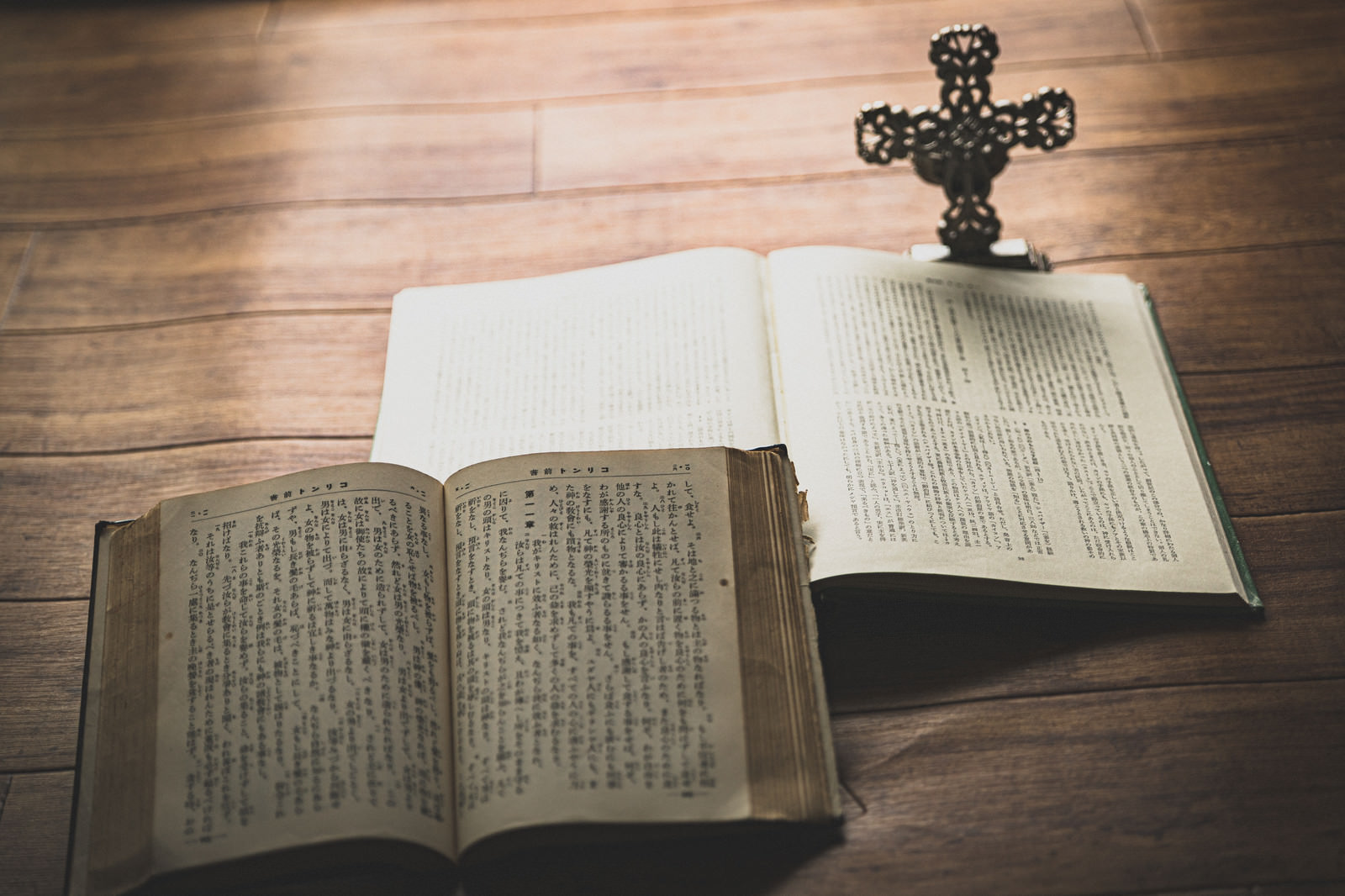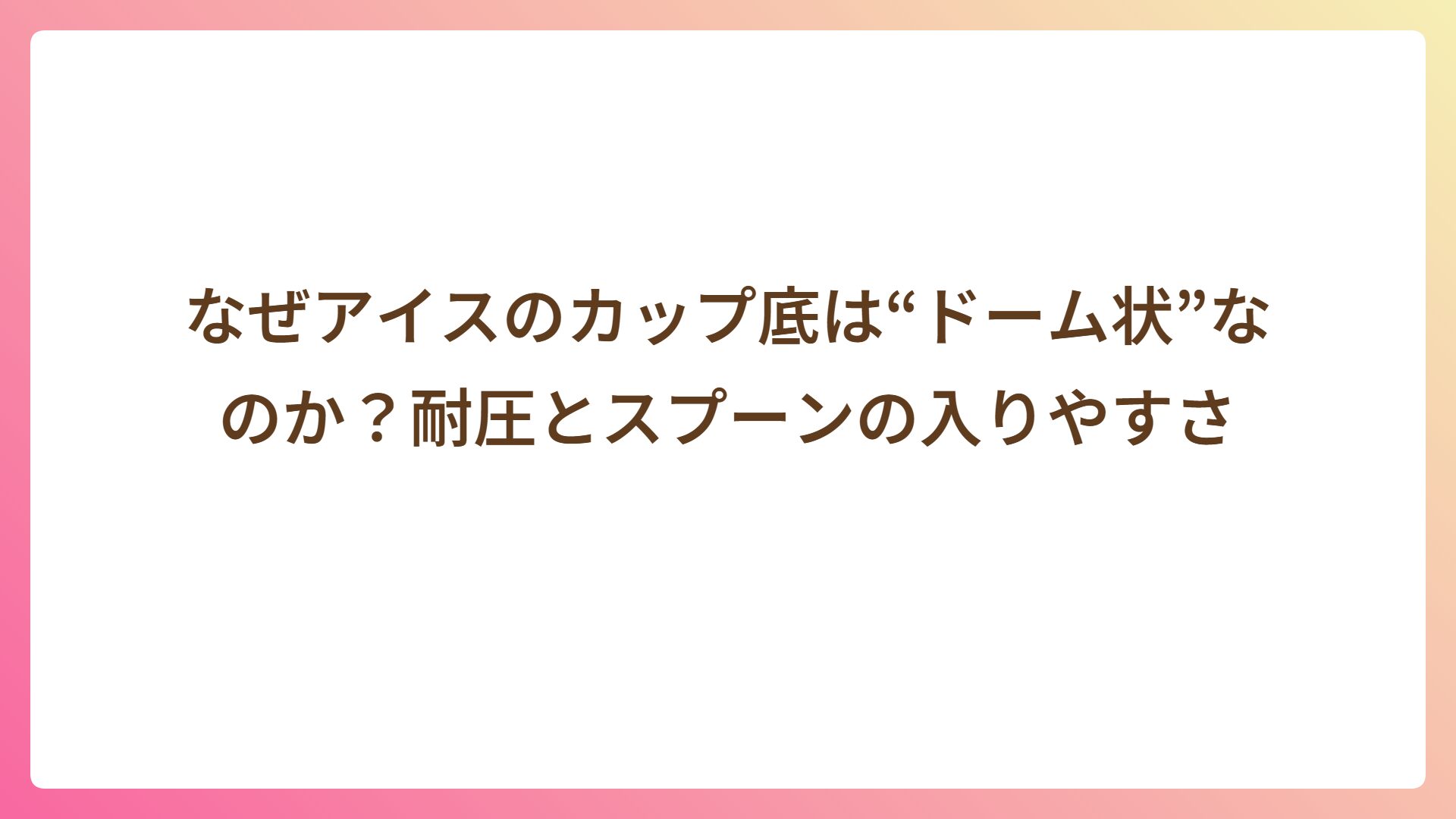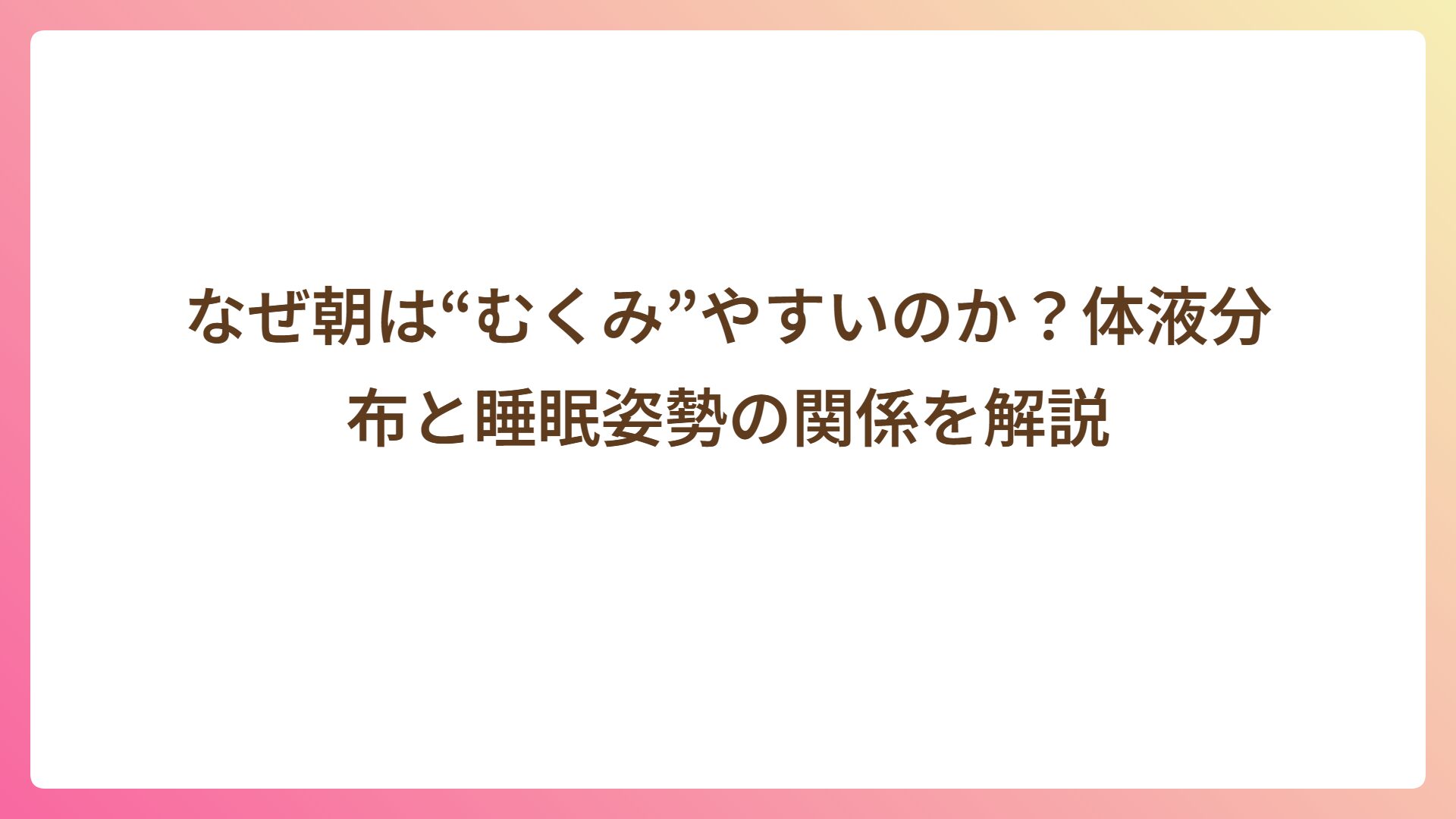「右に出る者がいない」はなぜ“右”?言葉の由来と左右の序列の歴史を解説

「将棋なら彼の右に出る者はいない」と聞くと、「彼は非常に強く、他に勝てる人はいない」という意味だとわかりますよね。
この表現には、「右=上位」「左=下位」といった横並びでの序列の意識が含まれています。
でも、ふと疑問が浮かびます――なぜ“右”が上で、“左”が下”なのでしょうか?
「右に出る者がいない」の語源は古代中国にある
辞書を引くと、「古代中国では右を上席とする制度があり、そこからこの表現が生まれた」とされています。
たしかに、左側に降格されることを意味する「左遷(させん)」なども、同じ価値観に基づいているように見えます。
つまり、「右側=高位、左側=低位」という意識は、古代中国の序列文化に由来しているというわけです。
この説明だけを見れば、「なるほど」と納得してしまいそうですが、実はこの考え方には例外も存在します。
「左大臣」のほうが上位?日本の例外
日本の歴史を学んだことがある方ならご存じの通り、古代の官職「左大臣」と「右大臣」では、左大臣のほうが右大臣よりも上の役職です。
これは、日本の律令制度が古代中国の制度を取り入れたものであるにも関わらず、先ほどの「右が上」という理屈とは矛盾するように思えます。
なぜこのような違いが生まれたのでしょうか?
古代中国でも「左右の優劣」は一貫していなかった
実は、古代中国における「左右の序列」も時代や王朝によって異なっていたのです。
漢和辞典『新漢語林』によると:
- 周の時代:左が上位
- 戦国時代・秦・漢:右が上位
- 六朝時代・唐・宋:再び左が上位
- 元:右が上位
- 明・清:左が上位
このように、時代ごとに「どちらが上か」が頻繁に変わっていたことがわかります。
日本では、それぞれの時代に定着した語彙や制度をそのまま取り入れてきたため、結果的に「右に出る者がいない」と「左大臣が上位」といった矛盾する表現が同居してしまったのです。
「右翼」「左翼」の語源はフランス革命
ちなみに、政治思想の対立を表す「右翼」「左翼」という言葉も、もともとは左右の席順に由来します。
この言葉が生まれたのは、18世紀のフランス革命期。国民議会において、議長席から見て:
- 右側に:保守・穏健派
- 左側に:急進・改革派
が座っていたことから、思想の立場を表す言葉として使われるようになったのです。
この場合、右が上位というわけではなく、単なる配置の違いから定着した用語です。
表現の背景を知ると、言葉がもっと面白くなる
「右に出る者がいない」という表現には、古代中国の価値観と、それを受け継いだ日本の制度の影響が複雑に絡んでいます。
左右の序列は一貫したものではなく、文化・時代・政治制度によって揺れ動いてきたものなのです。
こうした由来を知ることで、普段何気なく使っている言葉にも歴史や文化の奥深さを感じられるかもしれません。