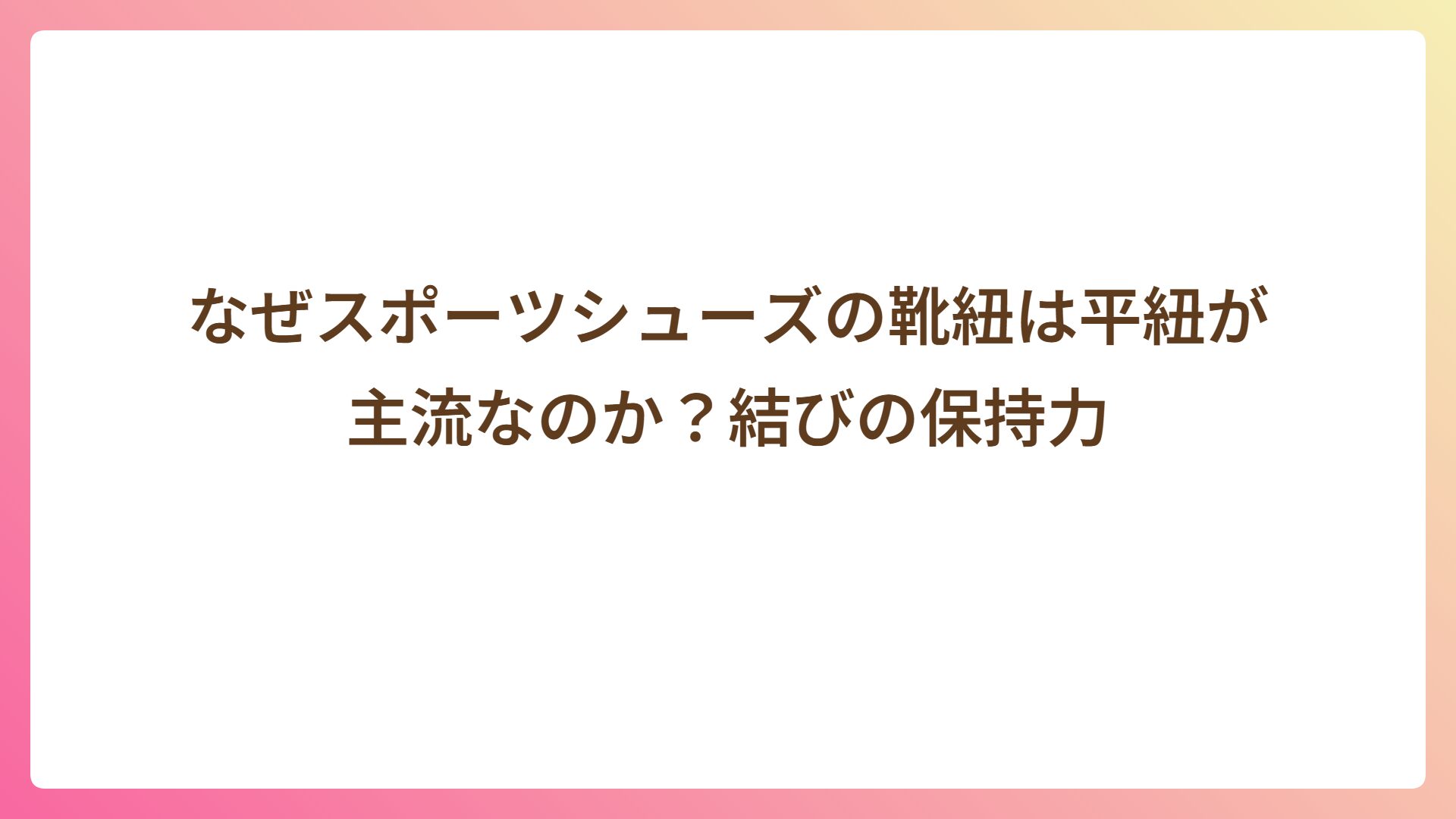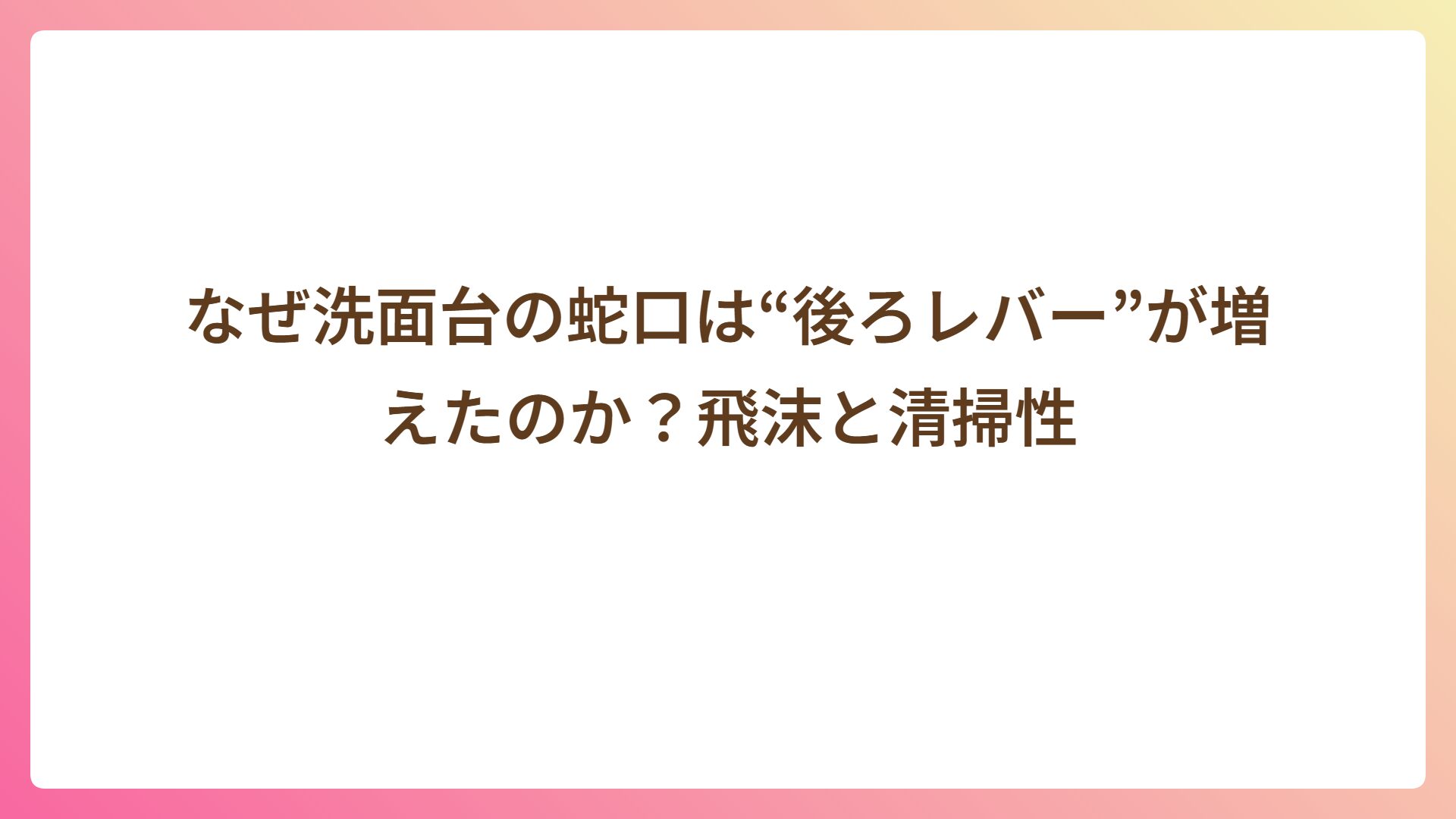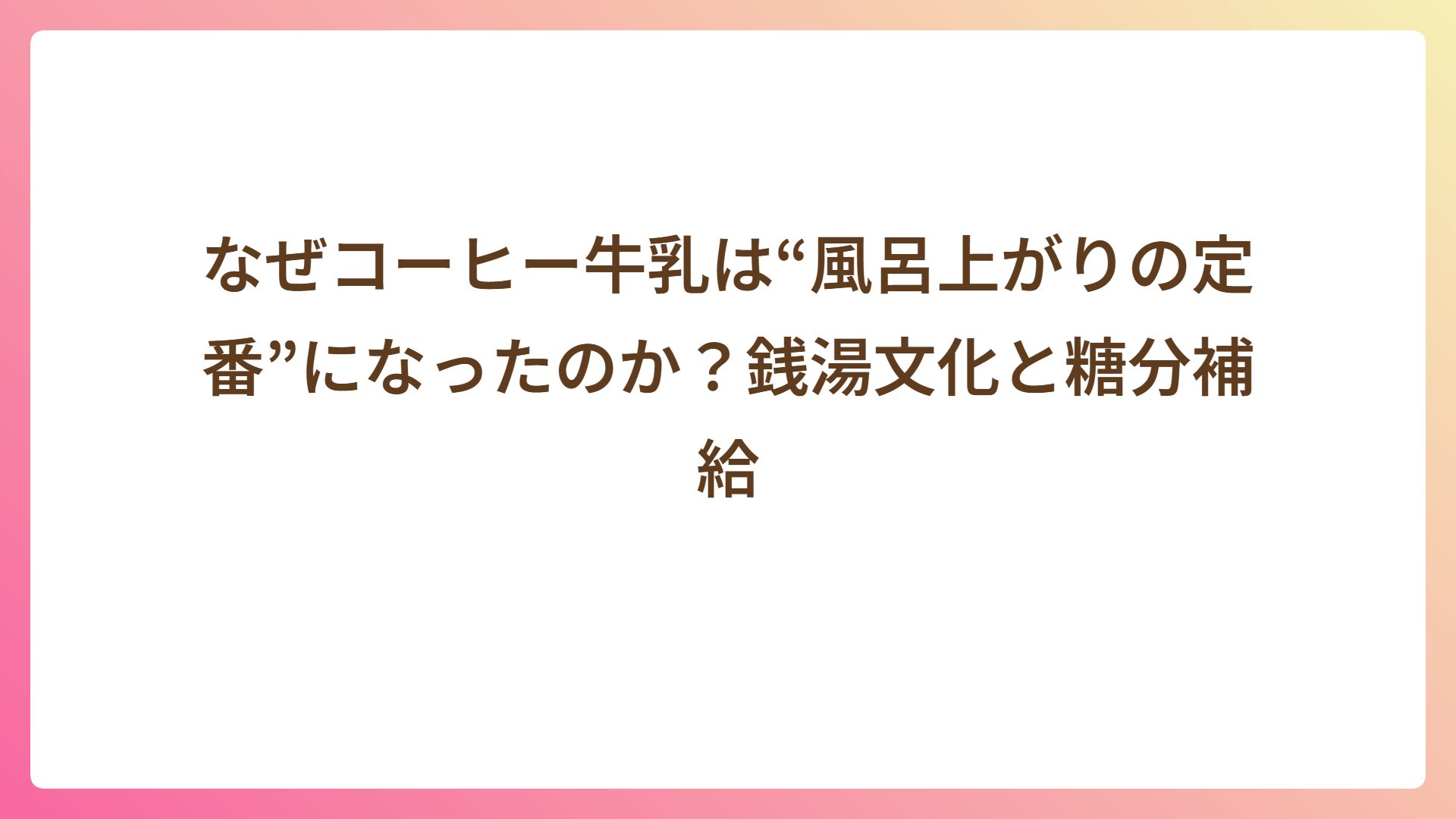なぜ納豆は“朝食”の顔になったのか?製造技術と配給の歴史
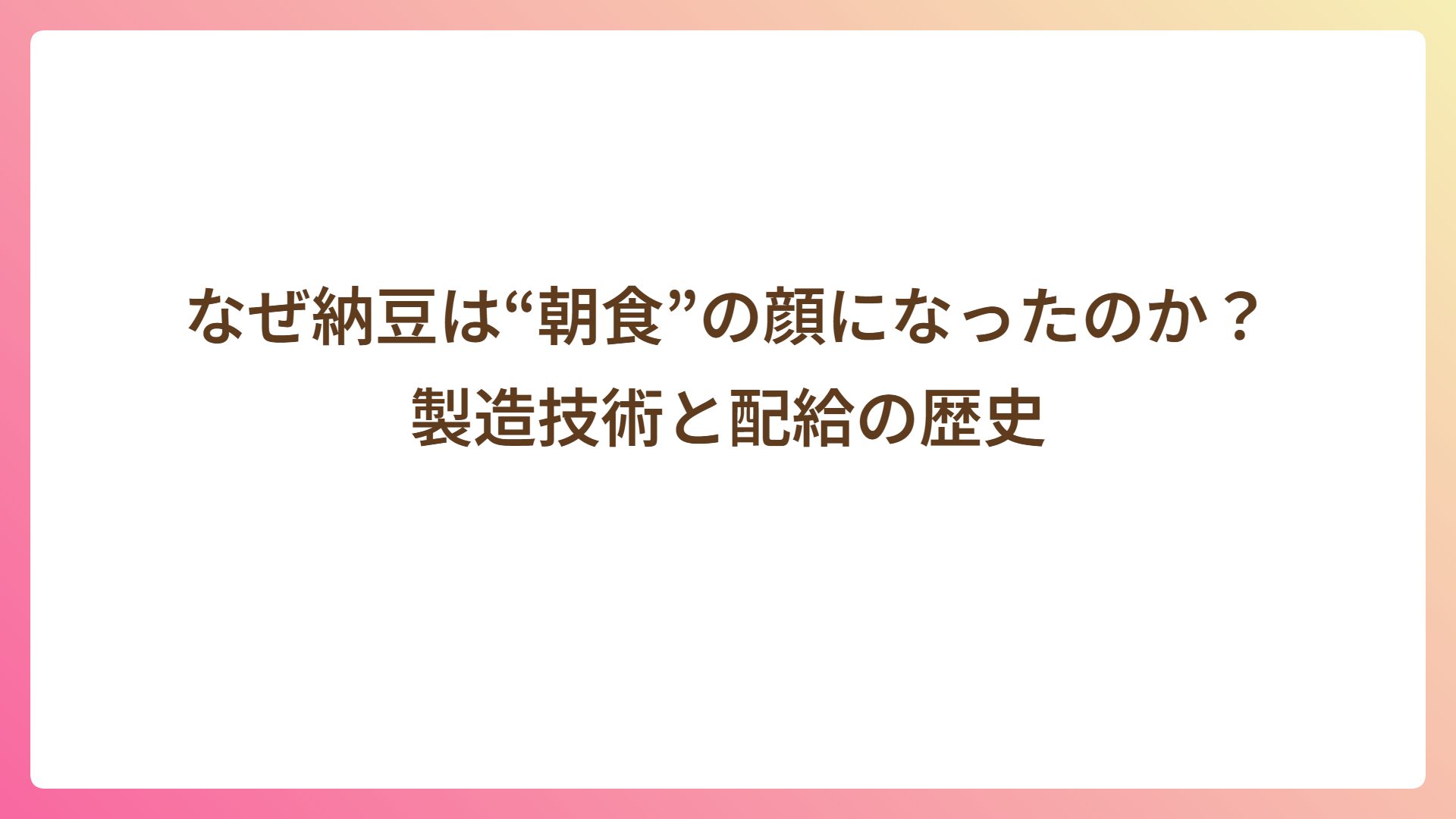
ご飯に味噌汁、そして納豆。
日本の典型的な朝ごはんといえば、この組み合わせを思い浮かべる人が多いでしょう。
しかし、納豆はなぜ“朝食の顔”という地位を得たのでしょうか?
そこには、戦後の食糧政策と製造技術の進化が深く関係しています。
納豆はもともと「保存食」だった
納豆の起源は1000年以上前にさかのぼるとされ、
稲わらに包んだ大豆が自然発酵してできたのが始まりです。
発酵食品である納豆は、冷蔵設備のない時代でも比較的日持ちが良く、
保存性の高い栄養源として重宝されてきました。
そのため、農作業の合間に食べる“野良仕事のエネルギー食”や、
寒い季節のたんぱく源として位置づけられていましたが、
当時は必ずしも「朝食専用」というわけではありませんでした。
戦後の配給制度で「朝食=納豆」が定着
第二次世界大戦後、食糧不足の中で日本政府は納豆を重要なたんぱく供給源として推奨しました。
昭和20年代には、学校給食や家庭用配給の一部として納豆が大量に流通。
その多くが朝食に提供されたことで、
「朝ごはんに納豆を食べる」習慣が全国に広まりました。
さらに、当時は炊き立てのご飯が朝にしか食べられなかったため、
納豆+ご飯+味噌汁というセットが“完全栄養食”として定着していきます。
納豆の大量生産と冷蔵流通の進化
昭和30年代以降、納豆の製造技術が急速に工業化します。
わら納豆から発泡スチロール容器への切り替え、
冷蔵輸送や真空包装の普及によって、
一年中どこでも手に入る「常備食品」へと変化しました。
この頃からスーパーや商店の朝市で納豆が並ぶようになり、
“朝食の定番”としてのイメージが完全に定着します。
調理の手間がなく、すぐ食べられる点も忙しい家庭に支持されました。
テレビCMと健康ブームによる再評価
1970年代以降、テレビCMや広告で納豆は「健康食品」として盛んに宣伝されました。
「1パックで1日分のたんぱく質」「朝にぴったりの発酵食品」といったキャッチコピーが広まり、
朝=健康=納豆というイメージが国民意識に浸透していきます。
特に「ご飯にかける」「混ぜるだけ」という手軽さは、
朝の限られた時間にぴったりの食習慣として定着しました。
地域差を超えて全国的に普及
もともと関西では納豆を食べる文化が薄く、
「においが苦手」とされることもありました。
しかし冷蔵保存の改良により、においの少ない製品が登場し、
1990年代には全国的な消費拡大を迎えます。
現在では、朝食のみならず昼食・夜食でも食べられますが、
“朝の定番”というイメージは今も根強く残っています。
まとめ
納豆が朝食の顔となったのは、
戦後の配給制度・技術革新・健康志向の三つの流れによるものです。
保存性に優れ、混ぜるだけで栄養満点。
戦後の食糧危機を支えた実用性が、
やがて日本人の朝を象徴する「国民的朝食」へと昇華したのです。