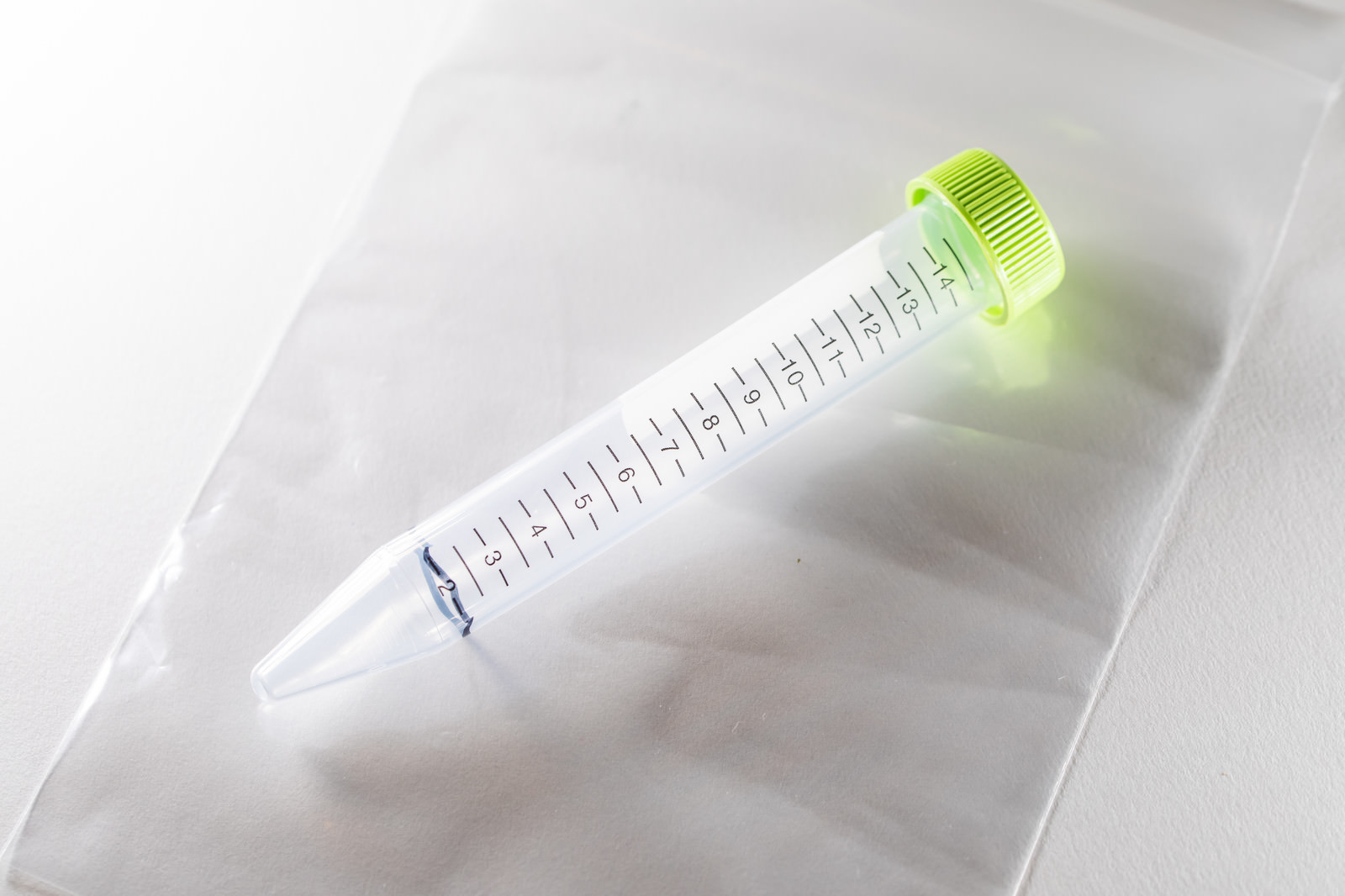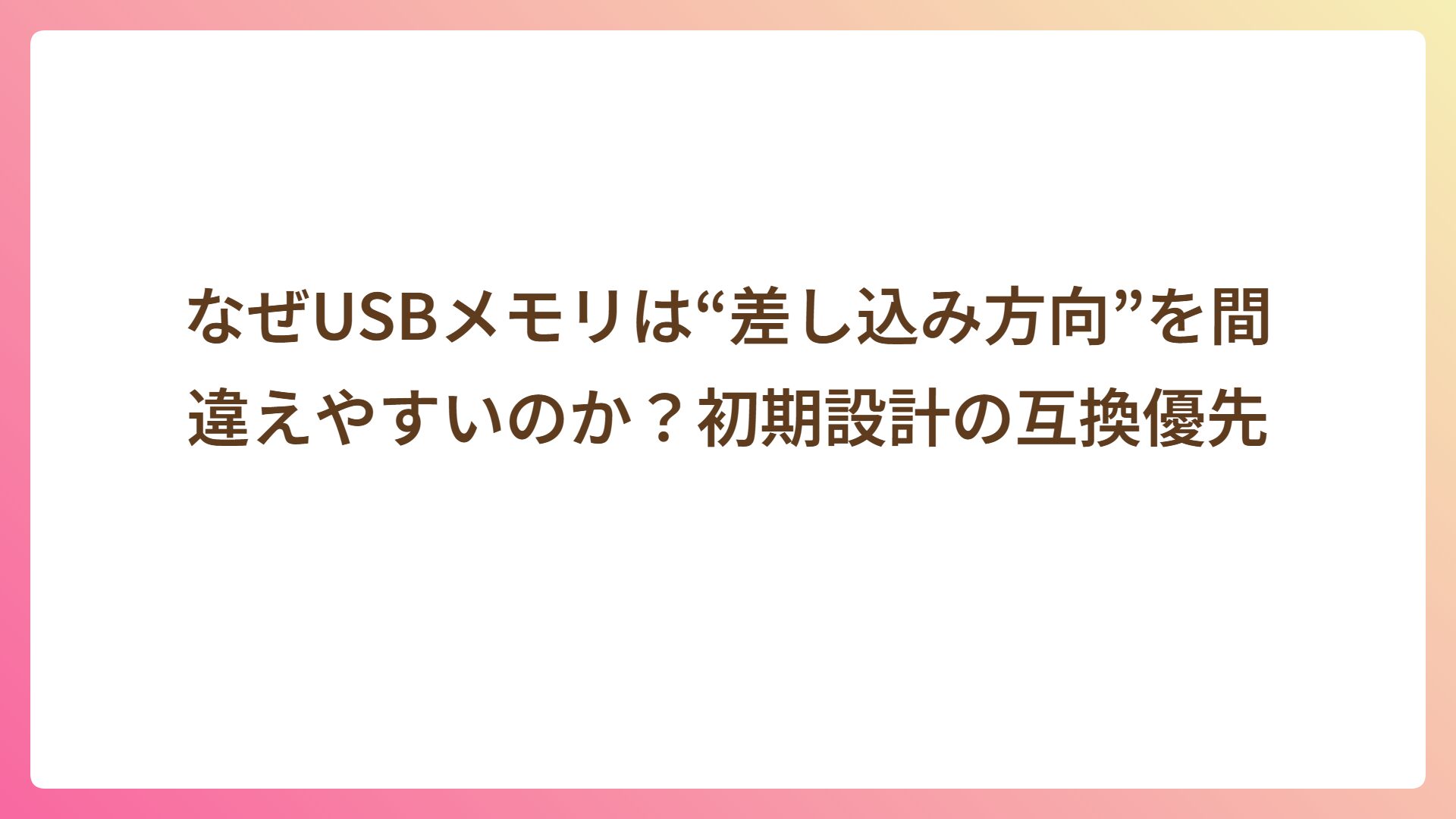なぜ七草粥は“春の七草”に限るのか?季節と薬効の体系
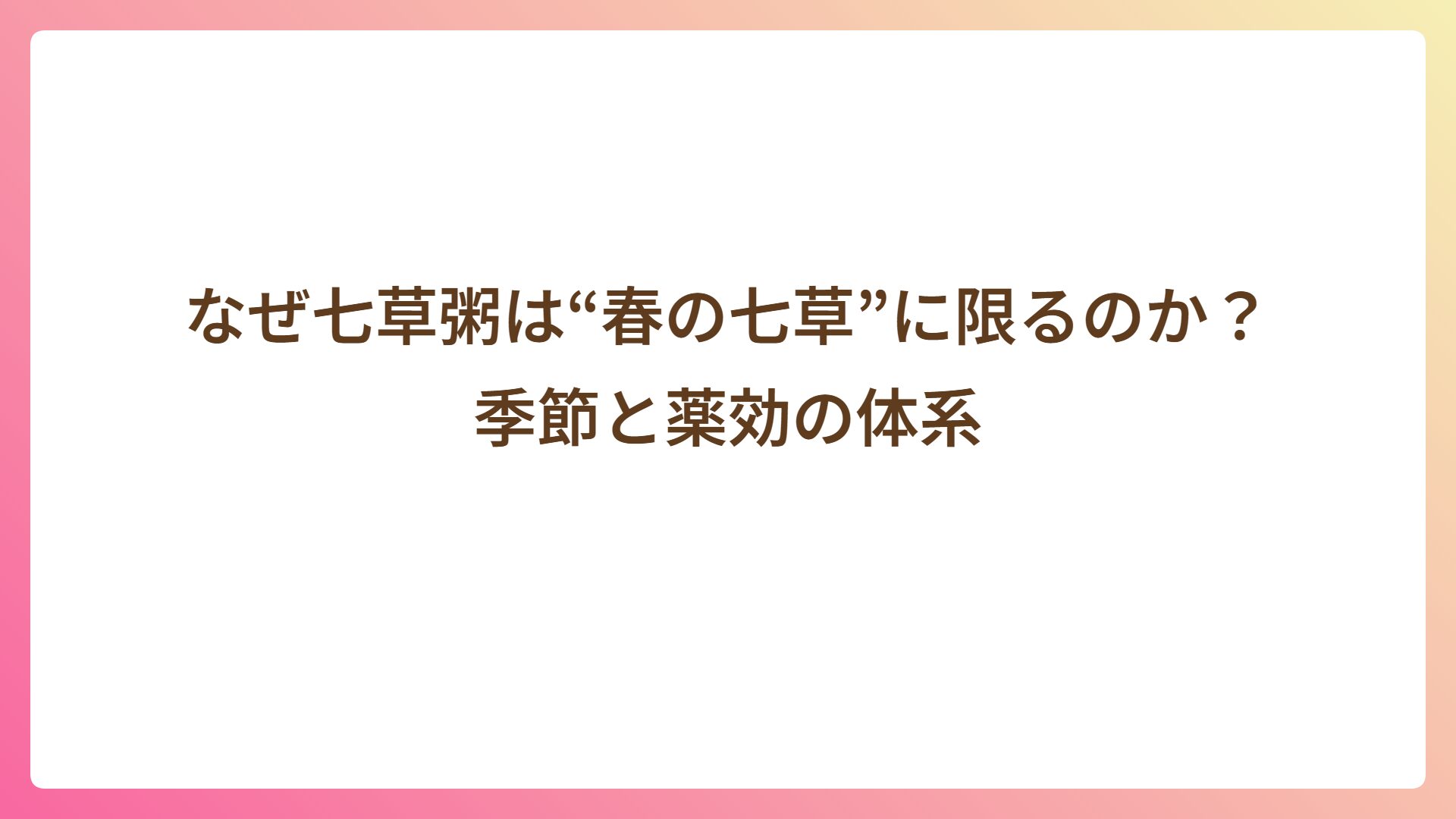
1月7日の朝に食べる七草粥。
せり・なずな・ごぎょう・はこべら・ほとけのざ・すずな・すずしろ——。
この「春の七草」は全国的に知られていますが、
なぜ“春”の草だけが選ばれているのでしょうか?
その理由は、早春の自然エネルギーと薬草文化が融合した、日本独自の養生体系にあります。
七草粥は“人日(じんじつ)の節句”の風習から
七草粥の行事は、中国の「人日(じんじつ)」という節句に由来します。
陰暦1月7日は「人を大切にする日」とされ、
七種の菜を煮て無病息災を願う習慣がありました。
この風習が平安時代に日本へ伝わり、
当初は七種の穀物(七種粥)でしたが、
のちに春の若菜を食べる“若菜摘み”の風習と結びつき、
現在の「春の七草粥」として定着したのです。
“春の七草”は季節の生命力を食すもの
春の七草はいずれも、冬を越えて最初に芽吹く野の若菜。
まだ雪の残る早春に地面から顔を出すこれらの草は、
古くから生命の再生を象徴する食材とされてきました。
それぞれの草には、体を整える薬効もあります。
| 草の名前 | 主な効能 | 象徴する意味 |
|---|---|---|
| せり | 解熱・整腸作用 | 明朗・競り勝つ |
| なずな | 利尿・解毒作用 | なでて汚れを除く |
| ごぎょう(母子草) | 咳止め・のどの薬 | 仏の安らぎ |
| はこべら | 歯茎の健康・整腸 | 繁栄・増える |
| ほとけのざ | 健胃作用 | 仏の座=安泰 |
| すずな(かぶ) | 消化促進・胃腸を整える | 神を呼ぶ鈴 |
| すずしろ(大根) | 消化促進・風邪予防 | 清白・無垢 |
いずれも、**冬に弱った体を目覚めさせる“春の薬草”**として理にかなっているのです。
なぜ秋や冬の七草ではないのか?
日本には「秋の七草」もありますが、
こちらは“鑑賞の草”であり、食用ではありません。
万葉集に詠まれた秋の七草(萩・尾花・葛・撫子・女郎花・藤袴・桔梗)は、
実りの秋を愛でるための象徴的な草花でした。
一方、春の七草は「食べることで生命力を取り込む」実践的な草。
寒さの中で芽吹くその力を体に取り入れることで、
季節の変わり目に体調を整える“薬食同源”の思想が反映されています。
七草粥は“リセットの食文化”
正月のご馳走で疲れた胃を休め、
野草の香りで体を清める。
七草粥は、冬の終わりに体をリセットするための食文化でもあります。
また、七草の数“七”には、
古代中国の陰陽五行における「調和・完全性」の意味があり、
一年の始まりに“七種の力”を体に取り込むことで、
邪気を払い、健康を保つという信仰が込められています。
“若菜摘み”と女性の春支度
平安時代には、七草粥の前に「若菜摘み」という行事が行われていました。
貴族の女性たちは早春の野に出て若菜を摘み、
春の訪れと生命の芽吹きを祝ったといいます。
この風習はやがて、
年神を迎える新春の神事と結びつき、
「新しい年の命をいただく食儀礼」として七草粥が位置づけられました。
まとめ
七草粥が“春の七草”に限られるのは、
冬を越えて芽吹く生命の力を食すことで、心身を整える養生文化だからです。
- 七草は早春の薬効植物であり、再生の象徴
- 食して冬の疲れを癒し、無病息災を願う
- 季節の生命サイクルに寄り添った食のリズム
七草粥は、単なる行事食ではなく、
“春を取り入れる食養生”という日本の知恵の結晶なのです。