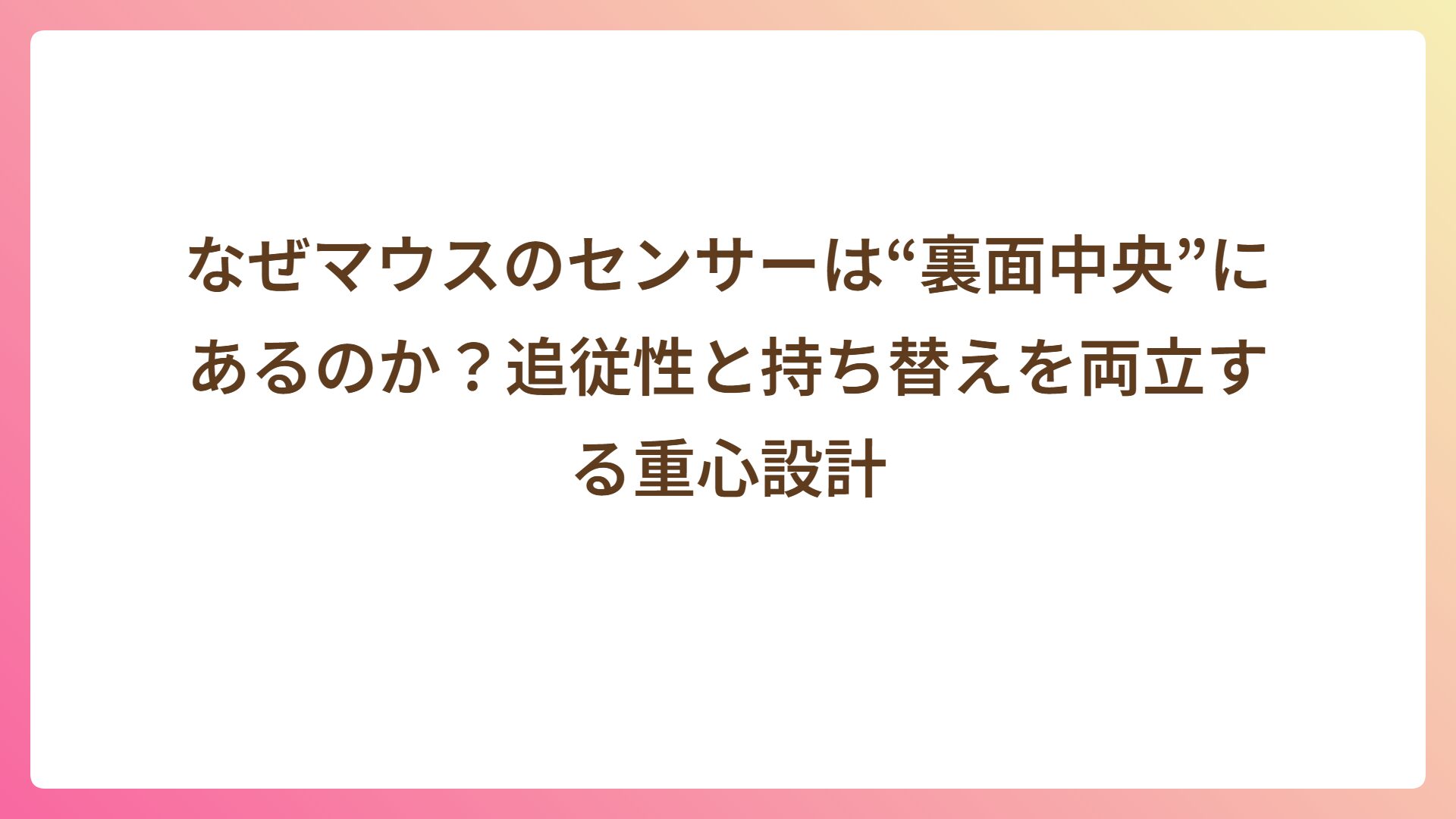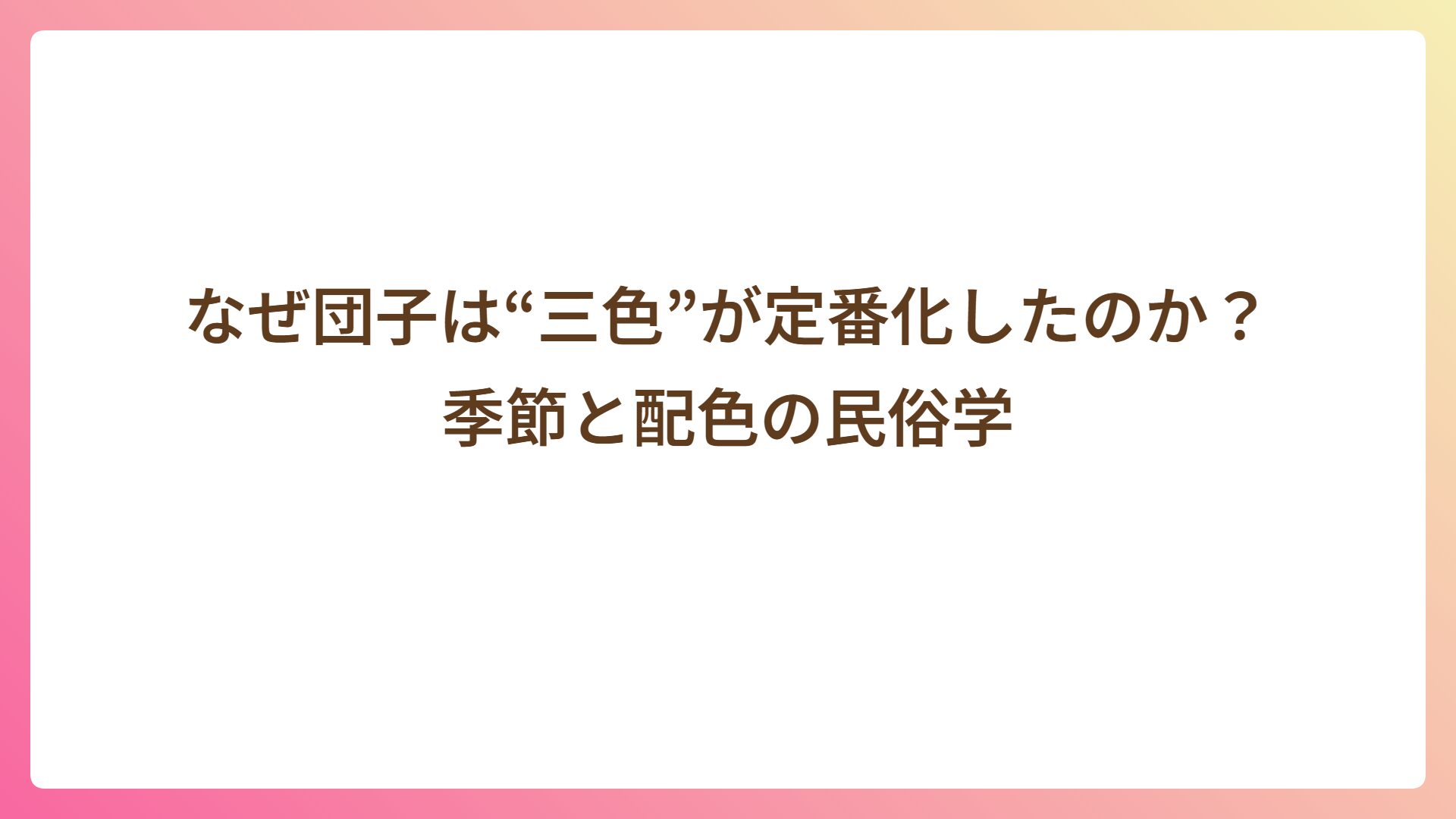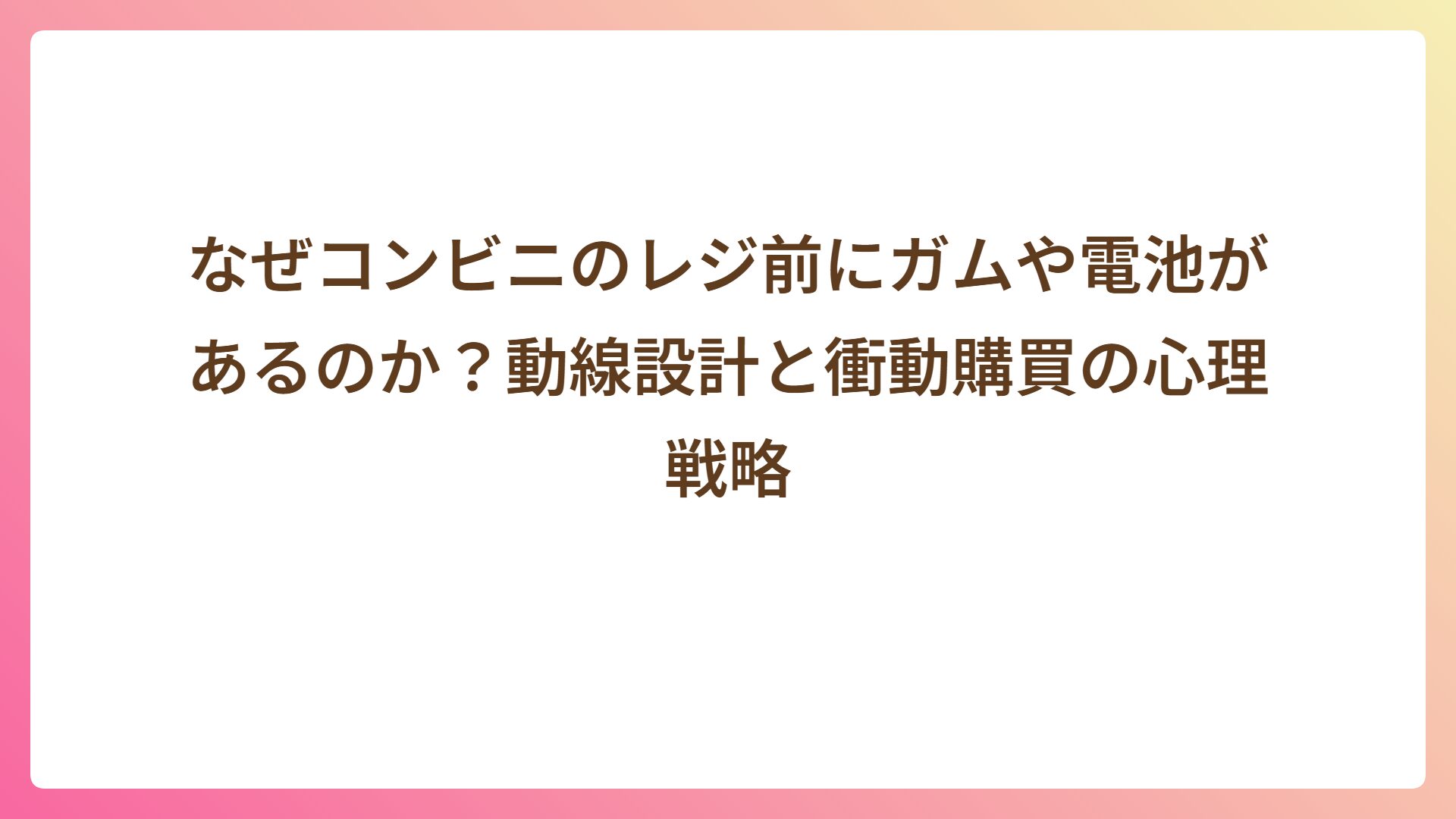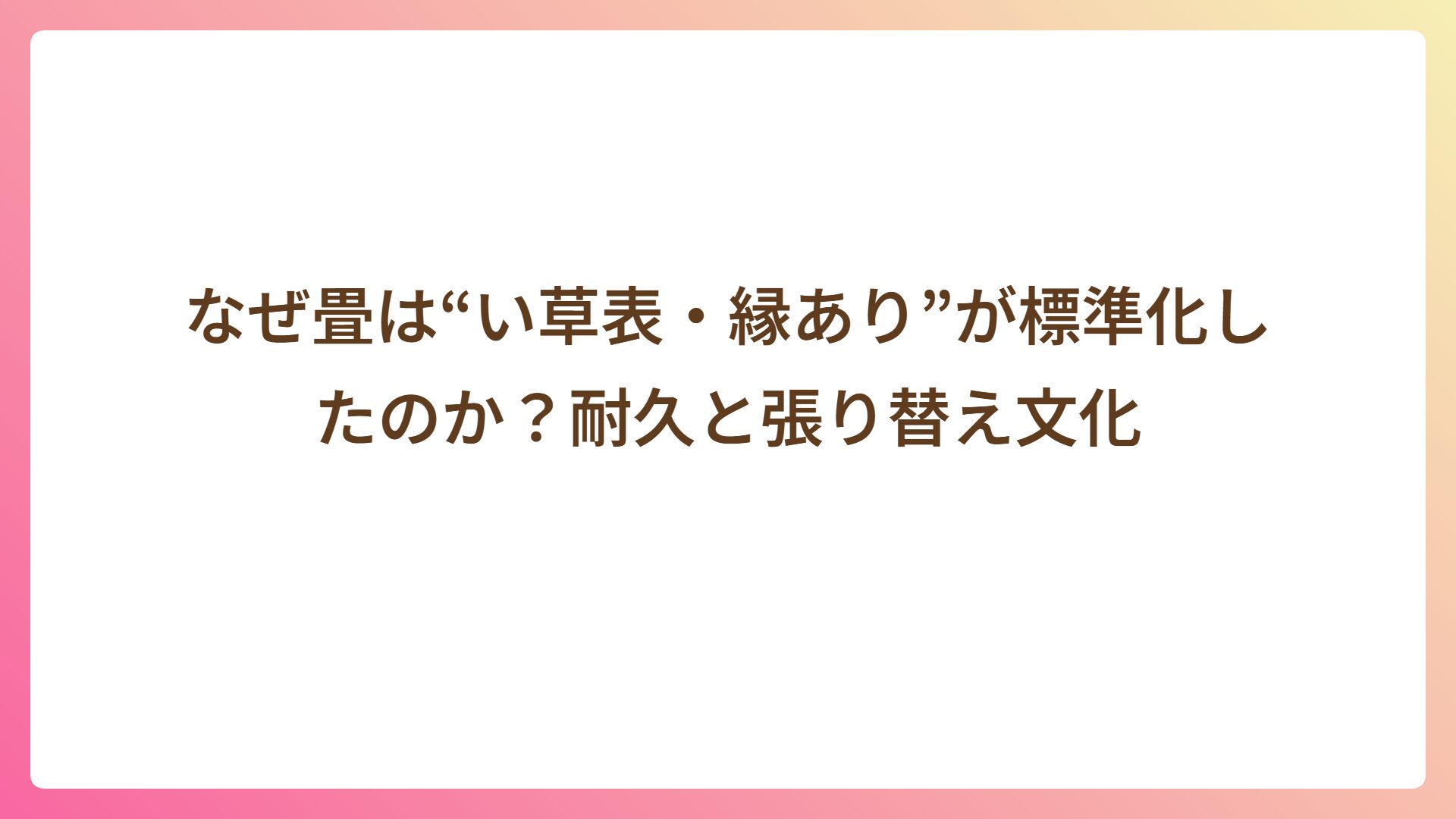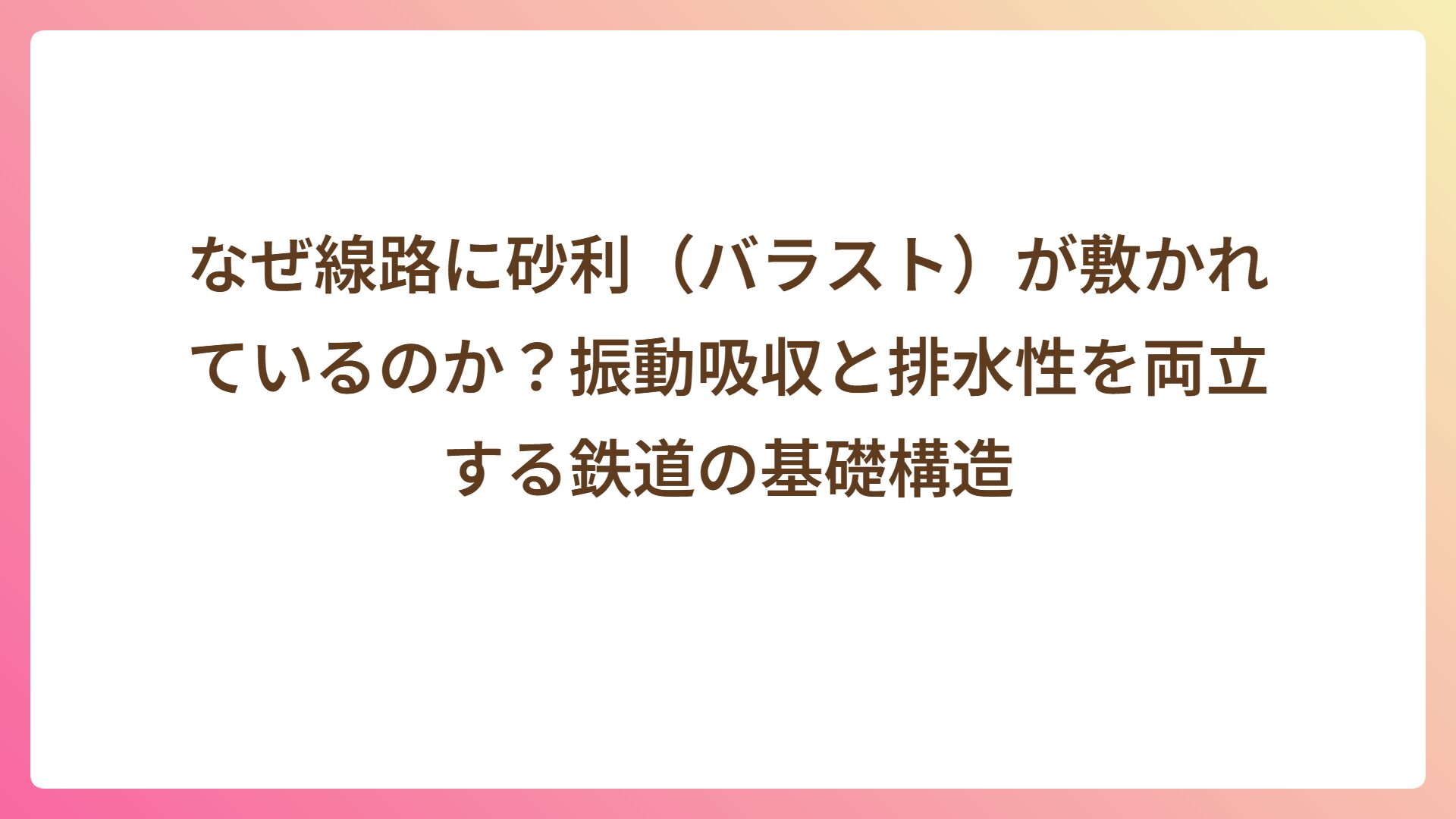日本酒の「辛口」と「甘口」の違いとは?味の基準と表現の由来

居酒屋のメニューや酒屋のラベルでよく見かける「辛口」「甘口」という表現。
カレーなら辛さの違いですが、日本酒に唐辛子や砂糖は使われていません。一体この「辛口」「甘口」とは何を意味しているのでしょうか?
日本酒の甘口・辛口は「糖分」と「酸度」で決まる
日本酒の味わいを示す「甘口」や「辛口」は、基本的に含まれる糖分の量と酸度によって決まります。
- 糖分が多い=甘口
- 糖分が少ない=辛口
が基本ですが、実はそれだけではありません。
同じ糖分量であっても、酸度が高いと辛口に感じやすく、酸度が低いと甘口に感じやすくなるため、日本酒の甘辛度は糖分と酸度のバランスによって判断されます。
つまり、日本酒における「辛口/甘口」は、カレーのような「辛味」や「刺激」ではなく、相対的な甘さの印象を表しているのです。
なぜ「甘口」の反対が「辛口」なのか?
ではなぜ、日本酒では「甘くない=淡麗」や「さっぱり」ではなく、「辛口」と呼ばれるようになったのでしょうか。
この表現の歴史は江戸時代にまでさかのぼります。井原西鶴の著書『日本永代蔵』にも「所酒のから口」という表現が登場し、当時から味の評価として「辛口」が使われていたことがわかります。
また、味覚は「甘味・塩味・酸味・苦味・旨味」の5つしかなく、「辛さ」は味ではなく痛覚による刺激として認識されます。江戸時代の日本酒は酸味が強く、アルコール度数も高かったことから、「刺激のある=辛い」と感じられたのかもしれません。
つまり、「辛口」とは「甘くないもの」に対して感覚的にそう呼ばれるようになった表現であり、必ずしも辛味成分を意味しているわけではないのです。
おわりに
日本酒の「辛口」「甘口」が、味覚ではなく糖分と酸度のバランスによる印象で決まるというのは意外に感じられたかもしれません。
なんとなくで使っていた味の表現も、知識を深めるとより一層お酒の楽しみ方が広がります。次に日本酒を選ぶ際には、辛口・甘口の意味を思い出してみてくださいね。