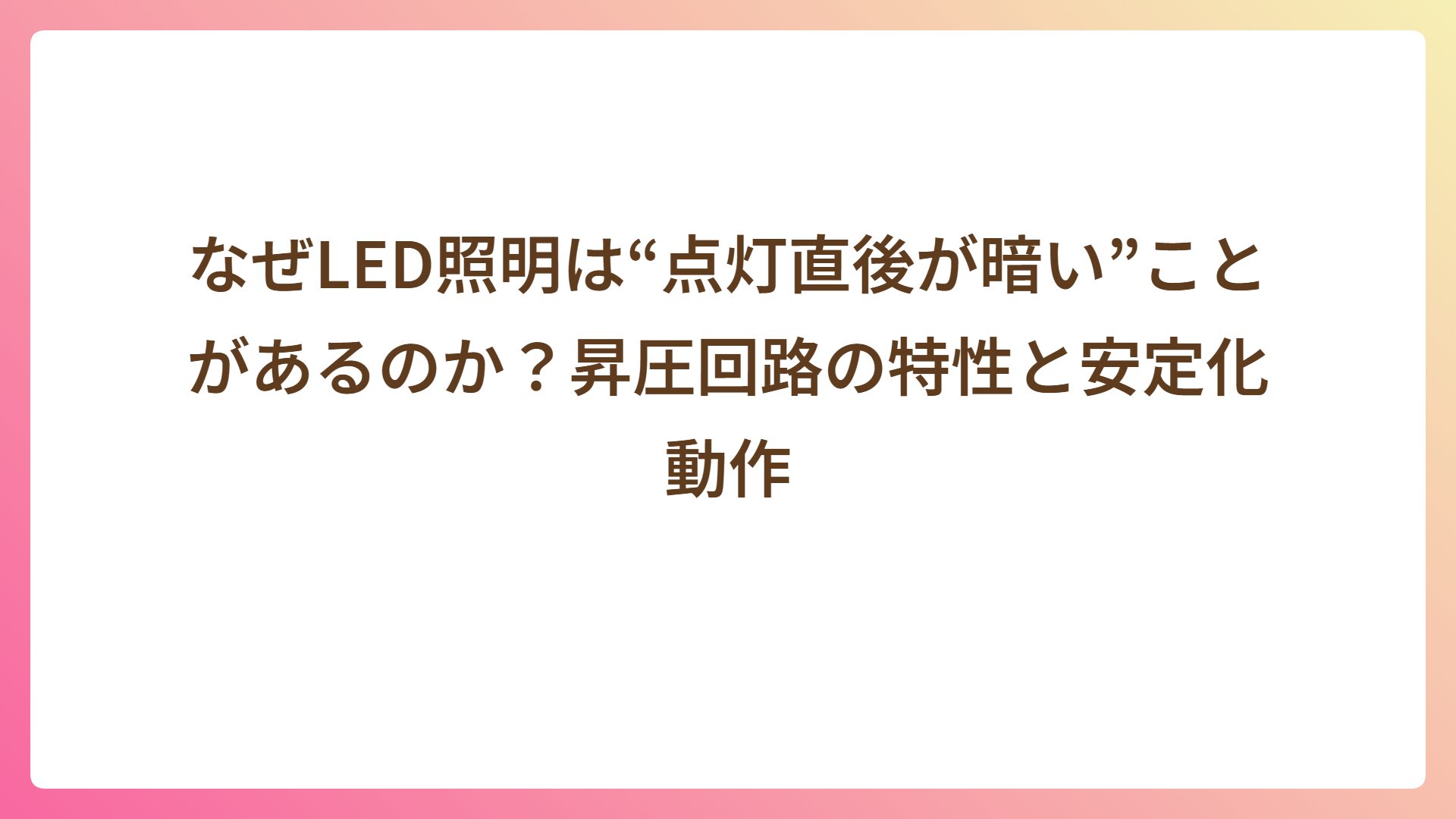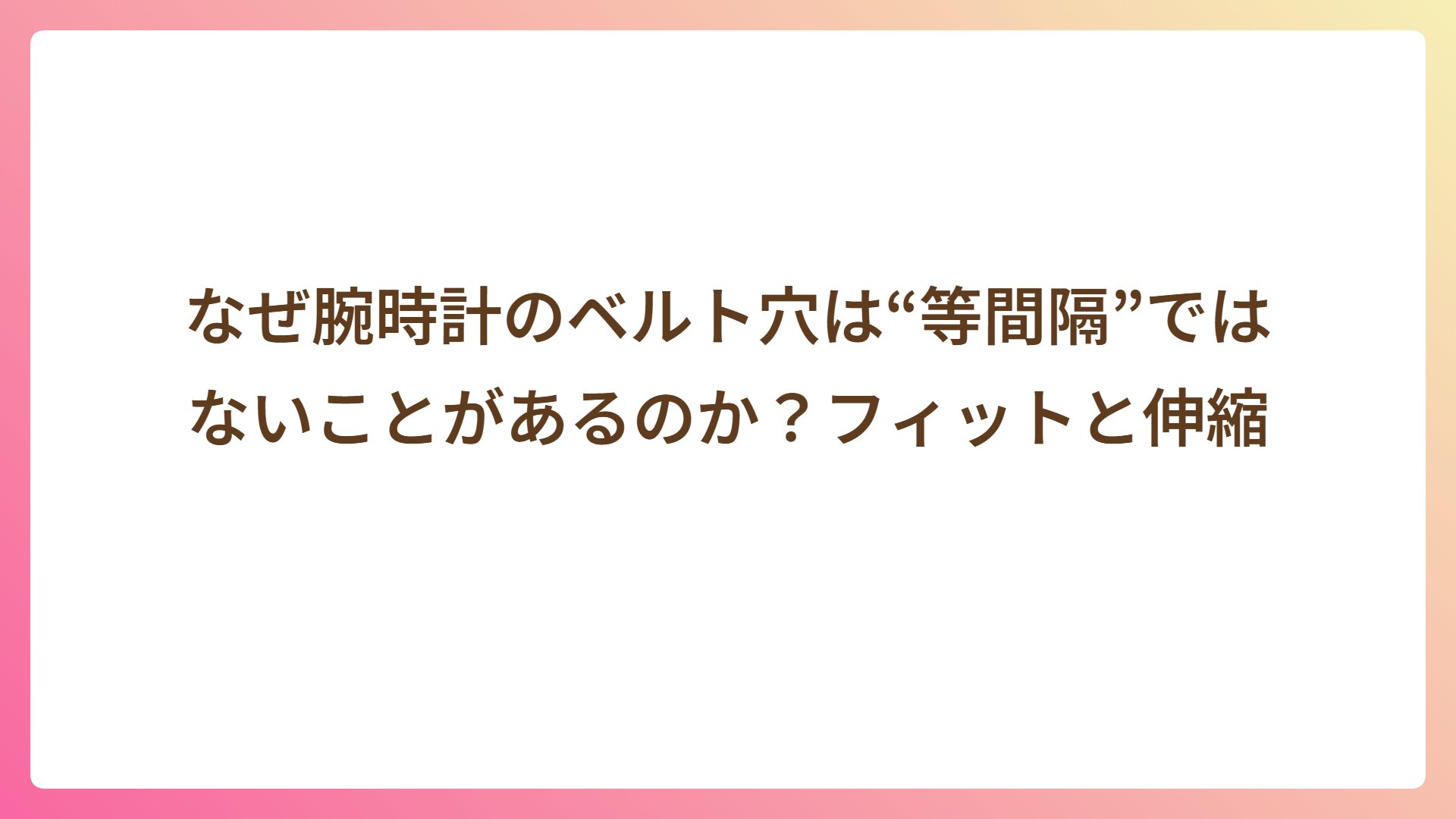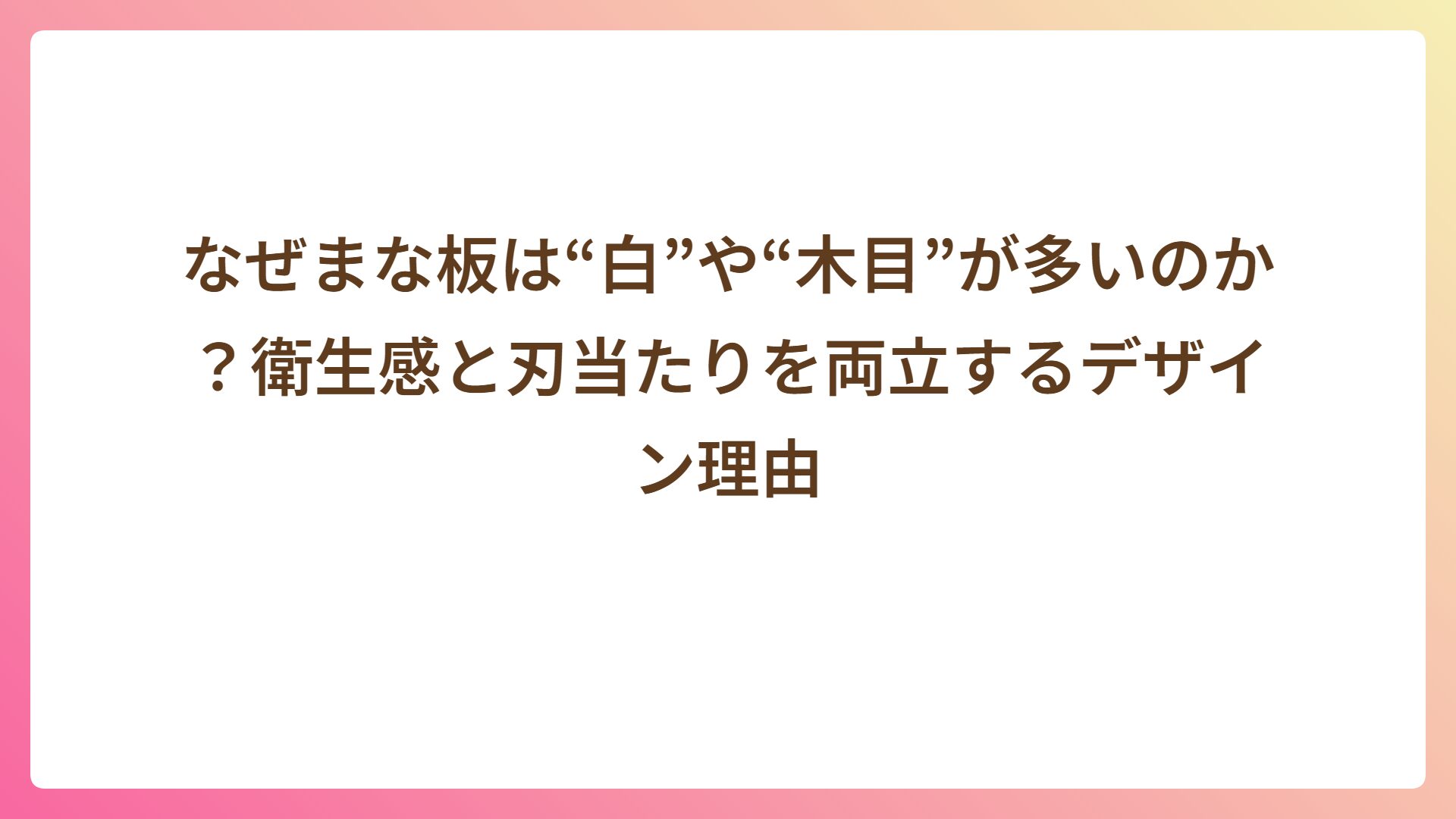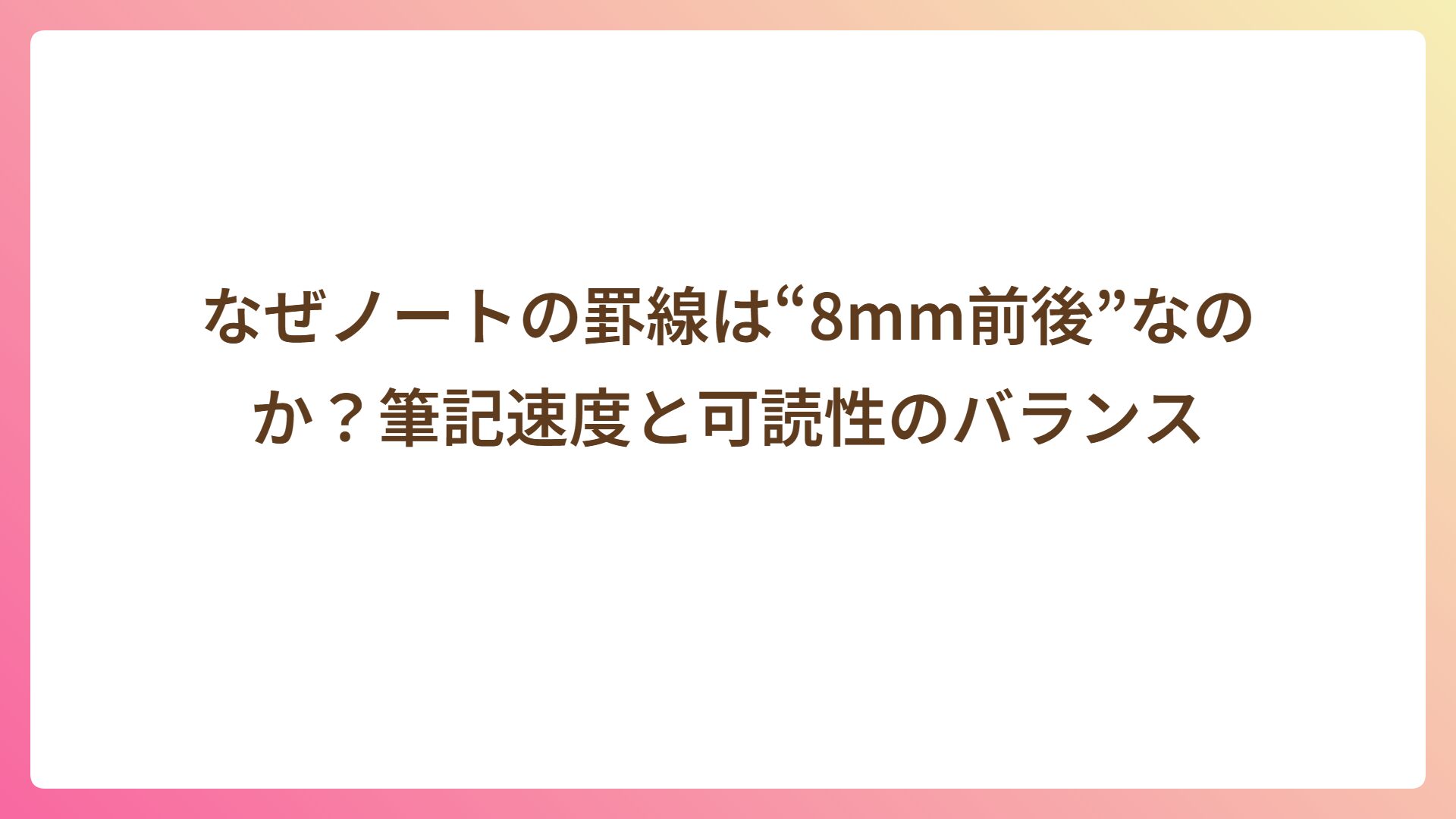なぜ虹の色の順番は世界共通ではないのか?文化と色の認知カテゴリーの不思議

私たちは学校で「虹は七色」と習います。
赤・橙・黄・緑・青・藍・紫――誰もがそう覚えていますが、実はこれは日本だけの常識です。
国によっては虹を六色、あるいは五色として数える文化もあり、
「虹の色」は自然現象ではなく、文化的な“認知の産物”なのです。
虹の色は連続しており、本来“区切り”はない
まず前提として、虹は太陽光が雨粒で分解された連続的な光のグラデーションです。
物理的には「赤から紫までの光のスペクトル」であり、明確な線引きは存在しません。
しかし人間は、その連続した光を「いくつかの色」として認識上で区切ることで理解しています。
つまり、虹の“色数”は自然現象ではなく、言葉と文化の側が決めているのです。
日本が「七色」なのはニュートンの影響
日本で虹が七色とされているのは、江戸時代にニュートンの光学理論が伝わったことがきっかけです。
ニュートンは光の分解実験を行い、
「音階(ドレミファソラシ)」と対応させて虹を7色に分類しました。
その考え方が日本にも伝わり、
明治期の理科教育で「虹=7色」という教えが定着したのです。
つまり、七色という区切りは科学的必然ではなく、教育的・文化的な選択だったのです。
世界の虹の数はさまざま:文化によって異なる色分類
国や地域によって、虹の“色の数え方”はまったく異なります。
| 国・地域 | 一般的な虹の色数 | 主な分類例 |
|---|---|---|
| 日本 | 7色 | 赤・橙・黄・緑・青・藍・紫 |
| アメリカ・イギリス | 6色 | 赤・橙・黄・緑・青・紫(藍を除外) |
| ロシア | 7色または6色 | 青と水色を別扱いすることも |
| ドイツ・フランス | 5色程度 | 赤・黄・緑・青・紫(中間色をまとめる) |
| ナミビア(ヒンバ族) | 3〜4色 | “緑”と“青”を区別しない言語体系 |
このように、虹の色数は文化や言語によって可変的であり、
どの数が“正しい”というわけではありません。
言語が「色の見え方」を変える?──認知カテゴリーの違い
人間の脳は、言語を通じて世界を分類しています。
たとえば、日本語では「青」と「緑」を明確に区別しますが、
古代日本語では両方を「青(あお)」と呼んでいました。
同様に、言語に「藍」や「橙」という語が存在しない文化では、
虹の中間色を独立した色として認識しにくくなります。
つまり、「どの色をひとつの“まとまり”として見るか」は、
言語が作る“認知カテゴリー”に依存しているのです。
この現象は「言語相対性仮説(サピア=ウォーフ仮説)」として知られています。
言葉の違いが、色や形、時間の感じ方にまで影響を与えるという考え方です。
「虹の七色」は文化の鏡
日本の「七色」という数え方は、
- 西洋科学(ニュートン理論)の影響
- 日本語における豊かな色表現文化
- 教育での固定的イメージ
といった要素が重なって生まれたものです。
一方で、アメリカでは「藍」を省き6色に簡略化し、
さらに多くの文化では「五色」「四色」が標準です。
どの文化の虹も、それぞれの言語と美意識の反映なのです。
まとめ:虹の色数は“自然”ではなく“文化”が決める
虹の色が国によって違うのは、
- 物理的な光は連続している
- どこで区切るかを決めるのは文化や言語
- 言葉が“見え方”そのものを変える
という、自然現象と人間の認知の境界に関わる問題です。
つまり、虹を見るという行為そのものが、
その人の「文化のレンズ」を通した体験なのです。