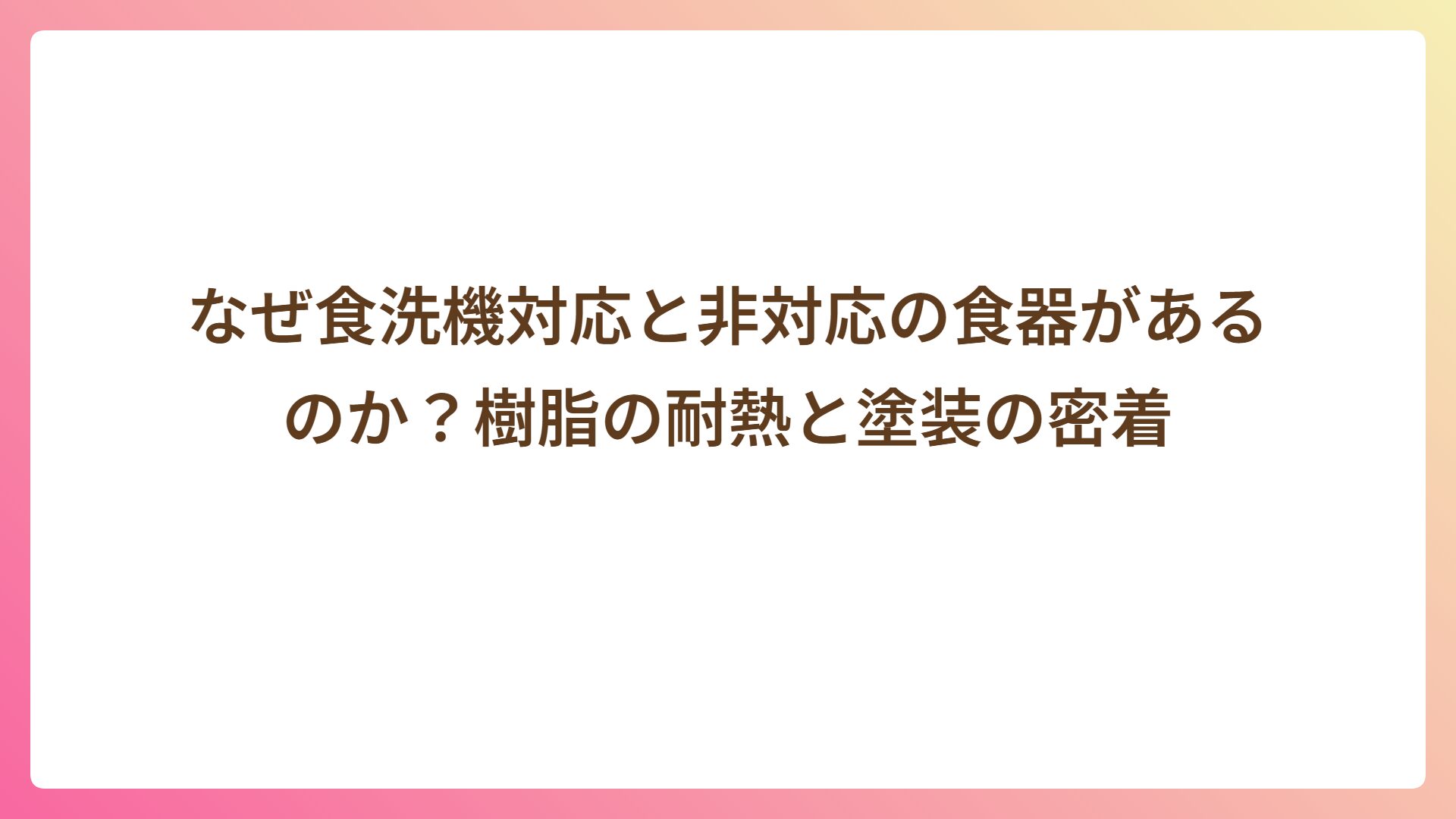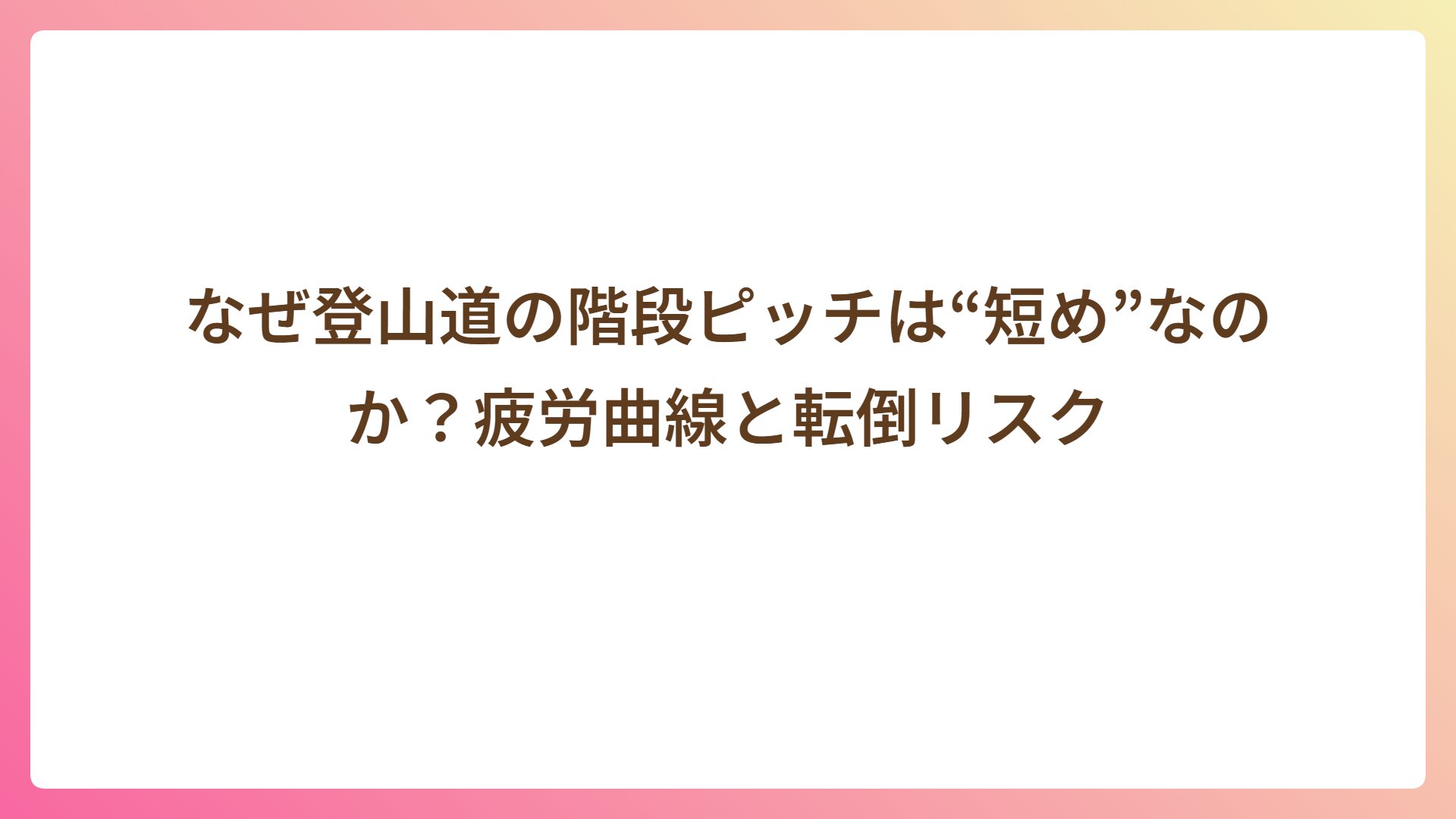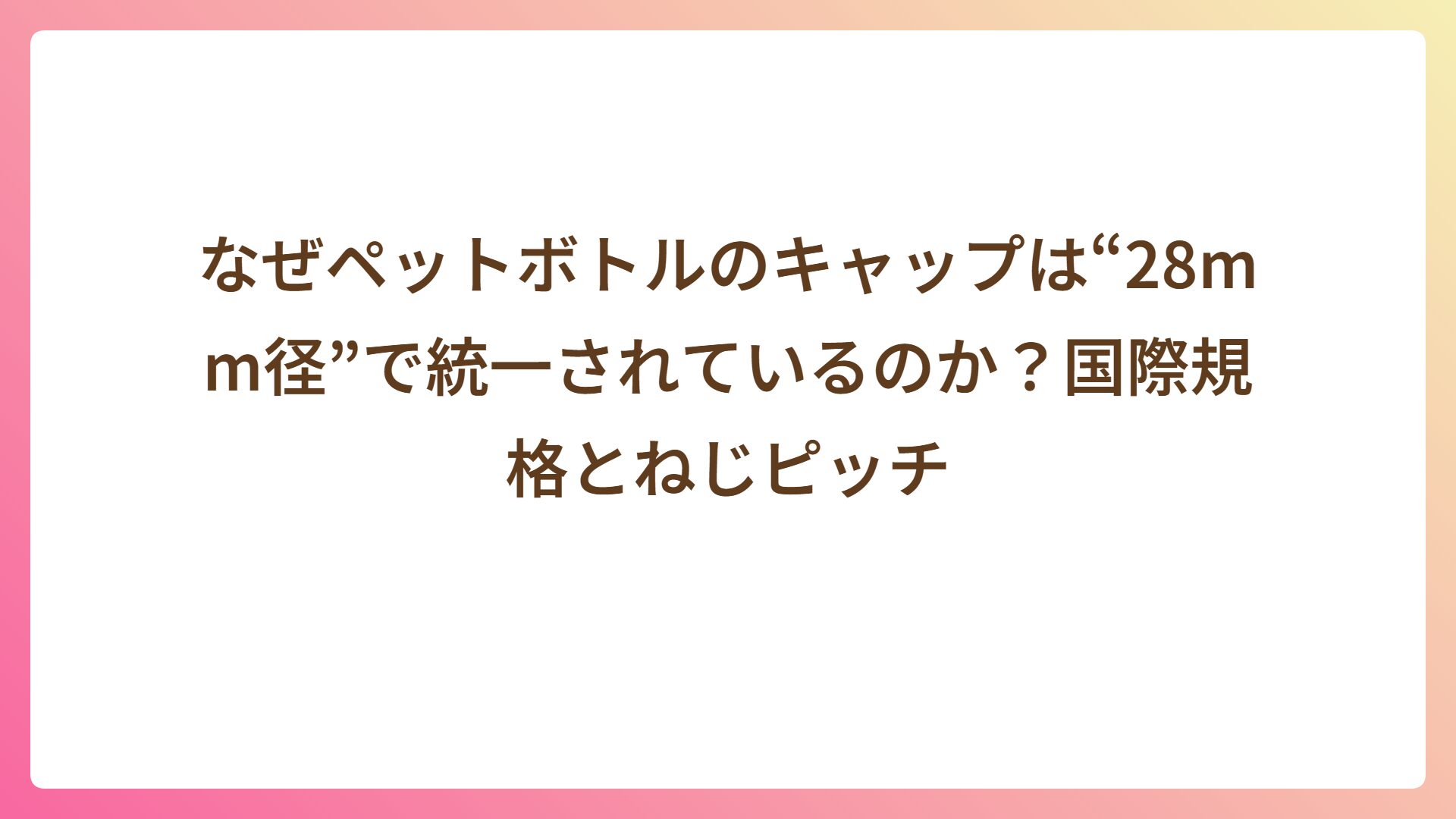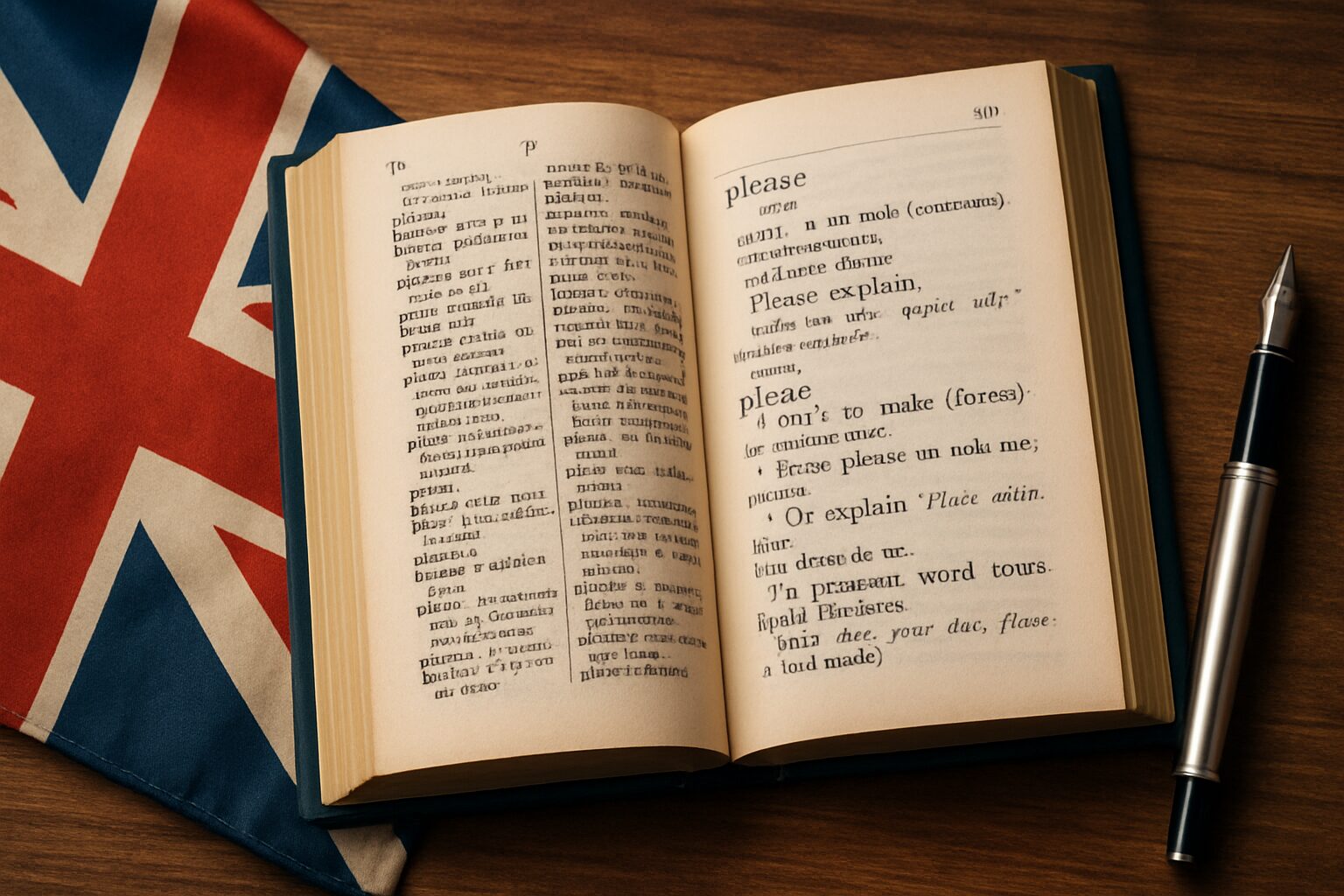なぜ虹は七色に見えるのか?光の屈折と分散の仕組みをわかりやすく解説

雨上がりの空に現れる虹。私たちが「赤・橙・黄・緑・青・藍・紫」の七色として覚えるあの美しい現象には、ちゃんとした科学的理由があります。
この記事では、虹が七色に見える仕組みを「光の屈折」「分散」という2つの物理現象から解説し、さらに国や文化によって“虹の色の数”が異なる不思議にも迫ります。
虹は「光の分解」でできている
虹は、太陽の光が空気中の水滴の中で屈折・反射・分散することで生まれます。
雨上がりの空気中には無数の水滴が漂っており、それぞれが小さなプリズムのような働きをしているのです。
- 太陽光が水滴に入るときに屈折(方向が変わる)
- 水滴の中で反射(内側で一度反射)
- 外に出るときに再び屈折し、色ごとに角度が変わる
このとき、波長の違いによって光が分かれ、結果として私たちの目には「七色の虹」として見えるのです。
光の“波長の違い”が色を作り出す
光は1本の線ではなく、さまざまな波長(長さの違う波)で構成されています。
波長が長いほど「赤っぽい色」に、短いほど「青っぽい色」になります。
水滴の中で屈折する際、波長の違いによって進む角度がわずかに変化するため、赤から紫までが広がって見えるのです。
具体的には――
- 赤:波長が長く、外側に見える(約42°)
- 紫:波長が短く、内側に見える(約40°)
この角度差が、虹のグラデーションを作り出しています。
なぜ「七色」なの? ― 実は国によって違う!
日本では「赤・橙・黄・緑・青・藍・紫」の七色として教えられますが、実はこれは文化的な区分にすぎません。
たとえば、
- アメリカやイギリスでは6色(藍を区別しない)
- ドイツでは5色
- ロシアでは7色より多く数える人も
つまり、虹が七色“に見える”のではなく、「七色と数える文化がある」というのが正確なのです。
この七色の考え方を広めたのは、物理学者アイザック・ニュートン。
当時の音階(ドレミファソラシ)になぞらえて、光のスペクトルも7つに区切ったと言われています。
虹の見える条件 ― 太陽と水滴の位置関係がカギ
虹が見えるためには、いくつかの条件が揃う必要があります。
- 太陽が背後にあり、空気中に水滴が浮かんでいる
- 太陽高度が低い(朝や夕方が見えやすい)
- 背を太陽に向け、雨雲がある方向を見る
また、二重に虹が出る「ダブルレインボー」は、水滴の中で光が2回反射したときに現れる現象です。
外側の虹は色の並びが逆(赤が内側・紫が外側)になるのが特徴です。
まとめ:虹の七色は「自然」と「文化」のコラボ
虹が七色に見えるのは、光の屈折と分散という物理現象によるもの。
しかし、「七色」と感じるのは文化的な感覚でもあります。
つまり、虹の美しさは科学と文化の融合の結果。
次に虹を見かけたら、「自然のプリズム」と「人間の感性」の両方を思い出してみてください。