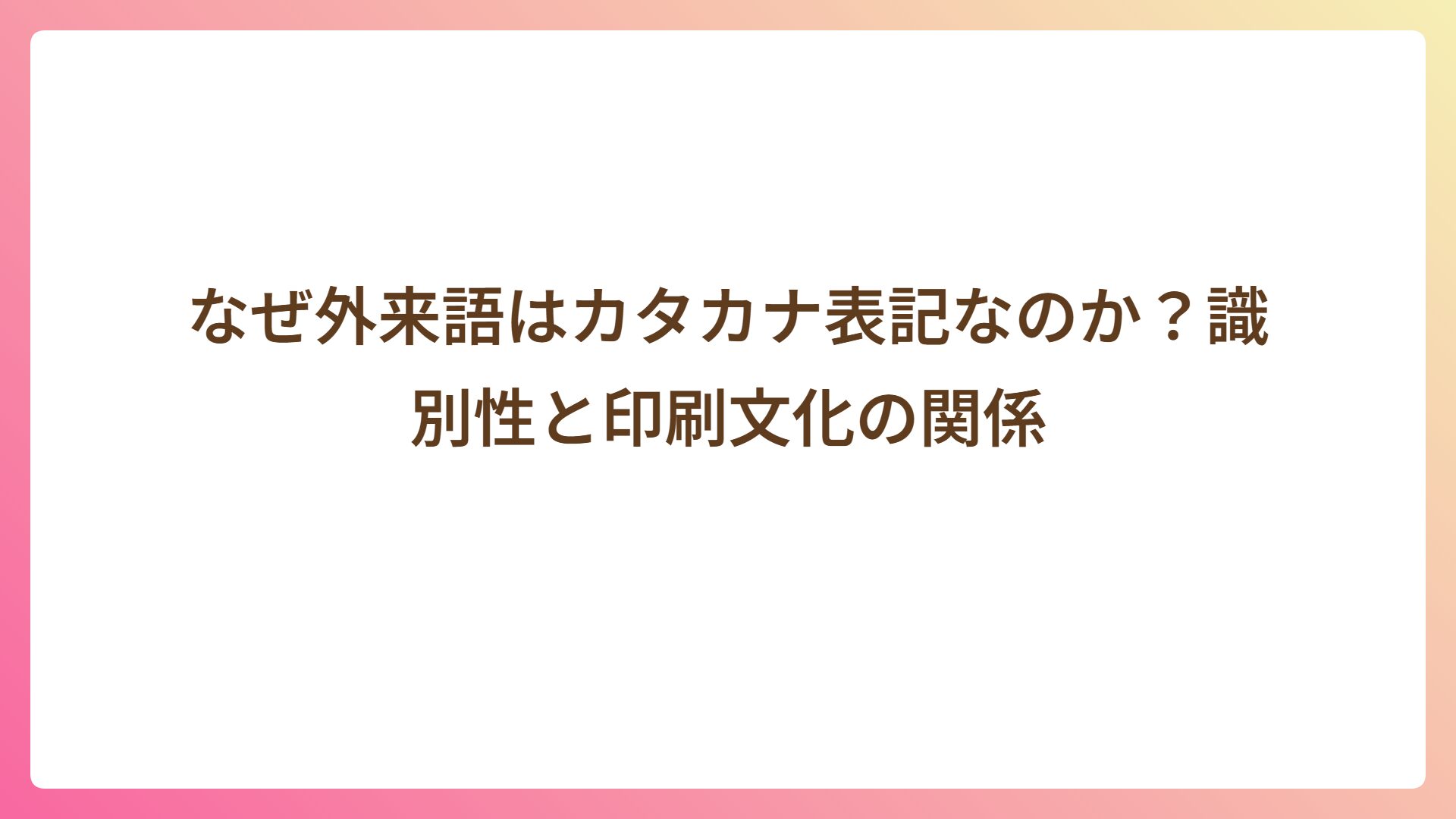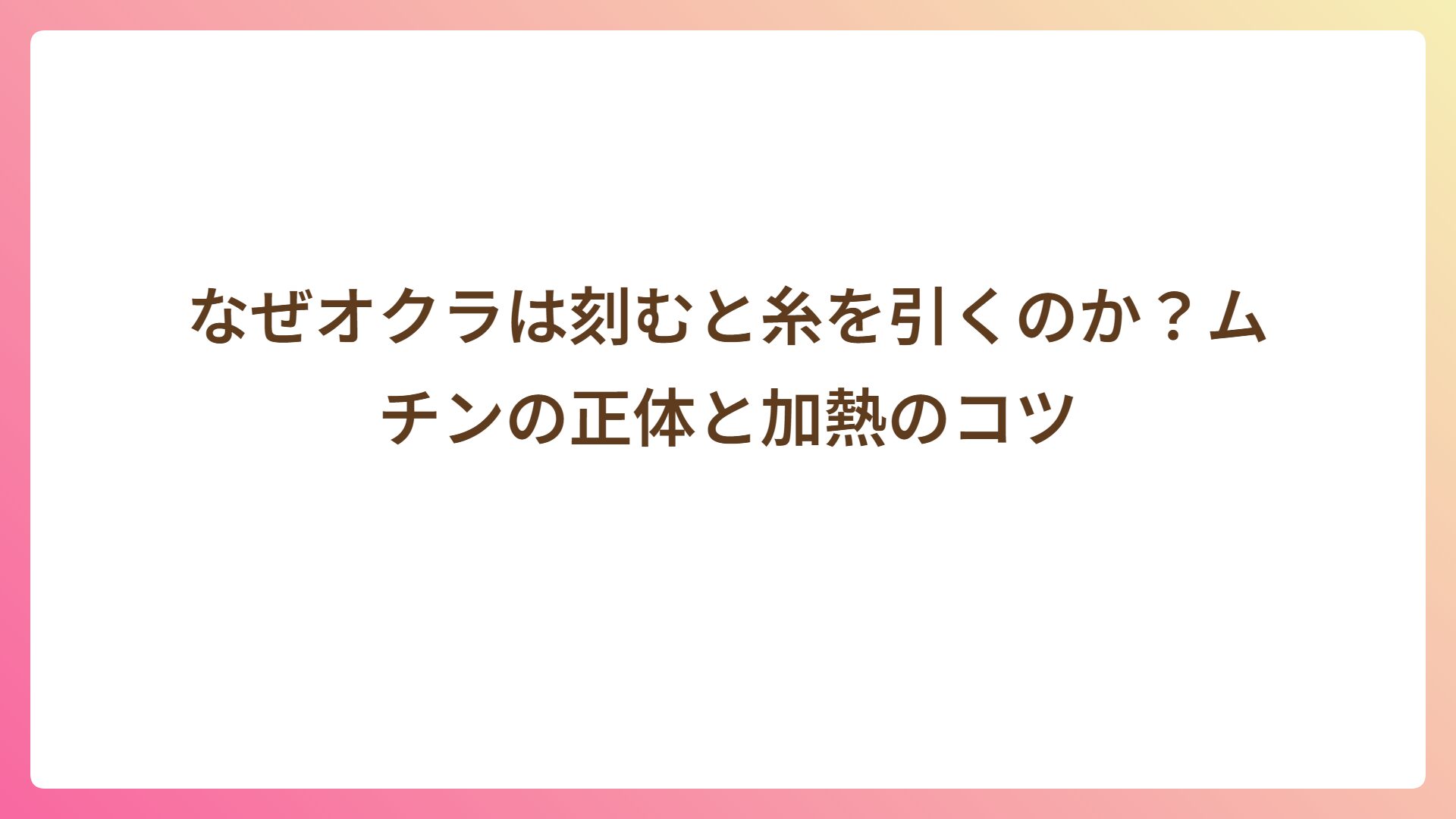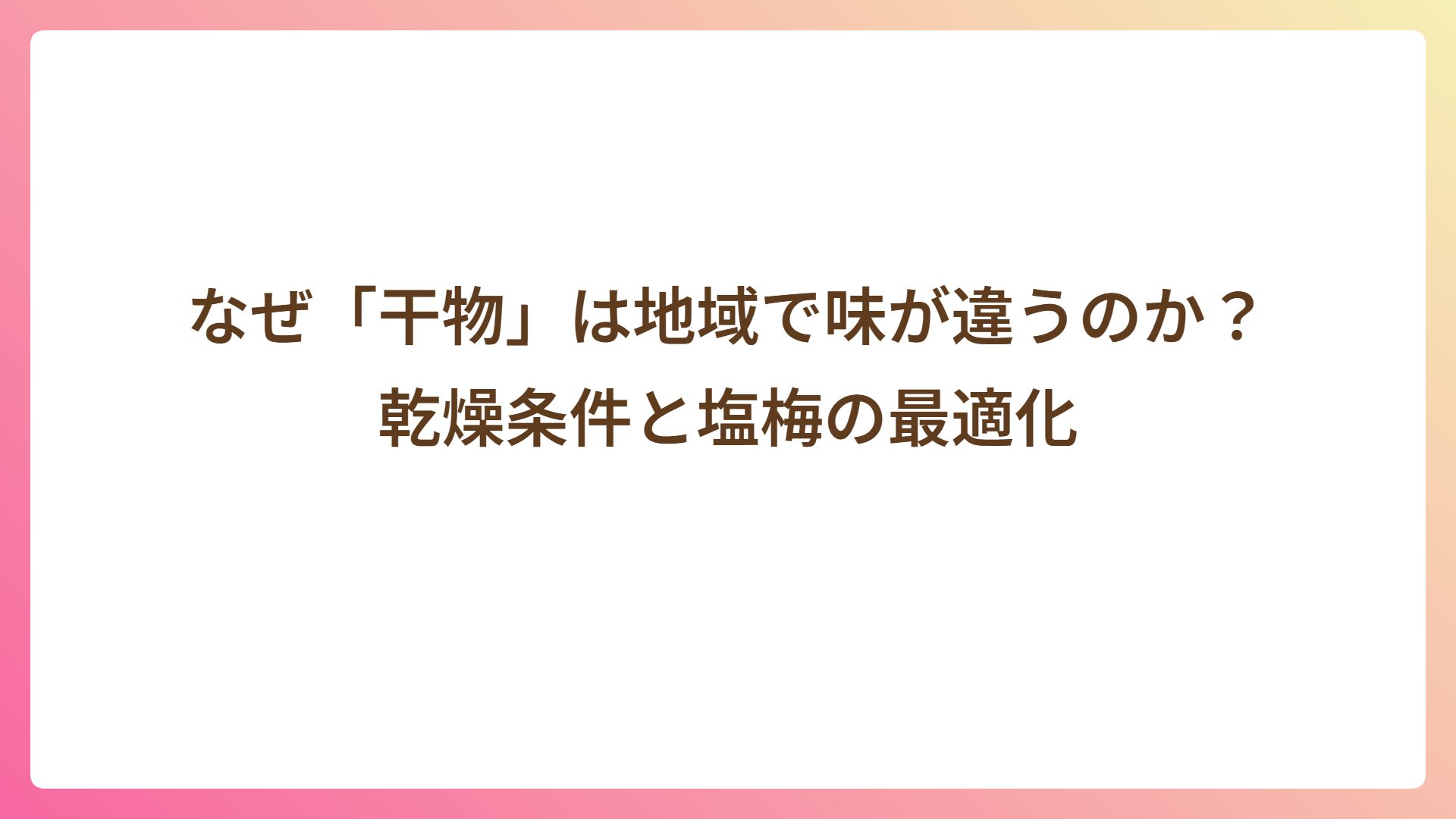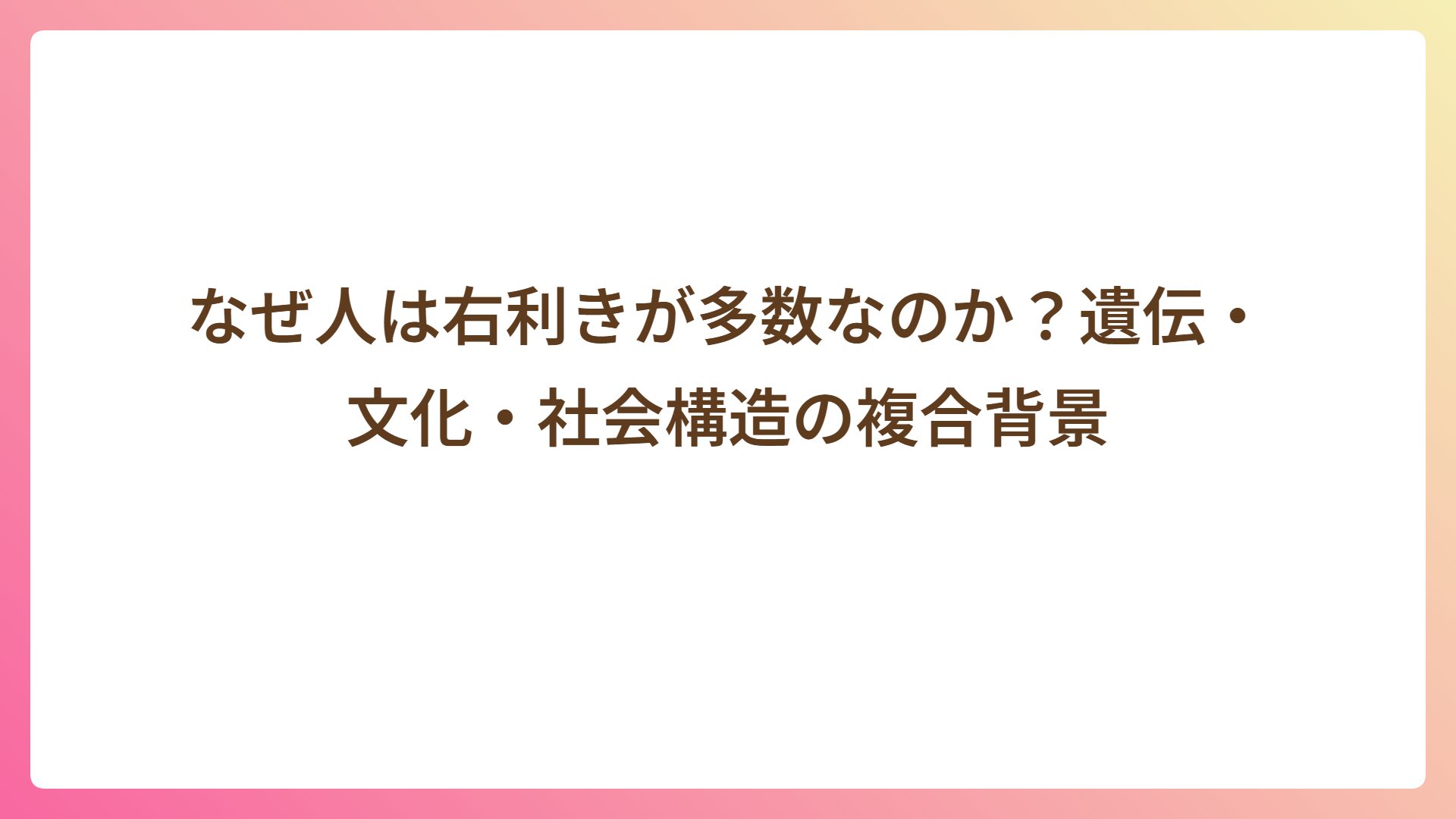なぜ「肉じゃが」は海軍発祥説が広まったのか?軍隊食と都市伝説
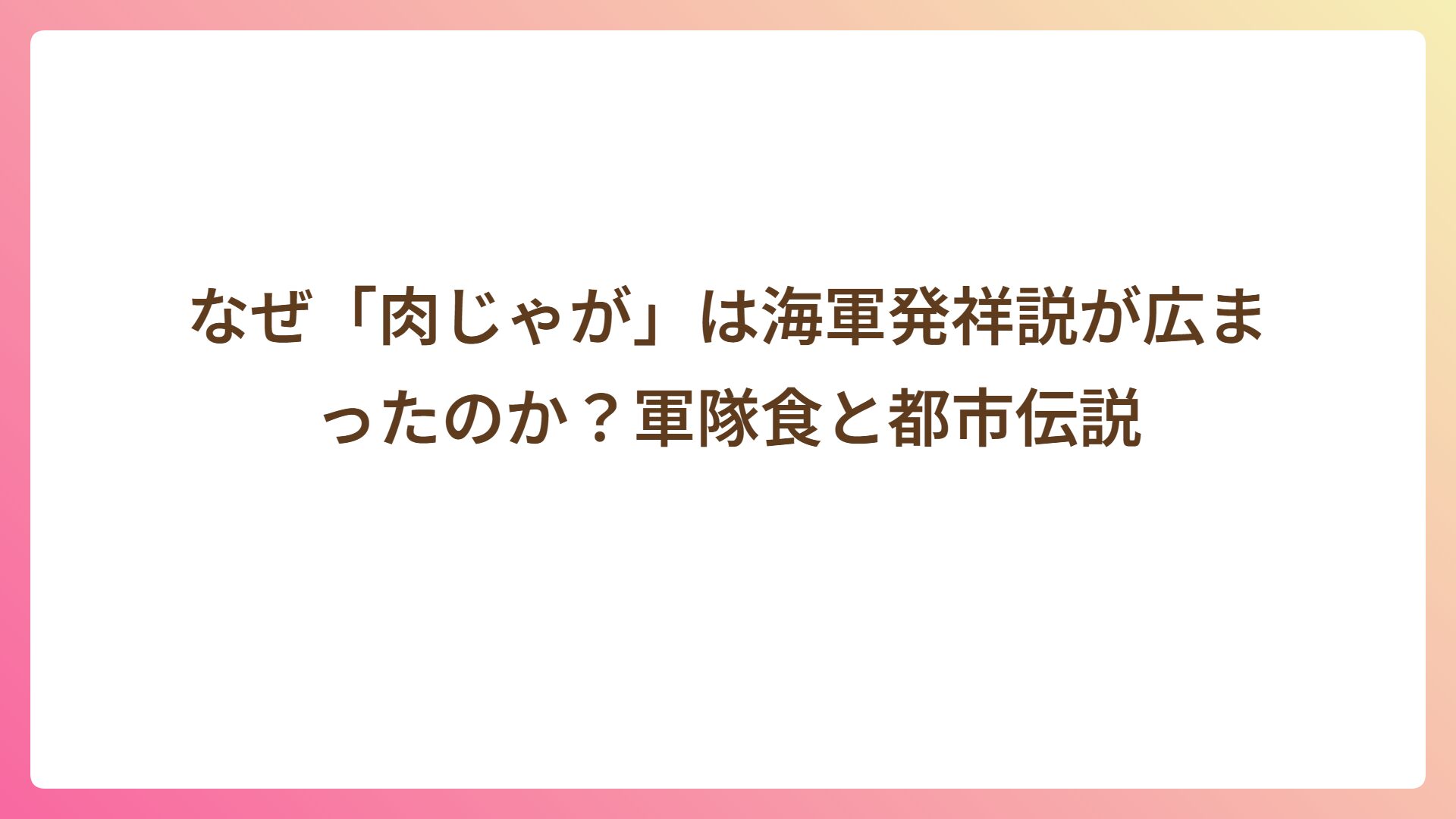
日本の家庭料理の定番「肉じゃが」には、「海軍の料理人がビーフシチューを再現したのが始まり」という有名な説があります。
しかし、これには史実としての裏付けが薄く、むしろ“都市伝説化した軍隊食”としての側面が強いのです。
なぜこの“海軍発祥説”がここまで広まったのか、その文化的背景をひもときます。
舞鶴と呉、二つの「発祥地」説
肉じゃがの発祥をめぐっては、京都府舞鶴市と広島県呉市がともに「海軍ゆかりの地」として名乗りを上げています。
舞鶴説では、明治期に海軍がイギリス留学経験を持つ東郷平八郎の命で「ビーフシチューを再現せよ」と命じ、材料が足りなかったために醤油と砂糖で代用して煮込んだのが始まりとされます。
一方の呉説は、同じく海軍基地の食堂で自然発生的に作られたという主張です。
ただし、どちらの説も当時の文献や記録が存在しないため、正確な起源は特定できません。むしろこの曖昧さが、後年「伝説」として物語性を強める要因になりました。
海軍食は“家庭料理の原型”をつくった
明治時代の海軍では、兵士の体力維持と近代化の象徴として、西洋風の食事を積極的に採用していました。
シチュー、カレー、コロッケなど、のちに家庭料理として定着する多くのメニューが海軍食発祥です。
特にカレーライスは、航海中でも保存が効く食材で栄養価も高く、週に一度の“カレーの日”が制度化されるほど人気でした。
その延長線上で、肉じゃがも「和風シチュー」的な存在として受け入れられたと考えられます。
つまり、海軍は単なる軍隊ではなく、近代日本の食文化を民間に輸出した装置でもあったのです。
なぜ「海軍発祥説」が信じられたのか
この説が強く広まった背景には、ストーリーとしての完成度があります。
「西洋料理を再現しようとした結果、日本独自の家庭料理が生まれた」という流れは、明治の文明開化を象徴する物語として非常に魅力的だったのです。
さらに、戦後になってから舞鶴市と呉市が地域活性化のシンボルとして“肉じゃが発祥の地”をアピールし、観光キャンペーンなどで全国的に知名度が拡大しました。
こうして「史実の裏付けよりも物語性が勝る」形で、海軍発祥説が定着していきました。
文献には登場しない“空白の時期”
実際に明治・大正期の料理書や軍隊の献立記録には、「肉じゃが」という名前はほとんど見当たりません。
確認できるのは戦後の一般家庭向け料理本からで、名称も「肉とじゃがいもの煮物」として紹介されていた程度です。
つまり、肉じゃがは家庭の味として自然に発展した料理であり、「海軍が考案した」と断定できる証拠は存在しないのです。
海軍食に似た調理法が民間に浸透し、後から“軍隊由来の物語”が付与された可能性が高いと考えられます。
まとめ:事実よりも“象徴”としての価値
「肉じゃが=海軍発祥」という説は、史実というより文化的な寓話(アレゴリー)に近い存在です。
- 明治の海軍が近代化の象徴だった
- 洋食を日本風に再構成する精神を体現していた
- 舞鶴・呉という二つの港町が地域アイデンティティとして語り継いだ
肉じゃがは、単なる煮物ではなく、日本人が西洋文化を“家庭の味”に変換した象徴でもあります。
その物語性こそが、事実を超えて人々に受け入れられてきた理由なのです。