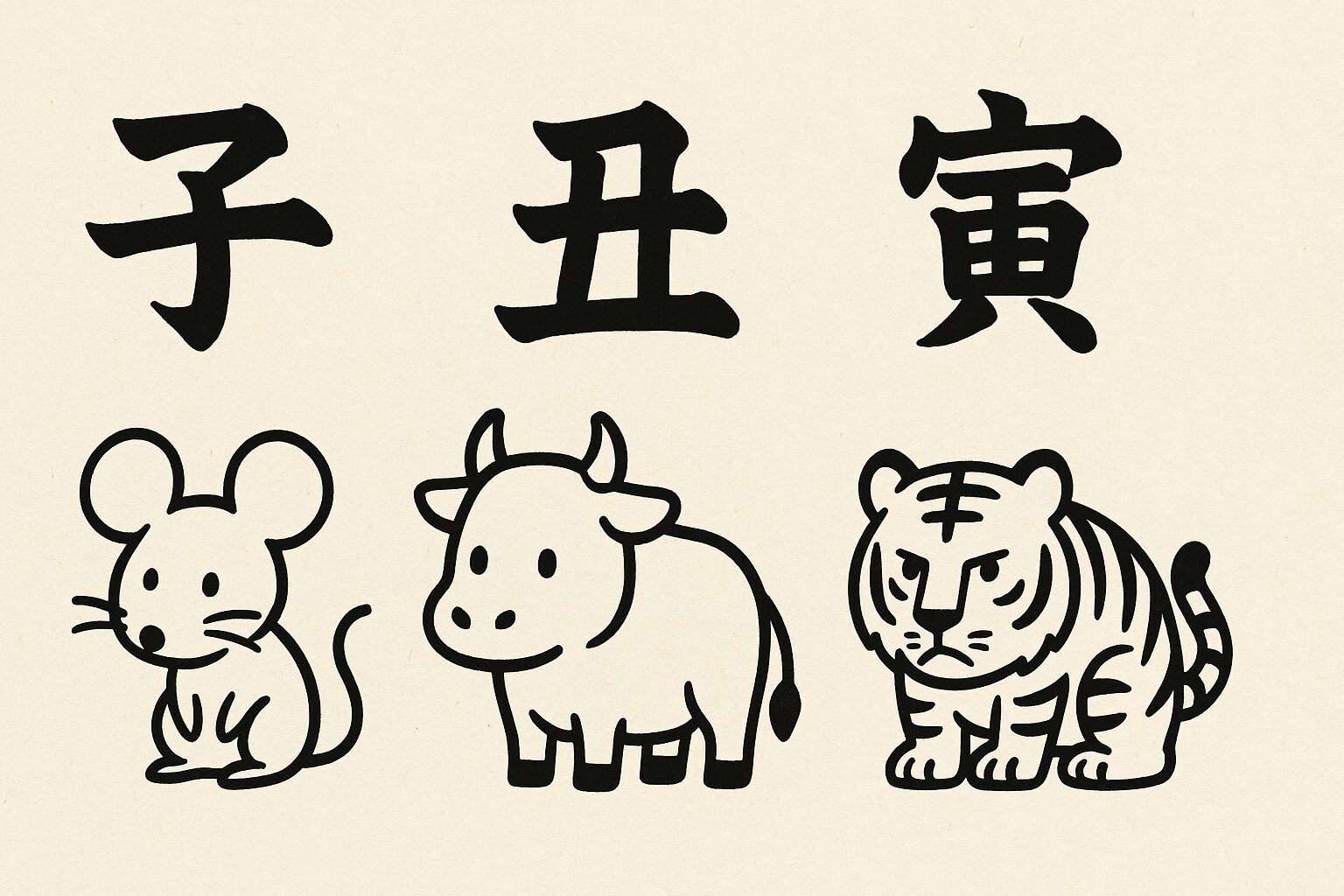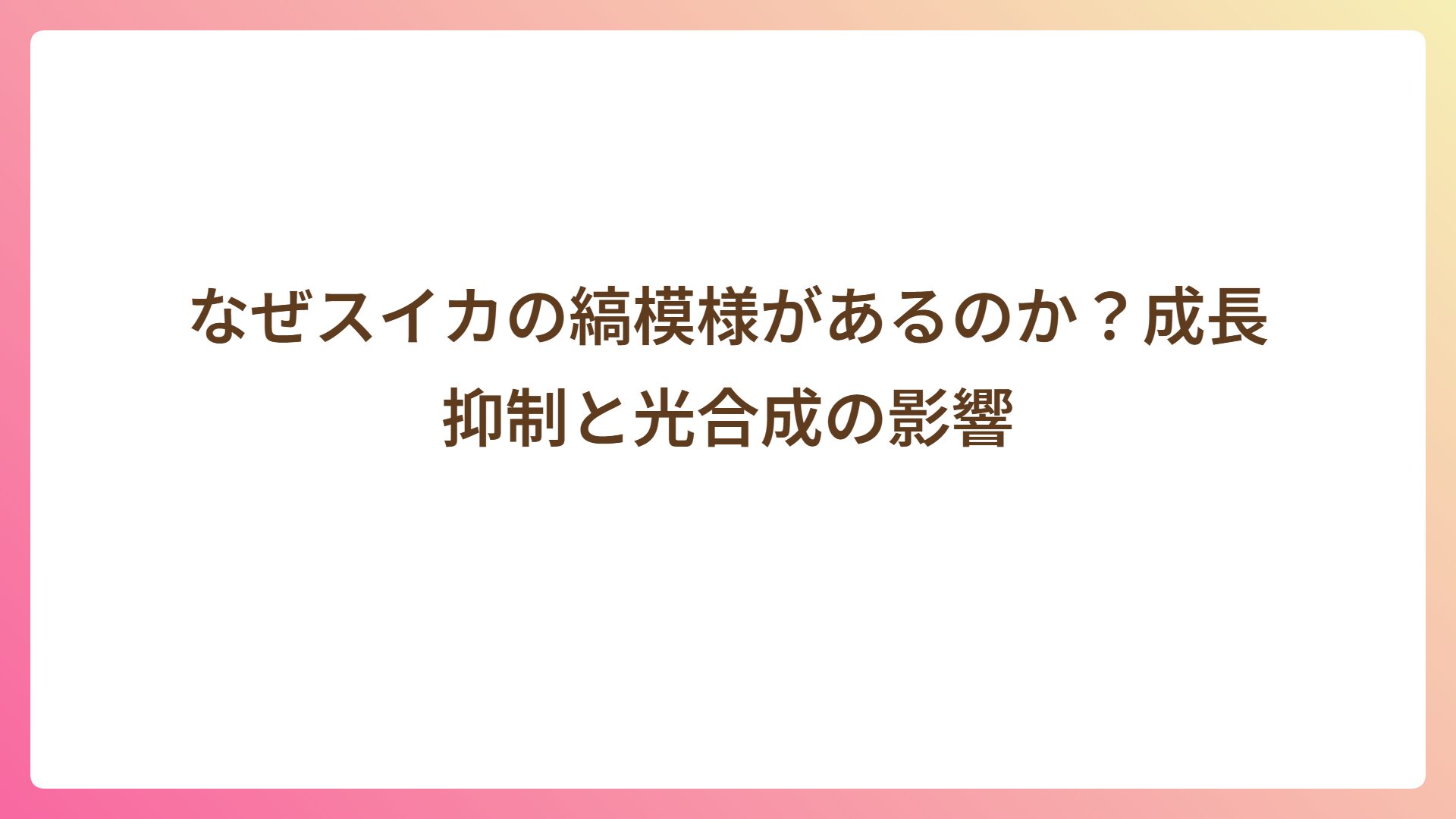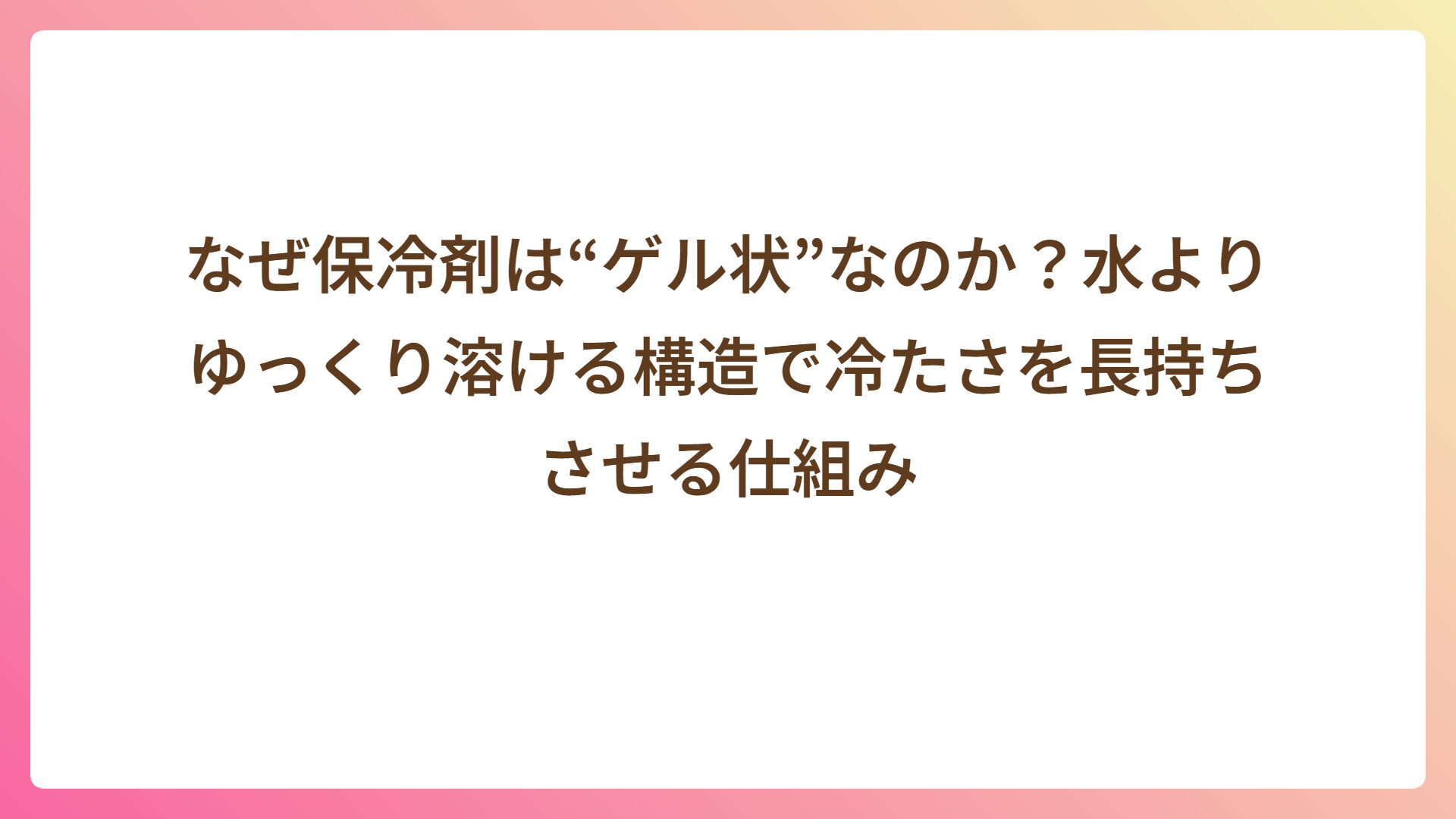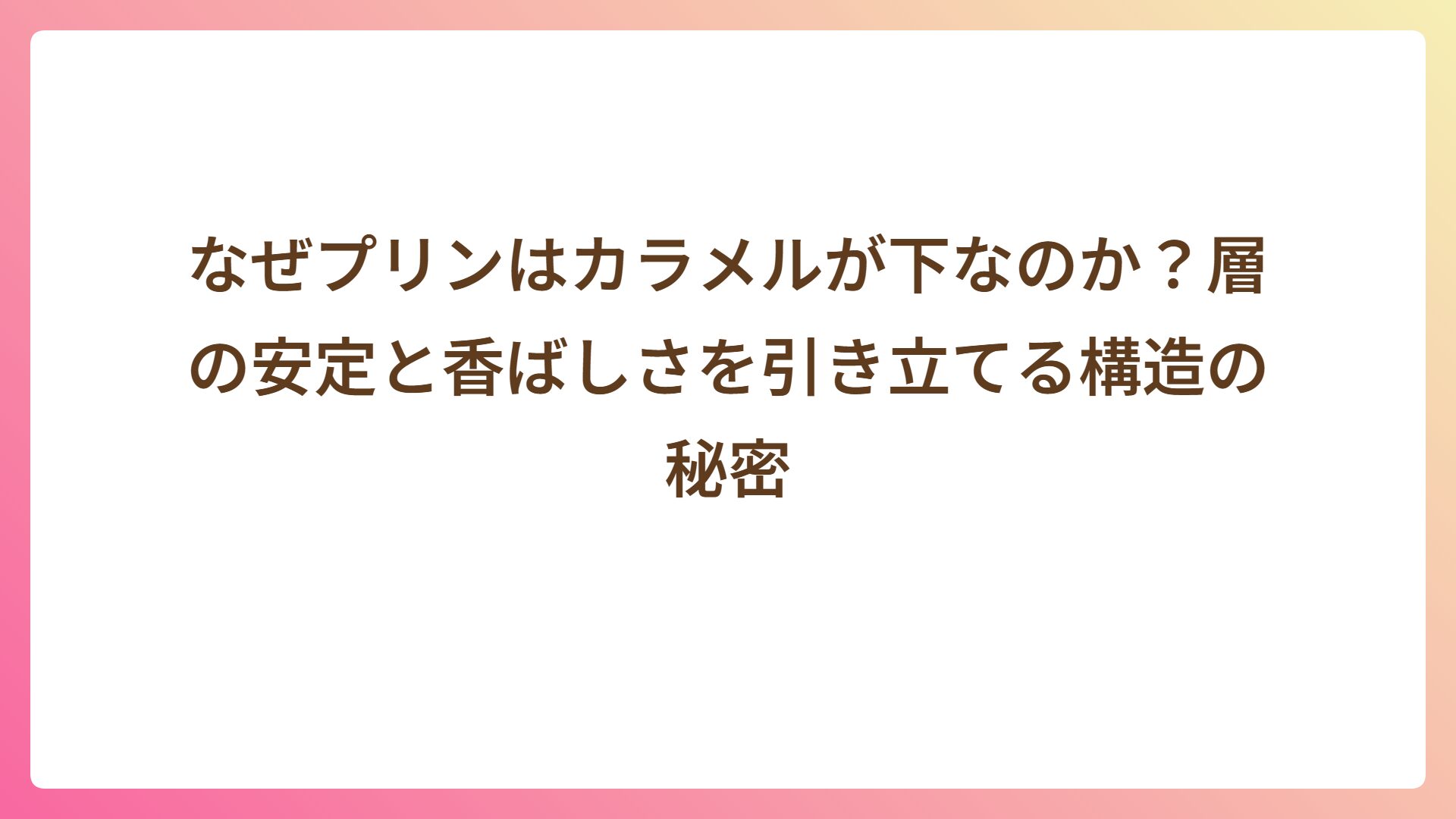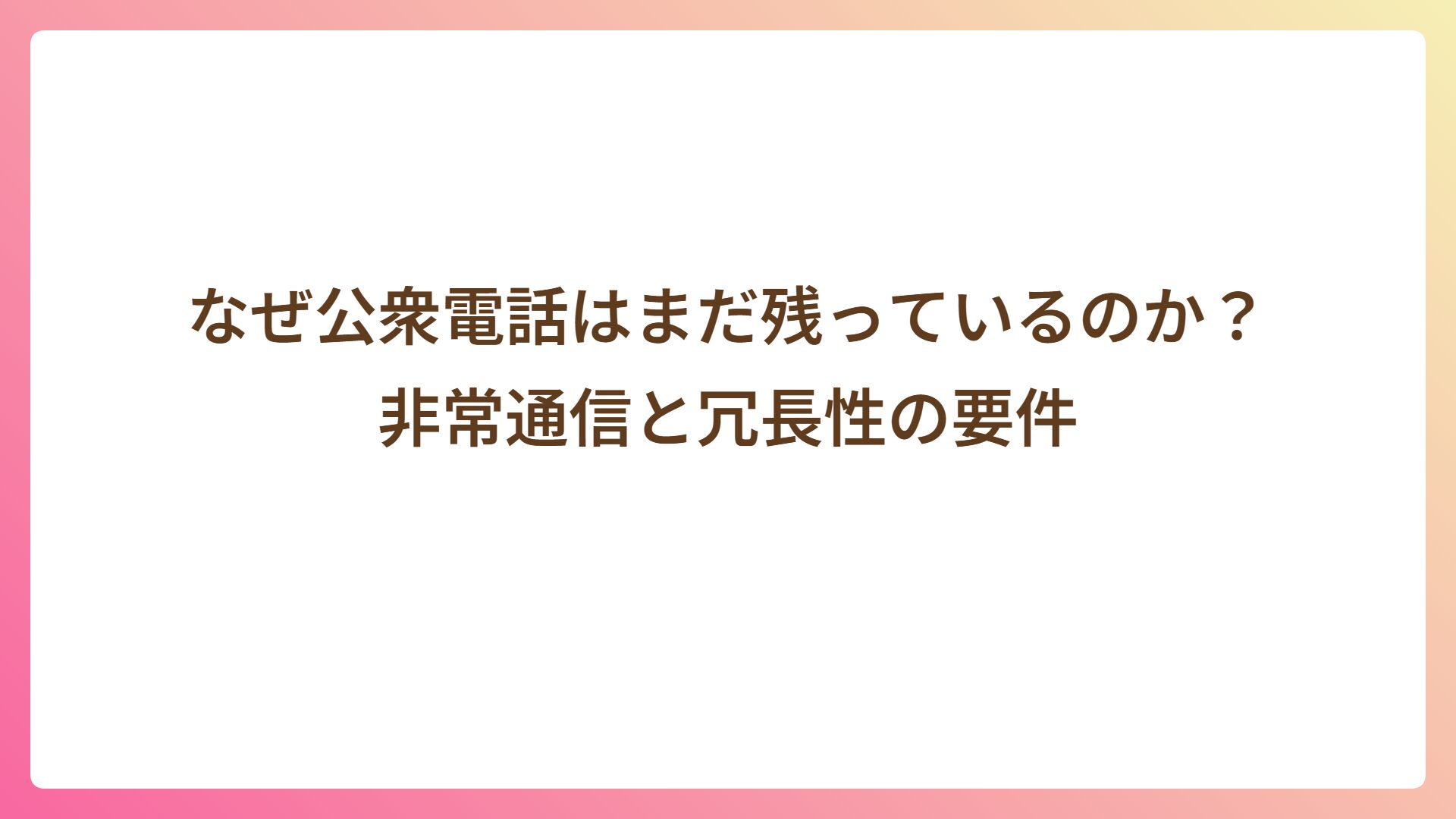なぜノートPCのヒンジは中央より分割型が多いのか?トルク分散と開閉寿命
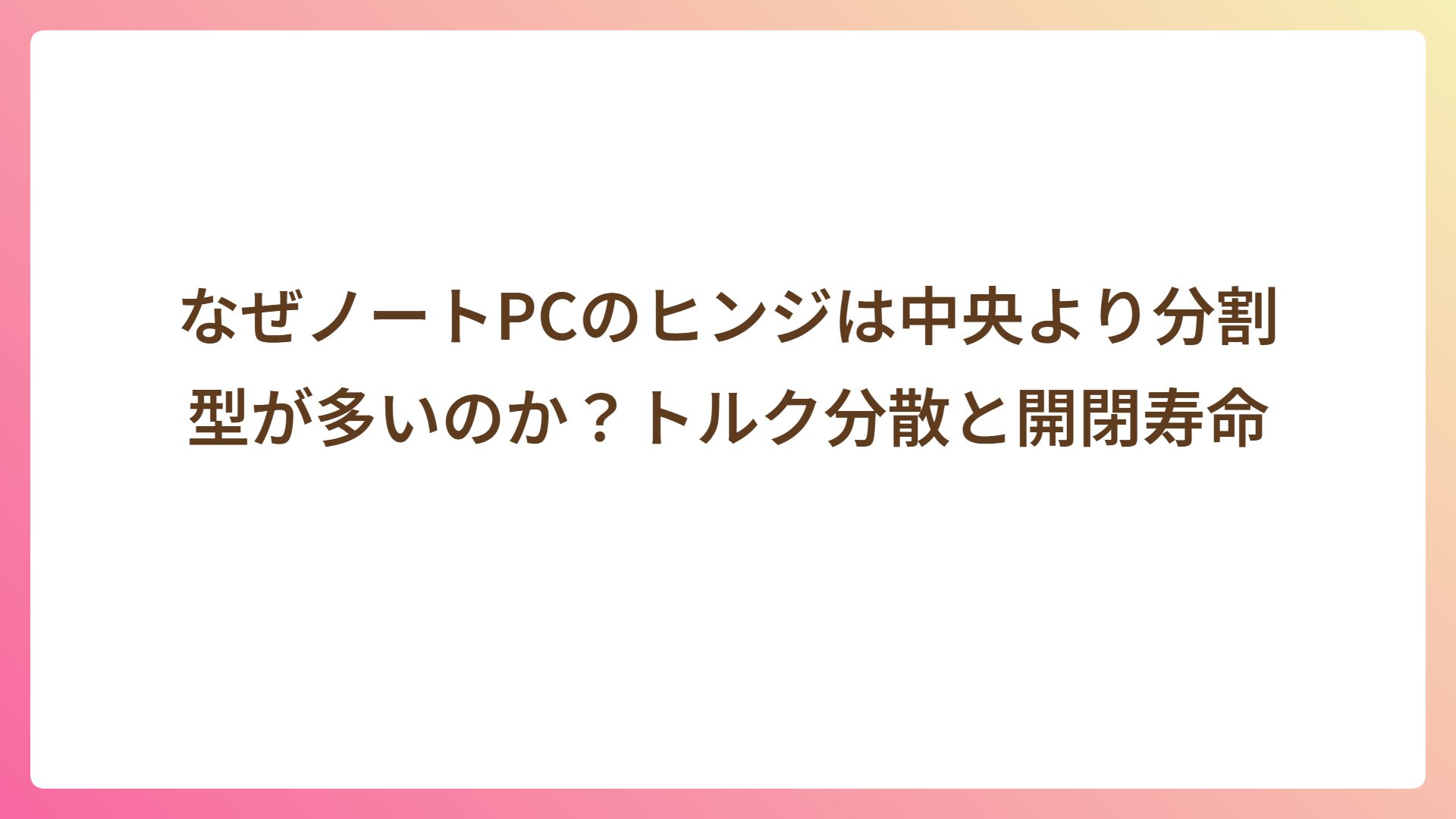
ノートパソコンを開くと、画面の下にあるヒンジ(蝶番)が動きます。
よく見ると、ほとんどの機種でヒンジは中央ではなく左右に分かれて配置されています。
なぜメーカーは、わざわざ2つに分けて設計しているのでしょうか?
そこには、開閉のしやすさと耐久性を両立させるための明確な理由があります。
開閉トルクを左右に分散できる
ノートPCの画面は軽そうに見えても、内部には液晶パネルやフレームがあり、それなりの重量があります。
この重みを支えるため、ヒンジには「一定のトルク(ねじれ力)」がかかります。
もし中央1か所にヒンジを置くと、その1点に力が集中し、金属軸や樹脂カバーが早く摩耗してしまいます。
左右に分けることで、トルクをバランスよく分散し、どちらか一方に負荷が偏らないようにできるのです。
これにより、長期間使ってもヒンジが緩みにくく、開閉の感触が安定します。
画面のねじれや歪みを防ぐ構造
中央ヒンジの場合、開閉時に画面の両端との距離が遠くなるため、トルクの伝達が偏って液晶パネルがねじれやすくなります。
その結果、フレームの歪みや画面のたわみが起こりやすくなります。
左右2つのヒンジ構造なら、画面全体を均等に支えながら動かせるため、歪みやひび割れを防ぐことができます。
特に薄型ノートでは剛性が低いため、この分散構造が欠かせません。
開閉角度と冷却設計の自由度を確保
分割型ヒンジにすることで、内部の構造設計にも余裕が生まれます。
中央部分を空けることで、排熱用の通気口やケーブル配線スペースを確保できるのです。
最近のノートPCでは、ディスプレイ下部に吸気口やヒートパイプが通っており、冷却効率を高めるために中央を開放する設計が主流となっています。
さらに、左右独立式のヒンジは角度制御もしやすく、180度開くモデルやタブレットモードに変形する2in1機でも採用されています。
まとめ
ノートPCのヒンジが分割されているのは、
トルク分散・画面保護・排熱設計・可動自由度といった複数の要素を両立させるためです。
見た目以上に、開閉の“気持ちよさ”と“長寿命”を支える緻密な設計。
左右に分かれたあの小さなヒンジこそ、ノートPCの信頼性を支える要の部品なのです。