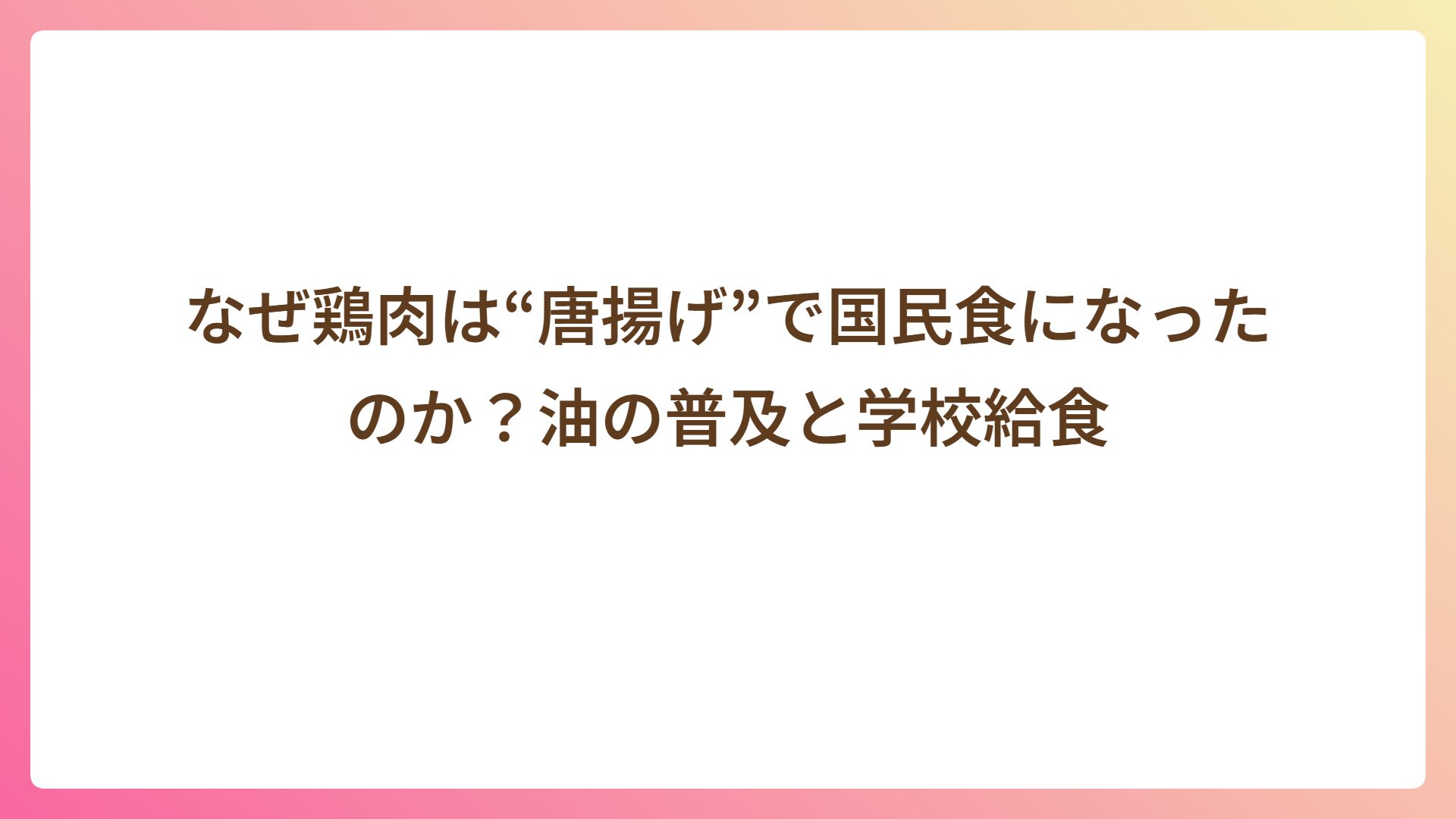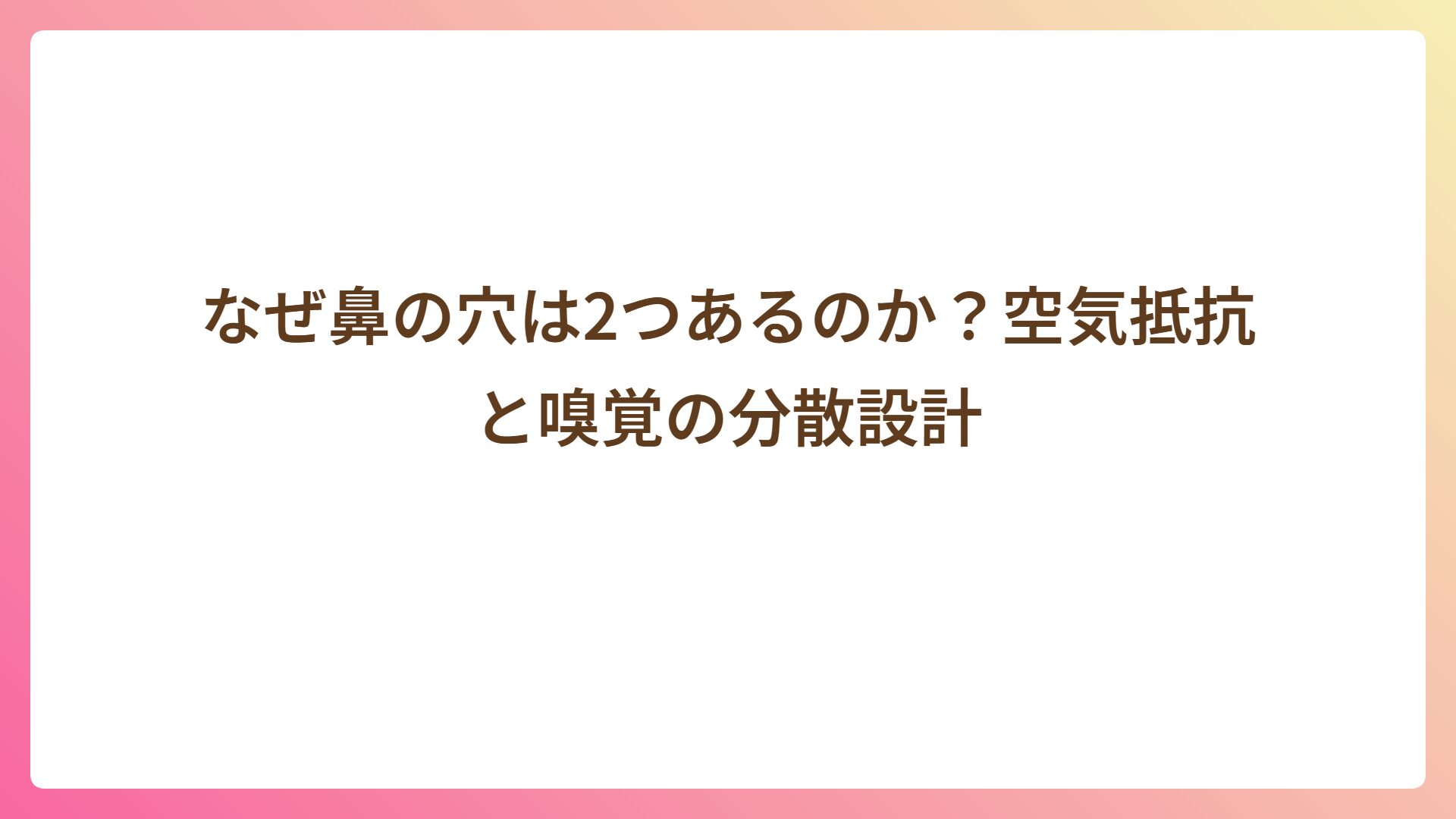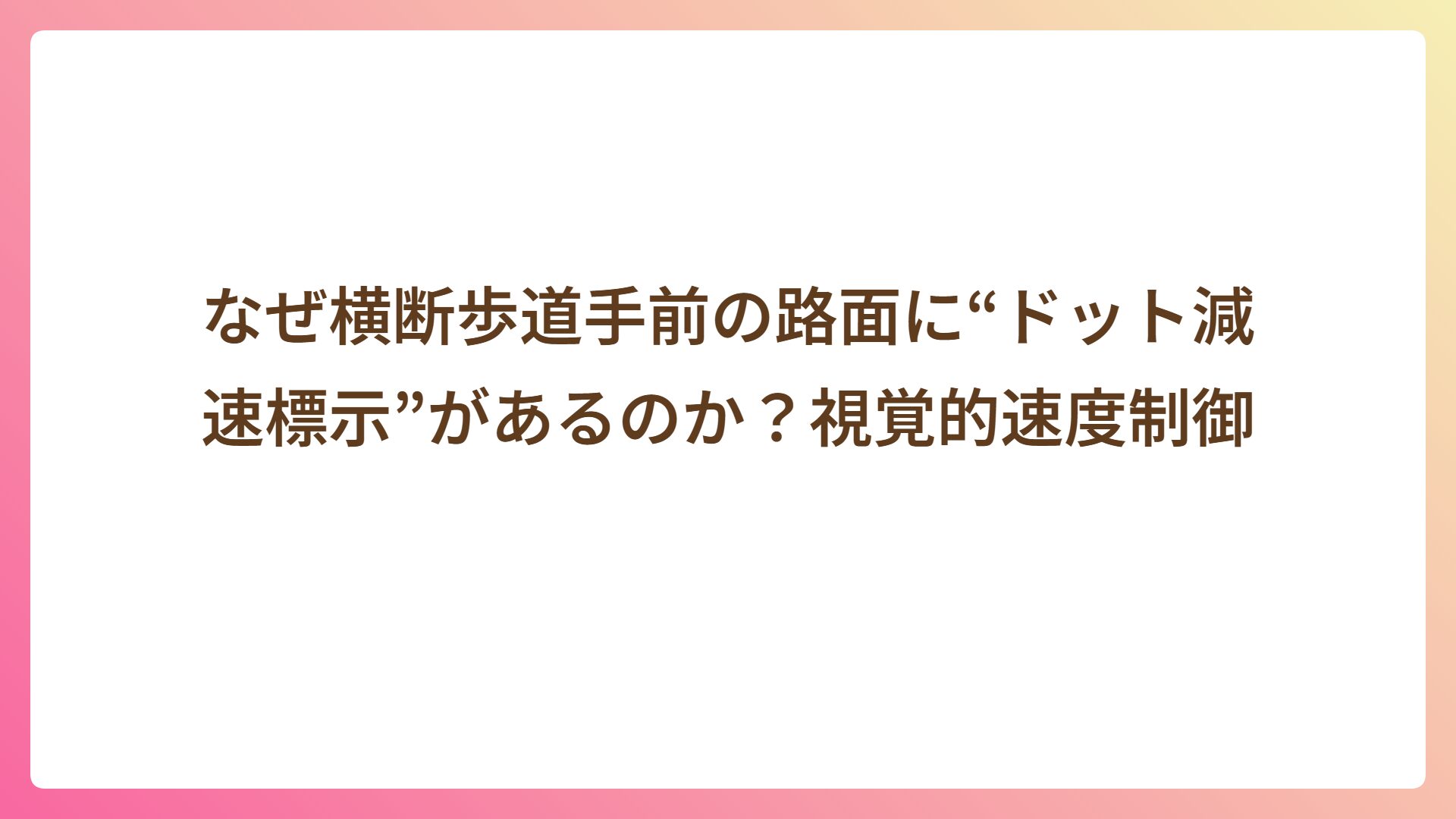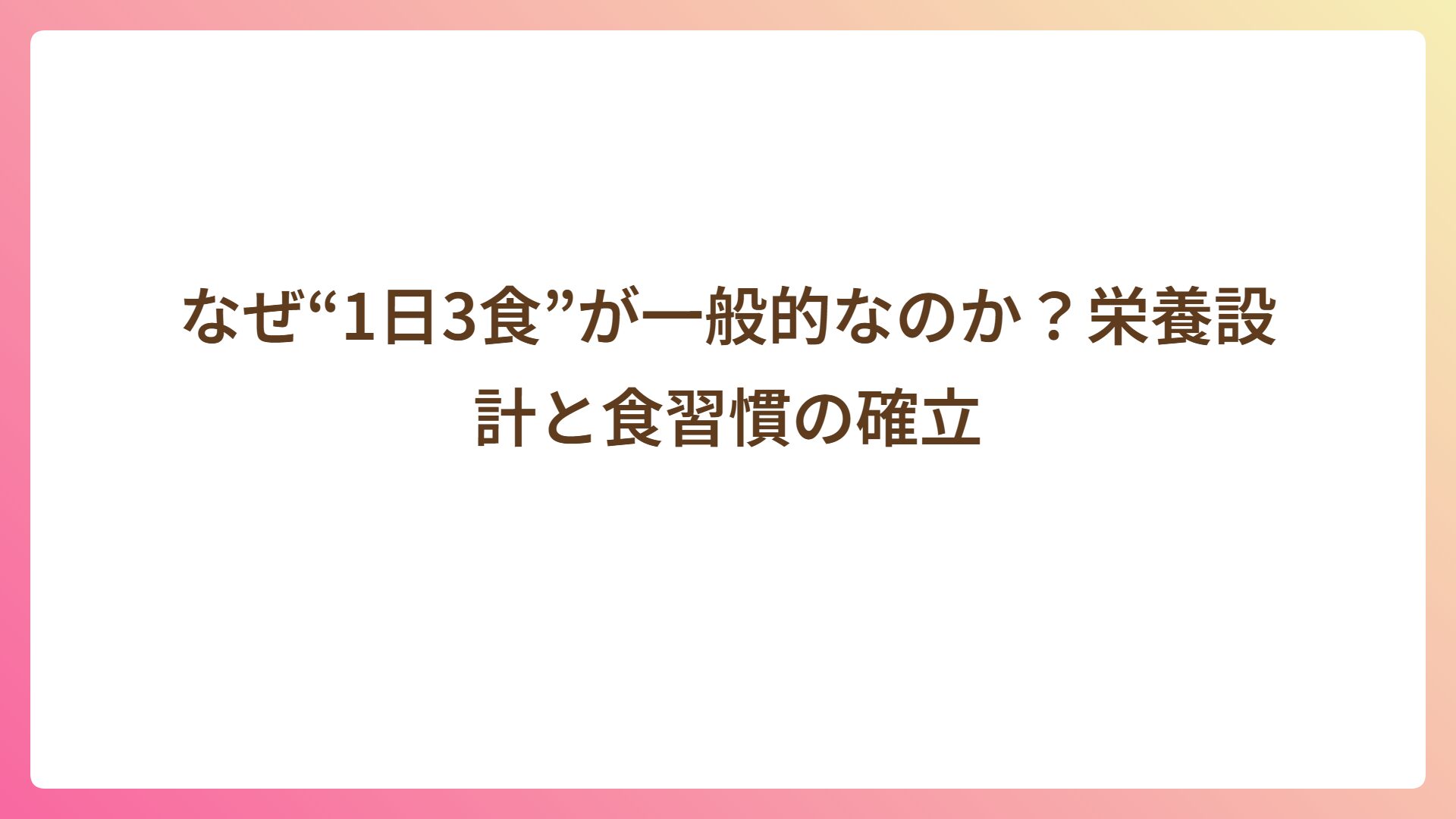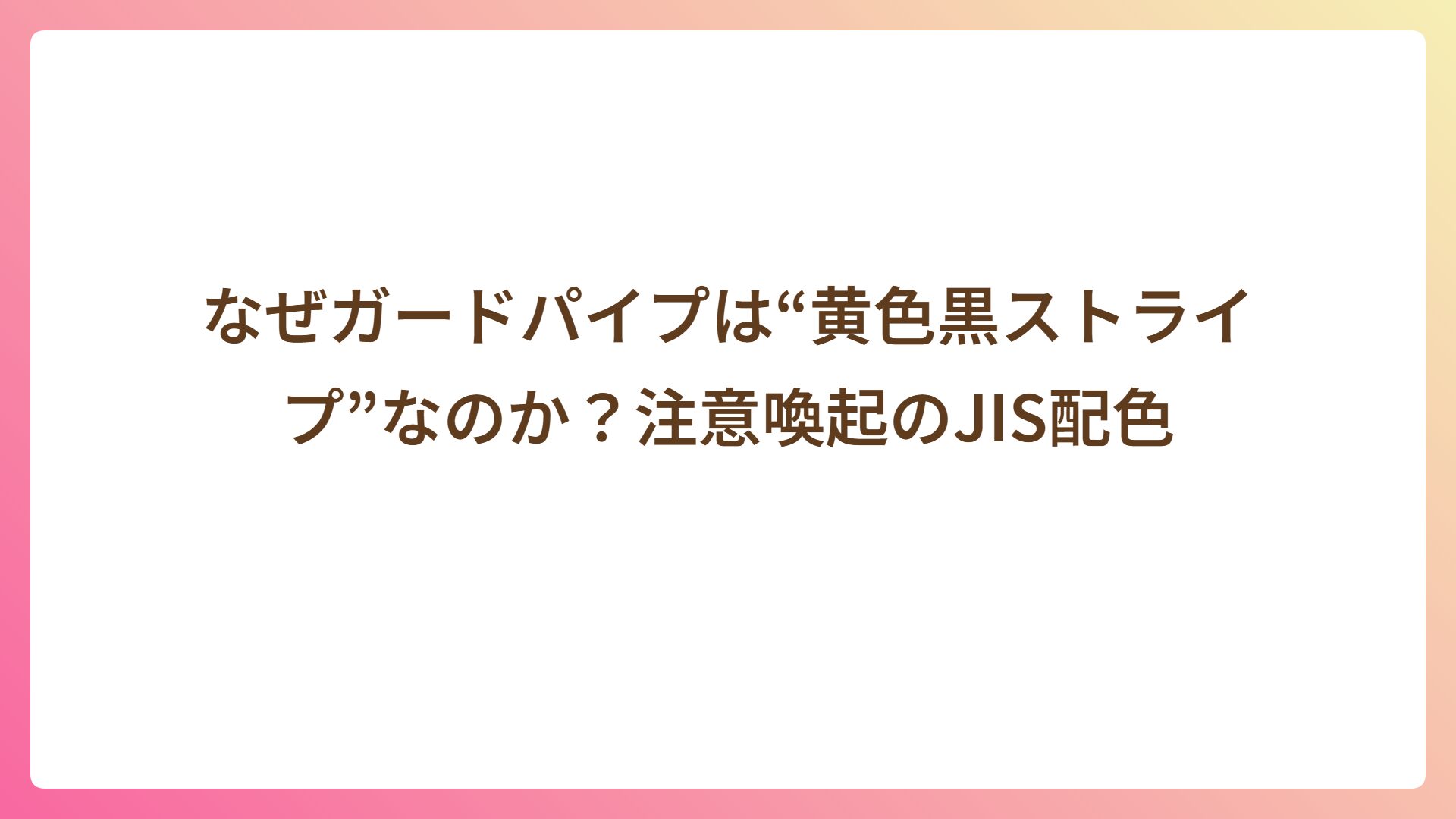なぜ「おはぎ」と「ぼた餅」で名前が変わるのか?季節と呼称の使い分け
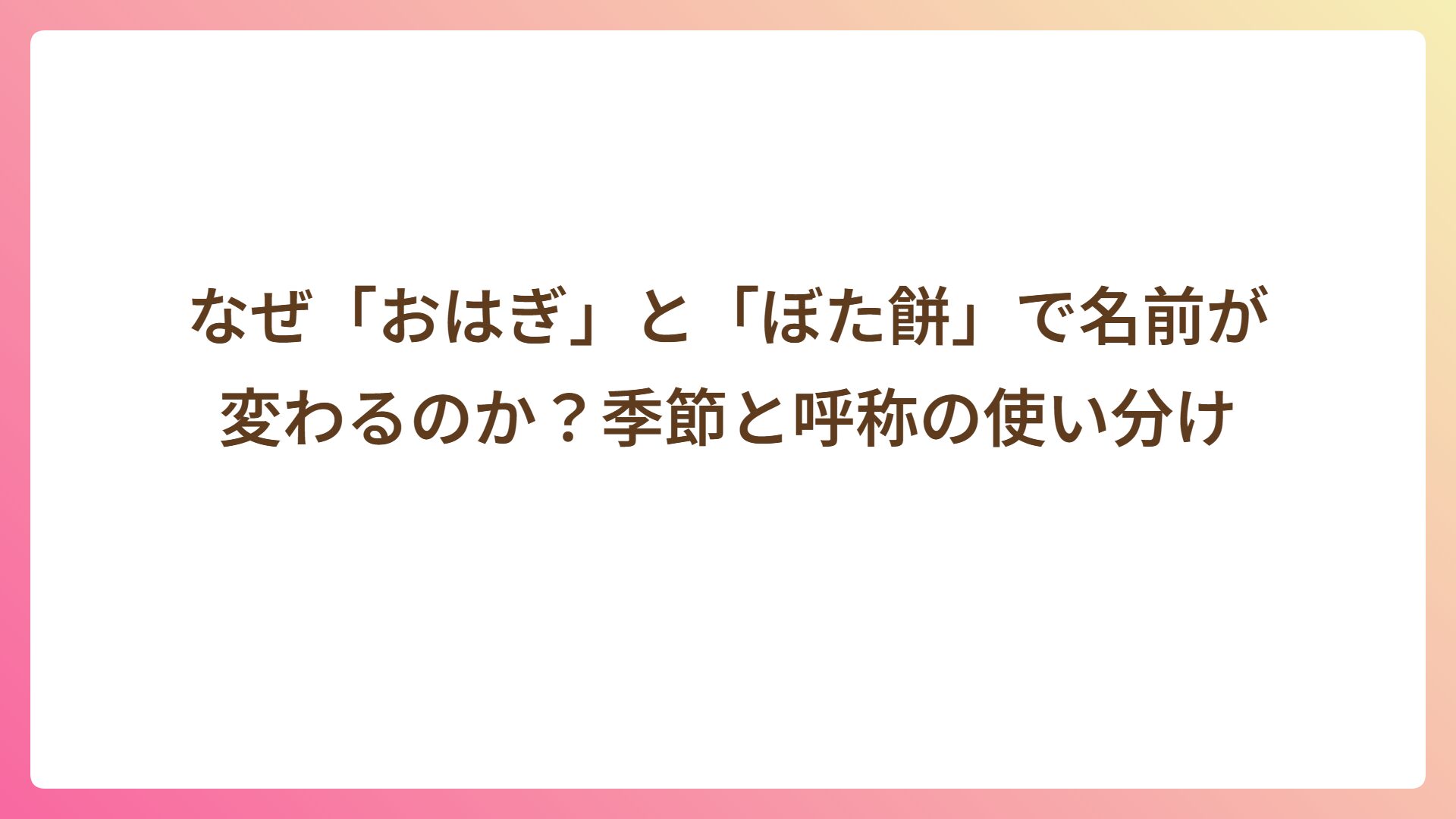
春は「ぼた餅」、秋は「おはぎ」。
同じような餅菓子なのに、季節で呼び方が変わるのはなぜでしょうか?
実はこの違い、日本人の四季感覚と、供え物としての信仰的な背景から生まれたものなのです。
「ぼた餅」と「おはぎ」はもともと同じ食べ物
どちらも、もち米やうるち米を軽くついて丸め、あんこで包んだもの。
味や作り方に大きな差はなく、材料もほぼ同じです。
違うのは、作られる時期とそれにまつわる花の名前なのです。
- 春の彼岸に作る → 牡丹(ぼたん)の花にちなみ「ぼた餅」
- 秋の彼岸に作る → 萩(はぎ)の花にちなみ「おはぎ」
つまり、「ぼた餅」と「おはぎ」は季節の花を映した詩的な呼び分けなのです。
春と秋、それぞれの花が象徴するもの
牡丹も萩も、古くから仏事や供え物に使われる花として知られていました。
- 牡丹:春の代表花で、豪華で丸みのある形 → 丸く大きいぼた餅
- 萩:秋の草花で、可憐で細やかな姿 → 小ぶりな形のおはぎ
形の違いもここから派生したといわれています。
季節の花に合わせて形を変え、自然の移ろいを食で表現する——これが日本的な美意識なのです。
小豆の状態にも“季節の違い”がある
春と秋で違うのは、花の名前だけではありません。
あんこの仕上げ方にも微妙な違いがあります。
- 春(ぼた餅):冬を越した小豆は皮が固くなりやすいため、裏ごししてこしあんに
- 秋(おはぎ):新豆の季節で皮が柔らかいので、粒を残したつぶあんに
つまり、春はなめらかな上品な味わい、秋は豆の風味を生かした香ばしさ。
食材の状態に合わせて最適な調理を行う、理にかなった季節料理なのです。
「彼岸」と深く結びついた供え物文化
おはぎ・ぼた餅は、春と秋の「彼岸」に食べられる供え物として広まりました。
彼岸は、太陽が真東から昇り真西に沈む春分・秋分の日を中心とした七日間。
祖先の霊を供養し、自然に感謝する期間とされます。
小豆の赤色は古くから魔除け・厄除けの色とされ、
もち米の「ハレの食材」と合わせることで、
邪気を祓い、先祖を慰める供え物としての意味を持ちました。
したがって、おはぎ・ぼた餅は単なる甘味ではなく、
信仰・感謝・季節感が融合した日本の伝統食なのです。
呼び分けは地域と時代でゆるやかに変化
現在では、春でも「おはぎ」と呼ぶ地域や、通年で同名に統一しているお店もあります。
江戸時代後期にはすでに両方の言葉が混在しており、
「季節の呼称としての違い」から「地方文化としての違い」へと変化してきました。
ただし、伝統的な和菓子職人の間では今も、
「春=ぼた餅、秋=おはぎ」として作り分ける風習が残っています。
まとめ
「おはぎ」と「ぼた餅」は、材料も味もほとんど同じ。
違いは、季節・花・小豆の状態・供養の意味にあります。
- 春(ぼた餅)=牡丹の花、こしあん、丸く大きい
- 秋(おはぎ)=萩の花、つぶあん、小ぶりで素朴
- いずれも彼岸の供え物であり、魔除けと感謝の象徴
名前の違いは、自然の移ろいをことばと味で感じ取る日本人の感性の結晶。
おはぎとぼた餅は、四季を愛でる文化そのものを映した甘味なのです。