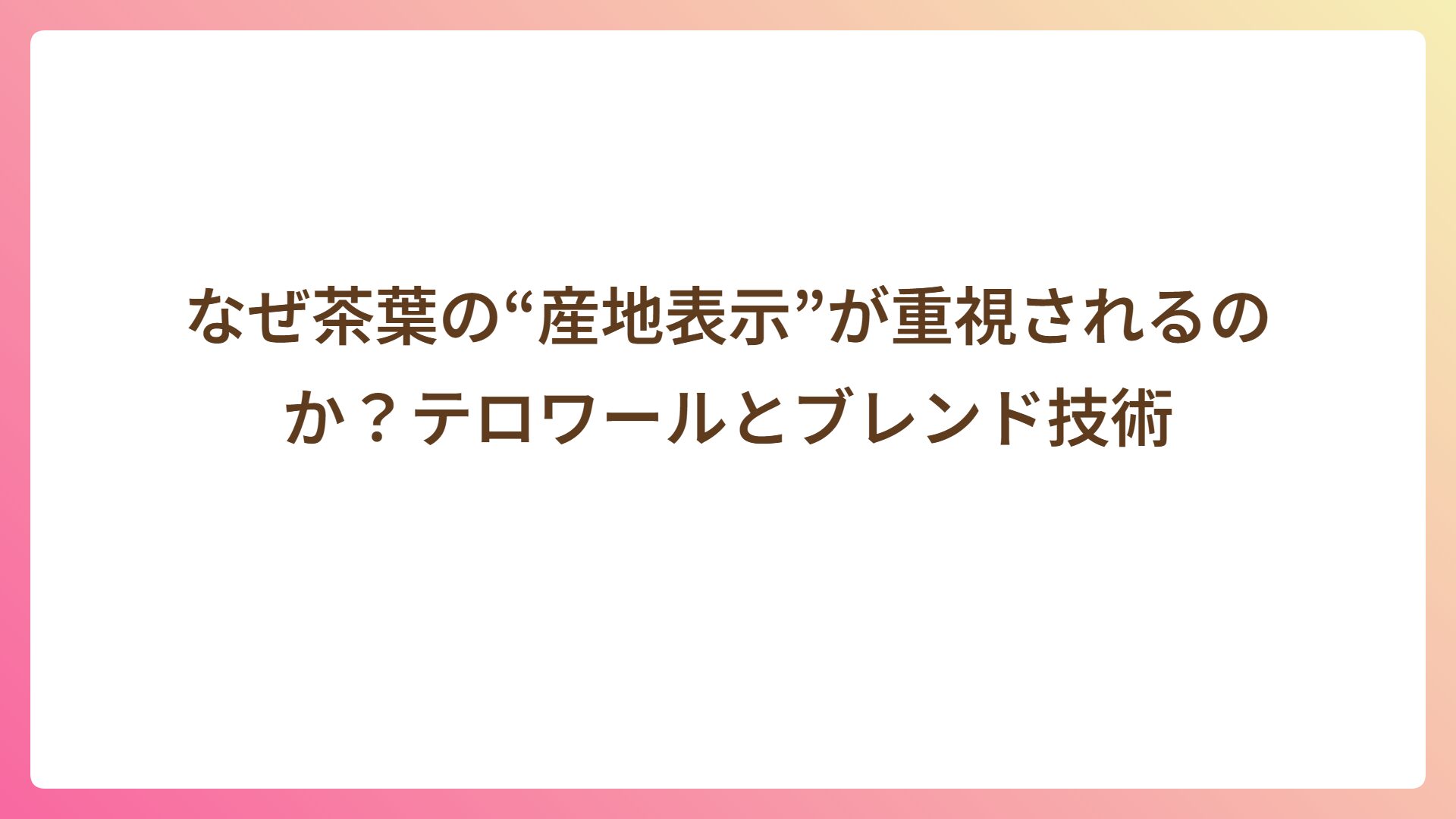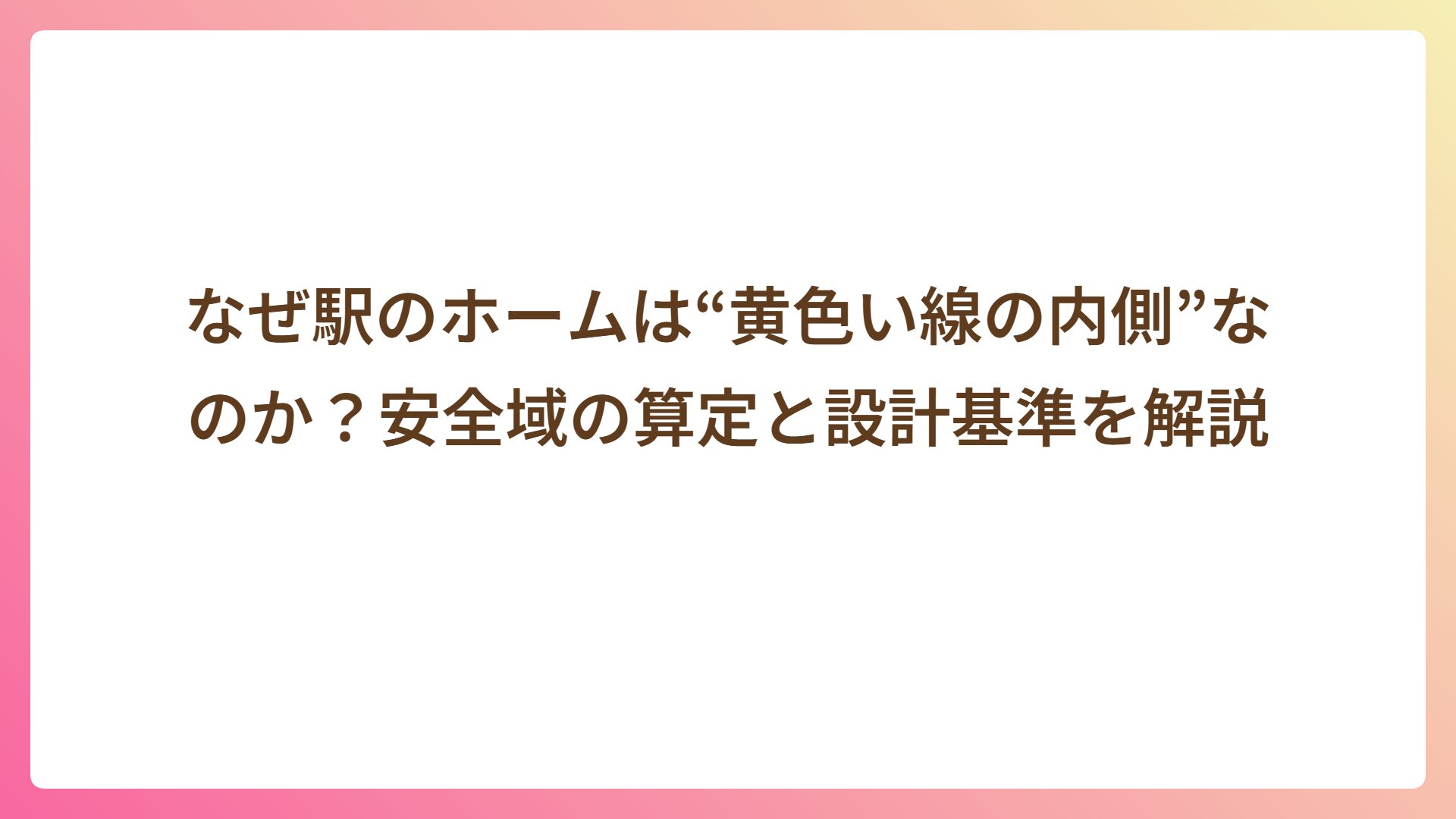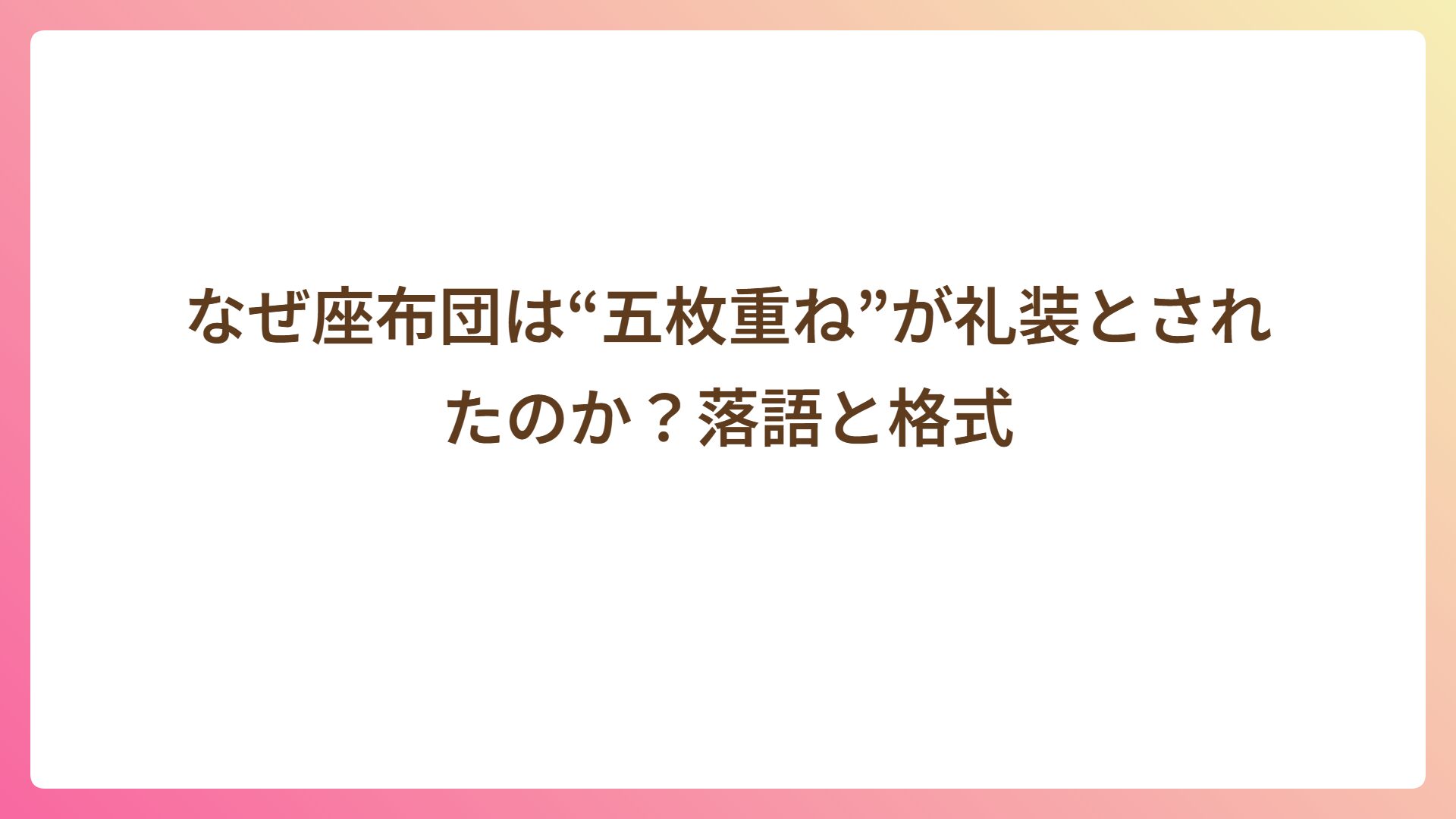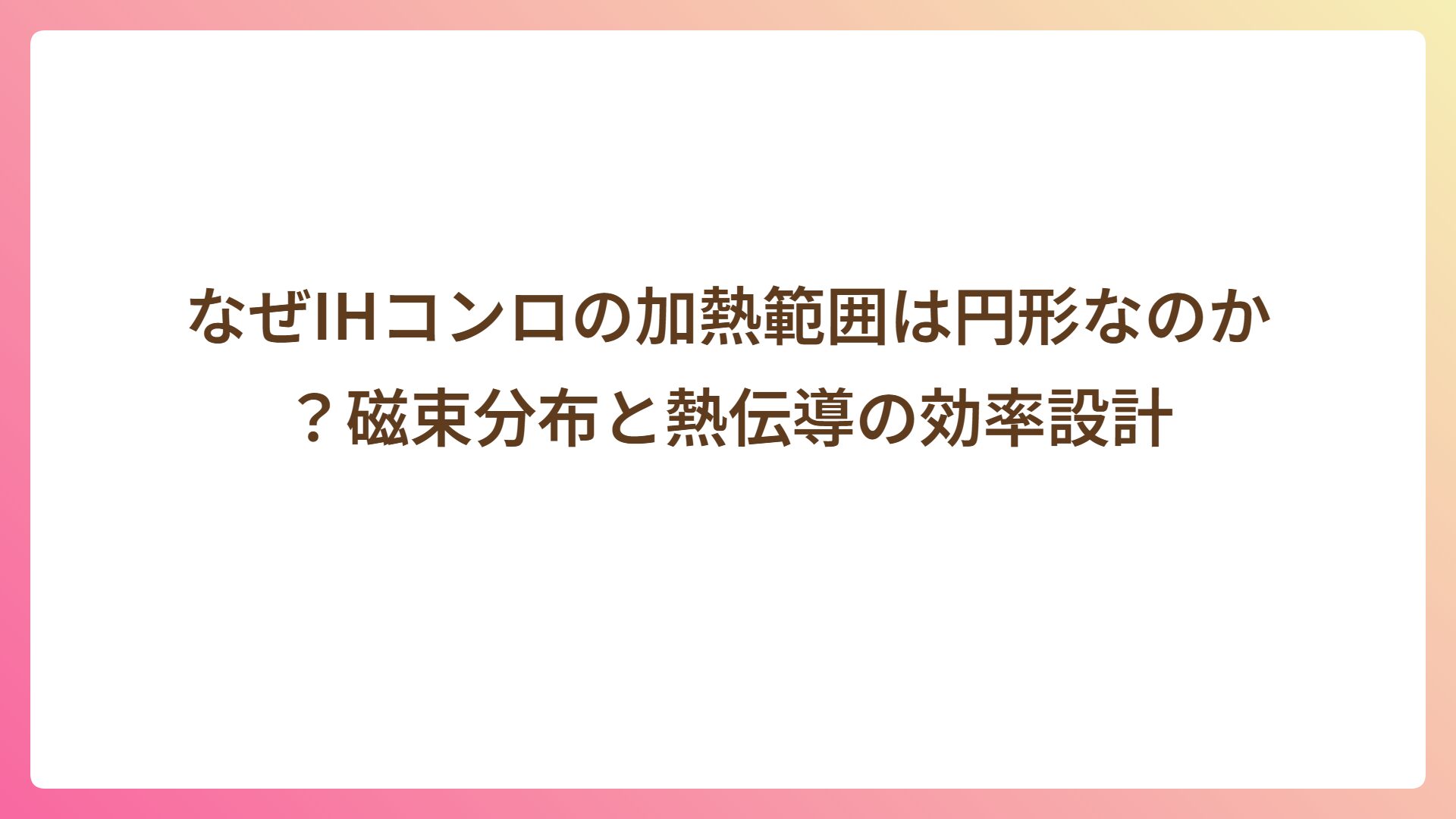なぜ「OK」と「NG」は日本語化したのか?放送現場の用語が日常語になった背景
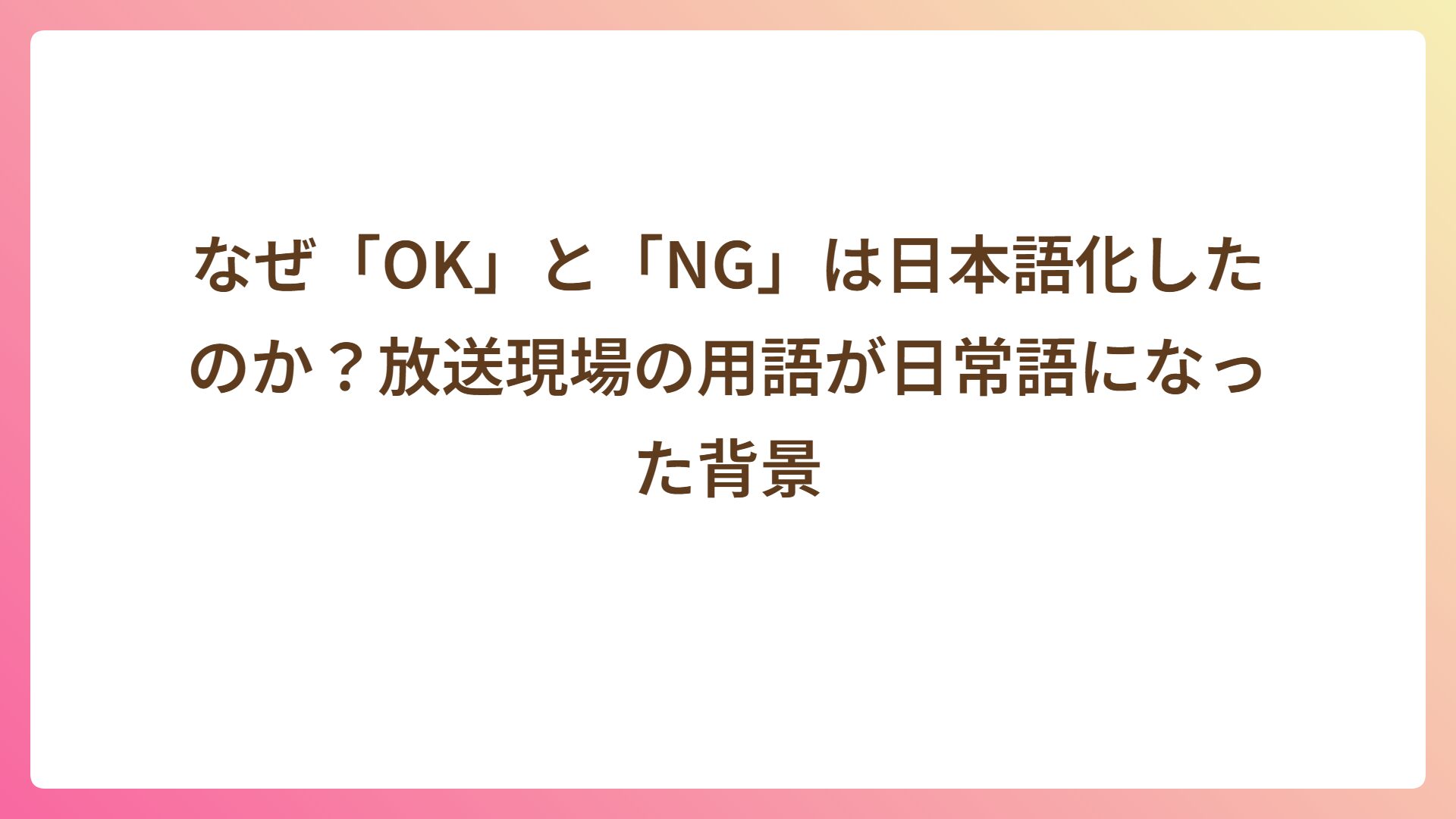
日常会話で「OK」や「NG」という言葉を何気なく使っていませんか?
これらは英語由来の略語ですが、実は日本語として定着しており、しかもその普及には放送・映像現場の“略語文化”が深く関わっています。
この記事では、「なぜ“OK”“NG”が日本語化したのか」を、役割・歴史・業界慣習の観点から解説します。
理由①:「NG」が映像・放送現場用語として定着したから
日本の放送・映画・演劇の現場では、収録や撮影の際に「使えないテイク」を“NG”と呼びます。 ウィキペディア+1
この「NG=No Good(良くない)」という略語が用いられたことで、業界内での共通語となり、さらに一般語として拡散していきました。
理由②:「OK」の流通・用語化も業界が一因
「OK(オーケー)」は英語圏でも古くから使われている肯定語ですが、日本で略語的に“使えて/通る”という文脈で広まった背景には、放送や制作現場での簡略な確認用語としての利用があったと考えられています。 온라인 영어 회화 네이티브 캠프+1
このような“即時判断(このテイクOK/このカットNG)”の場面で用いられたことで、略語の日本語化・浸透が進みました。
理由③:略語として“短く・記号的”に使われやすかった
OKやNGは、短くて発音・記憶が容易であり、テキストや会話で即時に「良・悪」の判定を示すのに適した言葉でした。
放送・撮影現場ではタイムリミットがあり、英語フレーズをそのまま使うより「OK/NG」と略す方が効率的だったという実務的理由があります。
理由④:放送・映像業界が言葉を一般化させる“媒体”だった
テレビ番組や映画、バラエティ番組の制作現場から出た“NGテイク集”や「NG集」という番組ジャンルの拡散もあり、NGという言葉が視聴者の認知に入る機会が多くなりました。 ウィキペディア
このように、業界発の用語が“一般語化”するメディア動線が、日本で「OK/NG」が普通に使われるようになった大きな要因です。
理由⑤:日本語として好まれる“二文字略語”文化とも合致
日本語では短く略せる言葉が浸透しやすく、例えば「OK」「NG」といった二文字略語は覚えやすく定着しやすい特徴があります。
そのため、業界内用語として始まった「OK/NG」が、一般社会にも受け入れられ、日常語化したと言えます。
理由⑥:英語圏では通じない“独自意味”として発展した
「NG」は英語圏では “No Good” の略として略語が使われていないため、日本で独自に意味を加えられた“和製略語”とも言えます。 らくらく英語ネット+1
その結果、英語話者には通じない場合が多く、日本語内での用法・ニュアンスが独自に育まれました。
理由⑦:言語変化・時代背景とともに広く一般化した
戦後の映像文化の成長、テレビ・ラジオ・雑誌・広告の発展とともに、放送用語や編集用語が一般語化する流れが強まりました。
この時期に「OK/NG」という略語も、制作現場から広く普及し、現在では「良い/ダメ」の意味で幅広く使われています。
まとめ:OKとNGが日本語化したのは“業界から世間へ”の道筋があったから
「OK」「NG」は、放送・映像制作の現場用語として使われ始め、
略語としての使いやすさ、略語文化との親和性、メディアの拡散力など複数の要因により、
日本語として定着・一般化した言葉です。
つまり、単に英語を借りただけではなく、業界実務と社会的普及が合わさった“言語変化”の結果なのです。