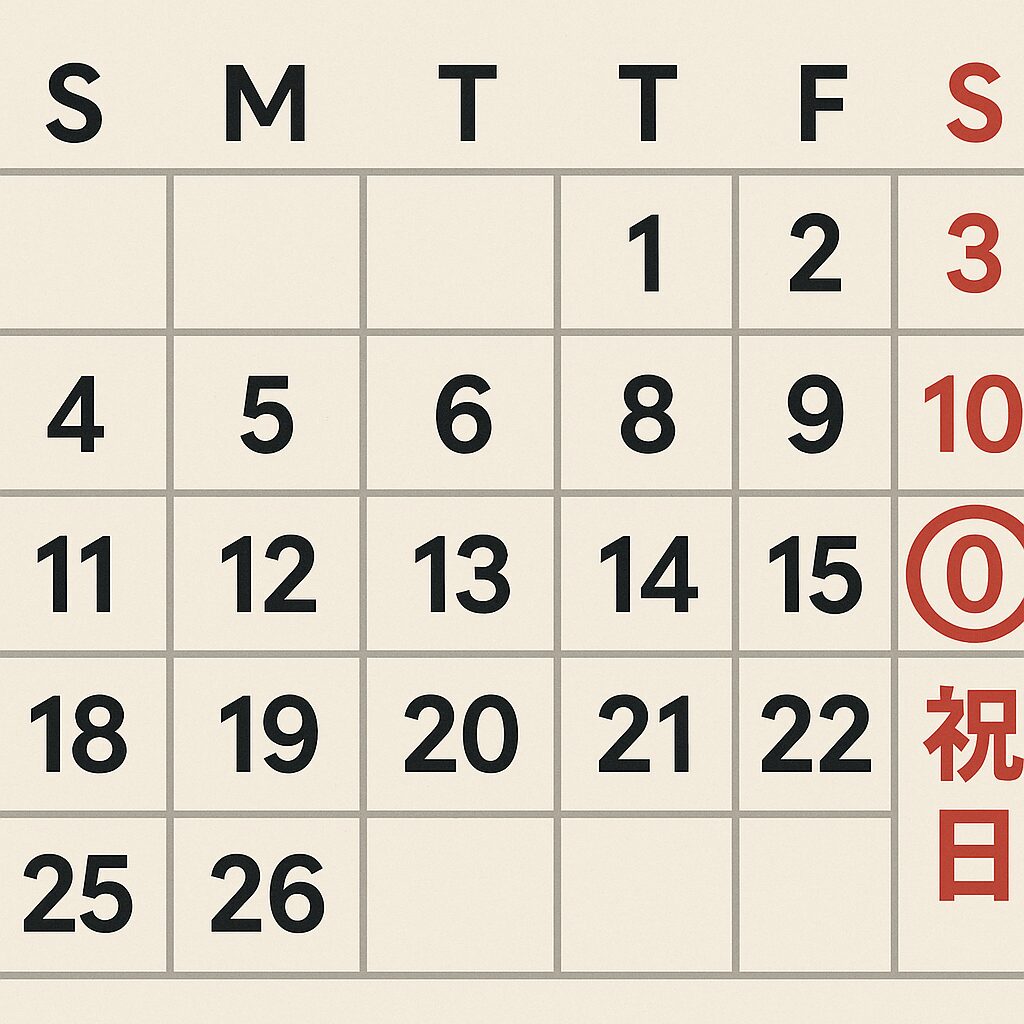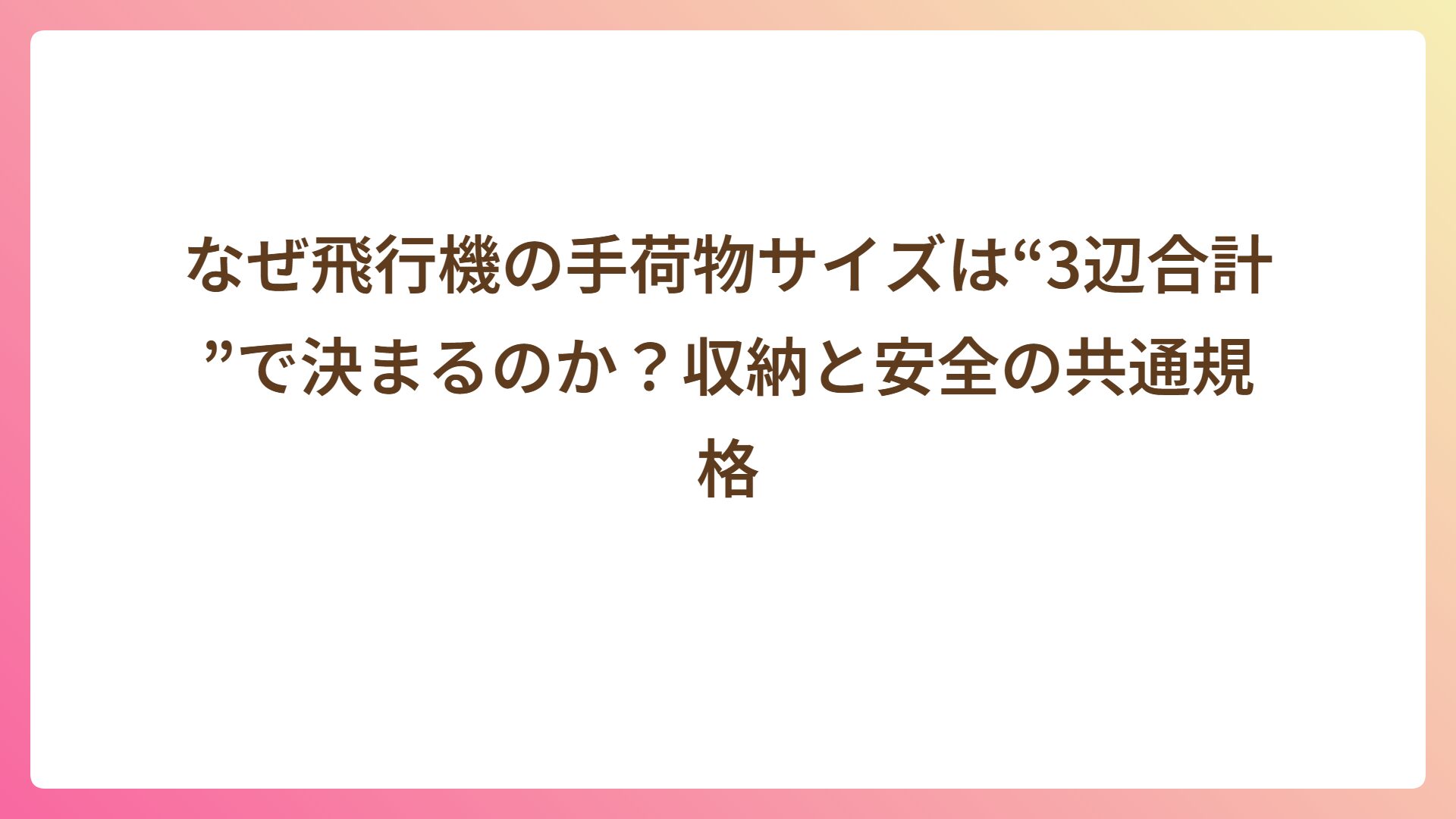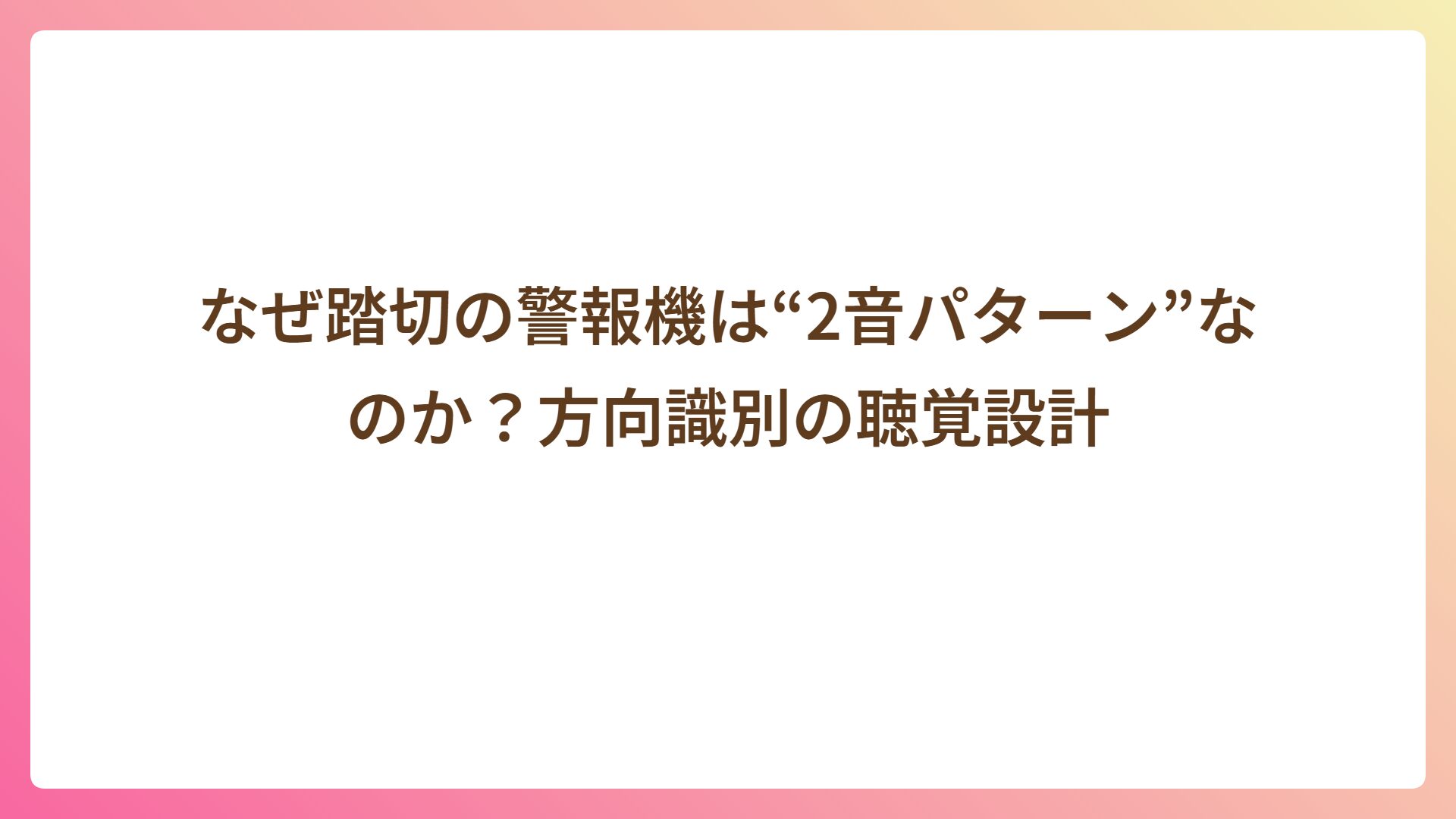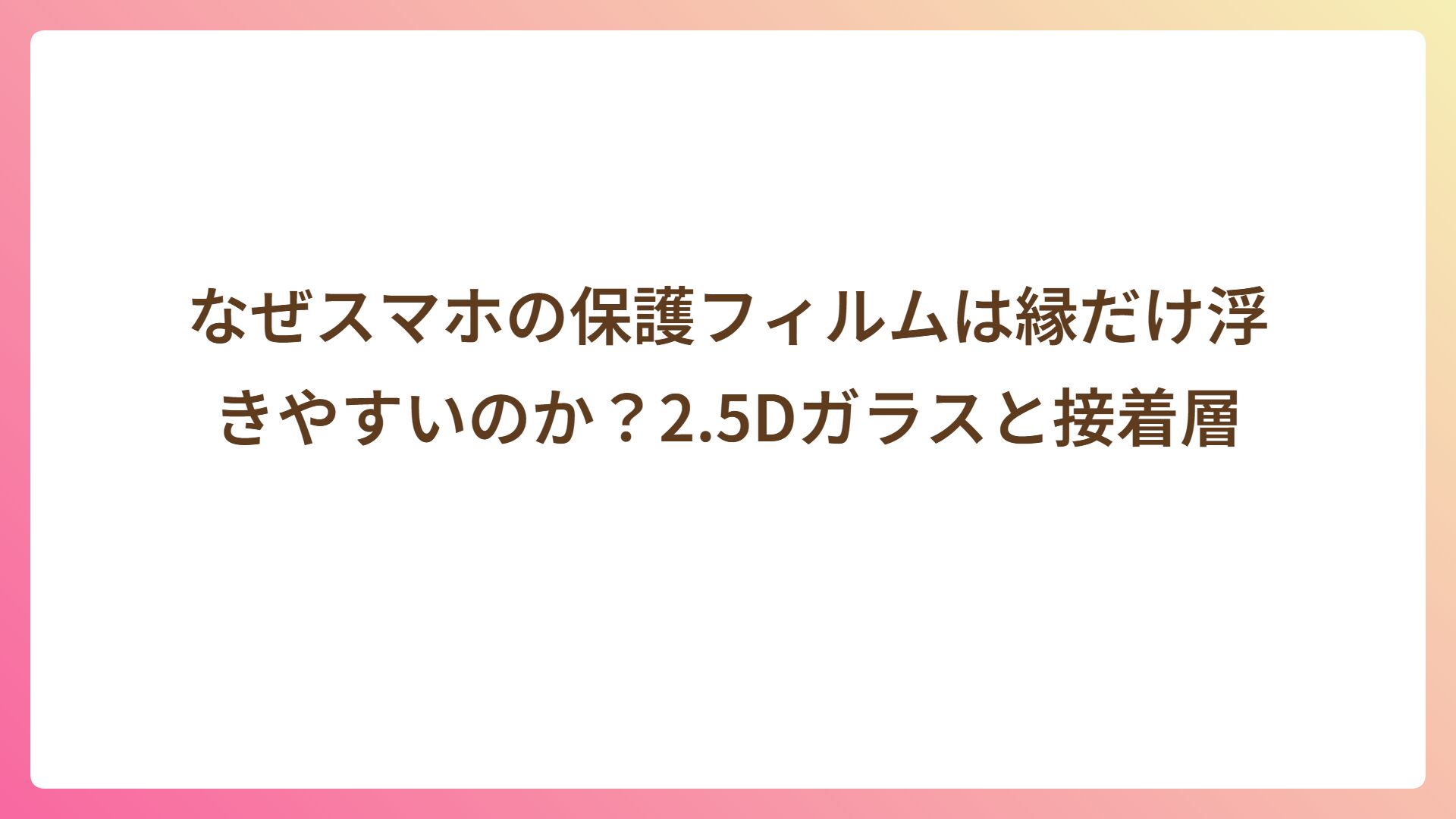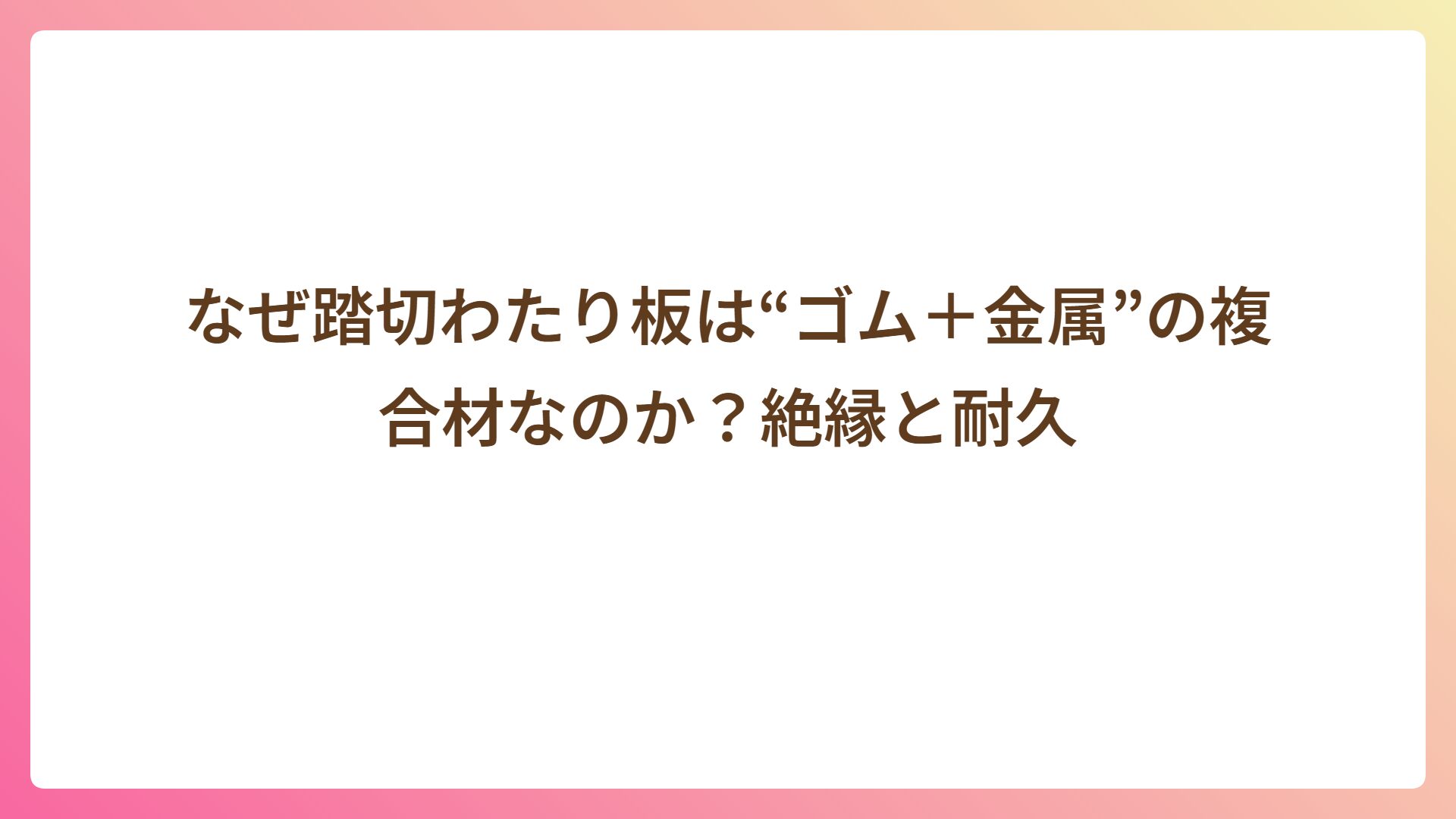なぜオクラは刻むと糸を引くのか?ムチンの正体と加熱のコツ
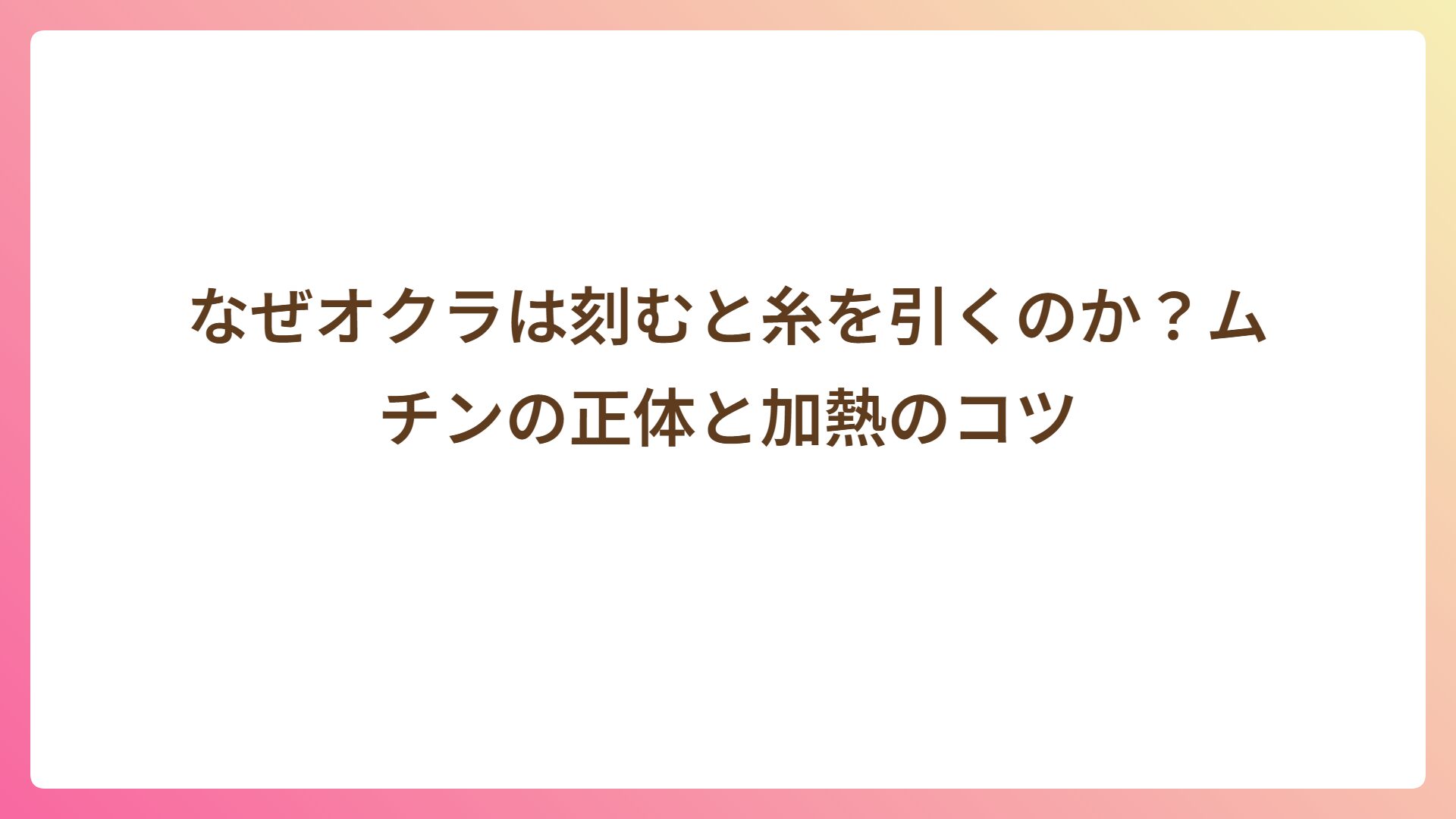
夏野菜の代表・オクラ。
包丁で刻むと、ねばねばの糸が長く伸びるのが特徴です。
この粘りの正体はいったい何なのでしょうか?
実はオクラのねばりには、健康効果と調理科学の両面が隠されています。
糸を引くのは「ムチン」と「ペクチン」の働き
オクラの粘りの主成分は、ムチン・ペクチン・ガラクタンなどの多糖類や糖タンパク質です。
特にムチンは、糖とタンパク質が結合した高分子物質で、
水を含むと強い粘性を発揮する性質を持っています。
包丁で刻むと細胞が壊れ、内部に蓄えられていたこれらの成分が溶け出し、
水分と結合して糸を引くように見えるのです。
つまり、あの“ねばねば”は細胞の中身が外へ出た結果というわけです。
ムチンは胃や喉を守る天然の潤滑剤
ムチンは人間の唾液や胃粘膜にも含まれる成分で、
粘膜を保護し、炎症を防ぐ役割があります。
そのため、オクラや山芋、モロヘイヤなどの粘り野菜は、
昔から「夏バテ予防」「胃にやさしい食材」として食べられてきました。
また、ムチンにはタンパク質の消化を助ける酵素も含まれており、
肉や魚との相性が良いのも科学的に裏付けられています。
刻み方で“粘りの強さ”が変わる
オクラの粘りは、刻むほど強くなります。
これは、細胞破壊の度合いが増えるほどムチンが多く放出されるためです。
細かく刻む「みじん切り」や叩く「ねばねば和え」にすると糸が長く、
輪切り程度ならさらっとした口当たりになります。
逆に、粘りを控えめにしたいときは、塩でもみ洗いして産毛と表面の粘質を軽く落とすのがコツです。
加熱すると粘りはどう変わる?
オクラの粘り成分は熱に比較的強く、
短時間の加熱では失われません。
ただし、長く煮たり炒めすぎると、多糖類が分解して粘りが弱まります。
強いねばりを活かしたい場合は「さっと湯通し」や「軽い蒸し加熱」が最適です。
一方で、スープやカレーなどに使うときは、
あえて加熱してとろみを自然に溶け込ませる方法もあります。
まとめ
オクラを刻むと糸を引くのは、
ムチンやペクチンが細胞から放出され、水と反応して粘るためです。
その粘りは、食感を作るだけでなく、体を守る天然の機能でもあります。
包丁の入れ方や加熱時間を変えるだけで、
ねばり具合を自在に調整できる——
オクラはまさに、科学と健康が融合した“夏の粘り野菜”なのです。