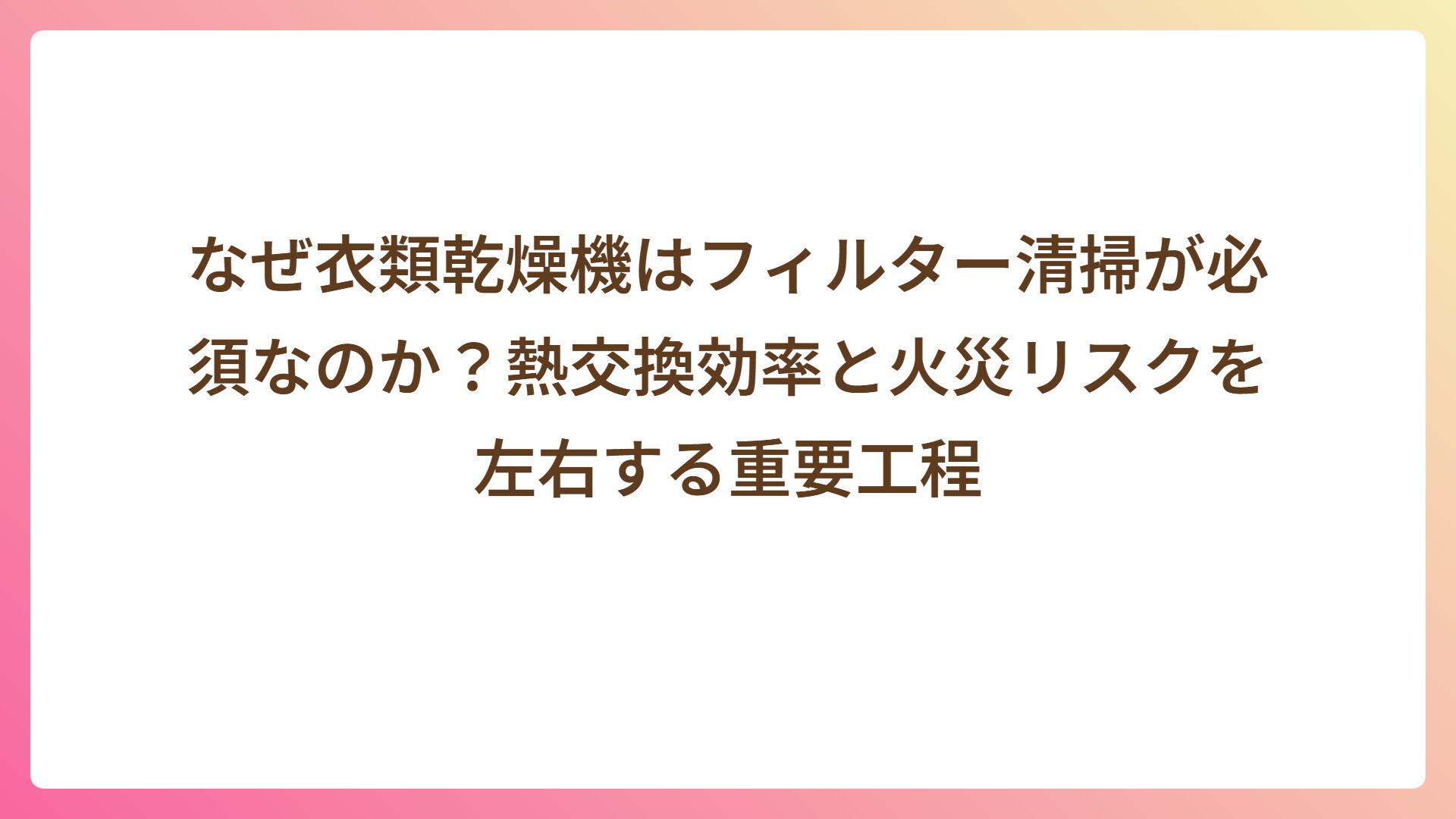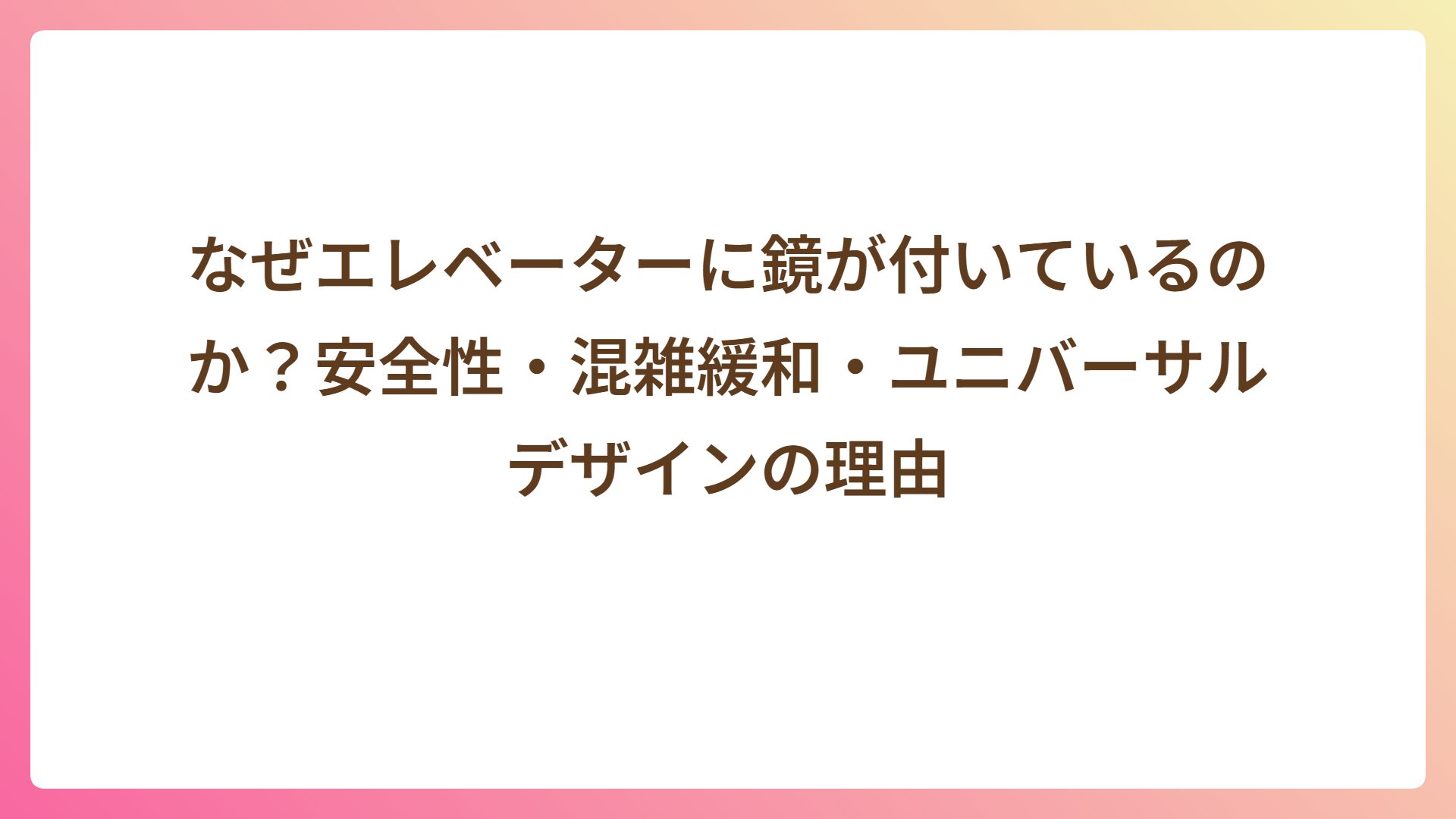なぜ温泉地に“饅頭”が多いのか?蒸気と観光土産の相性
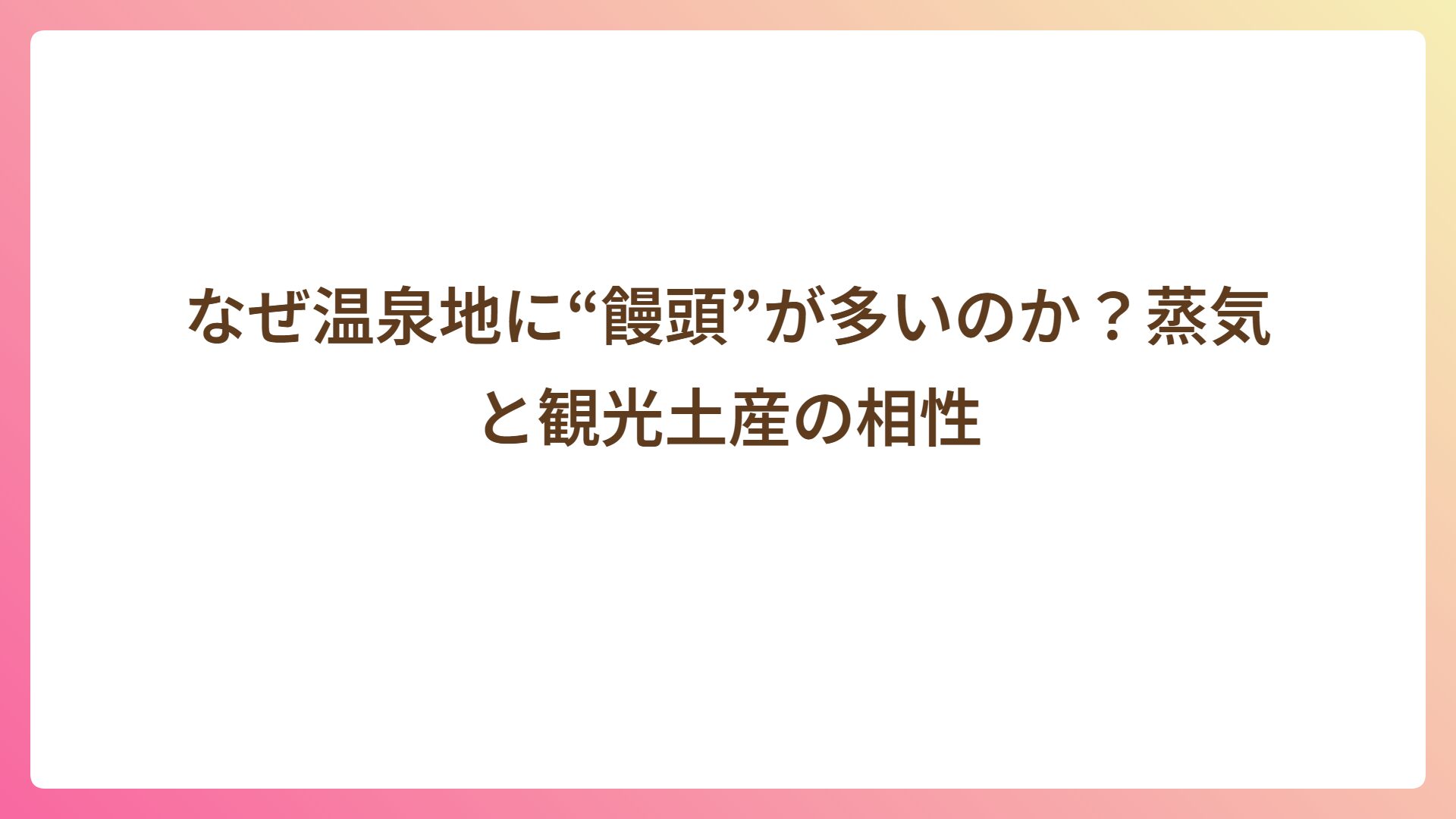
草津、伊香保、箱根、別府……どの温泉街にも必ずといっていいほど並ぶ「温泉饅頭」。
なぜ全国の温泉地で、これほどまでに饅頭が定番となったのでしょうか。
そこには、蒸気という地の利と、観光文化の発展が重なった必然がありました。
発祥は“伊香保温泉の湯乃花饅頭”
温泉饅頭のルーツは、群馬県の伊香保温泉にあります。
大正時代初期、旅館「勝月堂」の初代が、温泉の湯気で蒸し上げた茶色い饅頭を考案しました。
当時の温泉の湯には鉄分が多く、茶褐色の湯花が浮かぶことから、「湯乃花饅頭」と命名。
この饅頭が観光客に大ヒットし、全国の温泉地へと広まっていったのです。
つまり、温泉饅頭は“温泉地発祥の土産文化”の第一号といっても過言ではありません。
温泉の蒸気は“天然の蒸し器”
温泉地で饅頭が作られた最大の理由は、蒸気の存在です。
饅頭は蒸して仕上げる菓子であり、温泉の湯気を使えば、
火を使わずに一定の温度と湿度で大量に蒸すことができます。
特に、硫黄泉や塩化物泉などの源泉は100℃近い高温蒸気を安定的に供給でき、
製造にも演出にも最適でした。
観光客が「湯けむりの中で饅頭を蒸している光景」に惹かれるのも、
この土地の特性と製法が一致している“見せる調理”の魅力によるものです。
茶色い皮にも“温泉の色”が宿る
温泉饅頭の多くが茶色いのは、黒糖を使っているためです。
黒糖の甘みと香ばしさが温泉の香りとよく合い、
さらに日持ちと風味保持にも優れているという実用的な理由もあります。
伊香保や草津の湯の色が茶褐色であることから、
その色味を反映した黒糖生地が「温泉らしさ」の象徴になりました。
つまり、温泉饅頭の茶色は風景と味覚をリンクさせたデザインなのです。
“手土産に最適”という観光経済の論理
観光客にとって、饅頭は持ち運びやすく、配りやすい理想的な土産です。
小分け包装しやすく、常温保存ができ、見た目にも高級感がある。
しかも、誰が食べても好まれる“無難で上品なお菓子”という点が評価されました。
温泉街が観光地として整備されていく中で、
「温泉=饅頭」は鉄道土産文化の波に乗って全国化していきました。
駅前で湯気を立てる蒸籠(せいろ)は、観光客の購買意欲を刺激する“演出装置”でもあったのです。
地域ごとの“温泉饅頭アレンジ”
全国の温泉地には、それぞれ特色ある温泉饅頭が存在します。
- 箱根:こしあんの「箱根まんじゅう」
- 草津:黒糖香る「湯の花まんじゅう」
- 有馬:しっとり皮の「炭酸まんじゅう」
- 別府:塩味をきかせた「地獄蒸しまんじゅう」
どれも源泉の性質や地域の味覚に合わせて改良され、
“地域の味覚×温泉の個性”を融合させた土産として発展してきました。
温泉饅頭=“土地の記憶”を持ち帰る菓子
温泉地で饅頭が定番になった理由をまとめると、次の通りです。
- 温泉の蒸気が饅頭づくりに最適だった
- 黒糖生地が湯けむりと相性抜群だった
- 見た目・香り・保存性のすべてが観光土産向き
- “湯けむりで蒸す”という演出が観光客を惹きつけた
つまり、温泉饅頭は単なる菓子ではなく、「旅先の風景を持ち帰る仕掛け」なのです。
袋を開けた瞬間にふわりと立ちのぼる香ばしい香りは、
湯けむりとともに過ごした旅の記憶そのもの。
温泉饅頭は、まさに“味で帰る温泉文化”の象徴といえるでしょう。