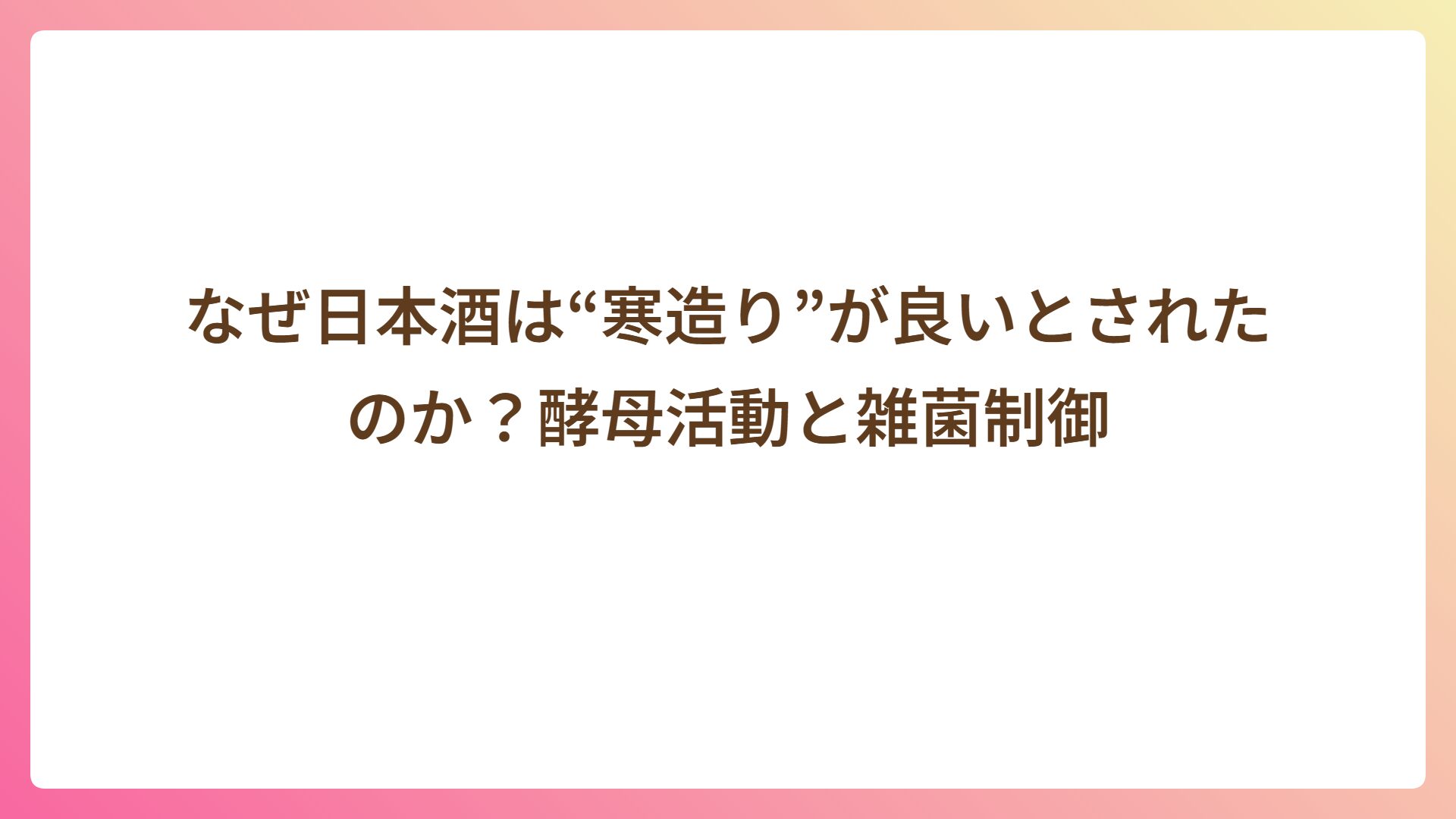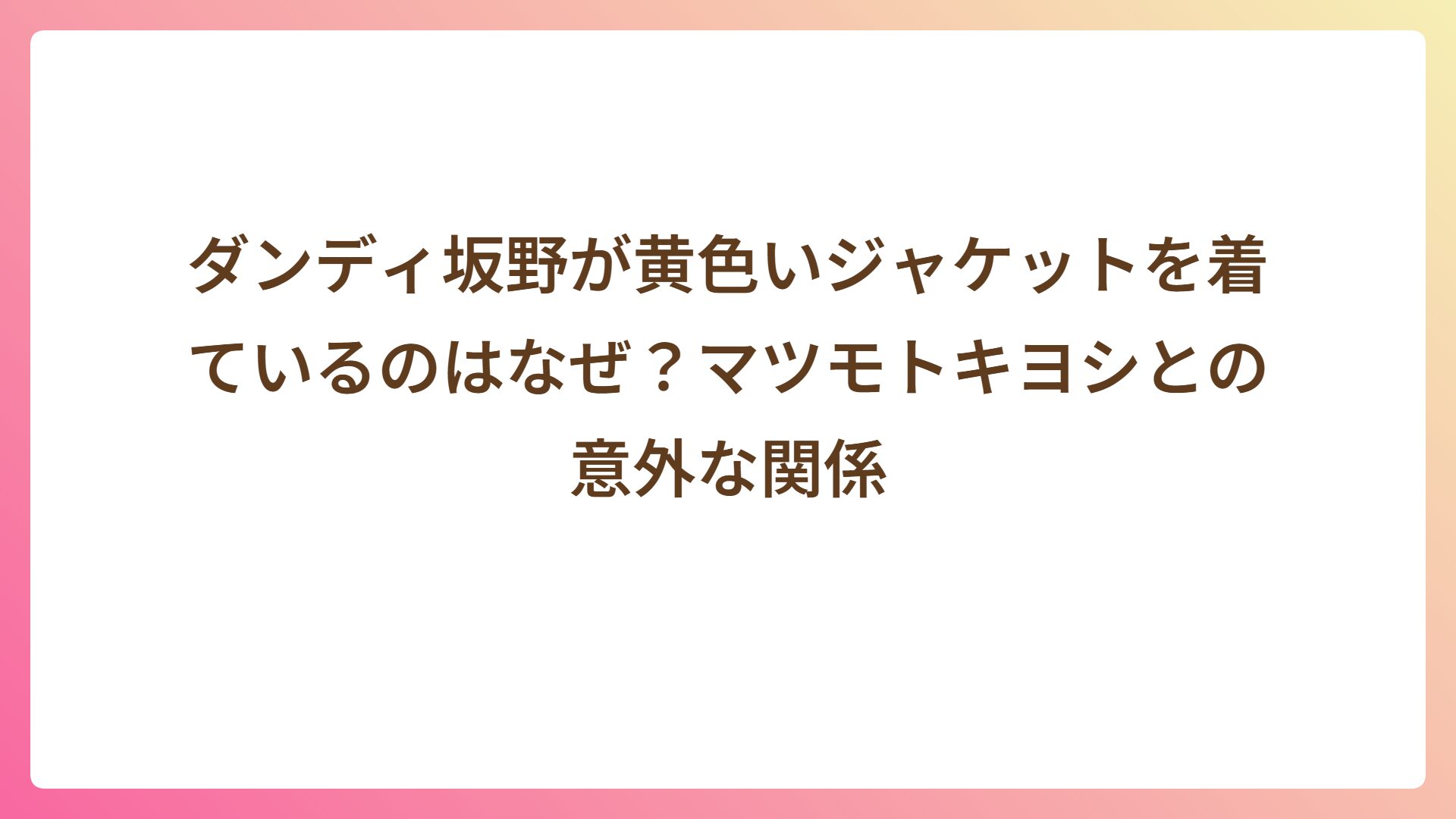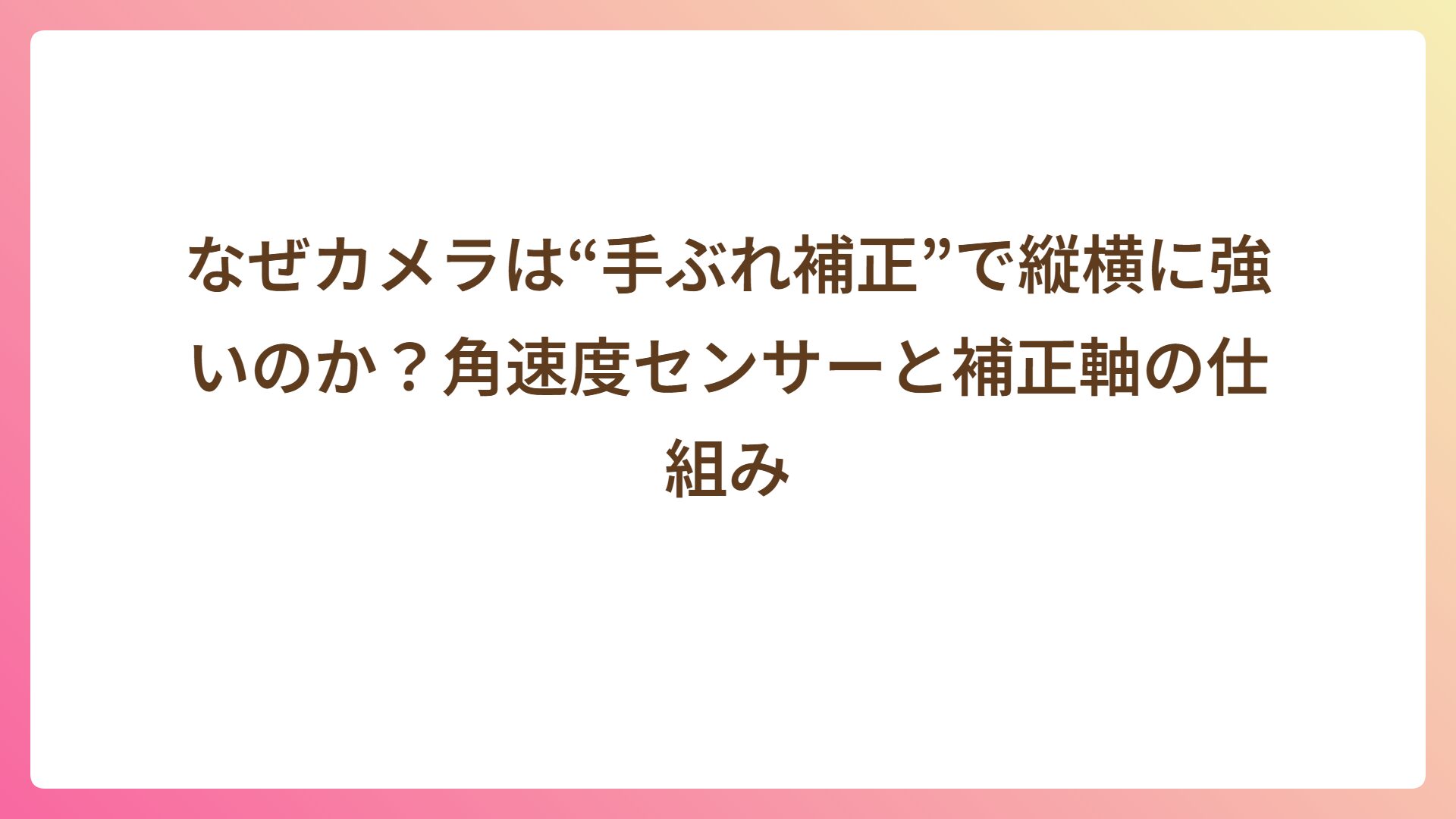なぜ「お屠蘇」は新年に飲むのか?生薬と邪気払いの由来
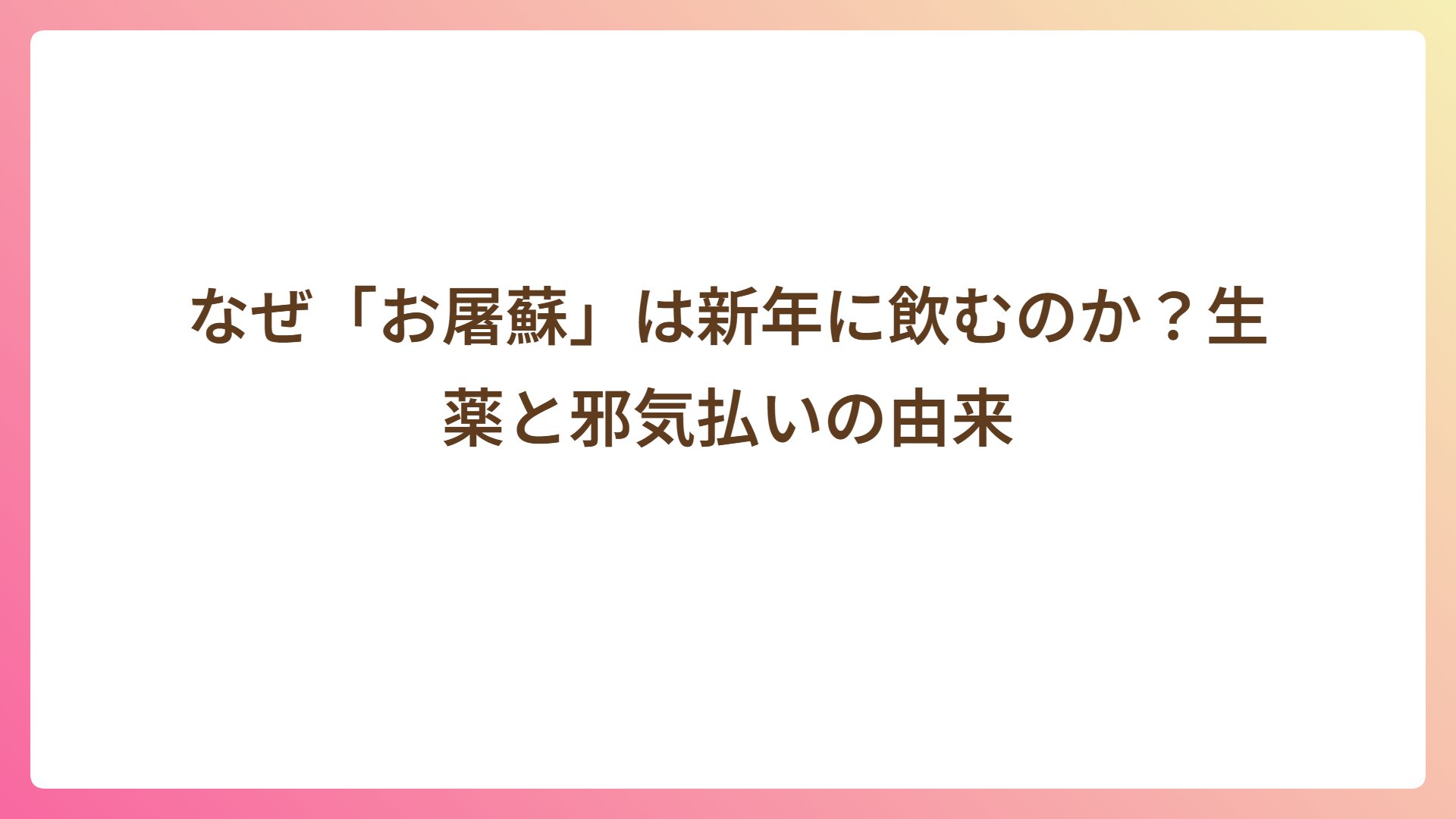
正月に家族そろって「お屠蘇」を口にする——。
日本では新年の定番行事として親しまれていますが、
なぜこの特別な薬酒を“年の初め”に飲むのでしょうか?
そこには、古代中国の風習と日本の歳神信仰が融合した健康祈願の儀礼が隠されています。
お屠蘇とは「邪気を祓う薬酒」
お屠蘇(屠蘇酒)は、山椒・桂皮(シナモン)・防風・桔梗などの生薬を調合した薬草酒です。
漢方的には、体を温め、消化を助け、風邪や邪気を遠ざける効能があるとされます。
「屠蘇」という言葉には、
- 「屠」=邪を屠(ほふ)る(退治する)
- 「蘇」=魂を蘇らせる(甦り・回復)
という意味があり、
**“悪気を退け、新しい命を得る”**という願いが込められています。
つまり、お屠蘇とは**「年の初めに飲む厄除けの薬酒」**なのです。
起源は中国・三国時代の風習
お屠蘇の風習は、中国・三国時代の医師「華佗(かだ)」が考案したと伝えられています。
正月に邪気が入りやすいとされた冬の終わり、
「薬草を酒に浸して飲めば、病を防げる」という健康法が生まれました。
この風習は、唐代には「元旦の朝に一家でお屠蘇を飲み、年長者から順に盃を回す」として定着し、
やがて平安時代に日本へ伝来します。
当時の日本では宮中行事として採用され、
「歳旦祭」の一環として年神を迎える神聖な飲み物となりました。
日本では“延命長寿”の象徴へ
平安貴族の間では、お屠蘇は「年のはじめに新しい生命をいただく」儀式とされ、
新年最初に口にする食べ物=**“邪気を払う第一の飲食”**として重視されました。
江戸時代には庶民にも広まり、
薬種屋が「屠蘇散(とそさん)」と呼ばれる生薬セットを販売。
人々はそれを酒やみりんに浸し、家庭で一年の無病息災を祈る風習を受け継ぎました。
こうして、お屠蘇は**「祝い酒」+「薬酒」**という二つの意味を持つようになったのです。
飲み方にも“祈り”が込められている
お屠蘇を飲む際は、
若い人から年長者へと盃を回すのが正式な作法とされています。
これは「若い人の生気を年長者へ分け、共に長寿を願う」という意味。
また、盃は三段重ねの「屠蘇器(とそき)」を用い、
三回に分けて少しずつ飲むのが一般的です。
この“三”という数も、陰陽道で「陽の数」「再生の象徴」とされており、
健康と再生を祈る儀礼的な所作といえます。
現代でも生きる“健康祈願の酒”
現代の家庭では、薬草を浸した本格的なお屠蘇は少なくなりましたが、
屠蘇散や屠蘇酒キットが薬局やスーパーで手軽に手に入ります。
お屠蘇を飲むという行為そのものが、
「一年を健やかに過ごしたい」という気持ちの表れであり、
今なお“健康と節目を意識する伝統的な日本の作法”として受け継がれています。
まとめ
お屠蘇を新年に飲むのは、
古代中国の薬酒文化と日本の年神信仰が融合した「邪気払いの儀式」だからです。
- 生薬による健康祈願
- 「屠(退治)+蘇(再生)」の象徴的意味
- 若者から年長者へ生命力をつなぐ作法
お屠蘇とは、単なる祝い酒ではなく、
「新しい一年の命を迎えるための再生の酒」なのです。