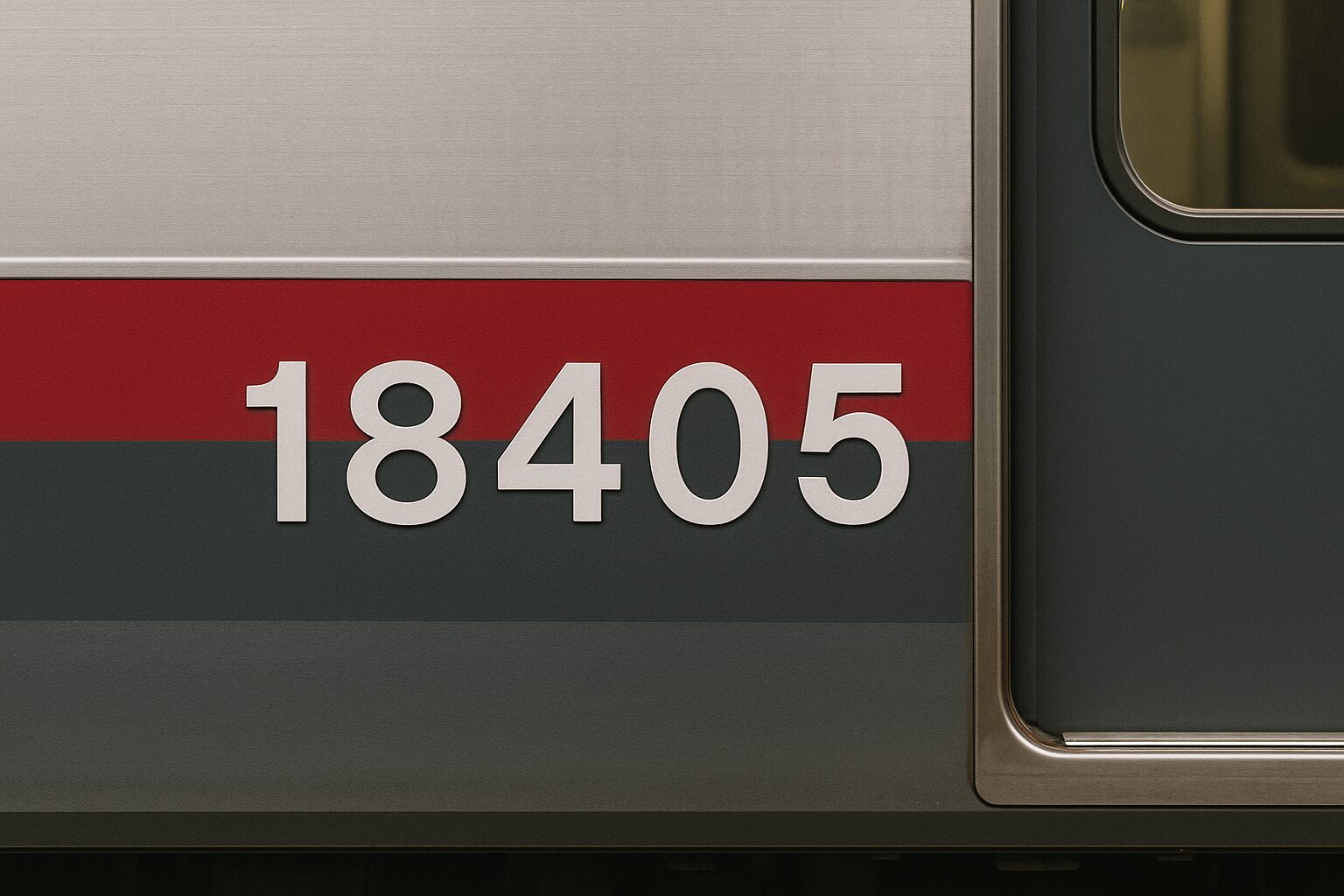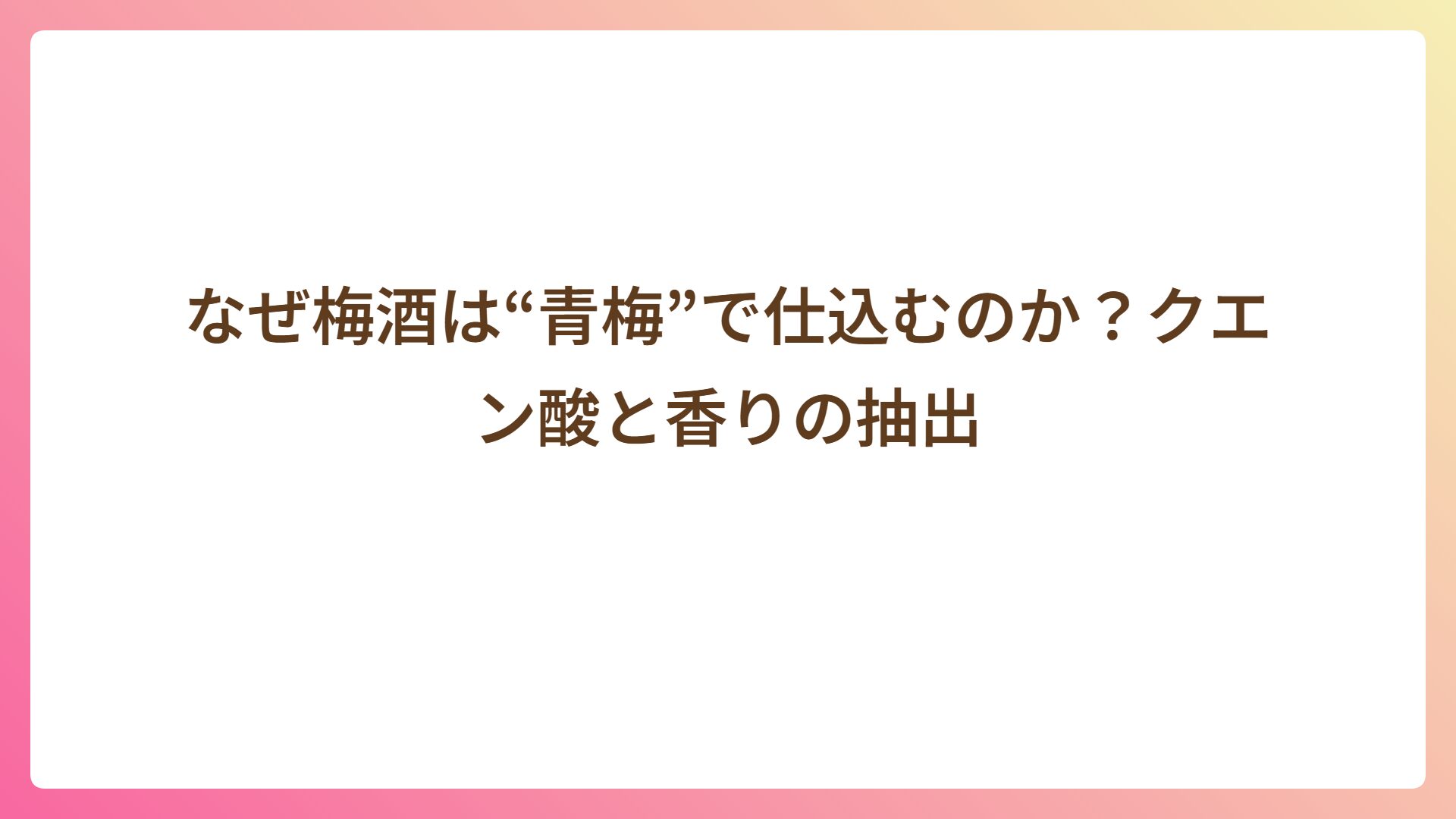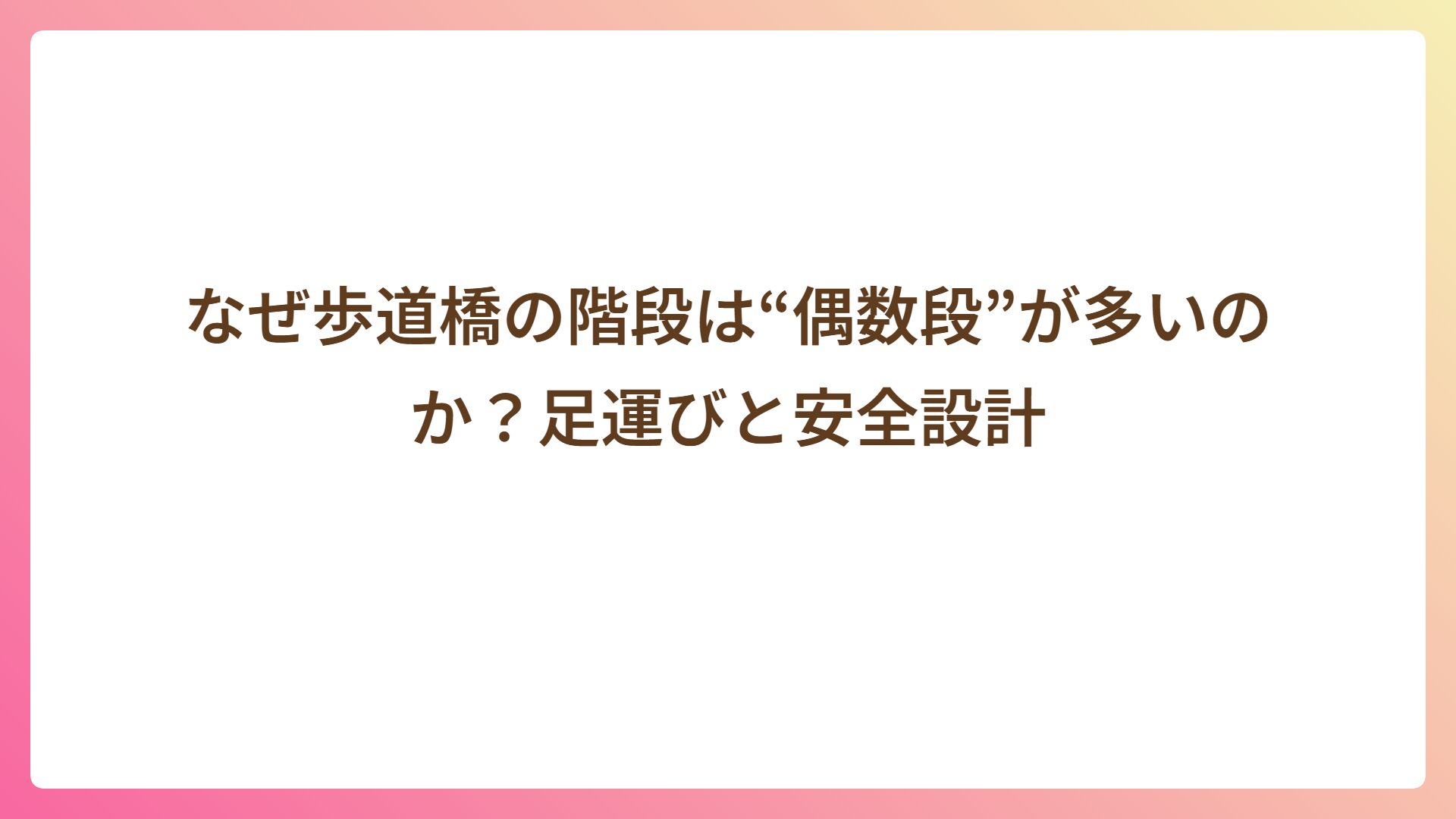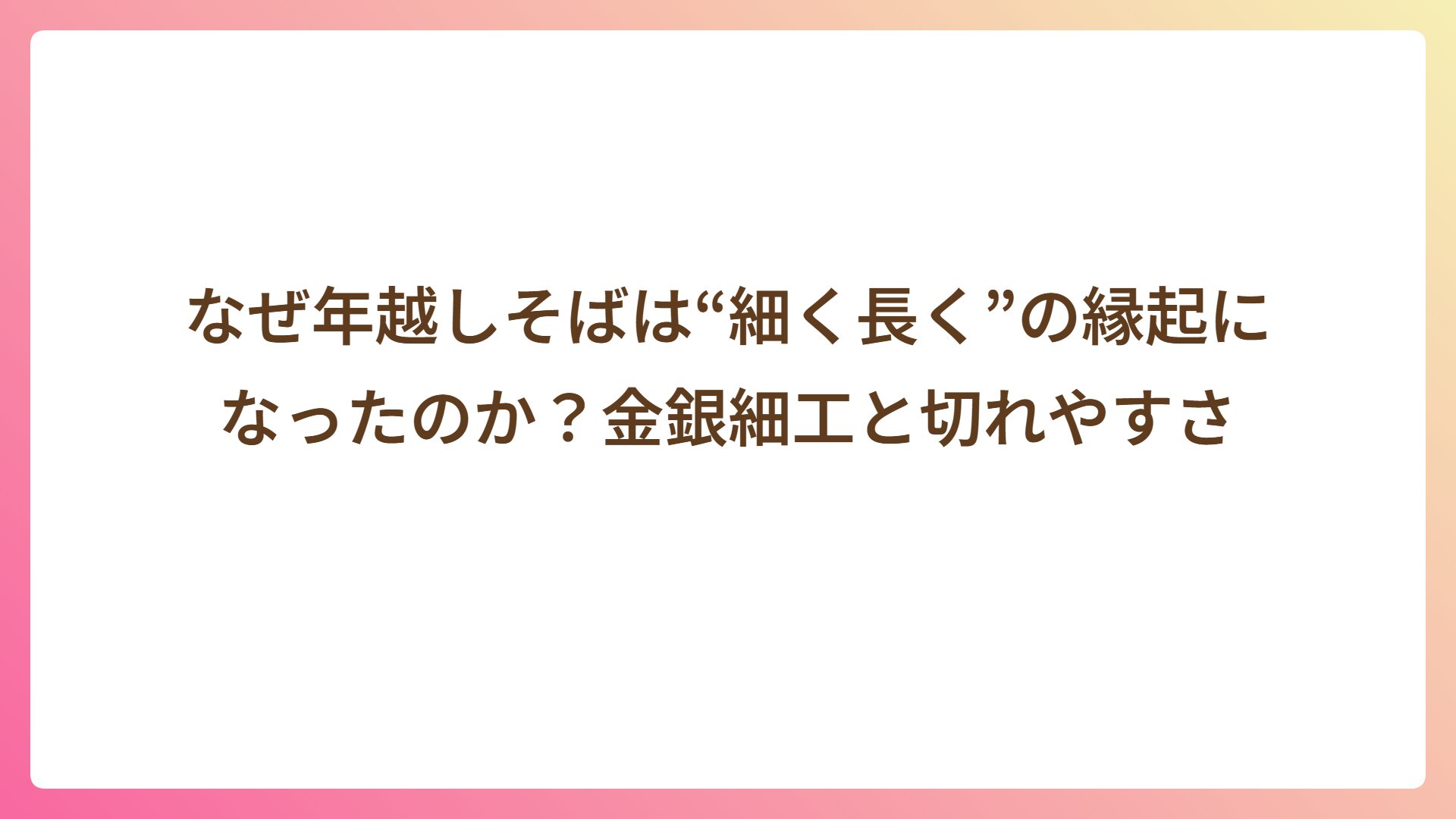なぜペットボトルの底は“星型”が多いのか?耐圧性と成形技術が生んだ最適構造

ペットボトルを裏返してみると、底が“星のような形”に凹んでいるのを見たことがあるでしょう。
なぜ平らではなく、わざわざこの形をしているのでしょうか?
実はこの「星型構造」には、耐圧・安定・製造効率といった機能的な理由が隠されています。
この記事では、ペットボトルの底が星型になっている理由を、物理と成形技術の視点から解説します。
理由①:炭酸ガスの“内圧”に耐えるための形
ペットボトルの多くは、炭酸飲料など高い内圧がかかる液体を入れるために設計されています。
炭酸飲料では内部圧力が最大で約0.5~0.6MPa(5〜6気圧)にもなり、
平らな底面では内圧によって中央が膨らみ、ボトルが転がる・変形する恐れがあります。
そのため、底部を五つの脚のように放射状に凹ませる「ペタロイド底(petaloid base)」を採用。
これにより、
- 圧力が五方向に均等に分散される
- 凹み構造がドーム状の強度を生む
- 膨張しても形状が保たれる
という効果が得られます。
つまり星型は、見た目ではなく耐圧性を高めるための合理的な構造なのです。
理由②:安定して“自立”できる
星型の底は、単なる耐圧構造にとどまらず、自立性の確保にも貢献しています。
放射状の5本の脚の先端が地面に接することで、
わずかな凹凸のある場所でもぐらつかずに立つように設計されています。
もし完全にドーム状で平らな底なら、
- 接地面が狭く不安定になる
- 転がりやすくなる
という欠点が生じます。
星型底はその両立を狙い、
「耐圧ドーム構造」+「5点支持による安定」
というハイブリッド構造になっているのです。
理由③:成形時の“収縮”を均一にするため
ペットボトルは、PET樹脂を高温で加熱してから空気で膨らませる「ブロー成形」という方法で作られます。
このとき、底部に厚みのムラや応力集中があると、
- 成形後に変形やひび割れが起きる
- ボトルが冷却時に“へこむ”
といったトラブルが発生します。
そこで底を星型にすることで、
- 応力を均等に逃がす
- 冷却時の収縮を分散する
- 金型からの離れをスムーズにする
という製造上の利点が得られるのです。
つまり星型は生産工程の安定性を保つための形状でもあります。
理由④:ドーム構造が“内圧を押し返す”
ペットボトルの星型底をよく見ると、中央が少し内側に丸くへこんでいます。
これは「圧力を押し返すドーム構造」になっており、
中のガスが膨張しても、力が外ではなく中心に向かって分散するように作られています。
このドーム構造は、卵の殻や建築ドーム屋根と同じ原理で、
少ない材料で大きな力に耐えられる“構造的強度”を生み出しています。
理由⑤:飲料の“種類”によって底の形が違う
実は、すべてのペットボトルが星型なわけではありません。
飲料の内容物や用途によって、底の形状が異なります。
| 飲料の種類 | 底の形状 | 理由 |
|---|---|---|
| 炭酸飲料 | 星型(ペタロイド底) | 高い内圧に耐えるため |
| 水・お茶 | 平底 | 内圧がないので安定重視 |
| ホット飲料 | 円錐型(ドーム+リング) | 熱膨張・変形を防ぐ |
| 業務用大容量 | 平底+補強リブ | 安定とコスト重視 |
つまり、星型は「炭酸ボトルに最適化された設計」。
圧力・安定・コストのバランスを取った機能美の結晶なのです。
理由⑥:視覚的にも“炭酸らしさ”を演出
最後に、デザイン面の理由もあります。
星型の底は、光を反射してキラキラと見える特徴があり、
「冷たさ」「爽快感」「清涼感」を視覚的に強調する効果があります。
これは無意識に「炭酸=キリッと冷たい飲み物」という印象を与えるため、
マーケティング上も好まれる形状になっています。
まとめ:星型の底は“強さと安定の最適解”
ペットボトルの底が星型なのは、
- 内部の炭酸圧力を分散して耐圧性を高める
- 5点支持で安定して自立できる
- 成形時の応力や収縮を均一化できる
- ドーム構造で強度と軽量化を両立する
という、物理的・工学的に最も合理的な設計だからです。
つまり、星型の底はデザインではなく「構造の答え」。
見た目の美しさの裏には、圧力・製造・使用のすべてを最適化した機能美が隠されているのです。