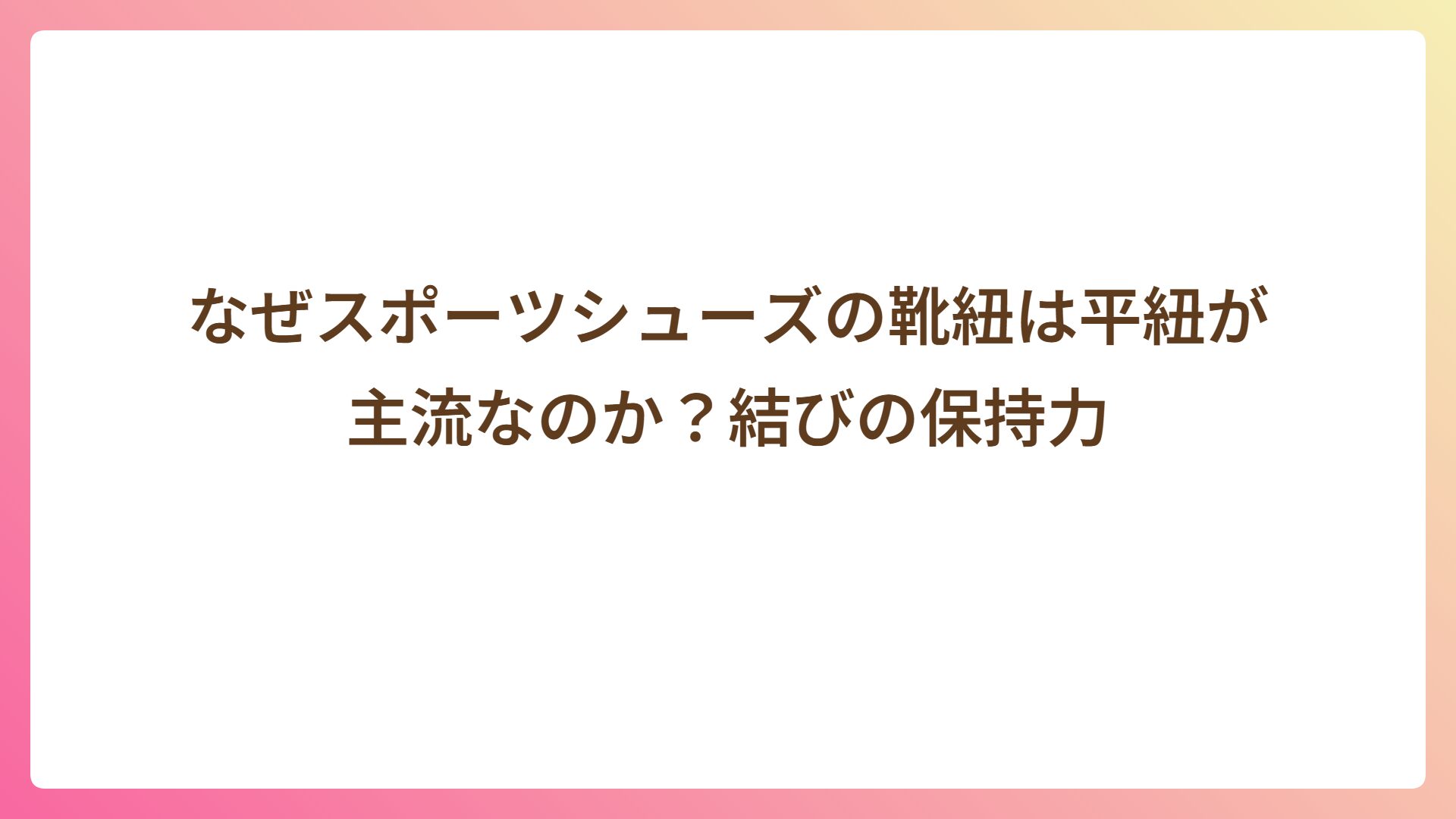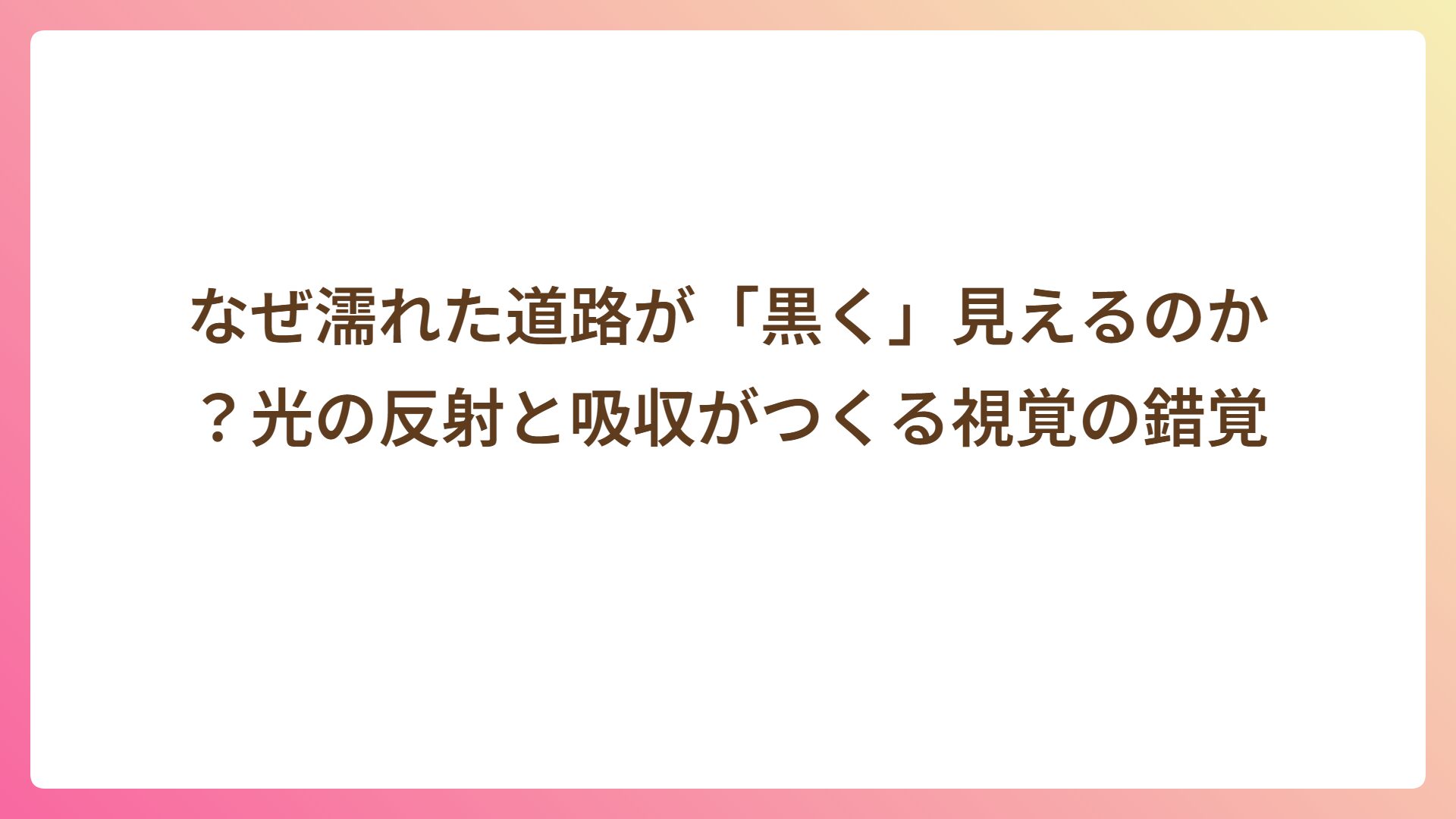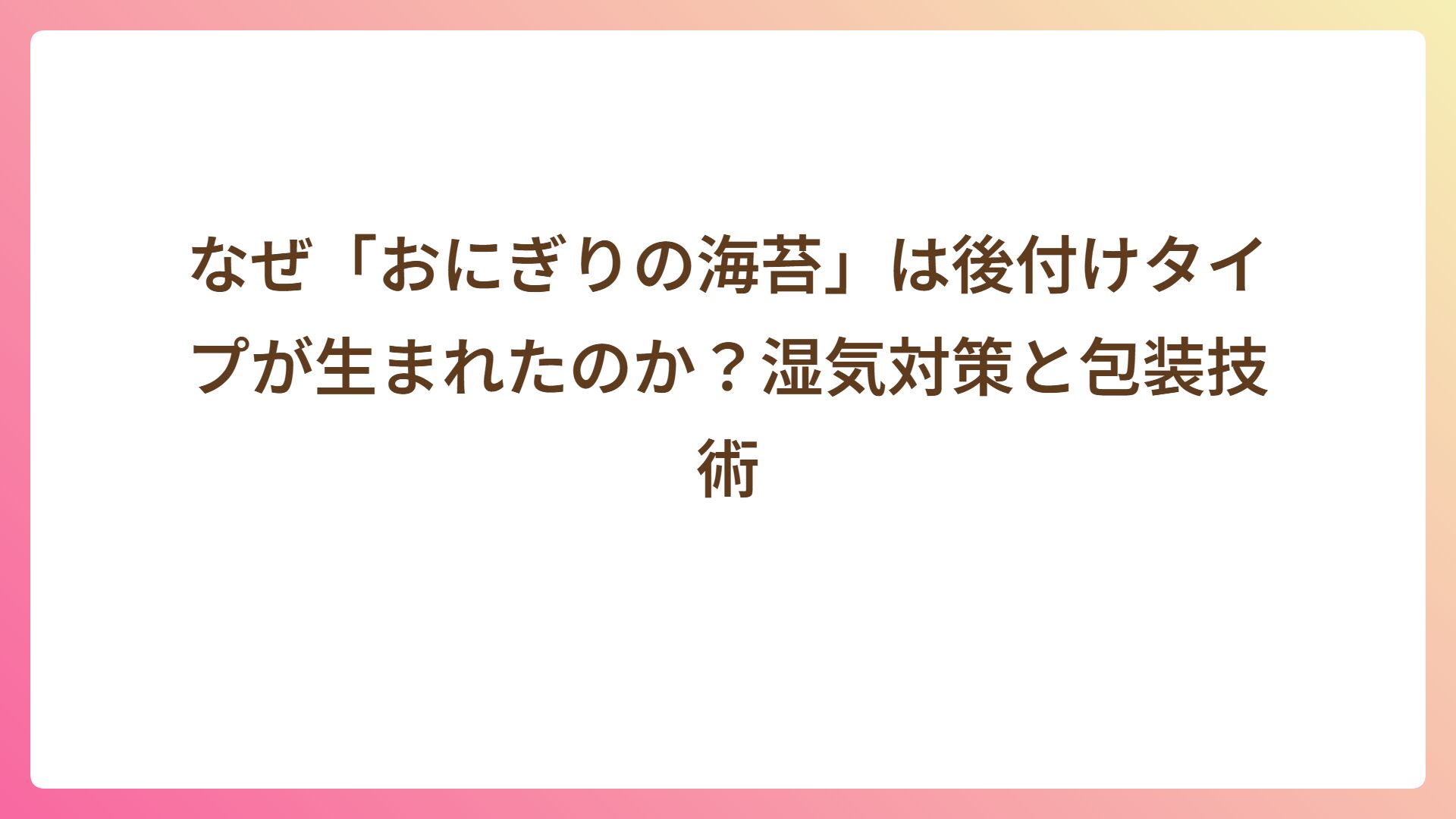なぜ郵便ポストは角型が主流なのか?集配効率と投函エラー防止
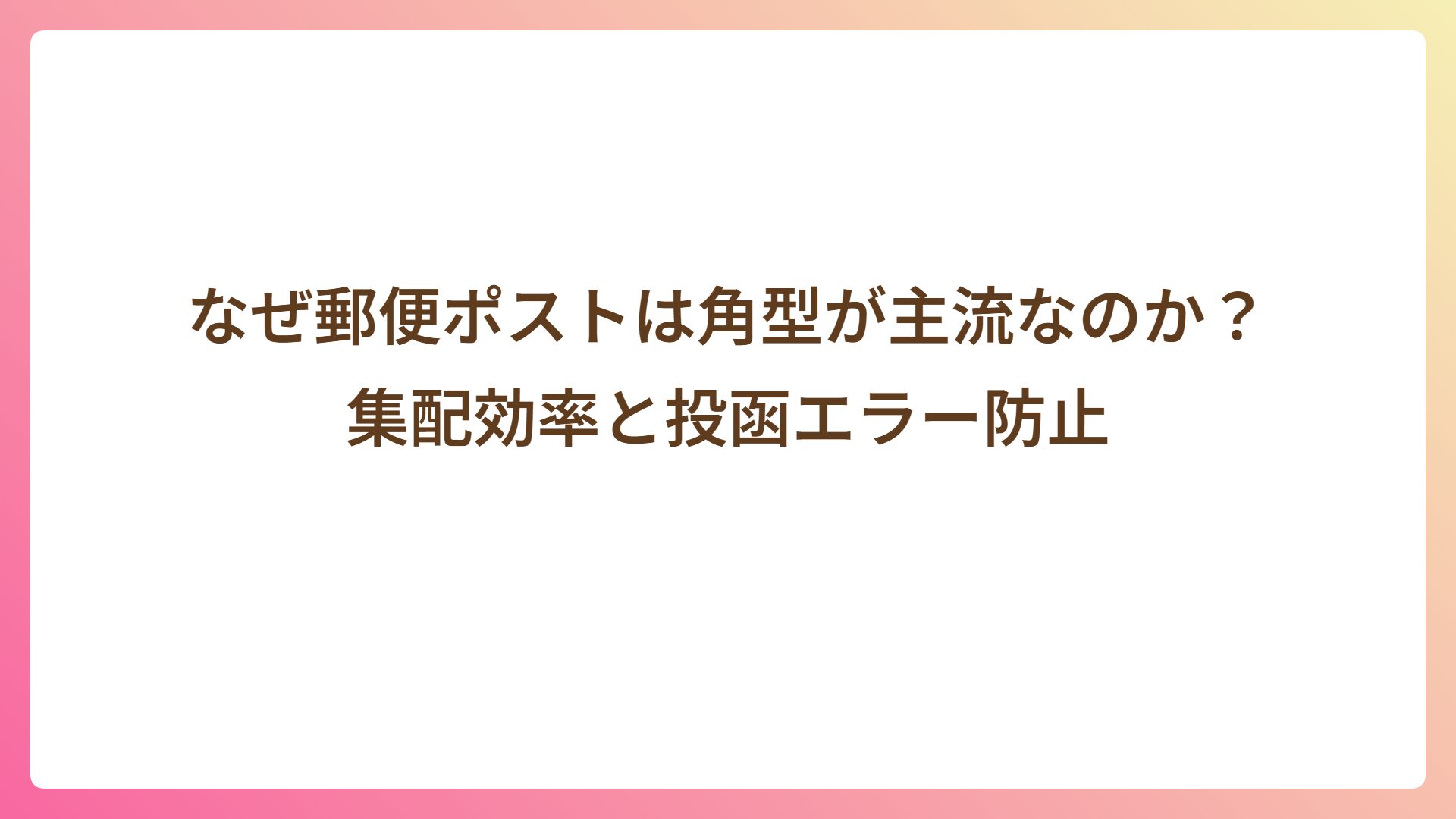
街中で見かける郵便ポストの多くは、四角い箱型のデザインです。
昔ながらの丸型ポストも残っていますが、今ではすっかり少数派。
なぜ現代の郵便ポストは角型が主流になったのでしょうか?
その理由は、投函・回収・分類を効率化するための機能設計にあります。
丸型から角型への移行は“実用性の進化”
かつて日本で主流だったのは、戦前から昭和中期にかけて使われた円筒形の赤いポスト。
しかし、封筒サイズの多様化や郵便物の増加により、
丸い内部では容量の限界と仕分けの非効率さが問題となりました。
そこで1960年代以降、郵政省(現・日本郵便)は角型ポストを本格導入。
箱型構造によって内部の空間利用率を最大化し、
同じ高さでも収納量を約1.5倍に増やすことができたのです。
投函口の形状が“封筒向け”に最適化
角型ポストは投函口が水平スリット状になっており、
A4封筒や長形封筒などの平たい郵便物をスムーズに差し込める設計です。
丸型ポストのように上部から差し込む構造だと、
厚みのある封筒や曲げたくない書類が入れづらく、誤って折れ曲がることもありました。
さらに、角型では投函方向が自然に前向きになるため、
人が並んで作業しやすく、交通の邪魔にならない配置もしやすいという利点があります。
集配作業を“まっすぐ取り出せる”構造
郵便局員がポストを開けて郵便物を取り出す際、
丸型では底のカーブに沿ってかがみながら掻き出すように作業する必要がありました。
一方、角型ポストは内部が直方体のため、
底部の郵便物をそのまままっすぐ引き出せる構造になっています。
この単純化により、1台あたりの回収時間が数十秒短縮され、
1日で何百台も回る集配ルート全体では、大幅な省力化が実現しました。
投函エラーを防ぐ“2口構造”
現在主流の大型ポストには、
- 手紙・はがき用
- 小包・速達・厚封筒用
の2種類の投函口が設けられています。
角型構造はこの2口を上下・左右に分けて配置しやすいため、
誤って厚い封筒を小口に入れるようなミスを防ぐことができます。
また、内部では投函口ごとに仕分けスペースが独立しているため、
回収後の分類作業が格段にスムーズになるのです。
雨風・衝撃への耐久性も高い
角型ポストは、鋼板を曲げずに溶接できるため構造的な剛性が高く、
風雨による歪みやサビを最小限に抑えられます。
丸型は構造的に美しい反面、曲面加工が多くコストが高い上に、
内部構造を密閉しづらいためメンテナンスコストが上がる欠点がありました。
また、四隅に補強材を入れることで倒れにくく衝撃に強い設計にできるため、
安全面でも角型が有利です。
デザインの“機能美”としての定着
角型ポストは、1970年代以降の都市景観にも馴染みやすいデザインとして定着しました。
特に現在主流の「前入れ・前取り出し式(〒マーク付き角型)」は、
機能性と視認性を兼ね備えた公共デザインの代表例とされています。
直線的なフォルムにより清掃や再塗装も容易で、
全国どこでも同じ使い勝手を実現する“ユニバーサルポスト”として普及したのです。
まとめ
郵便ポストが角型なのは、
投函しやすさ・回収効率・分類精度・耐久性をすべて高めるための結果です。
丸型から角型への進化は、単なるデザイン変更ではなく、
人と郵便の動きを最適化するための公共インフラとしての合理設計。
その四角い形には、郵便制度を支える実用美と機能の哲学が詰まっているのです。