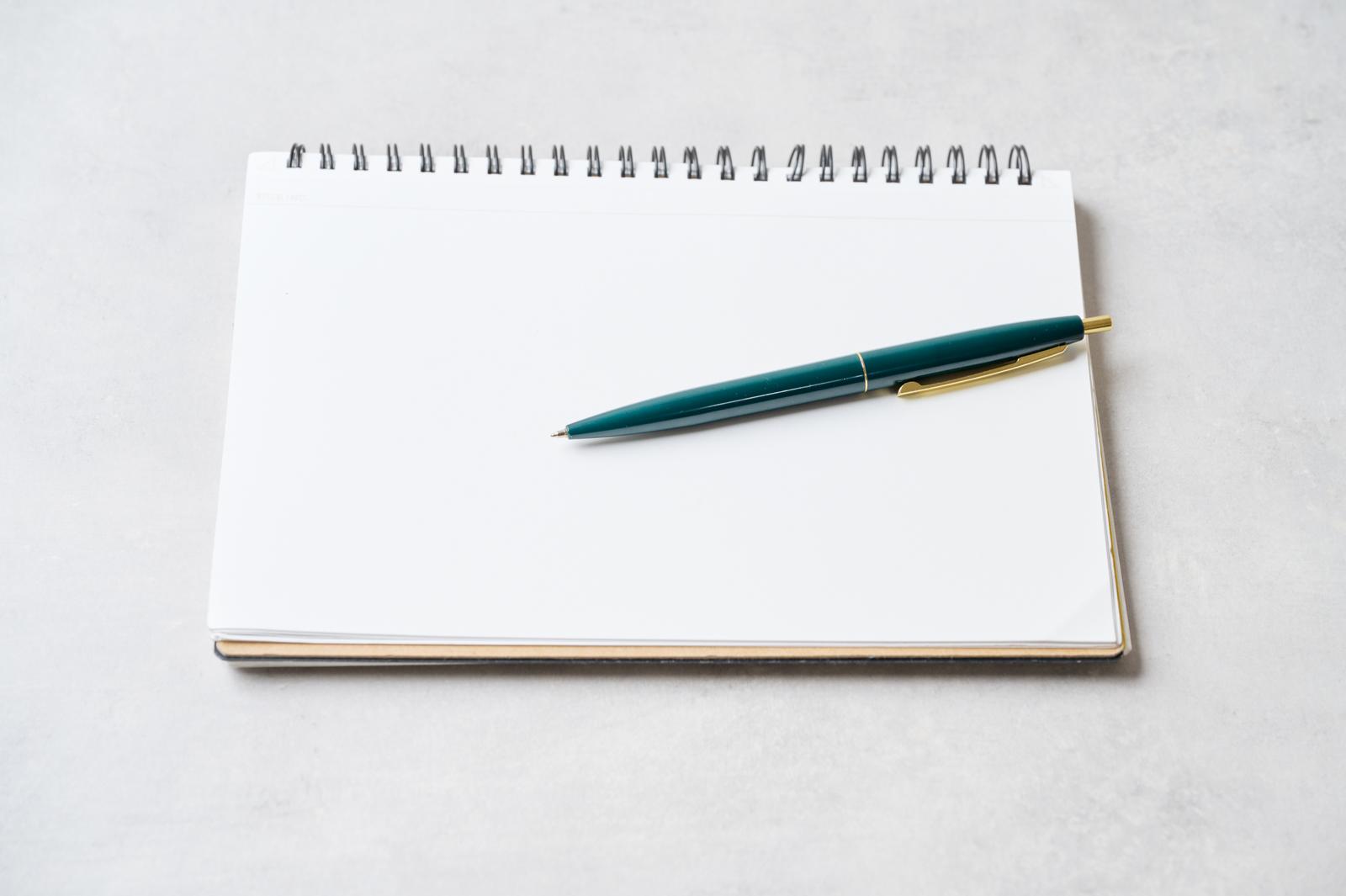桃太郎のおじいさんが山でしていたのは「芝刈り」ではなく「柴刈り」だった?勘違いしやすい言葉の違い

昔話『桃太郎』の冒頭には、こんな有名な一文があります。
「おじいさんは山へしばかりに、おばあさんは川へ洗濯に行きました。」
この「しばかり」を、みなさんはどんな漢字で思い浮かべるでしょうか?
おそらく多くの人が「芝刈り」と想像するのではないでしょうか。
でも実はこの「しばかり」、正しくは「柴刈り」と書くのです。
なぜ「芝」ではなく「柴」なのでしょうか?
今回はこの言葉の違いや意味を丁寧に解説していきます。
「柴刈り」は雑木や薪を集めること
まず、「芝刈り」と「柴刈り」は漢字からして似ていますが、意味はまったく異なります。
- 芝刈り:庭などに生えている芝生を刈ること(またはその機械)
- 柴刈り:山に自生する細かい枝や薪に使える雑木を刈り取ること
つまり、『桃太郎』でおじいさんがしていたのは、庭の手入れではなく、生活に使う焚き木(たきぎ)を集める作業だったわけです。
江戸時代の暮らしを考えれば、薪や柴は貴重な燃料源。山へ「柴刈り」に行くのはごく自然な行動です。
現代人が「芝刈り」と誤解する理由
では、なぜ多くの人が「芝刈り」と誤解してしまうのでしょうか。
それは、現代では「柴刈り」という言葉自体があまり使われなくなったことに加え、音だけ聞くと「芝刈り」のほうが馴染みやすいためです。
日常では芝生を整える「芝刈り機」のイメージが強く、ついそちらを思い浮かべてしまう人が多いのかもしれません。
英語では意味がはっきりしている
日本語だと誤解が生じやすいこのフレーズですが、英語訳ではどうでしょうか。
英語の『桃太郎』では、
“The old man went to the mountain to cut firewood.”
つまり、「おじいさんは薪を切りに山へ行った」と訳されています。
英語だと「firewood(薪)」が使われており、柴刈りの意味がはっきりと伝わる表現になっているのです。
言葉の使い方を見直すきっかけに
「芝」と「柴」は漢字も読み方も同じですが、その意味や背景はまったく違います。
普段何気なく使っている言葉でも、本来の意味や由来を知ることで新しい発見があるかもしれません。
『桃太郎』の一節をきっかけに、あなたも“思い込み”で覚えていた言葉がないか、見直してみてはいかがでしょうか?