なぜSNSでバズるネタは似通るのか?拡散の構造と人間心理の法則を解説
mixtrivia_com
MixTrivia
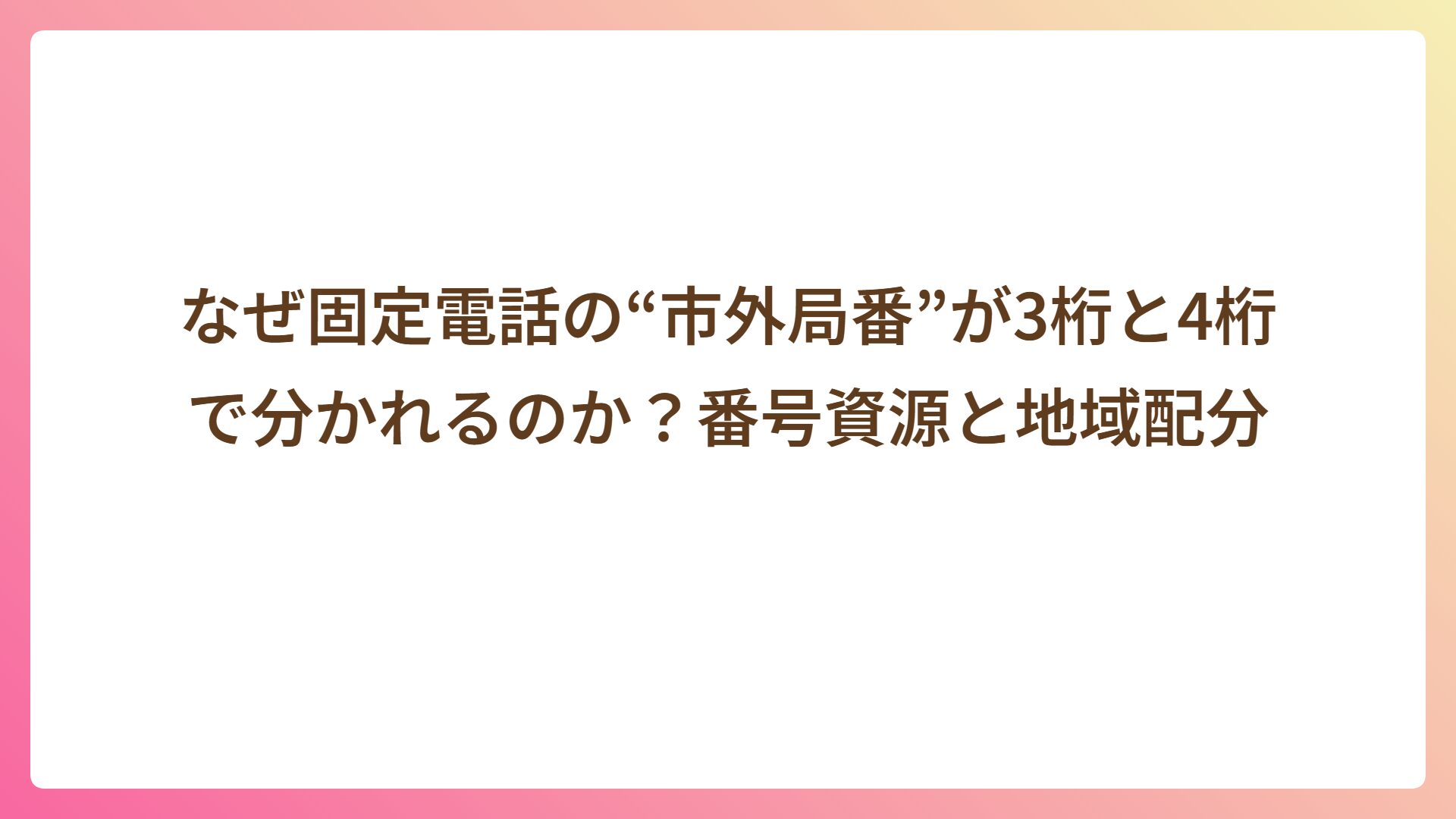
東京「03」、大阪「06」、札幌「011」——一方で地方では「0995」など4桁の市外局番も存在します。
なぜ市外局番は地域によって桁数が違うのでしょうか?
実はこの違いには、通信インフラを効率的に使うための論理的な理由があるのです。
電話番号は全国で一意になるよう、市外局番+市内局番+加入者番号という構成で決められています。
このとき、地域ごとの人口や事業所数に応じて必要な番号の数が異なるため、番号を使いやすくするために桁数が調整されています。
つまり、番号の桁数は「地域ごとの需要バランス」で最適化されているのです。
固定電話の番号は、基本的に市外局番+市内局番+加入者番号=10桁で構成されます。
たとえば、
どの地域でも最終的に「10桁」で収まるよう、局番の桁数を調整しているのです。
これにより、全国の通信システムで統一的に処理できる仕組みになっています。
もともと電話交換が手動だった時代、局番は地域を示す“識別コード”として設計されていました。
人口が集中する都市では加入者数が膨大なため、短い市外局番で広範囲をカバーし、
逆に地方では少数の番号で済むため、細かいエリアごとに長い局番を割り当てるという方針が取られました。
この仕組みはデジタル化後も引き継がれ、今日の「3桁と4桁の混在」という形に残っているのです。
固定電話の市外局番が地域によって異なるのは、
人口密度に応じて番号資源を最適に分配するための仕組みです。
都市では短く、地方では長く。
その桁数の違いは、全国に電話を張り巡らせるための通信設計上の合理性を示しているのです。